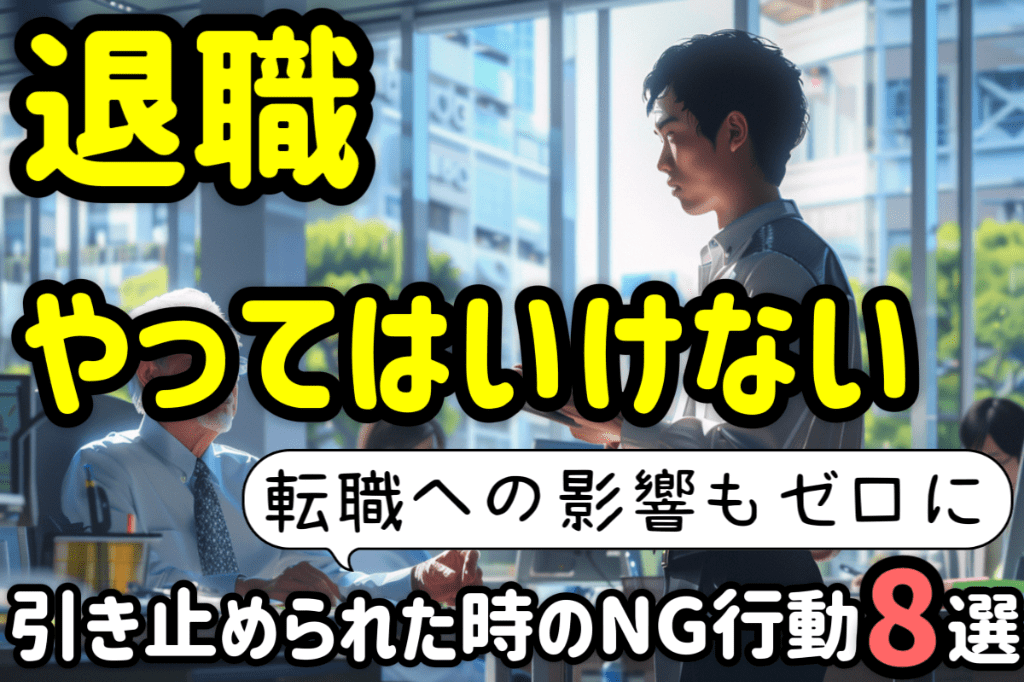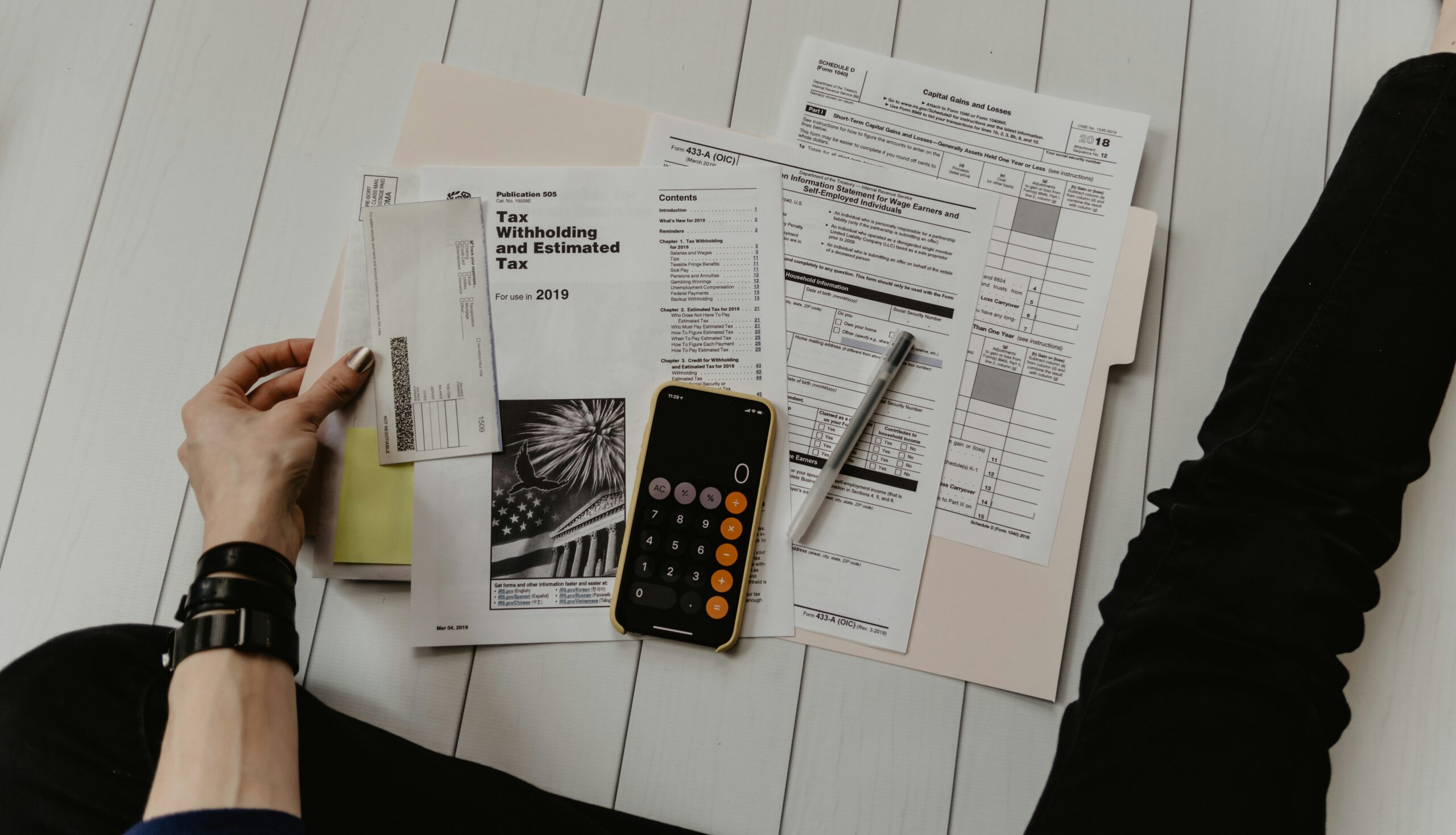新株予約権付社債のメリット・デメリットを弁護士が解説
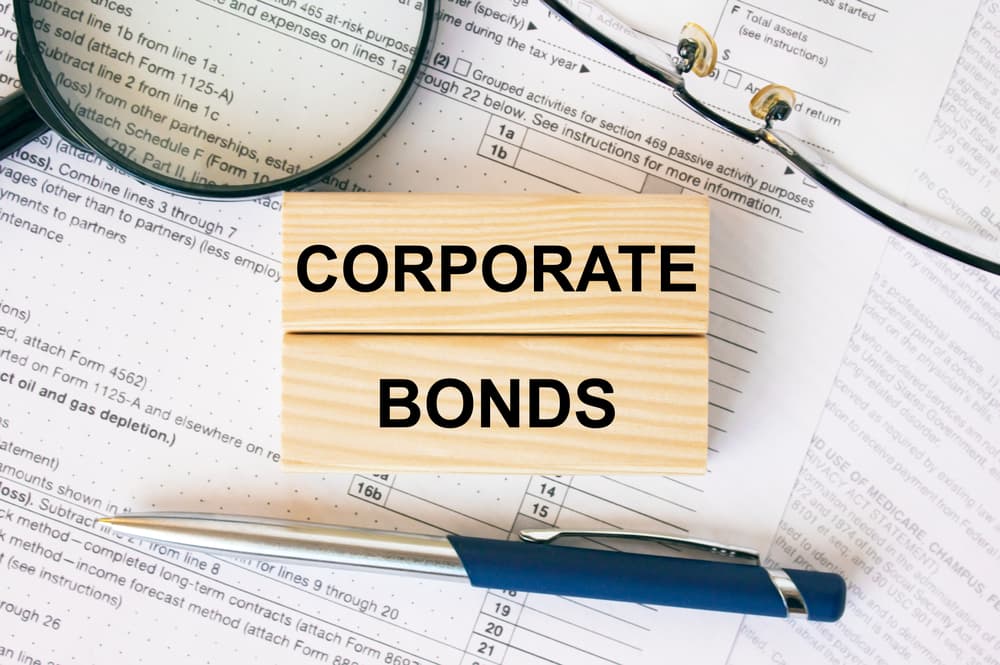
はじめに
「新株予約権付社債」は、資金調達方法の一つとされています。
少し前までは、アーリーラウンドにあるスタートアップなどのように、起業後間もない事業者が使う資金調達方法でした。
現在では、そのような事業者に限られず、追加で資金調達を実施する事業者にも使われている資金調達方法になっています。
「新株予約権付社債」と聞くと、何となく複雑な仕組みになっているようにも思えますが、実際のところどのような仕組みになっているのでしょうか。
今回は、「新株予約権付社債」について、その仕組みやメリット・デメリットなどをわかりやすく解説します。
1 新株予約権付社債とは

「新株予約権付社債」は、会社法で次のように定義されています。
-
【会社法2条22号】
新株予約権付社債 新株予約権を付した社債をいう
言葉とおりの定義ですが、これだけではよくわからないという方もいらっしゃると思います。
「新株予約権」と「社債」に分けて、それぞれについて見ていきましょう。
新株予約権と社債は、会社法でそれぞれ次のように定義されています。
-
【会社法2条21号】
新株予約権 株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいう
【同条23号】
社債 この法律の規定により会社が行う割当てにより発生する当該会社を債務者とする金銭債権であって、第六百七十六条各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう
まずは、新株予約権について見てみましょう。
「新株予約権(ストックオプション)」とは、株式そのものではなく、権利行使することにより株式を取得できる権利のことをいいます。
たとえば、行使価格が100円の新株予約権を保有している場合、株価が200円の時に新株予約権を行使すると100円で200円の株式を取得できることになります。
その後、株価が500円にまで上昇した時点で株式を売却すると、400円の差額が生まれます。
これを「キャピタルゲイン」といい、この差額が利益になるわけです。
次に、社債について見てみましょう。
「社債」とは、事業者が発行する債券のことをいい、額面の額に対して金利が定められており、社債権者(社債の保有者)は利息を受け取ることができる仕組みになっています。
簡単にいってしまうと、社債とは事業者にとって借金をすることを意味します。
満期になると、事業者は社債権者に対して利息付きでお金を償還することになります。
本題に戻しますが、新株予約権付社債とは、つまりは、発行された社債に新株予約権が付いているということです。
新株予約権付社債は、あくまで社債であるため償還を受けるまで社債を保有し続けるという使い方もできますし、株価が上昇した場合には権利行使により株式に転換してキャピタルゲインを得るという使い方もできるのです。
2 新株予約権付社債を発行するメリットとデメリット
(1)メリット
新株予約権付社債により資金調達をする場合、そこで発行されるのは株式ではなくあくまで「社債」です。
株式発行による資金調達では、バリュエーションの評定が必要となりますが、あくまで社債であるため、バリュエーションの評定が必要なくなります。
ここでいう「バリュエーション」とは、企業の価値を金銭的に評価したものをいいます。
特に、起業後間もないような事業者にとっては、バリュエーションの算定が難しいことが多いです。とはいえ、バリュエーションの評定を誤ると、それ以降の資金調達が思うようにできなくなるおそれもあります。
その点、新株予約権付社債では、バリュエーションの評定を先送りにすることができるため、資金調達時においては最大のメリットといえます。
(2)デメリット
既に見たように、新株予約権付社債は事業者にとっては「借金」です。
そのため、満期になれば元金を返済しなければならないうえ、満期になるまでの間は社債権者に利息を支払うことも必要になります。
また、社債と新株予約権のそれぞれに適用される規制を課されることになるため、会社法だけでなく金融商品取引法上による規制も確認しておくことが必要になります。
とはいえ、規制内容は極めて複雑になっており、正確に理解することは容易なことではありません。
これらは、弁護士などの専門家であっても、難しいとされる法規制であるため、相談する際にはこの分野に強い専門家を選ぶことをおすすめします。
3 満期に償還が困難になった場合|償還期限の延長等

新株予約権付社債を発行後、償還期限を迎えると事業者は社債権者に元金を返済しなければなりません。
もっとも、償還期限に償還することが難しく、償還期限を延長したいというケースもあるかもしれません。
このような場合、新株予約権の部分と社債の部分とで、それぞれに期限変更の手続きを踏む必要があるものと考えられます。
新株予約権の部分については、株主総会による決議と、新株予約権を保有するすべての権利者の同意を得る必要があります。
社債部分についても同様に、株主総会による決議と社債権者すべての同意を得ることが必要になると考えられ、これに加えて社債権者集会による決議なども必要になる可能性があります。
もっとも、この点は実務においても見解が分かれているため、専門家に相談しながら進めていくことが必要になると考えられます。
4 まとめ
「新株予約権付社債」は、あくまで社債であるため、資金調達の場面ではバリュエーションの評定を先送りできるというメリットがあります。
ですが、新株予約権と社債の側面を持ちあわせているため、押さえておくべき規制は多岐にわたり、その内容も極めて複雑です。
また、法規制を回避するためのスキーム等を検討する必要もあります。
新株予約権付社債により資金調達を実施する場合には、その分野に強い専門家の力を借りながら進めていくことをおすすめします。
弊所は、資金調達支援にも対応しています。
ビジネスモデルのブラッシュアップから法規制に関するリーガルチェック、利用規約等の作成等にも対応しております。
弊所サービスの詳細や見積もり等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。