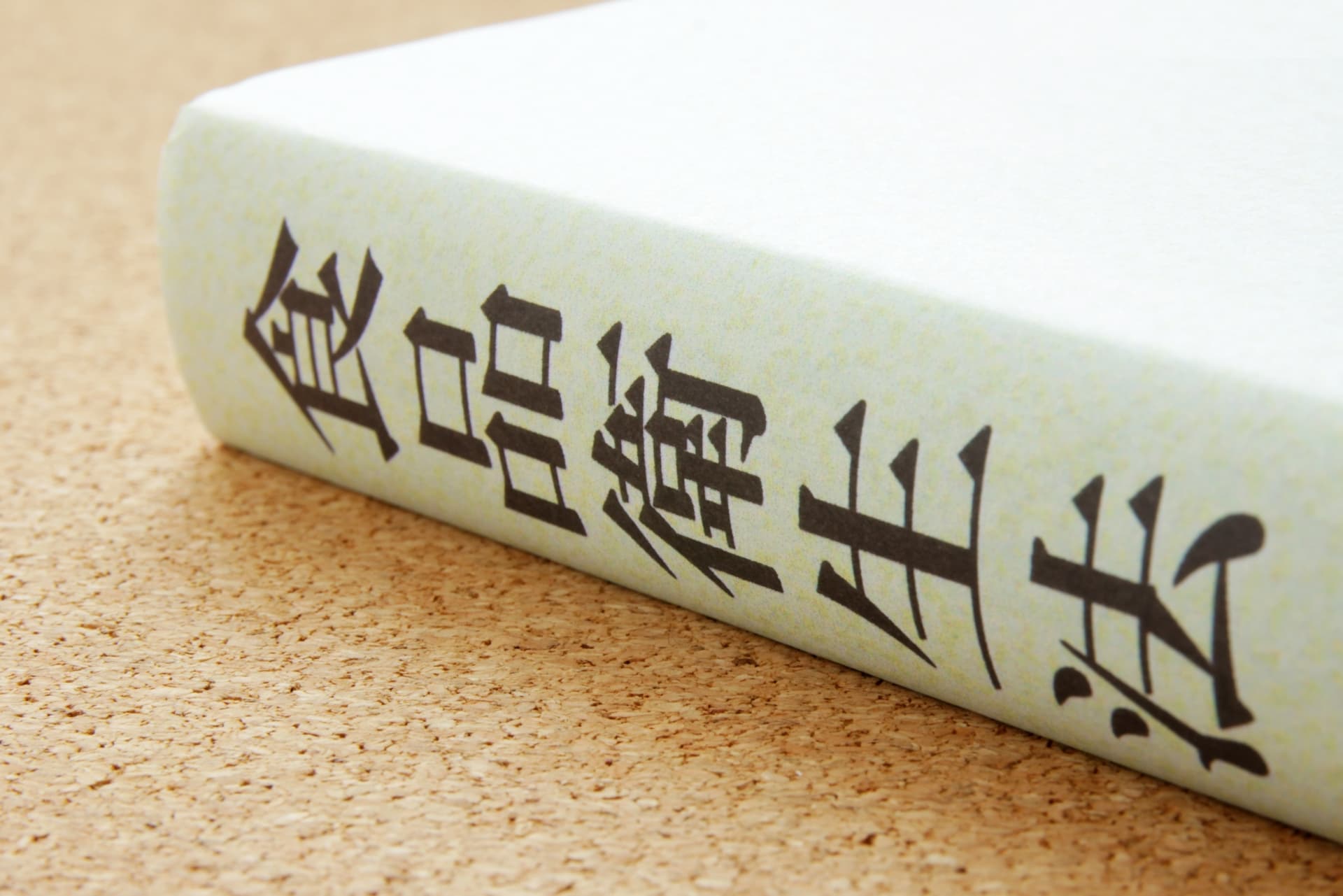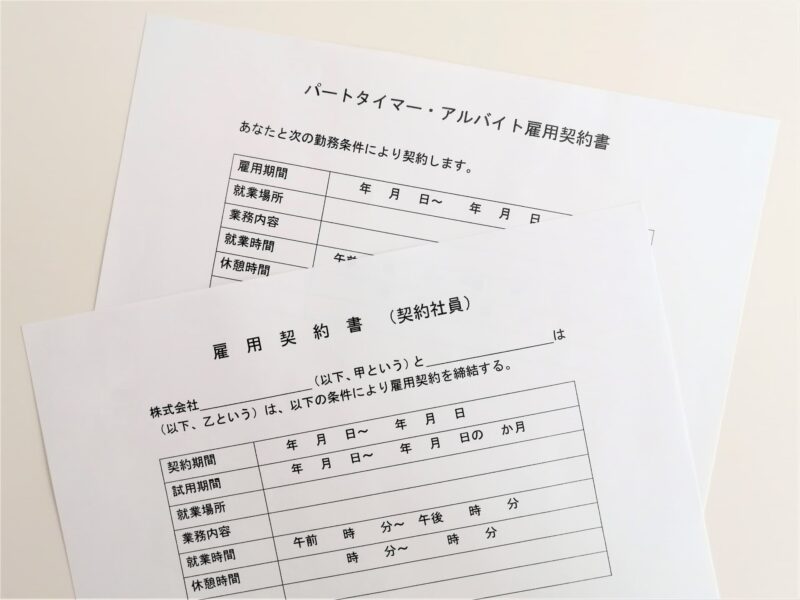同一労働同一賃金ガイドラインにおける4つのポイントを弁護士が解説

はじめに
2020年4月施行の「同一労働同一賃金」制度は、当初は大企業のみを対象としていましたが、2021年4月からは中小企業も適用対象となりました。
事業者は、いまいちど「同一労働同一賃金」制度について、その内容を確認しておくことが大切です。
その際には、厚生労働省が公表している「同一労働同一賃金ガイドライン」も併せて一読することをおすすめします。
今回は、「同一労働同一賃金」について、厚労省ガイドラインのポイントをわかりやすく解説します。
1 「同一労働同一賃金」とは

「同一労働同一賃金」は、同じ仕事に就いている限り、正規社員であるか非正規社員であるかを問わず、同じ賃金を支給するという考えに基づき、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間に生じていた不合理な待遇差を解消することを目的とした制度です。
正規社員と非正規社員の間に生じている不合理な待遇差を解消することにより、どのような雇用形態を選んでも同じ待遇を受けることができるため、多様な働き方を自由に選ぶことができるようになります。
2 同一労働同一賃金ガイドラインのポイント
- 基本給
- 賞与
- 手当
- 福利厚生
3 基本給

基本給は、労働者の能力や経験、業績や成果、勤続年数などに応じて支払われることが一般的です。
これらの趣旨や性格に照らして、通常の労働者との間に違いがなければ、パートタイム・有期雇用労働者に対しても同一の基本給を支給しなければなりません。
通常の労働者との間に違いがあれば、違いに応じた基本給の支給を行う必要があります。
また、労働者の勤続による能力の向上に応じて昇給を行う場合、同一の能力の向上に対しては通常の労働者と同一の昇給を行わなければなりません。
たとえば、労働者の能力や経験に応じて基本給を支給している事業者が、通常の労働者よりも経験が浅いことを理由として、有期雇用労働者に比べて通常の労働者に多くの基本給を支給している場合において、通常の労働者のそれまでの経験が現在の業務と関連性を持たないような場合は、不合理な待遇差として問題となる可能性があります。
一方で、通常の労働者とパートタイム労働者・有期雇用労働者に適用される賃金の決定基準などに違いがある場合があります。この場合、賃金の決定基準に違いがあることが合理的な理由によるものでなければなりません。
具体的には、職務内容や配置の変更範囲といった客観的・具体的な実態に照らし、決定基準に違いを設けることが合理的であると認められる必要があります。
4 賞与

賞与についても基本的な考え方は、基本給の場合と同じです。
賞与は、一般的に業績への労働者の貢献度に応じて支給されるものです。
この趣旨や性格に照らして、通常の労働者とパートタイム・有期雇用労働者の貢献が同一である場合には、同一の賞与が支給されなければなりません。
貢献に違いがあれば、違いに応じた賞与を支給することが求められます。
たとえば、業績への労働者の貢献度に応じて賞与を支給している事業者が、通常の労働者と同一の貢献があるパートタイム・有期雇用労働者に対し、通常の労働者と同一の賞与を支給していない場合は、不合理な待遇差として問題となる可能性があります。
また、通常の労働者に対しては、業績への貢献度を問わず全員に賞与を支給しているにもかかわらず、パートタイム・有期雇用労働者に対しては賞与を一切支給していないような場合は、不合理な待遇差として問題となる可能性が高いです。
5 手当

手当には、通勤手当や役職手当などさまざまな種類の手当てがあります。
各種手当についても、基本的な考え方は基本給や賞与の場合と同じです。
役職の内容に対して支給される役職手当については、同じ内容の役職には同一の役職手当を支給しなければなりません。
役職の内容に違いがあれば、違いに応じた支給を行うことが必要です。
そのほかにも、精皆勤手当や通勤手当、出張旅費や単身赴任手当など、各種手当について同一の支給を行うことが必要です。
時間外労働手当や深夜・休日労働手当の割増率についても同様に、同一の割増率を適用しなければなりません。
たとえば、役職の内容に対して役職手当を支給している事業者が、通常の労働者(役職)と同一の役職名であって同一の内容の役職に就く有期雇用労働者に対し、通常の労働者(役職)に比べ低い役職手当を支給しているような場合は、不合理な待遇差として問題となる可能性があります。
また、通常の労働者と職務内容や時間数が同一の深夜労働を行ったパートタイム労働者に対し、深夜労働以外の労働時間が短いことを理由として、深夜労働に対して支給される手当を通常の労働者よりも低く設定している場合には、不合理な待遇差として問題となる可能性が高いです。
6 福利厚生

通常の労働者と同じ職場に勤務するパートタイム・有期雇用労働者に対し、通常の労働者と同じように食堂や休憩室といった福利厚生施設の利用を認めなければなりません。
また、認められるための要件が同一の場合の転勤者用社宅や慶弔休暇などに伴う勤務免除・有給保障についても、通常の労働者と同じように利用・付与を行う必要があります。
さらに、勤続期間に応じて法定外の有給休暇などを認めている場合は、通常の労働者と同一の勤続期間であれば同じように付与しなければなりません。
7 まとめ
同一労働同一賃金制度は、雇用形態にかかわらず、労働者を平等に扱うことを目的として定められた制度です。
これまでは、正規社員か非正規社員かの違いで、待遇に大きな差を設けることが当たり前のようにもなっていました。
同じ条件で働いている以上、待遇差を設けずに同一の待遇で扱おうとする「同一労働同一賃金」は、理にかなった考え方だと思います。
事業者の方は、これを機に自社の運用をいまいちど見直してみてはいかがでしょうか。
弊所は、ビジネスモデルのブラッシュアップから法規制に関するリーガルチェック、利用規約等の作成等にも対応しております。
弊所サービスの詳細や見積もり等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。