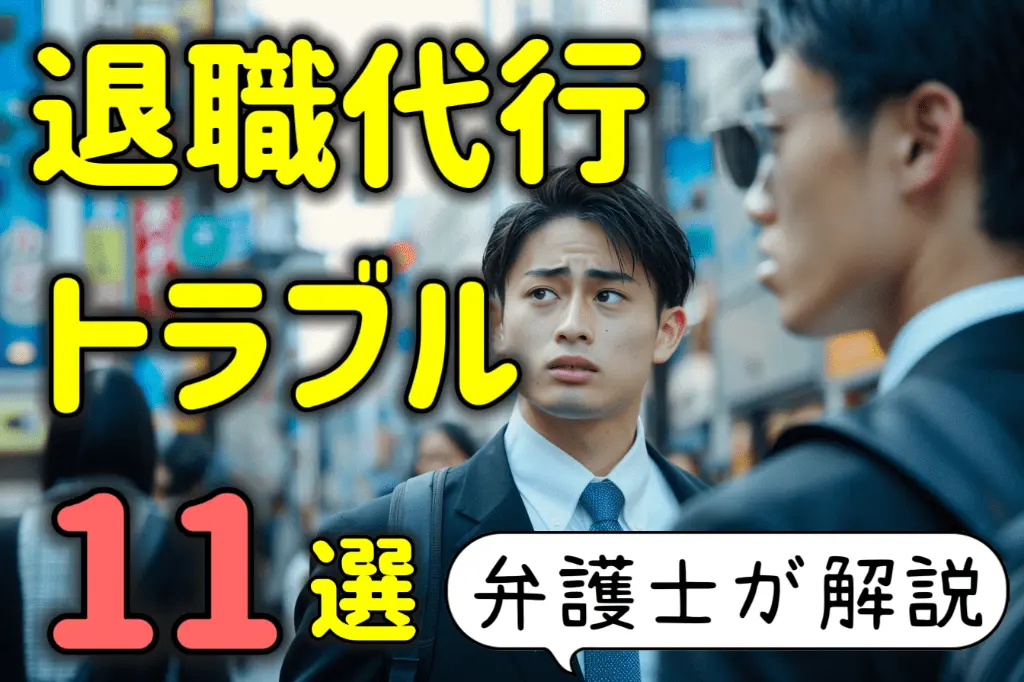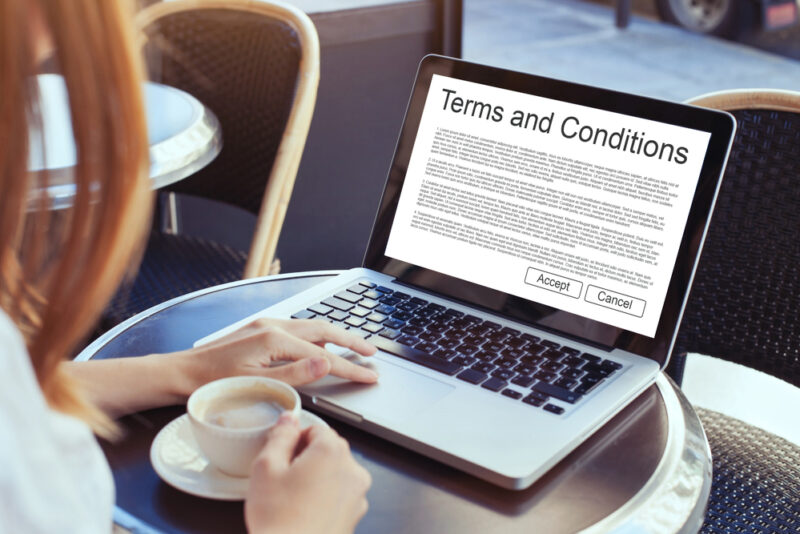利用規約の作り方は?押さえておくべき3つの基本的条項を解説!
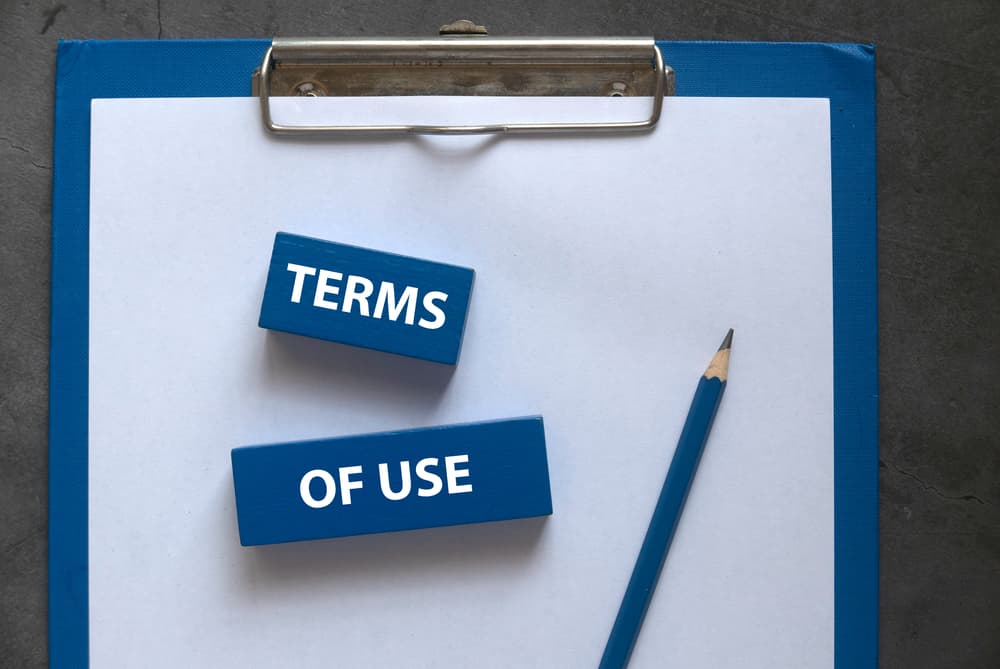
はじめに
はじめて利用規約を作る事業者の中には、何をどのようにして作ったらいいのかわからないという方もいらっしゃると思います。
利用規約の作成にあたっては、自社サービスとの関係で必要となる条項を漏れなく盛り込み、自社サービスに合った利用規約にする必要があります。
そのためには、利用規約で盛り込まれることが多い基本的な条項について、その意味をきちんと理解しておくことも重要です。
今回は、利用規約に定める基本的な条項を中心に弁護士がわかりやすく解説します。
この記事を執筆したのは

- 弁護士・中小企業診断士 勝部 泰之
- 注力:知的財産権・著作権/ライセンス、ブロックチェーン、データ・AI法務
GWU Law LL.M.(知的財産法)
事業の成長とリスクを両立する実務寄りの助言に注力しています。 - 詳しいプロフィールはこちら
1 利用規約とは
「利用規約」とは、サービスを利用するにあたって遵守すべきルールを定めたもので、事業者とユーザーとの間で締結する契約のことをいいます。
たとえば、アプリをダウンロードするときには、「利用規約」の画面が必ずといっていいほど表示されます。
これに対して、アプリを利用しようとするユーザーが「同意する」を選択することで、実際にアプリを利用できるようになるわけです。
事業者は、多くのユーザーにサービスを提供することを想定しているため、本来であれば、個別にユーザーとの間で契約を締結することになります。
ですが、個別に契約を締結しようとすると多くの手間がかかり、現実的ではありません。
また、そもそも利用上のルールを設ないとすると、いざユーザーとの間でトラブルが生じた場合に対処することが困難になります。
このような理由で、「利用規約」は、サービスを提供する事業者にとって必須のものなのです。
2 利用規約で定める基本的な条項
事業者は、自社サービスに合った利用規約を作ることが必要ですが、そのためには、多くの利用規約で定められる基本的な条項の意味をきちんと理解しておかなければなりません。
そうすることで、自社サービスとの関係で必要な条項を適切に盛り込むことが可能になるのです。
基本的な条項としては、以下のようなものが挙げられます。
- 禁止事項
- 免責事項
- 知的財産権に関する事項
3 禁止事項
ユーザーにはさまざまな人がいるため、サービス運営に悪影響を及ぼすような行動に出るユーザーがいないとも限りません。
このような事態になった場合に、利用規約に「禁止事項」が定められていないと、事業者は迅速に対処することができません。
このような行動をすぐに排除することができないと、サービスの信用性にも影響し、ひいては、サービスを利用する人がいなくなってしまうおそれがあります。
サービスの運用を阻害するユーザーの行動をできるだけ迅速にコントロールすることは、事業者にとって、サービスの信用性や継続可能性に関わる重要な要素なのです。
そのため、「禁止事項」は、利用規約に定める条項の中でも極めて重要な条項の一つといえます。
では、具体的にどのような事項を禁止事項として定めるべきなのでしょうか。
これは、自社サービスとの関係で想定されるトラブルを洗い出すことにより、決定するほかありません。
また、自社サービスと類似するサービスを展開している他社の利用規約を参考にすることも方法の一つでしょう。
※禁止事項の定め方について、詳しく知りたい方は、「利用規約の禁止事項の定め方は?3つのポイントをわかりやすく解説!」をご覧ください。
4 免責事項
「免責事項」とは、サービスの利用に関して発生したトラブルについて、損害賠償責任を免除・制限するために設けられる条項です。
免責事項を定めておくことで、トラブルが発生した場合に、事業者とユーザーが負うべき責任を明確にすることができます。
免責事項を定めていないと、トラブルが発生した場合に、誰がどのような内容で責任を負うかがハッキリしないため、解決できないどころか、事態が悪化する可能性が高くなってしまいます。
加えて、免責事項には、想定されるトラブルに関して、留意すべき点などを盛り込んでおくことも大切です。
もっとも、BtoCのサービスにおいて、免責事項を定めるにあたっては、注意しなければならないこともあります。
事業者としては、できるかぎり損害賠償責任を負わないように、免責事項を定めておきたいところでしょう。
ですが、一方的に事業者に有利になるような内容で免責事項を定めてしまうと、場合によっては、「消費者契約法」により無効となる可能性があるため、注意が必要です。
たとえば、「会社は一切の責任を負わない」といった免責事項は、消費者契約法により無効となります。
※免責事項の定め方について、詳しく知りたい方は、「利用規約の免責事項を作成しよう!4つのビジネスモデル別に徹底解説」をご覧ください。
5 知的財産権に関する事項
ウェブを使ったサービスでは、「知的財産権」に注意する必要があります。
ユーザーがコンテンツを自由に投稿できるようになっているウェブサービスは数多く存在します。
このようなサービスを提供する場合、利用規約に「知的財産権に関する事項」を定めておく必要があります。
ユーザーが創作したコンテンツが、著作権法上の「著作物」にあたる場合、同コンテンツは著作権により保護されることになるため、創作者以外の者が創作者に無断で使用することは原則としてできません。
そのため、利用規約に「知的財産権に関する事項」を定めておかないと、事業者は、ユーザーが投稿したコンテンツをコントロールすることができなくなり、サービスの運用に支障が生じるおそれがあります。
また、ユーザーが投稿したコンテンツの著作権が、実はユーザー以外の第三者に帰属しており、ユーザーが第三者に帰属する著作権を侵害している可能性もあります。
このようなケースに備えて、コンテンツの投稿について、ユーザーが適法な権利を有していること、また、第三者の権利を侵害していないことを表明保証させる旨の定めが必要になってきます。
また、ユーザーが投稿したコンテンツについて、事業者が利用できることを権利として定めておくことも必要です。
6 まとめ
利用規約には、基本的な条項をはじめ、自社サービスとの関係で必要な条項を漏れなく盛り込んでおくことが大切です。
そうすることで、あらゆる局面において、柔軟に対応することが可能になり、サービスの向上・信頼性確保にも繋がります。
弊所は、ビジネスモデルのブラッシュアップから法規制に関するリーガルチェック、利用規約等の作成等にも対応しております。
弊所サービスの詳細や見積もり等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。