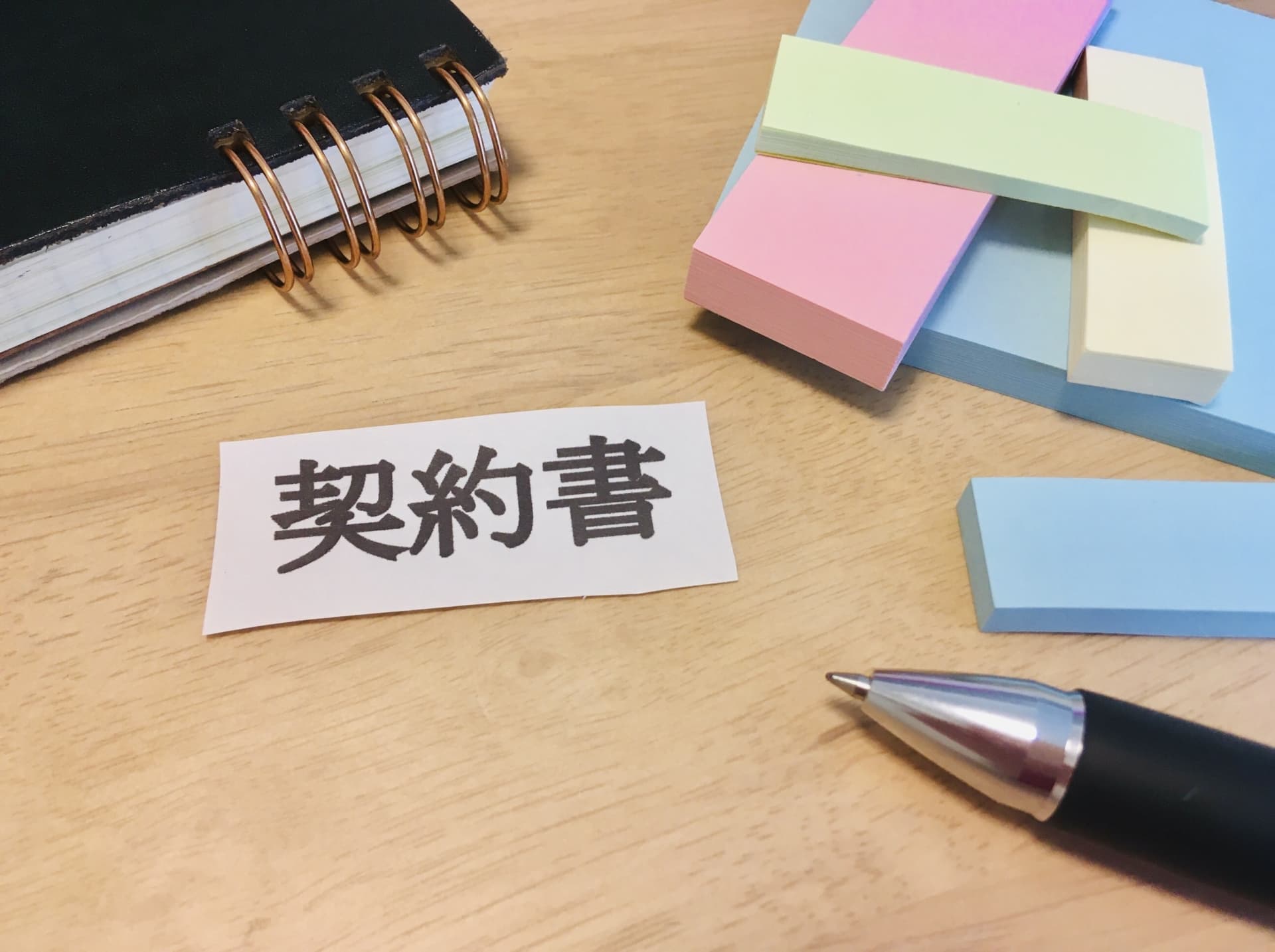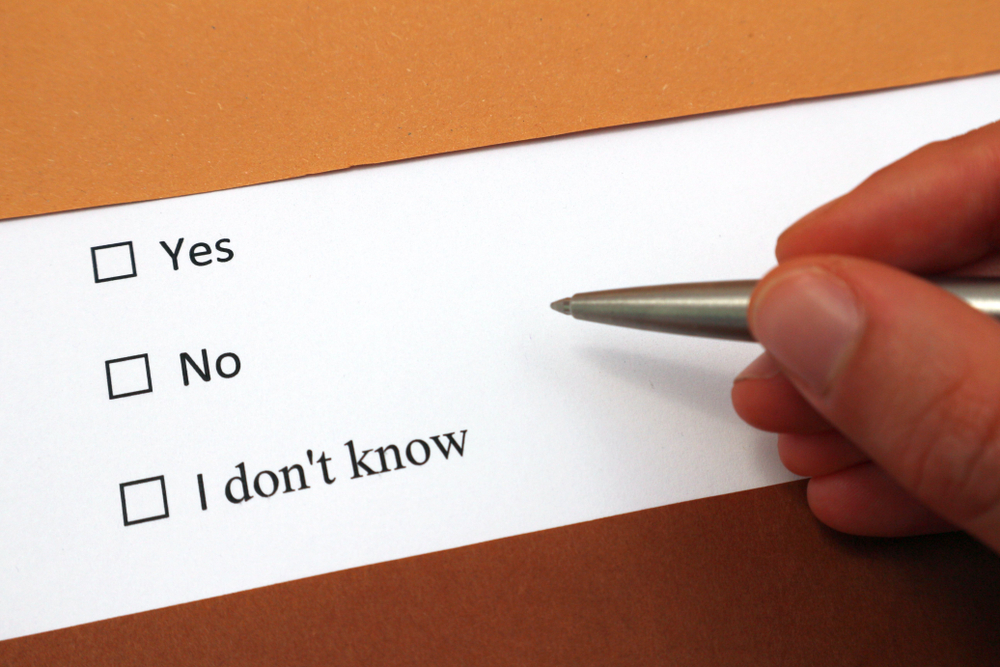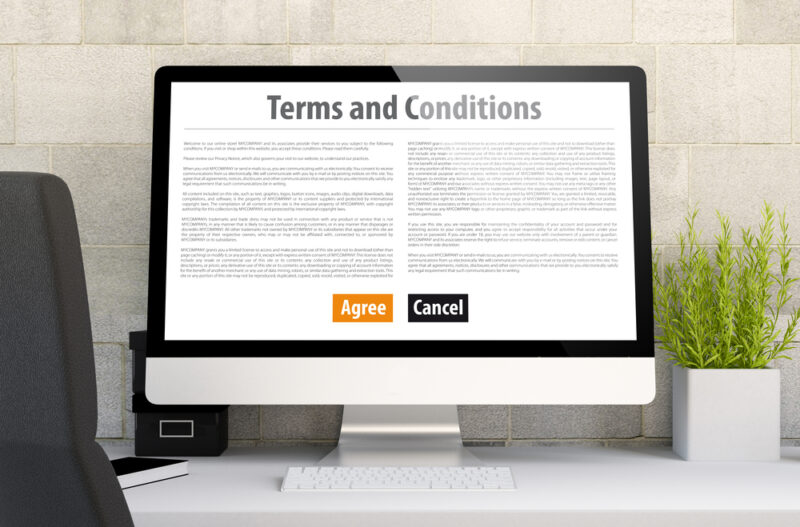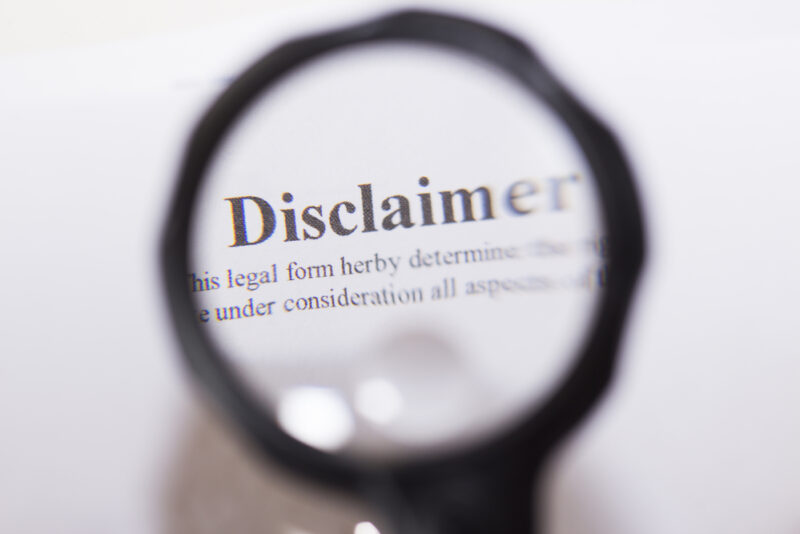利用規約の禁止事項の定め方は?3つのポイントをわかりやすく解説!

はじめに
サービス事業を行う際、必ず定める利用規約。
利用規約を設けておくことで、各利用者と個別に契約を締結する必要がなくなり、また、利用規約に定めたルールに則りトラブルを解決することができます。
さて、利用規約にはいくつか定めておくべき事項がありますが、そのうちのひとつが「禁止事項」です。
そこで今回は、利用規約における禁止事項の定め方やポイントなどを中心に、弁護士がわかりやすく解説します。
この記事を執筆したのは

- 弁護士・中小企業診断士 勝部 泰之
- 注力:知的財産権・著作権/ライセンス、ブロックチェーン、データ・AI法務
GWU Law LL.M.(知的財産法)
事業の成長とリスクを両立する実務寄りの助言に注力しています。 - 詳しいプロフィールはこちら
1 禁止事項はなぜ必要なのか
利用規約における「禁止事項」とは、事業者が利用者に対して一方的に禁止行為を設定することで、その遵守を求める条項のことをいいます。
もしも禁止事項を設けていなかった場合、利用者は何の制約も受けずに、自由にサービスを利用できてしまいます。
例えば、画像投稿サイトにおいて、「第三者が著作権を有する画像の投稿を禁止する」といったルールを設けていなかった場合について考えてみましょう。
この場合、第三者が著作権を有する画像を、利用者が投稿することを容認してしまうことになり、結果として、著作権者の権利を害することになってしまいます。
サイトの運営会社が違法行為を助長したと言われても仕方ありません。
このような事態を避けるためにも、禁止事項を設けて、利用者の行為を制限しておく必要があるのです。
特に、BtoCビジネスの場合、BtoBビジネスよりも利用者数が多くなることが想定されるため、禁止事項を置く必要性が増すものと考えられます。
適切にサービスを運営していくためにも、禁止事項を設定することが必要なのです。
2 禁止事項を定める際の3つのポイント
禁止事項を定めるときは、以下の3つのポイントを押さえておく必要があります。
- 何を禁止事項とするか
- 禁止事項が具体化されているか
- 禁止事項に違反した場合にどんなペナルティを負わせるか
それぞれ見ていきましょう。
3 何を禁止事項とするか
提供する商品やサービスの内容によって、禁止事項に定めておくべき内容も異なります。
そのため、事業者は、自社の事業内容に応じて、利用者に求める禁止行為を考えていくことになります。
とはいえ、簡単に思い付かない場合もあります。
そのような場合は、
-
- 同業他社は何を禁止しているか
↓
-
- 事業者が利用者にやられて困ることは何か
↓
-
- 権利侵害にならないようにするためには何を禁止すべきか
↓
- 法令違反にならないようにするためには何を禁止すべきか
といった順番で検討することになります。
(1)同業他社は何を禁止しているか
まずは、同業他社の利用規約を参考までに確認してみましょう。
どのような禁止行為を設けているのかを網羅的に確認することで、どのようなトラブルが発生しうるのかを想定でき、定めるべき禁止事項を固めていくことができます。
(2)事業者が利用者にやられて困ることは何か
同業他社の利用規約はあくまで参考程度に確認するためのものです。
なぜなら、その会社が自社と同一の商品・サービスを提供しているわけではないからです。
同業他社が定める禁止事項と同一の内容を定めるのではなく、自社の商品・サービスと参考にした会社の商品・サービスとの違いを考慮したうえで、必要に応じた取捨選択・追加が必要になってきます。
自社がサービスを展開していくにあたり、どのようなことを利用者にされると困るのか、検討してみましょう。
(3)権利侵害にならないようにするためには何を禁止すべきか
次に、利用者による第三者への権利侵害が起こらないよう、禁止すべき行為を考える必要があります。
特に配慮しなければならない権利としては、以下のようなものがあります。
- 知的財産権
- 肖像権
- プライバシー権
ここで、画像の投稿サイトを例に権利侵害について考えてみましょう。
「知的財産権」とは、人間の知的活動によって生み出されたアイディアや物に関して発生する権利のことで、特許権や著作権、商標権などが知的財産権に分類されます。
例えば、漫画の紙面を無断でインターネット上に公開する違法アップロードは、著作権の侵害に当たります。
知的財産権のほかにも、個人が特定できる形での画像の公開は「肖像権・プライバシー権」の侵害にあたる可能性があります。
このように、提供する商品・サービスによっては、様々な権利に配慮して、権利侵害とならないような禁止事項を検討しなくてはなりません。
(4)法令違反にならないようにするためには何を禁止すべきか
最後に、法令に違反しないために、利用者に禁止するべきことを検討しましょう。
「法令に違反しないための禁止事項」を検討する際には、以下の2つの視点を持たなければなりません。
- 利用者が法令に違反しないための禁止事項
- 事業者が法令に違反しないための禁止事項
①の例としては、利用者において、犯罪行為や公序良俗に違反するような行為を禁止することが挙げられます。
②には、利用者に求められる資格や届け出、認可などが関係しています。
提供している商品・サービスによっては、利用者にも一定の資格が必要になることもあるため、そうした条件をクリアしていない利用者に商品を販売してしまうと、事業者が法令違反となってしまいます。
そのため、一定の条件をクリアしていない利用者に限り、サービスを利用することを禁止する必要があるのです。
例えば、毒物・劇物を18歳未満の少年に販売することは禁止されているため、18歳未満の少年が購入することを禁止する旨の事項を設けておかなくてはなりません。
このように、法令違反に関する禁止事項を設けるときは、利用者と事業者の双方が法令に違反しないように内容を定めていきます。
ただし、先に触れたとおり、「権利侵害」と「法令違反」に関し、適切な禁止事項を定めるためには、自社サービスに関連する権利や法令を把握・理解していることが前提となるため、一般的な事業者には策定が難しいと思われます。
そのようなときは、弁護士に策定を依頼してみてください。
4 禁止事項が具体化されているか
禁止事項を策定するときは、ある程度禁止事項を具体化する必要があります。
例えば、禁止事項として「当サービスに支障をきたす一切の行為を禁止する」と定めている場合、この文言だけでは具体的にどのような行為が禁止されているのか、利用者にはわかりません。
このように、禁止事項を定める際には、ユーザーにおいてどのような行為が禁止されているのかが具体的に把握できる内容にしなければなりません。
もっとも、禁止事項を具体化しようとして内容を細かくし過ぎると、その禁止事項を適用できる範囲が極端に狭まる可能性もあるため、それらのバランスがとれた内容を定めていく必要があります。
以上のように、禁止事項を定める際には、利用者が禁止されている行為を理解できる程度に具体化する必要があるということを念頭に置いておきましょう。
5 禁止事項に違反した場合にどんなペナルティを負わせるか
禁止事項を定めるときは、同時にペナルティを設ける必要があります。
禁止事項だけを設けて、その違反に対するペナルティを設けていないと、利用者が禁止事項に違反したとしても、事業者は利用者に対し、何らアクションを起こすことができません。
そうすると、禁止事項は「お願い」程度の効果しか持たなくなってしまいます。
このように、禁止事項に違反した場合のペナルティを併せて定めておく必要があるのです。
とはいえ、禁止事項として定めた行為とそれに違反した場合のペナルティの軽重について、バランスが取れていなかった場合、利用者からの反発を招き、炎上にもつながりかねません。
そのため、ペナルティを定める際は、禁止行為の態様とのバランスに配慮する必要があります。
※利用規約違反へのペナルティについて詳しく知りたい方は、「利用規約違反への制裁は?定めるべき2つの措置の有効性を徹底解説!」をご覧ください。
6 具体的な禁止事項の内容
それでは、サービス全般に共通して定めるべき禁止事項に加え、サービス内容に応じて個別に定めが必要となる禁止事項について、以下で見ていきましょう。
(1)共通して定めるべき禁止事項
提供する商品・サービスの内容に関わらず、共通して定めるべき禁止事項は、以下の通りです。
- 法令違反の禁止
- 公序良俗違反の禁止
- 権利侵害の禁止
これらは、利用規約であれば必ず禁止事項として定めておく必要があります。
仮に、これらを禁止事項として定めていないと、犯罪にサービスが利用されたり、他者(社)の権利が侵害されるなど、サービス内の秩序を保てなくなる可能性があります。
(2)アカウントの登録が必要となるサービスの場合
利用者に会員登録をしてもらうサービスの場合、以下のような内容を禁止事項として定めることが考えられます。
- 虚偽の情報に基づいた登録の禁止
- アカウントの使いまわしの禁止
- なりすましの禁止
- 複数アカウントの取得の禁止
(3)サーバなど何らかのシステムを利用する場合
インターネットサービスやアプリケーションなど、何かしらのサーバーシステムを利用するサービスを行う場合は、そのシステムに関して不適切と考えられる行為を禁止することが必要になってきます。
たとえば、以下のような内容を禁止事項として定めることが考えられます。
- リバースエンジニアリングの禁止
- 情報の改ざん・消去の禁止
- システムに支障を生じさせる行為の禁止
- アクセス制御、プロテクトの回避の禁止
(4)利用者が何かしらの表現を行う場合
例えば、コメントや画像、動画などの投稿サイトを運営する場合、利用者の表現に対して以下のような禁止事項を設けておく必要があります。
- 暴力的表現、残虐表現、脅迫的表現の禁止
- わいせつ表現の禁止
- 差別的表現の禁止
- 犯罪を助長する表現の禁止
(5)事業者への問い合わせが可能な場合
お問い合わせ窓口を設置するなどして、利用者からの相談・問い合わせを受け付ける場合は、明らかに商品・サービスとは関係のない問い合わせや度を越す要求を禁止することも検討しましょう。
7 「その他事業者が不適切と判断した行為」を禁止事項に定めてよいか
禁止事項は、ある程度具体化することが必要であることを解説してきましたが、いくつかの禁止事項とともに、「その他事業者が不適切と判断した行為」を禁止事項として設ける場合があります。
この文言からもわかるように、決して具体化されている条項とはいえませんが、個々の禁止事項をすべて列挙することは難しいため、このような包括的な禁止事項を定めておく必要があります。
包括的な禁止事項を設けておくことで、当初は想定していなかった行為に対しても、カバーすることができます。
とはいえ、包括的な禁止事項を適用して利用者にペナルティを課す場合には、注意が必要です。利用者にとっては、禁止事項として具体化されていない行為を対象としてペナルティを課されることになるため、不意打ちに近い状況となってしまいます。
このような包括的な条項ばかりを適用して、利用者にペナルティを課すと、
- ユーザーからの信頼をなくす
- 炎上する
といったことも考えられます。
そのため、禁止事項は、可能なかぎり具体化しておくことが妥当であるといえますが、想定していなかった事項を随時禁止事項として追加していくなど、できるだけユーザーにとって不意打ちとならないよう配慮することが大切です。
8 小括
利用規約で定める禁止事項には、サービス内容を問わず共通して定めるべき事項に加え、ビジネスモデルや提供する商品・サービスによって独自に定めるべき事項があります。
禁止事項は、利用者にとって不意打ちとならないよう、ある程度具体的に定める必要がありますが、詳細になりすぎると適用されるケースが狭まることにもなるため、これらのバランスに配慮することが必要です。
禁止事項とペナルティをセットで策定し、適切にサービスを展開するようにしましょう。
9 まとめ
これまでの解説をまとめると、以下の通りです。
- 利用規約における禁止事項は、事業者がユーザーに対して一方的に禁止行為を設けることで、ルールの遵守を求める条項のことである
- 禁止事項を定めるときは、①何を禁止事項とするか、②禁止事項が具体化されているか、③禁止事項に違反した場合にどんなペナルティを負わせるか、の3点を押さえておく必要がある
- 基本的には、①同業他社は何を禁止しているか、②事業者が利用者にやられて困ることは何か、③権利侵害にならないようにするためには何を禁止すべきか、④法令違反にならないようにするためには何を禁止すべきか、の順番で定めるべき禁止事項を検討していく
- 禁止事項を定めるときは、ある程度具体化する必要があるが、細かく決めすぎてしまうと、適用の範囲が狭まるおそれもあるため、バランスを考えながら内容を定めていく必要がある
- 禁止事項を定めるときは、違反した場合のペナルティも併せて定めておく必要がある
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。