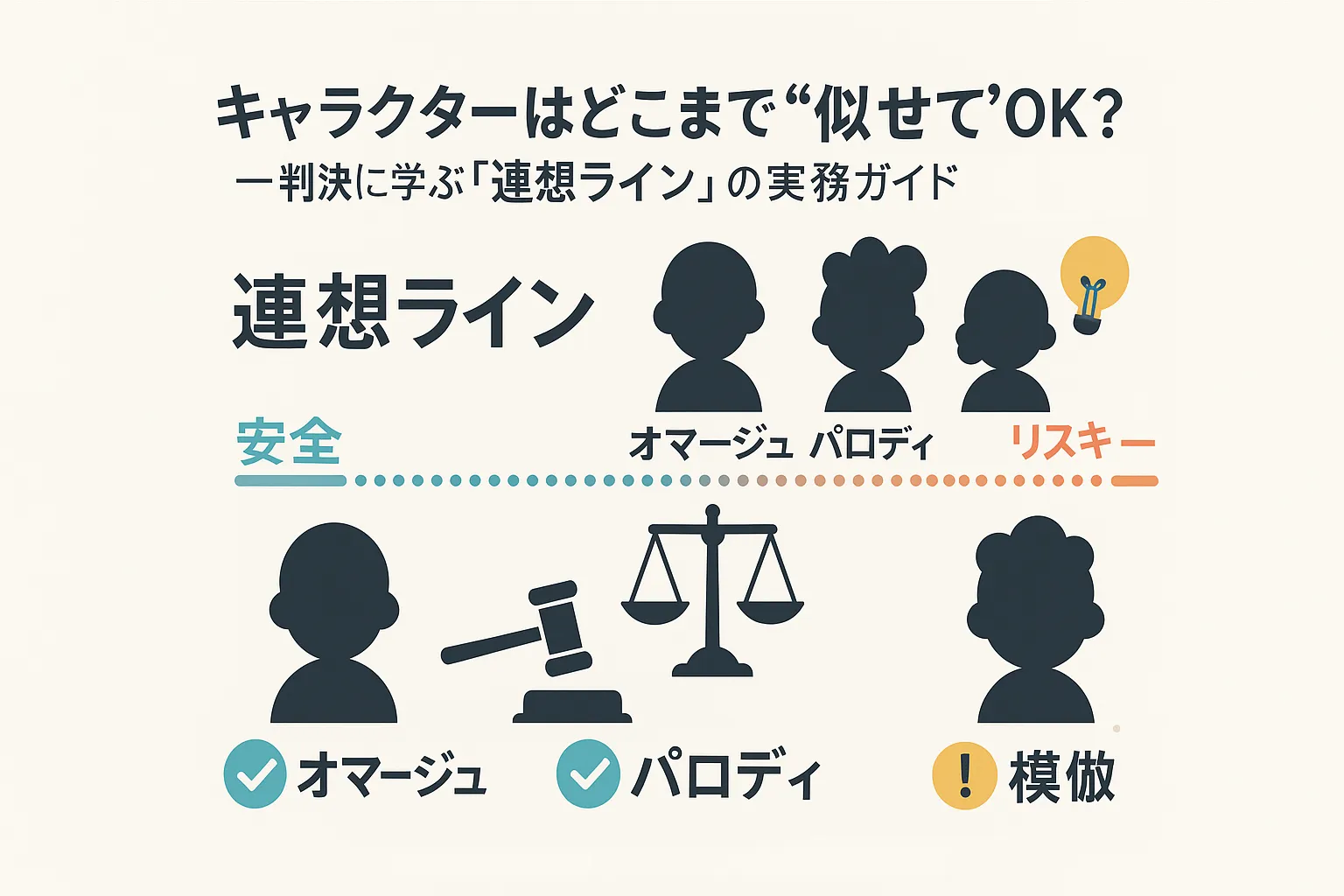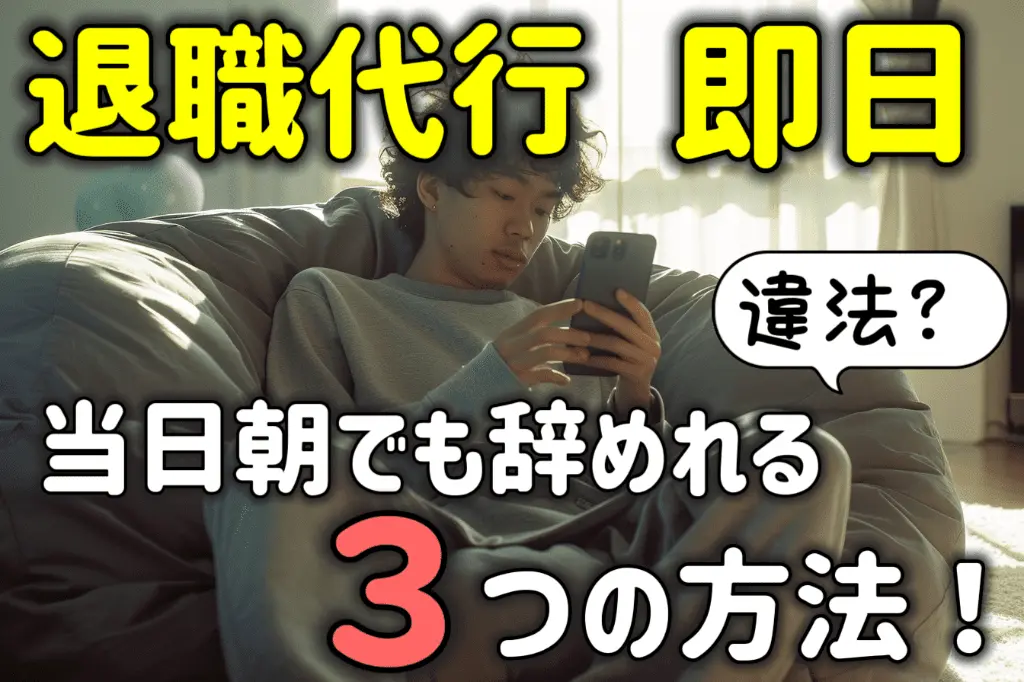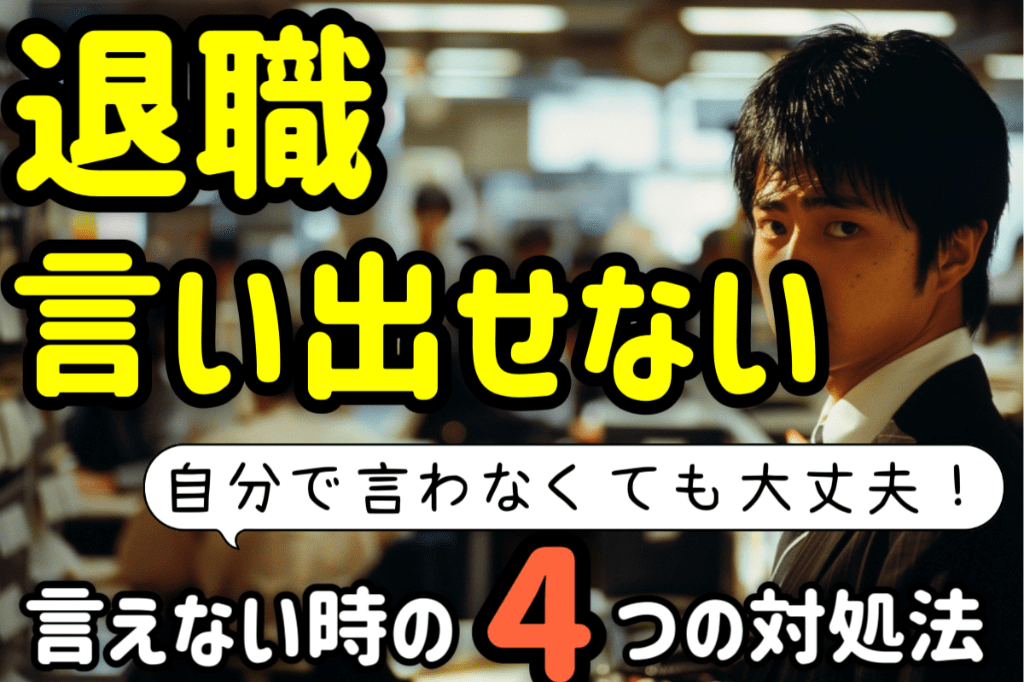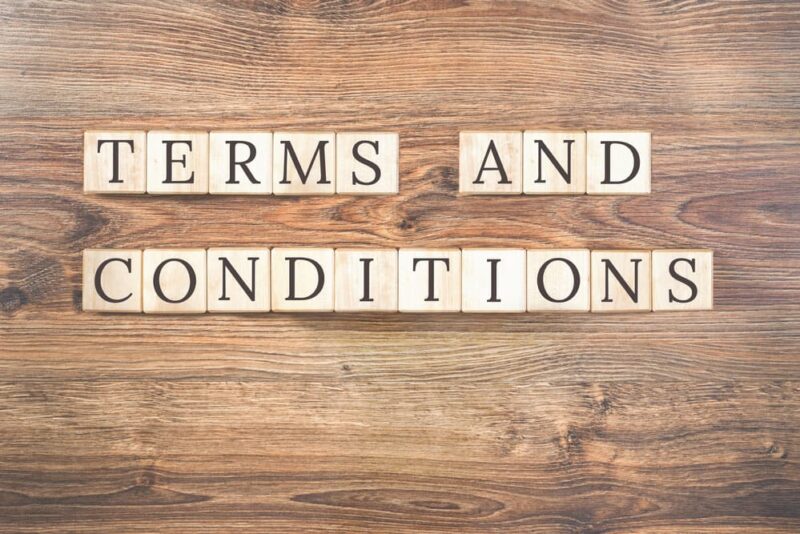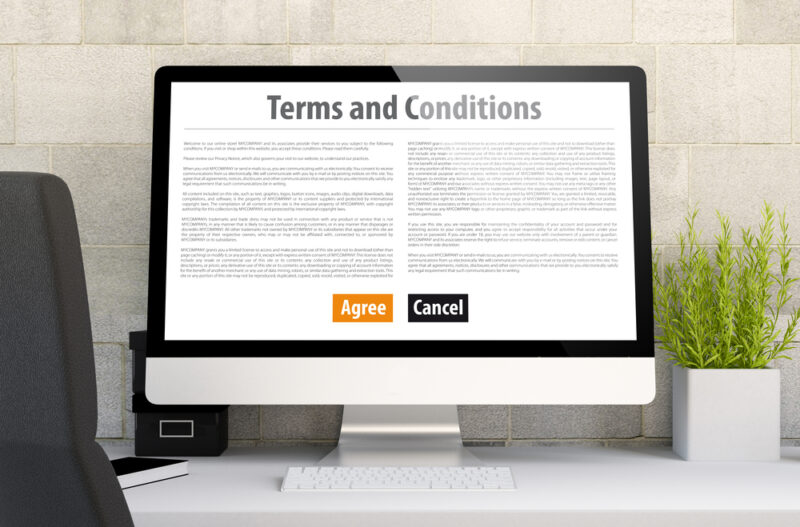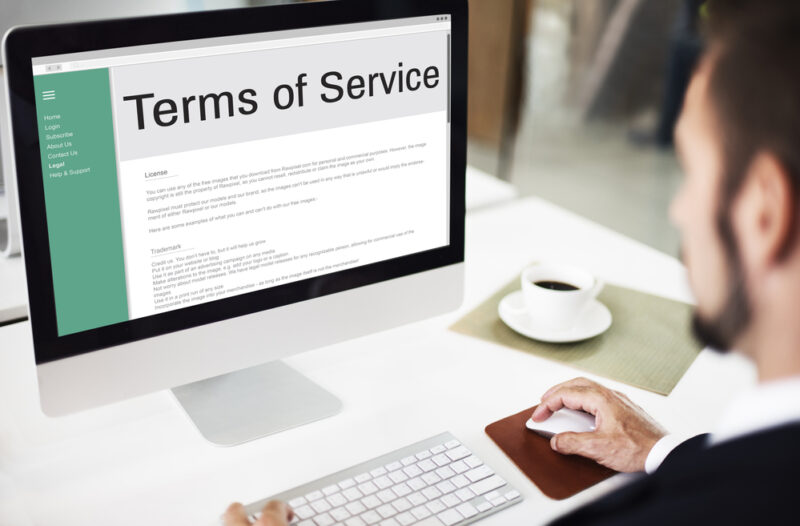利用規約の免責事項を作成しよう!4つのビジネスモデル別に徹底解説
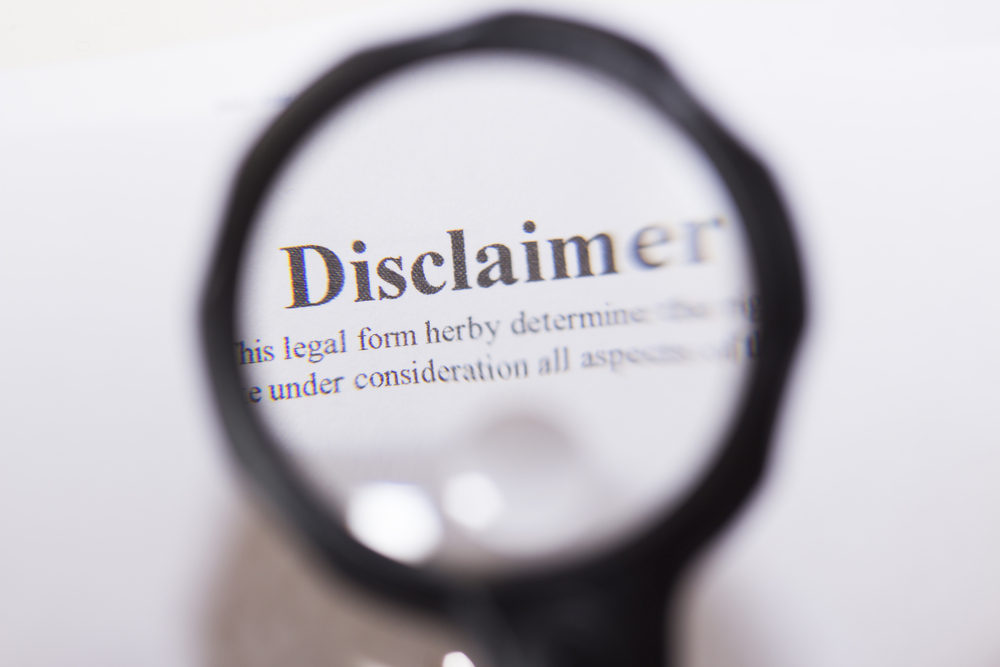
はじめに
サービスを始めるとき、必ず必要となる「利用規約」。
いくつか定めるべき事項があり、その1つが「免責事項」です。
免責事項をしっかりと定めておくと、事業者の責任範囲を明確化でき、トラブルを未然に回避することができます。
もっとも、偏りすぎた内容にしてしまうと、免責条項自体が無効となる可能性もあるため、注意が必要です。
この記事では、利用規約の免責事項について、必要とされる理由や注意すべき点、定めるべき内容などを解説していきます。
この記事を執筆したのは

- 弁護士・中小企業診断士 勝部 泰之
- 注力:知的財産権・著作権/ライセンス、ブロックチェーン、データ・AI法務
GWU Law LL.M.(知的財産法)
事業の成長とリスクを両立する実務寄りの助言に注力しています。 - 詳しいプロフィールはこちら
1 利用規約の「免責事項」とは

(1)免責事項とは
「免責事項」とは、サービスなどを利用することで発生しうる、何かしらのトラブル等に関して、損害賠償の責任を制限・免除するためのルールを示した項目のことです。
ユーザー側と事業者側、それぞれどこまで責任を負うのか、どういったケースだと責任を負わないのかが明記されています。
また、免責事項には、こうした損害賠償の責任の制限・免除だけを設けるわけではありません。
サービスを提供するうえで、トラブルとなりうる事柄に関して、留意すべき点や注意すべきポイントを免責事項の中に記載しておくことも大切です。
例えば、無料配信のニュースサイトが免責事項の中に「提供されている情報に関して、正確性や安全性は保証しない。ユーザー自身が判断を行うこと」などの規定を盛り込むことがあります。
このように、免責事項には、責任の制限・免除に関する内容に加え、サービスを利用するユーザーに対して様々な注意点を盛り込むことも大切なのです。
(2)利用規約に免責事項を設ける理由
それでは、何故利用規約の中に、免責事項を設ける必要があるのでしょうか。
その理由として、利用規約はユーザーから同意を得て運用していることが挙げられます。
サービスの提供開始時には必ず、ユーザーに対して利用規約を表示し、その内容への同意を得る必要があります。
この同意を得ることで、ユーザーを利用規約のルールに縛ることができるのです。
そのため、免責事項に定められている内容が現実化した場合、ユーザーや事業者は、免責事項のルールに縛られることになります。
もしも、免責事項がなかった場合、少しのミスやトラブル、また、事業者には関係のないところで発生したトラブルにまで高額な損害賠償を求められてしまうかもしれません。
そのような事態を避けるために、免責事項で「このようなときは、責任を免除する」というルールを設けているのです。
もっとも、「会社はすべての責任を負わない」といったように、事業者の利益のみを優先した条項は、無効となるため注意が必要です。
また、そのような内容の条項を設けていると、ユーザー側からの反発を招くなど、さまざまなリスクも発生してしまいます。
2 免責事項が無効になるケース

(1)無効になるケースは?
例えば、以下のような内容を免責事項に入れていたとしましょう。
- 会社の損害賠償責任をすべて免除する
- 会社側に故意・重過失がある場合であっても、ユーザーが責任を負う
このように、一方的に事業者側の利益を優先し、ユーザー側が著しく不利になっているような条項は、無効となります。
このような条項が無効となる根拠は、以下の2つにあります。
- 消費者契約法
- 定型約款
(2)消費者契約法
「消費者契約法」は、消費者が売買契約などの契約を事業者と結ぶ際、消費者への不当な勧誘や一方的に不利な内容の契約締結などを防止し、消費者の利益を守るための法律です。
このように、消費者契約法では一方的に消費者に不利となるような契約などが禁止されているため、事業者・消費者間の契約ともいえる利用規約においても、ユーザー側に著しく不利となるような内容は、消費者契約法により無効となります。
具体的には、以下のような条項は無効と定めています。
- 事業者の債務不履行により、消費者に損害が生じた場合の、事業者の賠償責任をすべて免除、もしくは、責任の有無を事業者が決定する
- 事業者の債務不履行(故意・重過失)により消費者に損害が生じた場合、事業者の賠償責任の一部を免除、もしくは、責任の限度を事業者が決定する
- 消費者契約において、事業者の不法行為によって消費者に損害が生じた場合、事業者の損害賠償責任をすべて免除、もしくは、責任の有無を事業者が決定する
- 消費者契約において、事業者の不法行為(故意・重過失)よって消費者に損害が生じた場合、事業者の賠償責任の一部を免除、もしくは、責任の限度を事業者が決定する
(3)定型約款
「定型約款」とは、2020年4月1日から施行される改正民法によって規定された利用規約の新ルールです。以下の3つすべてに当てはまっている利用規約は、「定型約款」として扱われ、定型約款の規制を適用されます。
- ある特定の者が不特定多数の者を相手方とする取引であること
- 内容の全部または一部が画一的であることが当事者双方にとって合理的であること
- 契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体であること
定型約款の規制のうちの1つに、「ユーザーの不利益条項が含まれていないこと」という規制があります。
そのため、利用規約が定型約款にあたる場合、ユーザーにとって著しく不利益な免責条項などは、無効となります。
なお、オンラインサービスの利用規約であれば、基本的に定型約款に当たるとみていいでしょう。
3 免責事項を作成する

免責事項を作成するときは、ユーザー側が著しく不利とならないよう、ユーザー側と事業者側、双方のバランスをとった内容とすることが大切です。
それでは、実際にどのような事項を設ければいいのでしょうか。
以下の2つのポイントを見ていきましょう。
- 定めるべき内容
- ビジネスモデルごとに必要な内容
4 定めるべき内容

どのような業態やビジネスモデル、サービスでも、基本的に定めておくべき内容がいくつかあります。
具体的には、以下の5つは基本的に定めておくべき内容といえますが、それぞれ、どのような書き方をすべきなのか、また、もしもこの内容がないと、どのような事態を招いてしまうかなどについて、解説していきます。
- 責任の制限
- 提供サービスに関するもの
- 現状有姿
- 機器のトラブル・メンテナンス
(1)責任の制限
まず、事業者が責任を負う範囲について、明確にしておく必要があります。
責任の制限について、規定を設けていなかった場合、何らかのトラブルが発生しても、責任のなすりつけ合いになりかねず、紛争に発展してしまう可能性があります。
その点、あらかじめ、責任を負わない事項や責任の上限を定めておけば、そのような事態を未然に防ぐことが可能になるのです。
そのため、どこまでの損害に対して責任を負うのか明記しておくことが必要です。
具体的には、以下のような条項を設ける必要があります。
- 本サービスのご利用に際して、ご利用者様が被った損害について当社が責任を負う場合であっても、当社の故意または重過失がない限り、当社の責任は直接かつ通常の損害に限られるものとします
(2)提供サービスに関するもの
音楽や画像などのコンテンツやサービスサイトなど、何かしらのサービスを提供する場合には、主に以下の3つの視点から免責事項を定める必要があります。
- 利用
- 正確性
- 品質
以下で具体的に見ていきましょう。
①利用
まず、そのサービスを利用することでユーザーが取得することとなった情報に起因してトラブルが起きた場合の責任について、記載しましょう。
例えば、画像提供サイトで提供されている画像を使用して脅迫文を作成し、第三者(Aさん)を脅迫したユーザーがいたとしましょう。
このようなケースにおいて、提供サイトは責任を負わないことを明記しておかなかった場合、脅迫文に使用されている画像が提供サイトのものと知ったAさんは、「脅迫に協力した」などとして提供サイトを訴えるかもしれません。
そのような事態を防ぐため、サービスの利用と生じたトラブルとの間に一定の関連性が認められるような場合であっても、以下のような文言で、責任を負わないことを明記しておくことが大切です。
- 当サービスサイトに掲載されている情報を利用することで発生した紛争や損害に対し、当社は責任を負わないものとします
- 当該コンテンツに起因してご利用者様および第三者に損害が発生したとしても、当社は責任を負わないものとします
②正確性
特に、情報提供サイトの場合、情報の正確性について、但し書きを設けておく必要があります。
たとえば、掲載している情報が100%正確・安全とは言い切れないこと、また、最新性、信頼性などを保証するものではないことなどを記載しておく必要があります。
仮に、このような定めを置いていなかった場合、提供している情報に誤りがあると、「この情報を信じて行動を起こしたのに」などとクレームを入れられ、場合によっては、損害賠償を求められることにもなりかねません。
具体的には、以下のように記載しましょう。
- 当ウェブサイト上のコンテンツについて、できる限り正確に保つように努めていますが、掲載内容の正確性・完全性・信頼性・最新性を保証するものではございません
- 当社は、本サイト等の内容およびご利用者様が本サイトを通じて得る情報等について、その正確性、完全性、有用性、最新性、適切性、確実性、動作性等、その内容について何ら法的保証をするものではありません
③品質
例えば、ウイルス対策を行っていたとしても、サービスサイトがウイルスに感染してしまう可能性があります。
そのほか、予期せぬ事態でサービスの提供を一時停止するなど、対策を行っていても避けられない事態を想定し、免責事項に提供サービスの品質について明記しておきましょう。
たとえば、以下のような内容が考えられます。
- 当社は、ご利用者様が本サイトを利用する際に、コンピューターウイルスなど有害なプログラム等による損害を受けないことを保証しないものとします
- 理由の如何に関わらず、本サイトに掲載されている情報の変更および本サイトの運用の中断・中止によって生じるいかなる損害についても、当社は責任を負わないものとします
(3)現状有姿
例えば、ゲームアプリやサービスサイトの場合、常に開発が進められ、サービスやコンテンツが変化していきます。
そのような場合、現状で提供されているサービスやコンテンツは未完成ともいえるため、「現状ベースで提供する」という記載をしておく必要があります。
具体的には、以下のような内容を記載しましょう。
- 適用法令により許容される限度において、本サービス及びコンテンツは、いかなる保証もなしに、「現状有姿」で提供されます
(4)機器のトラブル・メンテナンス
サービスサイトを運営していると、突如サーバーがダウンしたり、サーバーのメンテナンスを行うなどして、サービスを中止せざるを得なくなることがあります。
そのような事態に備えて、以下のような定めを設けておきましょう。
- 当サイトはシステム障害またはサーバのメンテナンス等により、予告なく一時的または長期に停止する場合がございます
- 当サイトは、本サービス等の提供の一時的中断または停止により、ユーザーが被ったいかなる損害も責任を負わないものとします
5 ビジネスモデルごとに必要な内容

前項の基本の内容に加えて、ビジネスモデルやサービスごとに、免責事項で定めておくべき内容がいくつかあります。
今回は、以下の4つのビジネスモデルを見ていきましょう。
- BtoCプラットフォーム
- CtoCプラットフォーム
- コンテンツ提供サイト
- 課金アプリ
(1)BtoCプラットフォーム
事業者と消費者をつなぐBtoCプラットフォームを運営している場合、消費者が購入した商品に関するトラブルについて責任の所在を明確にする必要があります。
つまり、提供される商品に関して、何かしらの瑕疵(欠陥)があったとしても、プラットフォーム事業者は場を提供しているだけであり、責任を負う立場ではないことを明記しておくことが大切です。
- ご利用者様が提携企業から商品を購入した場合、売買契約の当事者は当該提携企業であり、当社は、ご利用者様が提携企業から購入した商品に関して責任を負わないものとします
(2)CtoCプラットフォーム
消費者同士がつながるCtoCプラットフォームの場合、代金の未払いや商品の不具合などの、ユーザー間のトラブルが想定されます。
たとえば、個人間取引において売手が買手に対して負う、商品不具合などに対する責任を「瑕疵担保責任」と呼びますが、買手からすれば、プラットフォームを通じて商品を購入しているため、運営会社にも瑕疵担保責任を求めたくなります。
こうした事態に関しては、経済産業省の「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」が、「運営会社は原則として責任を負う必要はないが、運営会社の対応に問題があった場合には、損害賠償義務が発生してしまう可能性がある」と定めています。
このことから、免責事項には以下のように記しましょう。
- 当社は、ご利用者様による本サービスの利用に起因または関連してご利用者様が他のご利用者様に及ぼした損害、ならびにご利用者様と他のご利用者様との間の紛争について、責任を負わないものとします
- 商品の瑕疵や商品の引き渡し、代金の支払等に関する問題が発生した場合、当社に故意・重過失がある場合を除き、当社は責任を負わないものとします
(3)コンテンツ提供サイト
画像や音楽、動画など、何らかのコンテンツをユーザーに提供する場合、そのコンテンツ入手後の取り扱いについて、ユーザー自身が責任を負う旨を明記しておく必要があります。
- ご利用者様がアクセス、ダウンロード、その他の方法でサイトの使用中に、あるいは使用を通じて取得したコンテンツは、ご利用者様自身の裁量とリスクをもって使用されるものとします
(4)課金アプリ
課金アプリの場合、課金要素として独自のコインやポイントなどを発行していることがほとんどでしょう。
独自コインやポイントを使用し、ユーザーが入手したアイテムは、当然そのアプリでのみ利用するものであり、もしもサービスが終了してしまったら、もう使用することができません。
つまり、「これまでユーザーが費やしたお金分のアイテム」が水の泡となってしまうため、ユーザーにとって損害となってしまうのです。
そのため、サービス終了を想定し、ユーザーの損害に対する責任について以下のように明記しておく必要があります。
- サービス終了に伴い、ご利用者様に何かしらの損害が発生しても、当社は責任を負いません
なお、アイテムなどにまだ変換されていない独自のコインやポイントに関しては、サービス終了に伴い、一定期間払い戻しの対応を行わなくてはなりません。
これ自体は免責事項ではありませんが、そうしたコイン・ポイントの取り扱いについても、必ず記載しておいてください。
6 小括

利用規約の免責事項は、事業者の責任範囲を定めるだけでなく、注意事項を記載するなどして、利用上のお願いを提示する場でもあります。
もっとも、あまりに事業者側に有利となる免責事項は、消費者契約法などにより無効となる可能性があるため、ユーザーの利益とのバランスを考慮する必要があります。
自社のサービスに適した免責事項を策定し、できるだけ未然にトラブルを回避することが大切です。
7 まとめ
これまでの解説をまとめると、以下の通りです。
- 「免責事項」とは、サービスなどを利用することで発生しうるトラブル等に関して、損害賠償の責任を制限・免除するためのルールを示した項目のことである
- 免責事項には、留意すべき点や注意ポイントなどを設けることもある
- 事業者側の利益を優先し、ユーザー側が著しく不利になっている条項は、①消費者契約法、②定型約款などにより無効となる
- 「消費者契約法」は、消費者が売買契約などの契約を事業者と結ぶ際、消費者への不当な勧誘や一方的に不利な内容の契約締結などを防止し、消費者の利益を守るための法律である
- 「定型約款」とは、2020年4月1日から施行される改正民法によって規定された利用規約の新ルールであり、「ユーザーの不利益条項が含まれていないこと」がルールとして設けられている
- 免責事項を定めるときは、基本的に①責任の制限、②提供サービスに関するもの、③現状有姿、④機器のトラブル・メンテナンス、などについて策定する
- ビジネスモデルやサービスによって、特に設けるべき免責事項もあるため、十分な検討が必要である
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。