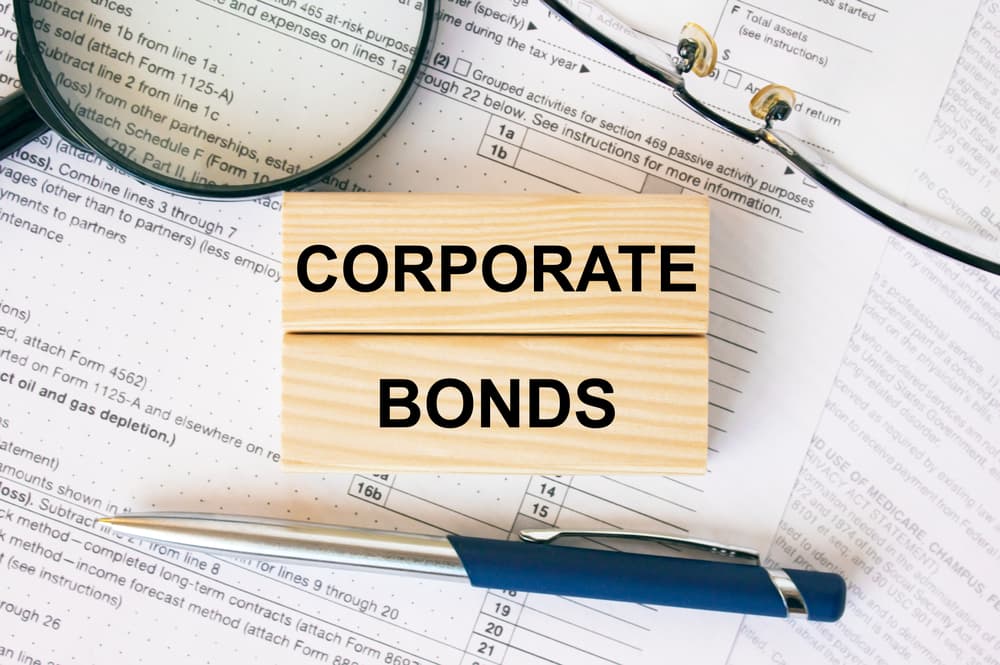おまけ(景品)にも法律の規制がある!?景表法4つのポイントを解説

はじめに
キャンペーンや抽選会などで景品をもらって「ラッキー!」って思ったこと、みなさん1度はありますよね。
本来の目的だった商品よりも景品(おまけ)としてもらったものの方が豪華で、お得感を感じることも少なくありません。
ですが、消費者から見れば、もらって嬉しいはずの景品(おまけ)についても、実は、「景品表示法(けいひんひょうじほう)」(略:景表法)という法律によって一定の規制がされているのです。
「消費者に迷惑をかけるわけでもないのだから、好き勝手やってもいいじゃないか?」、
そう考える方がほとんどですよね。
ではなぜ、景品(おまけ)は、法律で規制されるのでしょうか?
以下では、企業が実際にキャンペーンや抽選会などを企画した場合を念頭に、景表法で定められている景品規制について、その全体像と企業が守るべきポイントを詳しく解説していきたいと思います。
1 景品類とは

まず最初に、景表法で規制される「景品類」とは一体どのようなものなのかを解説していきます。
(1)「景品」の意味
一般的にイメージされる「景品」は、粗品、おまけ、賞品などのことをいいますが、景表法では、「景品」の意味について次のように定められています。
- お客を誘引するための手段として
- 本体商品・サービスの取引に付随して提供する
- 物品・金銭・その他の経済上の利益
- これら3つにあてはまるもののうち、国が指定するもの
①~④すべてにあてはまるものが景表法上の「景品」となり、規制の対象となります。反対に、この4つの条件にあてはまらないものは、景品にはなりません。
「景品」にあてはまると、提供するおまけの価格に上限が付されることになります。
詳しくは追って解説しますが、例えば、「10円のガムを買ったお客さんには、もれなく10万円分のハワイ旅行(おまけ)があたります!」みたいなエゲつないおまけキャンペーンはできません。
このような景品規制がされる理由は、本体商品と比べてあまりに豪華な景品をプレゼントした場合、おまけがなかったら買わないような質の低い商品や、割高な商品を買わされてしまうリスクがあるからです。
本質的には、「品質と価格で勝負する」のが商売の大原則であるから、おまけなどどいう邪道なものでお客を釣ろうとする「コスい」やり方を規制して、健全な競争を守るためです。
それでは、それぞれの要件がどのような内容となっているのか具体的にみていきましょう。
①お客を誘引するための手段として
これは、「お客さんを集めたり、興味を持ってもらうために」という意味です。
「お客を誘引するための手段」かどうかは、事業者がどう思っていたか、という主観ではなく、あくまでも客観的に判断されます。
そのため、例えば、企業としては、お客さんと仲良くなるという目的で景品を提供した場合でも、客観的にみてお客さんを誘引しているように見えたら、①の要件にあてはまってしまいます。
また、新規のお客さんを集めるためではなく、既存のお客リピート率を高めるために景品を提供する場合も「顧客の誘引」にあたるので注意してください。
②取引に付随して提供する
「取引」には、物の売り買いだけでなく、賃貸や交換なども含まれます。
ポイントは、「付随して」の部分です。
「付随して」とは、原則として「この商品を購入したらプレゼントがもらえる!」などのように、「取引」をすることを条件として、おまけを提供する場合を意味します。
ただ、例外として、「取引」が条件となっていない場合でも、以下のように実質的には取引きが条件となっているような場合には、取引に「付随して」いるものとみなされます。
- 商品の包装の一部(裏側など)に懸賞の企画内容などが告知されている場合
- 商品やサービスを購入・利用することによって、懸賞に応募する権利をもらえたり、懸賞クイズのヒントをもらえたりして、賞品を得ることが可能または簡単になる場合
- ECサイトで商品を購入するときに、無料会員になることを条件にして賞品などをプレゼントする場合
「経済上の利益」とは、その価値を現実的にお金に換算することのできるもの、という理解でオッケーです。
ただし、事業者が費用をかけることなくおまけを提供することができたり(=景品の仕入れにお金がかかっていないということ)、通常は市販されておらず、市場価値がつかない物を提供する場合でも、消費者側からみたときに、普通ならお金を支払ってでも手に入れるだろうといえる物であれば、「経済上の利益」に含まれます。
かなり広い範囲のものが「経済上の」利益に含まれるということになりますね。
一方で、表彰状やトロフィーなどように一部のマニアしか欲しがらない物は経済上の利益から除外されます。
④国が指定するもの
これら①~③の要件にあてはまるだけでは、「景品」にはなりません。
①~③に加えて、④として、国が指定したものだけが「景品類」として規制の対象となります。
どのようなものが指定されているかというと、物品や金券、映画のチケットや旅行など、景品としてプレゼントされそうなものは大体含まれています。
指定内容について詳しく知りたい方は消費者庁の「景品規制に関するガイドライン」をご参照ください。
以上の①~④の要件をみたす「おまけ」だけが、景表法上の「景品」として、規制されることになります。
このような「景品」を利用して行われる競争も、それが「適度」に行われている限りは、事業者にとっても消費者にとってもメリットのあるものです。
他方で、事業者が過大な景品を提供することによって消費者が惑わされてしまい、質の良くないものや割高なものを買わされてしまうのであれば、消費者にとってデメリットになります。
また、豪華すぎる景品による競争がエスカレートしてしまうと、事業者は本体の商品やサービスそのものでの競争に力を入れなくなり、これもまた消費者にとってデメリットとなります。
このため、景表法では景品類に上限としてのキャップを設けるなど、一定の規制をすることで、一般消費者の利益を守ると同時に、過大な景品による不健全な競争を防いでいるのです。
(2)「景品類」にあてはまらないもの
次に、一見すると「景品」にあたりそうなのだけれど、実は「景品」にあてはまらない物を確認します。
①値引き
先ほども出てきた「景品規制に関するガイドライン」では、「正常な商慣習に照らして値引きと認められる」場合については、景品類に含まれないとされています。
つまり、普通の「値引き」については景表法の規制対象にはならないということです。
適正な値引きであればそれは商慣習として様々な場面で頻繁に行われていることであって、特に消費者に不利になるものでもないため、わざわざ規制の対象にする必要がないからです。
よくある値引きの例としては、「2つ以上商品を買った人には〇〇円引き!」としたり、「レシートの金額の〇〇%を返金します!」といったケースがあります。
携帯電話を買うときによくみられるキャッシュバックキャンペーンも、原則として「値引き」にあたるため、景表法の規制をうけません。
ただし、キャッシュバックキャンペーンであっても、以下のような場合には、「値引き」とは認められず、「景品」として規制の対象となります。
-
- ⅰ)懸賞によりキャッシュバックを行う場合
-
- 例:くじや抽選によってキャッシュバック行う
-
- ⅱ)キャッシュバックしたお金の使い道を限定する場合
-
- 例:キャッシュバックされたお金が特定の商品やサービスの代金にのみ使える
-
- ⅲ)同じキャンペーン内で他の景品の提供をし、どちらかを選ばせる場合
- 例:キャッシュバックと旅行券のどちらかを選択させる
ⅰとⅲについては、キャッシュバックされるかどうかが確実ではないため「値引き」として認めることはできません。
ⅱについては、本来キャッシュバックされた分については消費者が自由に使えるものであって、それが消費者の期待するところでもあるのに、使い道を限定している時点でもはやキャッシュバックと呼ぶことはできず、「値引き」とは認められません。
このように、キャッシュバックの条件や内容を決めるときには、ちゃんと「値引き」として認められるかどうかを慎重に検討しなければなりません。
「値引き」についてさらに詳しく具体例が知りたい方は消費者庁の「景品規制に関するガイドライン」をご参照ください。
②取引の本来の内容をなすもの
宝くじの当選金や、喫茶店でコーヒーを頼んだ時についてくる砂糖とクリームなどは、それらそのものが取引の内容となっているので、景品類にはあてはまりません。
③仕事の報酬としてもらえるもの
モニターを募集して商品やサービスのアンケート調査を行い、その謝礼として支払われる報酬などは、モニターとしての労力に対する報酬といえるため、景品類にはあてはまりません。
④同一商品の付加
スーツを一着買ったらスペアのズボンをもう一本プレゼントするとか、コーヒーを5杯飲んだら同じコーヒーを1杯無料でサービスするなど、一定の条件をみたす場合に本体商品と同じものを提供するケースでは、経済的には、ある意味値引きと同じと考えられるため、景品類にはあたりません。
ただし、コーヒーを5杯飲んだらジュースの無料券をサービスする場合や、ハンバーガーを買ったらポテトが無料でついてくるなど、別の商品やサービスを提供する場合には「同一商品の付加」にはあたらず、景品類にあてはまるので注意が必要です。
⑤商品を組み合わせて販売することが商習慣になっているもの
車とスペアタイヤのように、ある商品を2つ以上組み合わせて販売するのが当たり前になっているものについては、それぞれが独立した商品なので景品類にはあたりません。
⑥商品を組み合わせることにより独自の機能、効用をもつ商品
プロ野球チップス(ポテトチップスのおまけに野球選手のカードが付いてくるもの)や、食事やお土産が付いてくるパック旅行など、組み合わせによってそれ自体が相乗効果をもって1つの商品になるというものは、景品類にはあたりません。
以上の①~⑥のいずれかにあてはまるおまけについては、「景品」ではないため、景品の上限に制限はありません。
反対に、①~⑥のいずれにもあてはまらない場合には、「景品」として、次の項目で説明する「懸賞」のやり方ごとに、規制される上限の額が変わってきます。
2 懸賞とは

雑誌や新聞、テレビなどでよく見かける懸賞ですが景品を提供する「懸賞」のやり方によって、景品の上限の額やパーセンテージが変わってきます。
懸賞は、大きく分けると、取引を条件とするかどうかによって、
- オープン懸賞
- クローズド懸賞
の2つがあります。
以下で詳しくみていきましょう。
(1)オープン懸賞
「オープン懸賞」とは、特に取引したかどうかに関係なく、誰でも応募できるタイプの懸賞をいいます。募集をかける媒体は、新聞や雑誌、テレビ、webサイトなどを問いません。
だいぶ昔のテレビ番組になりますが、芸人のなすびさんが懸賞だけで生活をするという企画があったのを覚えているでしょうか?
彼は懸賞雑誌にかたっぱしから応募していましたが、あれがまさにオープン懸賞です。
誰でも応募することができるので「オープン」懸賞という名前なんですね。
このオープン懸賞は、「取引に付随」しないため、オープン懸賞で提供されるおまけは、そもそも「景品」ですらなく、景表法による規制がありません。
また、提供する景品類の上限額についても、かつては1000万円までとされていましたが、景品ですらない以上、規制の必要はないとの考えに至り、現在では特に上限の決まりはありません。
(2)クローズド懸賞
「クローズド懸賞」とは、広告主である企業の商品やサービスを購入・利用すること(=取引きすること)を条件に応募することができる懸賞のことをいいます。
オープン懸賞に対し、応募できる人が限られていて、取引が条件となっていることから「クローズド(=closed、閉じられたという意味)」懸賞といいます。
それでは次の項目で、クローズド懸賞の具体的な内容についてみていきましょう。
3 クローズド懸賞の景品規制

クローズド懸賞は、そのやり方や景品の付け方によって3種類に分かれています。
そして、それぞれ「景品類自体の上限額」と「すべての景品類の総額」に上限を設けています。
それでは順番に説明していきます。
(1)一般懸賞
「一般懸賞」とは、一つの企業が、自社の商品やサービスの利用者に対して行う懸賞のことをいいます。
一般懸賞では、くじ引きなどの偶然性を利用したり、特定の行為の優劣などによって景品類の提供をします。
例えば、コンビニで商品を一定の金額分購入するとくじが引けたり、商品のバーコードや応募シールをはがきに貼って応募するタイプのものがこれにあてはまります。
また、最近よくあるケースとして、有料アプリの販売キャンペーンで、アプリを買った人がそのプレイ動画をSNSなどのキャンペーンサイトに投稿すると、抽選でプレゼントがもらえる、というものがあります。
このケースも一般懸賞にあてはまります。
一般懸賞では、①本体商品の取引価額(値段【税込】)を基準として、景品自体の上限額と、②そのキャンペーンにかかる本体商品の総売上(予定)のかねあいで、景品総額の限度額が決められています。

景品の限度額は、本体商品の取引価額(値段【税込】)が
- 5000円未満の場合には、その20倍まで
- 5000円以上の場合には、10万円まで
となっています。
また、懸賞で提供されるすべての景品の総額は、
- その懸賞に関する売上予定総額の2%まで
となっています。
例えば、1個500円の商品を買うとくじが1回引ける場合には、取引価額は、「500円」となるので、「5000円未満」にあたります。そのため、景品1つにつき、「20倍まで」の景品なら提供できるため、その上限額は1万円(500円×20)となります。
そして、仮に、本体商品の売上予定総額が1億円であれば、当たりくじでプレゼントするすべての景品の総額は1億円×0.02=200万円が限度額となります。
(2)共同懸賞
「共同懸賞」とは、複数の企業が共同して、商品やサービスの購入者・利用者に対して行う懸賞のことをいいます。
例えば、商店街やショッピングモール、地下街などの店舗が共同して行う母の日キャンペーンや、全国のカメラメーカーが共同して行うカメラ祭りなどがこれにあたります。
一般懸賞との違いは、懸賞を実施する企業が1社なのか複数なのかという点にあり、そのほかの実施方法や応募方法などは一般懸賞と変わりありません。
そして、共同懸賞では、本体商品の取引価額(値段【税込】)に関係なく、①本体商品の取引価額(値段【税込】)を基準として景品自体の上限額と、②そのキャンペーンにかかる本体商品の総売上(予定)を基準として景品総額の限度額が決められています。

共同懸賞では、複数の企業で共同して懸賞を行うため、懸賞の規模も大きくなると考えられます。
そのため、その上限額についても一般懸賞より高く設定されています。
景品自体の上限額は、
- 取引価額にかかわらず30万円
すべての景品の総額は
- 売上予定総額の3%まで
となります。
例えば、先ほどと同じように1個500円の商品を買うとくじが1回引ける場合でも、共同懸賞では景品自体の限度額が30万円となります。
また、こちらも先ほどと同じように1万個販売する場合でも、本体商品の売上総額は1億円×0.03=300万円までとなります。
(3)総付景品
「総付景品(そうづけけいひん)」とは、ある商品を買ったりお店に来店するなどの、一定の条件をみたした人全員にもれなくプレゼントされる景品のことをいいます。
「全員もれなく景品がもらえる」という特徴から、「ベタ付け景品」とも呼ばれています。
一般懸賞や共同懸賞と違って、くじ引きや抽選(=偶然性)によって景品がもらえるか決まるわけではないので、細かく言うと懸賞にはあたりませんが、この総付景品も景表法の規制の対象となっています。
例えば、ヤマザキ春のパン祭り(ある点数を集めると必ずお皿がもらえる)や、携帯電話の新規加入でもれなく〇〇グッズのプレゼントなどが総付景品にあたります。
また、ここ数年女性誌についてくる豪華な付録が注目を集めていますが、この付録も総付景品にあてはまります。
総付景品では、本体商品の取引価額(値段【税込】)を基準として、
- 1000円未満の場合には、200円まで
- 1000円以上の場合には、20%まで
が景品の上限額となっています。
また、一般懸賞や共同懸賞と違って、本体商品の予定売上総額については上限がありません。

例えば、商品を1万円以上購入した人にはもれなく景品をプレゼントする場合、取引価額は「1万円」となり、景品の上限額は、本体商品の値段の「20%」となるため、2000円(1万×20%)となります。
他方で、500円分の商品を購入した人にもれなく景品をプレゼントする場合、取引価額は「500円」となり、景品の上限額は、「200円」となります。
なお、「全員がもれなくもらえる」ものであっても、講習会の教材や旅館・ホテルへの送迎サービス、ラジオを買ったときについてくる乾電池などは「商品に付随する一連のサービス」であるとして、総付景品にはあてはまりません。
また、プレンゼントキャンペーンの中には、購入金額にかかわらず商品を買った人に景品をプレゼントする場合も考えられます。
このケースでは、取引価額の計算が困難なため取引価額は、一律に原則100円とみなされ、その結果、「1000円未満」の規制と同じように、景品の上限額は200円までとなります。
ただ、例外として、その店では価格が1万円未満のものは扱っていないなど、最低購入額が1万円以上と分かっている場合には、反対に、「1000円以上」の規制が適用され、景品の上限額は、その20%の2000円(1万×20%)となります。
4 ペナルティ
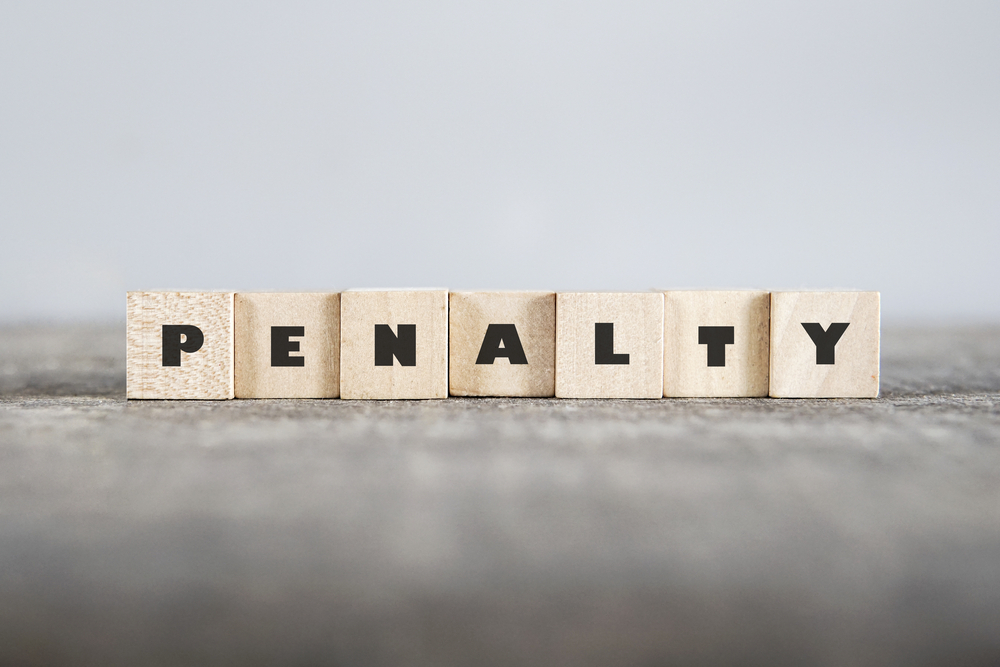
それでは、これまで解説してきた景品規制のルールに違反してしまった場合、どのようなペナルティがあるのでしょうか?
景表法に違反している疑いのある場合、お役所は、事業者への事情聴取などの調査を開始します。
調査の結果、景表法違反の行為があると認められると、事業者にはまず言い訳のチャンス(=弁明の機会)が与えられます。
ここで上手く言い訳ができずに景表法違反と認められてしまうと、「措置命令」が行われます。
措置命令の内容としては、違反したことを一般消費者に知らせることや、再発防止策をすることなどがあります。
そして、この措置命令に従わなかった場合、
- 最大2年の懲役
- 最大300万円の罰金
のどちらかまたは両方が科せられるリスクがあります。
そして、措置命令は、消費者庁のウェブサイトに企業名とともに公表されます。
細かい事実関係や違反行為の態様まで載せられてしまうため、それが世間に広まってしまえば企業にとっては信用を大きく落とすことにもなり、ダメージは大きいといえます。
景表法は、消費者を守ることを目的としているので、キャンペーンなどを行う事業者がついうっかり違反してしまった場合でも、違反した事実さえあれば措置命令が出されてしまいます。
知らないうちに違反していたということの無いよう、景品の上限額などはあらかじめ確認しておくことをお勧めします。
5 具体例の検討(ポイントサービスを例に)

これまで、景品規制の全体像をみてきましたが、具体例をみるとよりわかりやすいので、 普段私たちがよく利用するポイントサービスを例に、実際の景品の限度額の設定方法などについて、詳しく解説していきます。
まず前提として、ポイントサービスにおける「ポイント」は、景品やおまけとして利用者に発行されるものであって、これが景表法上の「景品」にあてはまる場合には、景表法の規制対象となり、上限がつけられます。
つまり、ポイントの最高額や総額が制限される可能性があるということですね。
景品類にあたるかどうかの判断基準はすでに説明したとおり、以下の4つになります。
- お客を誘引するための手段として
- 本体商品・サービスの取引に付随して提供する
- 物品・金銭その他の経済上の利益
- これら3つにあてはまるもののうち、国が指定するもの
それでは以上の点を踏まえたうえで、次の3つのケースについてみていきましょう。
(1)「値引き」にあたり「景品」にならない事例
- 事例1:商品を1000円分買うごとに200ポイントもらえて、そのポイントは1ポイント1円としてその店の買い物で利用できる(自社ポイントの発行)
まずはじめに、ポイントが景品にあたるのかどうかを考えます。
ポイントサービスは、販売促進や顧客の囲い込みのために導入するもので、①消費者を誘引するための手段であるといえます。
また、利用者が商品を買ったりサービスを受けるときに景品やおまけとしてポイントが発行されるので、②取引に付随して提供する、③経済上の利益ということができます。
これだけ見ると、ポイントはまさに「景品」にあたるようにも思えますね。
ただし、「景品」といえるためには、①~③にあたるもののうち「国が指定するもの」でなければならず、「値引き」については「景品類」にはあたらないものとされていましたね。
つまり、ポイントサービスが「値引き」であるといえる場合は、規制の対象にはなりません。
そこで次に、どのようなものが「値引き」にあたるのかを考えます。
これについては消費者庁の「値引きに関するガイドライン」があり、その中で、「値引き」とは、「取引の相手方に対して支払うべき対価を減額すること」と定められています。
つまり、ポイントの利用がいつであっても、商品の代金からポイント分の値段が引かれ、本来の価格よりも下がるのであれば、それは「値引き」にあたるということになります。
ですので、今回のケースのように、発行されたポイント分が事業者自身の商品やサービスから減額される場合には、そのポイントサービスは「値引き」であるといえ「景品」にはあたりません。
「景品」にあたらないので、もちろん上限規制にはかかりません。
(2)「総付け景品」にあたる事例
- 事例2:商品を1000円分買うごとに200ポイントもらえて、そのポイントは1ポイント1円として他社のポイントと交換できる(他社ポイントの発行)
今回のケースでは、貯まったポイントは「他社」のポイントと交換することしかできないため、(1)とは違い、ポイントを発行した「事業者自身の」商品やサービスについて減額されるとはいえません。
このようなポイントサービスは「値引き」にはあたらず、「景品」として上限規制の対象となります。
そして、ポイントをためることによって全員もれなく「他社ポイント」という景品がもらえるため、「総付景品」として規制されることになります。
総付景品は、取引価額が1000円以上の場合、景品の上限額はその20%まででした。
今回のケースでは、1000円の取引額に対して200円分の価値を持つ200ポイントが発行されるため、上限の範囲内として景表法に違反していないことになりますね。
(3)「一般懸賞」にあたる事例
- 事例3:100円につき1ポイントがもらえて、100ポイントたまると抽選券と交換でき、抽選の結果ハワイ旅行などが当たる
今回のケースでも、貯まったポイントは抽選権と交換することとなっていて、ポイントを発行した事業者自身の商品やサービスについて減額されるとはいえません。
そのため、「値引き」にはあたらず、「景品」として上限規制の対象となります。
そして、貯めたポイントは抽選権と交換でき、抽選の結果ハワイ旅行などが当たる仕組みとなっているため、このようなポイントサービスは「一般懸賞」として規制されます。
次に、取引価額がいくらになるのかを計算します。
取引価額によって景品の上限や総額の上限が変わってくるので、重要です。
今回のケースでは、100円につき1ポイントもらえて、それが100ポイント貯まると抽選券と交換することができるので、100円×100ポイント分=「1万円」が取引価額となります。
その結果、取引価額が「5000円以上」の場合となるので、抽選の結果提供する商品やサービスの価格は「10万円以内」に収める必要があります。
また、すべての景品の合計額についても規制がかかるため、対象商品の「売上予定総額の2%以内」となるように設計する必要があります。
6 小括

このように、景品(おまけ)を配布する場合には、上限をはじめ様々な規制があります。
自分たちが行おうとしているキャンペーンや抽選が規制の対象となるのかをまずは確認して、仮に規制対象となるのであれば、それぞれの上限を踏まえた上で景品の内容を考える必要がありますね。
7 まとめ
これまでの内容をまとめると以下の通りです。
-
- 「景品類」とは、
①消費者を誘引するための手段として
②事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する
③物品・金銭その他の経済上の利益
④これら3つにあてはまるもののうち、国が指定するもの
-
- 懸賞にはオープン懸賞とクローズド懸賞があり、規制の対象となるのはクローズド懸賞
- クローズド懸賞は次の3種類に分かれる
①一般懸賞
②共同懸賞
③総付景品
- ポイントサービスは、付与したポイントの使わせ方によって規制の有無やその種類が変わってくるので注意
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。