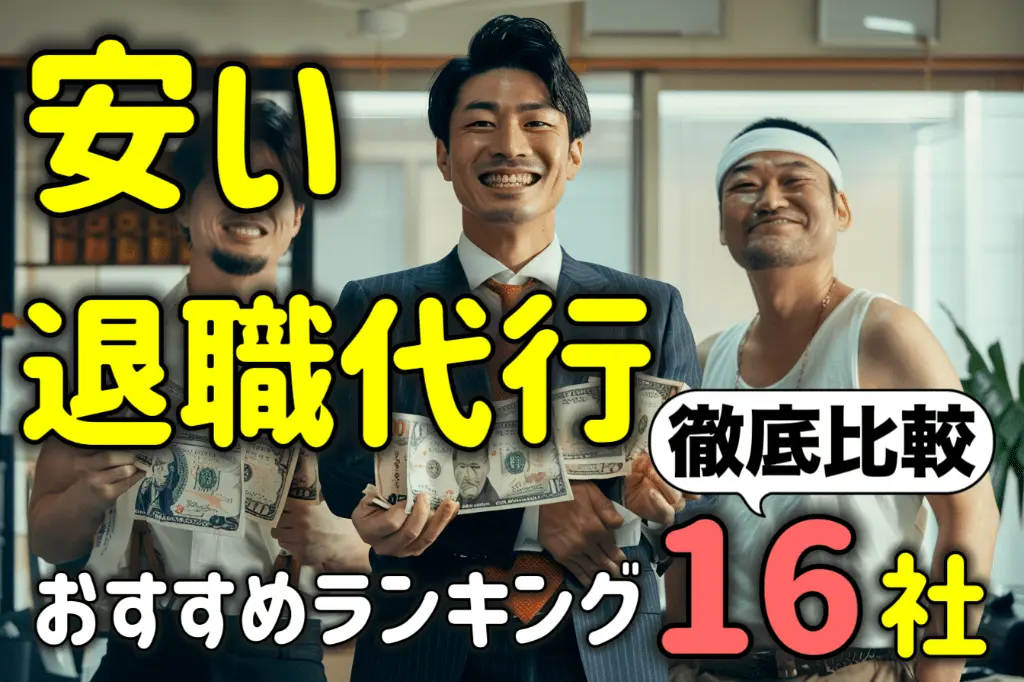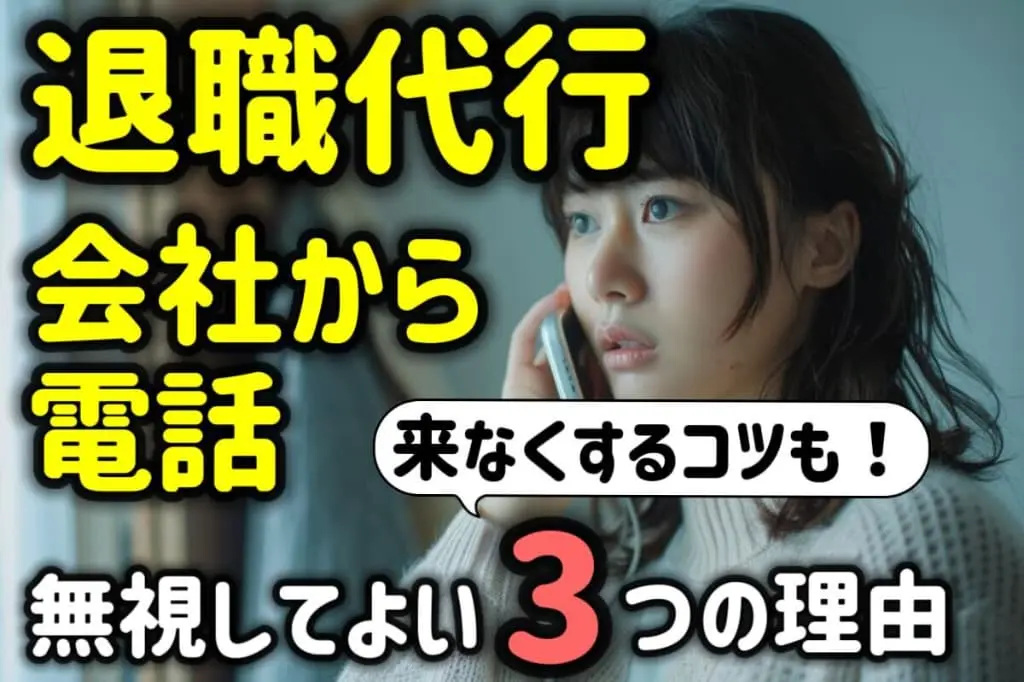【テンプレート有】特定商取引法に基づく表記の書き方13のポイント

はじめに
他社のサイトをみると、webページのフッター部分に「特定商取引法に基づく表記」という記載を見たことがあるのではないでしょうか?
そこをクリックすると会社の名前や住所、電話番号、商品・サービスの価格、返品の可否などが記載されています。
この表記のことを「特定商取引法に基づく表記」といいます。
自社でアプリやECサイトなどのサービスを提供しようとする場合には、この「特定商取引法に基づく表記」というものを作らなければなりません。
ただ、作ると言っても、実際に何をどのように書くべきなのか、正直よくわからないですよね。
わからないので、とりあえず他社HPに掲載ているものを適当にマネするか、ネットに転がっているテンプレート・雛形を少しいじって作るといった企業がほとんどではないでしょうか?
しかし、特商法には、厳格なルールがあり、記載しなければならない項目は、企業のビジネスモデルによって微妙に違います。
そのため、他社のものを適当にマネしてそれらしいものができあがったとしても、よくよく見ると、必要な表記に“モレ・ヌケ”があり、お役所の方から厳しいお叱りを受けるケースが後を絶ちません。
実は、このルールをきちんとと守らないと、
- お役所の方から、「業務停止命令」を受けたり、
- 「社名公表」という恥ずかしめをうける
- 悪質な業者については、刑事罰として、最大で2年間の懲役刑を受ける
ことがあります。
そこで、今回は、アプリ・WEBサービスなどを始める際に必要な「特定商取引法に基づく表記(表示)」について解説していきます。
1 特定商取引法に基づく表記とは

(1)特定商取引法とは
事業者と消費者との取引に代表される「BtoC(Business to Consumer )」取引では、消費者の方がパワーが弱く、情報弱者で、セールストークにダマされやすい、と考えられています。
このBtoC取引について何もルールがないとすると、事業者が好き勝手やりたい放題したり、消費者が大して欲しくないものを無理やり買わされたり、欲しいものであってもあり得ない高値で買わされたりしてしまう・・・という事態になりかねません。
そこで、こういった事業者による横暴を禁止し、弱い立場にある消費者を守るために、消費者からみて有益な情報の公開を義務付けたのです。
それが、「特定商取引法」(略して、「特商法」といいます。)という法律です。
特商法では、化粧品や布団などの訪問販売、Amazonや楽天などの通信販売、引越し業者や健康食品などの電話勧誘販売など、トラブルが起きやすい販売方法について規制をしています。
(2)「特定商取引法に基づく表記」の意義
「特定商取引法に基づく表記」とは、特にAmazonなどの通信販売をしている事業者に課せられている義務で、商品・サービスの値段や返品に関する情報など、ユーザーが特に関心のある情報を一覧化したものです(例:アマゾンの特定商取引法に基づく表記)。
具体的には、
- 販売価格
- 代金の支払い時期、方法
- 商品の引渡し時期
- 事業者の氏名
- 業務責任者の氏名
などを広告に表示することが義務付けられています。
では、なぜこのような表記が必要なのでしょうか?
その理由は簡単です。
例えば、Amazonで何か商品を購入するとします。
その際、店頭での購入とは違って直接顔を合わせることはなく、私たちはネット上の情報だけを頼りに、モノを売り買いします。
顔の見えない事業者と取引をするのは、ユーザーからみたとき、とても不安ですよね。そのため、ユーザーが安心して取引できるようにするために通信販売をする際には、事業者の住所地や商品の金額、支払い方法などを表示する義務を事業者に課したのです。
実際に自分がモノを買ったときのことを考えると、きちんと情報を開示してくれているネットショップの方が信頼できますよね。
みなさんがよく利用するネットショップにも必ずこの記載があると思うので、一度参考にしてみてもいいと思います。
2 どういう場合に特定商取引法上の表記が必要なのか?~通信販売~

さて、「特定商取引法に基づく表記」が求められるケースはAmazonやジャパネットタカタなどのような「通信販売」のビジネスをする場合です。
「通信販売」とは、インターネット、やカタログ・チラシなどの「広告」を通じてユーザーから注文を受け、商品やサービスを提供する販売方法のことをいいます。
「広告」の媒体については特に制限がないため、新聞や雑誌の広告だけではなく、テレビ放送、新聞の折り込みチラシ、web上のホームページ、ダイレクトメール、電子メールなどに表示される広告も含まれます。
その結果、有料アプリやアプリ内課金機能のあるアプリについても、ホームページなどで以下のような形で掲載する場合には、「広告」として、通信販売にあたり、「特定商取引法上の表記」必要になります
 出典:メルカリ
出典:メルカリ
※矢印のあるところが主に、「広告」と認定されます。その結果、メルカリのホームページ内(ピンク色の囲み部分)に、「特定商取引法上の表記」を掲載しているわけです。
そもそも、日本国内で有料アプリや課金機能のあるアプリを販売する場合、サポートサイトやアプリの中に、特商法の規定に従って、特定の情報(アプリの売り手の名前、住所、連絡先情報など)を表示することを求めています。
一方Google Playでは、有料アプリの開発者に対して住所(所在地)の公開が義務付けられていますが、「日本国内でアプリを販売する場合」という条件は付いておらず、特商法との関連についても明らかにされていません。
いずれにせよ、アプリの開発をする際には、特定商取引法上の表記が求められることがあるので、注意が必要です。
3 ペナルティ

では、仮に特定商取引法に基づく表示義務に違反してしまった場合、どのようなペナルティがあるのでしょうか。
実は、表示義務に違反してしまったとしても特に罰則(刑事罰)はありません。
しかし、表示義務に違反し続けていると
- お役所から厳重注意をうけたり、
- ひどいケースでは業務停止処分、
- 社名公表
といったペナルティが課されます。
このような事態になると会社の信用を著しく落とすことになるので、消費者からの信頼を得るためにも、きちんと情報開示をしておくべきです。
また、特定商取引法に基づく表記のルールとは別の話になりますが、商品・サービスを売りたいがために、「盛りすぎ広告」をしていると、特商法上の誇大広告の禁止規定に違反してペナルティを受けてしまうこともある点には、注意が必要です。
この場合、重いものだと業務停止命令を受ける可能性があるため、いずれにせよ、情報は正確にわかりやすく表示することが必要ですね。
4 テンプレートのダウンロード

さて、自社のアプリ・webサービスに「特定商取引法に基づく表記」が必要な場合の表記の書き方を解説していきます。
ゼロベースから練り上げるのは大変なので、「特定商取引法に基づく表記」の無料のテンプレートをご用意いたしましたので、ご自由にダウンロードしてください。
主にアプリサービス提供をする場合の表記内容となっております。
【ひな形】特定商取引法に基づく表記
5 「特定商取引法に基づく表記」の書き方

それではテンプレートを参考にしながら、「特定商取引法に基づく表記」の各項目について詳しく見ていきましょう。
(1)提供するサービスの名称
- アプリ名:〇〇〇〇
まず最初に、提供するサービスの名前を書きましょう。
(2)販売事業者名(法人の名称)
- 販売事業者名(会社名):株式会社トップコート
販売事業者の正式名称を書きましょう。
法人の場合は、登記されている名称を書きます。
通称や、商業登記されていない屋号のみを表示することは認められません。
個人事業主の場合は、氏名または登記された商号を記載します。
個人情報がばれてしまうためフルネームを出したくないと思うかもしれませんが、氏名を表示する場合は戸籍上の氏名を表示しなければなりません。
(3)代表者名(責任者名)
- 代表者名:代表取締役○○ ○○
販売事業者の代表者名か本サービスの責任者の名前を書きましょう。
必ずしも代表権を有している必要はありません。
個人事業主の場合は、先ほどと同様に自分のフルネームを書きます。
(4)所在地
- 所在地:〒○○○-○○○○ 東京都港区○○○○ー○○
事業者の所在地を書きます。
個人事業主の場合、個人の住所を載せることが多いと思いますが、それが自宅の住所である場合、重要な個人情報を公開することになるため抵抗を感じる方も多くいらっしゃると思います。
このような場合に、仮の住所としてバーチャルオフィスの住所を記載することができるのか、という問題があります。
結論から言いいますと、仮の住所の記載は可能なのですが、その場合には、
- それがその販売業者のものではないこと
- 消費者からの請求によって正確な住所を記載した書面をすみやかに交付し、または住所を記録した電磁的記録をすみやかに提供すること
を表示する必要があるとされています。
(5)問い合わせ先
-
- お問い合わせ:こちら(****@****.co.jp)からお問い合わせください。
- ※弊社電話番号はお客様からのご要望に基づき遅滞なく電子メールにて通知いたします。弊社電話番号が必要なお客様は上記フォームよりお申し出ください。
お客様からの問い合わせ先を書きましょう。
電話番号を直接載せてもかまいませんが、いたずら電話などが心配な場合はテンプレートのようにメールでの通知をおすすめします。
(6)販売価格(代金・利用料)
- 販売価格:購入手続きの際に画面に表示されます。消費税は内税として表示しております。
基本的に、商品そのものの販売価格を書きます。
事業者が消費者から消費税も徴収する場合には、消費税を含んだ価格を意味します。
テンプレートのように別途明記するものアリです。
(7)ユーザーが負担すべき金銭(通信料、送料等)
- 販売価格以外でお客様に発生する金銭:当サイトのページの閲覧、コンテンツ購入、ソフトウェアのダウンロード等に必要となるインターネット接続料金、通信料金は、お客様のご負担となります。
アプリをダウンロードするときやアプリ起動中って、ネットの通信費がかかりますよね。
こういった通信費のように、商品やサービスを買う際などに、本体の商品とは別に、ユーザーにかかる費用がある場合には、その金額をすべて表示する必要があります。
例えば、ネットの通信費、工事費、設置費、代金引換手数料などです。
-
- 【ダメな表示例】
- 送料のほか、常識の範囲内での梱包手数料をいただきます。
上に挙げた例は、箱詰めや設置が必要な商品を売るケースになりますが、アプリを提供する場合であれば、テンプレートのようにサイトの閲覧やダウンロードに必要な通信料金は消費者負担になることを記載しましょう。
(8)代金の支払い方法
-
- お支払方法:以下のいずれかのお支払方法をご利用いただけます。
-
- ・各種クレジットカード
-
- ・携帯電話の料金回収サービス
- ・その他、購入にかかる決済を代行する会社が提供するお支払方法
ここでは代金の支払い方法をすべて書きましょう。
他の支払い方法があるのに、ここに一部の支払い方法しか載せないというのは認められません。
(9)商品の購入方法
- 商品購入方法:App Store・Google Playで提供する各アプリケーションの詳細ページから「購入」ボタンを押下し、各種お支払方法で決済していただきますと、アプリケーションがダウンロードできるようになります。
商品の購入方法を記載します。
アプリなどの提供媒体や、ダウンロード方法を表示しましょう。
(10)商品の利用が可能となる時期
- デジタルアイテム等の利用が可能となる時期:特別な定めを置いている場合を除き、お支払い手続き完了後直ちにご利用いただけます。
購入された商品の利用可能時期を書きます。
アプリの提供の場合、テンプレートのように支払い手続き完了後に直ちに利用できるケースがほとんどでしょう。
(11)アプリケーション等の動作環境
- 動作環境:アプリケーションによって利用環境・対応機種が異なります。各アプリケーションのダウンロードの前に、必ず各アプリケーションの詳細ページで利用環境・対応機種をご確認ください。
動作環境について書きます。
アプリの中には、App Storeでのみダウンロードできて、Google Playではダウンロードできないなど、デバイスの種類や状況によって、利用できないものが多くあります。
そのため、アプリの動作環境(アプリを使用できるOS・CPUの種類やメモリの容量など)についての情報が必要になります。
(12) 返品・キャンセルについて
-
- 返品・キャンセル
-
- 1.お客様のご都合による返品・キャンセル
-
- 商品の性質上、各アプリケーションご購入後の返金・返品はできかねます。あらかじめ月額コース対象コンテンツ、利用環境・対応機種および各アプリケーションの利用環境・対応機種をよくお確かめの上、お申込み、もしくはご購入願います。
-
- 2.アプリケーションの瑕疵に基づく返品(キャンセル)
-
- アプリケーションに瑕疵が発見されたときは、瑕疵を修補したアプリケーションをアプリケーションのバージョンアップ又はその他適切な方法で提供いたします。
- 3.その他、App Store・Google Playなどの各アプリケーション提供サイトの取り決めに従うこととします。
返品・キャンセルについて表示します。
返品やキャンセルを認めるか否か、その条件は何か、送料の負担の有無などを記載しましょう。
また、商品に瑕疵があった場合の事業者の瑕疵担保責任についても定める場合はここに表示しましょう。
- 【ダメな表示の例】
- ノークレーム、ノーリターン
- 返品不可
⇒瑕疵がない場合の返品の可否についても明確に表示しましょう。
(13)販売数量の制限等、特別な条件
-
- 特別条件
-
- 1.クーリングオフについて
-
- 特定商取引法に規定されているクーリングオフが適用されるサービスではありません。
-
- 2.定期課金方式の注意事項
- 契約期間途中の解約となった場合も契約満了日までの料金が発生し、日割生産等による返金を含めた一切の返金は行われません。この場合、サービスも契約満了日まで提供されます。
上記項目以外になにか特別な条件がある場合にはここで表示します。
テンプレートのようにクーリングオフについて記載したり、そのほか、未成年者が契約する場合に保護者の許可を得ることなどを記載しましょう。
6 どこに掲載すればいいのか?

「特定商取引法に基づく表記」は、わかりやすい表現で、かつ、消費者がすぐに見つけられる場所に掲載しましょう。
なぜなら、「特定商取引法に基づく表記」は、アプリなどのサービスを買う際に、ユーザーが知りたい情報を盛り込んだものなので、見えにくい場所に置かれていたのでは、ユーザーにとって意味をなさないからです。
具体的には、
- 「特定商取引法に基づく表記」について、専用のページを設ける
- その上で、商品の購入ページに「特定商取引法に基づく表記」へのリンクを用意する
- さらに、トップページにも「特定商取引法に基づく表記」へのリンクを用意する
という3つのポイントを守りましょう。
特商法では、表記をホームページ上のどこに掲載すべきか?については特に決められていないため、どこに「特定商取引法に基づく表記」をするかは事業者の自由です。
しかし、ユーザー目線に立ち、トップページやその他のわかりやい場所に一括して表示させるなど、誤解のない様な見やすい場所に表示をすべきですね。
7 まとめ
これまでの解説をまとめると、以下ようになります。
- 「特定商取引法に基づく表記」とは、消費者が安心して取引できるよう、事業者に義務付けられた情報の表示義務のこと
- 「特定商取引法に基づく表記」は、通信販売、要するに、ネットなどを使って商品を売る場合に必要になる
- 有料アプリ・課金機能のあるアプリは、通信販売にあたり、「特定商取引法に基づく表記」が必要
- 表示義務に違反したとしても刑事罰はないが、業務停止や社名公表などのペナルティがあるため、消費者の信頼を得るためにもきちんと情報開示をすべき
- 「特定商取引法に基づく表記」は、わかりやすい表現で、消費者が簡単に見つけられる場所に掲載すること
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。