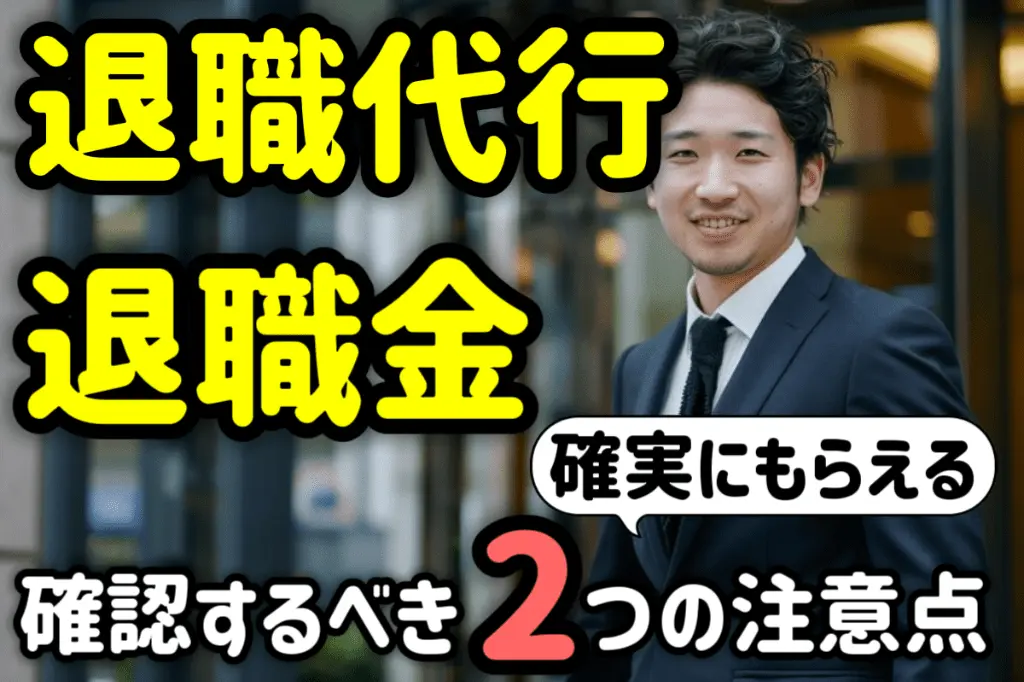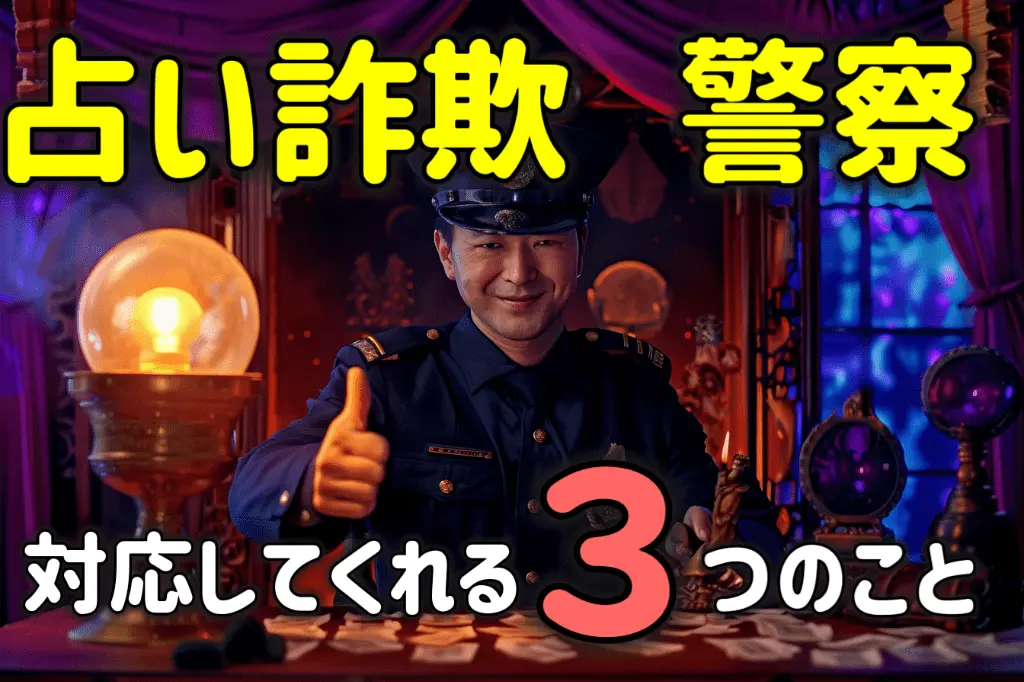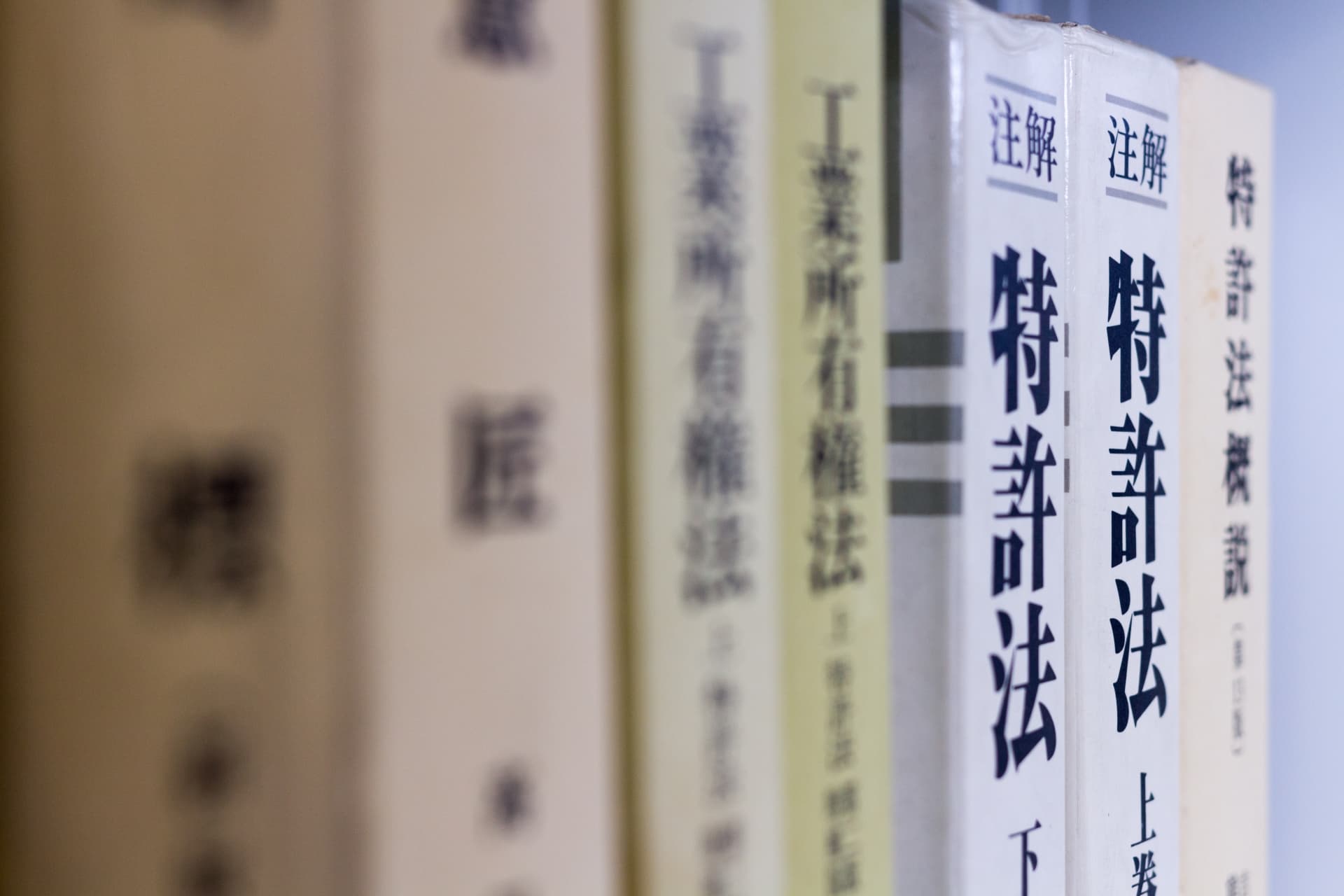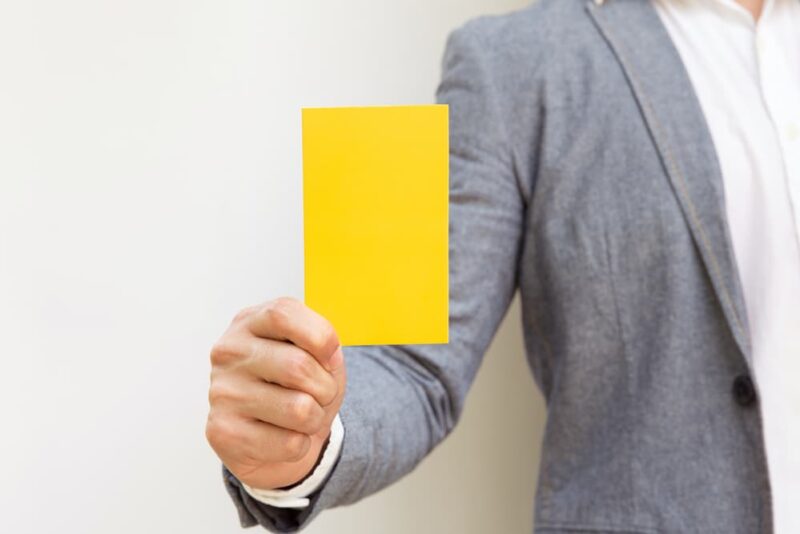景品表示法が規制する景品の金額は?3つの類型ごとに上限などを解説

はじめに
魅力的なノベルティ―を商品に付けたり、購入者を対象として景品が当たるくじ引きを実施したりすることは、消費者を引き付ける販売促進方法の一つです。実際に「おまけにつられてつい商品を買ってしまった」という消費者の声も少なくありません。
とはいえ、商品にはどんなおまけをつけても良いのでしょうか?
よく「豪華賞品をプレゼント!」といったキャンペーンが見受けられますが、仮におまけの価値が程度を超えて高価になってしまうと、消費者は合理的な判断に基づいて商品を選択できなくなるおそれがあります。
このようなことがないよう、商品などに付随する景品類の金額について、一定のルールを設けているのが「景品表示法」です。
この記事では
- 「景品」とは?
- 総付景品の限度額
- 懸賞の限度額
- 違反者に対するペナルティー
などについて、弁護士が詳しく解説します。
1 景表法とは
「景品表示法(景表法)」は、商品やサービスの広告に係る表示やおまけ(景品類)について規制する法律です。
この記事では、「おまけ(景品類)」に関する規制にフォーカスしてご説明します。
景表法上の「景品類」は、以下の4つの条件をすべて満たすものをいいます。
- 顧客を誘引するための手段であること
- 事業者が自己の供給する商品またはサービスの取引に付随して提供すること
- 物品、金銭その他の経済上の利益であること
- 上記3つに当てはまるもので、内閣総理大臣(国)が指定するもの
具体的には、下記のようなものが「景品類」にあたります。
- 物品および土地、建物その他の工作物
- 金銭、金券、預金証書、当選金付き証票および公社債、株券、商品券その他の有価証券
- 映画、演劇、スポーツ、旅行その他催し物等への招待または優待など
- 便益、労務その他サービス
景表法が規制する景品類は、さらに以下の2つの種類に分かれています。
- 総付景品(ベタ付景品)
- 懸賞
次の項目から順番に説明していきます。
2 総付(ベタ付)景品
「総付景品」とは、懸賞によることなく、商品・サービスの購入者や利用者、来店者などにもれなく提供する景品です。「先着順●名様」などと、決まった人数に提供される景品類も、原則として、総付景品にあたります。
たとえば、以下のようにして提供される粗品や賞品などは、総付景品にあたります。
- 開店当日に来店した全員に粗品をプレゼント
- 先着●名様に賞品をご提供
- 申込者全員に記念品を送付
- 賞品Aをご購入の方全員に粗品Bを贈呈
消費者などに総付景品を提供する場合には、限度額を守る必要があります。ここでいう限度額は、総付景品をつける商品・サービスの価格(取引価格)が「1000円未満か、1000円以上か」で決められます。
下記の表を参考にしてみてください。
3 懸賞
 「懸賞」は、応募をすれば必ず貰えるものではなく、抽選やクイズの正答、ゲームの勝ち負けなどに応じて景品類が提供されます。
「懸賞」は、応募をすれば必ず貰えるものではなく、抽選やクイズの正答、ゲームの勝ち負けなどに応じて景品類が提供されます。
このように、懸賞は偶然性や優劣が関わるため、応募者に必ず「当たり」や「景品を貰う権利」が発生するわけではありません。
ここでいう「懸賞」には下記の2つの種類があります。
- オープン懸賞
- クローズド懸賞
それぞれ詳しく解説します。
(1)オープン懸賞
「オープン懸賞」とは、メディアやインターネットのWebサイトなどで、対象を特定しない形式で応募者を募り、郵便やメール、SNS、応募フォームなどで申し込みを可能とするものをいい、当選者は抽選で決まります。
オープン懸賞については、景表法上の規制を受けません。
オープン懸賞では、事業者と応募者の間になんらかの取引があることを必要とせず、誰でも応募することができるためで、景表法上の「景品」に当たらないというのが理由です。
そのため、オープン懸賞を企画する場合、事業者は高額商品を提供することも可能です。
(2)クローズド懸賞
「クローズド懸賞」とは、景品を提供する事業者と応募者の間に取引が発生することが条件になる形式の懸賞のことをいいます。
限定的な条件の下で応募できる懸賞であることから「クローズド懸賞」と呼ばれます。
クローズド懸賞により提供される景品は、景表法上の「景品類」にあたるため、同法により規制されることになります。
クローズド懸賞は、さらに次の2種類に分かれます。
- 一般懸賞
- 共同懸賞
順番に見て行きましょう。
①一般懸賞
「一般懸賞」とは、事業者が単体で実施する懸賞のことをいいます。
一般懸賞の例としては、たとえば、次のようなものがあります。
- 一定金額以上の商品購入でもらえる抽選券
- 一定金額以上を購入したレシートを添付することを条件とした応募
- 飲料のフタの裏などに付いている景品
- クイズなどの正解者に当たる景品
- じゃんけんやゲーム、競技の優劣に応じて貰える景品
一般懸賞によって提供される景品に対しては、取引価格(本体商品やサービスの取引価格)に応じて、その限度額が定められています。
具体的には、以下の表のとおりです。
このように、一般懸賞における景品は、取引価格が5000円未満となるか5000円以上となるかによって、その最高額に違いがあります。
また、景品の総額についても、「懸賞に係る売上予定総額の2%」という限度額が設けられているため、注意が必要です。
たとえば、以下の図のように、100円分の商品を購入するごとにくじを1回引けるキャンペーンがあったとしましょう。
この場合、取引価格は100円であるため、提供できる景品の最高額は100(円)×20=2,000(円)ということになります。
②共同懸賞
「共同懸賞」とは、複数の事業者が共同で実施する懸賞のことを言います。事業者が複数参加するため、金額や規模も一般懸賞より大きくなることが特徴です。
共同懸賞の例としては、たとえば、次のようなものがあります。
- ショッピングモールに入居する複数店舗が共同で開催する福引
- 商店街にある複数の店舗が開催するくじ引き
- 地域の同業者が複数参加する懸賞
共同懸賞によって提供される景品については、一般懸賞とは違い、取引価格を問わず、最高額は一律で30万円と決められています。
具体的には、以下の表のとおりです。
4 業種別の景品とは
特定の業種に係る景品については、別途景品への規制が設けられています。
景品付販売は、その実態が多岐にわたっており、それらを一つの法律で画一的に規制することにはなじまないため、公正取引委員会が必要に応じて制限や禁止を設けたものです。
具体的には、下記の4つの業種が指定されています。
- 新聞業
- 雑誌業
- 不動産業
- 医療用医薬品業、医療機器および衛生検査所業
以下では、それぞれについて、景品の限度額を紹介します。
(1)新聞業
新聞業を営む事業者は、新聞の購読者に対し、以下の範囲を超えて景品類を提供してはなりません。
- 【懸賞により提供する景品類】
- 最高額:取引価格の10倍に相当する金額または5万円の、どちらか低い金額
- 総額:取引価格の予定総額の0.007%に相当する金額
- 【懸賞によらずに提供する景品類(総付景品)】
- 取引価格の8%に相当する金額、または6ヶ月分の購読料の8%に相当する金額のうち、いずれか低い金額
(2)雑誌業
雑誌業を営む事業者は、以下の範囲を超えて一般消費者に対し景品類を提供してはなりません。
- 【懸賞により提供する景品類】
- 最高額:取引価格の20倍に相当する金額(10万円を超える場合は10万円)
- 総額:取引の予定総額の2%に相当する金額
- 【懸賞によらずに提供する景品類(総付景品)】
- 取引価格の20%に相当する金額(200円未満の場合は200円)
(3)不動産業
不動産業を営む事業者は、以下の範囲を超えて一般消費者に対し景品類を提供してはなりません。
- 【懸賞により提供する景品類】
- 最高額:取引価格の20%に相当する金額(10万円を超える場合は10万円)
- 総額:取引の予定総額の2%に相当する金額
- 【懸賞によらずに提供する景品類(総付景品)】
- 取引価格の10%に相当する金額、または100万円の、いずれか低い方の金額
(4)医療用医薬品業、医療機器および衛生検査所業
提供する景品類についての限度額の定めはありません。
もっとも、医療用医薬品や医療機器の製造・販売などを扱う事業者は、医療機関などに対し、取引を不当に誘引するための手段として、医療用医薬品や医療機器などの使用・利用に応じて必要となる物品またはサービスの範囲を超えて景品類を提供してはなりません。
この業種では安全や品質が特に厳しく求められるため、事業者が提供する景品類によって、医療機関などが判断を誤ることがないように徹底する必要があります。
5 ペナルティ
景表法上の景品規制に違反をすればペナルティーが科される可能性があります。
もっとも、違反することで直ちに罰則を受けるわけではなく、違反者には、違反行為を是正する機会が与えられます。
具体的には下記の通りです。
- 調査
↓ - 指導
↓ - 措置命令
↓ - 罰則の適用
景品規制に違反している疑いのある事業者には、消費者庁などによる聴き取りなどの「①調査」が実施されます。
調査の結果、違反の事実は認められないものの、そのおそれがあると認められた場合には、是正のための「②指導」が入ります。
他方で、調査の結果、違反の事実が認められた場合は、違反行為の差止めや再発防止のための措置を講ずることなどを命ずる「③措置命令」が発令されます。
措置命令を受けたにもかかわらず、事業者が従わない場合には、消費者庁のWebサイトで事業者名や措置命令の内容などを公表される可能性があります。そうなると、事業者は、イメージダウンに繋がり、多大な損失を被る可能性があります。
また、措置命令に従わない場合は、「④罰則」を科される可能性もあります。
具体的には、
- 最大2年の懲役
- 最大300万円の罰金
のいずれか、または、両方を科される可能性があります。
さらに、法人の場合は、違反行為者とは別に、その法人に対し、
- 最大3億円の罰金
が科される可能性があります。
6 小括

景品(おまけ)や懸賞などの販促活動は、消費者に商品やサービスの付加価値を感じてもらうには適したツールです。おまけが話題を呼んで売れ行きを左右するということも少なくありません。
もっとも、おまけを提供する際にも、消費者の合理的選択を阻害することがないよう注意する必要があります。
そのためには、景表法が定める限度額をきちんと理解し、その範囲で最適なおまけを提供することが大切です。
7 まとめ
これまでの解説をまとめると、以下の通りです。
- 景表法における「景品(おまけ)」とは、①顧客を誘引するための手段であること、②事業者が自己の供給する商品またはサービスの取引に付随して提供すること、③物品、金銭その他の経済上の利益であること、④上記3つに当てはまるもので、内閣総理大臣(国)が指定するものを指す
- 「総付(ベタ付)景品」とは、懸賞によることなく、サービスの購入や来店などでもれなく消費者全員に提供されるものをいう
- 「懸賞」とは、抽選やゲームの勝敗、クイズの正誤などに応じて景品の内容や送り先が決まるもので、「オープン懸賞」「クローズド懸賞」の2種類がある
- ①新聞業、②雑誌業、③不動産業、④医療用医薬品業・医療機器および衛生検査所業の4業種については、業種別に景品の制限が別途決められている
- 景品規制に違反した場合のペナルティーには、指導、措置命令、罰則がある
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。