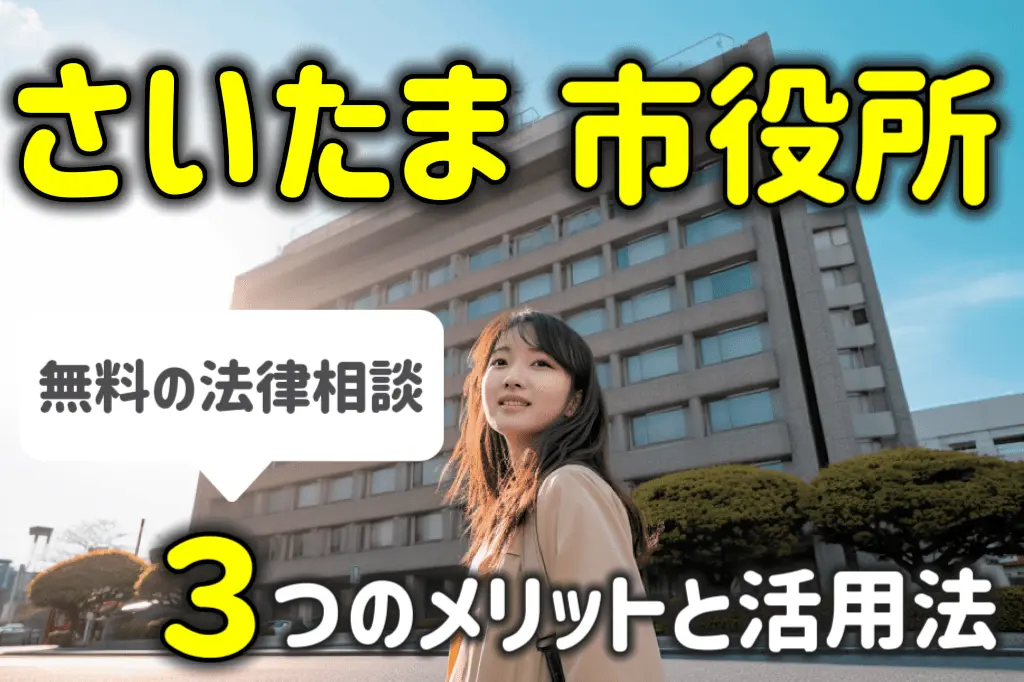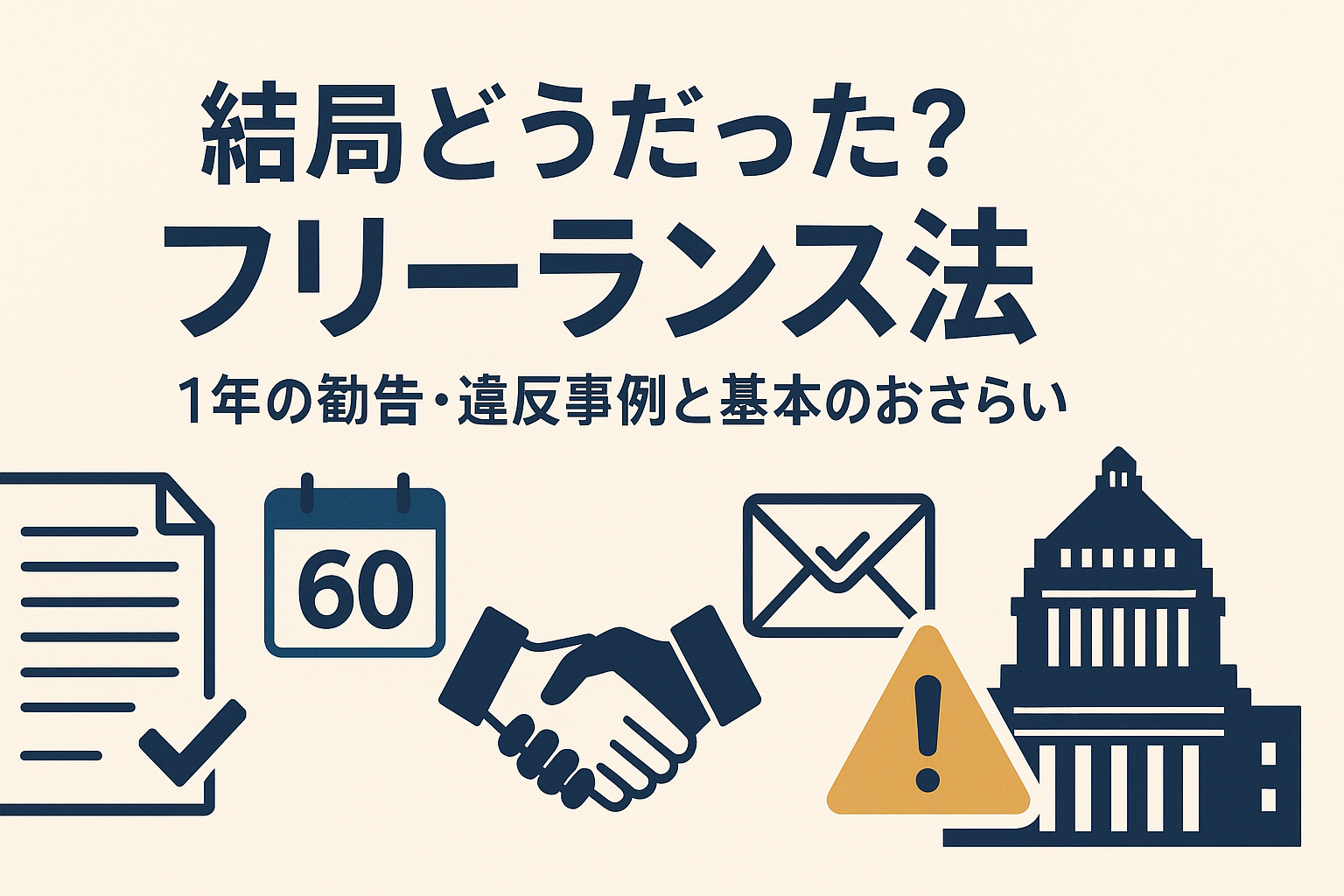請負契約と準委任契約のメリット・デメリットを弁護士が3分で解説

はじめに
人材不足に悩む事業者にとって、フリーランスの利用が、事業を効率的に進めていくうえで新たな手段となっています。
この場合、フリーランスとの間で「業務委託契約」を締結することが一般的になっていますが、契約時のトラブルも少なくありません。
このようなトラブルを回避するためには、事業者と受注する側の双方において、契約内容についての理解に食い違いが生じないようにすることが重要になってきます。
「業務委託契約」は、その性質によって「請負契約」と「準委任契約」という2つの種類に分類されるため、契約を締結する際には、各契約の性質はもちろんのこと、それぞれのメリット・デメリットを押さえておくことが大切です。
今回は、業務委託契約の2種類の契約について、それぞれのメリット・デメリットを中心に解説します。
1 業務委託契約における2種類の契約
「業務委託契約」とは、業務を外注に出す場合に、発注者と受注者との間で依頼内容などを定める契約のことをいいます。
業務委託契約は、その性質上、以下の2つの種類に分類することができます。
- 請負契約
- 準委任契約
(1)請負契約
「請負契約」とは、発注者が依頼した業務につき、受注者が完成義務を負うことを内容とする契約のことをいいます。
受注者にとっては、仕事の完成を義務付けられるため、負担の重い契約類型ということがいえます。
請負契約が締結される場面としては、たとえば、マイホームを購入する際の建物の建築やプログラミングなどを外注に出す場合が挙げられます。
(2)準委任契約
「委任契約」とは、発注者が依頼した業務を受注者が行うことを内容とする契約のことをいいます。
発注者が依頼した業務が法律行為にあたれば「委任契約」となりますが、法律行為にあたらない業務であれば、「準委任契約」ということになります。
準委任契約は、さらに次の2つの型に分類することができます。
- 履行割合型
- 成果完成型
「履行割合型」とは、受注者が発注者に提供した工数などに応じて報酬が支払われる形態の準委任契約です。
履行割合型では、受注者に依頼した業務が成果を上げているかどうかを問わず、業務の遂行に割かれた時間や工数などに応じて、発注者は報酬を支払わなければなりません。
これに対し、「成果完成型」とは、発注者に依頼した業務が達成された場合に、報酬が支払われる形態の準委任契約です。
成果完成型では、受注者は成果を達成できないかぎり、報酬を得られないということになります。
一見すると、請負契約と変わらないようにも思えますが、成果完成型の準委任契約において、仕事の完成は報酬が支払われるための条件にすぎません。
そのため、請負契約のように、受注者が仕事の完成義務を負っているということではありません。
準委任契約が締結される場面としては、たとえば、コンサルティングやシステム開発における要件定義などが挙げられます。
2 請負契約のメリット・デメリット
請負契約には、以下のようなメリット・デメリットがあります。
(1)メリット
請負契約は雇用契約のように受注者との間に雇用関係があるわけではなく、発注者と受注者の間に指揮命令関係はありません。
そのため、雇用契約において必要とされる従業員を対象とした管理業務を行う必要がありません。
また、メリットとして一番大きいのは、要望に沿った成果物を納品してもらえるということです。
既に見たとおり、請負契約では、受注者に完成義務が生じるため、発注者は完成された成果物を手に入れることができます。
さらに、請負契約では原則として、成果物の引き渡しと同時に報酬が支払われることになっています。
そのため、基本的には、受注者において仕事が完成していないかぎりは、報酬を支払う必要がないというメリットがあります。
仮に、契約の内容とは適合しない成果物が納品された場合、発注者は受注者に対して、いったん納品された成果物を契約内容に適合させるように求めることができ、また、報酬額の減額を請求することも原則として可能です。
受注者が負うこのような責任を「契約不適合責任」といいます。
(2)デメリット
受注者が仕事の完成義務を負っているとはいえ、どのような品質で成果物が納品されるかは受注者次第という側面があります。
そのため、受注者によっては、自社が要望する品質とは異なる品質の成果物が納品される可能性があります。
3 準委任契約のメリット・デメリット
準委任契約には、以下のようなメリット・デメリットがあります。
(1)メリット
準委任契約は、仕事の完成ではなくその遂行という行為そのものが契約の対象です。
そのため、具体的な作業を細かく指定しないことが多く、双方が柔軟に対応できるというメリットがあります。
たとえば、準委任契約によりソフトウェア開発を外注に出した場合、業務遂行の過程で仕様変更をすることも可能になります。
この点、請負契約では契約時においてある程度のことが固められるため、契約後に仕様変更をするといったことが難しくなります。
また、準委任契約には、原則として中途解約を自由にすることができるというメリットがあります。
とはいえ、発注者に不利な時期に解約をする場合、それがやむを得ないと認められないかぎり、発注者に生じた損害を賠償する必要があります。
(2)デメリット
準委任契約では、業務上の成果物が存在しないため、請負契約と比べて契約内容が曖昧になりがちです。
契約内容が曖昧だと、発注者と受注者の間に理解の食い違いが生じる可能性が高く、そうなると、業務遂行や報酬の支払いがスムーズに進まなくなるおそれがあります。
また、納期を定める場合には、準委任契約は適していないというデメリットもあります。
準委任契約では、受注者に仕事の完成義務がないため、納期までに成果物を納品できなかったとしても、原則として、受注者に責任は生じません。
4 まとめ
請負契約と準委任契約は、何を契約の目的とするかという点で違いがあります。
成果物にこだわる場合は「請負契約」、業務の遂行が必要だという場合は「準委任契約」というのがオーソドックスな基準になると考えられます。
加えて、各契約におけるメリットとデメリット、当事者に発生する権利義務の内容などを理解しておくことも重要です。
弊所は、ビジネスモデルのブラッシュアップから法規制に関するリーガルチェック、利用規約等の作成等にも対応しております。
弊所サービスの詳細や見積もり等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。