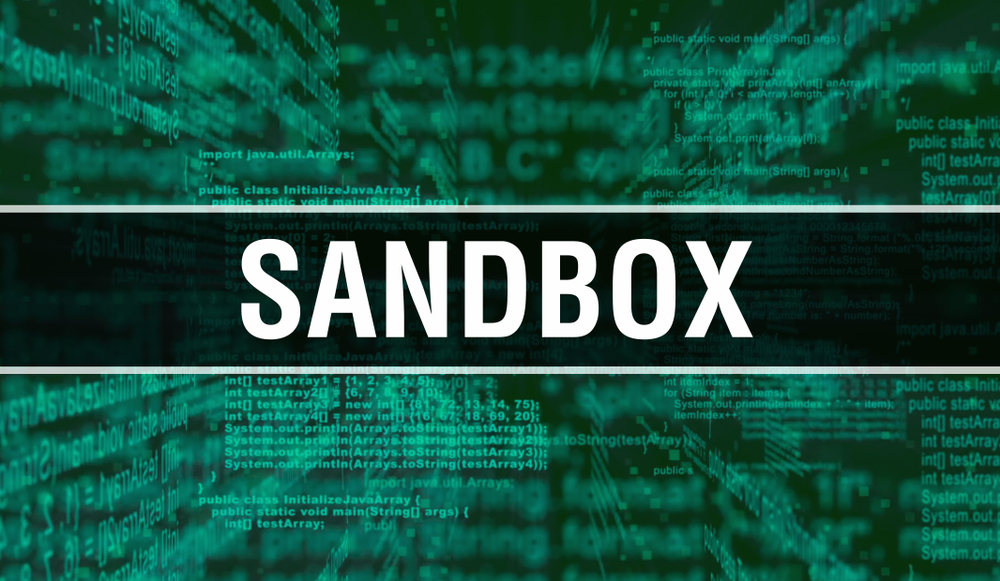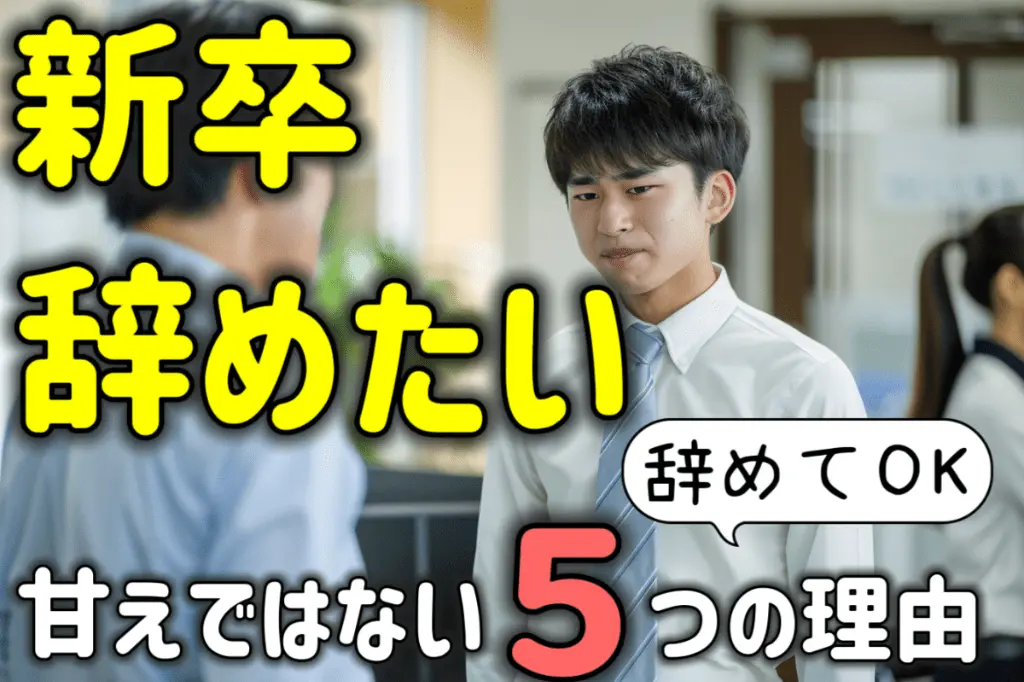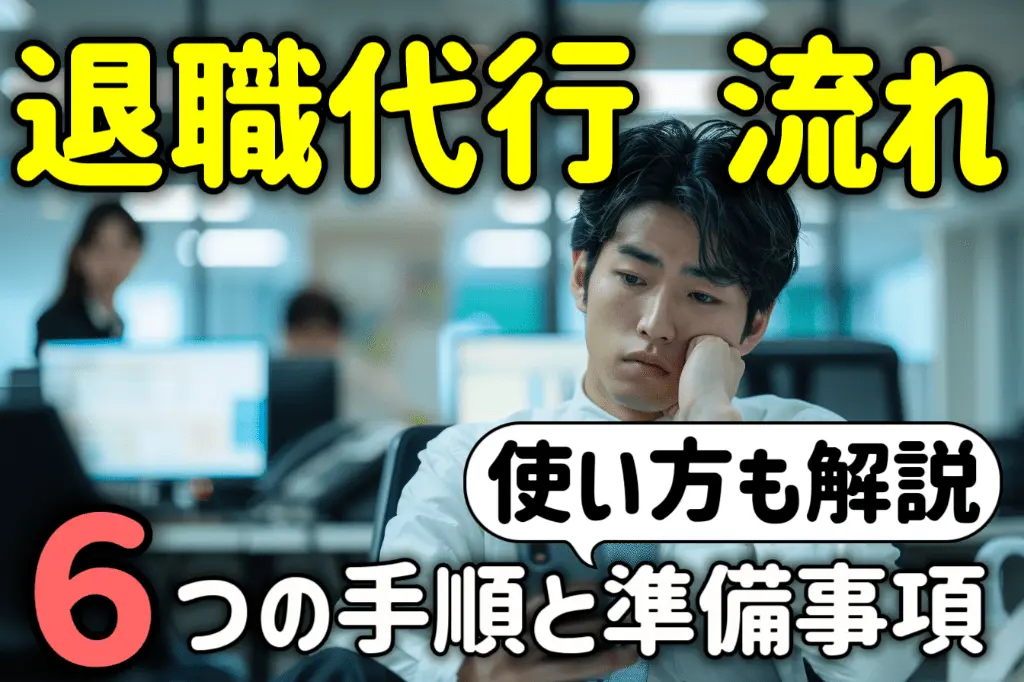システム開発契約書で定めるべき5つの事項を弁護士が解説!

はじめに
近年、さまざまな分野において、DX化(デジタルトランスフォーメーション)が推進されています。
ビジネスの多様化、従来のシステムの老朽化などから、今後もDX化がいっそう進められていくものと予想されます。
システム開発は、そのようなDX化を根幹から支える重要な役割を担っています。
もっとも、システム開発にはさまざまな形態があるため、開発委託をめぐるトラブルも少なくありません。
システム開発契約を締結する際には、その点にも十分に留意することが必要です。
今回は、システム開発契約書で定めるべき事項について弁護士がわかりやすく解説します。
1 システム開発契約とは
「システム開発契約」とは、発注者(ユーザ)が受注者(ベンダ)に対して、システム開発を依頼する際に締結する契約のことをいいます。
システム開発契約は、通常の契約とは性質が異なります。
たとえば、商品の売買契約について見てみましょう。
商品を購入しようとする者は、申し込みさえすれば、あとは商品が手元に届くのを待つだけです。
ですが、システム開発は、ユーザが自社の事業を実現したり、事業の効率化を図ったりするために、ベンダに依頼することが通常です。
そのため、システム開発を行うにあたっては、そこにどのような機能が必要かなど、ユーザ自身が求めることをできるだけ明確にベンダに示しておくことが必要になります。
ベンダはユーザが求めることを正確に把握したうえで、その要望に沿うシステムを開発する必要があるのです。
2 システム開発契約の法的性質
システム開発契約の法的性質は、一般的に、「請負」もしくは「準委任」のいずれかと考えられています。
なぜ、ここで法的性質に言及したかというと、この部分を確定しないことには、システム開発契約書で定めるべき事項も決まらないのです。
-
【請負】
当事者の一方がある仕事を完成することを約束して、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払
うことを内容とする契約類型
【準委任】
当事者の一方が法律行為でない事務の処理を相手方に委託することを内容とする契約類型
請負と準委任において、一番異なる点は、受注者が仕事の完成義務を負うかどうかという点にあります。
請負では受注者が仕事完成義務を負うのに対し、準委任では受注者は仕事完成義務を負いません。
システム開発は、いくつかの工程に分けて進められることが一般的であるため、工程ごとに、適切な契約類型を選択することが必要です。
※「請負契約」と「準委任契約」の違いについて詳しく知りたい方は、「請負契約と準委任契約は何が違うのか?6つのポイントを弁護士が解説」をご覧ください。
3 システム開発契約書で定めるべき事項
システム開発契約書を作成する際には、その特殊性や法的性質をうまく契約書に落とし込む必要があります。
以下は、システム開発契約書で定めるべき事項のなかでも特に重要な事項です。
- 定義
- 仕様の変更
- 契約不適合責任
- 知的財産権に関する事項
- 第三者ソフトウェアの利用
(1)定義
契約書で使われている用語について、一義的な解釈ができないと、その解釈をめぐってトラブルになるおそれがあります。
特に、システム開発に関する用語は、その多くについて明確な定義が存在しません。
そのため、契約当事者において各用語の定義を明確にしておくことが必要です。
(2)仕様の変更
システム開発契約では、開発過程での仕様変更が想定されます。
開発過程において仕様変更が生じた場合、そのことが契約当事者間で共通の認識となっていなければなりません。
仕様に関する認識のズレは、完成品の品質などをめぐるトラブルに発展する可能性が高いといえます。
そのため、仕様変更が生じた場合の対応などを、契約書できちんと定めておく必要があります。
(3)契約不適合責任
「契約不適合責任」とは、売買契約や請負契約において、目的物の品質や種類、数量などが契約の内容に適合しない場合に、売主や請負人が負う責任のことをいいます。
システム開発契約においても、ベンダにより開発されたシステムが契約の内容に適合しないということがあり得るため、契約不適合責任に関する条項を設けておくことが必要です。
この場合、契約不適合の内容(何をもって「契約の内容に適合しない」とするか)を定める必要がありますが、その内容があまりに抽象的だと、契約当事者間でトラブルに発展するおそれがあるため、注意が必要です。
(4)知的財産権に関する事項
システム開発契約に基づきベンダが開発したシステムは、知的財産権の対象となりうるため、その権利の帰属を定めておく必要があります。
また、ベンダが開発したシステムが他者の知的財産権を侵害する可能性も否定できないため、その場合のベンダの責任についても定めておくことが必要です。
(5)第三者ソフトウェアの利用
システム開発を行うにあたり、ベンダが第三者ソフトウェアを利用する場合があります。
この場合、第三者ソフトウェアが想定しない内容のものであったり、他の第三者の権利を侵害するものであったりするリスクがあります。
このようなリスクを回避するために、第三者ソフトウェアの利用に関して、契約不適合や権利侵害に関する条項を設けておくことが必要です。
4 まとめ
システム開発契約書で定めるべき事項は多岐にわたります。
今回見てきた事項だけでなく、開発されるシステムの内容に応じて、新たに定めておくべき事項がないかどうかを十分に検討することが大切です。
弊所は、ビジネスモデルのブラッシュアップから法規制に関するリーガルチェック、利用規約等の作成等にも対応しております。
弊所サービスの詳細や見積もり等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。