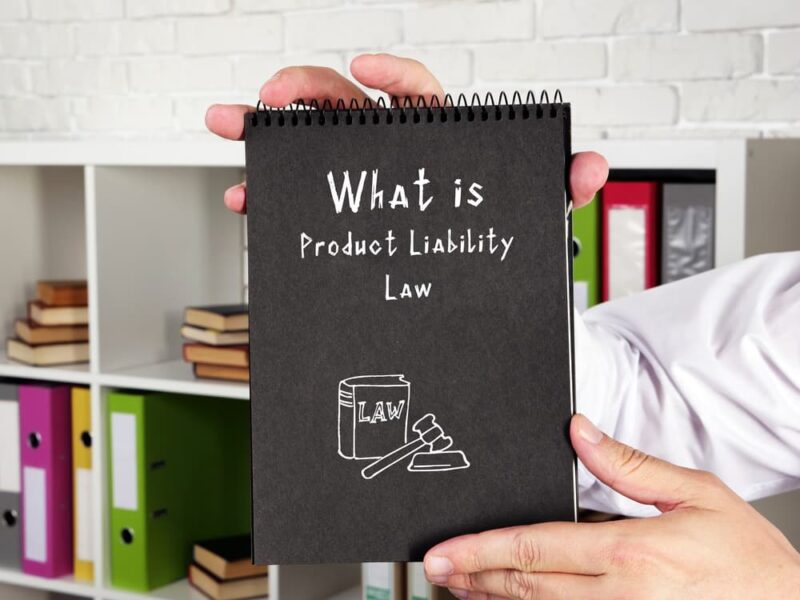特定商取引法とは?規制対象となる7つの事業と規制内容を解説

はじめに
商品の販売等を事業として行う場合には、「特定商取引法」という法律を必ず確認しておかなければなりません。
インターネットなどで「特定商取引法に基づく表記」という文言を見たことがあるという方も多いのではないでしょうか。
同種の事業を検討している事業者は、自社の事業が規制対象となるのか、規制対象となる場合どのような規制を課されるのか、気になるところです。
今回は、「特定商取引法」について、規制対象となる事業や規制内容をわかりやすく解説します。
1 特定商取引法とは

「特定商取引法」とは、事業者による違法・悪質な勧誘行為などを規制することにより、一般消費者の利益を保護するための法律です。
消費者との間でトラブルになりやすい取引を規制対象とするとともに、取引を行う事業者が遵守すべきルールが定められています。
具体的には、以下の7つの取引類型が規制対象となっています。
- 訪問販売
- 通信販売
- 電話勧誘販売
- 連鎖販売取引
- 特定継続的役務提供
- 業務提供誘引販売取引
- 訪問購入
(1)訪問販売
「訪問販売」とは、消費者の自宅に事業者が訪問して、商品販売や役務提供を行う契約をする取引のことをいいます。
訪問販売においては、強引な押し売りや詐欺被害などが問題となることが少なくありません。
(2)通信販売
「通信販売」とは、事業者が雑誌やインターネットなどを使って広告し、消費者から郵便や電話といった通信手段により契約の申込みを受ける形態の取引のことをいいます。
「通販」とも呼ばれる通信販売は、われわれにとって身近なサービスの一つになっています。
(3)電話勧誘販売
「電話勧誘販売」とは、言葉のとおり、事業者が電話で勧誘を行い、消費者から契約の申込みを受ける取引のことをいいます。
契約の申込みは、必ずしも電話でなされる必要はありません。電話をいったん切った後に、郵便で申込むを行う場合や再度電話で申込みを行う場合も「電話勧誘販売」にあたります。
(4)連鎖販売取引
「連鎖販売取引」とは、販売員として個人を勧誘し、その個人に次の販売員の勧誘をさせるといったように、連鎖的に組織を拡大して行う取引のことをいいます。
マルチ商法などと呼ばれることもあり、商品を販売して得られる利益よりも人を勧誘することで得られる「リクルートマージン」が主な収入となる傾向にあります。
そのため、勧誘行為が半ば強引になることも多く、問題の多い取引形態の一つだといえます。
(5)特定継続的役務提供
「特定継続的役務提供」とは、長期にわたり継続的に役務を提供し、高額となる対価の支払いを約する取引のことをいいます。
たとえば、エステティックサロンや語学教室などが「特定継続的役務提供」にあたります。
(6)業務提供誘引販売取引
「業務提供誘引販売取引」とは、仕事を提供するなどとして消費者を誘引し、その仕事に必要であるとして、商品などを販売する取引のことをいいます。
たとえば、ホームページの作成を仕事として提供するにあたり、作成に使うパソコンとソフトを販売するような取引をいいます。
(7)訪問購入
「訪問購入」とは、消費者の自宅などに事業者が訪問して、商品の購入を行う取引のことをいいます。
訪問購入では、消費者が意図していたものとは異なる商品(貴金属など)を安価で購入されるといった被害も出ています。
2 特定商取引法による規制
特定商取引法の規制対象となる事業者は、その取引類型に応じて、以下のような義務を課されます。
- 表示義務
- 不当な勧誘行為の禁止
- 広告規制
- 書面交付義務
(1)表示義務|特定商取引法に基づく表記
事業者は、取引をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、氏名・名称、契約の締結について勧誘をする目的である旨、勧誘に係る商品などを明らかにしなければなりません。
われわれがよく目にする「特定商取引法に基づく表記」は、ここにいう表示義務を履行する方法として一般的に用いられています。
(2)不当な勧誘行為の禁止
事業者は、勧誘にあたり、商品の品質や販売価格などについて、あえて事実を告げないようなことをしてはなりません。
また、契約を締結しない旨の意思表示をした消費者に対して、勧誘行為を行うことは禁止されています。
(3)広告規制|誇大広告等の禁止
事業者は、商品やその販売条件などについて広告をする場合、商品の性能や契約の申込みの撤回・解除に関する事項などについて、著しく事実と異なる表示をしたり、実際のものよりも著しく優良・有利であると消費者を誤認させるような表示をしてはなりません。
(4)書面交付義務
事業者は、消費者から契約の申込みを受けたときは、重要事項を記載した書面を消費者に交付しなければなりません。
ここでいう「重要事項」としては、商品の種類や販売価格、代金の支払時期、契約の申込みの撤回・解除に関する事項などが挙げられます。
3 その他の規制
特定商取引法は、以上のほかにも、消費者の救済を容易にするために以下のような規制を設けています。
- クーリングオフ
- 意思表示の取消し
- 損害賠償額の制限
(1)クーリングオフ
「クーリング・オフ」とは、契約の申込み後、一定の期間内に契約を無条件で解約することをいいます。
取引類型によって、期間に違いがありますが、一定の条件を満たしていれば、契約の申込み後8日~20日の間で契約を解約することが可能です。
もっとも、通信販売には、クーリングオフ制度は設けられていません。
(2)意思表示の取消し
事業者が勧誘をする際に、虚偽の説明をしたり、あえて事実を告げなかったりしたことで、消費者が誤認し契約を申込んだような場合、消費者は、その意思表示を取り消すことができます。
(3)損害賠償額の制限
消費者が中途解約する場合などに、事業者が消費者に請求できる損害賠償額に上限が設けられています。
4 特定商取引法違反の罰則
特定商取引法による規制に違反した場合、罰則を科される可能性があります。
たとえば、事業者が不当な勧誘行為を行った場合、
- 最大3年の懲役
- 最大300万円の罰金
のいずれか、または両方を科される可能性があります。
この場合において、事業者が法人である場合には、行為者とは別に法人に対して、
- 最大1億円の罰金
が科される可能性があります。
また、事業者が書面交付義務に違反した場合、
- 最大6ヶ月の懲役
- 最大100万円の罰金
のいずれか、または両方を科される可能性があります。
この場合において、事業者が法人である場合には、行為者とは別に法人に対して、
- 最大100万円の罰金
が科される可能性があります。
5 まとめ
特定商取引法は、取引の類型に応じて、さまざまな規制を設けています。
商品の販売、サービスの提供などを事業として行う場合には、自社の事業が特定商取引法の規制対象となるかをきちんと確認することが大切です。
うかつに事業を始めてしまうと、場合によっては、罰則の対象になるおそれもあるため注意するようにしましょう。
弊所は、ビジネスモデルのブラッシュアップから法規制に関するリーガルチェック、利用規約等の作成等にも対応しております。
弊所サービスの詳細や見積もり等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。