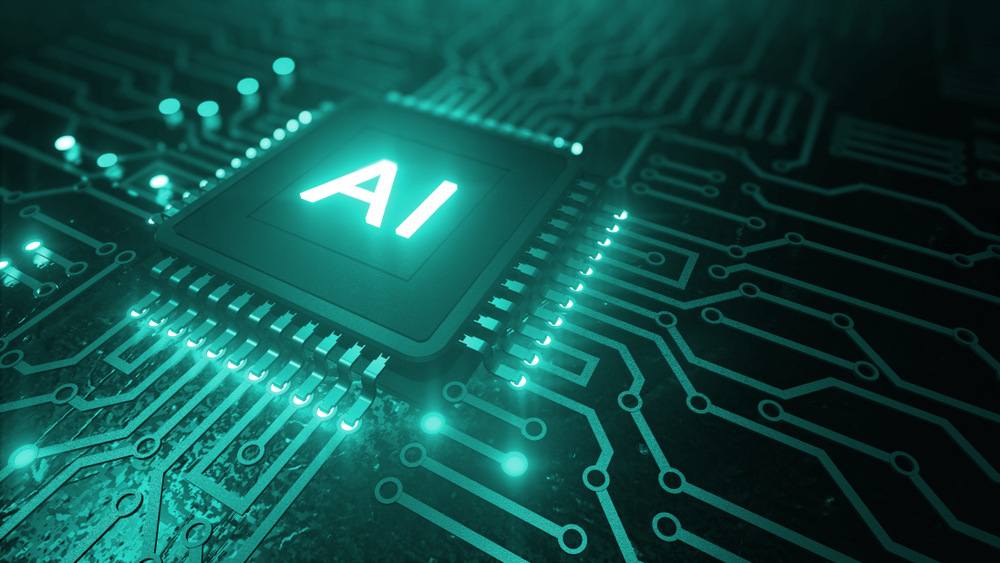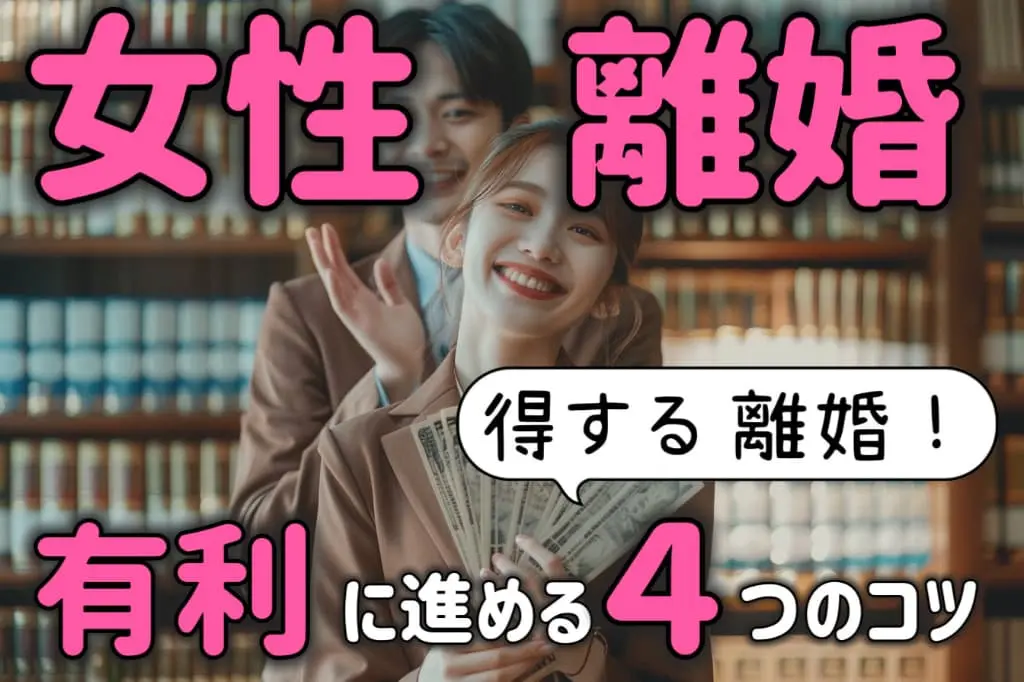ドローンが他人の土地上空を飛ぶのは違法?4つの視点で弁護士が解説

はじめに
他人の土地の上を許可なく自由にドローンを飛ばしてもいいのでしょうか?地上であれば他人の敷地内を勝手にウロウロするのはご法度ですが、上空についてのルールはよくわからない方もいるかと思います。
そこで今回は、他人の土地の上空でドローンを飛ばす場合に考慮しなければならない「土地所有権」とは何か、土地所有権はどの範囲まで及ぶのか、また、ドローンと土地所有権の関係についてなどを、分かりやすく解説していきたいと思います。
1 ドローンとは

「ドローン」とは、無人航空機の総称で、「空を飛ばすことができ、人が乗らずに操縦する機体」のことをいいます。
手のひらに乗るものから人を乗せることができる大きさのものまで、人が地上から操縦するもの、または、自動操縦によって飛行するものはすべて「ドローン」にあてはまります。
さて、ドローンを屋外で飛ばすとき、自己所有地以外の他人の土地の上空で飛ばしたい場合もあるでしょう。このときに考えなければならないのがドローンと「土地所有権」との関係です。
次の項目で詳しくみていきましょう。
2 土地所有権とは

「土地所有権」とは、文字どおり、土地を所有する権利のことをいいます。土地所有権があれば、所有者はその土地を自由に使用することができます。言い換えれば、その土地を他人が勝手に使用することはできません。
土地所有権の範囲は、民法で「その土地の上下に及ぶ」と定められています。要するに、私たちが立っているその土地の表面+地下+地上(上空)が土地所有権の及ぶ範囲となります。
そのため、普通に考えれば、他人の土地に入る場合はもちろん、その上空にドローンを飛ばす場合にも所有者の許可が必要となります。飛行機だって、その土地の上空を飛行している以上、所有者の許可を得なければならないはずです。
もっとも、土地所有権があるというだけでその地下・上空部分について無制限に権利を認めてしまうと、ドローンや航空機を飛ばすときに、飛行ルート上の土地所有者一人一人に飛行許可を得なければならないなど、不都合な点が多々生じます。
そのため、土地所有権は、2つの観点から制限がかけられています。
- 法律による制限
- 土地所有権の主張を認める必要がない場合の制限
この2つの制限によって、土地所有者は、自分の土地所有権を自由に主張することができなくなります。
次の項目で詳しく確認していきましょう。
3 土地所有権の限界

(1)法律による制限
土地所有権は、法律によって制限をうけることがあります。例えば、土地収用法や都市計画法による制限です。
【土地収用法による制限】
土地収用法とは、国や地方公共団体が、一定の条件の下で、他人の土地を公共の利益のために使用することができることを定めた法律です。
土地所有者の承諾がなくても、土地収用法に沿った手続きがされれば、その土地の所有権は元の所有者から国・地方公共団体に移ってしまいます。【都市計画法による制限】
都市計画法とは、街を計画的に作るための法律です。都市計画法の区域内に土地を所有している場合、建てられる建物の種類が限定されていたり、そもそも建物を建てることができないなど、その土地の利用について制限されます。
このように、何らかの法律によって土地の処分や利用に制限がかけられている場合、その土地の所有者はこれに従わなければなりません。
(2)土地所有権の主張を認める必要がない場合
土地所有権の範囲について、地下に関しては特別法で「一定の深さ以上の地下はすべて、公共性の高い事業での使用を可能とする」と定められています。一方、地上(上空)部分に関しては、上で挙げた土地収用法や都市計画法による制限がかからない限り、土地の利用を直接制限するような特別な規定はありません。
だからといってもちろん無制限に土地所有権が認められるわけではなく、土地所有権の及ぶ範囲は一般的に、「利益の存する限度」において認められるとされています。
「利益の存する限度」とは、所有者が、「ここは私の土地の範囲内だから勝手なことをするな!」と土地所有権を主張する場合に、それが認められるだけの正当な理由がある場合のことをいいます。
言い換えれば、土地所有権の主張について正当な理由がない=主張が認められたとしても土地の所有者に利益がない、つまり土地所有権の主張を認める必要が無いということとなり、土地所有者は、その部分について自由に所有権を主張することができなくなります。
では、上空部分について、土地所有者にとって「利益の存する限度」とはどこまでで、どこからが「利益のない部分」となるのでしょうか?
これについては、航空法に定められている「最低安全高度」が1つの目安となります。
「最低安全高度」とは、飛行機が飛ぶ際の飛行高度の基準のことで、地上にいる人や建物の安全のために定められているものです。これによれば、飛行機は、
- 市街地などの建物が密集している地域では、600mの範囲内で一番高い建物の上端(屋上など)から300m
- それ以外の場所では地上から150m
が最低飛行高度となります。
例えば、市街地では、一番高い建物の高さが100mであれば、100+300=400mが最低安全高度となります。
この最低安全高度以上の高度で飛行するのであれば、飛行機は、その下にある土地の所有者の許可を得る必要がありません。一定の高さ以上の上空であれば、飛行機が通過することに対して土地所有者には現実的な不利益がないため、土地所有権の主張を認める必要がない=土地所有権が及ばないと考えられるからです。
例えば、自分の土地の上空1万mを飛行機が通過したからといって、飛行機の騒音や振動などの被害をうけることは現実的に考えにくいですよね。そのため、土地所有権の主張を認める必要がありません。
これを言い換えれば、最低安全高度以下の上空(地上)部分(150m未満or300m未満)は、土地所有者に対する現実的な不利益が想定できるため、土地所有権の主張を認める必要がある=土地所有権の範囲内ということができます。
例えば、飛行機が自分の土地のすぐ上50mを飛んでいたとしたら、騒音や振動はかなりのものとなり、現実的な不利益が生じるといえます。そのため、土地の所有者は、土地所有権に基づいて損害賠償請求などをすることができます。
(3)最低安全高度以上の上空の扱い
なお、この「最低安全高度」はあくまでも目安であり、土地所有権の及ぶ範囲を定めたものではありません。そのため、最低安全高度以上の上空であっても、場合によっては「利益の存する範囲」として土地所有権が及ぶ可能性があることに注意が必要です。
例えば、市街地以外の場所では地上から150mまでの範囲に土地所有権が及ぶと考えられていますが、200mの高層ビルが建てられた場合、150m以上の上空部分についても土地所有権は及ぶと考えられます。
もっとも、飛行機が飛ぶような高度については、先ほど解説したのと同様に、仮に土地所有権が及ぶとしてもたいていの場合は土地所有者に現実的な不利益が想定できません。そのため、土地所有者による土地所有権の主張については、権利の濫用(自分の権利をむやみやたらに主張すること)とみなされ、否定される場合がほとんどであると考えられます。
ここまでの「土地所有権の範囲」についての解説をまとめると、以下のようになります。
- 何らかの法律によって土地の利用や処分に制限がかけられている場合には、所有者は、それに従わなければならない
- 市街地では上空300m未満、その他の場所では上空150m未満に土地所有権が及ぶと考えられる(=利益の存する限度)
- これよりも高い高度になると、土地所有権は及ばないとみなされる可能性が高い
4 航空法と土地所有権の関係

これまで土地所有権の及ぶ範囲・及ばない範囲について解説してきましたが、そもそも、ドローンの飛行については航空法上の規制があります。
具体的には、ドローンを飛ばせる場所や飛ばし方についての規制がありますが、飛行高度については、「上空150m未満であればドローンを自由に飛ばすことができる」と定められています。なお、150m以上の上空でドローンを飛ばす場合には、国の許可を得る必要があります。
(ドローンの飛行ルールについて詳しく知りたい方は、「ドローン企業が知るべき航空法とは?3つのポイントを弁護士が解説!」をご覧ください。)
では、航空法の規制にさえ違反しなければ、民法に規定される土地所有権に関係なく、他人の土地の上空にドローンを飛ばしてもいいのでしょうか?
この点について、航空法に則っているかどうかの判断と民法上の土地所有権を侵害しているかどうかの判断は、別問題となっています。
その理由は、航空法と民法の趣旨の違いにあります。
航空法は、飛行機やドローンなどの航空機(有人・無人含む)が安全に飛行するために定められた法律です。一方、民法は、私たちの普段の生活について定められた法律であり、その目的や趣旨は全く違います。
そのため、ドローン操縦者は、これらの法律のどちらか一方を守ればよいというわけではなく、両方ともきちんと守る必要があります。
なお、国土交通省の「ドローンの飛行に関するガイドライン」でも、以下のように述べられています。
-
- Q5-7 航空法に従って飛行すれば、第三者が所有する土地の上空を飛行してもよいのでしょうか。
A 航空法の許可等は地上の人・物件等の安全を確保するため技術的な見地から行われる ものであり、ルール通り飛行する場合や許可等を受けた場合であっても、第三者の土地 の上空を飛行させることは所有権の侵害に当たる可能性があります。
以上の解説を踏まえたうえで、次の項目では、ドローンと土地所有権の関係について考察していきます。
5 ドローンと土地所有権の関係

(1)基本的な考え方
ここで改めて、今回の問題の所在を確認しましょう。
-
- 【ドローンを飛ばす際の問題】
- 他人の土地上でドローンを飛ばしたいけど、「土地所有権」というものがあるため、所有者の許可を得る必要があるらしい。でも、いくつもの区画に渡ってドローンを飛ばす場合に、すべての所有者からあらかじめ許可を得なければならないのはドローンビジネスを行う上でとても煩わしい。実際のところ、ドローンと土地所有権の関係はどう考えればいいのか?許可を得なくてもドローンを飛ばす方法はないのか?
この問題については、結論からいうと、「現行法上は面倒でも飛行ルート上のすべての土地について、所有者や管理者の許可を得てからドローンを飛ばすこと」が最も無難で間違いのない答えといえます。
実際にドローンを飛ばす場合、国の許可が必要ない150m未満の範囲での飛行がほとんどです。とすると、他人の土地の上空であれば、そこは土地所有権の及ぶ範囲内ということになります。さらに、ドローンのように比較的低空を飛行させるタイプの無人航空機については、地上にいる人との物理的距離も近く、ドローンと土地所有権の関係については慎重に検討する必要があるといえます。
そのため、トラブルを起こさないためにも、ドローンを他人の土地上で飛ばしたいのであれば、あらかじめ土地所有者から許可を得ることがとても重要になります。
(2)土地所有権をクリアするための考え方
ドローンを他人の土地の上空で飛ばす場合、すべての土地所有者から許可を得ることが最も確実な方法であることは先ほど述べたとおりです。ですが、長距離にわたって上空から撮影を行うドローン事業者などからすれば、この作業はなかなか煩わしく、実際に1人1人から飛行許可を得ていたら仕事になりませんよね。
そこで、ドローンを飛ばす場合の土地所有権問題をクリアする考え方として、以下の2つが挙げられます。
- 飛行機と同様に考える
- 航空法上の許可・承認を得ていることを重要視する
順番にみていきましょう。
①飛行機と同様に考える
飛行機が他人の土地の上空を許可なく飛行できるのは、飛行機が飛ぶぐらいの高度においては、飛行機が通過することによる土地所有者への現実的な不利益が想定しにくく、土地所有権が及ばない、もしくは、このような場合に土地所有権を主張することは権利の濫用であると考えられるからでしたね。
ドローンについてもこれと同様に考えます。要するに、150m未満であって、普通は土地所有権の範囲内とされる空域を飛行する場合であっても、土地所有者に対して事実上の不利益(ドローンの飛行によって土地の利用が妨げられるなど)がないのであれば、その飛行空域については土地所有権が及ばない、もしくは、権利濫用として土地所有権が認められないと考えるのです。
そうすると、理屈上、ドローンは土地所有者の許可なく他人の土地上空を飛行することが許されます。
ただし、この考え方が認められるには、公共のインフラである飛行機とドローンを同じ視点から考えられるくらい、社会のドローンに対する理解が必要であるといえます。
②航空法上の許可・承認を得ていることを重要視する
ドローンを飛ばすにあたって、航空法上のルールに従うことと土地所有権の侵害があるかどうかは別問題であることは、すでに解説したとおりです。
ですが、例えば、航空法に従い国の許可や承認を得たうえでドローンを飛ばした場合、この「許可・承認」は、ドローン操縦者が「国からちゃんと許可とってるんだから、土地所有権なんて主張しても無駄だ!自由に飛ばせろ!」と言えるか否かの重要なファクターとなる可能性があります。
もっとも、この主張が認められてしまうと、航空法上の許可・承認さえとればよい、という考え方に結びつきやすくなり、土地所有者の立場が弱くなりすぎてしまう恐れがあります。
いずれにせよ、これら2つの考え方は現行法上正面から認められていません。繰り返しになりますが、現段階で一番ベストな方法は「すべての土地所有者から許可を得ること」で間違いありません。
6 ペナルティ

最後に、ペナルティについてみていきましょう。
ドローンを他人の土地上に飛ばしたことによって土地所有権を侵害した場合、
- 民事上のペナルティ
- 刑事上のペナルティ
が科されることが考えられます。
(1)民事上のペナルティ
ドローンの飛行により、仮に他人の土地所有権を侵害した場合には、次のペナルティが科される可能性があります。
- 損害賠償
- 飛行の差し止め
他人の土地の上空で勝手にドローンを飛ばす行為は、他人の「所有空間」の無断利用として不法行為(違法な権利侵害行為)にあたります。そのため、ドローン操縦者は、土地所有者から、不法行為に基づく損害賠償請求をされる可能性があります。
もっとも、実際問題として、「ドローンが自分の土地の上空を飛んだことによる損害」は認められない可能性が高いと考えられます。ドローンが落下した場合などは別として、ただ単に土地の上空数十メートルを通過しただけであれば、これによる財産的損害や精神的苦痛の発生は想定しにくいからです。
そのため、「ここでドローンを飛ばすのをやめてください!」という飛行の差し止め請求をされるパターンがほとんどであると考えられます。
なお、現在一般的に普及しているドローンは、小型カメラによる撮影ができるものがほとんどです。この小型カメラを利用し、他人の土地上空を飛行しながら勝手に撮影を行っていた場合、「盗撮」にあたり迷惑防止条例違反となる可能性があります。
迷惑防止条例は各都道府県ごとにその内容が定められていますが、例えば東京都の場合、盗撮による条例違反は
- 最大2年の懲役
- 最大100万円の罰金
のどちらかが科される可能性があります。
盗撮については、故意的に撮影するつもりではなくても違反行為として認められてしまうリスクがあるため、注意が必要です。
(2)刑事上のペナルティ
ドローンを他人の土地上空で勝手に飛ばした場合、他人の所有空間への侵入として「住居侵入罪」が問題となります。
もっとも、現在の刑法においては、住居侵入罪が成立するのはあくまでも「人間が侵入した場合」のため、ドローンが侵入したことそれ自体は犯罪として成立しません。
ただし、ドローンの操縦中に人間(操縦者)が他人の土地へ勝手に入ってしまった場合には、ドローン操縦者に対して住居侵入罪が成立します。この場合、
- 最大3年の懲役
- 最大10万円の罰金
が科される可能性があります。
7 小括

ドローンを飛ばす際には、航空法の規制とは別に土地所有権の問題についても考えなければなりません。ですが、ドローンと土地所有権の問題については、まだ法整備が追いついておらず、明確な答えはありません。
航空法にドローンに関する規制が組み込まれたように、土地所有権に関しても今後整備されていくと思いますが、それまでは、この記事で解説したことをきちんと理解し、慎重にドローンを飛ばすことが必要です。
8 まとめ
これまでの解説をまとめると、以下のようになります。
- 「ドローン」とは、無人航空機の総称で、「空を飛ぶことができるけど、人が乗らずに操縦する機体」のことをいう
- 「土地所有権」とは、土地を所有する権利のことをいい、民法では「その土地の上下に及ぶ」と定められている
- 土地所有権は、①法律による場合と②所有権の主張を認める必要がない場合という2つの観点から制限がかけられている
- 「土地所有権の主張を認める必要がない場合」の高度の目安として、航空法に定められる「最低安全高度」があり、最低安全高度以上の上空であれば、基本的vは土地所有権は及ばないものと考えられる
- 最低安全高度以上の上空であっても、場合によっては土地所有権が及ぶ場合もあるが、現実的には権利侵害が想定できないことがほとんどであるため、土地所有権の主張は否定されるケースがほとんどであると考えられる
- ドローン操縦者は、航空法と民法の規定の両方を守らなければならない
- ドローンと土地所有権の問題をクリアする考え方として、①飛行機と同様に考える、②航空法上の許可・承認を受けていることを重要視する、という2つの考え方がある
- ただし、現段階においては、ドローンを他人の土地上で飛ばすときにはすべての土地所有者から許可を得ることがベスト
- ドローンの飛行により他人の土地所有権を侵害した場合、民事上のペナルティとしては①損害賠償、②飛行の差し止め請求、③迷惑防止条例違反による懲役刑や罰金刑が科せられる可能性がある
- 刑事上は「住居侵入罪」が問題となるが、ドローンの侵入それ自体では犯罪は成立しない(操縦者については別途住居侵入罪が成立する可能性あり)
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。