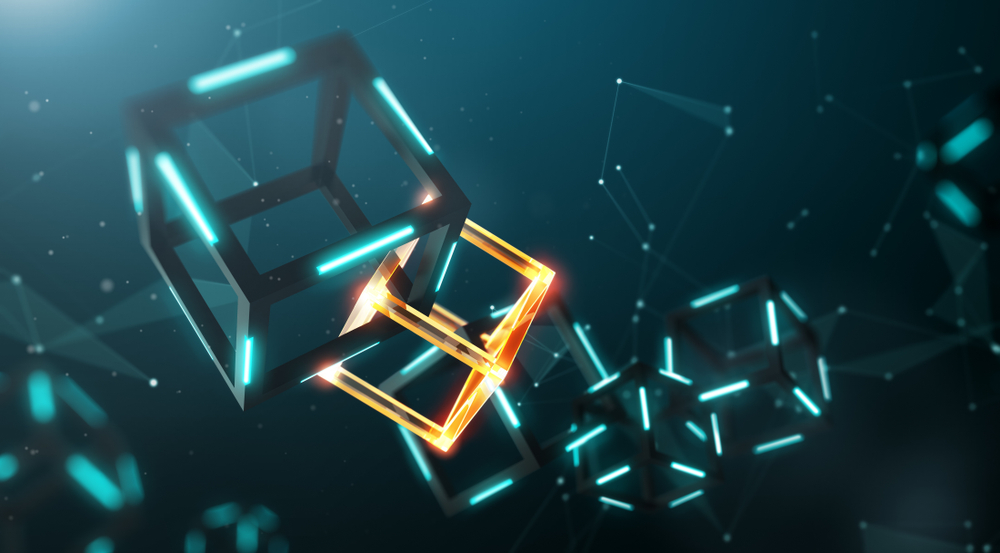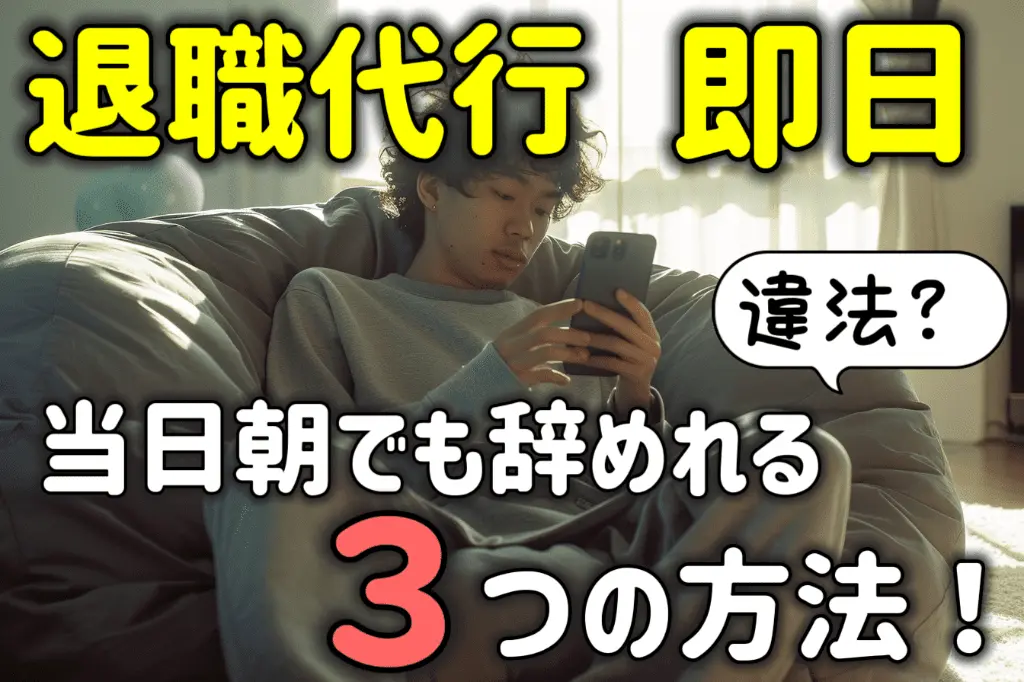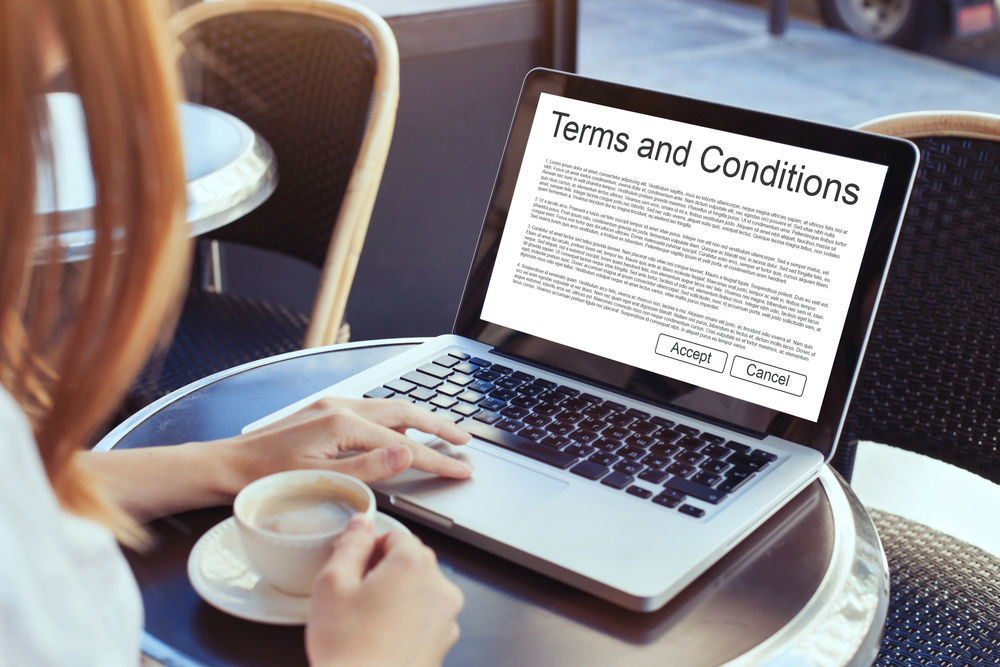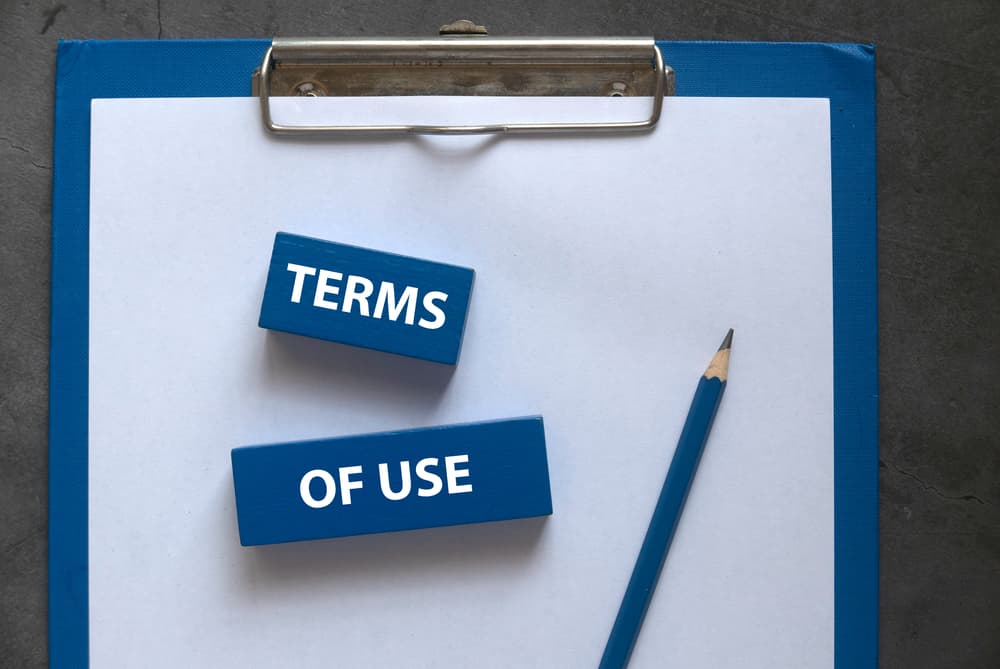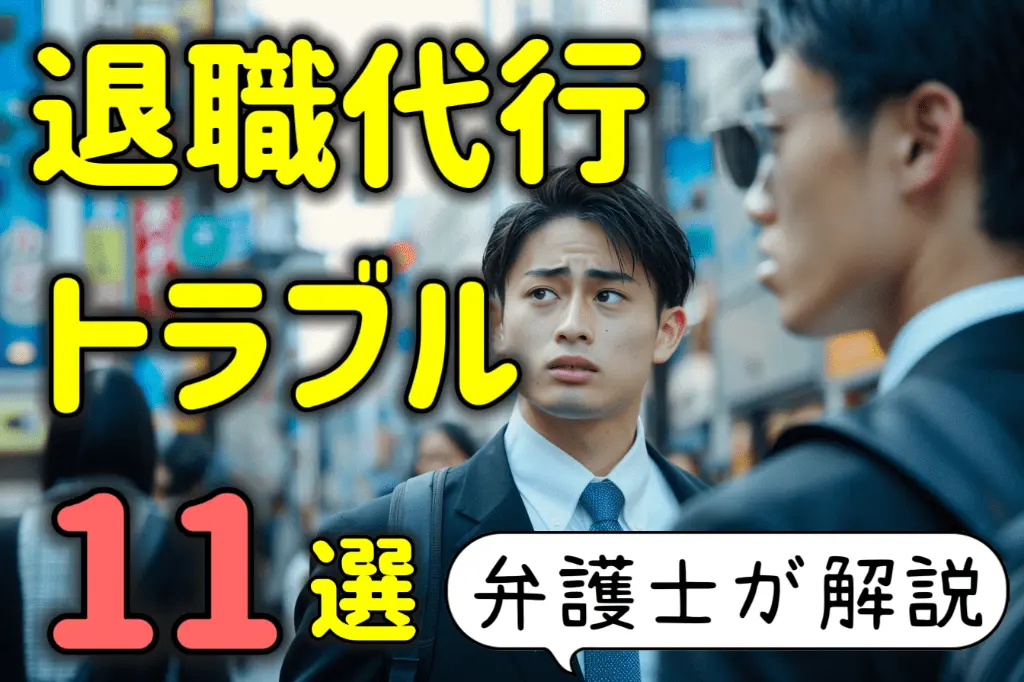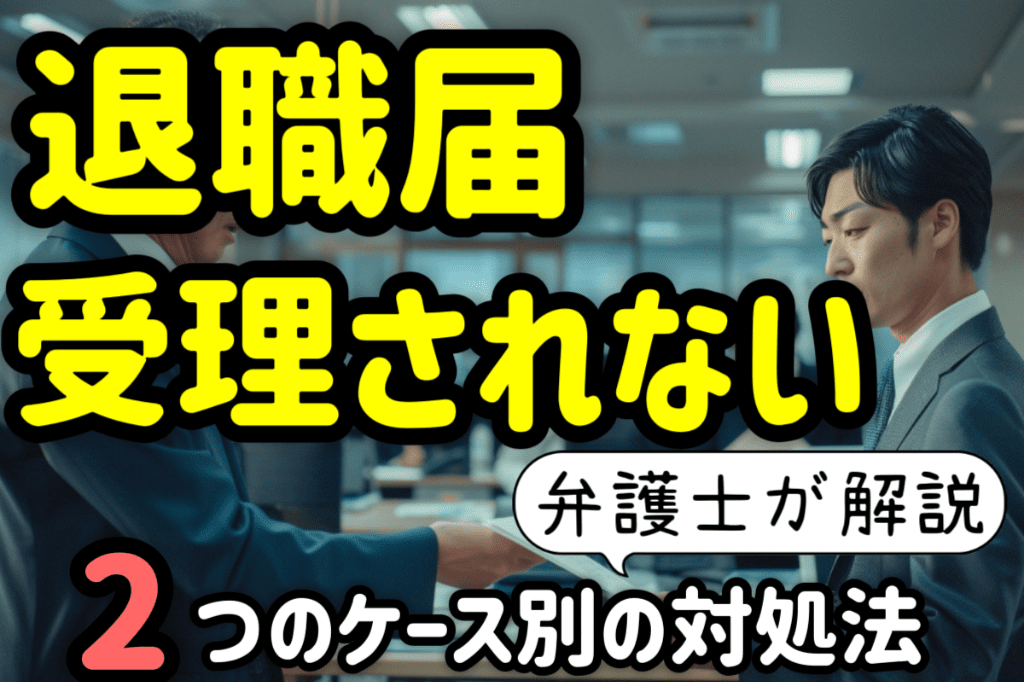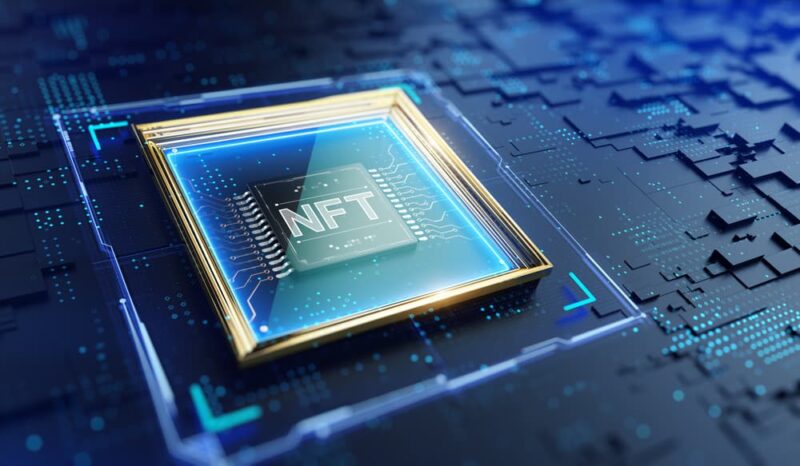もうICO詐欺に騙されない!7つの事例から読み解く6つの見分け方

はじめに
投資に対して積極的な方なら「ICO」という言葉を聞いたことはあるでしょう。ものすごく儲かるという成功体験がインターネット上に溢れている一方で、「ICO詐欺(スキャム)に引っかかってしまった!」という被害の声も後を絶ちません。また、ICOと検索すると専門家などが警鐘を鳴らすような記事もチラホラ存在していて、なかなか手を出しづらいですよね。
そこで本記事ではICO詐欺(スキャム)の事例、ICO詐欺の特徴、実際に詐欺かどうかの見分け方、そして引っかかってしまったらどうすればいいか?という点までをわかりやすく解説していきます。ICOに関心のある方や、ICO詐欺の被害に遭われてしまった方はぜひともご一読ください。
1 ICOとは?

「ICO」とはどのようなものなのでしょうか。
「ICO(アイシーオー・Initial Coin Offering)」とは、事業者側が発行した「トークン」と呼ばれる独自の暗号通貨を販売し、その対価として、投資家からイーサリアムやビットコインなどの仮想通貨の払い込みを受けてする資金調達の方法です。
この点「仮想通貨」とは、
- 円やドルのような通貨とはまったく別の
- 不特定多数の人々と交換可能な
- インターネット上で使用する
- 紙幣のような現金という概念のない
通貨のことを指します。有名なものに「イーサリアム」、「ビットコイン」、「ネムコイン」などがあります。
※仮想通貨の定義など、仮想通貨法(改正資金決済法)について詳しく知りたい方は「仮想通貨の法律規制とは?仮想通貨法6つのポイントを弁護士が解説!」をご参照ください。
また、ICOにおいては投資家へ、さらにプロジェクト内容を理解してもらうために「ホワイトペーパー」というものを作成します。
そもそもホワイトペーパーとは、
- 事業の発起人、トークンの開発者の身元
- 技術的な課題やソリューションの内容
- トークンの詳細
- ブロックチェーン技術の管理体制や作用
- 技術チームにいる人間の経歴など
- リスクについて
などが書かれた事業計画書のことをいいます。ICOに参加する投資家は通常、この「ホワイトペーパー」の内容を踏まえて、投資をするかどうかの判断をしています。
上記の前提を踏まえたうえで、以下で、具体例を交えながら「ICO」の仕組み、流れなどを見てみましょう。
-
【事例】
事業会社A社は最近起こされたまったく新しい事業会社です。先鋭的なビジネスの計画を持っているものの、とにかくお金がありません。そこでA社は「ICO」を用いて資金を集めることに決め、ホワイトペーパーを使って公に発表したところ、めでたく投資家のBさんが「4000万円」分の仮想通貨を投資してくれるという話になりました。
この事例で上げたA社を例として、実際のICOの流れを説明します。
- A社はまず「トークン」と呼ばれるまったく新しい独自の通貨を発行します。(この時点ではおもちゃのお金とまったく変わらないほぼ無価値なものです)
- 「ホワイトペーパー」を読んだBさんが事業に未来を感じ取り、「独自トークン」を「仮想通貨」で購入しました。
- A社は投資してもらったので「仮想通貨」を実際に手に入れることができました。
- A社は手に入った「仮想通貨」を仮想通貨交換所にて現金に換金することで、資金調達に成功しました。
この一連の流れをICOと呼びます。図解をすると以下のようなイメージです。

ここでポイントなのは、「一番最初の段階(トークン発行時点)においては独自トークンは事実上ほぼ無価値であり、投資家にとって魅力的なものではない」ということです。
一見すると「全然価値がないのに誰が買うの?」と思うかもしれませんが、A社の事業が大きくなるにつれてこの「独自トークン」の価値も上がっていきます。そうなると、投資家は価値の上がる前の「独自トークン」を購入しているわけですから、価値が上がれば上がるほど得をするわけです。
このメリットの部分だけ聞くと、「儲かりそう!」と思うかもしれません。現実でもインターネット上ではこの部分だけを言葉巧みに説明して投資へ促す書き込みも少なくありません。
ですが、現在の「ICO」においては、残念ながら詐欺目的で資金を集める悪質な事業者が後を絶ちません。せっかく未来に期待して投資をしたのに、多額をドブに捨てたような喪失感を覚えている投資家が世界中に溢れているのが現状です。
では、実際にどのくらいの割合で、どのような背景があってICO詐欺(スキャム)が増加しているのでしょうか。
以下で詳しく見ていきましょう。
2 ICO案件のうち詐欺の割合とは?

ICOにおいて、はたして詐欺事案はどのくらいの割合を占めるのでしょうか。まずは以下のグラフをご覧ください。
【グラフ1】

https://medium.com/satis-group/ico-quality-development-trading-e4fef28df04f
【グラフ2】

https://medium.com/satis-group/ico-quality-development-trading-e4fef28df04f
これらの図はニューヨークのICO、デジタルアセットに関するアドバイザー企業である「Satis Group LLC」が調査した統計データになります。内容は、Mcapという仮想通貨プラットフォームを使用したICO案件の割合を円グラフで示したものです。ここでは大まかに以下の6つに分類しています。
- 失敗(放棄をしたり、投資家へ資金を払い戻しするなど)
- 行き詰まり(一向に取引所へしない)
- 詐欺(サイトの公開や、入金先を掲載したあとにプロジェクト開発を行う意思がない、またはコミュニティにて詐欺とみなされている)
- 成功(目標資金調達額成功後→プロジェクト開発に成功)
- 先細り(目標資金調達額成功後→プロジェクト開発が先細り状態)
- 有望(目標資金調達額成功後→プロジェクト開発中)
上記のグラフから、ICOは詐欺が実に81%をも占めていることが分かりますね。このように、現状のICOは5件のうちの4件は詐欺であることが統計データとして表れています。
では、なぜICOには詐欺案件が多いのでしょうか。その理由を次の項目で確認していきましょう。
3 ICOには詐欺案件が多い理由

残念ながらICOにおいては、「最初から投資家を騙す目的の事業者が多い」のが現実です。詐欺業者たちは、資金を集めるだけ集めたら雲隠れしてしまうため、多くの投資家たちは泣き寝入りを強いられています。
では、一体なぜICOには詐欺が多いのでしょうか。その原因としては、
- これまでとは違い、簡単に参入できる
- 仮想通貨を取り巻く法整備がなされていない
- 仮想通貨、ICO、ブロックチェーンの技術の仕組みは非常に複雑で、投資家の理解が追い付いていない
- 聞こえのいい情報がネットなどで先行している
- ICOをしている側のシステムのセキュリティがまだまだ弱い
- ホワイトペーパーや公式HPが英語のものが多く、大多数の日本人は評判やイメージで投資をしてしまっていた
などが挙げられます。
投資家から見ると、豪華なHPがあって、ホワイトペーパーには壮大な展望が書いてあり、携わっている人間もすごい経歴だ、となるとついつい手を出したくなりますよね。それに加えて、詐欺師はパンフレットを配布したり、とにかくお金が増えるという点を強くプッシュしたりして投資家を惑わせます。そのため、知識の浅い投資家はまさにカモ状態で、不確定な未来に投資をした投資家が大損をしてしまうわけです。
そして、この手口はだんだんと巧妙になってきています。詐欺をする側からすると、ICOをきちんと理解している人がまだ少ない現状は、非常に詐欺がしやすいと言っても過言ではありません。
他方で、既存の被害事例からICO詐欺の手口の傾向が徐々に見えてきています。ICO詐欺に引っかからないようにするために、まず典型的な手口から見ていきましょう。
4 ICO詐欺の手口

ICO詐欺の手口としては以下の3パターンが代表的です。
- フィッシング詐欺パターン
- SCAMパターン
- 「荒らし屋」の自作自演
それぞれを詳しく見ていきましょう。
(1)フィッシング詐欺パターン
投資家がICOへ参加する際には、通常、事業者の公式HPに記載されているメールアドレスを通じて入金などを行います。過去の事例から、ハッカーはこの公式HPに目をつけ、公式HPをハッキングした上で個人情報を抜き取り、
-
公式HPと極めて似たサイトの作成
公式のメールを装って支払うように誘導してくる
などのフィッシング詐欺のような悪質な手口により資金を騙し取りました。
例えば、事業者側しか知り得ないような個人情報(例えば、投資家が入金した金額)などがメールの文面に織り交ざっていては、投資家側としてはそのメールの内容を容易に信じ込んでしまいますよね。
このように、セキュリティの観点では、その脆弱性が大きく問題視されています。
(2)SCAMパターン
「SCAMパターン」とは、そもそも詐欺の目的で、「ICO」を行い資金を集める手法です。発案したビジネス自体が架空のもののため、資金を集めるだけ集めたら逃亡します。詐欺師はあらゆる方法で投資家にアプローチをしていきます。人間の心理を逆手に取るような手段を使ってきますので、慎重な選択眼が求められます。
具体的には、以下のようなケースは詐欺の可能性が高いといえます。
- 「確実に儲かる」などと明言している
- セミナーや代理店を使った勧誘
- 電話で直接勧誘してくる
- 最低購入金額が決まっている
- 限定販売を謳っている
- 価格保証がある
たとえば、とにかく売ろう売ろうとプッシュするような事業者は疑ってかかってください。そもそも、素晴らしいICO案件はそんなことをせずとも自然と投資家がついてくるはずです。
また、ICOにおいて限定販売や価格保証はあり得ません。資金調達を目的にしているので限定販売をするメリットはまったく事業者になく、また、ICO自体が不確定要素が多いため価格保証などそもそもすることはできないからです。
(3)「荒らし屋」の自作自演
最近横行している手法で、「荒らし屋」と呼ばれる詐欺師が存在します。彼らは、将来性のある事業を見つけると、わざと誹謗中傷や虚偽の事実をネット上に書き込みます。そして、いま保有しているトークンを手放すようにと言葉巧みに持ち掛け、安値で買い叩きます。その後値上がりすると一斉に売りさばき一人勝ち状態を作り出そうとしています。
上記のような手口からも分かる通り、ネット上の情報を鵜呑みにせず、疑わしい点は明らかになるまで調査をすることが重要です。
こうした手口は全て実際に起きた事例に基づいています。過去、実際にあったICO詐欺事例については次項でみていきましょう。
過去の詐欺事例を知ることによって、ICOの問題点を浮き彫りにすることができます。
5 実際にあったICO詐欺の事例

(1)「Dircoin」ICO詐欺事件
「Dircoin(ディールコイン)」は、アラブを含む中東の10ヵ国が、原油の取引や決済のために共同使用することを目的とした仮想通貨です。別名オイルコインともいいます。当初の予定では、韓国のビットコインを最も保有していた「ヌリ・ブリッジ」社がマイニングを行い2015年に正式に発表されると言われていた仮想通貨でした。「石油王が仮想通貨を作りました!」と大々的に触れ込み、約100億円は集めたとされています。
ところが、蓋を開けるとブロックチェーン技術などはまったく利用されておらず、ただのHTML形式のデータでしかありませんでした。当然、HTML形式のデータではサーバーがダウンしてしまった場合にコインの価値そのものが完全に消滅してしまいますよね。投資家はこの事実に一時騒然となりました。
被害状況として、いわゆるねずみ講のようなセミナーを用いて高齢者向けに投資をすすめ、資金を振り込むとまったく返信がなくなってしまったという被害が多数寄せられました。現状は、公式HPは閉鎖、運営側も所在が分からない状態ですから詐欺コインとして有名になりました。
(2)「Recoin」ICO詐欺事件
「Recoin」はアメリカのRecoinクラブ・ファンデーション社が発行していた不動産投資ICOとして注目を集めたトークンです。本トークンは、業界初の不動産を担保にした新しいICOを提案し、一斉を風靡しましたが、米証券取引委員会(SEC)は詐欺及び違法証券発行の罪で立件をしました。
今回の事件の大きなポイントとしては、
- 弁護士、会計士、優れたブローカーや不動産の専門家が携わっていると情報を公開していたが、その事実がまったくなかった
- 4億円近くの資金調達に成功していたとしていたが、実際には3000万円の資金調達しか確認が取れなかった
という虚偽の表示が見られ、明らかに投資家を騙そうとしていた模様です。米証券取引委員会(SEC)がICO投資について初めて立件をした事例としても大きな話題となりました。
また、代表を同じくするダイヤモンド発掘事業会社のダイアモンド・リザーブ・クラブが発行する仮想通貨「DRC」に対しても同じ罪状で立件を行っています。
(3)「Seele」ICO詐欺事件
多数の投資家から苦情が相次ぎ、ICOを行っていた事業者「Seele」チームは「架空のICOプロジェクトの提案による詐欺が発生しました」と発表しました。
本件では、何者かが管理者であるニック・スミス博士を装い「公式の集金に先立つプライベートセールだからイーサを送金してね。」というメッセージを送り、偽物のウォレットを用いて約2億円を騙し取られました。
現在、「Seele」側は、
- 管理者のアカウントに二段階の認証システムを導入
- 緊急対策チームを設置
- 調査の結果を公に発表することを約束する
- 被害者向けの緊急のホットラインを設置する
- 被害金額の返還に向けて細かな計画を作成していると名言している
などの状況改善の措置を行っていることを明らかにしました。
一部では、「管理者を装うというのは、管理側しかできないのではないか?」という声も挙がっており、内部犯行の疑念が広がりつつあります。
現状、とても注目されているICO詐欺事例です。
(4)「Parity」マルチシグウォレット資産盗難事件
Parity社を含むイーサの中で最も規模の大きい3つのマルチシグウォレットからイーサリアムが盗まれました。2017年度の仮想通貨業界に最も衝撃を与えた事件です。
「マルチシグウォレット」とは、ざっくりいうと、仮想通貨が保管されている金庫のようなものです。このマルチシグウォレットの、セキュリティ上の脆弱性に目をつけたハッカーは、その全ての中身を引き出しました。総額は最終的に118億円相当とされています。事件後、Parityの対策チームが最善を尽くしましたが、結局失った仮想通貨が戻ってくることはありませんでした。
(5)「Parity」マルチシグウォレット資産凍結事件
2017年11月19日、「Parity」のセキュリティ上に極めて重大な脆弱性が再度発見されました。
ハッキングによる盗難などはありませんでしたが、ユーザーがソフトウェアのバグを発見したことがトリガーとなり、2017年11月6日に約300億円のイーサリアムが凍結したことが発覚しました。これは、投資家が入出金などの手続がまったくできなくなったことを意味します。
極めて高い技術者がセキュリティのシステムを組んでいるにも関わらず、このような事態に直面しているため、仮想通貨、ICOの課題が目に見えて分かったことに世間の注目は集まりました。
また、同じ会社による年内2度目の大きな事件ということで、セキュリティの甘さにイーサリアムなど仮想通貨自体への批判が相次ぎました。
(6)「Enigma」ハッキング事件
仮想通貨の投資家向けプラットフォームである「Enigma」がハッカーにハッキングされるという事件が起こりました。このハッキング事件の数日前から、投資家たちがICOに参加できるようなプラットフォームの準備を進めていたものの、
- 公式のドメイン
- 「slack」の管理者のアカウントやメールリスト
がハッキングされ、本物のメールアドレスから送金を促すメールを送られてしまいました。被害総額は、約5500万円とされています。
「Enigma」の運営サイドはアカウントの正常化には成功したものの、盗まれた金額が戻ってくることはなく、投資家は泣き寝入りを強いられました。
(7)Tetherトークンハッキング事件
Tether Limited社が発行している仮想通貨「USDT(Tether)」がハッカーによって盗み取られたという事件です。
そもそもUSTDは、1ドル=1Tetherとし、国が発行している通貨と同価値の通貨として広く流通していました。他の仮想通貨は、価格が上がったり下がったりと極めて不安定なため、投資家が一時的に預ける用途などで使用されていました。
2017年11月19日 Tether Limited社は34億円相当のUSTDが流出したことを発表、その後ビットコインの価格が暴落するなど大きな騒ぎとなりました。
USDT運営チームは、「流出したUSTDを、ハードフォークというブロックチェーン上の技術を用いて価値を無効化することに成功した」と公にはしたものの、世評を著しく下げてしまう結果となりました。
以上が実際にあったICOの詐欺事例です。もっとも、上記以外にも多くの詐欺事例があり、各国の法律規制が追い付いていない現段階では、いかに詐欺師のターゲットになりやすいかはご理解いただけたのではないでしょうか。となると、投資家側からすると詐欺を疑うことすら難しいのかもしれません。
しかし、上記の詐欺事例などからある程度ICO詐欺を見分けるパターンが見えてきています。「こういうケースは手を出さない方がいいよね。」というケースがいくつか存在しますから、以下で確認していきましょう。
6 ICO詐欺の特徴・見分け方

ICOはとにかくまだまだ情報が少なく、詐欺かどうかというのは個人の判断で見分けていく他ありません。
したがって、ICO投資を行うに際しては上記の過去の詐欺事例などを参考にして、こういうパターンのものは詐欺である可能性が高い、というものを意図的に回避していくことが必要になります。実際に詐欺と疑わしいパターンを紹介します。
(1)公式HPなどの翻訳対象が日本語のみの場合がある
海外の事業者がICOをしていて、公式HPなどの翻訳対象が日本語だけの場合は詐欺を疑って下さい。そもそも、日本のみICOの対象にするというのも変な話で、中国語などが優先して翻訳されたりするのが常です。日本人の情報弱者をカモにしようという意図があると考えてもよいでしょう。
(2)ICOの掲示板の検索に引っかからない、または変な書き込みがたくさんある
掲示板が無い場合はその時点で詐欺と断定しましょう。意図的に悪評を隠そうとしている可能性が極めて高いからです。
他方で、掲示板がある場合は、その投稿内に詐欺かどうかの書き込みが大抵あります。
異様に褒め称えたり、逆に誹謗中傷ばかりの書き込みばかりの場合は投稿者のアクティビィを確認して、投稿者が信用に足る情報源かを判断してください。
また、海外ICOの場合は必ず海外掲示板を閲覧するようにしましょう。
- bitcointalk ※「ICO名+bitcointalk」 で検索すると出てきます。
- coin jinja
こちらのサイトは代表的なICO情報の検索プラットフォームです。
会員登録が必要なサイトは新規で会員登録をして閲覧をするようにしてください。
(3)開発者、開発チームの人間が怪しい
ホワイトペーパーに記載のある開発者名や開発チームの人間についてをかたっぱしから検索していきましょう。
- googleなどの検索エンジンで人名を検索
- linkedinにて検索
様々な検索機能を使用して、開発者の情報を収集することが大事です。
また、以下のような場合には詐欺を疑ってください。
- 他人の写真を使っている
- 検索にひっかからない、または極めて引っかかりにくい
(4)高い配当率を謳っているICO
とにかく配当率の高さを売りにしたようなICO案件は真っ先に詐欺を疑ってください。というのも、過去の事例から、
- 少額を集金してはICOの広告費用に充てるという、いわゆる自転車操業を繰り返したのちにある程度の資金が貯まったら逃亡してしまう
といったケースが多く見られます。利益率のみを考えて投資をしてしまうと痛い目を見るかもしれません。
ICO詐欺に多い特徴と見分け方についてはいかがだったでしょうか。
「いろいろ検討してみたが詐欺と疑わしい点は特に見当たらないぞ。」という方は次のステップに進みましょう。具体的には参加をしようと決断してからも気をつけることがあります。実際に過去の事例では、ICOに参加意思のある人間が姑息な手段で騙されています。では、一体何に気をつけるべきなのでしょうか。次の項目でチェックしていきましょう。
7 ICOに参加するときに気をつけること

ICO詐欺に引っかからないためにはやり過ぎなレベルの注意が必要です。
以下のチェック項目を必ずチェックするようにしてください。
(1) 送金専用のアドレスが添付されているメールが届いていないですか?
ICOにおいて、送金用のアドレスをメールの本文に記載をすることはほとんどありません。ですから、メール内に送金専用のアドレスの記載がある場合には注意が必要です。通常は公式HPなどに送金専用アドレスが表記されています。
ですが、「これが公式の手順ですよ。」といった場合には掲示板などのコミュニティで入念な調査を行いましょう。そこでも、明らかな情報が得られなかった場合には、ICO投資への参加を見送った方が良いでしょう。
(2)コミュニティに変なことを書いていないですか?
ICOに参加する際に、ネット上の公式コミュニティを必ず確認しましょう。
代表的なチャットアプリのTelegramを用いたコミュニティなどはとても充実しています。こういったコミュニティをきちんと確認し、できれば積極的にチャットに参加することをオススメします。ある程度情報の基盤が固まるまではICOに参加をしない、という姿勢が非常に大事です。
(3)セミナーや口頭での勧誘をされていませんか?
セミナー、口頭での勧誘はまず信用しないようにしましょう。
これは、何もICOに限らず言えることですが、自分の資産を他人の口車に乗って運用することは非常に危険なことです。魅力的なセミナーがあるときは、出来得る限り情報を集めてください。すこしでも「怪しいな。」と感じたときは絶対に手を出してはいけません。
(4)参加するICO案件に関する情報を可能な限り集めつくしましたか?
情報はICOへの参加において最も大事なことです。そもそもICO詐欺が多くなった原因としては、投資家側がホワイトペーパーをよく読まなかったりと、情報収集不足が原因で詐欺を見抜けなかったからです。ですから、ICOの情報をより多く集めることは非常に重要なことです。そこで、最低限以下の項目はチェックするようにしましょう。
- ブロックチェーン技術の利用はありますか?
- ホワイトペーパーに書いてある内容は理に適っていますか?
- ICOで資金調達する目的は何ですか?
- 事業の描いているビジネスプランの伸びしろはありますか?
- ライバル会社はいますか?
- ロードマップは適正ですか?
- どんな人たちが関与していますか?調査の段階で怪しい経歴の人間はいないですか?
- 公式にて事業者と直接やりとりはできますか?
- ネット上ではどのような評判ですか?
- ICOの資金調達後の明確な動向の説明はありますか?
上記のチェック事項をもとに、ICOをする事業者側に積極的に質問をするなどして、一つ一つの疑問点を全て解消させるまで手を出さないようにしましょう。
(5)ICOに参加をしないことも視野に入れる
「情報を集めても疑問点が拭えない。」そんな場合はICOから早急に手を引きましょう。
ICOにおけるトークンはそもそも現状においては無価値になってしまう可能性があることを意識することが大切です。
さらにICOに成功したとしても、計画通りにビジネスを動かしてもらえる保証はどこにもありません。ですから深追いはせず、ICOに参加するときは、「信用に足る情報が揃っている」という状況下で投資をすることが賢明と言えます。
(6)実際に上場した後にICOに参加する
これはそのままの通りで、ICOに参加する段階でどうしても不安が拭えないけど諦めきれない場合にはその動向を静観してみるのも一つの方法です。その上で軌道に乗り、上場をした場合に購入するという方法はある意味堅実と言えます。
8 ICO詐欺に遭ってしまったら?

どんなに注意深くICOに参加しても、詐欺に引っかかってしまうことは大いに考えられる未来です。実際にICO詐欺で資金を失ったときはどのように動けばいいかわからないですよね。そこで、あまりに悪質な詐欺に引っかかってしまって納得がいかない場合には、以下に相談することをおススメします。
もっとも、相談したからといって解決に至るかというとそうではありません。原則、ICO投資への参加は自己責任です。したがって、補償などをしてもらえるようなものではないことは念頭に置きましょう。
ですから、ICO投資を行う場合には、
- ICOの知識を広く獲得する
- 入念は調査行う
- 無理な投資は行わず、余っている資金内で投資を行う
という意識を必ず持っておいてください。
9 小括

ICOの詐欺事例と詐欺かどうかの判断方法はいかがだったでしょうか?
不明確な要素の多い投資ですから、とにかく情報収集が大事だということはご理解いただけたかと思います。残念ながら、現状では巧妙に投資家を騙す詐欺事業者は後を絶ちません。本当にICOをして事業発展をしようとしている企業にとっては向かい風となっている時代です。投資家側も過去の事例や情報を収集し、適正な判断を下すことが大切です。とともに、ICOにおけるトークンはそもそも現状「無価値になってしまう可能性がある」ことを常に意識しましょう。ICOへの参加は自己責任ですから慎重に判断して投資を行ってください。
10 まとめ
- ICOとは事業者が独自に作った「トークン」と呼ばれるものを、投資家が既存の「仮想通貨」を用いて購入することで、事業者側は資金を手に入れることができるという資金調達の方法を指す
- ICOの詐欺が多い理由として、①簡単に参入できる、②法整備がなされていない、③投資家の理解が追い付いていない分野である、④メリットばかり目に付く、⑤セキュリティがまだまだ弱い、⑥大多数の日本人は評判やイメージで投資をしてしまっていた、などが挙げられる
- 事例から見るICO詐欺の手口として、①フィッシング詐欺、②そもそも詐欺目的の事業展開、③荒らし屋の自作自演などが挙げられる
- ICO詐欺と疑わしいパターンとして、①翻訳対象が日本語のみの場合、②掲示板に情報がない、③あったとしても異様に褒め称えるような投稿が多い、④高い配当率を売りにしているなどがある
- 送金専用のアドレスがメールに記載されている場合や、セミナー、口頭での勧誘も注意するべきである
- ICO詐欺に引っかからないために、ホワイトペーパーの読み込みやコミュニティへの参加などを駆使して出来得る限り情報集める
- 上場後に投資をすることや、そもそも参加しないことも視野に入れる
- ICO詐欺に引っかかってしまった場合は、金融庁や消費者ホットラインに相談をする
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。