事故調査にドローンを活用する場合の3つの法律規制を弁護士が解説!

はじめに
ドローンは、リモコンによる遠隔操作で飛ばすことができるため、人が立ち入りにくい事故現場の調査するには大変便利なツールです。
もっとも、事故調査のためであるからといって、自由にいつでもドローンを飛ばせるわけではありません。ドローンには落下や衝突のリスクがあることから、「航空法」をはじめとした法律によって一定の規制がかけられています。
そのため、事故調査にドローンを用いる際も、航空法等の規制を守りながらドローンを飛ばさなければなりません。
そこで今回は、事故調査にドローンを活用する際に重要となる法規制のポイントをITに詳しい弁護士が解説していきます。
1 事故調査におけるドローンの活用

事故が発生すると、多くの場合損害保険会社や同社から委託を受けた損害鑑定事業者は現地に赴き、損害の状況を詳細に調査して損害額などを鑑定します。
このような「事故調査」は、被害者救済の見地から、迅速であることが求められるため、近時では、事故調査をドローンによって実施する保険会社も出てきています。
ドローンを用いることで、ヘリを使った調査よりも手続や費用の負担が軽いというメリットがあり、また、大規模な自然災害や化学工場の爆発事故など、人が立ち入って調査することに大きな危険が伴うような現場であっても、ドローンであれば、安全・正確に調査することが可能です。
このようにドローンを使った損害調査には多くのメリットがあるため、今後ますますドローンが活用されていくものと考えられます。
とはいえ、ドローンが空を飛ぶ機体である以上、「航空法」を始めとした関連法規の規制を受けることは避けられません。
ドローンの飛行を申請するドローン事業者はもちろん、ドローンを操作するスタッフや現場で安全管理を受け持つ事業者などにおいても、航空法を始め、関連法規に対する適切な理解と万全の安全管理対策が求められることになります。
2 航空法による2つの法律規制

事故調査を目的とするかどうかに関わらず、ドローンを飛ばす場合には、以下の2つの航空法上の規制を受けます。
(1)飛行「場所」の規制
ドローンの飛行中に衝突や落下が起きると人や物に大きな危害を与える可能性があります。
そこで航空法では、被害が拡大しやすい次の2つの場所を「飛行禁止区域」と定め、ドローンの飛行を原則的に禁止しています。これらの場所で例外的にドローンを飛ばすためには、国の許可が必要です。
①航空機の安全に影響するおそれのある場所
具体的には、「空港周辺」や「地面または水面から150メートル以上の空域」がこれにあたります。空港の周辺は昼夜を問わず航空機が飛び交っているため、ドローンの飛行が禁止されるのは当然です。
また「地面または水面から150メートル以上」の高さでドローンを飛ばすと、他の航空機の航路とバッティングする可能性があることから、この場合も原則としてドローンを飛ばすことはできません。
②人口集中地区(DID地区)での飛行
「人口集中地区(DID地区)」とは、人や家屋が密集する場所のことをいいます。
このような場所の上空でドローンを飛ばして事故を起こしてしまうと、人や物に危害を与えるおそれが飛躍的に高まるため、原則としてこのような場所の上空でドローンを飛ばすことはできません。
DID地区については、国土地理院が出している「人口集中地区マップ」で確認できます。
上の画像で、赤く色が塗られている地区が人口集中地区(DID地区)にあたります。

(2)飛行「方法」の規制
航空法は、飛行「場所」のほかに、飛行「方法」について以下の6つのルールを定めています。これらのルールに反する形でドローンを飛ばすには、国の承認が必要です。
- 日の出から日没までの間に飛ばすこと
- ドローンとその周辺を直接目で見て常時監視すること
- 人や物との間に30m以上の距離を保つこと
- 人が多く集まるイベント会場の上空で飛ばさないこと
- 爆発物などの危険物を輸送しないこと
- ドローンから物を投下しないこと
①日の出から日没までの間に飛ばすこと

ドローンの機体は小型であるため、暗くなると肉眼で常時監視することが難しくなります。そのため原則として日の出から日没までの間に飛ばさないといけません。
②ドローンとその周辺を目視で常時監視すること

ドローンを目視で常時確認できない状態で、ドローンを飛ばすのは大変危険です。
そのため、ドローンを飛ばすためには、直接自分の目でドローンの位置などを確認しなければなりません。
なお、目視外飛行の承認を受けるためには、「機体」や「操縦者」などについて課される基準をクリアしていなければなりません。
③人や物との間に30m以上の距離を保つこと

30m以上の距離を保てない場合は、原則としてドローンを飛ばすことはできません。人や物との間に距離がない状態でドローンを飛ばすと、衝突のおそれがあるためです。
④人が多く集まるイベント会場の上空で飛ばさないこと

多数の人が集まる場所でドローンが落下すると、大変危険です。
そのため、展示会などのように、多数の人が集まる会場の上空でドローンを飛ばすことはできません。
⑤爆発物などの危険物を輸送しないこと

火薬類などのような危険物をドローンで輸送することはできません。
万一、輸送中に危険物が落下してしまったりすると、重大な危害を与えるおそれがあるからです。
⑥ドローンから物を投下しないこと

ドローンから物を投下することは禁止されています。投下された物により、人や物に危害を与えるおそれがあるからです。
もっとも、ドローンで輸送した物を地面などに置くことは、ここでいう「投下」には該当しないため、許されています。
以上のように、ドローンを飛ばすためには、飛行場所(飛行禁止区域)と飛行方法(飛ばし方)という2つのルールを守ることが必要です。これらのルールに反することとなる場合には、国の許可・承認が必要となります。
このことは、損害保険会社の事故調査にドローンを用いる場合であっても同じです。
※航空法上の規制について詳しく知りたい方は、「ドローン企業が知るべき航空法とは?3つのポイントを弁護士が解説!」、「ドローンを用いたソーラーパネル点検の法律規制を弁護士が5分で解説」をご覧ください。
3 損害保険会社による事故調査

(1)問題となる航空法の規制
事故調査にドローンを用いる場合、先に見た航空法上の規制の中でも特に以下の規制との関係で問題となります。
①人口集中地区(DID地区)での飛行
既に見たように「人口集中地区(DID地区)」でドローンを飛ばすことは原則として禁止されています。
人口集中地区は、「人口密度が1平方km当たり4,000人以上の基本単位区(学校区や町、字など)」を基準としていますが、この基準だけでは実際にドローンを飛ばす場所が人口集中地区にあたるのかを判断できないこともあります。
そのため、先に見た「人口集中地区マップ」などを使って、ドローンを飛ばす地域がDID地区にあたるかどうかを確認し、DID地区にあたるようであれば、きちんと国の許可を取ることが必要です。
②ドローンとその周辺を目視で常時監視すること
調査対象となる現場が山間部・崖下のような場所である場合、ドローンとその周辺を目視で常時監視することができないことがあります。
このような中でドローンを飛ばすことは「目視外飛行」にあたるため、国の承認が必要になります。
なお、目視外飛行のための承認を受けるためには、「機体」・「操縦者」・「安全確保のための体制」という3つの基準をそれぞれみたしていなければなりません。
また、安全確保のための体制として配置を求められる補助者については、これを配置しないことも可能ですが、その場合は、さらに厳しい基準をみたしていることが承認を受けるための条件となります。
※目視外飛行のための承認基準について詳しく知りたい方は、「ドローンを用いたソーラーパネル点検の法律規制を弁護士が5分で解説」をご覧ください。
③人や物との間に30m以上の距離を保つこと
調査対象となる事故現場は、地上・水上を問わず、さまざまです。ドローンを飛ばす際には、地上や水上の人・物との間に30m以上の距離を保たなければなりません。
なお、30m以上の距離を保つべき「人」には、ドローンの操縦者やその関係者は含まれません。たとえば、事故調査を実施する損害保険会社の関係者などはここでいう「人」には含まれません。
また、30m以内の距離でドローンを飛ばすことについて承諾をしている者が管理している物はここでいう「物」に含まれません。
調査対象となる現場によっては、人や物との間に30m以上の距離を保つことが困難な場合もあります。
このような場合には、国の承認を得たうえで、ドローンを飛ばす必要があります。
以上のように、事故調査のためとはいえ、ドローンを飛ばす際には、その場所や方法を確認し、国の承認・許可が必要なのかどうかをきちんと確認することが重要です。
(2)事故調査におけるドローン飛行の許可・承認
事故調査を目的としてドローンを飛ばす際に、国の承認・許可が必要となる場合は、そのための申請を行う必要があります。
もっとも、将来的に事故がいつどこで発生するかを予測することは不可能です。また、事故が発生したことを受けて申請を行っていたのでは、十分な事故調査を実施できなくなる場合もあります。
そこで、このような場合には、一般的である個別申請ではなく「包括申請」による方法で飛行申請をすることが考えられます。
「包括申請」とは、ドローンを飛ばす地域や時について、一定の幅を持たせた申請方法です。
一般的である個別申請では、飛行日と飛行場所が特定されています。他方で、包括申請では、飛行日を「〇月〇日~〇月〇日」、飛行場所を「新宿区全域」というように、時や場所に幅を持たせることができます。包括申請によって得られる許可・承認は、原則として3か月以内、最長で1年間有効です。
このように、将来的に発生する事故を予測することができない以上、そのことを踏まえて、適切な申請方法を選択することが重要です。
誤った申請方法で承認・許可を受けてしまうと、実際に事故が発生しているにもかかわらず、ドローンを飛ばすことができない、なんてことにもなりかねません。
なお、国による承認・許可を受けるためには、次の項目で見るように、操縦者に飛行キャリアや飛行させるための知識・能力が必要になるなど、細かく設けられた条件をクリアしなければなりません。
このような条件をクリアできる操縦者がいてはじめて、国の承認・許可を受けられることになります。
4 許可・承認の審査基準
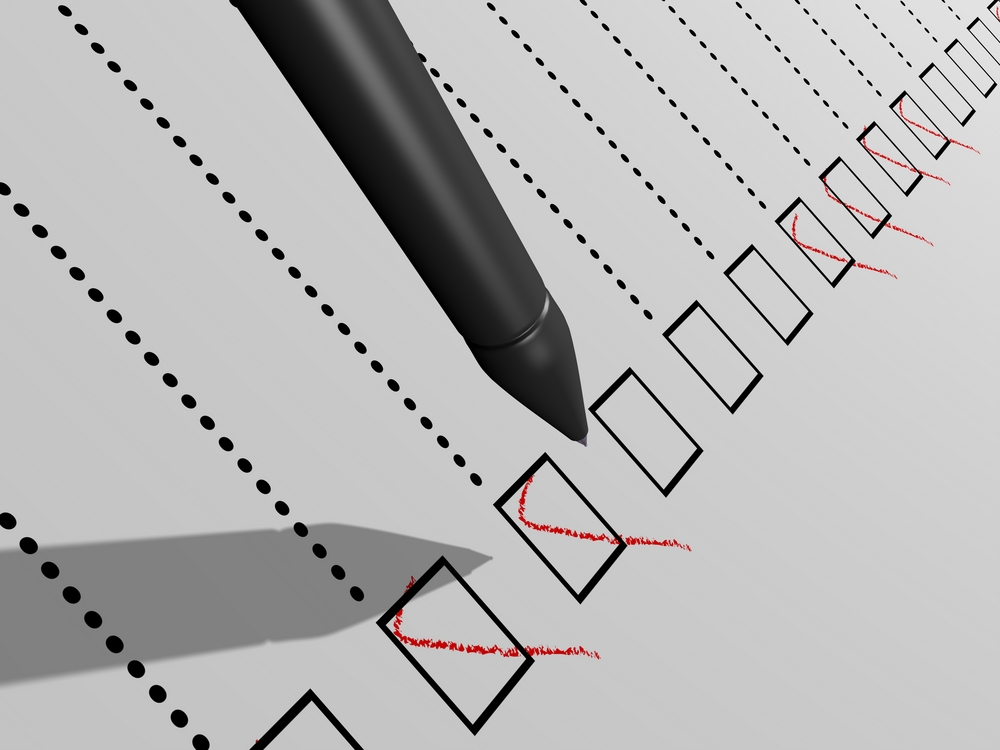
許可・承認の審査基準には、「基本的な審査基準」とは別に、ドローンの飛ばし方に応じて追加的に設けられる「追加基準」があります。
(1)基本的な審査基準
基本的な審査基準は、以下の3点です。
- ドローンの機能・性能
- 操縦者の飛行経歴や知識、能力
- 安全確保のための体制
①ドローンの機能・性能
ドローンの落下・衝突などにより、人や物に危害を与えることのないように、ドローンそのものに一定の安全性が求められます。
具体的には、突起物のない機体であること、目視で監視できるようにライトを点灯できることなどの基準を備えている必要があります。
②操縦者の飛行経歴や知識、能力
ドローンを安全に飛ばすために、操縦者は一定のキャリアや知識などを持っていなければなりません。
具体的には、操縦者に10時間以上の操縦経験があること、航空法やドローンの操作技術などに関する知識を有していることが必要です。
③安全確保に関する審査基準
ドローンを飛ばす際には、安全を確保するために必要な体制を取らなければなりません。
具体的には、気象条件や飛行経路などが安全に飛行できる状態かどうかを確認すること、
不要な低空飛行、急発進、急降下などを行わないことなどが求められます。
これら3つの基準は、いずれも基本的な基準であるため、許可・承認を受けるためには、原則としてすべてみたしていなければなりません。
以上に加えて、ドローンの飛行場所や飛行方法に応じて求められる追加的な基準をみたすことが必要となります。
(2)追加基準
空港周辺や人が大勢集まる場所でドローンを飛ばす場合のように、高い安全性が求められる場合は、基本的な基準に加え、追加基準をクリアしないかぎり、許可・承認が受けられないことになっています。
追加的に基準が課されるのは、以下の場所・飛ばし方でドローンを飛ばす場合です。
- 空港周辺または高度150メートル以上の空域
- 人や家屋が密集する場所(DID地区)の上空
- 夜間飛行
- 目視で常時ドローンを監視できない場合
- 人または物と30メートル以上の距離を保てない場合
- お祭りやイベントなど大勢の人が集まる場所の上空
- 危険物を輸送する場合
- 物を投下する場合
①空港周辺または高度150メートル以上の空域
主に、航空機との接触を避けるために求められる基準です。
具体的には、遠くから機体の存在を確認できるように、ライトをつけたり派手な塗装をしたりすること、空港に離着陸する航空機がない時間帯に飛行させることなどが求められます。
②人や家屋が密集する場所(DID地区)の上空
ドローンが落下して大勢の人や家屋に甚大な被害をもたらすことを避けるために求められる基準です。
具体的には、プロペラガードのような人や物への危害を軽減する装置をつけること、飛行経路全体の監視や通行人などに対する注意喚起を行うスタッフを配置することなどが求められます。
③夜間飛行
暗い中でもドローンをきちんと把握できるように求められる基準です。
具体的には、ドローンの存在を十分に確認できるだけの明るいライトを点灯させること、
離着陸スペースを照明で明るく照らすことなどが求められます。
④目視で常時ドローンを監視できない場合
目視ができない状況でもドローンを安全に飛ばすことを可能にするために求められる基準です。
たとえば、自動操縦装置を装備すること、GPSなどでドローンの位置を常時把握することなどが求められます。
⑤人または物と30メートル以上の距離を保てない場合
この場合は、原則として第三者の上空でドローンを飛ばすことはできません。やむなく第三者の上空を飛ばすような場合は、②DID地区の上空で飛ばす場合と同様の基準をみたす必要があります。
⑥お祭りやイベントなど大勢の人が集まる場所の上空
この場合も、原則として第三者の上空でドローンを飛ばすことはできません。やむなく第三者の上空を飛ばすような場合は、②DID地区の上空で飛ばす場合と同様の基準をみたす必要があることに加え、お祭りやイベントの主催者と事前に協議のうえ、安全確保の対策を講ずる必要があります。
⑦危険物を輸送する場合
危険物を安全に輸送するために求められる基準です。
具体的には、危険物の輸送に適した頑丈な機体であること、飛行経路全体の監視や通行人などに対する注意喚起を行うスタッフを配置することなどが求められます。
⑧物を投下する場合
物を投下する際に、人や他の物に危害を与えないようにするために求められる基準です。
具体的には、安全ロックを外さないと物を投下できないようになっている設計であること、操縦者においてドローンから物を投下させる経験が5回以上あることなどが求められます。
このように、国の許可・承認を受けるための審査では、基本的な基準に加え、ケースによっては、かなり細かく決められた基準が課されます。
そのため、事故調査にドローンを活用する場合には、損害保険会社はいずれのケースに該当するかを正確に見極めることが重要です。基本的な基準はもちろんのこと、追加基準を課されるケースであれば、追加基準についてもきちんとクリアしているかどうかを確認したうえで、許可・承認申請することが重要です。
以上のように、ドローンを事故調査に活用する際には、主に「航空法」との関係で問題となりますが、注意しなければならないのは航空法だけではありません。
※許可・承認の審査基準について詳しく知りたい方は、国土交通省が出している「無人飛行機の飛行に関する許可・承認の審査要領」をご覧ください。
5 航空法以外に注意すべき法律

ドローンで事故調査を行う場合、航空法以外にも、
- 個人情報の保護
- 他人の土地利用
という2つの問題が存在します。
(1)個人情報保護法
①問題の所在
ドローンを使って空中から事故現場を撮影すると、事故とは関係のない第三者などが映り込んでしまう可能性があります。個人の容ぼうが映り込んだ画像や動画は、特定の個人を識別できる個人情報保護法上の「個人情報」にあたります。
個人情報保護法上の「個人情報」を取り扱う事業者には、一定の義務が課されます。
②ドローン事業者にどういった義務が課されるのか?
個人情報を取り扱うドローン事業者には、次のような義務が課されます。
- 個人情報の利用目的の特定
- 取得した個人情報の通知・公表
- 個人情報の安全管理
- 取得した個人情報の目的外利用の禁止
- 不正な手段による個人情報の取得禁止
このように、個人情報を取り扱うドローン事業者は、まずは撮影により映り込んでしまった第三者の画像や動画が特定の個人を識別できるものかどうかをきちんと見極める必要があります。
そのうえで、特定の個人を識別できるのであれば、個人情報の取り扱いについて、上で見た義務をきちんと守り、適切に個人情報を取り扱う必要があります。
(2)土地の利用制限
土地の利用制限の問題は、「道路交通法」と「他人の土地所有権」との関係で問題となります。
①道路交通法との関係
事故現場が公道の近くである場合、事故現場の調査でドローンを飛ばすためには、道路交通法にしたがって道路の使用許可が必要になるようにも思えます。
この点に関しては、「交通の円滑を阻害したり、一般交通に著しい影響を与えたりするようなドローンの使い方をしないのであれば、道路の使用許可は不要」というのが警察庁の見解です。
そのため、機体の大きなドローンを複数飛ばして撮影するような場合や、低空飛行で撮影をするため車や通行人などに衝突するおそれがあるような場合は、一般交通に一定の影響を与えるおそれがあるため、所轄の警察に相談し、道路の使用許可が必要かどうかを確認するようにしましょう。
②他人の土地所有権との関係
土地所有権の効力は、一定の場合を除き、土地の表面・地下・上空のすべてにおよびます。そのため、他人の土地の上空でドローンを飛ばすことは、形式的には土地所有者の土地所有権を侵害することになります。
それでは、ドローンで事故調査をする場合、飛行経路下にあるすべての土地の所有者からドローンを飛ばすことについて許可を得ないといけないのでしょうか。
この点、事故現場の調査には迅速性が求められるため、土地所有者全員から許可を取らなければならないとするのは、あまりにも非現実的です。
そこで、このような点を回避するための考え方として、以下の2つのような考え方が挙げられます。
- 航空法上の許可・承認を得ている
- 土地所有者に事実上の不利益が生じない
(ⅰ)航空法上の許可・承認を得ている
航空法上の許可・承認を得てさえいれば、仮に、第三者の土地でドローンを飛ばしたとしても、土地所有権の侵害には当たらない、なんてことにはなりません。
ですが、航空法上の許可・承認を得ているという事実は、土地所有権の主張に対抗できるかどうかの大事な要素となる可能性があります。
もっとも、この言い分が通ってしまうと、航空法上の許可・承認を得たという事実が、他人の権利侵害を正当化する一つのツールになってしまうおそれがあります。
(ⅱ)土地所有者に事実上の不利益が生じない
飛行機は、飛行経路下の土地所有者にいちいち許可は得ていません。これは、飛行機が飛ぶような高度を通過しても、土地所有者に対する事実上の不利益は生じないと考えられるからです。
この理屈によれば、ドローンを飛ばして事故現場の調査をしても、土地所有者に現実的な不利益を与える可能性は低いといえます。
そのため、土地所有者の許可なしに、土地の上空でドローンを飛ばすことができるということになります。
もっとも、以上に示した2つの考え方は、いずれも現行法上認められているものではありません。
そのため、少なくとも現状においては、飛行経路の範囲にある土地の所有者全員から許可を受けることがもっとも無難な方法であるといえます。
6 航空法に違反した場合の罰則(ペナルティ)

航空法上の許可・承認を得ることが必要であるにもかかわらず、これを得ずにドローンを飛ばした場合、
- 最大50万円の罰金
が科される可能性があります。
仮に、損害保険会社の従業員が航空法に違反してドローンで事故調査を行った場合には、ドローンを飛ばした従業員とは別に、その従業員が在籍する損害保険会社にも最大50万円の罰金が科されることになります。
このようなことになってしまうと、損害保険会社にとっては信用失墜にもつながりますので、ドローンを飛ばす際には、国の許可・承認が必要となるケースかどうかをきちんと確認し、適切にドローンを飛ばすことが極めて重要になってきます。
7 航空法上の許可・承認申請のやり方

航空法上の許可・承認を得るためには、そのための申請が必要です。
(1)申請の種類
申請の種類は「個別申請」と「包括申請」の2つの種類があります。
①個別申請
飛行日・飛行経路が特定している場合は、「個別申請」によることとなります。
②包括申請
「包括申請」とは、飛行予定日や経路の急な変更などに備えて、期間や経路に幅を持たせる申請のことをいいます。
包括申請には、さらに、飛行日に期間を設定する「期間包括申請」と飛行経路に範囲を設定する「飛行経路包括申請」の2種類があります。
(2)申請方法
申請方法には、以下の4つの方法があります。
- 郵送
- 窓口提出
- オンライン申請
- 電話・電子メール・FAX
なお、電話・電子メール・FAXによる申請は、大規模災害などの緊急時にのみ許される申請方法であるため、原則は「郵送」、「窓口提出」、そして「オンライン申請」のいずれかとなります。
(3)申請に必要な書類
国の許可・承認を得る場合、申請書のほかに次のような書類を提出する必要があります。
- ドローンの機能・性能に関する基準適合確認書
- ドローンを飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書
- 飛行経路の地図
- ドローンおよび操縦装置の仕様がわかる設計図または写真
- ドローンの運用限界およびドローンを飛行させる方法が記載された取扱説明書等の該当部分の写し
- 許可等が必要な内容に応じた追加基準への適合性を示した資料
- ドローンを飛行させる者の一覧資料
- 操縦者の過去の飛行実績または訓練実績等を記載した資料
- 飛行マニュアル
※申請書の様式や作成の要領について詳しく知りたい方は、国土交通省のホームページ(「3.許可・承認手続きについて」)をご覧ください。
(4)申請書の提出先
申請書の提出先は、「空港事務所」または「地方航空局」です。どちらに提出するかは、以下のように、ドローンを飛ばす場所や飛ばし方によって決まります。
-
【空港事務所が提出先となるケース】
- 空港周辺空域での飛行
- 150m以上の空域での飛行
- 【地方航空局が提出先となるケース】
- 人口集中地区(DID地区)上空での飛行
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 人または物と30メートル以上の距離を保てない飛行
- イベント会場の上空での飛行
- 危険物を輸送する飛行
- 物を投下する飛行
地方航空局が提出先となる場合、さらに東京航空局か大阪航空局に分かれます。
管轄地の詳細については、国土交通省が出している「無人航空機の飛行に関するQ&A」(P19)をご覧ください。
※ドローンの飛行許可申請のやり方について、詳しく知りたい方は、「ドローンの飛行許可申請のやり方は?5つのポイントを弁護士が解説!」をご覧ください。
8 小括
ドローンビジネスの活況を受けて、より使い勝手の良い高性能なドローンが登場してきています。これからは、損害保険会社にとっても、ドローンを活用した事故調査はごく標準的な方法として定着するものと考えられます。
もっとも、ドローンの活用機会が増えれば、それだけ衝突・落下事故も起きやすくなります。航空法上のルールを始め、その他関係するルールを十分に理解し、ドローンを適切に飛ばすことが何よりも大切です。
9 まとめ
これまでの解説をまとめると、以下のようになります。
- 損害保険会社がドローンを飛ばして事故調査をする場合、航空法によって「場所」と「方法」の規制を受ける
- 航空法で禁止される場所や方法でドローンを飛ばす場合には、国の許可・承認を得る必要がある
- 航空法が規制する「飛行禁止区域」には、①航空機の安全に影響するおそれのある場所、②人口集中地区(DID地区)がある
- 航空法が規制する「飛行方法」とは、①夜間飛行、②目視外飛行、③人や物との間に30m以上の距離を保てない状態での飛行、④イベント会場上空での飛行、⑤危険物の輸送、⑥物を投下する飛行の6つである
- 損害保険会社の事故調査にドローンを使う場合、①人口集中地区(DID地区)での飛行、②目視外飛行、③人や物との間に30m以上の距離を保った状態での飛行、という3つの規制との関係が特に問題となる
- 飛行の許可・承認については「基本的な審査基準」と「追加基準」がある
- 航空法以外に注意すべき法律上の問題点として、①個人情報保護、②道路交通法、③他人の土地利用などがある
- 航空法に違反した場合、最大50万円の罰金に科される可能性がある
- 航空法上の許可・承認の申請手続としては、①申請の種類、②申請方法、③申請に必要な書類、④申請書の提出先の4つを押さえる
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。




















