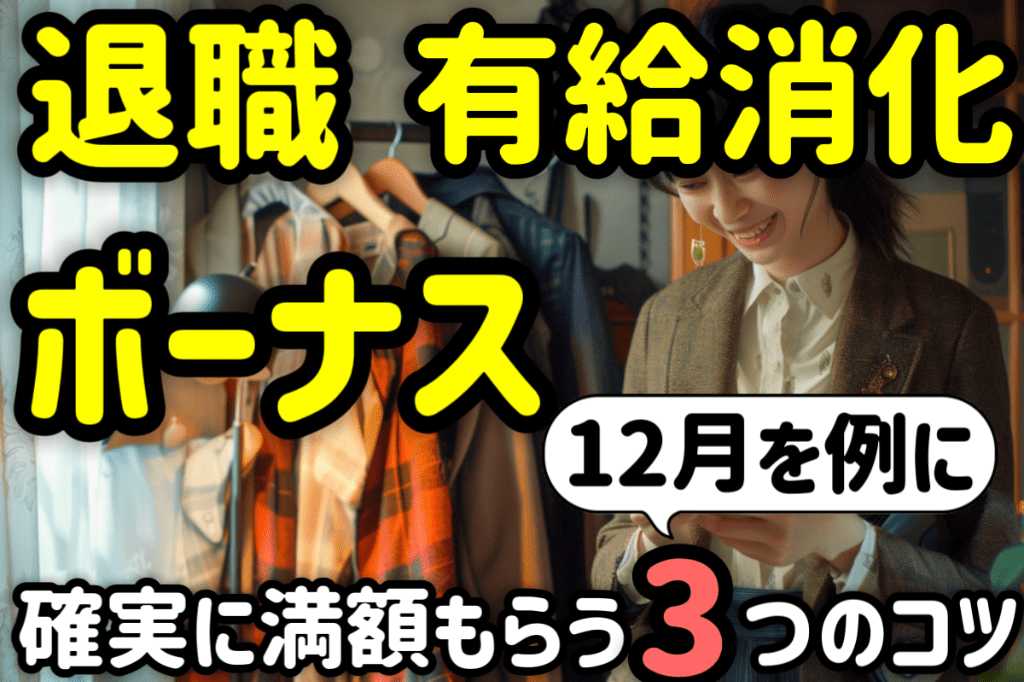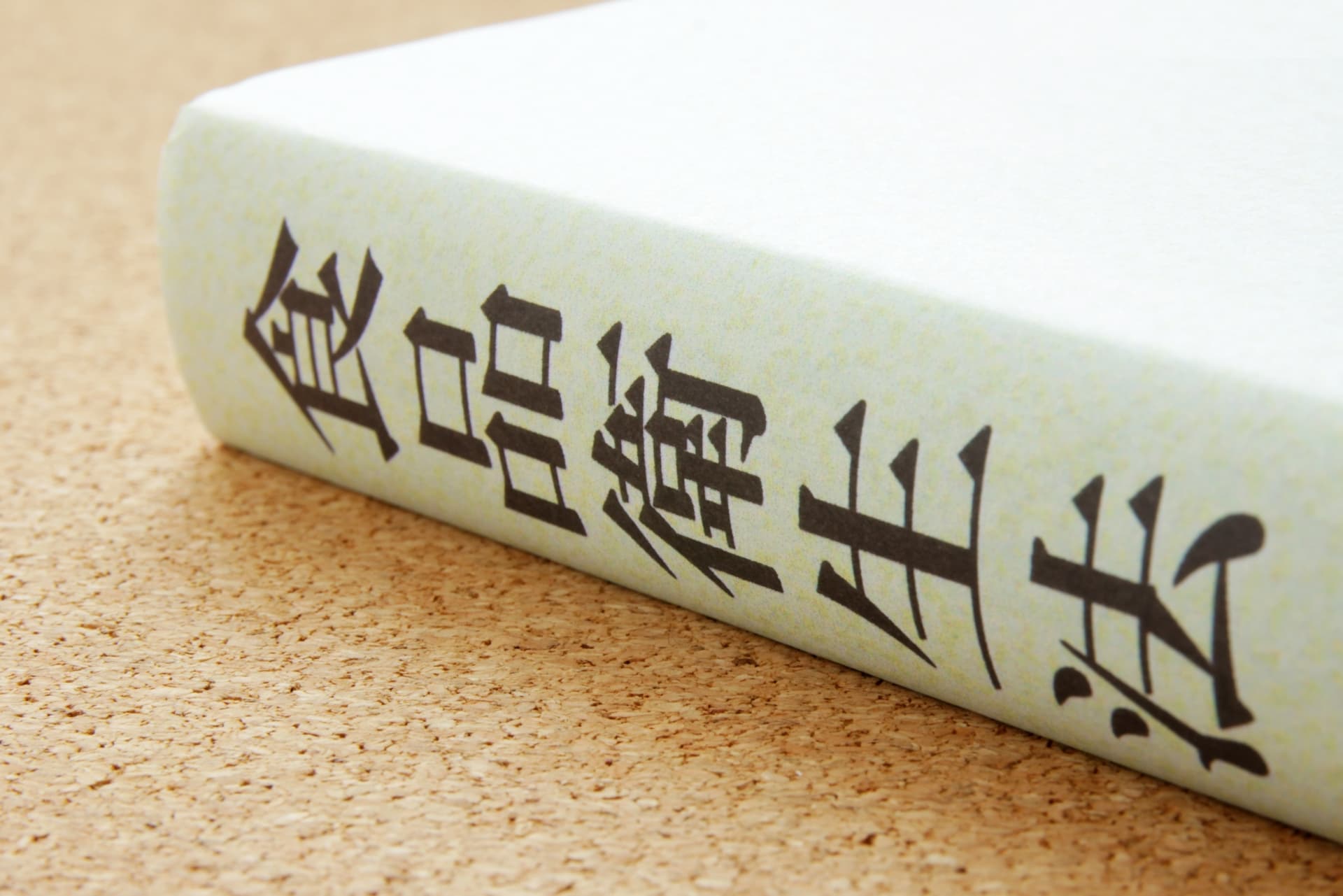資金決済法改正の3つのポイントを弁護士がわかりやすく解説!

はじめに
2021年5月1日より改正資金決済法が施行されました。
政府は、2025年までに40%のキャッシュレス化実現を目指しているため、決済に関する法令の改正が順次行われています。
関係する事業者は、法改正の動向を注視するとともに、その内容を十分に理解しておくことが必要です。
今回は、2021年5月施行の改正資金決済法について、そのポイントを弁護士がわかりやすく解説します。
この記事を執筆したのは

- 弁護士・中小企業診断士 勝部 泰之
- 注力:知的財産権・著作権/ライセンス、ブロックチェーン、データ・AI法務
GWU Law LL.M.(知的財産法)
事業の成長とリスクを両立する実務寄りの助言に注力しています。 - 詳しいプロフィールはこちら
1 資金決済法改正のポイント
今回の改正ポイントを以下の3つに分けてそれぞれ解説します。
- 前払式支払手段
- 資金移動業
- 収納代行等
2 前払式支払手段
本改正において、前払式支払手段との関係で重要となるのは以下の規定です。
-
- 改正資金決済法13条(利用者の保護等に関する措置)
- 前払式支払手段発行者は、第一項に規定するもののほか、内閣府令で定めるところにより、前払式支払手段の利用者の保護を図り、及び前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な措置を講じなければならない
このように、事業者は前払式支払手段の利用者保護を図るために、必要な措置を講じることが必要になります。
これまでも、事業者には自社の名称や前払式支払手段の支払可能金額など、一定事項を利用者に提供しなければならないとする情報提供義務が課されていました。
今後は、これに加えて、以下の事項につき適切な措置を講じることが義務付けられます。
- 未使用残高の移転
- 損失の補償
未使用残高(チャージ残高)を他人に譲渡することにより、前払式支払手段の移転が可能なものに対して、譲渡可能な1回もしくは1日あたりの未使用残高の上限を合理的な金額に設定することが必要になります。
また、繰り返し一定以上の金額につき譲渡を受けている者の特定など、不自然な取引を検知する体制を整備するとともに、不自然な取引を行っている者に対しては、利用停止等の対応に加え、原因となっている取引の内容などを確認することが求められます。
さらに、必要がある場合には、前払式支払手段の利用者以外の者に損失が発生した場合の損失補償その他の対応などの方針についてその者に周知するための適切な措置を講じなければなりません。
3 資金移動業
従来、資金移動業に類型は設けられていませんでしたが、本改正により、取り扱うことのできる送金額に応じて、以下の3類型に区分されました。
- 第一種資金移動業
- 第二種資金移動業
- 第三種資金移動業
(1)第一種資金移動業
第一種資金移動業は、送金額につき上限なく為替取引を行うことが可能な類型です。
第一種資金移動業を行うためには、資金移動業の登録が必要になることはもちろんのこと、業務実施計画を定めたうえで、内閣総理大臣の認可を受ける必要があります。
ここでいう「業務実施計画」には、以下のような事項を定めておくことが求められます。
- 設定するときは為替取引の上限額
- 取引に使用するシステムの管理方法
- 滞留規制を遵守するための体制等
第一種資金移動業の場合、利用者による具体的な送金指図を伴わない資金の受入れは禁止されています。
また、利用者の資金につき、運用・技術上必要とされる期間を超えて滞留することも禁止されています。
(2)第二種資金移動業
第二種資金移動業は、従来の資金移動業に対応する類型であり、為替取引として取り扱うことのできる送金額に100万円以下という上限が設けられている類型です。
第二種資金移動業の場合、利用者1人あたりの受入額が100万円を超えている場合に、利用者の資金と為替取引の関連性を確認するための体制を整備しておかなければなりません。
(3)第三種資金移動業
第三種資金移動業は、為替取引として取り扱うことのできる送金額に5万円以下という上限が設けられている類型です。
第三種資金移動業の場合、利用者1人あたりの受入額が5万円を超えてはなりません。
そのため、1件あたりの送金額だけでなく利用者1人あたりの受入額についても、5万円を超えることのないように体制等を整備しておくことが求められます。
4 収納代行等
いわゆる割り勘アプリのように収納代行と謳いながらも、実質において為替取引であるものについては、資金移動業の規制対象となることが明文化されました。
-
- 改正資金決済法2条の2
- 金銭債権を有する者(以下この条において「受取人」という。)からの委託、受取人からの金銭債権の譲受けその他これらに類する方法により、当該金銭債権に係る債務者又は当該債務者からの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)その他これに類する方法により支払を行う者から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、当該受取人に当該資金を移動させる行為(当該資金を当該受取人に交付することにより移動させる行為を除く。)であって、受取人が個人(事業として又は事業のために受取人となる場合におけるものを除く。)であることその他の内閣府令で定める要件を満たすものは、為替取引に該当するものとする
ここでいう「要件」とは、具体的には以下の①+②もしくは①+③を指します。
-
- 受取人が個人であること
+
-
- 事業者が弁済として資金を受け入れた時までに債務者の債務が消滅しないこと
or
- 受取人が有する金銭債権が、割り勘アプリのように連帯債務者の一人としてする弁済などによってする当該金銭債権に係る信用の供与をしたことによって発生した場合に、当該金銭債権の回収を目的として資金を移動させること
「①+②」もしくは「①+③」に該当する場合、原則として「為替取引」にあたり、資金移動業の規制対象となります。
なお、コンビニの収納代行のように、債権者が事業者であり、かつ、債務者において二重払いの危険がないもの、また、エスクローサービスについては、引き続き、規制は課さないとしています。
5 まとめ
今回の改正により、体制の見直し・整備等が必要になる事業者もいらっしゃると思います。
一方で、高額送金が可能となった資金移動業について、新たにビジネスを立ち上げようと検討している事業者もいらっしゃるのではないでしょうか。
いずれにしても、今回の改正点をきちんと理解することはもちろんのこと、今後の動向にも注意しておく必要があります。
弊所は、ビジネスモデルのブラッシュアップから法規制に関するリーガルチェック、利用規約等の作成等にも対応しております。
弊所サービスの詳細や見積もり等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。