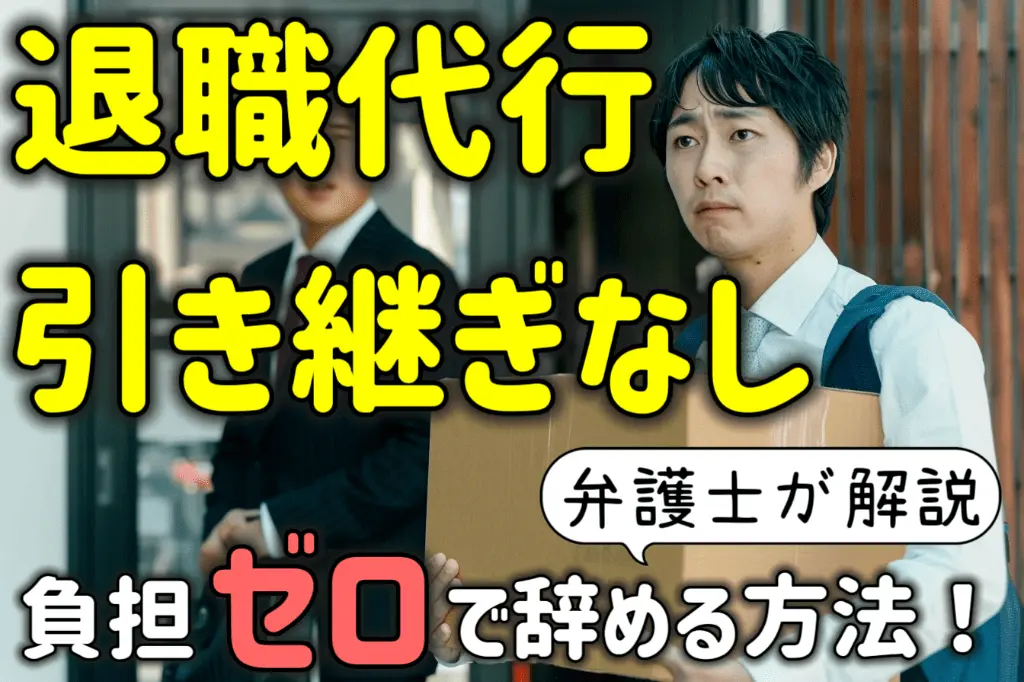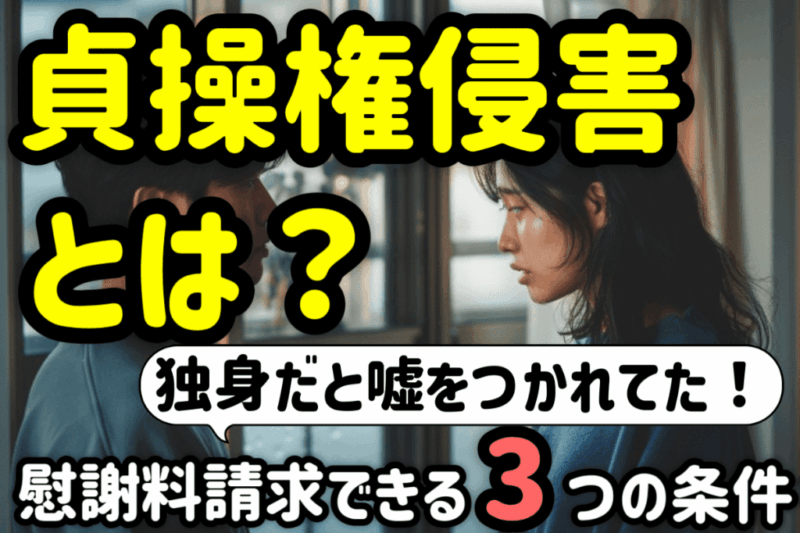特許権に期限はある?延長の可否や権利が消滅する2つのケースを解説

はじめに
特許権は「発明」を保護するための権利です。
発明に至るまでには、多くの時間と労力を要することが一般的であるため、他社が模倣しないようにしっかりと保護することが必要です。
ところで、特許権には有効期限があることをご存知でしょうか。
いったん特許権を取得すれば、その状態が半永久的に続くと思っていた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、特許権の具体的な有効期限と期限を延長する方法について、弁護士がわかりやすく解説します。
1 特許期限とその計算方法
特許法は、特許権の存続期間について、以下のように定めています。
-
【特許法67条1項】
特許権の存続期間は、特許出願の日から二十年をもつて終了する
このように、特許権の存続期間は、特許を出願した日から20年間です。
ここでいう「特許を出願した日」とは、特許登録を受けた日とは異なるため、注意が必要です。
特許を取得するためには、そのための出願書類を特許庁に提出して、審査を受けなければなりません。
特許庁による審査を通過して、特許料(登録料)を納付してはじめて特許権が発生するのです。
話を本題に戻しますが、特許権の存続期間は実際に特許権が発生した日ではなく、特許を出願した日から起算されるということを覚えておきましょう。
そして、特許権者は、特許権が有効に存続している期間は、特許権を侵害する行為について差し止めを請求したり、損害賠償を請求したりすることができるのです。
2 特許期限は延長できる?
特許権は、原則として出願後20年が経過すると消滅しますが、例外的に特許権の存続期間を延長できる場合があります。
この点、特許法は、存続期間の延長について、以下のように定めています。
-
【特許法67条2項】
存続期間は、特許権の設定の登録が特許出願の日から起算して五年を経過した日又は出願審査の請求があつた日から起算して三年を経過した日のいずれか遅い日以後にされたときは、延長登録の出願により延長することができる
【特許法67条4項】
存続期間は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間があつたときは、五年を限度として、延長登録の出願により延長することができる
簡単に言い換えると、以下の場合には、存続期間を延長できるということになります。
- 審査遅延による延長
- 政令の処分を受けるために必要な延長
(1)審査遅延による延長
特許権の存続期間は、出願した日から起算されるため、審査などに時間がかかってしまうと、それだけ存続期間も短くなります。
もっとも、審査や登録に至るまでの遅延が、特許庁の不合理な審査に起因する場合にまで、その結果を特許権者に負わせてしまうのは酷です。
そこで、「特許を出願した日から5年を経過した日」または「出願審査請求から3年を経過した日」のいずれか遅い日以後に特許権の登録がされた場合は、特許庁の不合理な審査により遅延した期間を上限として、特許権の存続期間を延長することが認められています。
(2)政令の処分を受けるために必要な延長
医薬や農薬などの発明については、特許を受けたとしても、監督官庁による許可などを受けないことには、それらを販売したり製造したりすることができません。
そのため、特許権者は特許権を取得したとしても、監督官庁などによる許可を受けるまでは、特許権を十分に行使することができないのです。
そこで、政令の処分を受ける必要があったために特許発明を実施することができなかった期間を回復するために、存続期間満了後5年を上限に存続期間を延長することが認められています。
3 特許権が消滅する2つのケース
特許権が発生していても、その権利が消滅することがあります。
具体的には、以下の2つのケースです。
(1)特許の期限切れ
「特許の期限切れ」とは、特許権の存続期間が満了することを意味します。
既に見たように、特許権の存続期間は特許を出願した日から20年です。
そのため、出願日から20年が経過すると、原則として特許権は消滅し、それ以降は誰でも自由に実施することができるようになります。
(2)存続期間中の権利消滅
存続期間中であっても、特許権が消滅するケースがあります。
具体的には、以下の3つのケースです。
- 登録料(更新料)の未納
- 特許権が取り消された場合
- 特許権を放棄した場合
①登録料の未納
特許権を取得した者は、その後も特許権を維持するために毎年登録料を支払わなければなりません。
登録後3年分については初回にまとめて支払う必要がありますが、4年目以降は毎年登録料を支払うことが必要になります。
仮に、登録料を支払わなかった場合、6ヶ月間にかぎり追納することが可能ですが、追納期間に登録料を支払わなかった場合、たとえそれが存続期間中であっても特許権は消滅します。
②特許権が取り消された場合
特許の無効審査請求を申し立てられ、その結果権利無効の審判が出てしまうと、いったん登録された特許権は取り消されます。
ここでいう「無効審査請求」とは、特許侵害などを理由として、他者に係る特許権を取り消してもらうための制度です。
無効審査請求を受理した特許庁は、問題となっている特許について審理を行った結果、無効事由が認められる場合は、特許権が無効である旨の審決を下します。
審決があった日から30日以内であれば、裁判所に対して審決の取消訴訟を提起することができますが、この期限内に取消訴訟を提起しなかった場合や取消訴訟において請求が認められなかった場合は、特許権の無効が確定することになります。
③特許権を放棄した場合
特許権は、放棄することが可能な権利です。
たとえば、利用することがなくなった特許権について、コスト負担(登録料の負担)をなくすために、特許権を放棄することができます。
特許権を放棄する際には、所定の手続きを踏む必要がありますが、提出書類等に問題なければ、特許権は消滅します。
4 まとめ
特許権は、権利を取得した後も、更新の手続きや存続期間の管理などが必要になります。
思いがけない形で特許権を消滅させてしまっては、事業者にとって多大な痛手となります。
自社の発明を保護するためにも、適切に管理することが大切です。
弊所は、ビジネスモデルのブラッシュアップから法規制に関するリーガルチェック、利用規約等の作成等にも対応しております。
弊所サービスの詳細や見積もり等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。