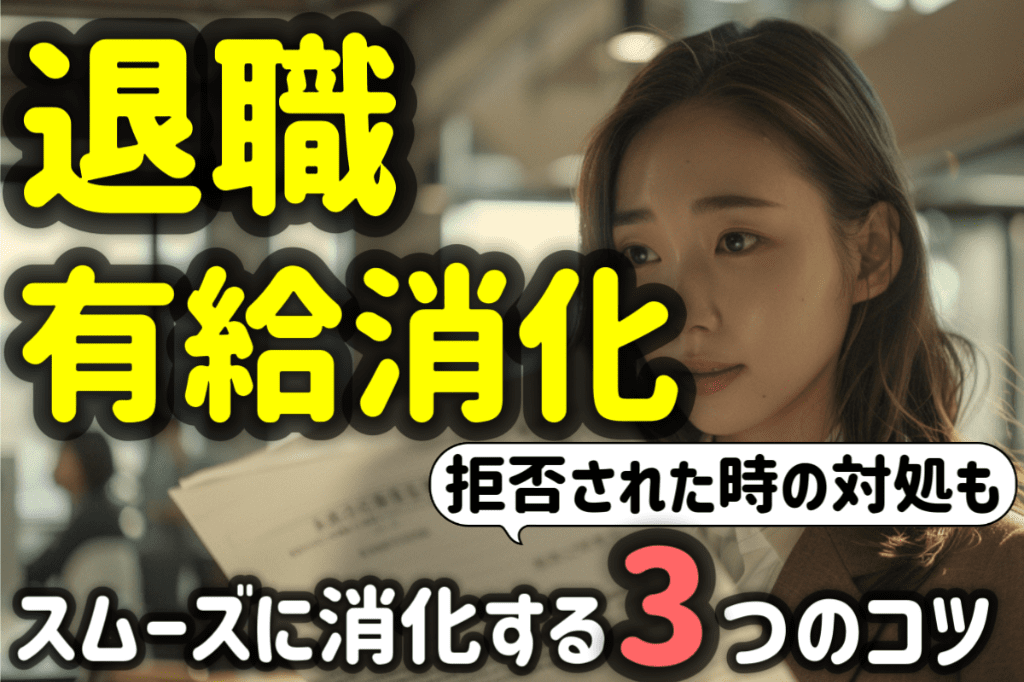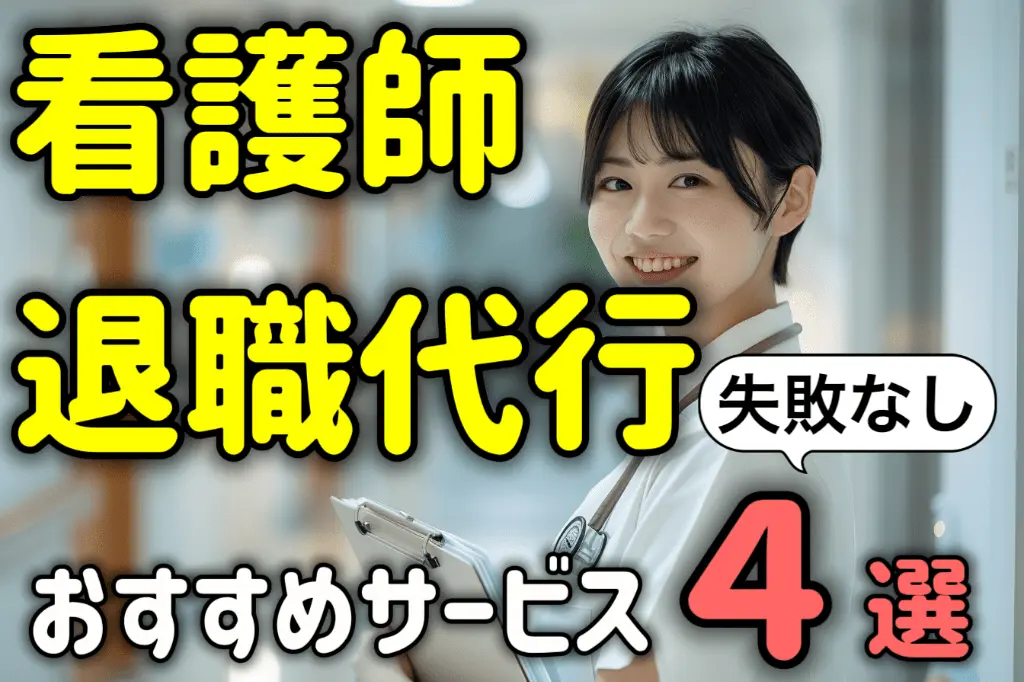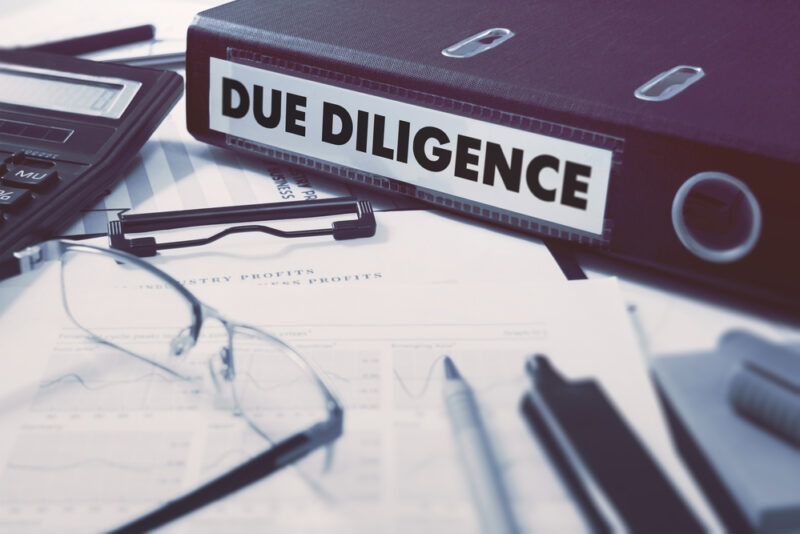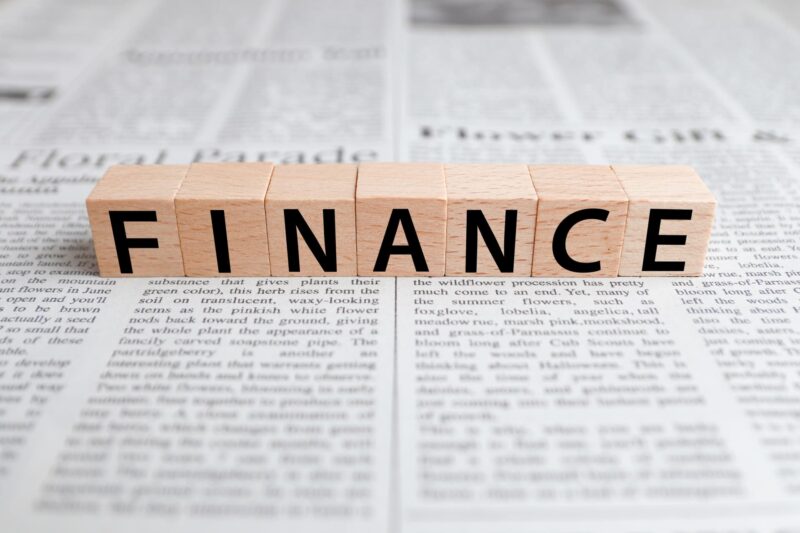種類株式とは?9つの種類とメリット・デメリットを弁護士が解説!

はじめに
株式会社において、資金調達をする場合や経営権を行使する場合などには「株式」は必要不可欠なものです。
「株式」と聞くと、普通株式をイメージする方が多いと思いますが、普通株式のほかに「種類株式」があるのをご存知でしょうか。
近年では、スタートアップ企業などにおいても、資金調達をする際に種類株式を利用するケースが多く見受けられます。
そもそも、種類株式とはどのような内容の株式なのでしょうか。
種類株式を発行する際には、株式の内容はもちろんのこと、独自のメリット・デメリットを理解しておくことも必要です。
そこで今回は、種類株式とはどのような株式なのかを中心に、弁護士がわかりやすく解説します。
1 種類株式とは
「種類株式」とは、権利の内容が異なる2種類以上の株式を発行する場合の各株式のことをいいます。
株式を手に入れたいと考えている人のニーズは一律ではありません。
たとえば、発行会社の経営に関心がある人は議決権を重視しますが、経営に関心がない人は配当や優待券を重視します。
種類株式を発行することにより、このような買い手のニーズに応えることが可能になるため、多くの株式を発行して資金調達がしやすくなるわけです。
また、一般的に、会社側は自社の経営に口出しをされたくないと考えるため、種類株式を発行することにより会社側のニーズを満たすことも可能になります。
種類株式は、権利の内容に応じて、以下の9つの種類に分類されています。
- 剰余金の配当
- 残余財産の分配
- 議決権の制限
- 譲渡の制限
- 取得請求権
- 取得条項
- 全部取得条項
- 拒否権
- 役員選任権
株式会社がこれらの種類株式を発行しようとする場合には、種類株式の権利内容、種類株式の発行数などを定款で定める必要があります。
※種類株式の具体的権利内容、定款への記載方法について詳しく知りたい方は、「9つの種類株式すべてを網羅!定款への記載例を弁護士がくわしく解説」をご覧ください。
2 種類株式を発行するメリットとデメリット
(1)種類株式を発行するメリット
種類株式を発行するメリットは、主に以下の2点です。
①資金調達をしやすくなる
投資家にとって、種類株式はさまざまなメリットを受けることのできる株式です。
そのため、事業者は種類株式を利用することにより資金調達がしやすくなります。
たとえば、優先株式には、普通株主に優先して剰余金や残余財産の配当を受けることができるという大きなメリットがあります。
また、取得請求権付株式では、その株式を取得するようにいつでも会社に請求することができるため、投資家はリスクを抑えることができるというメリットがあります。
これらのメリットは投資家にとって魅力的でもあるため、種類株式の人気は高く、事業者にとって資金調達を容易にしてくれるというメリットがあります。
②会社経営の介入を防止できる
種類株式のなかでも、たとえば、議決権制限株式を保有する株主は、株主総会で議決権を行使することができないのが原則です。
また、そのほかにも、譲渡制限付株式や取得条項付株式、全部取得条項付株式を発行することにより、会社にとって好ましくない者が株主となって会社経営に介入することを防ぐことができます。
このように、種類株式の権利内容によっては、会社経営への介入を防止できるというメリットもあります。
(2)種類株式を発行するデメリット
種類株式は、事業者にとってはメリットが多く、特に注意しなければならないデメリットは存在しません。
とはいえ、たとえば、優先株式を利用した資金調達手法は、日本においてまだまだ浸透していないのが実情です。
優先株式を保有する株主には、配当について優先権を確保できるというメリットがありますが、これはあくまで株主となる投資家が剰余金や残余財産の配当で利益を上げたいと考えている場合にしかあてはまりません。
そのため、株式の売買で利益を上げたいと考えている投資家には向いていないということになります。
このように、種類株式の特徴が要因となって、種類株式に出資しようとしない投資家がいることも事実です。
3 種類株式の発行手続き
種類株式を発行する場合には、種類株式の権利内容やその発行可能総数を定款で定める必要があります。
これらのことを定款で定めるためには、株主総会の特別決議によって定款変更の決議を経る必要があります。
「特別決議」とは、株主総会において議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行われる決議のことをいい、普通決議よりも厳しい決議要件となっています。
種類株式を発行する時点で、すでに他の種類株式を発行している場合には、発行している種類株式の株主で構成される種類株主総会の決議も必要となるため(当該種類株主総会で議決権を行使できる種類株主がいない場合は不要)、注意が必要です。
また、定款変更の手続きは、種類株式の内容ごとに行う必要があります。
たとえば、全部取得条項付株式を発行する場合には株主総会の特別決議で足りますが、議決権制限株式を発行する場合には株主総会の特殊決議が必要となり、さらに決議要件が厳しくなることにも注意しておく必要があります。
このように、種類株式の内容に応じて必要となる手続きが異なるため、あらかじめ確認しておくようにしましょう。
4 まとめ
スタートアップ企業などでは、種類株式を利用して資金調達をするケースが増えています。
種類株式を発行して資金調達を行う場合には、その前提として、9つに分類された権利内容をきちんと理解し、資金調達方法として適しているかどうかをしっかりと検討することが大切です。
弊所は、ビジネスモデルのブラッシュアップから法規制に関するリーガルチェック、利用規約等の作成等にも対応しております。
弊所サービスの詳細や見積もり等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。