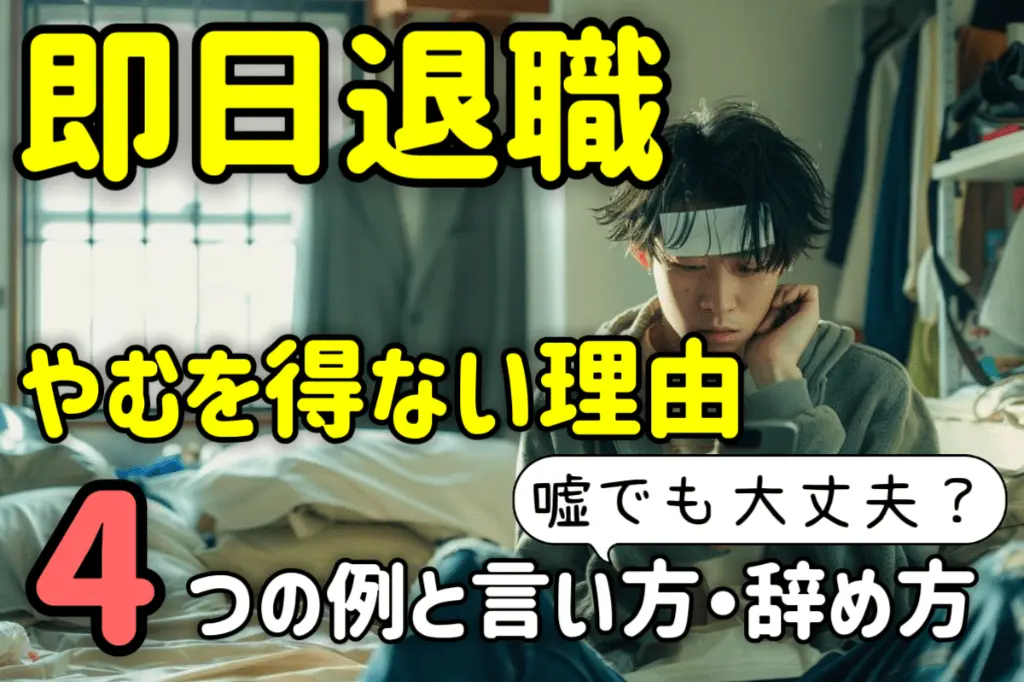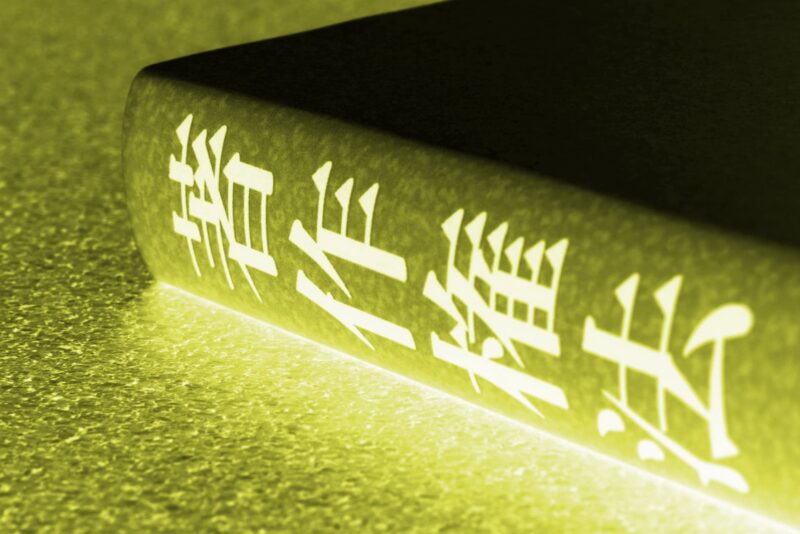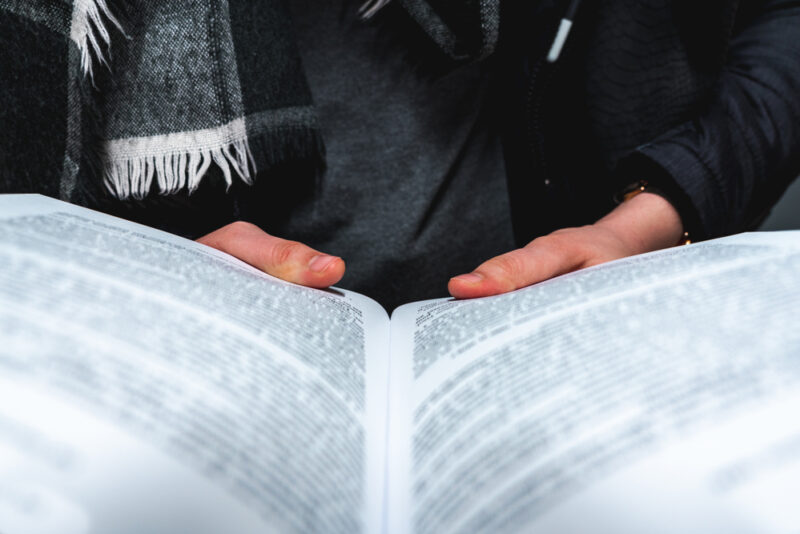著作権法改正(2021年1月施行)の4つのポイントを弁護士が解説

はじめに
書籍や漫画などに見られる海賊版の対策を強化する改正著作権法が2021年1月1日から施行されました。
これまでは、映像と音楽のみが違法ダウンロードの規制対象でしたが、今後はその対象が書籍や漫画、ソフトウェアのプログラムなどにも拡大することになります。
このほかにも、著作物の円滑な利用、著作権の適切な保護を図るために、一定の改正がなされました。
今回は、2021年1月施行の改正著作権法について、そのポイントをわかりやすく解説します。
この記事を執筆したのは

- 弁護士・中小企業診断士 勝部 泰之
- 注力:知的財産権・著作権/ライセンス、ブロックチェーン、データ・AI法務
GWU Law LL.M.(知的財産法)
事業の成長とリスクを両立する実務寄りの助言に注力しています。 - 詳しいプロフィールはこちら
1 著作権法改正のポイント
本改正のポイントは、以下の4点です。
- リーチサイト対策
- 侵害コンテンツのダウンロード違法化
- 著作権侵害訴訟における証拠収集手続の強化
- アクセスコントロールに関する保護の強化
2 リーチサイト対策
「リーチサイト」とは、他のウェブサイトで違法にアップロードされた著作物など(侵害コンテンツ)のリンク情報等を提供するウェブサイトのことをいいます。
リーチサイトの対象となるのは、以下の2つです。
- 公衆を侵害著作物等に殊更に誘導するものであると認められるウェブサイト
- 公衆による侵害著作物等の利用のために用いられるウェブサイト
このように、リーチサイトは一定の条件を満たすウェブサイトのことを意味します。
ここでいう「ウェブサイト」とは、ドメイン名が共通するウェブページの集合物であって、ウェブサイトの一部を構成する複数のウェブページであり、公衆への提示が一体的に行われているものを含むとされています。
今回の改正により、今後、リーチサイトを運営する行為は刑事罰の対象となります。
また、リーチサイトにおいて侵害コンテンツへのリンクを掲載すると、著作権侵害行為とみなされ、行為者は民事上・刑事上の責任を負う可能性があります。
民事上の責任としては、
- 差止請求
- 損害賠償請求
を受ける可能性があり、刑事上の責任としては、
- 最大3年の懲役
- 最大300万円の罰金
のいずれか、または両方を科される可能性があります。
なお、リンクの提供行為およびリーチサイトの運営行為は、いずれも親告罪となっているため、著作権者による告訴がなければ、行為者が刑事上の責任を負うことはありません。
3 侵害コンテンツのダウンロード違法化
これまでも、映像や音楽の違法ダウンロードは、著作権法上違法とされていましたが、それ以外のダウンロードは、特に規制されていませんでした。
今回の改正により、映像や音楽に加え、書籍や漫画、ソフトウェアのプログラムなど著作物全般についての違法ダウンロードが規制対象に加えられました。
具体的には、違法にアップロードされたことを認識しながらダウンロードした場合、たとえそれが私的使用のためであっても、原則として著作権侵害とみなされます。
その結果、民事上の責任(差止請求や損害賠償請求)を負う可能性があります。
なお、この場合、違法にアップロートされたことを知っている必要があり、重大な過失により知らなかった場合は、著作権侵害とみなされません。
また、侵害コンテンツのダウンロードを継続的に又は反復して行った場合、
- 最大2年の懲役
- 最大200万円の罰金
のいずれか、または両方を科される可能性があります。
なお、侵害コンテンツのダウンロードは親告罪となっているため、著作権者による告訴がなければ、行為者が刑事上の責任を負うことはありません。
4 著作権侵害訴訟における証拠収集手続の強化
著作権侵害訴訟では、裁判所が、当事者の申立てに基づき、侵害行為の立証や侵害行為による損害額の算出に必要な書類の提出を命じることができるようになっています。
もっとも、書類を所持する当事者において、その提出を拒否する正当な理由がある場合、裁判所は提出を命ずることはできません。
これまでは、ここにいう「正当な理由」の有無を判断するために、裁判所は書類の所持者に対して、書類の提示を求めることができました。
ですが、侵害行為の立証や侵害行為による損害額の算出に必要かどうかを判断するために、書類の所持者に書類の提示を求めることはできませんでした。
今回の改正により、これらを判断するためであっても、つまり、書類の提出命令の要否を判断するために必要な場合には、書類の所持者に書類の提示を求めることができるようになりました。
また、当事者の同意を条件として、専門委員(専門的知見を有する者:専門家や大学教授など)に対し、提示を受けた書類を開示できるようになりました。
5 アクセスコントロールに関する保護の強化
著作物の不正使用を防止するための保護技術(アクセスコントロール技術)のうち、シリアルコードを使ったライセンス認証などの最新技術が保護対象に含まれることが明確化されました。
また、ライセンス認証を回避する機能をもつ不正なシリアルコードを提供する行為を著作権侵害行為とみなし、民事上・刑事上の責任を問いうるようになりました。
民事上の責任としては、
- 差止請求
- 損害賠償請求
を受ける可能性があり、刑事上の責任としては、
- 最大3年の懲役
- 最大300万円の罰金
のいずれか、または両方を科される可能性があります。
なお、不正なシリアルコードの提供行為は親告罪となっているため、著作権者による告訴がなければ、行為者が刑事上の責任を負うことはありません。
6 まとめ
今回の改正は、インターネット上の海賊版対策を強化することに重点を置いた改正だといえます。
このほかにも、今回の改正により、著作権者から許諾を受けて著作物を利用することのできる権利を著作権の譲受人や第三者に対抗できるとする対抗制度が導入され、また、プログラムの著作物に係る登録制度も整備されています。
著作権侵害に対しては、極めて重い罰則が設けられているため、著作権に関わり合いをもつ事業者は、今回の改正もきちんと把握しておくことが大切です。
弊所は、ビジネスモデルのブラッシュアップから法規制に関するリーガルチェック、利用規約等の作成等にも対応しております。
弊所サービスの詳細や見積もり等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。