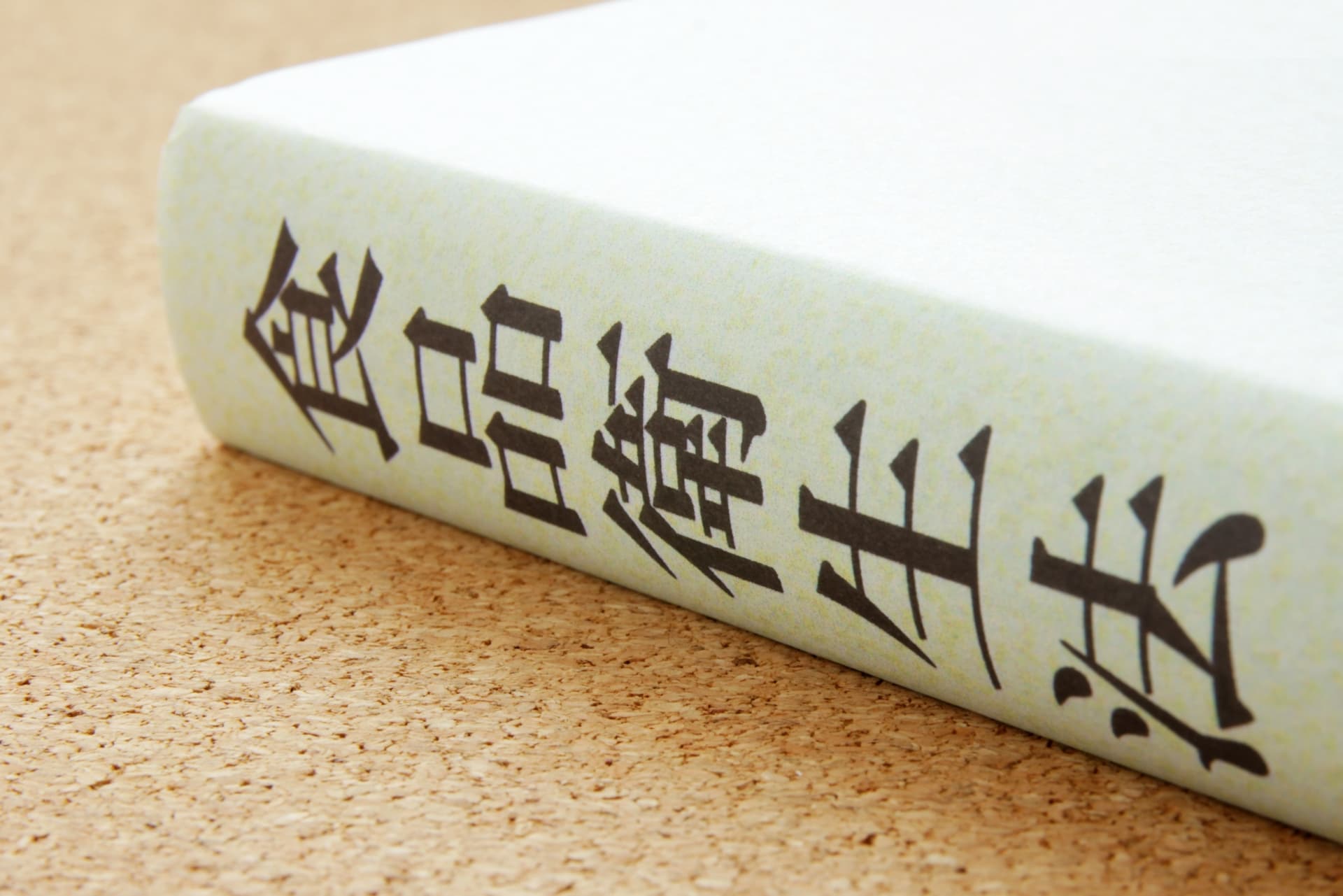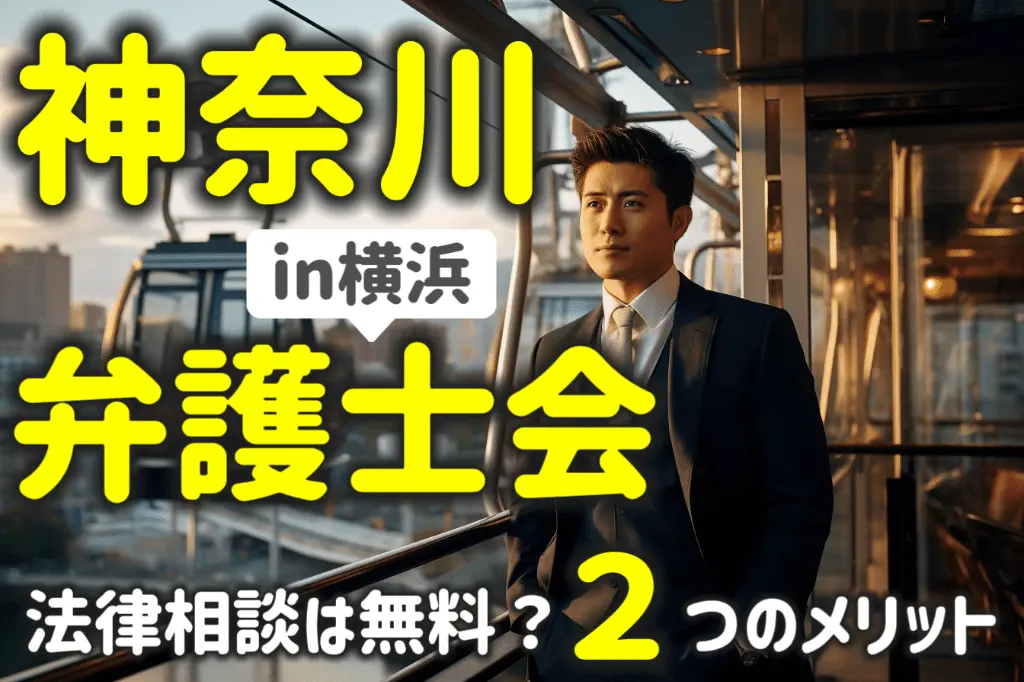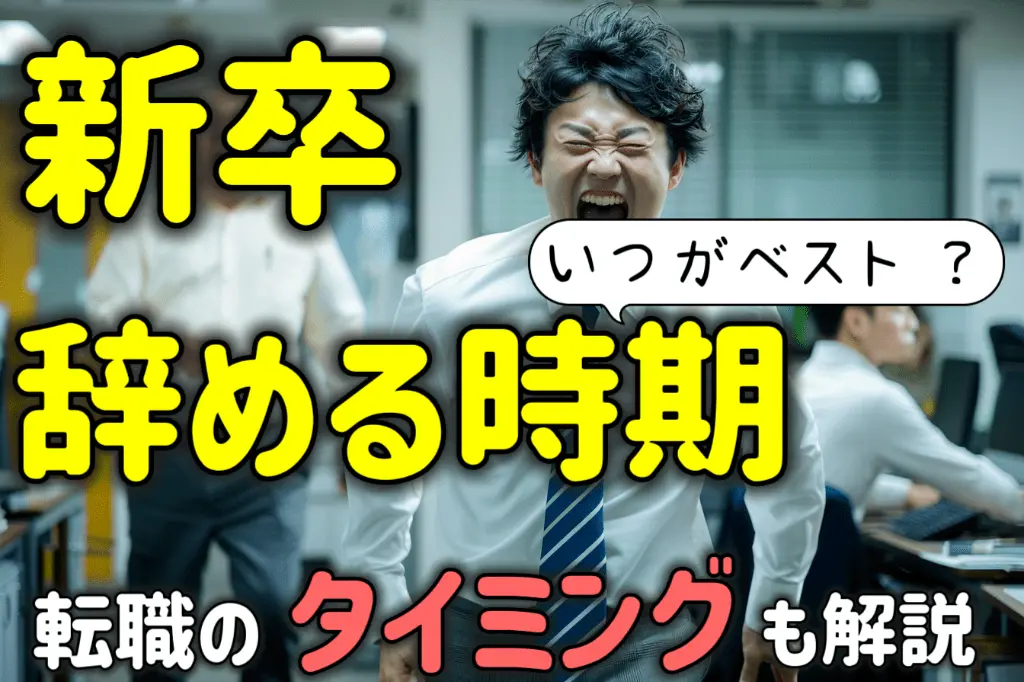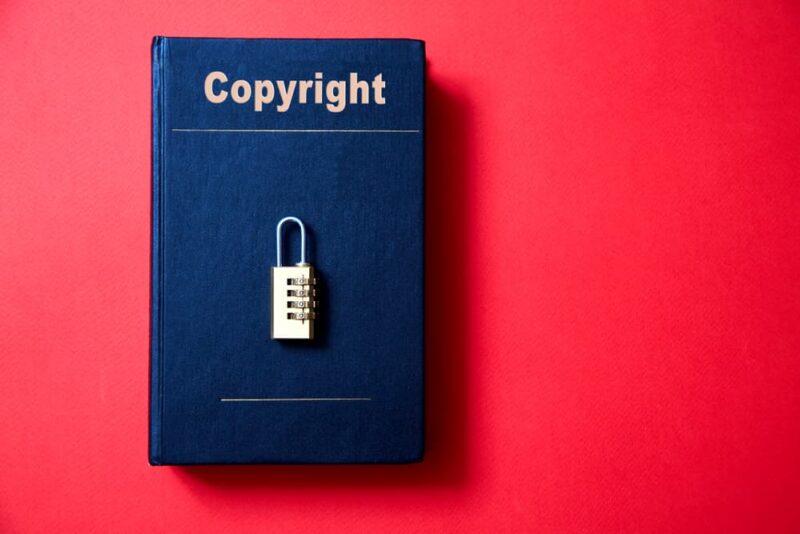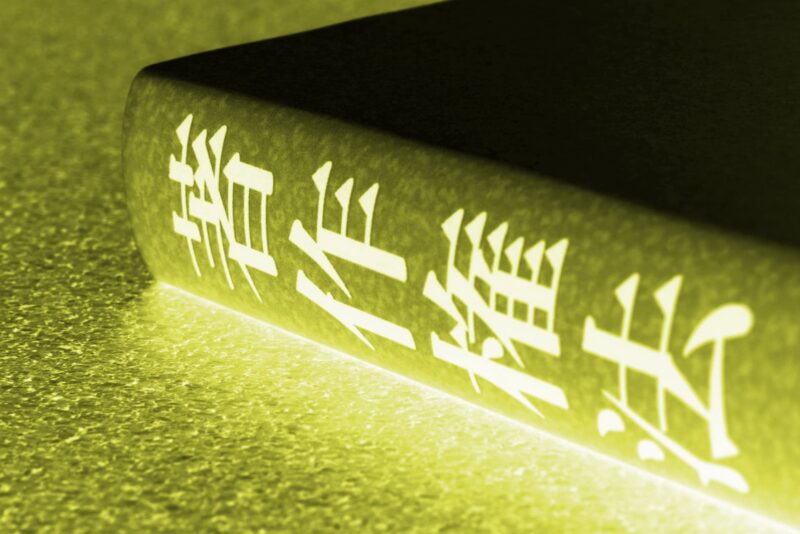従業員が生み出したものは会社のもの?職務著作の4つの要件を解説!

はじめに
従業員が業務を通して、マニュアルやプログラム、データベース、アプリなどを作成することはよくある話で、生み出されたものには「著作権」が認められることがあります。
では、これらのマニュアルやプログラム、データベース、アプリに関して権利をもつ「著作者」は誰になるのでしょうか。
作成者である従業員が権利を持つのか、その作成業務をさせていた会社が権利を持つのか、よくわかりませんよね。
原則的には、従業員が著作者になるのですが、法律上、一定の条件をみたした場合、会社が著作者となる「職務著作(法人著作)」という制度があります。
そこで今回は、職務著作とは何か、その条件、職務著作の条件を満たさない場合に会社が権利を得る方法などについて弁護士がわかりやすく解説していきます。
この記事を執筆したのは

- 弁護士・中小企業診断士 勝部 泰之
- 注力:知的財産権・著作権/ライセンス、ブロックチェーン、データ・AI法務
GWU Law LL.M.(知的財産法)
事業の成長とリスクを両立する実務寄りの助言に注力しています。 - 詳しいプロフィールはこちら
1 著作権とは
(1)著作権とは
「著作権」とは、作成した小説や絵画などの著作物を独占的に利用できる権利のことをいいます。著作権は、著作者が著作物を生み出した時点で自動的に発生するため、著作権を得るために国に対する「申請」・「登録」など特別な手続をする必要はありません。
(2)著作物とは
「著作物」とは、次の4つの要件をみたすもののことをいいます。
- 思想または感情であること
- 表現されていること
- 創作性があること
- 文芸、学術、美術、音楽の範囲に属していること
この条件では、何を生み出せば「著作物」となるかわかりづらいですよね。
たとえば、「著作物」になり得るものは以下のようなものです。
- 論文、レポート、小説などの言語
- 楽曲や歌詞などの音楽
- ダンス、パントマイムなどの振り付け
- マンガ、絵画、彫刻などの美術
- 寺、橋、庭園などの建築物
- 地図、図表、設計図などの図形
- 映画、CM、ドラマ、テレビゲームの映像
- 肖像写真や風景写真などの写真
- プログラム
一方、4つの条件を1つでもみたさない場合、「著作物」にはあたりません。
たとえば、「京都には金閣寺がある」といった単なる事実やデータは①の要件をみたさず、頭の中にアイデアがあっても表現されていない段階では②の要件をみたしません。
また、個性が現れておらず誰が表現しても同じものは③の要件をみたさず、工業製品は④の要件を満たしません。
冒頭で例としてあげたマニュアルは、それを構成する文章や図に作成者の個性が表現されていれば、その文章や図が著作物となります。アプリも、それを構成するプログラム、画像、動画、音楽それぞれが著作物となる可能性があります。
(3)著作権者にできること
著作物を作成した著作者には、著作権として「著作者人格権」と「著作権(財産権)」という権利が与えられます。。著作者人格権については後ほど説明することにしてここでは、「著作権(財産権)」について解説していきます。
「著作権(財産権)」とは、著作物の財産的な利益を保護する権利のことをいいます。具体的には、著作権(財産権)をもつ者には、以下を行う権利が与えられます。
- 複製権:印刷や録画、コピーする権利
- 上演権・演奏権:演劇を上演したり、楽曲を演奏したりする権利
- 上映権:映画やアニメなどを上映する権利
- 公衆送信権・公の伝達権:テレビやラジオなどを通して公に伝える権利
- 口述権:朗読など口頭で公に伝える権利
- 展示権:美術品や写真などを公に展示する権利
- 頒布権:映画やアニメなどを譲渡したり、貸与したりする権利
- 譲渡権:⑦以外の著作物を不特定多数の人に譲渡する権利
- 貸与権:⑦以外の著作物を不特定多数の人に貸与する権利
- 二次的著作物の創作権:小説を翻訳、映画化、ドラマ化したり、楽曲を編曲したりする権利
- 二次的著作物の利用権:著作物(原作)から生み出された二次的著作物を利用することに関する原作者の権利(原作者からの許諾も必要とする権利)
これらの著作権(財産権)はその全部を譲渡することもできますし、「○○権」を譲渡するといった形で一部に限って譲渡することもできます。
著作権(財産権)を譲り受けた人は著作物を生み出していないため著作者ではありませんが、著作権はあるため「著作権者」と呼ばれます。著作者も、著作権を譲渡していないかぎりは著作権を持っているため、著作権者にあたります。
これまで確認してきたとおり、著作権は、著作物を生み出した作成者に与えられることが原則です。もっとも、従業員が作成した著作物については、例外的に会社が著作者となる「職務著作(法人著作)」という制度があります。
2 職務著作とは
「職務著作(法人著作)」とは、一定の条件のもと、会社が著作者になることをいいます。
なぜ例外的に著作物の作成者ではない会社が著作者になることが法律上認められているかというと、原則を貫いて従業員が著作者になると、業務に支障がでてしまうからです。
業務を通して従業員が生み出した著作物を会社がコピー(複製)したり、改変(二次著作物の創作)したりする度に、いちいち作成した従業員に許諾を得なければいけなくなると手間も時間もかかり、業務がスムーズにいかなくなってしまいます。
そのため、一定の条件のもと、会社が著作者になる「職務著作」制度が法律で定められているのです。
次の項目では、職務著作となるための要件について具体的に見ていきましょう。
3 職務著作となる要件
職務著作となるためには、次の4つの要件をみたす必要があります。
- 法人等の発意にもとづくこと
- 法人等の業務に従事する者が職務上作成するものであること
- 法人等の名義の下に公表するものであること
- 作成時における契約、就業規則その他に別段の定めがないこと
ここでいう「法人等」とは、法人その他使用者のことをいいます。また、「法人」には自治体やPTA、○○協会といった法人格を有しない社団または財団も含まれています。この定義を前提として4つの要件について、1つずつ確認していきましょう。
(1)法人等の発意にもとづくこと
「発意にもとづくこと」とは、法人などが企画をたてることをいいます。
たとえば、法人等が従業員に対して業務命令をだしたり、企画立案したりしている場合には、法人等の発意にもとづいていることになります。
(2)法人等の業務に従事する者が職務上作成するものであること
「法人等の業務に従事する者」とは、法人等と雇用関係にある者のことをいいます。
なお、雇用関係になくとも、雇用関係と同じように法人等の指揮命令の下で業務を行っている者も含まれています。
たとえば、派遣を考えてみてください。
派遣元と派遣社員は雇用関係にありますが、派遣先と派遣社員は雇用関係にありません。もっとも、派遣社員は派遣先の会社の指揮命令の下で業務を行うため、「法人等の業務に従事する者」にあたるとされています。
また、「職務上作成する」とは、従業員が法人等の仕事として作成することをいいます。たとえば、従業員の自由な時間に仕事とは関係ない小説を書いたりしたとしても、「職務上作成する」にはあたらないことになります。
(3)法人等の名義の下に公表するものであること
たとえ、従業員が会社の業務命令で仕事として著作物を作成していたとしても、公表する際に、「法人等の名義」としなければ、職務著作とはなりません。従業員の名義で公表した場合には、この要件をみたさず、著作者は従業員となります。
公表する前であっても、法人等の名義の下に公表する予定があればこの要件をみたします。公表しない著作物については、この要件をみたさず職務著作とならないように思えますが、仮に公表するとすれば法人等の名義が含まれる場合にはこの要件をみたすとされているため、公表しない著作物でも職務著作となることはあります。
(4)作成時における契約、就業規則その他に別段の定めがないこと
これまで確認してきた3つの要件をみたす場合であっても、著作物を作成した時点で、
- 職務を通して従業員が作成した著作物に関する権利は作成した当該従業員に帰属する
といったように、会社が「職務著作」制度に基づいて著作者にならないことが雇用契約書などの契約書、就業規則、社内規程などで定められている場合には、その定めが優先することになっていまるため、そのような定めがないことが要件になっています。
以上の4つの要件をすべてみたす場合には、「職務著作」となり、法人等が著作者となります。もっとも、プログラムの著作物については例外的に③の要件をみたさなくても他の要件をみたしていれば職務著作となります。次の項目では、なぜプログラムの著作物のみ③の要件が不要とされているのかを確認していきましょう。
4 プログラムの著作物に関する例外
プログラムの著作物は、職務著作となるための要件が他の著作物とは少し異なります。
具体的にいうと、プログラムの著作物については「法人等の名義の下に公表すること」という要件はありません。そのため、
- 法人等の発意にもとづくこと
- 法人等の業務に従事する者が職務上作成するものであること
- 作成時における契約、就業規則その他に別段の定めがないこと
という3つの要件をみたしていれば職務著作となります。なぜなら、プログラムには他の著作物と異なり、社内でのみ利用するなど、外部に公表しないことが多いという性質があるからです。
なお、アプリのようにプログラムを含めた複数の著作物で構成されているものもあります。それぞれ独立した著作物であり、プログラム以外の画像や音楽といった著作物については、「法人等の名義の下に公表すること」も含めた4つの要件を満たさなければ職務発明にあたらない点にも注意してください。
では、職務著作の要件をみたさない場合には、会社はいちいち従業員などから、著作物の利用に関して許諾を得なければいけないのでしょうか。これでは手間がかかってしょうがないですよね。
次の項目では、職務著作の要件をみたさない場合に、職務著作制度以外の方法で会社が著作権を得て著作権者になる方法を解説していきます。
5 職務著作にあたらなくても会社が著作権を得る方法
職務著作の要件をみたさない場合には、原則どおり、従業員個人が著作者となり、その従業員に著作権が生じます。もっとも、その場合でも会社が著作権を得る方法があります。それは、
- 就業規則に定める方法
- 個別の著作権譲渡契約
を締結する方法の2つです。それぞれについて説明した後、2つの方法を使い分ける判断基準を解説します。
(1)就業規則に定める方法
「就業規則」とは、従業員向けに会社で働くうえでのルールや待遇について定められた書面のことをいいます。
この就業規則に、
・職務を通して従業員が作成した著作物に関する権利(著作権法第27条および第28条の権利を含む)は会社に帰属する
などの規定を置くという方法です。著作物の権利関係について定めておくことで、会社の発意にもとづかなかったり会社の名義の下で公表しなかったりして職務著作にあたらない場合でも、会社が著作権を得ることができます。
(2)個別の著作権譲渡契約を締結する方法
もう1つの方法は、著作権をもっている従業員と会社との間で、著作権譲渡契約を締結するという方法です。
※著作権譲渡契約について詳しく知りたい方は「【雛形付き】著作権譲渡契約書の作成で気を付けたい11のポイント!」ご覧ください。
(3)2つの方法を使い分ける判断基準
以上のとおり、会社が従業員から著作権を得る方法は2つあります。この2つの方法は、場合に応じて使い分けることが重要です。
判断ポイントは
- 雇用関係にあるか否か
- 個別の条件を設定したいかどうか
の2つです。
①雇用関係にあるか否か
就業規則に定める方法によって会社が著作権を得るためには、当然ですがその人に就業規則が適用されることが前提です。就業規則は雇用関係にある従業員に適用されるものであるため、外注先の従業員やフリーランス、派遣社員など雇用関係にない人には適用されません。また、従業員であっても退職後は雇用関係が消滅するため、退職した元従業員にも就業規則の適用はありません。退職後に元従業員が作成した著作物は、就業規則を根拠に会社が著作権を得ることはできないことになります。
一方、個別の著作権譲渡契約であれば、雇用関係にかかわらず誰とでも締結できます。そのため、雇用関係にない人から著作権の譲渡を受けたい場合はこの方法を選択しましょう。
②個別の条件を設定したいかどうか
就業規則は従業員に一律に適用されます。そのため、「この従業員の著作物の譲渡についてはこの条件」で、「別の従業員の著作物の譲渡についてはこの条件」でといった具合に、従業員ごとに個別の条件を設定したい場合に就業規則を用いることは難しいです。
以上から、雇用関係にある場合であっても、個別の条件を設定したい場合には、会社は従業員ごとに著作権譲渡契約を締結するほうがいいでしょう。
このように「職務著作」の要件を満たさない場合にも、会社が従業員などから著作権を得る方法はあります。もっとも、この際に注意しなければいけないのは、著作物を生み出した著作者に与えられる「著作者人格権」という権利です。
6 注意しなければいけない著作者人格権
著作物を生み出した著作者には「著作者人格権」と「著作権(財産権)」という権利が与えられること、「著作権(財産権)」については自由に譲渡ができることは既に説明した通りです。
ここでは、「著作者人格権」について説明します。
「著作者人格権」とは、著作物を生み出した著作者の感情を守り、精神的に傷つけられないようにするための権利のことをいいます。
この「著作者人格権」は、著作者の感情を守る権利であるため、譲渡することはできないことになっています。
そのため、譲渡によって移転することができないということは、就業規則・著作権譲渡契約によって譲渡できるのは「著作権(財産権)」のみであることを意味します。
著作者には「著作者人格権」として次の権利が与えられます。
- 公表権:著作物を公表するか否か、公表する場合の時期や方法を決められる権利
- 氏名表示権:著作物を公表する際に著作者名を表示するかどうか決められる権利
- 同一性保持権:著作物の内容や題などを勝手に改変されない権利
- 名誉または声望を害する方法で利用されない権利:著作者の名誉などを害するような著作物の利用を禁止できる権利
つまり、会社は、「著作権(財産権)」全ての譲渡を受けたとしても、譲渡不可の「著作者人格権」の4つの権利に注意しなければいけないことになります。
もっとも、特に同一性保持権といった権利を気にしていては、作成してもらった著作物を修正する際にもいちいち著作者に確認が必要になってしまいます。
実は、著作者人格権は、譲渡することはできませんが、その権利の行使を制限することができます。
そのため、会社が著作権の譲渡を受ける際には、必ず「会社に対して著作者人格権を行使しないこと」に関して著作者と合意し、そのことを契約書などの書面に残すようにしましょう。
7 小括
従業員が業務中に作成した著作物であっても必ず職務著作として会社が権利を得ることができるわけではありません。生み出された著作物が何かによって要件が変わります。職務著作となる要件を正しく理解することが重要です。
また、職務著作の要件をみたさない場合にも、適法に会社が権利を得る方法も知っておくことで、従業員と著作権に関して争うといったトラブルを回避することができます。
8 まとめ
これまでの解説をまとめると、以下の通りです。
- 「著作権」とは、作成した小説や絵画などの著作物を独占的に利用できる権利である
- 「著作物」とは、①思想または感情であること、②表現されていること、③創作性があること、④文芸、学術、美術、音楽の範囲に属していることの4つの要件をみたすもののことをいう
- 著作者には、著作権として「著作者人格権」と「著作権(財産権)」という権利が与えられる。
- 「著作権(財産権)」とは、著作物の財産的な利益を保護する権利のことをいう
- ・「職務著作(法人著作)」とは、一定の条件のもと、会社が著作者になることをいう
- 「職務著作」となる要件は①法人等の発意にもとづくこと、②法人等の業務に従事する者が職務上作成するものであること、③法人等の名義の下に公表するものであること、④作成時における契約、就業規則その他に別段の定めがないことの4つの要件である
- プログラムの著作物について職務著作となるかどうか判断するときは、法人等の名義の下に公表することという要件は不要である
- 職務著作とならない場合に会社が著作権を得る方法として①就業規則に定める方法、②個別の著作権譲渡契約を締結する方法の2つがある
- 就業規則と著作権譲渡契約のどちらを選択するかは、①雇用関係にあるか否か、②個別の条件を設定したいかどうかがポイントである
- 職務著作にあたらない場合でも会社が「著作権(財産権)」を得ることはできるが、「著作者人格権」を得ることはできない
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。