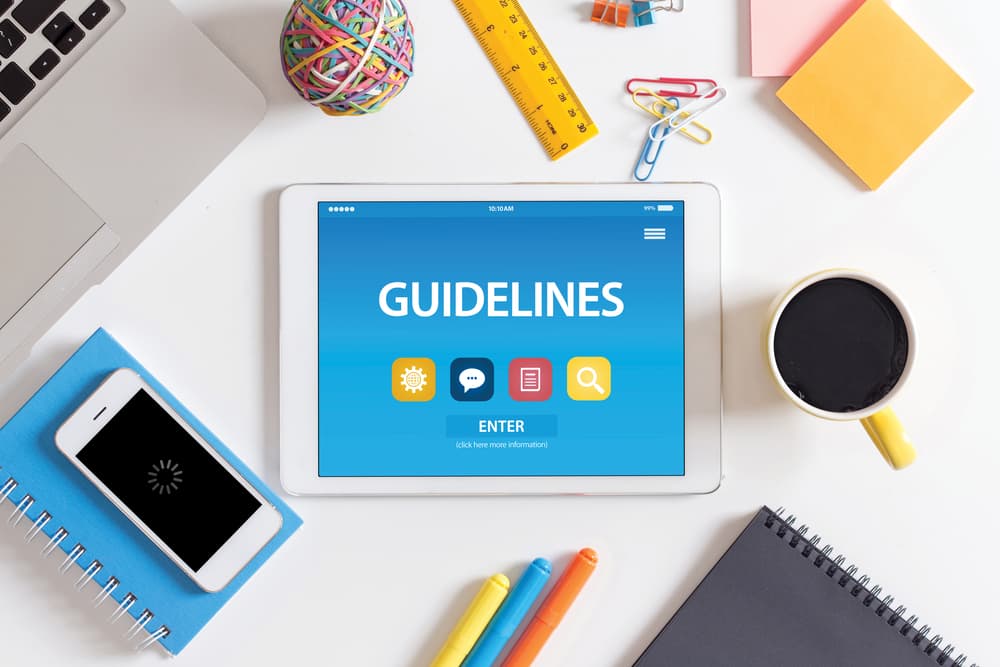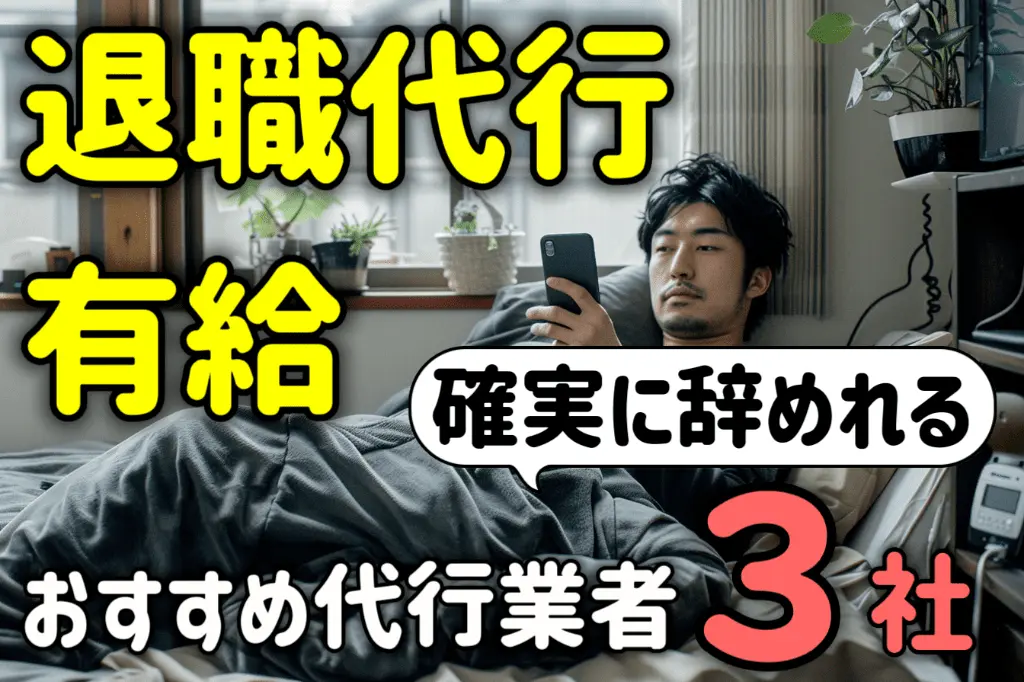厚労省「スタートアップ労働条件」に学ぶ就業規則の3つの要点を解説

はじめに
スタートアップ企業において、労働条件を考えることは、会社を発展させるうえでも、きわめて重要なことです。とはいえ、会社の労働条件や労働環境が適切であるかを、自ら判断することは簡単なことではありません。
ですが、適切な労働条件などを構築していくためにも、自社の労働条件などを精査することを後回しにすべきではありません。
これらのことを後回しにしてしまうと、改善点を発見することもできないまま、場合によっては、労働条件が適切でないとして、労働基準監督署から是正勧告を受けてしまうことにもなりかねません。
そこで今回は、厚労省から出された「スタートアップ労働条件」を参考に、労働条件などの整備にとって、特に重要な「就業規則」について、その必要性や記載すべき内容などのポイントを、弁護士がわかりやすく解説していきます。
1 「スタートアップ労働条件」とは?
「スタートアップ労働条件」とは、スタートアップ企業などの労働条件や就労環境について、その適切性を診断する目的で開設された厚生労働省のポータルサイトです。
このサイトでは、以下の6つの項目について設けられている質問に回答することで、自社の労務管理・安全衛生管理などに問題点がないかを診断できるようになっています。
- 募集、採用、労働契約の締結
- 就業規則(★)、賃金、労働条件、年次有給休暇
- 母性保護、育児、介護
- 解雇、退職
- 安全衛生管理
- 労働保険、社会保険、その他
今回の記事では、これらの中でも重要なうちの一つである「就業規則」について説明してしていきます。
2 就業規則とは
(1)就業規則とは?
「就業規則」とは、労働者に支払われる賃金や労働時間などを含む労働条件について、会社や労働者が守るべきルールを定めた規則集のことをいいます。
規則集とはいっても、労働者を監視し、会社の意のままに働かせるためのものではありません。就業規則は、会社と労働者がお互いの権利を守り、かつ義務を果たしながら、会社を発展させていくことを目的として作成されるものです。労使双方(労働者と使用者)が職場のルールとして就業規則を守ることで、労使間の無用のトラブルを防ぐという役割をも果たします。
もっとも、すべての事業所に就業規則の作成が義務づけられるわけではありません。
事業所が就業規則の作成を義務付けられるのは、「常に10人以上の労働者を雇用している場合」です。ここでいう労働者は、正社員だけでなく、アルバイトやパートなどのすべての雇用形態の労働者を含みます。つまり、雇用形態を問わず、会社内で常に10人以上の労働者を使用している事業所は、就業規則の作成・届出が義務付けられるということになります。
このように、一定の事業所において、作成・届出を義務付けられる就業規則ですが、そもそも、就業規則を作成する意義は何なのでしょうか。
この点については、就業規則がなかったらどうなるのか、という視点で見ていくとわかりやすいと思います。
(2)就業規則がない場合の不都合性
既に見たとおり、雇用している労働者が10人未満の事業所は、就業規則を作成する義務を負いません。
ですが、就業規則がないということは、職場のルールが存在しないということを意味します。そのため、「ルールに違反する」という事態も起きえないことになり、このことが、さまざまな不都合性を生みます。
たとえば、以下のような点で不都合が生じることが想定されます。
- 欠勤の扱い
- 退職の扱い
- 懲戒免職
それぞれを詳しく見ていきましょう。
(1)欠勤の扱い
労働者が欠勤などをすれば、その分を給与から控除されるというのが一般的です(いわゆる「ノーワーク・ノーペイの原則」)。
これは、前提として、就業規則において、賃金の計算方法などがきちんと定められており、そのことが根拠となるからです。
ですが、就業規則がない場合や、就業規則はあるものの、賃金の計算方法などがあいまいにしか定められていないような場合には、欠勤分を控除できる根拠がないということになり、控除できなくなる可能性があります。
また、精神的な理由などにより、労働者が長期にわたって欠勤した場合についても、就業規則がないと休業期間などに関するルールがないことになるため、会社と労働者の間で意見の対立が生じるおそれがあります。
(2)退職の扱い
法律上、労働者が会社を退職するためには、遅くとも会社を退職する日の2週間前までに会社に退職の意思を伝えなければなりません。
もっとも、仕事の引継ぎなどを考えると、2週間という短い期間で、労働者の退職に対処するというのは困難です。
この点、就業規則があれば、退職の意思を伝える時期などを任意に定めることができるため、実際に退職するまでの期間を2週間よりも長い期間に設定することができますが、就業規則がない場合には、この法律上の2週間という期間に拘束されてしまいます。
つまり、就業規則がない場合には、会社は、2週間という短い期間で、労働者の退職に対処しなければならなくなります。
(3)懲戒免職
労働者において、業務上の怠慢や不誠実な勤務態度などが認められた場合、会社は、その労働者に対して、懲戒免職や減給などの処分を与えようと考えるはずです。
もっとも、就業規則がない場合、会社は、ルール違反によるペナルティを、その労働者に与えることができません。仮に、就業規則によらずに労働者を解雇してしまうと、最悪の場合、不当解雇として訴えられる可能性もあります。
以上に見てきたように、就業規則がないと、処分などをする際に必要となる根拠がないために、然るべき対応が取れない、といった事態を招くおそれがあります。このような不都合な事態は、以上に挙げた場面に限られず、このほかにも存在するものと考えられます。
以上からも、就業規則を作成しておくことがいかに重要なことであるかがおわかり頂けたのではないでしょうか。
就業規則を作成することの意義を確認したところで、次の項目では、就業規則で具体的に定めるべき内容について、詳しく見ていきたいと思います。
3 就業規則の内容
就業規則に記載する事項には、大きく分けて
- 絶対的必要記載事項
- 相対的必要記載事項
の2つがあります。
(1)絶対的必要記載事項
「絶対的必要記載事項」とは、労働基準法において、就業規則に必ず記載しなければならない事項とされているものをいいます。
具体的に、「絶対的必要記載事項」とされているのは、
- 労働時間
- 賃金
- 退職
の3つです。
①労働時間
労働時間に関する内容として、
- 始業、終業時間
- 休憩時間(与える時間や与え方)
- 休日(その日数や与え方)
- 休暇(年次有給休暇、産前産後休業、生理休暇、特別休暇など)
- 交代制の場合、就業時転換に関する事項(交替期日、交替順序など)
を記載しなければなりません。
②賃金
賃金に関する内容として、
- 賃金の決定、計算方法(賃金の決定要素と賃金体系)
- 賃金の支払方法(直接支給、銀行振込など)
- 賃金の締切日、支払日(月給、週給、日給の区分。月給、週給の場合は、その締め日と支給日)
- 昇給に関する事項(昇給の時期、その他の条件)
を記載しなければなりません。
③退職
退職に関する内容として、
- 退職、解雇、定年の理由
- 退職、解雇、定年の際の手続き
を記載しなければなりません。
以上のように、絶対的必要記載事項とされている内容は、労働者・使用者にとっては、どれも基本的な事項であるということがいえます。
なお、絶対的必要記載事項の一部が記載されていない就業規則を作成・届出した場合であっても、その就業規則は、労働者と使用者の間では有効です。
もっとも、その就業規則の不備を補正しない場合には、労働基準法に違反し、
- 最大30万円の罰金
を科される可能性があります。
(2)相対的必要記載事項
「相対的必要記載事項」とは、労働基準法において、必ずしも就業規則に記載しなければならない事項ではないものの、独自にルールを定めるのであれば必ず記載しなければならない事項とされているものをいいます。
具体的に、「相対的必要記載事項」とされている内容は、以下の7つです。
- 退職手当
- 臨時の賃金や最低賃金額
- 費用負担
- 安全衛生
- 職業訓練
- 災害補償や業務外の傷病扶助
- 表彰や制裁
①退職手当
退職手当の対象となる社員の範囲や、退職手当の計算および支払方法、退職手当の支払時期を定めなければなりません。
②臨時の賃金や最低賃金額
臨時の賃金など(退職手当を除きます。)や最低賃金額に関する事項を定めなければなりません。
臨時の賃金には、賞与や結婚手当、傷病手当などが含まれます。たとえば、賞与の支払いに関して、ルールを定めるのであれば、必ず記載する必要があります。
また、最低賃金額は国によって定められているものですが、この最低賃金額に関してルールを定める場合にも、必ず記載する必要があります。
③費用負担
労働者に食費や作業用品に必要な費用などを負担させる場合については、その旨を定めなければなりません。
④安全衛生
安全衛生に関しては、たとえば、会社・労働者において、事業場における災害事故の防止や傷病予防などに努めるといったことをルールとして定めることが考えられます。
このようなルールを定める場合には、必ず就業規則に記載しなければなりません。
⑤職業訓練
訓練の種類、期間、受訓資格、訓練中後の処遇などについて定めなければなりません。
⑥災害補償や業務外の傷病扶助
災害補償に関しては、たとえば、労働者が業務上の事由などにより負傷したり、死亡したような場合における災害補償をルール化することが考えられます。
また、業務外の傷病扶助に関しては、たとえば、労働者が業務外の疾病にかかった場合の扶助などについて、ルールを定めることが考えられます。
⑦表彰や制裁
表彰の種類と事由、懲戒の事由、種類、手続きなどについて定めなければなりません。
ここで注意しなければならないのが、「制裁」の記載についてです。
会社は、制裁に関する内容を、法令や労働協約などに反しない限り、一方的に定めることができることになっています。
ここでいう「労働協約」とは、賃金額や労働時間などの労働条件や、労働組合と使用者との関係などについて、労働組合と会社の間で団体交渉を行い、合意に達した取り決めのことをいいます。
相対的必要記載事項としての「制裁」について、その内容が無制限に認められると、多額の減給処分を受けるなどして労働者の生活が脅かされるという事態にもなりかねません。そこで、減給の額については、1回の減給額が平均賃金の1日分の半額を超え、減給の総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならないとされています。
なお、就業規則の内容は、法令および当該事業場において適用される労働協約に反してはなりませんが、仮に、法令または労働協約に反する就業規則を作成した場合には、所轄の労働基準監督署長から、その変更を命じられる可能性があります。
このように、相対的必要記載事項は、そもそも、会社が独自にルールを定めようとする場合に記載するものですから、そのルールを作らないのであれば、相対的必要記載事項を記載しなくとも、法律上は問題ありません。
もっとも、会社が独自にルールを設けているにもかかわらず、相対的必要記載事項が記載されていない場合、絶対的必要記載事項の場合と同様に、就業規則自体は有効であるものの、場合によっては、
- 最大30万円の罰金
に科される可能性があります。
以上に見てきたとおり、就業規則は、絶対的必要記載事項を押さえることはもちろんのこと、相対的必要記載事項についても理解したうえで、作成することが重要です。
もっとも、就業規則は作成しさえすればそれで足りるというわけではありません。作成した就業規則は、所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があるうえ、作成しただけで効力が生じるわけでもありません。
4 就業規則の届け出
就業規則の作成を義務付けられる事業所は、これを作成または変更する場合には、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。
以下は、就業規則を作成・変更する場合に、その届出までのフローを図にしたものです。
このように、就業規則を届け出るまでの流れは、以下のようになります。
- 事業場単位での作成・変更
- 意見書の添付
- 労働者への周知
- 届出
↓
↓
↓
(1)事業場単位での作成・変更
就業規則は、企業単位ではなく、事業場単位で作成し、届け出る必要があります。
たとえば、1企業で2以上の営業所、店舗などを有している場合は、企業全体をとらえて1つの就業規則を作成すべきかどうかを考えるのではなく、それぞれの営業所、店舗などを1つの事業場としてとらえて、その事業場ごとに就業規則を作成すべきかどうかを考えます。つまり、企業全体の労働者の数を合計するのではなく、それぞれの事業場ごとに労働者の数を合計し、常時使用する労働者の数が10人以上である事業場については、就業規則を作成し、届け出をする必要があるということです。そのため、就業規則を作成した事業場は、それぞれの事業場を管轄する労働基準監督署長に、個別に届け出る必要があります。
なお、1企業で2以上の事業場を有する場合であっても、営業所、店舗などの就業規則が変更前・変更後を通して、本社の就業規則と同じ内容のものである場合には、本社の所在地を管轄する労働基準監督署長に、一括して届け出ることも可能です。
(2)意見書の添付
就業規則を届け出る際は、以下のように場合分けして、意見書を添付しなければなりません。
- 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合
- 労働者の過半数で組織する労働組合がない場合
①労働者の過半数で組織する労働組合がある場合
労働組合の意見を記し、その署名または記名押印のある意見書を、届出の際に添付する必要があります。
②労働者の過半数で組織する組織する労働組合がない場合
労働者の過半数を代表する者(「過半数代表者」といいます。)の意見を記し、その者の署名または記名押印のある意見書を、届出の際に添付する必要があります。
なお、ここでいう「過半数代表者」は、労働者の立場を代表する者であるため、
- 事業の種類にかかわらず、監督もしくは管理の地位にある者、または機密の事務を取り扱う者でないこと
- 投票、挙手などの方法で選出された者であり、使用者の意向により選出された者でないこと
のいずれも満たしていることが必要です。つまり、会社の経営陣ではなく、労働者の代表者として就業規則の内容に意見をいえる人間でなくてはならないということです。
(3)労働者への周知
就業規則は、職場のルールになるため、その内容を労働者に周知しなければなりません。労働者への周知がなされていない就業規則はその効力が否定されることになります。就業規則の周知方法などについては、次の項目で詳しく解説します。
(4)届出
就業規則の作成・変更が完了した後は、(1)~(3)の事項を遵守するともに、その内容をよく吟味して、所轄の労働基準監督署長に届け出ます。特に、労働者にとって就業規則を不利益に変更するような場合には、労働者の意見を十分に聴くとともに、変更の理由および内容が合理的なものとなるよう慎重に検討することが必要です。
以上のように、就業規則を届け出る際には、就業規則の作成・変更に加え、必要書類の添付や労働者への周知を忘れないようにしなければなりません。
特に、労働者への周知は、次の項目でも見るように、就業規則の効力にも関わってきますので、注意が必要です。
5 就業規則の周知
就業規則は、その職場におけるルールそのものであるため、就業規則を作成した場合には、その内容を労働者に知ってもらわなければ意味がありません。
そのため、作成した就業規則は、適当な方法により、労働者に周知しなければならないこととされています。
周知方法としては、主に、
- 常時各作業場の見やすい場所に掲示する、または備え付ける
- 書面で労働者に交付する
- 電子媒体に記録し、それをモニターなどで確認できるようにしておく
などが挙げられます。
また、労働者に就業規則を周知することは、就業規則の効力との関係でも極めて重要な事項です。先に見たように、就業規則の効力は、就業規則を作成しただけでは発生しません。就業規則が何らかの方法によって労働者に周知されたといえることが効力発生のための条件となります。そのうえで、たとえば、就業規則に施行期日が定められているときは「施行期日」、施行期日が定められていないときには、「労働者に周知された日」が就業規則の効力発生日になると考えられています。
このように、労働者に就業規則を周知することは、労働者に自社のルールを知ってもらうという目的に加え、就業規則の効力にも関係する極めて重要な事項です。
労働者に周知されていない就業規則は、効力が発生せず、無効なものとなりますので、注意するようにしましょう。
6 小括
スタートアップ企業などにおいて、適切な労働条件のあり方を検討する際には、「就業規則」の存在を外すことはできません。
就業規則を作成する目的は、会社と労働者がお互いの権利を守り、かつ義務を果たしながら、会社を発展させていくことです。
そのため、労使間のパワーバランスにも配慮して、会社側の主張ばかりを盛り込むのではなく、労働者側の意見をも取り込んだ就業規則を作成することが重要になってきます。
また、就業規則は、労務トラブルが生じた際に「解決の根拠」ともなる重要な機能を持っています。
以上のような就業規則を作成することの意義をきちんと理解したうえで、適切な就業規則を作成するようにしましょう。
7 まとめ
これまでの解説をまとめると、以下のようになります。
- 「スタートアップ労働条件」では、スタートアップ企業などの労働条件や就労環境を診断することができる
- 「就業規則」とは、賃金や労働時間などの労働条件について、会社や労働者が守るべきルールを定めた規則集のことをいう
- 就業規則は、事業所が常に10人以上の労働者を雇用している場合に作成が義務付けられる
- 就業規則がない場合、①欠勤の扱い、②退職の扱い、③懲戒免職、といった点に不都合が生じるおそれがある
- 就業規則に記載する事項には、「絶対的必要記載事項」と「相対的必要記載事項」がある
- 「絶対的必要記載事項」とは、就業規則に必ず記載しなければならない事項のことをいい、①労働時間、②賃金、③退職の3つがある
- 「相対的必要記載事項」とは、独自にルールを定めるのであれば記載しなければならない事項のことをいい、①退職手当、②臨時の賃金や最低賃金額、③費用負担、④安全衛生、⑤職業訓練、⑥災害補償や業務外の傷病扶助、⑦表彰や制裁の7つがある
- 就業規則の作成を義務付けられる事業所において、就業規則を作成または変更する場合、所轄の労働基準監督署長に届出が必要である
- 届出にあたっては、①事業場単位での作成・届出、②意見書の添付、③労働者への周知の3点に留意する
- 作成した就業規則は、各作業場の見やすい場所への掲示、備え付け、書面の交付などによって労働者に周知しなければならない
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。