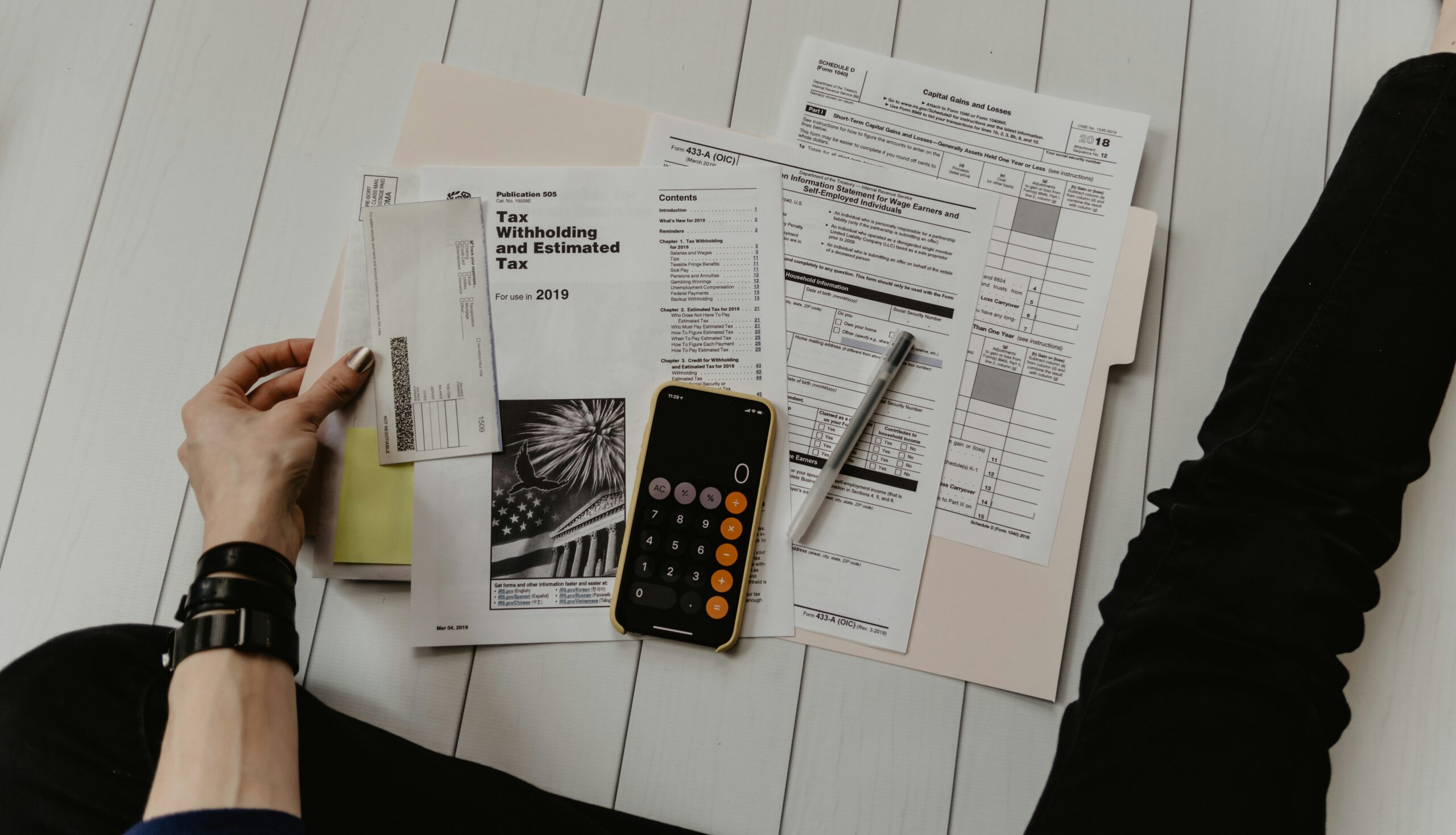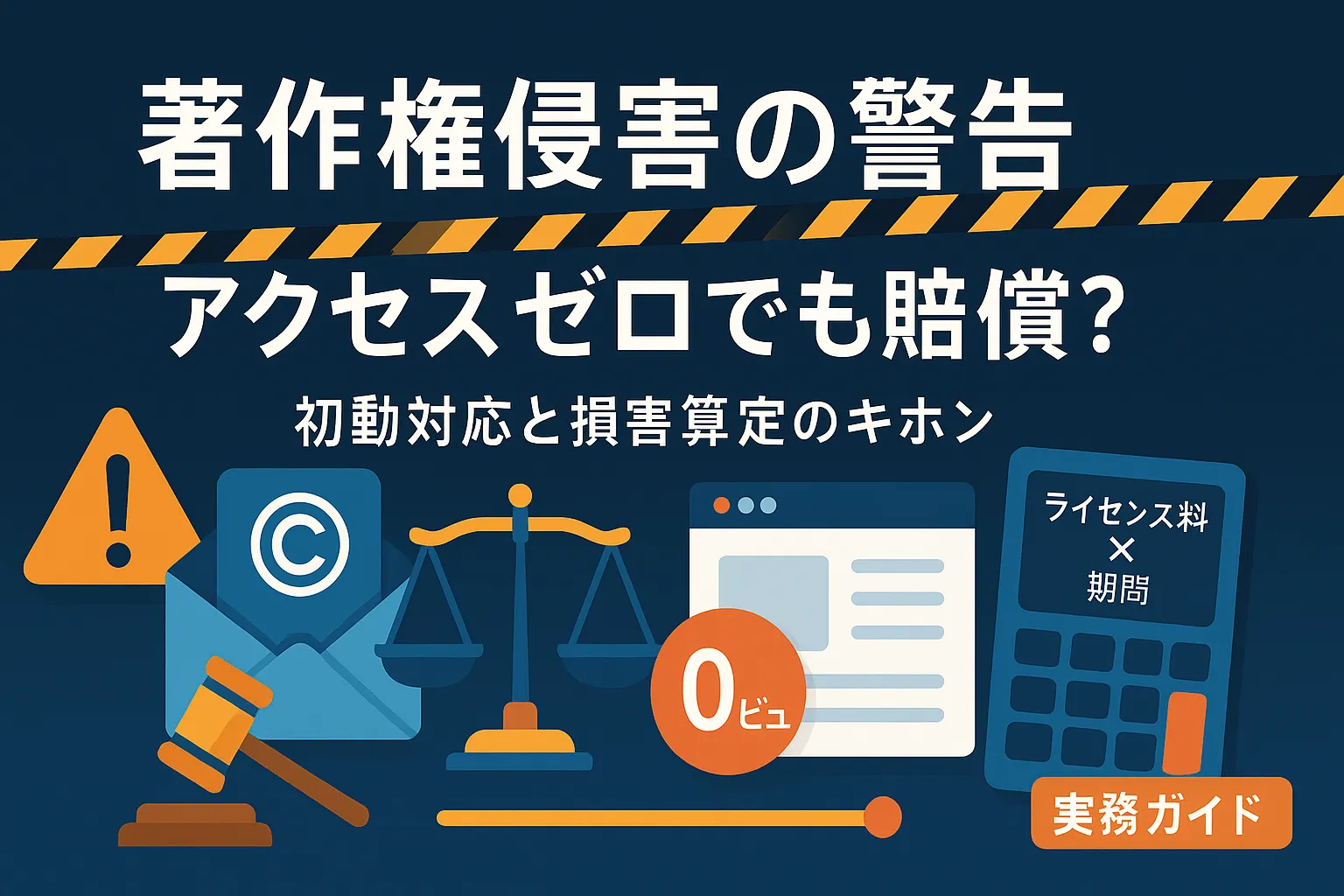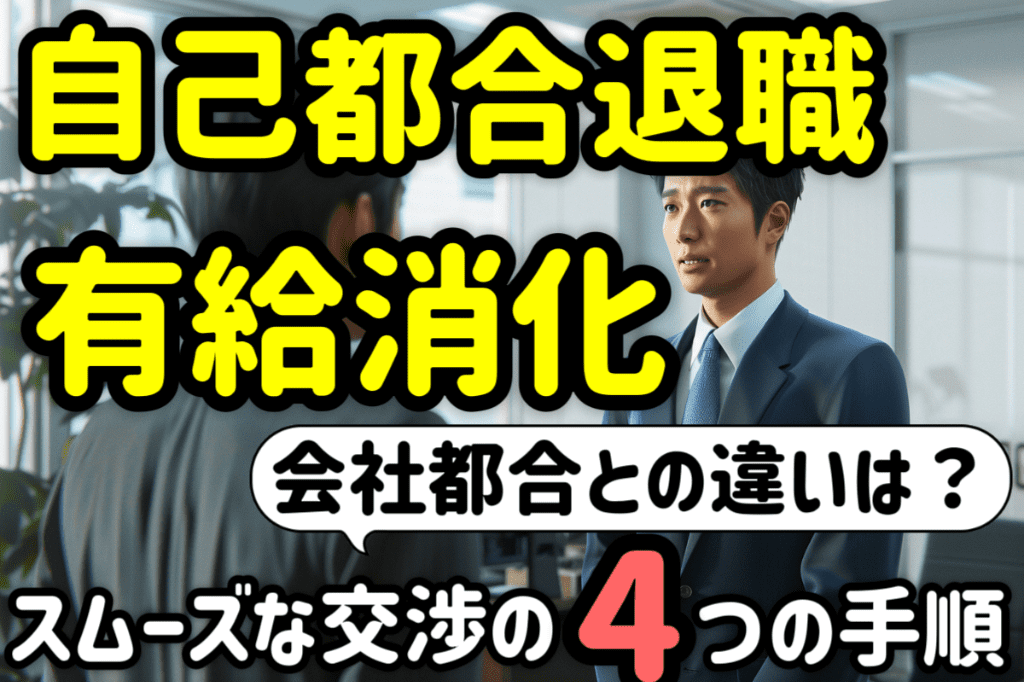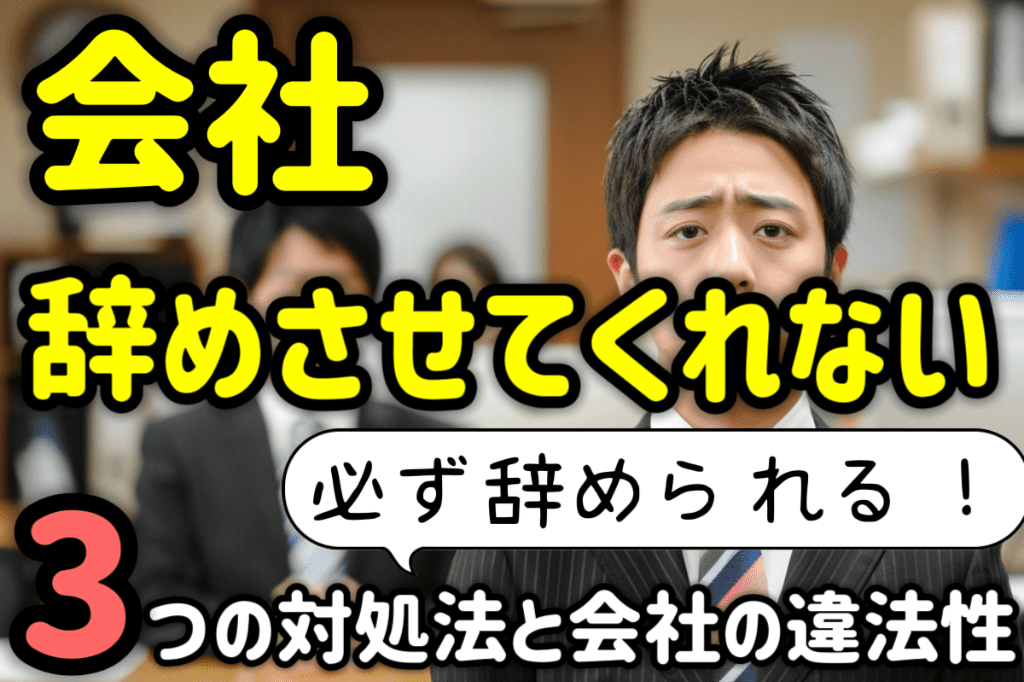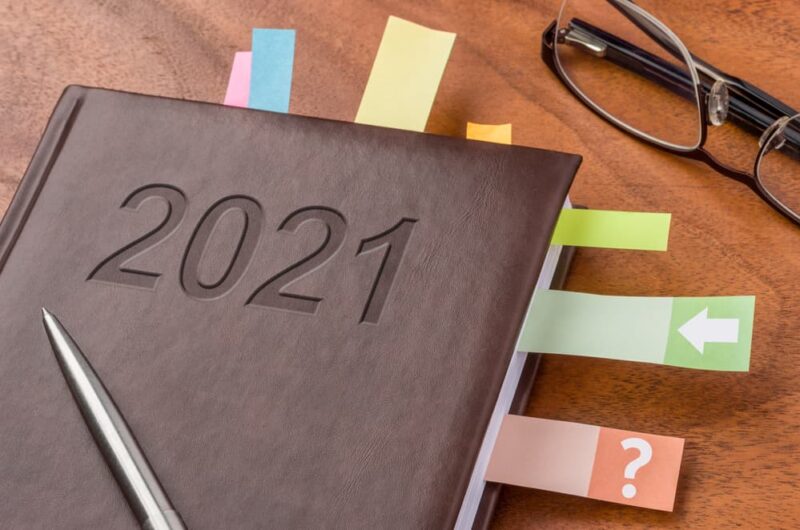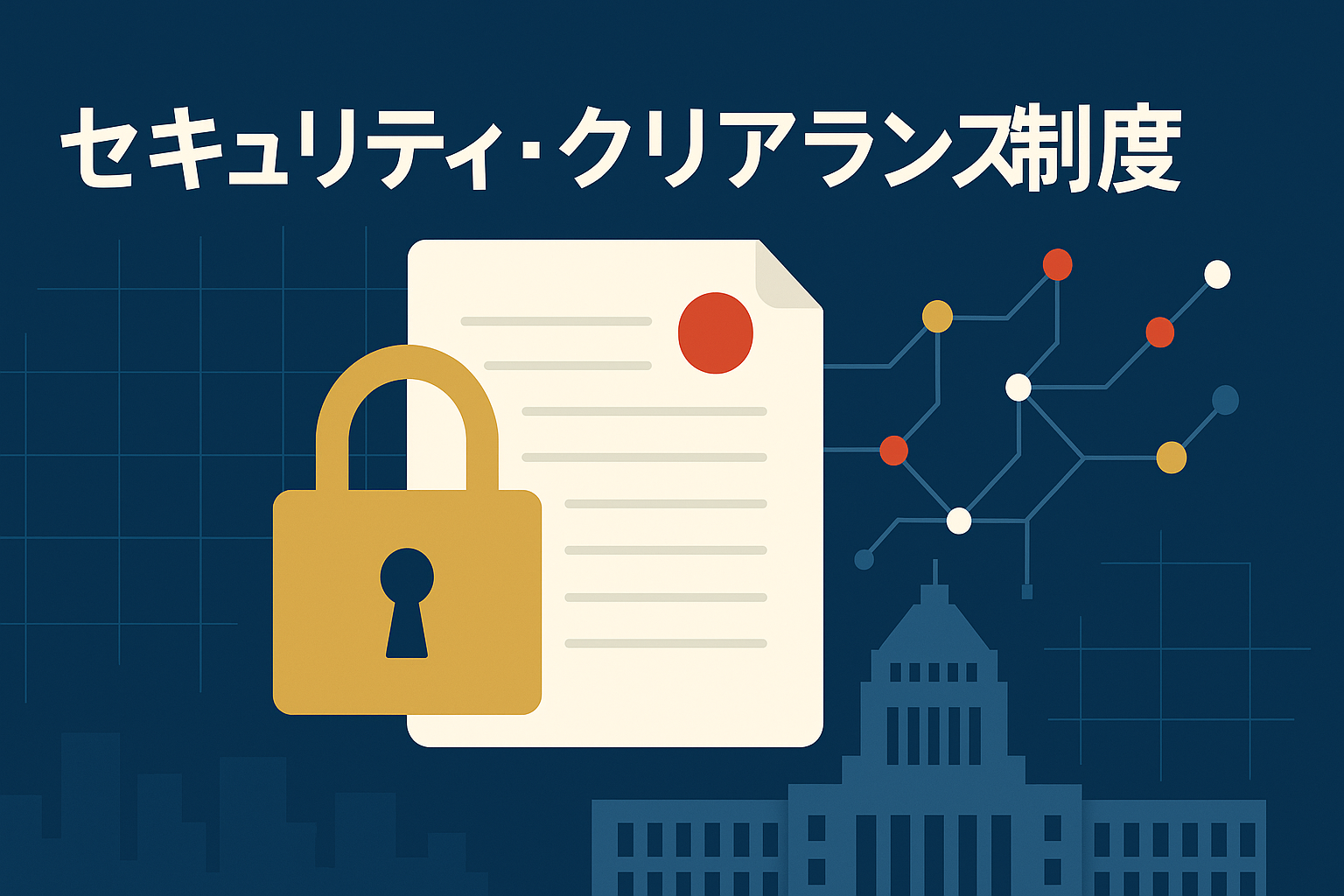弁護士が解説する2024年フリーランス新法の改正点まとめ|今後の働き方への影響と注意点

はじめに
弁護士の勝部です。
2024年11月に、フリーランス(特定受託事業者)が安心して業務に従事できる環境を整備するため、フリーランスに関する新たな規制である「フリーランス新法」が施行されます。
これにより、フリーランスとして活動する人々や、フリーランスに仕事を発注する企業にとって大きな変革をもたらされます。
私は2024年現在、経済産業省・中小企業庁主催の適正取引講習会「下請法(実践編)」の講師を務めておりますが、法施行が近づいてきたこともあり、講習会の中でこのフリーランス新法に関する質問を受けることもあります。
このフリーランス新法は、労働法と下請法のどちらも適用されないフリーランスの権利を保護するために制定されたものです。
この記事では、この新法施行の背景から具体的な変更点、法施行後に必要な対応について、フリーランスや自営業の方、業務委託契約を頻繁に行う企業にとっても、知っておくべき重要なポイントをわかりやすくご紹介します。
なお、フリーランスに関する問題のうち、エンジニア常駐などに関するSES契約について気になる方は、関連する「偽装請負とは?4つの判断基準と罰則を弁護士がわかりやすく解説!」「SES契約とは?契約の性質や派遣法との違いについて弁護士が解説!」も参考にしてください。
1. 2024年のフリーランス新法とは?
(1) フリーランス新法の概要
フリーランス新法は、正式名称を「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)といいます。令和5年4月28日に可決・成立し、同年5月12日に公布されました。 この施行により、フリーランスの稼働条件の向上や報酬トラブルへの対策が強化され、フリーランスの権利保護が大幅に向上します。
(2) フリーランス新法制定の背景と目的
2024年11月に施行される「フリーランス新法」は、急増するフリーランス人口とその働き方に対応するために策定されました。日本では、働き方改革が進む中、従来の会社員という形態だけではなく、フリーランスとしての働き方が注目を集めています。
しかし、労働法が想定しているのは主に雇用者と従業員の関係であり、フリーランスはその保護対象から外れていました。
また、企業から業務委託を受けて仕事をする下請事業者については、従来から下請法の保護がありましたが、下請法の適用があるのは、資本金1000万円を超える親事業者からの発注であり、これに該当しない場合には下請法の適用もありませんでした。
こういった状況において、報酬トラブルや不適切な契約内容によってフリーランスが不利益を被る事例が後を絶ちませんでした。
フリーランス新法の目的は、そうした問題を解決してフリーランスの⽅が安⼼して働ける環境を整備するため、①フリーランスの⽅と企業などの発注事業者の間の取引の適正化と②フリーランスの⽅の就業環境の整備を図ることを⽬的としています。(フリーランス法1条参照)。
(3) フリーランス新法の具体的な内容
フリーランス新法は、フリーランスが業務委託契約やプロジェクトベースの契約を結ぶ際に直面する問題を解決することを目指しています。以下のような主なポイントが含まれています。
- フリーランスの定義の明確化
- 報酬支払いの規定強化
- 業務委託契約における契約内容の明確化【注:特定業務委託事業者は、(期間の長短を問わず)重要な取引条件を書面または電磁的方法でフリーランスに明示しなければならない。/根拠:フリーランス法3条】
- 労働条件に関する法的保護の強化
これらのルールによって、フリーランスがより公正で安心して働ける環境が整備されます。
2. 2024年フリーランス新法の主なポイント
(1) フリーランスの定義を明確化
この法律の対象は、フリーランスと企業(発注事業者)の取引です。
それぞれの定義は以下のとおりです。
フリーランスは「業務委託を受ける側」で、従業員を雇っていない個人事業主のことを指します。
企業は「業務を依頼する側」で、従業員を雇用している事業者です。
例えば、個人のカメラマンやプログラマが企業から仕事(撮影やコーディング)を依頼される場合、この法律が適用されます。
ただし、従業員を雇っているフリーランスや、消費者を相手にしているフリーランスにはこの法律は適用されません。
(2) 発注事業者の義務
発注事業者には、フリーランスとの取引において、いくつかの義務が課されています。
この義務は、基本的には下請法における親事業者の義務とほぼ重なります。ですので、下請法の取引類型に該当する発注をすでにしており、下請法に基づいた発注ルールを理解している事業者においては、対応方針はおのずと見えてくると思います。
ここでは具体的な内容を説明します。
① 書面での取引条件の明示
企業がフリーランスに仕事を依頼した際には、すぐに「業務内容」「報酬」「支払期日」などの取引条件を書面や電子的に明示しなければなりません。
この書面又は電磁的方法による明示を「3条通知」といいます。
書面とありますので、口頭や電話での伝達はNGです。
ただし、発注書や契約書を紙で作成することが必須というわけではなく、以下の伝達方法も認められています。
- ファクシミリ(紙が排出される、又は受信データの記録機能を有するものに送信する場合)
- 電子メール
- チャットツール
- ショートメッセージサービス(SMS)
- CD-R、USBメモリ等
- ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)のDM機能
DM機能は、送信者が受信者を特定して送信することのできるものに限ります。 掲示板やブログのコメント欄への書き込みは不可です。
② 報酬支払期日の設定
報酬は、フリーランスが仕事を完了してから60日以内にできるだけ早く支払わなければなりません(フリーランス法4条)。
③ 禁止される行為
企業がフリーランスに対して次の行為をしてはいけません。
- 仕事が終わっても報酬を払わない(受領拒否)
- 約束した報酬を一方的に減らす(報酬の減額)
- 不必要な返品を求める(返品)
- 安く買い叩く(買いたたき)
- 無理に商品やサービスを買わせる(購入・利用強制)
- 不当な利益を要求する
- 一方的に契約内容を変更したり、やり直しを要求する
④ 募集情報の正確さ
フリーランスを募集する際には、虚偽や誤解を与える情報を掲載してはいけません。また、情報は常に最新で正確でなければなりません。
⑤ 育児や介護との両立への配慮
フリーランスが育児や介護と仕事を両立するために、例えば納期の延長やオンライン作業への切り替えなど、フリーランスの申し出に応じて必要な配慮を行わなければなりません。やむを得ない事情で配慮できない場合は、その理由を説明する必要があります。
⑥ ハラスメント対策
企業は、フリーランスに対するハラスメントを防ぐために、①ハラスメント禁止の方針を明確にし、周知する、②ハラスメントに対する相談窓口や対応体制を整える、③ハラスメントが発生した場合、迅速かつ適切に対応する義務があります。
⑦ 中途解除や契約更新拒否の事前予告
6か月以上の業務委託契約を途中で解除したり、契約を更新しない場合は、原則として30日前に予告しなければなりません。また、フリーランスから理由の開示を求められた場合は、その理由を説明する必要があります。
(3) 遵守すべき発注事業者の義務は発注事業者の種類によって異なる
これら7つの義務は発注事業者の基本的義務ですが、発注事業者の種類によって、どの義務規定が適用されるのかが異なってきます。
■発注事業者が従業員のいない法人や、個人である場合
この場合は、「① 書面での取引条件の明示」のみが適用されます。
なお、この規定からも分かるように、フリーランスからフリーランスへの発注であっても義務規定の適用はあります。
自分はフリーランスだから義務規定の適用はないということにはなりませんので、注意してください。
■発注事業者が従業員のいる法人や、個人である場合
この場合は、「① 書面での取引条件の明示」「② 報酬支払期日の設定」「④ 募集情報の正確さ」「⑥ ハラスメント対策」が適用されます。
■発注事業者が従業員のいる法人や、個人であり、1ヶ月以上の業務委託である場合(更新後の契約期間も含む)
この場合は、「① 書面での取引条件の明示」「② 報酬支払期日の設定」「③ 禁止される行為」「④ 募集情報の正確さ」「⑥ ハラスメント対策」が適用されます。
■発注事業者が従業員のいる法人や、個人であり、6ヶ月以上の業務委託である場合(更新後の契約期間も含む)
この場合は、①~⑦のすべてが適用されます。
3. フリーランス新法がフリーランスに与える影響
(1) 報酬に関する影響
フリーランスが最も気にかけるべきは報酬に関する問題です。 報酬については、まず、書面で明示されている必要があります(口頭発注はNG)。また、適正額であること、法令の定める期間内(仕事を完了してから60日以内)に支払いが完了すること、買いたたきや減額などの禁止行為に該当しないことも求められます。
(2) 労働条件(稼働条件)の改善とリスク管理
労働条件(稼働条件)に関しても、新法施行によって大きく改善される見込みです。特に、書面発注がなされることによって契約内容の曖昧さがなくなることで、フリーランスが契約時に直面するリスクが軽減されます。契約交渉時においても、法律の枠組みに基づいて権利を主張しやすくなるため、より公平な交渉が可能となります。
ただし、発注書面を作成していても必要な条項を欠いていたり、必要な条項は存在するものの、内容が不公平である場合も想定されます。
現に、下請法が適用される取引においても、発注書面(3条書面)の記載の一部を欠いているような契約書が作成されていることも少なくありません。下請法は企業法務を手掛ける弁護士にとっては必須の法律ではありますが、司法試験の受験科目ではありませんし、比較的マイナーな部類の法令に該当することが影響しているのかも知れません。
フリーランス新法についても個々の発注内容が法令に適合しているかどうかまでを保証するものでは当然ありませんので、最終的には発注事業者やフリーランスの方で適切な発注内容なのかを確認する必要があります。
(3) 契約交渉時の新たな注意点
新法施行により、契約書に記載すべき項目が増加します。これにより、契約交渉時には、より詳細な確認が必要となります。契約書において何を明記すべきかを理解し、フリーランスとしての権利を守るための準備が求められます。
4. 契約書の見直しポイント
(1) 契約書・発注書面に含めるべき必須項目
フリーランス新法では以下の取引条件を明示する義務があります。
- 業務の内容
- 報酬の額
- 支払期日
- 発注事業者・フリーランスの名称
- 業務委託をした日
- 給付を受領/役務提供を受ける日
- 給付を受領/役務提供を受ける場所
- (検査を行う場合)検査完了日
- (現金以外の方法で支払う場合)報酬の支払方法に関する必要事項
これらの発注条件が発注時に明確にされていることにより、契約内容の透明性が向上し、フリーランスの権利保護が強化されることになります。
(2) 支払い条件と権利保護に関する条項の強化
報酬に関する問題は、フリーランスが直面する最も一般的なトラブルの一つです。フリーランス新法では、支払い条件の明示が求められています。また、報酬に関する契約内容も事前に明確にする必要があります。
(3) 禁止行為の明確化
下請法でもたびたび問題となりますが、発注者と受注者のパワーバランスの差を背景とする不合理な取引というものが後を絶ちません。
例えば、発注後に発注数量を一方的に減らす、不当な減額をする、発注内容を途中で変更してやり直しをさせる、発注後に検査基準を変えて納品受領を拒否する、親事業者の店舗内作業を下請事業者スタッフに担当させる、等々、さまざまな違反類型があります。
フリーランス新法によって、発注時に書面化すべき事柄はクリアになっていますが、それだけでは不当な取引を防止することはできません。
禁止行為が法令によって定められていることにより、フリーランスは自らの権利を守り、トラブルの発生を防止することが可能となるのです。
5. 2024年以降の働き方にどう影響するか?
(1) フリーランスの働き方の変化
新法施行によって、フリーランスの働き方には大きな変化が予想されます。特に、契約内容が明確化されることで、より自由で柔軟な働き方が可能になる一方で、法的な義務や責任も明確になります。これにより、フリーランスとしてのリスク管理がより重要になってきます。
(2) 企業側の対応とフリーランスとの関係性
企業側もフリーランスとの契約方法を見直す必要があります。特に、法的なリスクを回避するために、契約内容の透明性を高め、フリーランスに対して公平な条件を提示することが求められます。
(3) 新法施行を受けた今後のトレンド
2024年のフリーランス新法施行を受け、フリーランス市場はさらに拡大することが予想されます。
今後注目されるのは、フリーランスの働き方がより安定することで、個人事業主としてのキャリアが拡大し、より一層プロフェッショナル化する可能性です。
例えば、5年前、10年前には個人のインフルエンサーが企業と対等な取引をして案件を受注することは一般的ではありませんでしたが、今では個人のインフルエンサーは下手な広告代理店よりも大きな成果を上げる存在として認知されています。
弁護士や税理士などの士業、コンサルタント、プログラマやデータアナリスト、デザイナーや音楽制作者などのクリエイターなど、企業側もフリーランスとの協力を深め、フレキシブルかつパワフルな労働力としてフリーランスを重要視する流れが強まることが予想されます。
また、育児や介護との両立を考える働き手など、フレキブルな労働スタイルを希望する方々にとっても、この新法施行は働きやすい環境を提供する可能性があります。
この動きは、今後TVや雑誌でも取り上げられる可能性が高く、フリーランスという働き方がさらに社会的に認知されるきっかけとなるでしょう。
同時に、フリーランスとしての働き方がより一層プロフェッショナル化し、契約や報酬に対する意識も高まることでしょう。
6. 新法施行に対するフリーランスの準備と対策
(1) 事前に準備しておくべき契約書や文書
フリーランス新法を見据え、フリーランスは契約書の見直しを進めるべきか、チェックする必要があります。契約書に記載すべき項目を確認し、報酬や業務内容についての明確な取り決めを行うことが重要です。また、業務内容や成果物に関する文書も整備しておくと安心です。
今後の動向を考えると、企業からの単純作業案件をただ受動的に受けるよりも、自身の強みと外部環境(市場環境や競争環境)を分析した上で、先回りしてサービス見直しをすることも効果的になります。
その際、フリーランス新法の内容を理解した上でサービス構築をするとよい視点が得られるかも知れません。
(2) 税務・社会保険制度の見直し
フリーランスは、自営業として税務や社会保険に関する義務を果たさなければなりません。新法施行を機に、税務や社会保険制度の見直しも行い、必要な手続きを忘れないようにしましょう。
(3) 弁護士への相談の重要性
契約書の作成やトラブルに備えるために、弁護士に相談することが推奨されます。特に複雑な業務委託契約や報酬トラブルに直面した場合、専門家のアドバイスを受けることでリスクを最小限に抑えることができます。
7. 新法施行を受けたトラブル防止策
(1) 契約書作成の際の注意点
フリーランス新法の施行を受けて、発注書面や契約書面の内容をより慎重に確認する必要があります。特に報酬や納期に関する取り決めを明確にし、後からトラブルにならないように細かく記載することが大切です。
(2) 法的に有効な契約締結方法
フリーランスとして契約を締結する際は、口頭ではなく、書面による契約を推奨します。また、電子署名など法的に有効な形で契約を結ぶことで、万が一のトラブルに備えましょう。【コメント:電磁的方法の可否・要件は条文・指針を確認(情報源外)。】
(3) 業務フローの見直し
法務対応は書面ひな形を作成しただけでは完了しません。営業などのフロント業務において、法令において定められている禁止行為がなされていないか、今一度業務フローをチェックしたり、フリーランス新法の内容を分かりやすく社内周知することも重要です。これによって、会社が法令違反トラブルに巻き込まれることを防ぐことが可能になります。
(4) 紛争解決方法と相談先
もし契約トラブルが発生した場合には、弁護士や労働基準監督署、または各種紛争解決機関に相談することができます。特に報酬未払いなどのトラブルに直面した際は、速やかに対応することが重要です。
フリーランス・事業者間取引適正化等法の違反被疑事実についての申出窓口(厚生労働省)
8. まとめ:2024年のフリーランス新法施行に向けた行動計画
(1) 新法施行に対応するための具体的アクション
2024年のフリーランス新法施行に備え、契約書の見直しや契約内容の書面化を進めることが重要です。また、報酬や労働条件に関する規定を理解し、フリーランスとしての権利を守るための準備を怠らないようにしましょう。
(2) 長期的なキャリア形成における新法施行の影響
新法施行を契機に、フリーランスとしてのキャリア形成にも影響が出ることが予想されます。法律を理解し、適切な対策を講じることで、より安定したフリーランスとしての活動が可能になるでしょう。
最後に
2024年11月に施行されるフリーランス新法施行は、フリーランスとしての働き方に大きな影響を与えます。この改正を理解し、必要な対策を講じることが重要になります。
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。