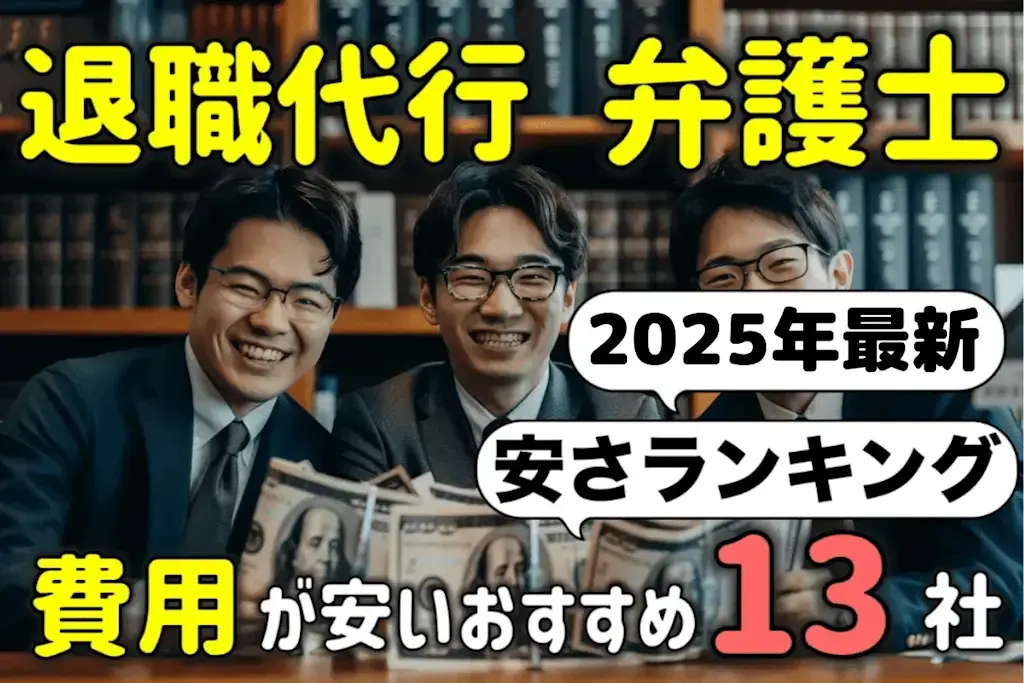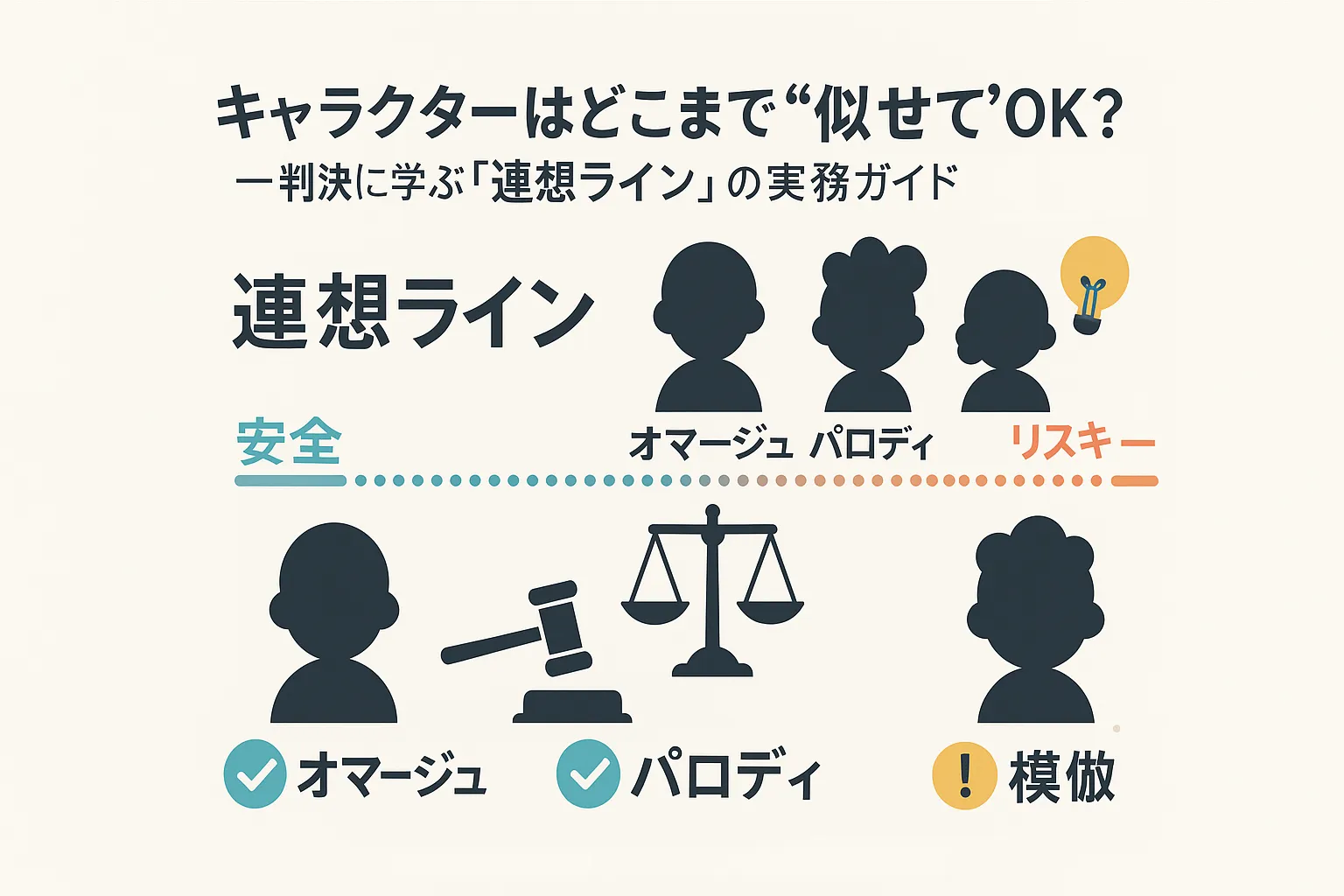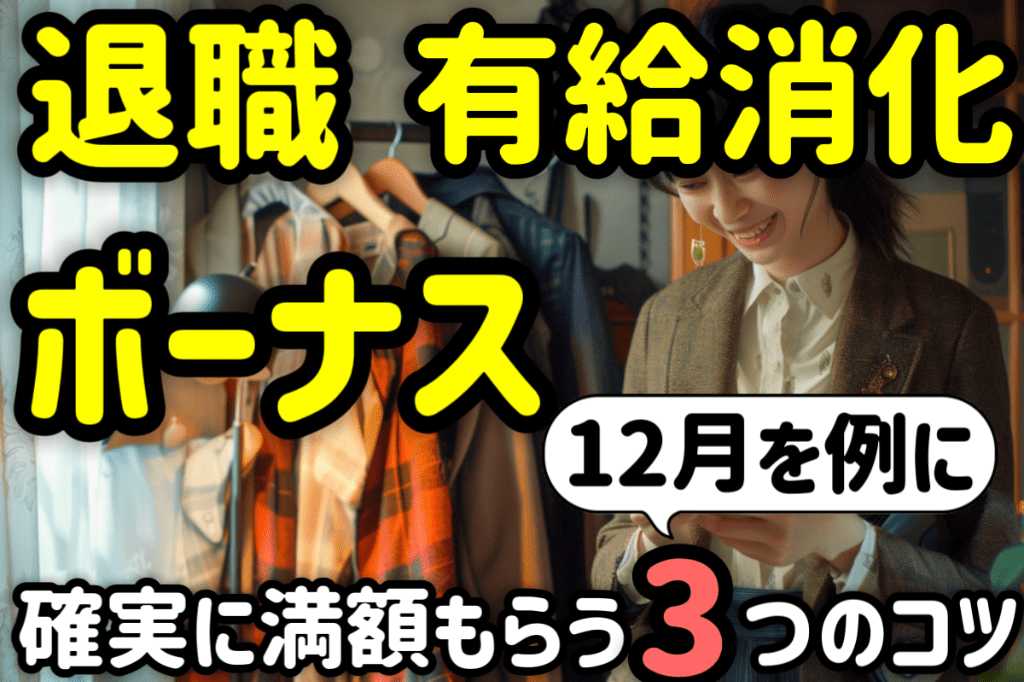年金改革法のポイントは?知っておくべき5つの改正点を弁護士が解説

はじめに
2020年6月に「年金制度改正法」(年金改革法)が公布されました。
近時では、高齢化社会に伴い、年金の受給開始時期である65歳以降においても就労を求める人が増加しています。また、いわゆる「ギグワーク」といったように、多様な働き方を求める労働者も増えてきています。
このような社会の変化を背景に、高齢労働者や短時間労働者の経済基盤を充実させる目的で制定されたのが今回の年金改革法です。
特に、中小企業に属する事業者にとっては、ポイントを押さえておくべき重要な法律です。
そこで今回は、年金改革法のポイントを中心に、弁護士がわかりやすく解説します。
1 改正のポイント

「年金改革法」は、2020年(令和2年)6月に公布されました。
今回の改正は、高齢期の長期化に伴う経済基盤の充実の必要性や短期労働者(アルバイトやパートなど)に対する保障の見直しの必要性などを背景として行われました。
主な改正のポイントは、以下の5つです。
- パート・アルバイトへ適用される被用者保険の拡大
- 在職中の年金受給のあり方の見直し
- 年金受給開始時期の選択肢の拡大
- 確定拠出年金の加入可能要件の見直し
- その他
2 パート・アルバイトへ適用される被用者保険の拡大(施行日:2022年10月1日)

一つ目の改正点は、「短時間労働者への被用者保険の適用拡大」です。
これまでは、被用者保険が適用されなかったパートやアルバイトの従業員でも、一定の条件を満たせば、被用者保険に加入できるようになります。
これまで、短期労働者が被用者保険の適用対象となるのは、従業員数が500人を超えている事業所に限られていました。
そのため、短時間労働者は、社会保険料をすべて自分で負担する必要がありました。
ですが、今回の改正により、一定の条件を満たす事業者は、被用者保険の適用対象に短期労働者を含めなければならなくなります。
ここでいう「一定の条件」とは、以下の4つのことを指し、これらをすべて満たす場合、事業者は、短期労働者を被用者保険の適用対象としなければなりません。
- 企業規模
- 労働時間
- 賃金
- 勤務期間
(1)企業規模
企業の規模に関する条件が、以下のように拡大されました。
- 2022年10月時点で従業員が100人を超えている
- 2024年10月時点で従業員が50人を超えている
ここでいう「従業員」とは、適用が拡大される前の通常の被保険者を意味するため、フルタイムの労働者と週あたりの労働時間が通常の労働者の3/4以上である短時間労働者の人数で判断されることになります。
また、直近1年のうち6ヶ月で上記①②の従業員数を超えている場合は、適用対象となります。
これにより、適用対象となる短期労働者は、これまで全額自己負担であった保険料のうち半額を事業者に負担してもらえるようになります。
(2)労働時間
被用者保険の適用対象となる労働者は、契約における週の所定労働時間が20時間以上であることが必要です。
この条件は、従来の条件を維持する形になっており、具体的には、契約における週の所定労働時間が2ヶ月続いて20時間以上となり、それ以降も続くと見込まれる場合は、3ヶ月目から保険に加入する必要があります。
(3)賃金
被用者保険の適用対象となる労働者は、月の賃金が8万8000円以上でなければなりません。この条件についても、従来の条件が維持されています。
ここでいう賃金は、基本給と諸手当の合計額のことをいい、賞与や残業代は含まれません。
(4)勤務期間
フルタイムなどの被保険者と同じように、勤務期間が2ヶ月を超えていることが必要です。
なお、以下の場合は、いずれも勤務期間が1年以上見込みとして扱われます。
- 雇用契約書などに契約が更新される旨や更新される場合がある旨が記載されている
- 同じ事業所で同様の雇用契約により雇用されている者が更新などで1年以上雇用された実績がある
もっとも、雇用契約の期間が1年未満で、契約更新の可能性を示す記載がなく、かつ、更新の実績もない場合には、上の2つは適用されません。
3 在職中の年金受給のあり方の見直し

二点目として、在職中における年金受給のルールが見直されたことが挙げられます。
具体的なポイントは以下の2点です。
- 在職定時改定
- 在職老齢年金制度の見直し
(1)在職定時改定(施行日:2022年4月1日)
これまでは、老齢厚生年金の受給権を取得した(65歳)後も引き続き働く場合、退職時、もしくは、70歳になった時のどちらか早い時期に、65歳以降の被保険者であった期間の厚生年金の支払額を加えて、老齢厚生年金の額が改定されていました(退職改定)。
そのため、65歳以降に支払う厚生年金の額は、70歳になるまで反映されることはありませんでした。
ですが、退職改定の下では、65歳以降に支払う厚生年金保険料の恩恵を感じにくいというデメリットがあります。
そこで、退職改定を見直し、今回の改正で導入されたのが「在職定時改定」です。
「在職定時改定」とは、65歳以降、年金の受給額を1年ごとに計算し直すことをいいます。つまり、これからは、年ごとに行われる改定により年金が上積みされていくようになります。
たとえば、65歳から66歳になるまでの1年間に支払われた厚生年金保険料は、すぐさま66歳で受給する年金額に反映されることになり、その後も、支払った厚生年金保険料が年単位で反映されることになります。
(2)在職老齢年金制度の見直し(施行日:2022年4月1日)
「在職老齢年金制度」とは、60歳以降に働きながら受け取る老齢厚生年金と月々の給料の合計額が一定の基準に達すると、受給できる年金額が一部減額され、または、その全額について支給が停止されるという制度です。
ここでいう一定の基準とは、従来、在職老齢年金額+収入=28万円でしたが、この基準に達する労働者は少なくないと考えられ、現に、そのことが就労に一定の影響を与えていることが確認されています。
そこで、在職老齢年金制度で設けられている基準が、以下のとおり引き上げられます。
- 在職老齢年金+収入=47万円(月額)
なお、65歳以上の在職老齢年金制度については、従来から基準額は47万円となっており、この基準額を維持することとされています。
4 公的年金の受給開始時期の選択肢の拡大

三点目は、公的年金の受給開始時期の選択肢の拡大です。
現在、公的年金の受給開始時期は、60~70歳の間で自由に選ぶことができます。
現行では、受給を開始する時期によって、受け取れる年金額が以下のように増減します。
- 65歳より早く受給を開始した場合(繰上げ受給)⇒ 年金額は月額で最大30%減額
- 65歳より後に受給を開始した場合(繰下げ受給)⇒ 年金額は月額で最大42%増額
以上が、年金受給開始時期とそれに伴う年金額の増減率に関する現行のルールですが、これが、以下のように変更されます。
(1)繰下げ受給の上限年齢・年金額の増減率の変更(施行日:2022年4月1日)
繰下げ受給の年齢の上限が、現行の70歳から75歳に引き上げられます。
そのため、今後は、公的年金の受給開始時期を60歳から75歳の間で選ぶことができるようになります。
また、繰上げ受給と繰下げ受給に係る増減率が以下のように変更されます。
- 繰上げ減額率 ⇒ 最大で24%
- 繰下げ増額率 ⇒ 最大で84%
なお、繰下げ受給の上限年齢に関する変更は、改正法が施行される2022年4月時点で70歳未満の者が適用対象となります。
(2)70歳以降に請求する場合の繰下げ制度(施行日:2023年4月1日)
70歳~80歳未満の者が年金を請求する場合において、請求時に繰下げ受給を選ばない場合は、5年前に遡って繰下げ受給の申出があったものとして、年金額が算定されることになります。
5 確定拠出年金の加入可能要件の見直し

最後の改正点として、「確定拠出年金(DC)」の加入可能年齢の引き上げが挙げられます。
(1)確定拠出年金とは
「確定拠出年金(DC)」とは、私的年金のことをいい、以下の2種類に分かれています。
- 企業型確定拠出年金(企業型DC)
- 個人型確定拠出年金(個人型DC)
①企業型DC
「企業型DC」とは、企業が掛金を拠出し、従業員が自分で運用する年金制度のことをいいます。企業型DCは、厚生年金被保険者のうち65歳未満の人が加入対象となっています。加入者は、60歳以降に、それまで積み立てられた年金資産を退職金もしくは年金という形で受け取ることになるため、60歳になるまでは原則として引き出すことはできません。
②個人型DC(iDeCo)
「個人型DC」とは、自分で掛け金を設定して積み立てていき、60歳以降に受け取ることができる年金制度のことをいいます。
個人型DCは、国民年金被保険者のうち60歳未満の人が加入対象となっています。
もっとも、企業型DCに加入している場合は、企業がiDecoとの併用を認めない限り個人型DCに加入することはできません。
(2)加入可能要件の見直し
これら2つの確定拠出年金に関し、以下の点が変更されます。
- 加入可能な年齢
- 制度面・手続面
①加入可能な年齢(施行日:2022年5月1日)
現行では、企業型DCについては「厚生年金被保険者のうち65歳未満の人」が、個人型DCについては「国民保険被保険者のうち60歳未満の人」が加入対象となっています。
この条件が、以下のように変更されます。
- 企業型DC ⇒ 厚生年金被保険者のうち70歳未満の人
- 個人型DC ⇒ 国民年金被保険者のうち65歳未満の人
このように、それぞれにおいて条件が緩和されたことにより、企業は高齢者雇用の状況に応じて柔軟に制度を運用することが可能になります。
また、高齢期の就労が増えてきている現状にも合った制度変更になっています。
②制度面・手続面
中小企業向けの企業年金制度の対象範囲が拡大されるとともに、企業型DCと個人型DCの併用条件が緩和されます。
設立手続きを簡素化した「簡易型DC」や企業年金の実施が難しい中小企業がiDeCoに加入する従業員の掛金に追加で掛金を拠出できる「中小企業主掛金納付制度(iDeCoプラス)」は中小企業向けの企業年金制度です。
これらの企業年金制度を実施するためには、従業員規模が100人以下であることが必要です。
ですが、中小企業における企業年金の実質率が低下しているため、これらの制度を実施するための条件が「従業員規模100人以下」から「従業員規模300人以下」にまで拡大されます(施行日:2020年6月5日から6ヶ月を超えない範囲)。
また、これまで企業型DCの加入者がiDeCoに加入するためには、その旨を認める規約の定めがあって、事業主の掛け金の上限を55,000円/月から35,000円/月に引き下げた従業員であることが必要でした。
ですが、現状においてあまり活用されていないことから、これらの条件がなくても、中小企業の拠出限度額から事業主の掛け金を差し引いた残りの範囲内で、iDeCo(20,000円/月の範囲)に加入できるようになります(施行日:2022年10月1日)。
6 その他

以上に見てきた改正点のほかにも、以下のような点が改正されました。
- 基礎年金番号通知書への切替え
- 脱退一時金制度の見直し
- 被用者保険の早期加入措置
- 日本年金機構の調査権限の整備
- 年金担保貸付事業の廃止
(1)基礎年金番号通知書への切替え(施行日:2022年4月1日)
現在において、被保険者情報はシステムで管理されており、また、マイナンバー(個人番号)が導入されたことにより、手帳という形式を維持することやその役割が希薄化しています。
そのため、国民年金の被保険者となる20歳到達者や20歳より前に厚生年金被保険者となった人などに対しては、国民年金手帳ではなく基礎年金番号通知書によって資格を取得した旨が知らされます。
(2)脱退一時金制度の見直し(施行日:2021年4月1日)
「脱退一時金制度」とは、日本の年金制度に加入した外国労働者が、老齢年金の受給資格期間(10年)を満たないまま帰国する場合に、払い込まれた保険料の一部を返金する制度のことをいいます。
これまで、脱退一時金は、外国労働人の被保険者期間に応じて、3年を上限として支給されていました。
ですが、2019年4月施行の改正出入国管理法において、期間の更新に限度のある在留資格の在留期間の上限が「5年」に改正されたとともに、制度が創設された当時からすると、外国人出国者(日本に3~5年滞在)の割合が増えたことから、制度の見直しが行われました。
今後、脱退一時金は、外国労働人の被保険者期間に応じて、5年を上限として支給されることになります。
(3)被用者保険の早期加入措置(施行日:2022年10月1日)
これまで、厚生年金保険と健康保険については、雇用期間が2ヶ月以内である従業員には適用されませんでした。
2ヶ月以内の雇用契約を繰り返し締結しているような場合は、これらの保険の対象になりますが、初回の雇用契約期間が適用対象から外されていたため、雇用の実態に即していないという問題がありました。
今後は、雇用期間が2ヶ月以内であっても、その期間を超えて雇用される見込みがある場合は、初回の雇用期間から保険の対象に含まれることになります。
(4)日本年金機構の調査権限の整備
日本年金機構は、厚生年金の適用の可能性がある事業所に対して、加入指導を実施することができます。
もっとも、指導を超えて、事業所に対し立入検査や文書の提出命令を行うには、事業所が現に厚生年金の適用を受けていることが必要でした。
そのため、未適用事業所については、指導することまでは可能ですが、法的権限に基づく立入検査などをすることはできませんでした。
これでは、社会保険を適切に適用するための対策として十分ではないため、未適用事業所であっても、適用事業所であると認められる事業所については、法的権限に基づく立入検査をすることができるようになりました。
(5)年金担保貸付事業の廃止(施行日:2022年4月1日)
「年金担保貸付事業」とは、年金受給権を担保として小口の貸付を行う事業のことをいいます。
これまで、年金で生計を立てる者が一時的にお金が必要になったような場合に利用されていましたが、受給した年金が返済に充てられ、高齢者の生活の困窮を招くといったケースが見受けられるようになりました。
年金は、老後の生活を支えるという重要な役割を持っており、十分に保護する必要があるため、2021年度末に新規貸付の受付を終了し、事業が廃止されることになりました。
7 小括

労働者にとってはメリットの大きい年金改革法ですが、事業者にとっては、事務手続きや保険料の負担が増すことになります。
特に、中小企業の中には、新型コロナウイルスの影響により事業の縮小や経営難に陥っているところもあり、負担増に不安な声も出ています。
今回の改正にはいくつかのポイントがあり、これまでは適用されていなかった規制が今後は適用対象として規制を課されることが出てきます。
それぞれにおいて施行日も異なるため、事業者は、これらのポイントを十分に理解したうえで、計画的に自社に導入していくことが必要です。
8 まとめ
これまでの解説をまとめると、以下の通りです。
- 年金改革法の主な改正ポイントは、①パート・アルバイトへ適用される保険適用の拡大、②在職中の年金受給のあり方の見直し、③年金受給開始時期の選択肢の拡大、④確定拠出年金の加入可能要件の見直し、⑤その他の5つである
- 事業者は、①企業規模、②労働時間、③賃金、④勤務時間の4つの条件を満たす場合、被用者保険の適用対象としなければならない
- 在職中の年金受給に関し、①在職定時改定、②在職老齢年金制度の見直しがなされた
- 公的年金の受給開始時期について、繰下げ受給の年齢の上限が75歳まで引き上げられた
- 確定拠出年金(DC)の加入年齢が、企業型DCでは70歳未満、個人型DCでは65歳未満まで引き上げられる
①基礎年金番号通知書への切替え、②脱退一時金制度の見直し、③被用者保険の早期加入措置、④日本年金機構の調査権限の整備、⑤年金担保貸付事業の廃止の5点も改正点である
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。