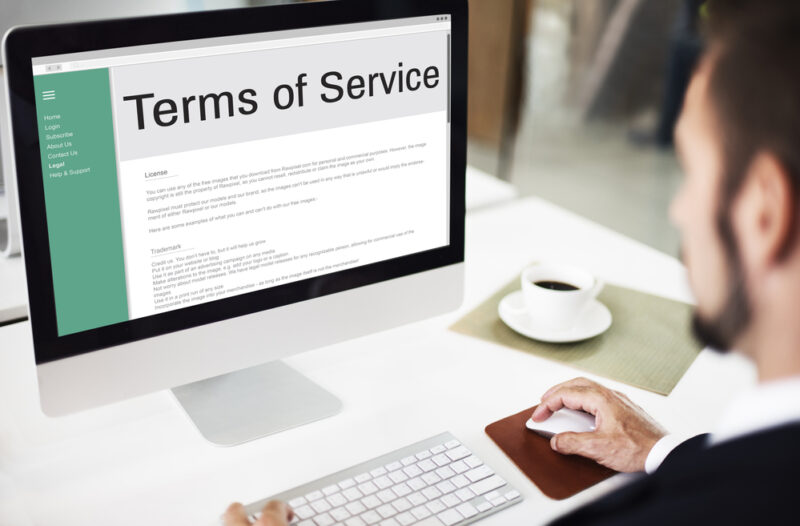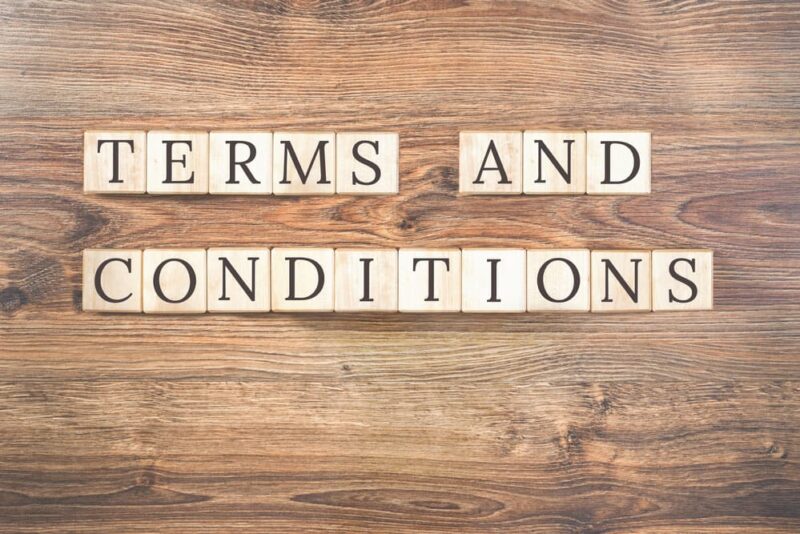プライバシーポリシーが必要となる2つの理由を弁護士が解説!

はじめに
何らかのサービスを開始するにあたっては、利用規約やプライバシーポリシーの作成が必要になってきます。
利用規約については、何となくその必要性が理解できても、なぜプライバシーポリシーが必要なのか、よくわからないという方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は、プライバシーポリシーがなぜ必要なのかということを中心に弁護士がわかりやすく解説します。
この記事を執筆したのは

- 弁護士・中小企業診断士 勝部 泰之
- 注力:知的財産権・著作権/ライセンス、ブロックチェーン、データ・AI法務
GWU Law LL.M.(知的財産法)
事業の成長とリスクを両立する実務寄りの助言に注力しています。 - 詳しいプロフィールはこちら
1 プライバシーポリシーとは
「プライバシーポリシー」とは、個人情報の取扱いについて事業者が採っている方針を文書にしたものをいいます。
多くのWebサービスなどでは、必ずといっていいほど「プライバシーポリシー」というページが存在します。
個人情報は、事業者が提供するサービスの内容によって取扱方法が異なるため、プライバシーポリシーはサービスごとに作成されることが一般的です。
2 なぜプライバシーポリシーは必要?
プライバシーポリシーは、その作成・公表が法律で義務付けられているわけではありません。
にもかかわらず、多くのサービスでは「プライバシーポリシー」のページが設けられています。
これはなぜでしょうか。
理由として挙げられるのは、以下の2点です。
(1)個人情報保護法が定めるルールを履行するため
個人情報保護法は、個人情報取扱事業者を対象に、個人情報の取扱いについてさまざまなルールを設けています。 そのなかには、ホームページなどにおいて公表することが義務付けられている事項もあります。
①通知・公表
事業者は、個人情報を取得する場合には、その利用目的を可能な限り特定したうえで、利用者に通知もしくは公表する必要があります。直接取得時は原則として明示が必要で、例外も限定列挙です(法21条2項、同4項)。「サービス向上」など抽象的すぎる目的は不適切とされます。
「通知」もしくは「公表」となっているため、その都度個別に通知するという運用方法でも問題ありません。
ですが、取得する個人情報の数が多くなればなるほど、個別に通知するという運用方法は現実的ではありません。
そのため、多くの事業者は、プライバシーポリシーに利用目的を記載することで、「利用目的を公表する」という義務を果たしているわけです。
なお、利用目的を変更する場合は、当初目的との関連性が合理的に認められる範囲内に限られます(法17条2項・法21条3項)。
②第三者提供
「第三者提供」とは、事業者が保有する個人データを、外部の他の事業者などに提供することをいいます。
第三者提供は原則、事前の本人同意が必要です(法27条1項)。オプトアウト提供は要配慮個人情報を除き、所定事項の公表等の厳格な要件が必要です(法27条2項)。また、外国にある第三者への提供は原則本人同意又は適切な体制確認が必要です(法28条1項)。第三者提供の記録作成・保存義務もあります(法29条1項)。
この点、「利用目的」の場合と同じことが言えますが、個人情報を第三者に提供する都度、個別に本人から同意を得るという運用方法でも特に問題はありませんが、運用方法としてはあまり現実的ではありません。
そのため、多くの事業者は、以下の事項を定めたプライバシーポリシーについて、本人から同意を得るという方法を採っているのです。
なお、包括同意を得る場合でも、同意は自由意思に基づく具体的・明確な内容であることが必要で、目的外提供には別途同意が必要となり得る点に注意が必要です。
③保有個人データ
「保有個人データ」とは、事業者が開示・訂正等を行う権限を有する個人データをいう(一定の例外除く)と定義されます(法16条4項)。
個人情報取扱事業者は、保有個人データに関して、以下の事項を公表することが義務付けられています。
- 個人情報取扱事業者の氏名・名称
- 利用目的
- 開示請求などの手続
- 苦情の申出先
保有個人データを保有する事業者の多くは、プライバシーポリシーに上記事項を記載する方法で公表義務を果たしているわけです。
※「開示請求などの手続」としてプライバシーポリシーに記載すべき具体的な事項は、「プライバシーポリシーとは?作成時の6つのチェックポイントを解説!」をご覧ください。
(2)プライバシーマーク(Pマーク)の取得
「プライバシーマーク」とは、個人情報の保護体制に対する第三者認証制度のことです。
個人情報などについて適切な取扱いをしていると認められた事業者は、一般社団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)からその旨の認定を受けることができ、「Pマーク」を使用できるようになります。
そして、同協会から認定を受けるためには、プライバシーポリシーがきちんと作成されていることが必要不可欠なのです。
【補足:Pマークは私的な第三者認証制度であり、法定義務ではありません。審査要件はJIPDECの規格・ガイドラインに基づきます。】
Pマークを使用できるようになれば、対外的に個人情報の保護体制をアピールすることができ、利用者の獲得にも繋がります。
3 定期的見直しの重要性
プライバシーポリシーは一度作ったからといって、それで終わりではありません。
一度作った後も、以下のような理由で、定期的に見直すことが大切です。
(1)サービス内容の変化
サービスの内容が変わると、それに伴い、個人情報の利用目的なども変わっていきます。
そのため、プライバシーポリシーとサービス内容の整合性などを定期的に見直し、必要に応じてプライバシーポリシーを変更するといった対応が必要になります。
なお、利用目的の変更は当初目的との関連性が合理的に認められる範囲内に限られ、範囲外に拡張する場合は本人同意が必要です(法17条2項・法21条3項)。
(2)個人情報保護法の改正
個人情報保護法が改正されると、それに伴い、プライバシーポリシーも変更しなければならなくなることがあります。例として、令和4年改正では保有個人データの定義変更(6か月除外削除)や第三者提供・越境移転の説明義務等が強化されました(法16条4項、法27条~28条、法32条等)。
そのため、法改正の動向には日頃から注意しておく必要があります。
4 まとめ
個人情報に係る利用目的や利用方法は、事業内容によっても大きく左右されます。
事業者は、インターネット上に転がっている雛形を流用するのではなく、自社の事業に適したオリジナルのプライバシーポリシーを作成することが大切です。
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。