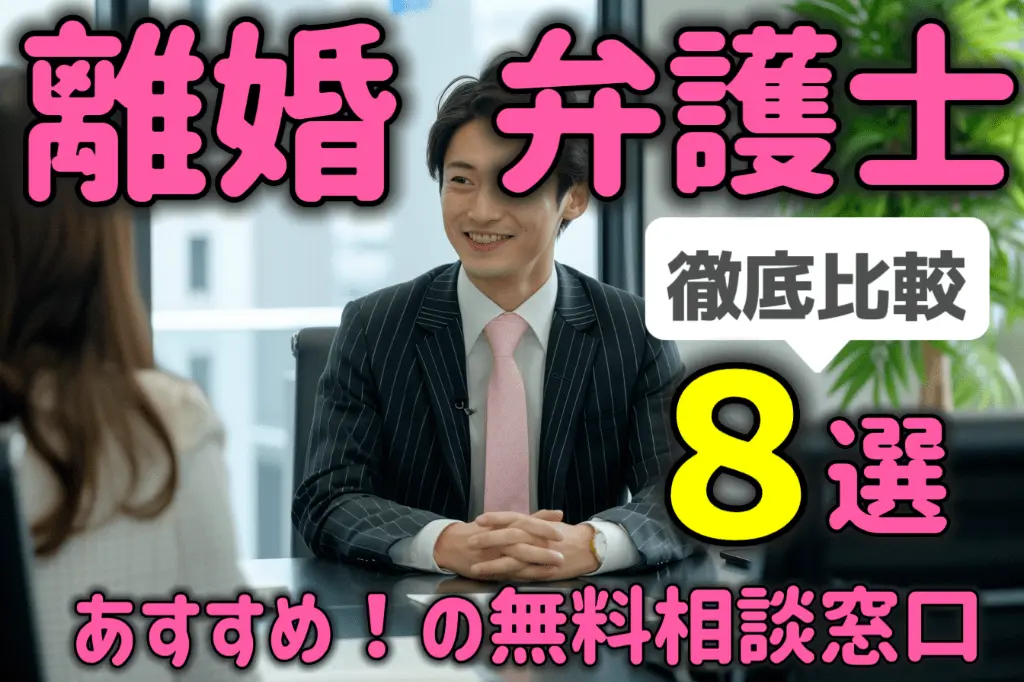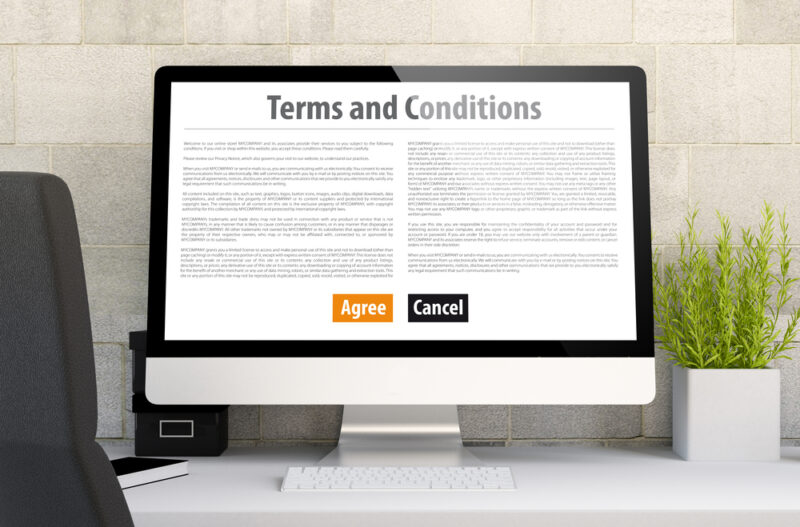利用規約を作成する際に押さえておくべき6つの法律を弁護士が解説!

はじめに
ユーザー(消費者)に何らかのサービスを提供する場合、「利用規約」を公開している事業者が多いといえます。利用規約は、法律に則って作成する必要がありますが、そこにどのような法律が関わってくるかをご存知でしょうか。
これについては、2020年4月から施行された改正民法をはじめ、業種に応じて個別に注意しなければならない法律もあります。
これらの法律をきちんと理解していないと、条項が無効という扱いを受けたり、ユーザーとのトラブルを招く要因にもなります。
この記事では、利用規約を作る際に注意すべき法律を、弁護士がピックアップして解説します。
この記事を執筆したのは

- 弁護士・中小企業診断士 勝部 泰之
- 注力:知的財産権・著作権/ライセンス、ブロックチェーン、データ・AI法務
GWU Law LL.M.(知的財産法)
事業の成長とリスクを両立する実務寄りの助言に注力しています。 - 詳しいプロフィールはこちら
1 利用規約に関わる法律は?
利用規約作成にあたっては、どのような法律に留意すべきなのでしょうか。自社サービスの内容にもよりますが、中心となるのは以下の6つの法律です。
- 改正民法(定型約款)
- 消費者契約法
- 個人情報保護法
- 特別商取引法
- 資金決済法
- 著作権法
2 改正民法(定型約款)
2020年4月から、改正民法が施行され、これまで使われていた「約款(利用規約)」のルールが変更されました。
ここでは下記の通り、変更後のルールである「定型約款」と、それに伴う利用規約作成上の注意点を解説します。
- 定型約款とは
- 利用規約を作成する際の注意点
- 変更の方法
(1)定型約款とは
「定型約款」とは、次の3つの条件をすべて満たすものを言います。
- 特定の者が、不特定多数の者を相手方として行う取引である
- その内容の全部または一部が画一的であることが、その双方にとって合理的なものである(「定型取引」という)
- 定型取引で契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体
たとえば、身近なところで定型約款にあたるもの・あたらないものは、下記のようになります。
- 定型約款にあたるもの⇒Webサイトやアプリの利用規約、公共交通機関の運送約款など
- 定型約款にあたらないもの⇒事業者間の取引で一方が準備した契約書の雛形、労働契約の雛形など
Webサイトやアプリの利用規約の多くは、不特定多数の者を相手方として行う定型取引(条件1、2)であるため、定型約款に当たることがほとんどです。
このほか、公共交通機関の運送約款なども、不特定多数の者を対象として(条件1)、同一条件での利用に同意を求めるもの(定型取引 条件2)です。
一方、事業者同士の取引や労働契約は、特定の相手に合わせて金額や条件などを個別に定めて締結するのが一般的であるため、不特定多数の者を相手方として行う取引ではありません。
また、このような場合、契約の内容が画一的であることが契約当事者にとって合理的なものであるともいえません。
そのため、これらの雛形は定型約款にはあたりません。
(2)利用規約を作成する際の注意点
利用規約が定型約款にあたる場合、その利用規約の中で、ユーザーに一方的に不利益を負わせるような条項(不利益条項)を入れることはできません。
具体的には、下記のような内容を含むことによりユーザーの利益を一方的に害することとなる条項は、ユーザーにおいて合意しなかったものとみなされます。
- ユーザーの権利を制限するもの
- ユーザーの義務を加重するもの
たとえば、
- 解約の際に高額な違約金を請求する
- 中途解約による返金を一切認めない
- ユーザーが事業者に損害賠償請求をすることを認めない、または事業者の賠償額が不当に低い
などの内容を含む条項は、ユーザーの利益を一方的に害するものとして、合意がなかったものとみなされる可能性があります。
また、ユーザーの視点でサービス内容を見たとき、通常では予見できない内容、一般的に含まれるはずのない条項(不意打ち条項)を入れることもできません。
たとえば、
- 全く関係のないサービスや商品を抱き合わせで販売することとする
などの条項がこれに当たります。
このような不意打ち条項も、不利益条項に当たりますので、ユーザーが形式上合意をしたとしても、この部分については合意をしなかったものとみなされます。
(3)変更の方法
一般的な契約で、その内容に変更が生じた場合には、相手方の承諾を得た上で、変更後の内容について双方が合意をしなければなりません。
ですが、利用規約(定型約款)の場合はユーザーが不特定多数であるため、変更に対する合意を個別に得ることは現実的ではありません。
この点、民法の改正により新たに加わった定型約款のルールでは、一定の条件を満たせば、ユーザー全員に個別で変更の承諾を得なくても、利用規約の変更を行うことができるようになりました。
具体的には、下記の1を満たすか、もしくは2~5のすべてを満たす場合です。
- 変更が、ユーザーの一般の利益に適合するor
- 変更が、契約の目的に反するものではない
- 変更に必要性があり、変更内容に相当性がある
- 「規約を変更することがある」という定め(変更条項)の有無やその内容などから変更に合理性がある
以上の条件を満たす場合、事業者は、変更後の利用規約(定型約款)についてユーザーが合意したものとみなし、個別に合意を得ることなく利用規約を変更することができます。
また、事業者は、利用規約を変更する際には、
- いつから効力が発生するか
- 変更をする旨
- 変更後の内容
を、インターネット(電子メールや公式サイトへの掲載)などを利用して、ユーザーに周知しなければなりません。
上記2~4を満たす形での変更を行う場合、効力の発生時期までにユーザーに周知をしない限り効力は発生しませんので、注意が必要です。
※定型約款について詳しく知りたい方は、「民法改正で利用規約・約款の何が変わる?定型約款3つのルールを解説」の記事でも解説をしていますので、参考にしてみてください。
3 消費者契約法
「消費者契約法」は、一般消費者と事業者が結ぶ契約において、両者における情報や交渉力の質・量の格差を考慮し、弱者の立場になりやすい消費者を保護するための法律です。
そして、一般消費者と事業者が結ぶ契約ともいえる利用規約についても、消費者契約法の適用を受けることになります。
消費者契約法では、以上のような趣旨から、たとえば、以下のようなルールが定められています。
- 消費者が誤認や困惑により申し込んだ契約や承諾の意思表示を取り消すことができる
- 事業者の損害賠償の責任を免除したり、消費者の利益を不当に害する条項の全部または一部を無効とする
商品やサービスを提供する事業者は、個人である消費者よりも質・量ともに多くの情報を持ち、資金力もあります。
そのため、消費者の無知に乗じるなどして、事業者が消費者を陥れたり、不利益に扱う可能性があります。
消費者契約法は、このような事態を招くことなく、消費者が安心して契約をできるようにさまざまなルールを定めています。
消費者契約法との関係でいうと、利用規約で条項を定める際のポイントは、以下の4つになります。
- 消費者にとってわかりやすい文章や内容になるよう配慮する
- 免責規定
- 制裁措置
- 損害賠償の金額
(1)消費者にとってわかりやすい文章や内容になるよう配慮する
消費者の権利義務や、その他の契約内容の解釈に不明瞭な点がないよう、わかりやすい文章や内容になるよう配慮しなければなりません。
(2)免責規定
「免責規定」とは、サービスを利用するうえで発生したトラブルなどについて、損害賠償責任を制限・免除することを定めた規定です。
事業者側に債務不履行がある場合に、事業者の損害賠償責任の全部または一部を免除したり、ユーザーが責任を負うような条項は、消費者契約法により無効になります。
また、事業者が不法行為によりユーザーに損害を与えた場合に、その責任の有無や限度を事業者が判断するような条項も無効です。
(3)制裁措置
「制裁措置」とは、ユーザーが規約に定めた禁止事項に違反した際、どのような処分をするかを決めた条項です。会員制サイトのアカウント停止などがこれに当たります。
違反行為に対するデメリット(制裁措置)をあらかじめ定めておくことで、ユーザーによる違反行為の抑止効果を狙うことができ、また、違反行為があった場合に、事業者側は規約に基づいて対処することができます。
ですが、ユーザーに一方的に不利となる制裁措置は、消費者契約法により無効となる可能性があるため、注意が必要です。
(4)損害賠償の金額
利用規約において、契約解除にあたり、ユーザーが事業者に支払う損害賠償額や違約金の額をあらかじめ定めておくことがあります。これらを規約で明らかにしておくことによって、ユーザーもあらかじめ金額を把握することができ、サービスを安心して使うことができます。
もっとも、不当に高額な金額を設定してしまうと、不当条項として無効になる可能性がありますので、注意が必要です。
4 個人情報保護法
「個人情報保護法」は、「個人情報」を取り扱う事業者が、その取り扱いに関して守らなければならないルールを定めた法律です。
(1)個人情報とは
個人情報は、適正に利用することにより、新たに便利なサービスを創出することができますが、その有用性とともに、個人の利益や権利も守る必要があります。
ここでいう「個人情報」とは、生きている個人に関する情報であり、下記のいずれかの条件を満たすものです。
- 情報に含まれる名前や生年月日などにより特定の個人を識別できるもの
- 他の情報と簡単に照合することができ、それによって特定の個人を識別できるもの
- 個人識別符号が含まれるもの
たとえば、サイトの会員登録で入力した氏名や生年月日は1に当たります。
また、「社員番号+所属企業」、「苗字のみ+住所+勤務先」といったように、1つの情報では特定の個人を識別できなくても、簡単に照合できる他の情報と組み合わせることで、特定の個人を識別することが可能になる情報は2にあたります。
3にある「個人識別符号」とは、生体識別(指紋、DNA、瞳の虹彩など)、公的証明書の番号(パスポート、運転免許、年金、マイナンバーなどの番号)などをいいます。
(2)プライバシーポリシーとの関係
「プライバシーポリシー」とは、個人情報の取り扱い方針を定めたものです。
現在では、サービス全体のルールを定めた利用規約とは別に「プライバシーポリシー」を定めることが一般的です。
プライバシーポリシーでは、事業者が取得した個人情報をどのように利用するかを明示しなければなりません。
たとえば、第三者に個人情報を提供する場合などは、原則として、
- 第三者への提供を利用目的とすること
- 提供方法
- 提供する個人データの項目
などをプライバシーポリシーに記載し、ユーザーに同意させることになります。
個人情報の漏えいは、近年大きな問題となっています。事業者の社会的信用に大きく関わる問題でもあるため、個人情報の取り扱いには最大限の注意を払う必要があります。
※プライバシーポリシーについては「プライバシーポリシーとは?作成時の6つのチェックポイントを解説!」を参照ください。
※個人情報保護法の罰則規定などについては「個人情報を漏洩した場合の罰則と損害賠償の相場は?2つの視点で解説」の記事を参考にしてみてください。
5 特定商取引法
「特定商取引法」は、通信販売や訪問販売といった悪質な勧誘から消費者を守るために、事業者に課されるルールを定めた法律です。
特定商取引法では、事業者による不意打ちやだまし打ちなどでトラブルが生じやすい下記7つの取引を規制対象としています。
- 訪問販売
- 通信販売
- 電話勧誘販売
- 連鎖取引販売(マルチ商法)
- 特定継続的役務提供(エステや語学教室など)
- 業務提供誘引販売取引(商材や教材を購入する副業紹介)
- 訪問購入
利用規約との関係で特定商取引法が問題となるのは、主に、以下の2点です。
- ⅰ) 通信販売のメール
- ⅱ) クーリング・オフ
ⅰ) 通信販売のメール
「通信販売」とは、新聞・雑誌やWebサイトなどで商品などを広告し、郵便やネットといった通信手段により消費者が商品などを申し込む形式の取引です。
この場合、消費者の同意を得ることなく、電子メールで広告やメルマガを送信することはできません。
このようなメールを送信することをサービス内で想定しているときは、その内容を利用規約に盛り込み、ユーザーの同意を得ておくことが必要になります。
※このほかにも、電子メールの送信については「メルマガを規制する法律は?2つの法律のポイントをわかりやすく解説」の記事で解説していますので、ご参照ください。
ⅱ) クーリング・オフ
「クーリング・オフ」とは、契約をした後一定期間に限り、無条件でその契約を解除することを可能にする制度です。
クーリング・オフの対象となるのは、原則として、消費者トラブルが特に多いとされる上記の取引ですが、これらのうち、通信販売はクーリング・オフの対象とはなりません。
それ以外の取引をサービスとして展開していくにあたり、利用規約を作成する際には、
クーリング・オフが適用される旨を明示する必要があります。
6 資金決済法
「資金決済法」は、サイトやアプリ、サービス内における「金銭」の取り扱いや決済に関するルールなどが定められた法律です。
具体的には、資金決済法は、主に、
- 暗号資産(仮想通貨)
- 前払式支払手段
- 資金移動業
の3つについてさまざまなルールを定めています。このうち利用規約に関わるのは、「前払式支払手段」です。
「前払式支払手段」とは、ゲームやサイト内などでユーザーが事前にお金を払って、購入するポイントやコインなどのことをいいます。
前払式支払手段を発行する事業者は、発行保証金の供託を義務付けられることになりますが、「発行保証金の供託」を回避するためには、利用規約においてエクスパイア条項を盛り込んでおく必要があります。
「エクスパイア条項」とは、前払式支払手段の有効期限を定めた条項です。
前払式支払手段を発行するサービスで、負担の重い供託義務を回避したい事業者は、前払式支払手段に有効期限を定めた「エクスパイア条項」を利用規約に入れておきましょう。
前払式支払手段は、その有効期限を6ケ月以内とすることで、供託義務の適用を免れることができます。
そのためには、前払式支払手段にあたるコインやポイントの有効期限を6ケ月(180日)とすることを利用規約で定めておくことが必要です。
※エクスパイア条項については、「資金決済法にいう「6ヶ月」とは?前払式支払手段の有効期限を解説!」の記事で詳細を解説しています。
7 著作権法
「著作権法」は、ユーザーが作成したコンテンツ(著作物)に発生する著作権などを保護するための法律です。
ユーザーが作成した写真やイラスト、動画、文章といったコンテンツを「ユーザー作成コンテンツ(UGC、User Generated Contents)」といい、これは「著作物」にあたります。
このような著作物にあたるコンテンツをユーザーが作成した時点で、ユーザーには「著作権」が発生します。
著作権が発生している著作物は、原則として、著作権者の許諾がなければ他人が勝手に利用したり、改変したりすることはできません。
このような場合に、著作権者に無断で著作物を利用してしまうと、著作権侵害にあたります。
そのため、自社が提供するサービスの中でユーザーの著作物を利用する場合には、著作権の所在を、利用規約で定めておくことが必要です。
たとえば、下記のようなコンテンツを扱うサービスの場合は、著作権に関するルールを利用規約に入れておくことが必要でしょう。
- SNS、掲示板、動画や画像の投稿サイト
- ブログサービス
- カスタマーレビューを投稿できる通販サイト
これらのサービスでは、ユーザーが投稿した動画や画像などの著作権の所在や利用方法について、あらかじめ利用規約で明確にしておかないと、ユーザーとのトラブル発生の元になり、サービス運営に支障が出る可能性があります。
たとえば、著作権を譲渡してもらう方法やライセンス形式で著作物の利用を許諾してもらう方法、そして、必要最低限の改変のみを承諾する方法などを規約に入れることが考えられます。
※詳しくは、「利用規約の注意点は?もつべき視点2つと作成方法のポイントを解説!」の記事でも解説しています。
8 小括
利用規約を作る際には、さまざまな法律が関わることになり、事業者が提供するサービスによって、気にするべき法律も異なります。
また、消費者保護の観点も忘れてはなりません。規約を作成する際には、事業者目線に寄っていないか、消費者に過度な不利益を強いていないかなどをチェックするようにしましょう。
9 まとめ
これまでの解説をまとめると、以下の通りです。
- 利用規約に関わる法律で、主なものは①改正民法(定型約款)、②消費者契約法、③個人情報保護法、④特別商取引法、⑤資金決済法、⑥著作権法の6つがある
- 改正民法では、不特定多数のユーザーに同意を求める形式である「定型約款」が導入された
- 消費者契約法は消費者保護のための法律で、事業者と消費者の情報や交渉力の質・量の格差を考慮したルールが定められている
- 個人情報を取り扱う「個人情報取扱事業者」は、個人情報保護法の規制を受ける
- 特定商取引法では、通信販売のメール広告を送信する際にユーザーの同意を得ていることが条件となっているほか、クーリング・オフや返品についても、利用規約に盛り込むことによりトラブル防止になる
- ゲーム内課金やポイントなど、前払式支払手段を発行する場合は、資金決済法で規制される
- 前払式支払手段発行事業者に課される供託義務は、エクスパイア条項を設けるなどして、前払式支払手段に6ヶ月の有効期限を設けることが必要である
- UGCなどを扱うサービスの場合、利用規約でコンテンツの著作権の帰属や利用の許諾について定めておく必要がある
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。