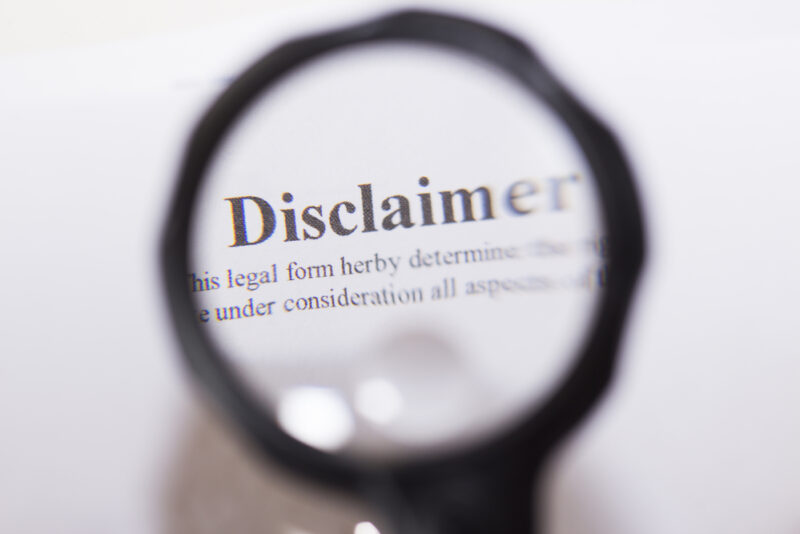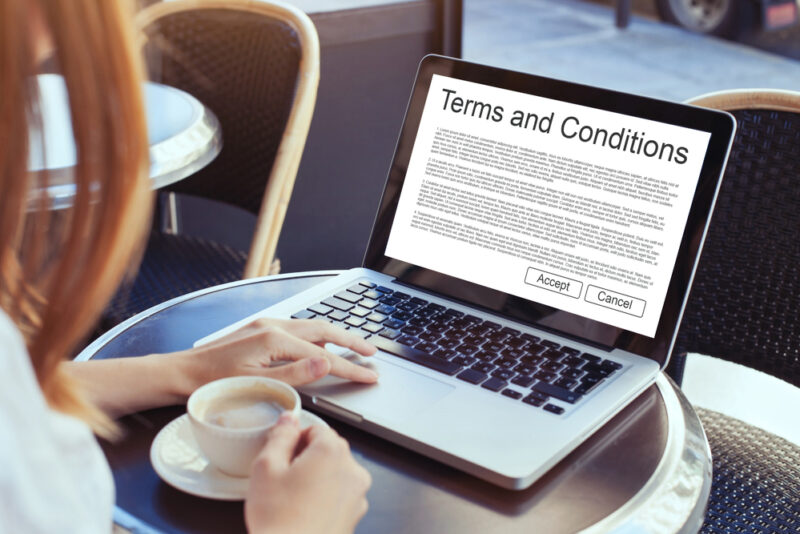利用規約の注意点は?もつべき視点2つと作成方法のポイントを解説!

はじめに
サービスの提供を開始したい場合、必ず「利用規約」を設ける必要があります。
「難しそうだし、弁護士に作成を依頼したほうがいいかな」と思う方は、もちろん法律の専門家である弁護士へ依頼しても問題ありません。
ただ、少しでもコストを下げたいときは、自分の手で利用規約を作成してみることもできます。
しかし、世の中にある利用規約を見てみても、何やら難しい言葉が羅列されていて、よくわからない……という人もいるはずです。
そこでこの記事では、利用規約を作成するうえで、特に注意しておきたいポイントを徹底的に解説していきます。作成の参考にしてみてください。
なお、基本的な利用規約の作成方法については、「【ひな形付】web・アプリ利用規約の書き方と9つのポイントを解説」で解説しています。
この記事を執筆したのは

- 弁護士・中小企業診断士 勝部 泰之
- 注力:知的財産権・著作権/ライセンス、ブロックチェーン、データ・AI法務
GWU Law LL.M.(知的財産法)
事業の成長とリスクを両立する実務寄りの助言に注力しています。 - 詳しいプロフィールはこちら
1 利用規約を作る場合の視点

「利用規約」とは、サービスやアプリ、Webサイト等における、利用上のルールのことです。何らかのサービスを運営するときは、必ず作成し、サイト上に掲載する必要があります。
利用規約を作成するときは、基本的に、「自社の利益を最大化する」という意識で内容を決定していくものですが、無用なトラブルを避けるために、以下の2つの視点を大切にしておきましょう。
- 自社のリスクを下げつつ有利な内容にする
- ユーザーに過度な不利益を及ぼさない
(1)自社のリスクを下げつつ有利な内容にする
まず、自社に降りかかるリスクはできる限り避けるルールにすることが大切です。
リスクとしては、提供しているサービスの利用者とトラブルが起きたときの損害賠償の有無や程度、利用者間で起きたトラブルにどこまで介入するのか、などが挙げられます。
こうした想定されるトラブルに関し、自社に有利なルールになるよう意識して利用規約を作成してみてください。
(2)ユーザーに過度な不利益を及ぼさない
もちろん、自社のリスクを下げるといっても、「どのようなときでも、会社側はすべての責任を負わない」としてしまうと、ユーザー側が著しく不利になってしまうため、ユーザーからの反発を招く可能性が高くなってしまうので注意が必要です。
また、事業者側が一方的に有利な条項は、「無効」になってしまいます。
このようなことを踏まえて、ユーザーに過度な不利益を及ぼさないよう、内容を調整する必要があります。
これらの視点を無視して、自社の利益やリスク低減を意識しすぎた利用規約にすると、逆に自社にとって不利益なトラブルが起きてしまうことがあります。
たとえば、画像投稿サイトの利用規約に「投稿された画像の権利はすべて、運営会社へ無償譲渡する」という条項が書かれていたとしましょう。
この場合、画像を投稿したユーザーは、もうその画像を自由に使用することができません。こうした条項は、「過度にユーザーの権利を侵害している」と判断され、インターネット上で炎上してしまう可能性が高いといえます。
実際、2014年5月19日に発表された、オリジナルTシャツ作成アプリ「UTime!」(ユニクロ)では、利用規約に「Tシャツを作成するために使用した画像に関するすべての権利を会社へ無償譲渡する」という内容が書かれていたため、炎上しました。
こうしたトラブルに巻き込まれないよう、利用規約を作成する際は、「会社側」「ユーザー側」双方の立場や視点を尊重し、バランスを取りながら内容を定めていきましょう。
2 汎用的な利用規約の注意点

利用規約には、多くのビジネスモデルにおいて、共通して策定するべき基本的な条項・内容が存在しています。そうした基本の条項の中で、特に注意しておくべきポイント5つをピックアップしました。
- 禁止事項(ペナルティ)
- 免責規定
- 著作権
- コイン・ポイントの取り扱い
- 個人情報の取り扱い
それぞれ見ていきましょう。
(1)注意点①:禁止事項(ペナルティ)
「禁止事項」とは、「このようなことはしてはいけない」というルールを定める条項です。ただ、ざっくりと禁止事項を書くのではなく、具体的な内容で禁止事項を列挙する必要があります。
たとえば、「当社に不利益を及ぼさないこと」という内容だけを禁止事項として書いていた場合、
- どのような行為を行うことなのか
- 不利益とはどのようなものなのか
といった具体性にかけた内容になっています。これだけでは、ユーザーも理解しづらく、個人個人の解釈によって、あいまいな禁止基準が生まれてしまうかもしれません。
そのため、具体的に禁止事項を記入し、すべてのユーザーがまったく同じ内容を理解できるよう、明確にしておくことが大切です。
その際、以下のような形で禁止事項を分類しておくと読みやすく、理解されやすくなります。
- 法令に違反する行為または犯罪に関連する行為
- 公序良俗に反する行為
- 本サービスを通じ、以下に該当または該当すると当社が判断する情報を投稿する行為
- 他人に不快感を与える情報が含まれるもの
- 第三者の個人情報が含まれるもの
同時に、こういった禁止事項に違反した場合の対処(ペナルティ)も記載しましょう。
ペナルティを記載しておくことで、会社側は違反者に対して迅速に対応でき、また、ユーザー側も違反行為をしたときのデメリットを理解でき、違反行為への抑止力としての機能も期待できます。
ペナルティとして、以下のような内容が考えられます。
- 違反している画像データをサイト上から削除する
- 一定期間の利用停止を設ける
- アカウントを削除する
上記のように、具体的で段階的なペナルティを設けるとよいでしょう。自社のサービス内容と照らし合わせ、最適なペナルティを策定してください。
(2)注意点②:免責規定
「免責規定」とは、サービスを利用することで発生しうる何かしらの損害賠償責任を制限・免除するためのルールのことです。
ユーザーと会社側、それぞれどこまで責任を負うのか、どういったケースだと責任を負わないのかを明記します。
できるだけ会社側に責任が来ないようにしたいものですが、以下のような、会社の免責のみを優先した条項は、成り立ちません。
- 会社に対する損害賠償責任をすべて免除する
- 会社側に故意・重過失がある場合であっても、ユーザーが責任を負う
このように、ユーザー側に著しく不利な条項は、「消費者契約法」や「定型約款」によって無効となります。
「消費者契約法」は、消費者が何かしらの契約を結ぶ際、一方的に不利な契約を締結させられないよう消費者側の利益を守る法律です。
そのため、ユーザーに一方的に不利となるような条項は、消費者契約法により無効となります。
「定型約款」とは、2020年4月1日から施行される改正民法によって規定された利用規約の新ルールです。以下の3つすべてにあてはまっていれば、定型約款として扱われます。基本的に、オンラインサービスの利用規約は定型約款にあたると考えていいでしょう。
- ある特定の者が不特定多数の者を相手方とする取引であること
- 内容の全部または一部が画一的であることが当事者双方にとって合理的であること
- 契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体であること
定型約款を規制するルールの1つとして、「ユーザーの不利益条項が含まれていないこと」が含まれているため、ユーザーにとって著しく不当な条項は無効となります。
こうしたことから、免責規定を設けるときは、ユーザーと会社のバランスを鑑みて、一方的にユーザーに不利とならないように注意することが大切です。
また、「このケースは想定されていないから、会社にも損害賠償請求ができる」といったケースに陥らないよう、考えうるトラブルを書き出し、免責規定に記載するか否か、よく検討しておきましょう。
※定型約款について詳しく知りたい方は、「民法改正で利用規約・約款の何が変わる?定型約款3つのルールを解説」をご覧ください。
(3)注意点③:著作権
「著作権」とは、何かしらの作品(コンテンツ)を生み出した著作者に発生する権利のことで、著作物の無断利用や転載などから著作者を法的に守ってくれます。
特に、ユーザーが何かしらのデータを投稿するサイトを運営する場合、「著作権」の所在を明確にしておく必要があるので、注意してください。
著作権に関する利用規約では、主に3パターンが考えられます。
- 譲渡型
- ライセンス型
- 必要最低限の改変
それぞれ、どのような内容なのか、見ていきましょう。
①譲渡型
「譲渡型」とは、ユーザーがコンテンツを投稿した時点で、コンテンツの著作権がすべて運営会社に譲渡されるパターンです。
つまり、運営会社は自由にそのコンテンツを利用することができ、3パターンの中で最もメリットがある方法といえます。
とはいえ、ユーザーからすれば、自分が作成したコンテンツを今後使用できなくなってしまうため、最も不利なパターンといえます。
このように、譲渡型はユーザーに一方的に不利なパターンであるため、第一章でご紹介した「UTime!」(ユニクロ)のように炎上するリスクが高く、また、サービスの利用そのものを敬遠される可能性が高いため、このパターンは避けたほうが無難でしょう。
②ライセンス型
「ライセンス型」とは、著作権そのものはユーザーが保有し、運営会社に対して(ほとんどの場合、無料で)使用許諾を与えるパターンです。
ライセンス型では、運営会社はコンテンツを自由に使用でき、ユーザーは投稿サービスに縛られることなく、自身のコンテンツを自由に利用できます。
もちろん、ユーザーとしてはコンテンツを投稿するたびに「ライセンスします」という意思はないでしょう。ただ譲渡するパターンよりも「座りがよい」ということで、ユーザーから運営会社に「無料でライセンスします」という規定にすることが実務では多いのです。
このように、ライセンス型は、運営会社とユーザーの双方にメリットがあり、バランスのとれた方法といえるでしょう。
③必要最低限の改変
「必要最低限の改変」とは、コンテンツに関する著作権はユーザーにあることを前提とし、サイト運営のために必要最低限な修正を運営会社が行うことを認めるパターンです。
たとえば、ブログを一覧表示するときに、一見して内容がわかるよう冒頭部分を抜粋するなど、サービスを運営するうえで必要最低限な修正・引用のみを行うことができます。
反対に、運営会社はこの限度を超えてコンテンツをいじることはできません。
つまり、運営会社がコンテンツを自由に使うことはできないため、ユーザーにとっては最も有利な方法といえるでしょう。
このように、利用規約で著作権に関する定めを置く場合には、自社のサービスにとって、どのパターンが最適なのかを吟味し、利用規約に記載してください。
また、利用規約の作成方法にも注意が必要です。
ゼロから利用規約を作成する際、類似業種・サービスの企業がどのような利用規約を設けているのか、参考にする人も多いでしょう。
その際、サービスが類似しているからといって、すべてをコピペしてしまうと、著作権侵害で訴えられてしまう可能性があります。
実際、利用規約を流用した企業が訴えられ、賠償金を支払ったケースもあり、安易なコピペはトラブルの元です。
(4)注意点④:コイン・ポイントの取り扱い
課金制のゲームアプリなどは、アイテムを入手するためにゲーム内コインやポイントを購入する形式を取りますが、そのコインやポイントの取り扱いには、特に注意が必要です。
ゲーム内コイン等は、事前にお金を支払って購入する「前払式支払手段」に相当し、資金決済法の規制対象となります。
「資金決済法」とは、商品券などの金券やSuicaといった電子マネーなどの取り扱いついてルールを定めた法律です。
また、「前払式支払手段」とは、以下の条件すべてに該当するもののことをいいます。
- 金額や物品・サービスの数量(個数等)が、記載・記録されていること
- 金額や数量に応ずる対価が支払われることにより発行されていること
- 商品購入などに利用できること
ゲーム内で使うコインやポイントが前払式支払手段にあたる場合、毎年3月末か9月末の時点で、未使用残高が1,000万円を超えていると、半額以上のお金を最寄りの供託所に預けなくてはなりません。
たとえば、10コイン100円で購入できるゲーム内コインの場合、3月末か9月末に1万コイン(1000万円分)が使われずにシステム内に残っていると、最低500万円を供託所に供託する義務(供託義務)があるのです。
とはいえ、現金で500万円以上を供託すると、スタートアップやベンチャー企業の場合、資金繰りが厳しくなってしまうケースもあるでしょう。
この点、供託義務を負わずにすむ方法として、前払式支払手段に有効期限を設ける方法があります。供託義務が発生する前払式支払手段は、有効期限が発行日から6ヶ月を超えているものとされています。
つまり、6ヶ月以内に有効期限が切れれば、前払式支払手段に該当するものの、規制対象から除外されるため、供託する必要はありません。
サービスが軌道に乗ってから、莫大な供託金を請求されるようなことが起こらないよう、必ず、利用規約にコインの有効期限を明記し、供託義務を回避しましょう。
ただし、App Storeにリリースするiosアプリの場合、「App Store Reviewガイドライン」の規定により、コインに有効期限を設けることができません。
そのため、
- 無料配布コインと有料購入コインを分けて管理し、有料購入コインが先に消費されるようにシステムを設定する
- 有料コインの消費を促すイベントを積極的に開催する
といった対応を行う必要があります。
アプリ内課金について、詳しく知りたい方は、「アプリ内課金を導入する際に知りたい!資金決済法4つのポイントとは」を参考にしてください。
(5)注意点⑤:個人情報の取り扱い
個人情報の取り扱いについては、利用規約とは別に「プライバシーポリシー」を設けましょう。
「プライバシーポリシー」とは、サービスを利用するため・利用している中で会社側が取得するユーザーの本名などの個人情報や利用履歴・閲覧履歴などのプライベートな情報の取り扱い方針についてまとめたものです。
サイトメニューが書かれているサイト下部などにページリンクが置かれていることがほとんどで、取得した情報を何に利用するのか、第三者に提供するのか、どのように管理するのか、などが明記されています。
これは、「個人情報保護法」に「事業者が個人情報を取得した場合は、あらかじめ利用目的を公表している場合を除き、速やかに、利用目的を本人に通知または公表しなければならない」というルールがあるためです。
つまり、あらかじめプライバシーポリシーを公表しておけば、個人情報を取得するたびに利用目的を通知する必要がないので、ほとんどのサイトでプライバシーポリシーをあらかじめ掲載しています。
この場合、利用規約には、「個人情報および利用者情報については、別途に定める『プライバシーポリシー』に基づき、適切に取り扱う」などと記載することがほとんどです。
そのような記載方法を採る理由として、ユーザーの「同意」が関係しています。
後で詳しく解説しますが、利用規約はユーザーの同意を得る必要があり、プライバシーポリシーでも同様に、ユーザーの同意を得なければなりません。
何度もユーザーに「同意」という作業をしてもらうより、利用規約の中にハイパーリンク付きでプライバシーポリシーを織り交ぜるなどして、一度の作業で両方に対して同意をしてもらう方が、ユーザーの負担が少なく、また、途中で離脱されにくいため、このような記載方法を採っている企業が多いのです。
※プライバシーポリシーの作成方法については、「プライバシーポリシーとは?作成時の6つのチェックポイントを解説!で詳しく解説しています。参考にしてください。
3 ビジネスモデルごとの利用規約の注意点

利用規約を作成するときは、これまで見てきた基本条項に加えて、ビジネスモデルごとに入れておくべき条項があります。
以下の4つのビジネスモデルについて、必要な条項・内容を見ていきましょう。
- CtoCプラットフォーム
- ユーザー投稿型メディアサイト
- 課金アプリ
- コンテンツ提供サイト
(1)CtoCプラットフォーム
「メルカリ」や「ヤフオク」に代表される、ユーザー間で取引が行われるプラットフォームを運営するビジネスのケースです。
①ユーザー間の取引ルール
取引をする際の手順やルールを明確に記載してください。
たとえば、
- 代金のやり取りは、プラットフォームが指示している方法で行うこと
- 架空の商品を掲載しないこと
- 取り扱いに免許が必要なものを販売しないこと
- 虚偽の説明を行わないこと
など、考えうるトラブルを回避するルールを明記しておきましょう。
また、「盗難品」「偽ブランド品」など、出品を禁止する商品一覧なども設けておいてください。
そして、これらのルールに違反した場合のペナルティも併せて書いておきましょう。具体的には、
- 一定期間の出品を停止する
- 購入を含め、すべてのサービス利用を一定期間停止する
- アカウントを削除する
などが考えられます。
②マネタイズ・課金方法
どのように収益を上げるのか検討してください。
具体的には、
- 仲介手数料を取る
- サイトに広告を掲載する
などの方法が考えられます。
たとえば、個人間売買のプラットフォームサイトで仲介手数料を取る場合、売り手側と買い手側、どちらに、どれぐらいの仲介手数料を負担させるのかを記載しましょう。
また、ユーザー間のお金と商品のやり取りにおいて、以下のようなフローでお金を預かる「エスクローサービス」を行う場合、「資金移動業者」として登録する必要があります。
-
- 運営会社が一時的に、購入者から代金を預かる
↓
-
- 購入者から入金があったことを出品者へ伝える
↓
-
- 出品者が商品を発送する
↓
- 購入者が商品を受け取ったら、預かっていた代金を出品者に渡す
※エスクローサービスや資金移動業者について、詳しくは、「3分でわかる!ECサイトでエスクローを導入する際の法的問題とは?」で解説しているので参考にしてください。
③代金未払いや商品不具合などの場合の責任
CtoCプラットフォームでは、「代金が支払われない」「届いた商品に不具合があった」などのユーザー間トラブルが起こることが想定されます。
ユーザー間のトラブルではありますが、運営会社は取引の場を提供しているため、「運営会社にも何かしらの責任があるのではないか」と思うユーザーもいるでしょう。
こうしたトラブルに対して、運営会社はどこまで責任を負う必要があるのでしょうか?
たとえば、CtoCプラットフォームを通して、AさんがBさんから商品を購入したケースにおいて、届いた商品に不具合(=瑕疵)があった場合、AさんはBさんに対して、契約を解除したり、損害賠償を請求することができます。
このように、個人間売買などにおいて、Bさん(売主)がAさん(買主)に対して負う責任のことを「瑕疵担保責任」といいます。
しかし、売買がCtoCプラットフォームを通す分、Bさんからすると、プラットフォームから商品を購入しているようにも見えるため、プラットフォームが瑕疵担保責任を負うのではないかが問題となります。
この点、経済産業省の「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」によると、
- 運営会社があくまで、ユーザー間における取引仲介の場を提供しているだけである場合、原則として運営会社は、ユーザー間の取引によって生じた損害に対して責任を負わない
- プラットフォームに盗難品等が出品され、警察から取引中止の命令を受けたにも関わらず、取引を中止せずに盗難品が購入され、その盗難品の本リアの持ち主から返還請求を受けた場合などは、損害賠償義務を負う可能性がある
と考えられています。
つまり、運営会社は、原則として責任を負う必要はありませんが、運営会社の対応に問題があった場合には、損害賠償義務が発生してしまう可能性があります。
これらのことから、利用規約内の免責規定には、
- 商品の引き渡しや代金の支払いに問題が発生しても、運営側は責任を負わないこと
- 商品に不具合があった場合でも、責任を負わないこと
と記載しておきましょう。このような条項を設けておくことで、運営会社は、先に見た瑕疵担保責任を負う必要がなくなるわけです。
なお、「会社に故意・重過失がある場合は責任を負う」という条項は、どのようなビジネスモデルであっても会社側の賠償責任の規定内に入れておく必要があります。
明らかに会社の落ち度が原因で起こったトラブル(故意・重過失)の賠償責任まで、一方的に消費者側に負わせるような条項は、消費者契約法により無効となるためです。
(2)ユーザー投稿型メディアサイト
「インスタグラム」や「note」など、画像や文章、動画などのコンテンツを投稿するメディアサイトを運営するビジネスのケースです。
①投稿された画像や音声データなどの著作権
先ほどご紹介したように、著作権の所在が誰にあるのか、会社側がどの程度までユーザーから使用許諾を得られるのか明記しましょう。
著作権の場合、考えられるパターンは、先に見たように以下の3つです。
- 譲渡型
- ライセンス型
- 必要最低限の改変
どのパターンが自社サービスにおいて適切なのか検討し、それぞれどの程度まで会社側に権利が渡るのか、使用が許可されるのかを記載してください。
②問題のあるコンテンツの投稿禁止
著作権者に無許可で第三者が投稿したコンテンツなど、問題のあるコンテンツの投稿を禁止する禁止事項を設けましょう。
このほかにも、たとえば、以下のような投稿は、場合によっては、名誉毀損にあたる可能性があります。
- 許可なく他人の個人情報を掲載する
- 他人になりすまして写真や情報を投稿する
- 虚偽の内容を投稿する
- 嫌がらせやいじめを目的に投稿する
同時に、そのようなコンテンツを投稿した場合のペナルティも規定してください。
たとえば、問題のあるコンテンツを投稿したユーザーに対し、「警告を行う」としたうえで、
- 一度目の警告の場合、1週間コンテンツ投稿を行えないようにする
- 最初の警告から60日以内に二度目の警告を受けた場合、1ヶ月サイトの利用を停止する
- 二度目の警告から60日以内に計三度目の警告を受けた場合、アカウントを削除し、これまで投稿したコンテンツすべてを削除する
というように、段階的にペナルティを設ける方法などがあります。
(3)課金アプリ
スマホゲームやLINEのように何かしらのポイントやコイン購入が発生するアプリを運営するビジネスモデルのケースです。
①有料コンテンツの取り扱い
そもそも、アプリ内に有料コンテンツが存在することや今後の価格改定があり得る旨を書いておきましょう。
「すべて無料だと思っていた」「いきなり値上げされた」といったトラブルを回避できます。
②コインに関する取り扱い
先ほどご紹介した通り、課金アプリのコインは前払式支払手段として扱われます。
供託義務が発生しないよう、「コインには6ヶ月の有効期限を設ける」等の取り扱いに加えて、
- 法令で認められる例外ケースをのぞき、払い戻しは認められない
- アプリ内アイテムを現実世界で現金で購入するRMT(リアルマネートレード)を禁止する
といった内容も記載してください。
なお、払い戻しに関しては、資金決済法により、サービス終了時などの場合をのぞき、原則禁止となっています。
自由な払い戻しを許してしまうと、元本の返還が保証されることになり、出資法が禁止する「預り金」にあたったり、また、送金手段として前払式支払手段を利用することが可能になり、銀行法が禁止する「為替取引」にあたる可能性があるためです。
③サービス終了時の取り扱い
アプリサービスが終了すれば、当然、それまでユーザーが課金した分の有料コンテンツが利用できなくなります。
そのため、
- サービスの終了は運営側の裁量で行える
- サービスが終了すると、有料コンテンツが使用できなくなる
- サービス終了に伴い、ユーザーに何かしらの損害が発生しても、運営側は責任を負えない
- サービス終了時に限り、未使用コインの払い戻しが可能である(期間は60日以上)
などを書いておきましょう。
(4)コンテンツ提供サイト
音楽や動画の配信など、会社がユーザーに対して何かしらのコンテンツを提供するビジネスモデルのケースです。
①提供しているコンテンツの取り扱い
提供しているコンテンツをダウンロードしたユーザーに対し、どのように使用していいのか、ルールを定めてください。
具体的には、
- ユーザーによるコンテンツの加工を認めるか否か
- 商用利用を認めるのか
などがポイントです。
②著作権の所在
先ほどご紹介した通り、著作権の所在は確実に明記しておく必要があります。
提供するコンテンツの著作権を誰が持っているのか、しっかりと書いておきましょう。
③ルール違反した場合の取り扱い
策定したルールにユーザーが違反した場合、どのようなペナルティを課すのか明確にしておきましょう。
そのほか、「【ひな形付】web・アプリ利用規約の書き方と9つのポイントを解説」の記事を参考にしてください。
4 同意を取る方法

これまで、利用規約を作成するときの注意点を中心にご紹介してきましたが、サービスの提供を開始する際にも注意が必要です。
「とりあえず、作った利用規約はアプリやサイトに掲載しておけばいい」というわけではありません。
経済産業省が公表している「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」では、利用規約の内容が効力をもつための条件として、以下のようなルールが定められています。
- 利用者が事前に容易に確認できるように適切にサイト利用規約をウェブサイトに掲載して開示されている
- 利用者がサイト利用規約に同意していると認定できる
つまり、ユーザーから同意を得ることで、「利用規約に従ってサービスを利用する」ことを了承してもらったということになります。
利用規約のルールを適用するためには、利用規約を掲載しておくだけでなく、サービスを利用しようとしているユーザーから、利用規約への同意を得る必要があるのです。
この同意の取り方としては、サイトのシステムでチェックボックスを組み込む方法が一般的でしょう。
具体的には、「新規利用申し込み」のページにおいて、利用規約をすべてスクロールした後、「利用規約に同意します」というチェックボックスにチェックをつけられるようにしておくことが考えられます。
もしくは、「新規利用申し込み」のボタンのすぐ下に、利用規約へのハイパーリンクをわかりやすく設置しておく方法もOKです。
後々発生しうるトラブルを避けるためにも、必ず、利用規約への同意を得られる仕組みを作っておいてください。
5 利用規約の変更方法

サービスを運営していくうちに、利用規約の内容を変更する必要が出てくるケースは多々あります。そのような事態を想定し、あらかじめ変更に関するルールを利用規約に入れておきましょう。
変更のルールがない場合、変更前の利用規約に同意しサービスを利用しているユーザーに対し、変更後の利用規約を適用できません。
そのため、すべてのユーザーに対して、変更後の利用規約を適用できるよう、変更のルールを規定しておく必要があるのです。
明記しておくべきポイントは以下の3つです。
- どのような条件で変更を行うか
- 周知のタイミング
- 周知の方法
また、利用規約の変更方法として、
- ガイドラインに基づいた変更
- 定型約款の変更
の2種類があります。それぞれ、どのような方法なのか次の章でご紹介します。
6 民法改正前後で変動!利用規約の変更方法2種

利用規約の変更方法は、2020年4月1日からの新ルール「定型約款」が適用されるか否かによって変わります。
民法改正前と後に分けて、解説していくので、参考にしてください。
(1)民法改正前(~2020年3月31日):ガイドラインに基づいた変更
2020年3月31日までは、経済産業省の「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」(ガイドライン)に基づいて利用規約の変更を行います。
具体的な変更方法としては、
- 再度同意を得る
- 黙示の同意を得る
の2パターンが考えられます。
①再度同意を得る
先ほどご紹介した通り、利用規約はユーザーの同意を得る必要があります。
そのため、変更する規約の内容に対しても、再度同意してもらうのが自然の流れです。
しかし、利用規約の変更頻度が高いと、ユーザーは、その都度同意をすることが必要になるため、サービス利用を敬遠する空気が生まれるかもしれません。
そこで、毎回同意を得る必要のない方法として、「黙示の同意を得る」という方法が考えられます。
②黙示の同意を得る
利用規約の変更について十分な告知を行ったうえで、ユーザーが継続してサービスを利用していれば、変更された利用規約に同意したものとみなす方法です。
告知方法としては、ホームページへのお知らせ掲載やメルマガでの情報発信などが考えられます。
(2)民法改正後(2020年4月1日~):定型約款の変更
以下の条件に該当する利用規約は、「定型約款」として扱われます。
- 不特定多数の者を相手方とする取引で、内容の全部または一部が画一的であることが当事者双方にとって合理的なもの
たとえば、インターネットサービスの利用規約や保険約款などはこの条件に該当しますが、就業規則などは該当しません。なお、それ以外の利用規約に関しては従来通りの変更方法を行ってください。
定型約款の変更方法は、以下の2パターンです。
- 再度同意を得る
- 改正民法の条件に従って変更する
それぞれ見ていきましょう。
①再度同意を得る
これは、ガイドラインに基づいた変更方法と同じです。
変更する度に、ユーザーから利用規約への同意を取得します。
②改正民法の条件に従って変更する
改正民法では、以下の2つの条件のどちらか一方に当てはまり、かつ、必要な手続きを行うことで、ユーザーから同意を得ずに利用規約を変更することができます。
- 利用規約の変更がユーザーの利益になる
- 変更することがサービス契約の目的に反せず、変更内容も合理的
「ユーザーの利益になる変更」については、著作権に関する規定を例にしてみましょう。
「投稿されたコンテンツに関するすべての権利を運営会社に譲渡する」という譲渡型のルールを、「著作権はユーザーが有し、運営会社には使用許諾を与える」というライセンス型に変更することは、ユーザーの利益につながっています。
このように、変更することがユーザーにとって有利に働くものであれば、「ユーザーの利益になる変更」といえるでしょう。
一方で、「変更することが契約目的に反せず、合理的」という条件は、サービスを悪用するユーザーに関する規定を追加するなどの変更が考えられます。
例えば、月額会員制のWebメディアにおいて、1アカウントを複数の人が使いまわしているケースが発覚したとしましょう。
この場合、「メディアの記事を読む」というサービスの目的に反しない形で、「1アカウントを複数の人物・端末で同時に使用することを禁止する」という禁止事項を設けることは、合理的といえます。
こうした条件を満たしたうえで、以下の手続きを踏めば、利用規約を変更できます。
- 変更後の利用規約の効力発生時期を定めること
- 変更後の利用規約の内容と効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知する
つまり、いつから変更が適用されるのかを明確にしたうえで、「変更の効力が発生する1ヵ月前までに、当社のホームページおよび登録メールマガジン、アプリケーションのプッシュ通知にて通知する」などと利用規約に明記していれば、そのルール通りに利用規約が変更されることになります。
7 小括
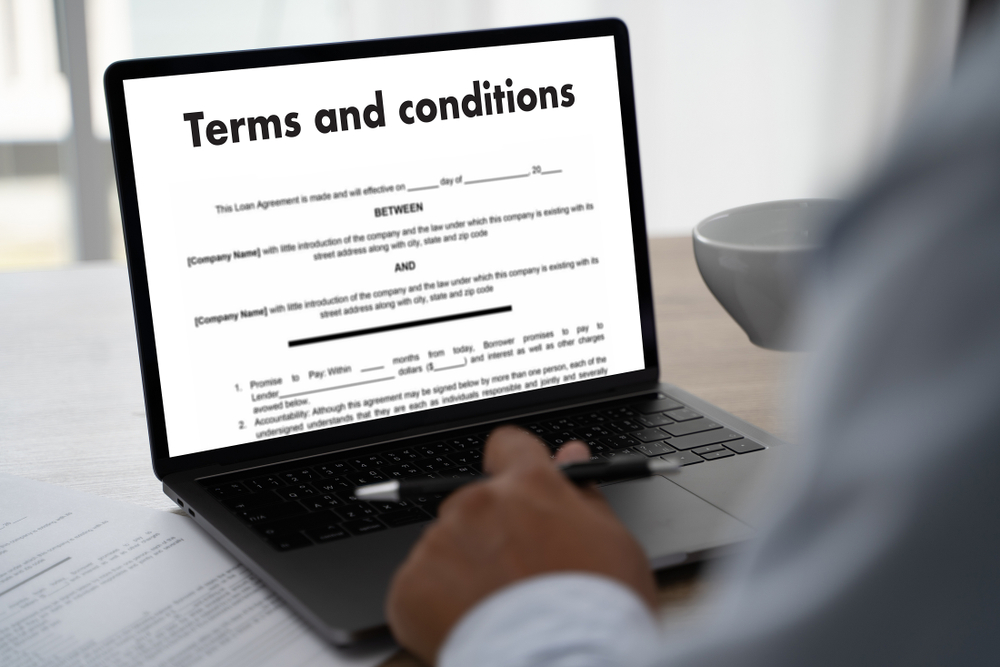
利用規約を作成・変更するときは、会社側のメリットだけでなく、ユーザー側にも配慮した利用規約にすることが大切です。
会社側が一方的に有利な利用規約としてしまった場合、その条項が無効になるだけでなく、ユーザーからの反発も招いてしまいます。
この記事を参考に、ぜひ、利用規約の作成にチャレンジしてみてください。
8 まとめ
これまでの解説をまとめると、以下のようになります。
- 利用規約を作成するときは、ユーザー側が著しく不利な内容とならないよう、バランスをとる必要がある
- ユーザーに対して不当な条項は、「消費者契約法」や「定型約款」によって無効となる
- 基本的な利用規約で、特に注意しておくべき条項としては、「禁止事項(ペナルティ)」「免責規定」「著作権」「個人情報の取り扱い」などが挙げられる
- 課金アプリなど発行されるコインやポイントは前払式支払手段にあたり、資金決済法の規制対象となる
- 資金決済法による供託義務を回避するためには、利用規約に「有効期限は6ヵ月(180日)とする」という記載を設けておくとよい
- ビジネスモデルごとに、追加で必要とされる条項が変化するため、自社サービスにおいて発生しうる条項を見極め、利用規約に盛り込むことが大切である
- 利用規約は、ユーザーの同意を得ない限り、効力を発揮しないため、有効的な同意を得られるようにサイトのシステムを設計する
- 利用規約の変更を行うときのルールについて、利用規約に記載しておく
- 利用規約の変更方法は、2020年4月1日から施行される改正民法によって変化するため、注意が必要である
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。