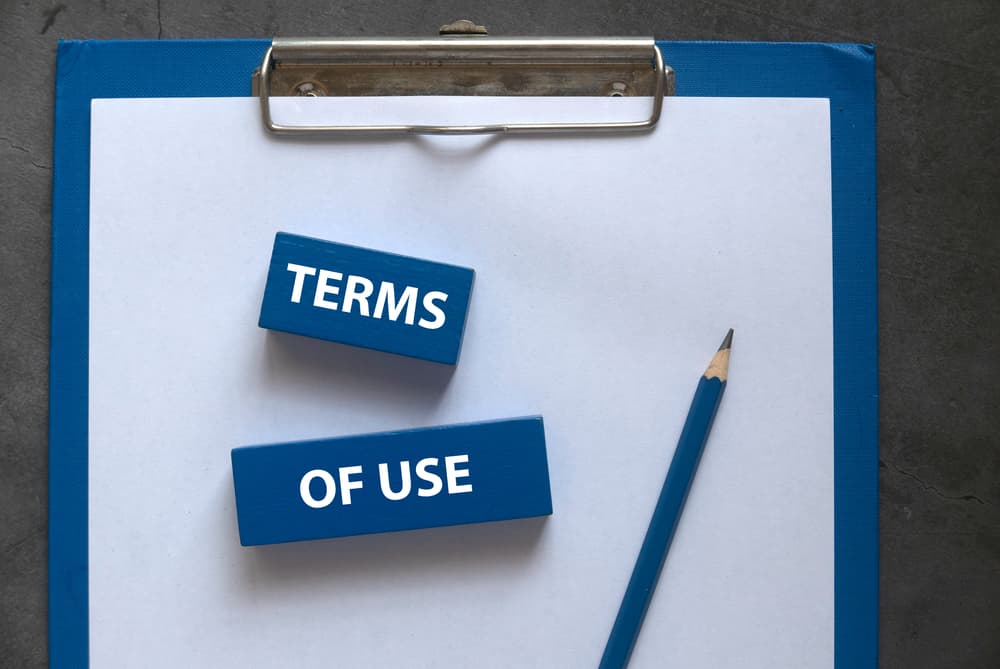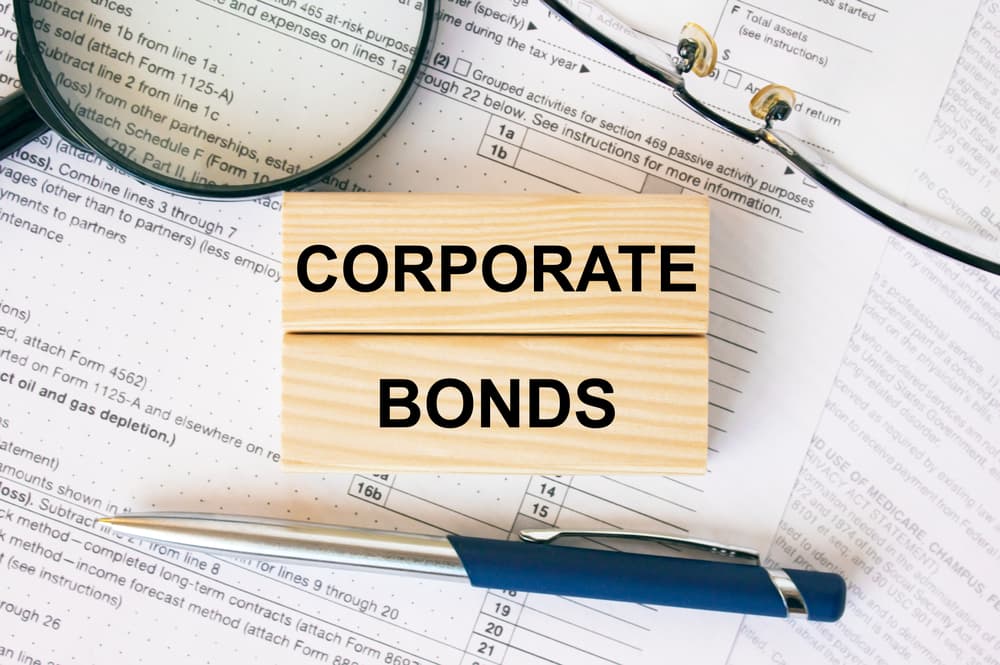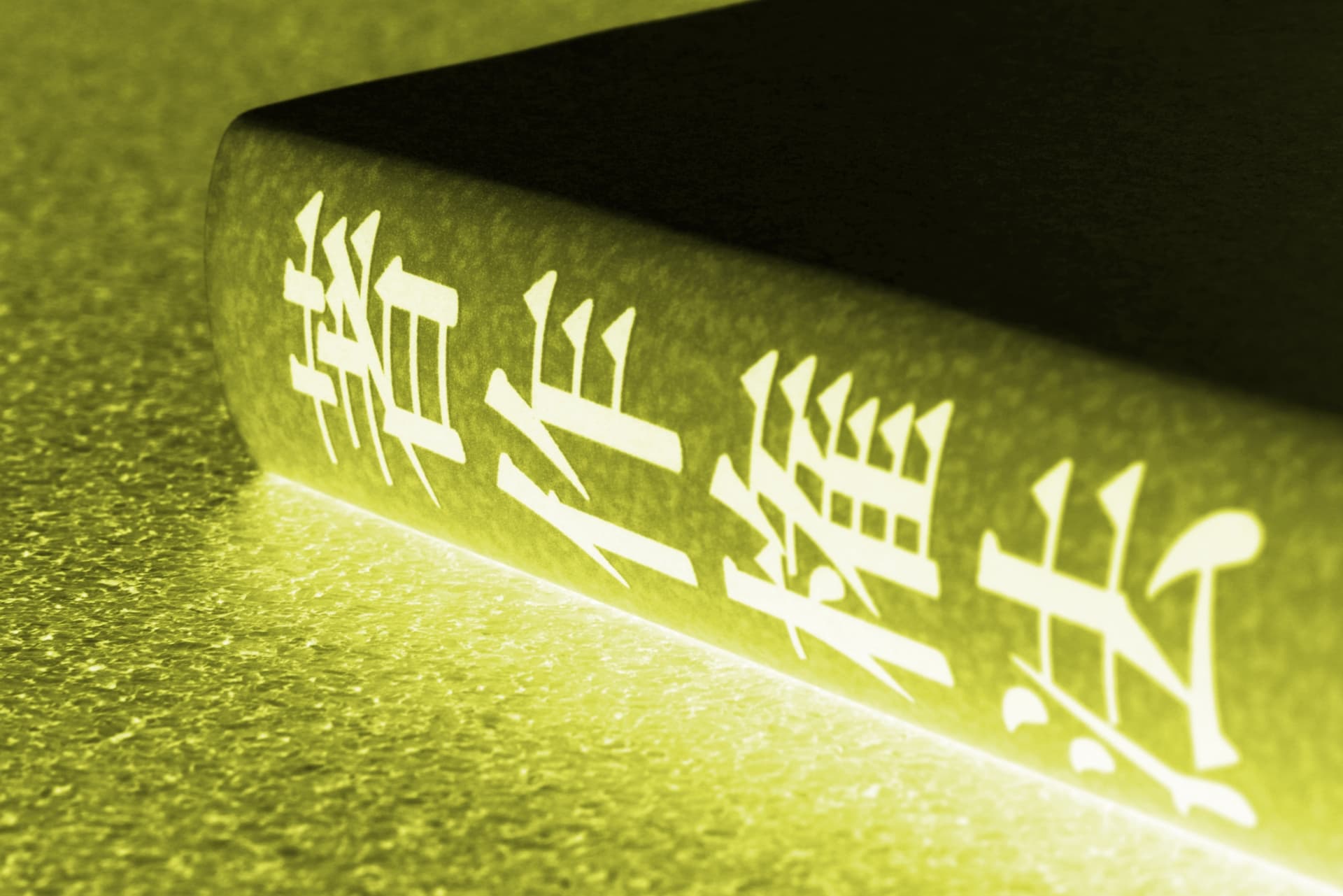仮想通貨にインサイダー取引規制が及ぶ?5つの注意点を弁護士が解説

はじめに
「インサイダー取引」が法律上禁止されていることについては、ご存知の方も多いと思います。もっとも、これはあくまで「株」などを対象とした規制であり、このインサイダー取引の規制が「仮想通貨」にも及ぶのかということについて、ご存知の方は少ないのではないでしょうか。
仮想通貨も投資行為の一種ではありますが、株式などのように法律で直接的に規制が明言されていません。そのため、仮想通貨に対してはインサイダー取引の規制が及ばないようにも思えます。
そこで今回は、実際にインサイダー取引疑惑のあった事例を紹介しながら、インサイダー取引とは何か、仮想通貨にインサイダー取引規制が適用されるのかなどをわかりやすく解説していきます。
1 「LISK」上場でインサイダー取引疑惑

まず始めに「仮想通貨取引がインサイダー取引にあたるのか」という点が実際に問題となった事例について見てみましょう。
2018年1月31日に、bitflyer(仮想通貨取引所)において、仮想通貨「LISK」と呼ばれる当時注目大の仮想通貨が上場しました。この上場により、大儲けした投資家が当然おり、その中には、LISKが上場することをあらかじめ知っていたことが儲けに繋がったと公表している方もいます。そういった言動を受けて、大儲けの裏では「インサイダー取引」が行われていたのではないか?という噂が広まりました。
この点、「株式」については、関係者からこっそりと「値上がり情報」を聞いた上でこれを取得した場合には、許されざる「インサイダー取引」として明確に禁止されています。これに対して、「仮想通貨」を対象としたインサイダー取引は禁止されているのでしょうか。
そもそも「インサイダー取引」とはどのような取引をいうのでしょうか。
次の項目でくわしくみていきましょう。
2 インサイダー取引とは

「インサイダー取引」とは、上場した会社の関係者や情報の受領者が、その会社の株価に影響を与える「重要な事実」を知りながら、その事実が公表される前に、会社の特定有価証券などの売買を行うことをいいます。このような取引は、金融商品取引法(通称:金商法)で禁止されています。図で表すと以下のようになります。

インサイダー取引について、もう少し細かく見ていきましょう。インサイダー取引が成立するためには、以下の要件をみたす必要があります。
- 規制の対象となっている人が
- 会社における重要な事実(株価に影響を与える事実)を知りながら
- その事実が公表される前に
- 会社の特定有価証券などを売買すること
それぞれの要件について、以下でくわしく解説します。
(1)規制の対象者
インサイダー取引の規制の対象になっているのは、大きく分けて、以下の2者です。
- 会社の関係者
- 情報の受領者
「会社の関係者」というのは、上場した企業の役員やアルバイトを含む従業員のことをいいます。また、これらの人で退職後1年経っていない人も含まれます。
さらに、上場した企業の大株主や取引先など、この企業と契約を結んでいる人や企業も「会社の関係者」に含まれます。
つまりは、上場した企業の業務などに関する重要な事実を知ることができる立場にある人や企業は、すべて「会社の関係者」に含まれるのです。
他方で、「情報の受領者」とは、「会社の関係者」にあたる人などから企業の業務などに関する重要な事実を直接聞いた人や企業のことをいいます。このような人や企業のことを「第一次情報受領者」といいます。第一次情報受領者から、さらに重要な事実を聞いた人(また聞きした人)は、ここでいう「情報の受領者」にはあたりません。
たとえば、上場企業である甲社の元役員であるA(退職後2ヶ月)から、甲社の業務に関する重要な事実をAの友人であるBが直接聞いたとしましょう。さらに、その事実をBの妻であるCに伝えた場合、Aは会社の関係者に、Bは情報の受領者にそれぞれあたりますが、Cは情報の受領者にはあたりません。
(2)会社における重要な事実
それでは、会社における「重要な事実」とはどのような事実を指すのでしょうか。
「重要な事実」については、金融商品取引法などが具体的に列挙しており、以下に挙げた事実はその一部です。
- 会社の合併や分割
- 新株予約権の発行
- 新製品や新技術の企業化
- 事業の譲渡あたる
- 業務提携
- 利益の配当
- 業務の過程で発生した損害
このほかにも、「重要な事実」は細かく決められています。
もっとも、「重要な事実」にあたるかどうかは、そのケースごとに判断され、軽微な場合などには、例外的に「重要な事実」から外されることもあります。
いずれにしても、自分が知ることになった事実が「重要な事実」にあたるかどうかをきちんと確認することが必要です。
(3)公表
重要な事実の「公表」については、何をもって「公表」されたといえるのかがこの言葉だけでは正確にわからないと思います。実際の取引が、公表の前だったのか、あるいは、公表の後だったのかによって、インサイダー取引が成立するかどうかが決まりますので、きちんと理解しておく必要があります。
ここでいう「公表」とは、2社以上のマスコミ(テレビや新聞など)が重要な事実を公開してから12時間を経過することをいいます。
たとえば、新聞社1社と放送事業者(テレビ局など)1社により重要な事実が報道された場合、一方に後れてなされた報道から12時間を経過した時点をもって「公表」されたといえるわけです。
(4)特定有価証券
「特定有価証券」とは、金融商品取引法において政令で新たにその範囲を定めるとされている、資産金融型の金融証券です。
たとえば、投資信託や外国投資信託の受益証券、特定社債や優先出資証券、あるいは、企業が発行する株券や社債券、新株予約権証券などが「特定有価証券」にあたります。
以上のように、インサイダー取引が成立するための要件は4つあります。
インサイダー取引にあたってしまうと、次の項目で解説するように、重いペナルティが待っていますので、取引の際には、慎重に検討することが求められます。
3 インサイダー取引のペナルティ

インサイダー取引にあたると判断された場合、その取引は、金融商品取引法に違反することになり、以下のように重いペナルティを科せられることになります。
- 最大5年の懲役
- 最大500万円の罰金
のどちらか、または両方が科せられます。
また、インサイダー取引によって得た資産や財産について、
- 没収
- 追徴
もしくは
が科せられます。
さらに、インサイダー取引を行った個人だけではなく、会社(法人)に対しても
- 最大5億円の罰金
が科せられます。
4 仮想通貨取引にインサイダー取引は適用されるの?
以上のように、「株」などの取引を対象に金融商品取引法で規制されている「インサイダー取引」ですが、「仮想通貨」取引においてはインサイダー取引を直接禁止するようなルールはありません。ですが、金融商品取引法が仮想通貨取引に適用されるのであれば、仮想通貨取引も「インサイダー取引」にあたる可能性が出てきます。
この点について、政府は以下の見解に立っており、仮想通貨取引に金融商品取引法は適用されないとしています。
- ビットコインは通貨にあたらない
- 仮想通貨取引は有価証券その他の有価証券等の取引にはあたらない
参考までに、参議院による答弁書(政府の見解)のリンクを貼っておきますので、詳しく知りたい方は、ご覧ください。
現在の政府の見解によれば、少なくとも現状においては、仮想通貨取引に金融商品取引法は適用されないため、インサイダー取引を行うことも許されるということになります。
もっとも、今後、仮想通貨取引が増えていけば、それに伴い、新たな法令が整備される可能性は十分に考えられます。
ここで、ICOについて注意喚起をしている金融庁のガイドラインをご紹介しておきます。
ICOが投資としての性格を持つ場合、仮想通貨による購入であっても、実質的に法定通貨での購入と同視されるスキームについては、金融商品取引法の規制対象となると考えられます。
以上からすると、仮想通貨による取引であることを理由に安心するのは危険です。なぜなら、仮想通貨取引の実質によっては、金融商品取引法の規制対象になる可能性があるからです。この点を十分に理解すべきです。
5 金商法以外にも気をつけるべきこと

これまでは、主に金融商品取引法との関係で見てきましたが、仮想通貨を対象としたインサイダー取引については、金融商品取引法による規制を受けなくとも、民事上の損害賠償責任を負う可能性があります。
たとえば、仮想通貨取引所の社員が重要な事実を漏洩したのであれば、仮想通貨取引所の社内規定に違反することになり、他の投資家に対する不法行為責任を負う可能性があります。
また、上場企業が重要な事実を漏洩したのであれば、他の投資家との出資契約の内容にもよりますが、場合によっては、債務不履行責任を負う可能性があります。
さらには、重要な事実を聞いた投資家がその事実を漏洩したのであれば、上場企業に対する債務不履行責任や他の投資家に対する債務不履行責任を負う可能性があります。
この他にも、仮想通貨取引所に対する業務妨害として、与えた損害の賠償責任を負う可能性も否定できません。
実際に、アメリカでは、インサイダー取引をした疑いがあることを理由に、投資家が仮想通貨取引所を相手取って、集団訴訟を起こした例もあります。
このように、仮想通貨を対象としたインサイダー取引には、金融商品取引法とは別に民事上の責任を負う可能性があるのです。
現時点では、仮想通貨を対象とした取引にインサイダー取引規制の適用はありませんが、インサイダー取引と強く疑われるような取引はしない方が無難であるということがいえます。
6 小括

以上のように、現在においては、仮想通貨取引にインサイダー取引規制の適用はありません。ですが、仮想通貨取引であることをもって安心するのは危険であり、場合によっては、金商法の規制対象になり、また、民事上の責任を負う可能性があるということをきちんと理解しておくことが重要です。
インサイダー取引のペナルティは非常に重く、取り返しのつかないことになるおそれもありますので、仮想通貨で取引をする際には、その取引の実態をきちんと確認したうえで、取引に入るようにしましょう。
7 まとめ
これまでの解説をまとめると、以下のようになります。
- インサイダー取引とは、上場した会社の関係者や情報の受領者が、その会社の株価に影響を与える重要な事実を知りながら、その事実が公表される前に、会社の特定有価証券などの売買を行うこと
- インサイダー取引の規制の対象者は、①会社の関係者、②情報の受領者である
- 重要な事実を「公表」したといえるためには、2社以上のマスコミが重要な事実を公開してから12時間を経過しなければならない
- インサイダー取引のペナルティは、非常に重い
- 政府の見解によれば、現状は、仮想通貨取引に金融商品取引法は適用されない
- 仮想通貨取引の実質によっては、金融商品取引法の規制対象になる可能性がある
- 仮想通貨を対象としたインサイダー取引について、民事上の損害賠償責任を負う可能性がある
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。