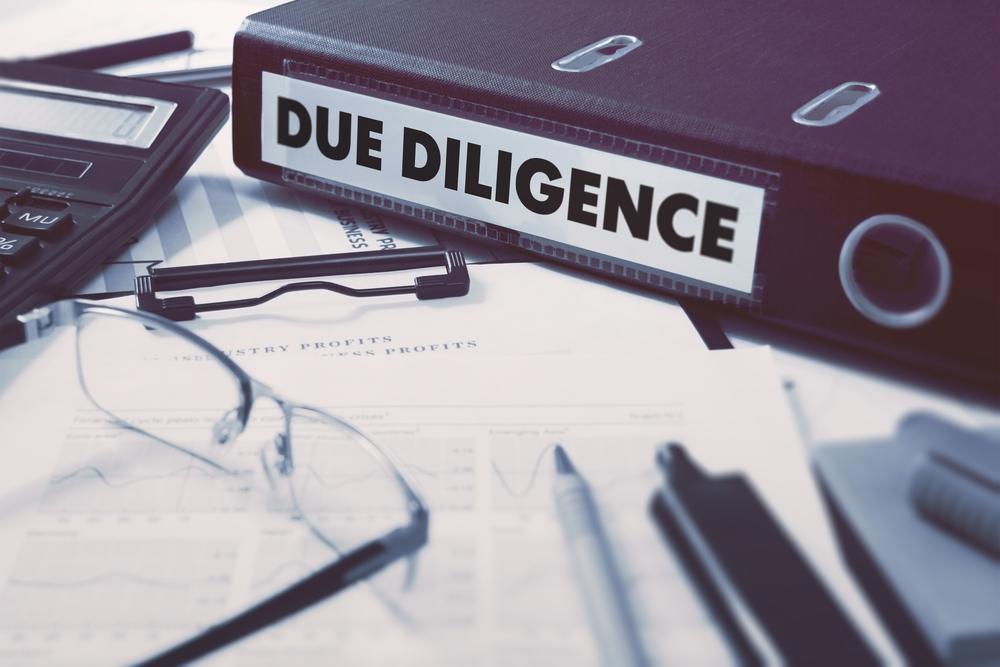【単なるツイートが3億円!】NFTの本質を法的に分析します(1)

0 はじめに
弁護士の勝部です。
この記事では、NFTの価値について、法的な解説をしていきたいと思います。
NFTについては、アート作品やトレーディングカードなどのデジタル所有権を取引の対象とするための技術である、と言われることがあります。
こういう説明を聞くと、何となく分かったような気にもなりますが、しかし、そもそも、日本の法令においてデジタル所有権というものは認められていません。
海外では、デジタル所有権(Digital property rights)という、人の権利の対象となる電子記録という概念が把握されてはいるようですが、著作権等の知的財産権やデータ自体に対する権利と何が違うのか、という点についてははっきりしないところもあります。
そこで、このブログでは、NFTが対象する権利の内容について、その外縁も含めて解説していきたいと思います。
(少し長いテーマなので、このテーマは何回かに分けて説明します)
1 NFTの内容はデジタル所有権か?
前述のように、NFTは、アート作品などのデジタル所有権を取引の対象とするための技術である、と言われることがあります。
しかし、日本の法制度では、所有権は実体のある有体物に対してしか成立しませんし、日本以外の法制度でも、基本的には似た考え方です。
通常、アート作品は絵画や彫刻など、実際に触れることのできる実体のある存在ですが、CGアートやフォトショップ等で作成したデータには実体がありません。
実体がない存在をどう取引の対象とするのか?
少なくとも、有体物自体を譲渡するという方法で取引の対象とすることはできません。
もちろん、データはDVDなどのメディアに記録すれば取引の対象とできます。
しかし、データ自体を取引の対象としているのとは少し異なります。
記録メディアを介した取引は、データが記録されたメディアの所有権を取引の対象としているにすぎないからです。
同じじゃないか、と思われるかも知れませんが、この点についてもう少し詳しく説明します。
2 記録メディアを介した取引方法
インターネットが普及する前は、音楽や映像はCDやビデオテープ、DVD等の媒体にコピーして、これらの複製物を取引の対象としていました。
このような記録メディア(複製物)は実体を伴うので、当然のことながら所有権の対象ともなりますし、有形的に譲渡することで取引の対象となります。
そして、こういった複製物を作成する権利を著作権(copyright)として認めることで、著作権者が著作物から収益を上げたり、違法な複製物に対して差し止めや損害賠償などの法的権利を行使することにより、自身の権利を守ることができるのです。
これが従来の常識的な発想です。
つまり、1点物のアート作品も、小説、音楽、映画などの複製可能な作品のいずれも、実体のある物を介して取引を行い、創作者の権利を著作権として保護する、という法秩序を前提として取引が成り立っているのです。
3 有体物を媒介としない取引方法
さて、このような常識に反し、実体のある物を介さずにアート作品を取引の対象とするにはどうしたらよいでしょうか?
まず、音楽や動画については、すでに有体物を媒介としない取引が当たり前になってきていますね。
音楽についてはiTunesやSpotify、動画についてはNetfrixやPrime Videoなどがあります。
CDやDVDなどの記録メディアを介さなくとも、視聴をする権利や一定期間のアクセス権に対してお金を払うことによって取引をするのがもはや当たり前になってきています。
こういった取引は、昔の物を介した取引に慣れている世代にとって抵抗のあるものでした。
「本やCDを受取らないのにお金を払うということに抵抗がある」
「物がないため、何か損をした気分になる」
最初はこういう感覚が先に立っていたのですが、慣れてくると、むしろ、失くしたり壊したりする心配もいらず、収納して管理する手間もない便利さが先にたってきます。
音楽、映画、書籍など、従来複製物を販売することにより取引がされていた作品については、すでに「実体のある物」を介することなく取引をすることが当たり前になってきています。
4 有体物を媒介せずに一点物アートを取引するには?
しかしながら、1点物のアート作品については、そのようなフォーマットによる取引にはなじみませんでした。
その理由について考察すると、1点物のアート作品には、その作品を見たり触ったりというというだけでは捉えきれない価値があるという特質があることに気が付きます。
例えば、絵画のモナ・リザは値段の付けようもない高価な一点物アート作品ですが、モナ・リザを所蔵(所有)することと、モナ・リザという作品を見たり触ったりすることの意味は全く異なります。
仮に、3Dスキャナによって、モナリザの精緻な3Dデータを作成し、インターネットでデータを販売したり、3Dプリンタで本物と見紛う複製を作ることができたとします。
確かに、名作を間近で堪能したいというニーズは存在します。
しかし、複製物の価値と、一点物を所蔵していることの価値は全く異なります。
特に、デジタルの世界では、いったんデータ化してしまえば複製や移転のコストは限りなくゼロに近くなります。
一点物がこのようなデータになってしまえば、その作品に見たり触れたりという価値はもはや特別なものではなくなってきます。
従来は、こういった特別感には、「世界に一つしかないモノ」という演出が不可欠でした。
世界に一つしかない本物を物理的に所有・占有している、という確かな認識がそこには必要であったと言えます。
しかし、電磁的に記録され、寸分違わぬ複製が簡単にできるデジタルデータには、オリジナルと複製物に有意な違いが見出しにくいという側面があります。
それでは、CGアートなど、出自がデジタルの作品には、古典アートが持つ価値を見出すことはできないのでしょうか?
その答えがNFTにあります。
NFTの技術自体は2017年頃からすでに存在していたのですが、NFTには、このような価値を実体化するための用途があることが発見され、そのために注目を集めてきているのです。
5 NFTと数量限定の関係は?
NFTがなくても、例えば、デジタル作品の公開時期や数量を限定することにより、希少性を高めることは可能です。
しかし、そのような限定的な性質によって生み出される価値と、一点物アートのNFTが取り扱おうとしている価値は、似ているようで少し異なります。
このことは、絵画のモナ・リザの3Dデータが誰でもアクセスできるようになった状況を想像してみれば分かると思います。
誰でも無料でモナ・リザを堪能できるようになったとしたら、確かにモナ・リザに見たり触ったりということの価値はコモディティ化し、全く特別なことではなくなりますが、世界に1つしか存在しないモナ・リザを所蔵する特別感はおそらく存在し続けるのではないでしょうか。
そして、このような「価値」を取引の対象とすることが、NFTであると言えるのです。
そもそも、電子データそのものを配布したいのであれば、電子データを持っている人から直接入手すればよいのであって、NFTを介して取引する必要は全くありません。
その電子データが気に入って、サブスクリプションなどで収益を上げたいと考えたのであれば、著作者に許諾を取ることによって頒布することができます。
NFTに電子データの著作権ライセンスを乗せて販売する、という技術も今後出てくるとは思いますが、それはNFTを使わなくても実現できることであって、NFTの本質とは少し異なります。
このことを示す良い例が、以下の例です。
-
【事例】
Valuables By Centというツイート売買のプラットフォームで、Twitter創業者であるジャック・ドーシー氏が出品した「最初のツイート」が3億円以上の価格で落札された(参照)
ジャック・ドーシー氏の最初のツイートはそもそもアート作品ではありませんが、「最初のツイート」は誰でもインターネットで見ることができます(「just setting up my twttr」https://twitter.com/jack/status/20)し、短文ながらも醸し出される味わい深さがあることは否定しないまでも、これを目にすること自体に3億円の価値があるはずもなく、また、NFTを購入したとしても、「最初のツイート」を独占できるわけでもなく、他の人は相変わらず「最初のツイート」を見ることができます。
このような例を考えると、NFTが「デジタル所有権」や「著作権」を管理するための媒介とは趣が異なる、ということが少し見えてくると思います。
6 小括
仮に、NFTの実体がデジタル所有権であるとするならば、管理可能性を独占できないジャック・ドーシー氏の最初のツイートに高い価値がつくことの説明ができません。
著作権とも少し異なります。
確かに、何らかの管理可能性に着目することになってはいくのでしょうか、最初のツイートはそもそも著作物ではないですし、少なくとも、創作的側面からの価値を見出せることがNFTの本質というわけでもなさそうです。
NFTを購入することによってクリエイターを応援する、パトロンのような存在になれる、という側面もありうるとは思いますが、アート市場の規模からいえばまだ普通に絵を売ったりクラウドファンディングなどのプロジェクトを立ち上げる方が適していると思います(今後変わってくるかも知れませんが)。そもそも、クリエイターを応援したいというのは取引の動機部分にすぎず、その動機に主たる意味があるという前提のもとでは、ツイートのNFTは売買の対象にすらならないでしょう。
逆に考えると、NFTには、今までの常識では値付けや取引の対象としにくいものを取引の対象にするのに有用な媒介であると言えます。
「今までの常識では値付けや取引対象としにくいもの」が取引の対象になったために、ブルーオーシャン状態となった市場において、このプラットフォームに適した商品の値段が一気に跳ね上がることになった、と言うことができると思います。
そうであるとすれば、既存のフレームワークですでに高額取引がされているものをあえてNFTにしても余り意味がないといえますし、
また、この概念が当たり前になってくる頃にはNFTの市場もレッドオーシャンになってくるかも知れません。
(2)では、この価値の概念についてもう少し深く掘り下げるとともに、法的に説明するとどのように理解するとしっくりくるのか、という仮説めいたものにも少し言及していきたいと思います。
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。