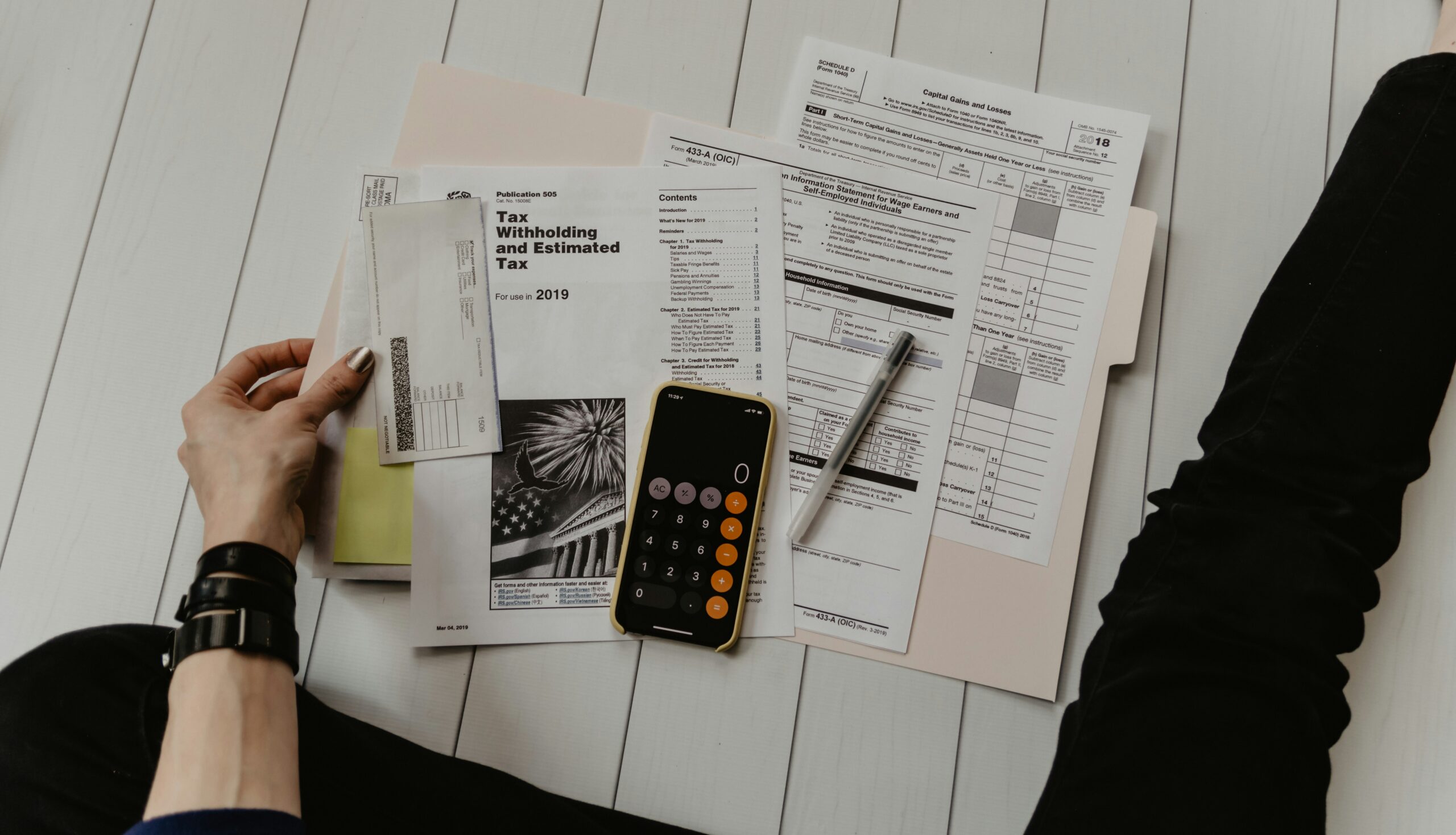下請法とは?規制対象となる4つの取引と資本金の額を弁護士が解説!

はじめに
下請取引を行う場合、「下請法」という法律に注意しなければなりません。
「下請法という法律を知らなかった」「法律は知っているが、何を規制しているのか知らない」という事業者もいらっしゃると思います。
下請法は、言葉のとおり、下請取引を規制対象とする法律ですが、必ずしもすべての取引が規制対象となるわけではありません。
取引の内容や資本金の額によって規制対象となるかどうかが異なるため、下請取引を行う際には、個別に判断する必要があります。
今回は、「下請法」について、規制対象となる取引・条件などをわかりやすく解説します。
1 下請法とは

「下請法」は、大規模な事業者が小規模な事業者・個人事業主などに発注した業務の対価を不当に減額したり、支払いを遅延したりすることを規制する法律です。
支払いの遅延などを防ぐことにより、取引の公正を確保するとともに、下請事業者の利益保護を目的としています。
いわゆる「下請けいじめ」を禁止しているのが下請法です。
そのため、下請事業者に責任がないにもかかわらず、発注後に下請代金を減額したり、正当な理由がないのに、下請代金の支払を遅らせたりするようなことはできません。
2 下請法の規制対象となる取引
- 製造委託
- 修理委託
- 情報成果物作成委託
- 役務提供委託
(1)製造委託
-
【下請法2条1項】
この法律で「製造委託」とは、事業者が業として行う販売若しくは業として請け負う製造(加工を含む。以下同じ。)の目的物たる物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料若しくはこれらの製造に用いる金型又は業として行う物品の修理に必要な部品若しくは原材料の製造を他の事業者に委託すること及び事業者がその使用し又は消費する物品の製造を業として行う場合にその物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料又はこれらの製造に用いる金型の製造を他の事業者に委託することをいう
「製造委託」は、発注者が品質や規格等を指定したうえで、物品の製造や加工を他社に委託する取引です。
たとえば、自動車メーカーが部品の製造を部品メーカーに委託することは「製造委託」にあたります。
(2)修理委託
-
【下請法2条2項】
この法律で「修理委託」とは、事業者が業として請け負う物品の修理の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること及び事業者がその使用する物品の修理を業として行う場合にその修理の行為の一部を他の事業者に委託することをいう
「修理委託」は、物品の修理の全部または一部を他社に委託する取引です。
修理委託の対象は、自社が使用する物品の修理だけでなく、自社が請け負った物品の修理も含まれます。
たとえば、電化製品を販売する事業者が、自社で請け負った電化製品の修理を他の事業者に委託することは「修理委託」にあたります。
(3)情報成果物作成委託
-
【下請法2条3項】
この法律で「情報成果物作成委託」とは、事業者が業として行う提供若しくは業として請け負う作成の目的たる情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること及び事業者がその使用する情報成果物の作成を業として行う場合にその情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託することをいう
「情報成果物作成委託」は、デザインや映像コンテンツ、プログラムなどの作成を他社に委託する取引です。
情報成果物作成委託の対象は、自社で使うデザインやコンテンツなどの作成に限られず、自社が作成を請け負ったデザインやコンテンツなどの作成も含まれます。
たとえば、プログラミングを請け負った事業者が、その全部を他の事業者に委託することは「情報成果物作成委託」にあたります。
(4)役務提供委託
-
【下請法2条4項】
この法律で「役務提供委託」とは、事業者が業として行う提供の目的たる役務の提供の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること(建設業(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第二項に規定する建設業をいう。以下この項において同じ。)を営む者が業として請け負う建設工事(同条第一項に規定する建設工事をいう。)の全部又は一部を他の建設業を営む者に請け負わせることを除く。)をいう
「役務提供委託」は、情報処理や運送などのように、サービスを顧客に提供する事業者が他社にその提供を委託する取引です。
たとえば、運送サービスを提供する事業者が、そのサービスの一部を他の事業者に委託することは「役務提供委託委託」にあたります。
3 下請法上の資本金要件

下請法の規制対象となる取引について見てきましたが、上記取引にあてはまるすべての取引が下請法の規制対象になるわけではありません。
これに加え、取引当事者の資本金額に以下のような条件があります。
(1)製造委託・修理委託の場合
資本金の額が3億円を超える事業者が、資本金の額が3億円以下の事業者に製造委託・修理委託を行う場合は、下請法の規制対象となります。
また、資本金の額が1000万円を超え3億円以下の事業者が、資本金の額が1000万円以下の事業者に製造委託・修理委託を行う場合も同様です。
(2)情報成果物作成委託・役務提供委託の場合
資本金の額が5000万円を超える事業者が、資本金の額が5000万円以下の事業者に情報成果物作成委託・役務提供委託を行う場合は、下請法の規制対象となります。
また、資本金の額が1000万円を超え5000万円以下の事業者が、資本金の額が1000万円以下の事業者に情報成果物作成委託・役務提供委託を行う場合も同様です。
このように、下請法は、規制対象となる取引の親事業者を資本金区分により優越的地位にあるものとして取り扱い、親事業者による不当な行為を効果的に規制することをねらいとしているのです。
4 まとめ
取引が下請法の規制対象となるかどうかは、取引内容と資本金の額の二つの面から確認する必要があります。
確認の手順としては、まずはじめに自社の取引が規制対象となる取引にあてはまるかを確認し、あてはまる場合は、取引当事者の資本金の額を確認しましょう。
本記事では触れていませんが、下請法の規制対象である場合、主に、親事業者に対しては一定の義務が課されることになります。
義務に違反すると、罰則を科される可能性もあるため、注意が必要です。
弊所は、ビジネスモデルのブラッシュアップから法規制に関するリーガルチェック、利用規約等の作成等にも対応しております。
弊所サービスの詳細や見積もり等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。