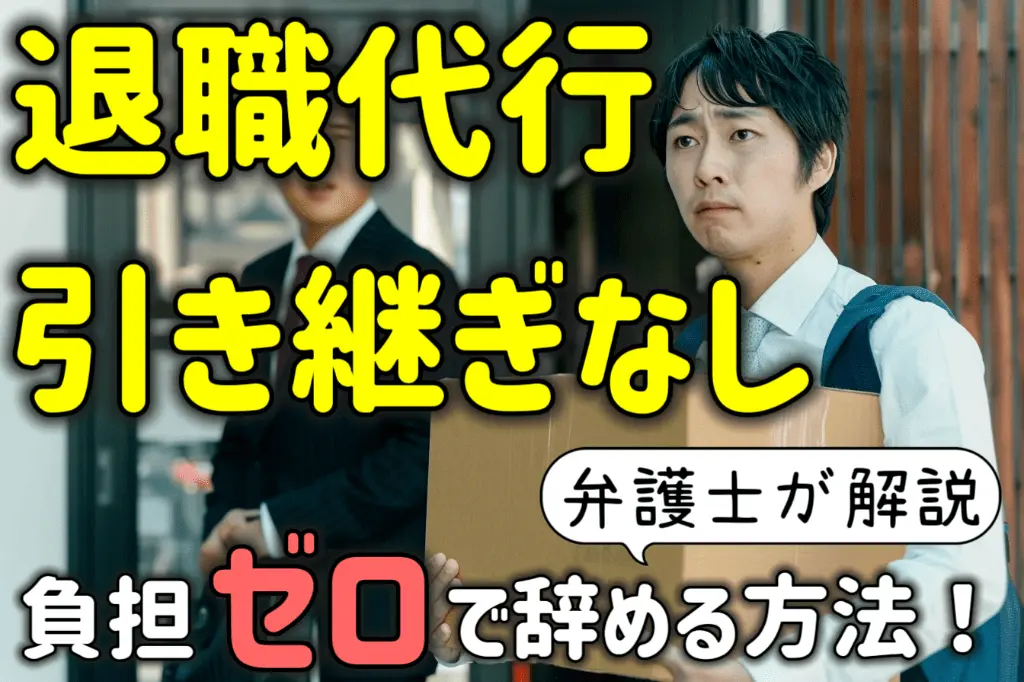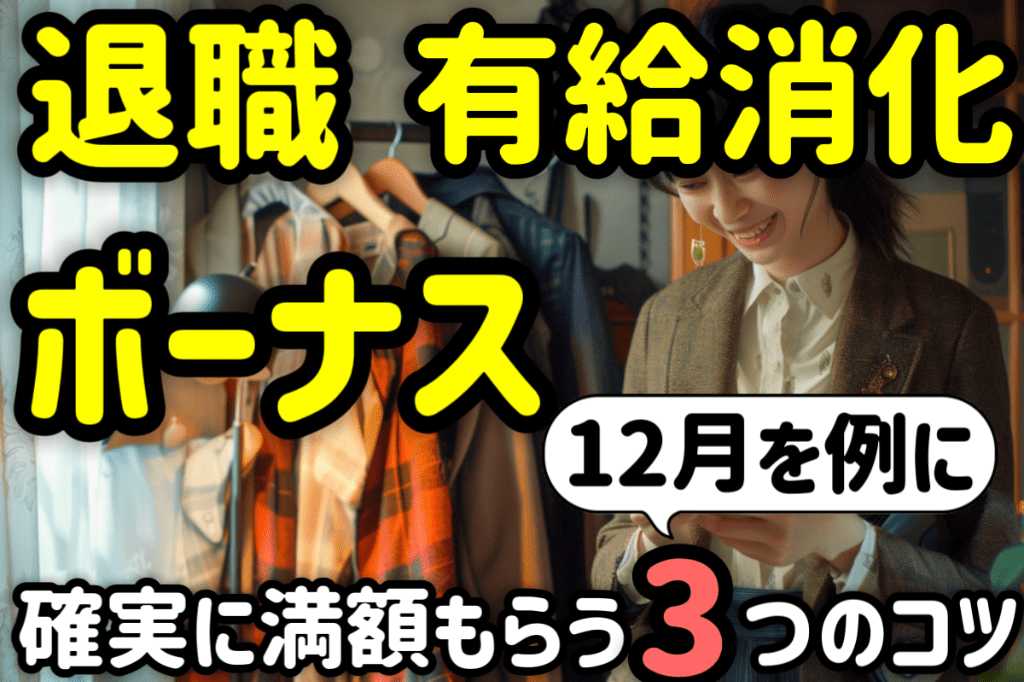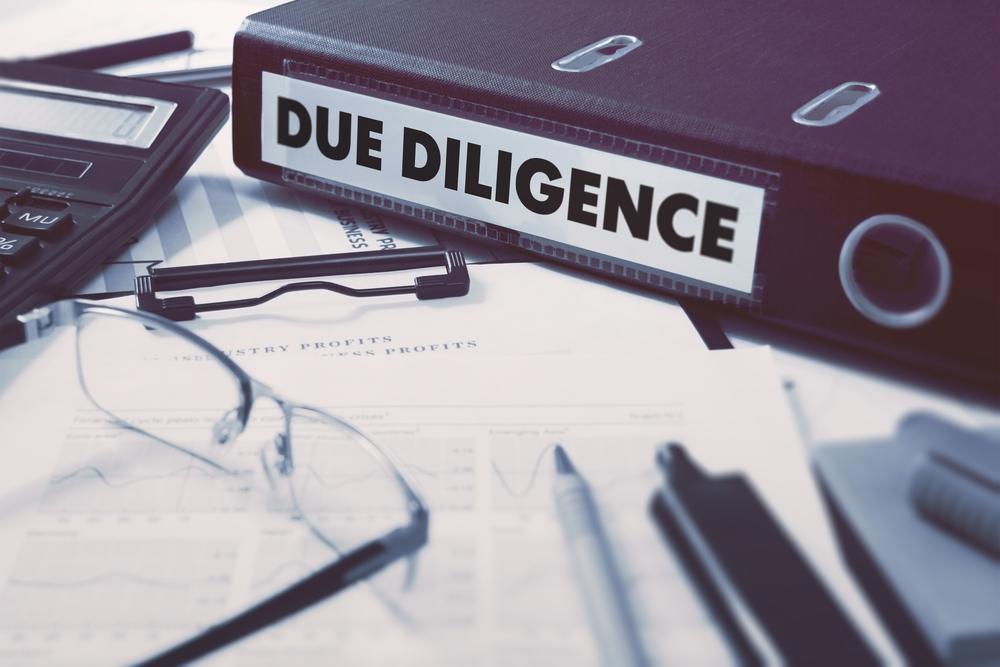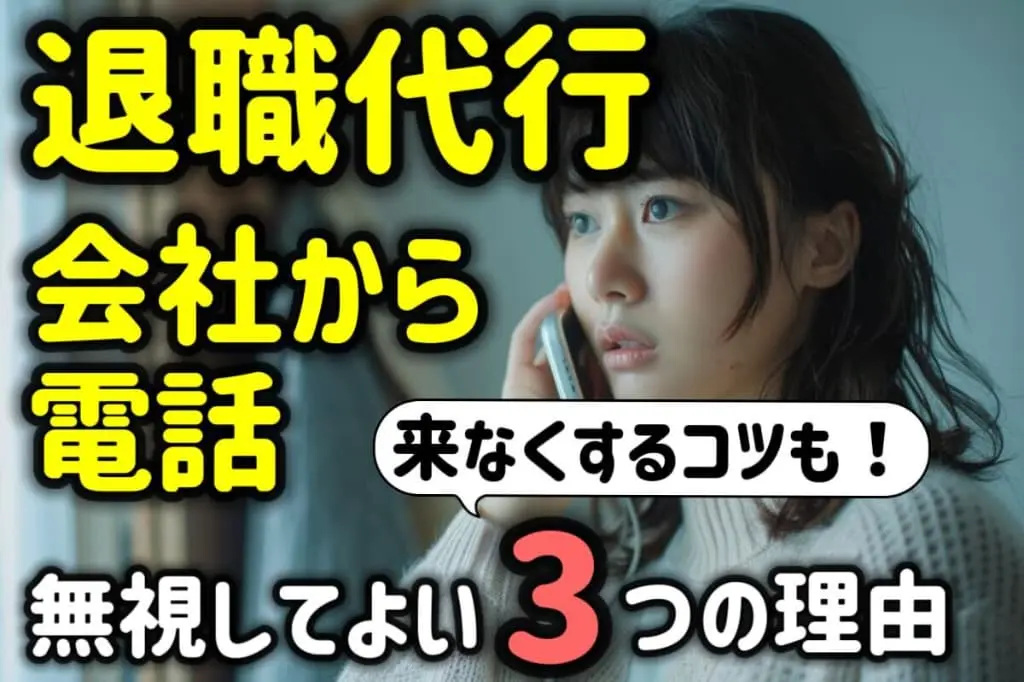医療×AI(Medtech)で注意すべき3つの法律を弁護士が解説

はじめに
医療現場では、少子高齢化による労働力不足や、扱うデータが膨大で有用なデータを活用しきれていないという問題があります。
このような状況の中、AIを医療の現場に導入し、労働力不足を補ったり、医療データを大量に処理したりする「Medtech(医療×AI)」の取り組みが期待されています。
もっとも、医療は人の生命・身体といった重大なものに直接かかわるものであるため、その分野で自由にAIを導入することはできません。そこには「医師法」を始めとしたいくつかのルールが存在しています。
そこで今回は、医療分野にAIを導入する際に、事業者が注意すべき法律などについて、ITに詳しい弁護士がわかりやすく解説していきます。
1 医療×AI(Medtech)とは?
(1)Medtechとは?
「医療×AI(Medtech)」とは、要するに、医療の分野でAIなどのIT技術を使うことをいいます。
この「Medtech」では、以下のようなことが期待されています。
- 医療プロセスの効率化、自動化の推進で労働力不足を解消すること
- 手術にロボットを使い、医師などの負担を減らすこと
- 患者がどこにいても最先端の医療を受けられるようにすること
- 時間や費用をかけずに画期的な医薬品や治療法を開発すること
- 先端医療への対応
- 介護ロボットを使い、介護者の負担を減らすこと
このように、医療分野にAIを活用することにより期待されるメリットは、どれをとっても医療分野の今後の向上のために重要なことであるといえます。
それでは、実際に医療のどの領域でAIの導入が推奨されているのでしょうか。
(2)医療分野へのAIの導入
国の政策によって、AIの導入が推奨されているのは、以下の6つの領域になります。
- ゲノム医療
- 画像診断
- 診断・治療
- 医薬品の開発
- 介護・認知症
- 手術
①ゲノム医療
「ゲノム医療」とは、遺伝子情報を調べて、病気の診断や治療を行うことを言います。
AIの導入が推奨される理由のひとつとして、ゲノム医療において、AIはとても有用であり、実現する可能性が高いということが挙げられます。
また、AI技術が発達したことで解析コストが低下し、技術的に実現可能段階にあることも理由のひとつです。
この領域においてAIを導入するメリットとしては、以下のようなことが挙げられます。
- 性質上、長時間を割いて膨大なデータを解析する必要があるものを短時間で処理できる
- 発見できなかった疾患を短時間で発見できる
- ゲノムの解析によって、適切な診療や治療方針を決定できるので、がんなどの難病治療に対処することができる
- 新たな医薬品開発が進む
現在、ゲノム医療をさらに発展させるために、国がゲノム情報や新しい療法などを見つけるための試験的な治療を通じて得られるデータを集めてデータベースを構築しています。このデータベースには、試験的なものだけでなく、普段、私たちが病院などで受ける診断や治療などのデータも含まれる予定です。
②画像診断
AIの導入が推奨される理由のひとつとして、日本には、レントゲン画像などのように活用できる医療画像データがたくさんあり、外国に比べて優位にあることが挙げられます。
大量のデータがあるとなぜ優位といえるかというと、AIにより高度なディープラーニングをさせることができるからです。
「ディープラーニング」とは、AIが必要な情報を自分で選んで学び、勝手に賢くなっていくというものです。このディープラーニングを活用することで、様々な医療に役立てることができます。
また、AIの活用によって、数の少ない放射線治療の専門医や、患者の細胞などを顕微鏡で観察して診断する病理の専門医の負担を減らすことも期待されています。
この領域においてAIを導入するメリットとしては、以下のようなことが挙げられます。
- 大量のデータを利用して、高度なAIのディープラーニングができる
- 専門医が存在しないへき地で、精度の高い画像診断ができる
- 医師の診断後にAIにダブルチェックをさせることで診断の見落としを低下させる
- 本来医師が見るべき画像をAIに選択させることにより、数少ない放射線治療の専門医や、細胞などを顕微鏡で診断する病理の専門医の負担を減らす
- 内視鏡、皮膚科、眼科、超音波にも画像診断が利用できる
現在、画像診断のさらなる発展のため、ディープラーニングの応用実用化が考えられています。具体的には、国が病理診断、内視鏡、放射線の画像データからデータベースを構築していることなどが挙げられます。今後は、さらに珍しい疾患の画像を収集し、さらにディープラーニングの精度を上げていく必要があると考えられています。
加えて、皮膚、眼科、超音波のデータベース構築も検討されています。
③診断・治療
AIの導入が推奨される理由のひとつとして、情報量の急激な増加に対応する必要性の存在が挙げられます。医療分野においては膨大な数の論文や、論文以外にもたくさんのデータがあり、医師などだけでは処理しきれていない現状があるため、AIによって、その処理速度を上げることが大きく期待されています。
この領域においてAIを導入するメリットとしては、以下のようなことが挙げられます。
- データを早く大量に処理できるので、医療従事者の負担軽減や診断・治療に役立つ
- 多くのデータを活用できるので、過疎地でも質の高い、専門外の医療を提供できる
- たくさんのデータを参考にできることから難しい疾患の見落としが減少する
- 客観的なデータの少ない精神科医療においても、患者の発話や表情などの情報を集めることができれば診療の精度が上がる
- 当直医の支援や、医学生などの教育にも役立つ
- 電子カルテに連結させれば、過去情報から推奨される治療法や避けるべき薬がわかる
今後は、国によってAIの医療上の取り扱いが明確にされることが考えられており、また、民間競争を促し、診断・治療におけるAI技術を発展させることなどが考えられています。さらに、医師によって診断や治療が異なるというようなことを生じさせないために、医療データに関する標準的なルールを作ることも考えられています。
④医薬品の開発
AIが導入される理由のひとつとして、現状のままだと、医薬品の開発に、時間とコストがかかりすぎることに加えて、医薬品を完成させる成功率も低いままであることが挙げられます。
この領域においてAIを導入するメリットとしては、以下のようなことが挙げられます。
- 時間と経費の削減
- AIに様々な医療データを学習させれば、これまで発見されてない創薬ターゲット(人の体内にある、薬が作用するたんぱく質などの物質)の発見が期待できる
- 創薬ターゲットと化合物が結びついたデータをディープラーニングさせることにより創薬ターゲットに、より効果のある化合物を見つけることができる
- 医薬品の候補になる化合物に関し毒性の予測ができるので、途中で開発中止をするリスクがなくなる
今後は、段階的に技術を発展させ、近い将来、AIによって医薬品を開発することが考えられています。そのために、AIのディープラーニングを促進する目的で製薬会社とIT企業の結びつきを促進させることが考えられています。
また、ディープラーニングには大量のデータが必要なため、公的機関や第三者、他社に知られないようにAIデータを作り、優先的に使用できるようにするなどして多くの企業が安心してデータを預けられるような体制を作ることが検討されています。
⑤介護・認知症
AIの導入が推奨される理由のひとつとして、現場の介護者の負担を減らし、また、高齢者の生活の質の向上を図ることが挙げられます。医療の分野においても、特に介護などの労働力が不足しがちであるため、AIを活用したロボットを利用して、これから増加が見込まれる要介護者や認知症患者に速やかに対応する必要があることも理由として挙げられます。
この領域においてAIを導入するメリットとしては、以下のようなことが挙げられます。
- 介護ロボットにAIを付けて、生活事象や生活リズムを知ることができれば、介護者の負担が減ることや要介護者の生活の質の向上が期待できる
- 加齢に伴う生体変化を把握することで血圧や呼吸状態などの生命活動に関する情報をAIに学習させれば、適切な治療、医療の質の向上が期待できる
今後は、生活事象や生活リズムのデータを集める手法や機器の開発が急務だと考えらえています。また、認知症に向けたAIの開発も検討されています。
⑥手術
AIの導入が推奨される理由のひとつとして、外科医は迅速な意思決定が必要になるなど、負担が大きい上に、その数は減少傾向にあるので、その負担軽減と労働力不足を補うことが挙げられます。
また、AIを導入するとなると、手術室で使う機器をネットワークに接続させなければなりませんが、日本のシステムは医療機器も含め多くの機器と接続することが可能であるため、この強みを活かして手術支援をするということも理由として挙げられます。
この領域においてAIを導入するメリットとしては、以下のようなことが挙げられます。
- AIが手術、その経過、治療後のデータを学べば、医師が適切な療法を容易に選択でき、負担が軽減される上、患者も質の高い医療が受けられる
- ディープラーニングによって手術ロボットに触覚がつけば、ある程度の自動化が見込まれるので、医師の負担が大きく軽減される上に、労働力不足の解消にもつながる
このように手術ロボットは、手術の領域においても多くのメリットを生むことが想定されますが、対象となるのは、人の生命・身体といった重大なものであるため、今後、法律を整備する必要があります。それだけでなく、すでにある様々なルールをクリアしなければならないなど多くの問題があります。
以上からすると、手術支援をロボットで自動化するようになるにはまだまだ時間がかかるものと考えられています。
もっとも、ディープラーニングにおいて技術の革新があれば、手術ロボットの自動化も早まる可能性があります。
以上のように、AI技術は、国の政策により、以上の6つの領域で導入されることが推奨されています。これからの医療分野における発展を考えると、これらの領域にAI技術を導入することの有益性は極めて高いということがいえます。
もっとも、AIを医療分野に導入する際には、注意しなければならないルールが存在します。
※AIの医療分野への導入推奨について、もっと詳しく知りたい方は、厚生労働省によりまとめられた「保健医療分野におけるAI活用推進懇談会報告書」をご覧ください。
2 AIを医療分野に導入する際に注意すべき規制
AIを医療分野に導入する際に注意すべき規制は以下の3点となります。
- 「医療機器」に関する規制(「医薬品医療機器等法」)
- 医業に関する規制(「医師法」)
- 個人情報保護法
3 「医療機器」に関する規制(医薬品医療機器等法)
「医療機器」とは、人の病気の診断・治療・予防に使用されるといったように、身体に影響を及ぼすことが目的とされているものをいいます。
そして、医療機器などの品質や安全を確保し、その使用による危害の発生を防止するためにさまざまなルールを定めている法律が「医薬品医療機器等法」です。
ある機器が、医薬品医療機器等法上の「医療機器」にあたる場合、以下の2点につき、国から許可・承認を得る必要があります。
- 機器の製造・販売
- 個別に安全性や有効性を確認すること
では、AIを活用したプログラムは、医薬品医療機器等法上の「医療機器」にあたるのでしょうか。
この点について厚生労働省は、「医療機器」にあたるかどうかは、以下の2つの要素を考慮して判断するとしています。
- 治療・診断への寄与度
- 機能障害が生じた場合の人命・健康に対するリスクの蓋然性
(1)治療・診断への寄与度
AIを活用したプログラムが、どれだけ人の治療などに使用されて役立ったか、医師の診断に影響を与えたか、という観点から、「医療機器」にあたるかどうかを判断します。
(2)機能障害が生じた場合の人命・健康に対するリスクの蓋然性
「医療機器」は、人の生命・健康に与える影響が大きいからこそ、一定のルールを作って制限を付ける必要があると考えられます。
このような観点から、AIを活用したプログラムが機能障害を起こした場合に人命や健康に与えるリスクがどの程度のものなのか、ということを考慮して、「医療機器」にあたるかどうかを判断します。
このように、AIを活用したプログラムが「医療機器」にあたるかどうかは、治療・診断への寄与度と機能障害が生じた場合のリスクの蓋然性という2つの要素によって決まります。寄与度と蓋然性、いずれもが高ければ高いほど、AIを活用したプログラムが「医療機器」にあたる可能性は高くなるといえます。
以下では、プログラム別に、「医療機器」に該当するAIプログラムと該当しないAIプログラムについて具体的に見ていきたいと思います。
-
【「医療機器」に該当するAIプログラム】
- 医療機器で得られたデータを加工などし、診断や治療に用いるためのグラフなどを作成するプログラム
- 治療計画や方法の決定を支援するためのプログラム
「治療計画や方法の決定を支援するためのプログラム」としては、たとえば「放射線治療計画システム」が挙げられます。これは、放射線治療における患者への放射線の照射をシミュレーションし、患者ごとに一番効果のある放射線の治療計画や方法の決定を支援するためのプログラムです。
このプログラムは、医師に適切な放射線治療を提案し、その診断に影響を与えるといえるため、「治療・診断への寄与度」があるといえます。
また、プログラムの提案した治療計画において、放射線の量が間違っていた場合、患者は死亡してしまう可能性があり、その生命は危険にさらされているといえるので、「人命・健康に対するリスクの蓋然性」があるといえます。
このことから、このプログラムは「医療機器」であると認められることになります。
-
【「医療機器」に該当しないAIプログラム】
- 医療機器で取得したデータのうち、元に戻せない形で圧縮をしたデータを加工せずに、他のプログラムなどに転送するプログラム
- CTなどの画像を利用して診断する機器で撮影した画像を、診療記録のために転送、保管、表示するプログラム
- 医学教育の一環として、医療関係者がメディカルトレーニング用教材として使用したり、トレーニングを補強したりすることを目的としたプログラム
- 日常的な健康管理のため、個人の健康状態を示す計測値を表示などするプログラム
「医療機器で取得したデータのうち、元に戻せない形で圧縮をしたデータを加工せずに、他のプログラムなどに転送するプログラム」としては、たとえば、患者の診断結果を別の機器に転送するために変換するプログラムがあります。
このプログラムは、医療機器で取得された患者の診断結果を別の機器に転送するために変換することを目的としたプログラムです。
そのため、このプログラム自体は治療・診断に直接影響を与えるものではないことから、「治療・診断への寄与度」があるとはいえません。
また、このプログラムに障害が生じても、患者がケガをしたり死亡したりするなどの影響はなく、「人命・健康に対するリスクの蓋然性」もありません。
そのため、患者の診断結果を別の機器に転送するために変換するプログラムは「医療機器」にはあたりません。
以上のように、AIプログラムが「医療機器」にあたるかどうかの判断においては、「治療・診断への寄与度」と「人命・健康に対するリスクの蓋然性」の2点が重要な要素となります。
これら2つの要素をみたすAIプログラムは、「医療機器」にあたるため、このようなプログラムの製造・販売などには、国の許可が必要になります。
もっとも、AIプログラムを用いて、医療にあたるようなことを行うためには、医師免許が必要になってくると考えられます。
そのため、次の項目で解説する「医師法」との関係でも問題となってきます。
4 医業に関する規制(医師法)
「医業」とは、医師免許をもつ医師にだけ認められた行為であり、医師の判断や技術がないと患者の体に危険が及ぶかもしれない行為を繰り返し行うことをいいます。
AIプログラムは、当然、医師免許を持っていません。それなのに、この「医業」にあたる行為をしてもいいのでしょうか。
上で挙げた放射線治療計画システムの例を使って具体的に説明していきます。
このシステムが行う行為は、放射線治療の診断、計画をたてることです。この行為は、医師の医学的な判断が必要とされる行為でもあります。そして、放射線の量を間違えて提案したら、患者の身体に危険が及びます。これを患者の診察の度に繰り返し行っていれば「医業」となってしまいますよね。
もっとも、現時点で、AIプログラムが「医業」にあたる行為をすることは禁止されていません。
放射線治療計画システムについても、現状において、機器だけに判断を任せて医師が全く関与していないということはありません。
このように機器による判断を参考にすることはあっても、患者の生命や身体を守るための最終決定は医師が行っているため、現時点でAIプログラムによる医業を禁止する必要性はないと考えられています。
この点について厚生省は、AIプログラムの行為は「医業」にあたるが、そのプログラムはあくまで支援ツールにすぎないとして、以下の2つの点を満たせば「医業」にあたる行為でも禁止しなくてよいとしています。
- 診断治療の主体は医師であること
- 最終責任も医師が負うこと
以上のように、厚労省の見解によれば、医療現場でAIプログラムを利用することは、「医業」に当たりますが、医師が主体になって判断し、最終責任者となるのであれば、AIプログラムによる医業が禁止されることはありません。
最後に、これまでの視点とは異なり、AIプログラムがディープラーニングなどで使うデータの扱いについて、注意すべきルールを解説していきます。
5 個人情報保護法
AIに大量の医療データを学ばせようとする場合、病院の診療データなどには患者個人の情報が多く含まれているため、その情報をどう保護すべきかが問題となります。
現在、「医療ビッグデータ」が構築され、運用が開始されていることからも、この点は特に問題になってくるといえます。
ここにいう「医療ビッグデータ」とは、個人の医療情報を集めたものをいい、集められる情報は、問診情報、各種検査結果、画像、薬の処方、手術の記録など様々な種類のものがあります。
「医療ビッグデータ」は、医療の質を向上させることを目的として、企業や病院に提供されることが想定されているため、「個人情報」との関係で特に問題となるわけです。
近時、「医療ビッグデータ」を有効に活用するために、「医療保険プラットフォーム」を作ることが進められています。
(1)医療保険プラットフォーム
「医療保険プラットフォーム」とは、個人の医療データが詰まった「医療ビックデータ」を活用して、医療機関や保険者、研究者、民間などが活用できるようにするとともに、国民の健康管理にも役立てるような情報を集めた場所のことをいいます。
国によって「医療保険プラットフォーム」の事業として具体的に検討されている事業は以下の4つになります。
- ビックデータの管理など
- 第三者へのデータ提供の充実など
- 都道府県等によるビックデータの活用の支援
- 研究者等によるビックデータの活用支援
このように、「医療保険プラットフォーム」については、データを活用した様々な事業が検討されています。もっとも、活用されるデータの中には、個人情報も多く含まれています。そのような個人情報を扱うことについてどのようなことに注意しなければならないのでしょうか。
(2)個人情報保護法による規制
「医療保険プラットフォーム」で取り扱う大量のデータの中には「個人情報」も含まれます。たとえば、特定個人の病歴などが記載されているデータは、「個人情報」のうちでも特に人には知られたくない個人情報であるといえ、このような情報を「要配慮個人情報」といいます。
「要配慮個人情報」とは、人のプライバシーのなかでもとりわけ重要で、安易に人に知られたくないような情報のことをいいます。具体的には、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実などが挙げられます。
そのため、「要配慮個人情報」を扱うためには、原則として、本人の同意が必要となります。
もっとも、例外的に本人の同意なく、「要配慮個人情報」を使える場合があります。
特に、医療分野でAIプログラムを導入する局面で重要となるのは、以下の2つの場合となります。
- データの匿名化
- 研究機関などの学術目的の利用
①データの匿名化
「データの匿名化」とは、氏名、生年月日、住所、個人識別符号など、個人を識別する情報を取り除くことで、特定の個人を識別できないようにすることをいいます。「医療保険プラットフォーム」で要配慮個人情報を扱う場合には、病歴などの情報を、第三者に提供しても大丈夫なように、名前を表示しないなどの工夫が必要になります。
ここに、顔写真などの情報も一緒に含まれていた場合は、目の部分をぼかすなどして個人を特定できないようにすれば匿名化されていると認められる可能性があります。
また、医療関係者など、自分たちだけが知ることのできる患者の特徴などの情報によって個人が識別できる場合には、その情報を記載しないようにするなどの配慮をするか、それが難しいようであれば、患者本人の同意が必要になると考えられます。
②研究機関などの学術目的の利用
大学や学術研究機関が、学術研究目的で利用するのであれば、その情報が「要配慮個人情報」であっても、本人の同意は不要であるため、個人情報の利用目的の特定・利用目的の本人への通知といった義務を課されることもありません。
「医療保険プラットフォーム」の事業でいえば、集められたデータのうち、「要配慮個人情報」にあたる個人の病歴などのデータを、本人の同意なく利用して論文を執筆することが挙げられます。
このように、「医療保険プラットフォーム」のように「医療ビッグデータ」を活用する際には、個人情報の扱いに慎重にならなくてはなりません。
もっとも、個人情報の取り扱いについては、あくまで保護することを図りつつも、その利用を促進させるために、以下で解説する「次世代医療基盤整備法」という法律が2018年に施行されています。
(3)次世代医療基盤整備法
「次世代医療基盤整備法」とは、電子カルテに代表されるように医療現場にあるデジタル化した膨大なデータを医療分野の研究などにスムーズに役立てることを可能にするための法律です。
同法の主なポイントは、以下の2点です。
- 認定匿名加工医療情報作成事業者の認定制度の創設
- 本人の同意なしに認定匿名加工医療情報作成事業者に医療情報を提供できること
①認定匿名加工医療情報作成事業者の認定制度の創設
大量の医療情報を匿名化できる技術があり、高度なセキュリティーの備えなどを確保している事業者は、国から「認定匿名加工医療情報作成事業者」として認定を受けられることとなりました。
②本人の同意なしに認定匿名加工医療情報作成事業者に医療情報を提供できること
本人が提供に反対しないかぎり、同意を得ていなくとも、認定匿名加工医療情報作成事業者に対して医療情報を提供できることとなりました。
このように、次世代医療基盤整備法の施行これによって、カルテなど医療機関の持つ患者個人の情報を、大学や企業における医療分野の研究開発で活用しやすくなりました。
患者個人に対し、医療情報の提供についていちいち同意を求める必要がなくなったため、データを迅速に集めることができるようになりました。
また、患者からすれば、自分の医療情報が自由に使われることに強い抵抗を感じるのであれば、いつでも拒否することができます。
6 小括
AI技術が医師に完全に取って代わってしまうことはできませんが、AI技術はすでに様々な医療分野で利用されています。
もっとも、法整備がまだ行き届いていなかったり、AI技術の革新が必要であるなどの理由で、現時点では利用できない領域も存在し、このような領域では、近い将来にAI技術が利用されるようになることが期待されています。
このような領域にはまだまだビジネスチャンスがあると考えられますので、これからこの分野に参入したいと考える事業者は、少なくとも現状の規制をきちんと理解しておくことが必要になるとともに、独自での理解が困難な場合は、ITに詳しい専門家に相談するなどして現状の規制の理解に努めることも選択肢の一つだといえます。
7 まとめ
これまでの解説をまとめると、以下のようになります。
- AIの導入は、①ゲノム医療、②画像診断、③診断・治療、④医薬品の開発、⑤介護・認知症、⑥手術の6つの分野で推奨されている
- AIを医療分野に導入する際に注意すべき規制は、①「医療機器」に関する規制、②医業に関する規制、③個人情報保護法の3つである
- 「医療機器」にあたる場合、①機器の製造・販売の許可、②個別に安全性や有効性を確認する承認の2点が必要になる
- AIを活用したプログラムが、「医療機器」と認められるには、①治療・診断への寄与度、②機能障害が生じた場合の人命・健康に対するリスクの蓋然性の2点が必要である
- AIを活用したプログラムの医療現場での使用は、「医業」にあたるが、①診断治療の主体は医師、②最終責任も医師の2点を満たすので現時点で禁止はされない
- 「医療ビッグデータ」活用のために、「医療保険プラットフォーム」を作ることが進められている
- 「要配慮個人情報」を扱うのには、原則として本人の同意が必要だが、例外的に①データの匿名化、②研究機関などの学術目的の利用の2つの場合は本人の同意は不要になる
- AIなどのITの発展のために、個人情報の保護とその利用の簡易化を内容とする「次世代医療基盤整備法」が2018年から施行された
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。