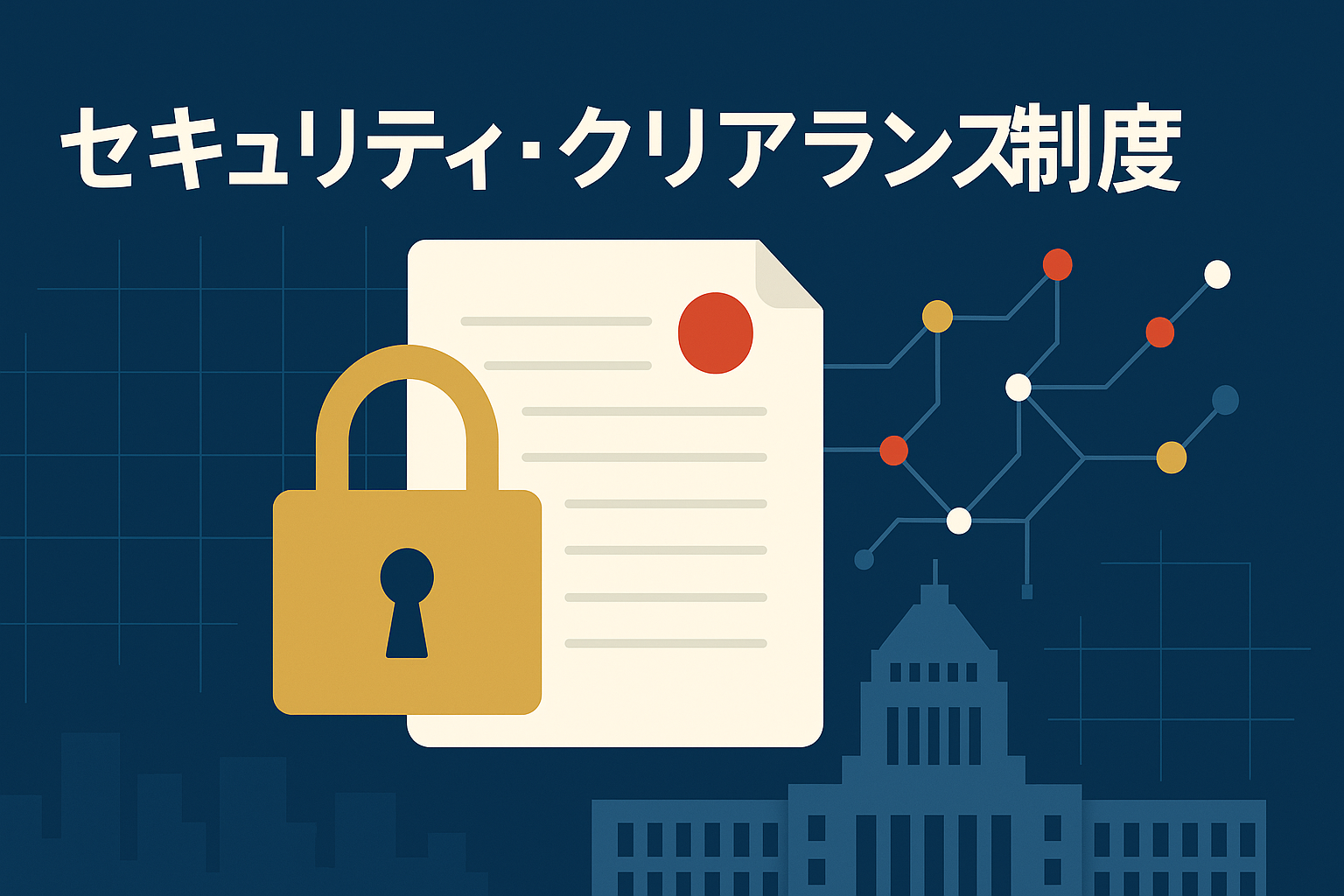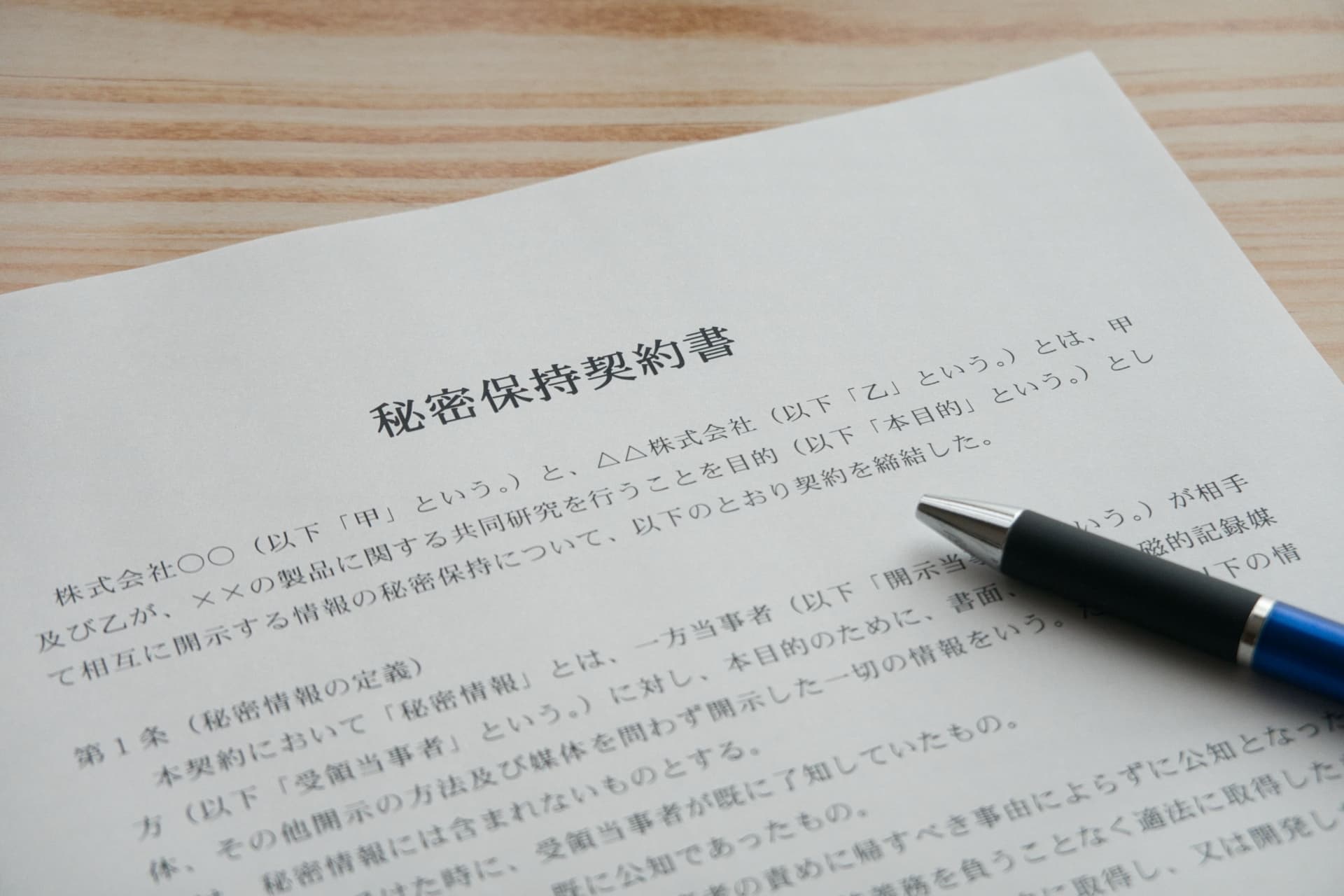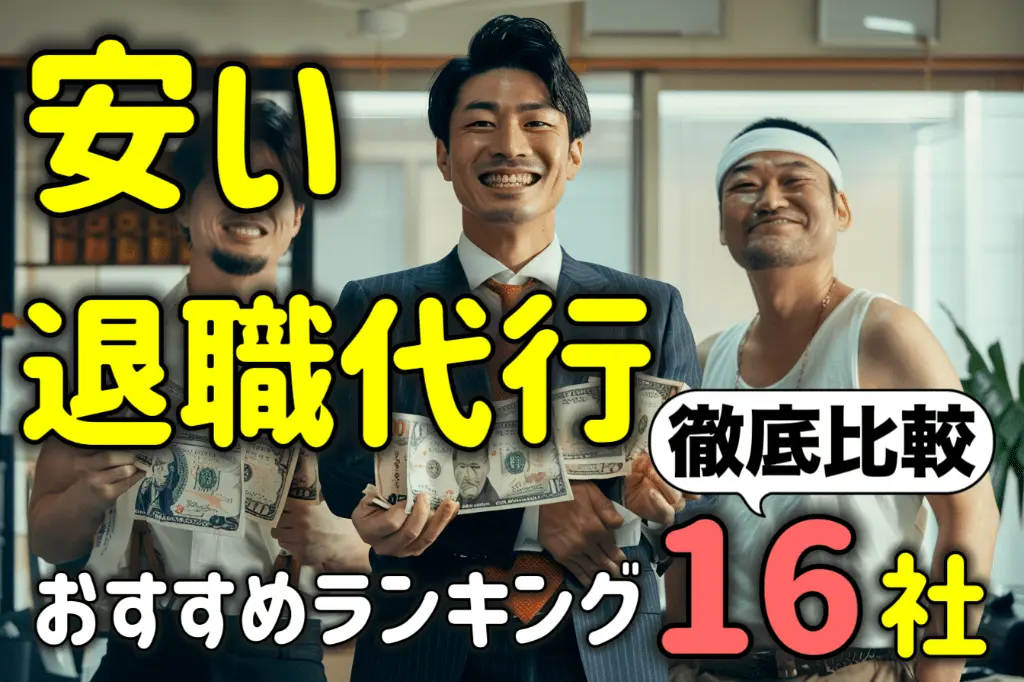警備にドローンを活用する際注意すべき3つの法律規制を弁護士が解説

はじめに
昨今、さまざまな分野でドローンの活用が広がってきており、その広がりは警備業界にも及んでいます。警備にドローンを活用できれば、人手不足の克服にも繋がるため業界からもドローンに対する期待が高まっています。
もっとも、警備のためであるとはいえ、ドローンを飛ばす以上、そこには守らなければならないさまざまなルールがあります。その代表的なルールとして「航空法」が挙げられます。
そこで今回は、警備システムにドローンを導入するにあたり、必ず知っておかなければならない「航空法」の規制について、ITに詳しい弁護士がわかりやすく解説します。
1 警備システムにおけるドローンの導入
軽量で小型なドローンは、従来警備員の目が届かない高所などを警備することを可能にします。また、進化するAIを併用することにより、不審者の追跡なども可能になり、犯罪の予防にも大きく役立ちます。
このように、警備システムにドローンを導入することには大きな利点があります。
そのため、近年では大手警備会社であるセコム株式会社も警備用ドローンの「セコムドローン」をサービスとして開始しています。セコムドローンは、民間防犯用に作られた監視サービスであり、不審者などを自動で追跡することにより、車のナンバーや不審者の顔などを撮影することを可能としています。
このほかにも、同社がドローンによる巡回警備サービスを開始していることなどからもわかるように、警備システムにドローンを導入するサービスが徐々に浸透しつつあります。
もっとも、警備目的とはいえ、ドローンをいつでも好き勝手に飛ばすことはできません。ドローンを飛ばすためには、「航空法」という法律が定めるルールをきちんと守ることが必要です。
2 航空法による法律規制
警備にドローンを活用する場合には、「航空法」が定めるルールをきちんと確認しておく必要があります。
航空法は、ドローンを含む無人航空機の飛行について、以下のように「場所(飛行禁止区域)」と「方法(飛ばし方)」について規制しています。
(1)飛行「場所」の規制(飛行禁止区域)
ドローンは空を飛んで移動するため、飛行機やヘリコプターなどの航空機や、周辺の建物・人などに衝突する危険があります。
そのため、航空法は、以下の2つの場所でドローンを飛ばすことを原則として禁止しています。
- 航空機の安全に影響を及ぼすような場所
- 人や建物の密集地域(DID地区)
①航空機の安全に影響を及ぼすような場所
航空法において、航空機の安全に影響を及ぼすような場所とされているのは、以下の2つです。
- 空港周辺
- 高度150m以上の空域
これらの場所でドローンを飛ばしてしまうと、飛行機の航行の妨害になるおそれがあるため、ドローンの飛行が規制されています。
もっとも、事前に国の許可を受けていれば、これらの場所でもドローンを飛ばすことができます。
②人や建物の密集地域(DID地区)
「人や建物の密集地域(DID地区)」とは、人口が集中している地域のことをいいます。DID地区にあたるかどうかは国土地理院の「人口集中地区マップ」で確認することができます。
上の地図は、東京近郊を示す人口集中地区マップです。赤く色がついている地域がDID地区にあたります。
これらの場所でドローンを飛ばすためには、事前に国の許可を得る必要があります。
警備でドローンを使う場合、飛ばそうとする場所が以上で見た2つの場所にあたるかどうかをきちんと確認する必要があります。仮に、以上の2つの場所にあたる場合、事前に国の許可を受けなければなりません。
もっとも、建物内を警備する目的で建物内に限ってドローンを飛ばす場合には、航空法上の規制を受けませんので、国の許可を受けることなくドローンを飛ばすことができます。
(2)飛行「方法」の規制
飛行場所の規制をクリアさえしていれば、あとは自由にドローンを飛ばすことができるかというとそうではありません。誤った飛ばし方をすると、危険な場合もあるため、航空法は、飛行方法(飛ばし方)についても規制しています。
具体的には、以下の6つのルールを守って飛ばさなければなりません。
仮に、これらのルールに反する形でドローンを飛ばす場合は、事前に国の承認を得ておく必要があります。
- 日中(日の出から日没までの間)に飛ばすこと(★)
- ドローンや周辺を直接目で見て常に監視すること(★)
- ドローンと人や物件との距離を30m以上に保つこと(★)
- 祭りや展示会など、人の多く集まるイベントの上空で飛ばさないこと
- 爆発物などの危険物を輸送しないこと
- ドローンから物を投下しないこと
これらの中でも、以下では警備でドローンを使う際に特に問題となる以下の3つのルールに絞って解説していきたいと思います。
①日中(日の出から日没までの間)に飛ばすこと
飛んでいる位置や状態を正確に把握するために、ドローンは日中に飛ばす必要があります。そのため、日没後から日の出までの夜間に、警備をする目的でドローンを飛ばす場合には国の承認が必要になります。
②ドローンや周辺を直接目で見て常に監視すること(目視外飛行)
安全にドローンを飛ばすには、周囲の状況を正確に把握できていなければなりません。そのため、ドローンの操縦者は、自分の目で直接ドローンの位置や状態を確認できなければなりません。
このように、ドローンの操縦者が直接自分の目でドローンの位置や状態を確認できなければならないため、補助者が見ていたというのではこの条件を満たしません。
また、ドローンに搭載されているカメラなどから送信される映像をモニター越しに見ながら操縦するというのも、本人が直接目でドローンを確認しているわけではないためこの条件を満たしません。
これらの場合は、いずれも「目視外飛行」にあたるため、国の承認を得る必要があります。
一般に、警備でドローンを使う場合、モニターの映像を見ながらドローンを飛ばすことが想定されているため、「目視外飛行」にあたります。そのため、事前に国の承認を得る必要があります。
この承認を受けるためには、「機体の基準」、「操縦の技能についての基準」、「安全確保の体制についての基準」をそれぞれ満たす必要があります。
「機体の基準」としては、自動操縦システムを装備し、機体のカメラで機外の様子を監視できることなどが求められます。
「操縦の技能についての基準」としては、モニターを通して遠隔操作によって意図した飛行経路を維持しながら飛行でき、経路周辺において安全に着陸できることなどが求められます。
「安全確保の体制についての基準」としては、飛行経路全体を見渡せる位置に、ドローンの飛行状況などを常に監視できる補助者を配置することなどが求められます。
もっとも、補助者については、配置しないことも認められていますが、その場合、さらに厳しい条件が追加で課されることになります。
※「目視外飛行」の承認基準について、詳しく知りたい方は、「ドローンを用いたソーラーパネル点検の法律規制を弁護士が5分で解説」をご覧ください。
③ドローンと人や物件との距離を30m以上に保つこと
警備でドローンを使う場合には、ドローンが人や物に接近する可能性があります。そのため、航空法では、人や物に危害を及ぼさないように、ドローンの飛行は人や物との間に30m以上の距離を確保しなければならないとされています。
仮に、30m未満の距離でドローンを飛ばす場合には、国の承認を得る必要があります。
もっとも、ここでいう「人」とは、ドローンを飛ばす関係者以外の者を指し、また、「物件」についてもドローンを飛ばす者やその関係者が管理する物件以外のものを指します。
たとえば、自社の工場を警備する目的でドローンを飛ばす場合、工場で働く人はドローンを飛ばす関係者にあたるため、30m以内の距離でドローンを飛ばしても国の承認を得る必要はありません。また、自社の工場内に存在する物は、ドローンを飛ばす者が管理する物件にあたるため、同じように国の承認を得る必要はありません。
④小括
このように、航空法は「飛行場所(飛行禁止区域)」と「飛行方法(飛ばし方)」について一定のルールを設けています。これらのルールに反する形でドローンを飛ばす場合は、国の承認を得る必要があります。
もっとも、ドローンを警備に利用する場合は、既に見たように、目視外飛行が想定されていると考えられるため、ほとんどの場合で国の承認が必要になると考えられます。
3 航空法に違反した場合の罰則(ペナルティ)
先に見たように、ドローンの飛行場所や飛行方法には一定のルールがあります。
これらのルールに違反すると、航空法違反となり、
- 最大50万円の罰金
が科せられる可能性があります。
罰金といっても刑罰の一種であるため、科されると前科がつきます。
このような事態にならないためにも、警備用ドローンを飛ばす際にはあらかじめ国の許可・承認が必要となるのかどうかをきちんと確認し、適切にドローンを飛ばすことが必要です。
4 航空法上の許可・承認申請のやり方
先に見たとおり、警備でドローンを使う場合は、目視外飛行となることが通常であるため、国の承認を受ける必要があります。
国の許可や承認を受ける必要がある場合、まずは、国土交通大臣に対して承認の申請を行う必要があります。
(1)申請の種類
申請をするにあたっては、申請の種類を正しく理解して、自らの飛行予定に合った方法で申請をする必要があります。
ドローンの飛行許可申請には、大きく以下の2つの方法が用意されています。
- 個別申請
- 包括申請
①個別申請
「個別申請」は、もっとも基本的な申請方法です。
あらかじめ飛行の日時が決まっていて、飛行の経路(場所)も特定されている場合には個別申請を利用することになります。
②包括申請
飛行の日時や経路が特定しておらず、一定の期間内において飛行の許可や承認を受けたい場合や、異なる複数の場所で飛行を行いたい場合には、「包括申請」を利用することができます。
たとえば、「平成31年2月○○日から同年●月●日まで」といった形で、飛行ができる期間を設定して申請する方法を「期間包括申請」といい、「東京都渋谷区全域」といった形で、飛行場所に範囲を設定して申請する方法を「飛行経路包括申請」といいます。
期間包括申請によって許可・承認を受ければ、その期間内であれば繰り返しドローンを飛ばすことができますし、この申請に対しては、最大で1年間の許可・承認が与えられます。
以上のような申請種類を正しく理解した上で、自社の利用方法に合った申請種類を選択して申請を行うことになります。
(2)申請書を作成する際のポイント
許可や承認を受けるためには、一定の基準をみたしていることが必要です。
ここでは、警備でドローンを使うための許可申請で特に重要となる以下の2つのポイントについて、見ていきたいと思います。
- 操縦者の技能
- 飛行マニュアル・安全飛行の意識と体制
①操縦者の技能
警備でドローンを利用する場合には、繰り返しになりますが、目視外飛行にあたることが通常です。そのため、操縦者において、目視外飛行のための技能が備わっていることを証明する必要があります。
具体的には、
- モニターを見ながら、遠隔操作により、意図した飛行経路を維持しながらドローンを飛ばすことができること
- 飛行経路周辺においてドローンを安全に着陸させることができること
を証明する資料を添付する必要があります。
また、その際に補助者を配置しないのであれば、以上に加えて、遠隔操作などに関し座学や実技による教育訓練を少なくとも10時間以上受けていることを証明する必要があります。
訓練の内容が次のようなものであったことを証明できれば、承認を受けられやすくなるということがいえます。
- 飛行中に、カメラ等からの情報により、飛行経路直下又はその周辺における第三者の有無等、異常状態を適切に評価できるようになるための訓練
- 把握した異常状態に対し、現在の飛行地点や機体の状況を踏まえて、最も安全な運航方法を迅速に判断できるようになるための訓練
- 判断した方法により遠隔から適切に操作できるようになるための訓練
もっとも、これらの訓練を個人から受けるというのは現実的ではないため、実際は、航空局ホームページに掲載されている団体などが行った技能認証を受け、その上で技能認証を受けたことを証明する書類の写しを申請書に添付することになります。
なお、技能認証団体によって、目視外飛行の技能認証を受けられる団体とそうでない団体がありますので、事前にホームページなどで確認をした上で技能認証を受けることをお勧めします。
※技能認証を受けられる団体について、詳しく知りたい方は、国土交通省のHPに掲載されている「航空局ホームページに掲載されている講習団体を管理する団体」をご覧ください。
②飛行マニュアル・安全飛行の意識と体制
申請に際して、あらかじめ飛行マニュアルが作られていて、安全にドローンを飛ばす意識や体制が整っていることが必要です。
マニュアルについては、航空局のホームページにある航空局の標準マニュアルか、航空局のホームページに記載されている団体等が作成したマニュアルを使用して作成することになります。
※飛行マニュアルについて、詳しく知りたい方は、「ドローンの飛行許可申請のやり方は?5つのポイントを弁護士が解説!」をご覧ください。
(3)申請書の提出
飛行許可申請書は、飛行を開始する予定日の10開庁日前までに、空港事務所もしくは航空局に提出する必要があります。
提出方法としては、インターネットを利用したオンラインでの提出と直接記入した申請書を郵送または窓口に持参して提出する方法があります。
オンラインで申請をする場合は、「ドローン情報基盤システム」を利用することになります。ドローン情報基盤システムにアクセスして、質問に答えていくと自動的に申請書が完成するという形になっています。回答方法に複雑な点もないため、簡単に申請手続きが行えるようになっています。
オンライン申請を利用しないで、記入した申請書を提出する形で申請する場合は、指定された申請方式に従って作成した申請書を郵送または指定された窓口に直接提出することになります。
※申請書の提出先などを詳しく知りたい方は、「ドローンの飛行許可申請のやり方は?5つのポイントを弁護士が解説!」をご覧ください。
5 小括
警備目的であるとはいえ、ドローンを飛ばすことに変わりはありません。そのため、航空法などの規制を正しく理解していなければ、ペナルティを科せられる可能性もあります。加えて、ドローンを迅速に警備システムに導入するためにも、許可や承認を得るためのポイントを正しく理解しておくことが無用なコストを抑えることにもつながります。
6 まとめ
これまでの解説をまとめると、以下のとおりです。
- ドローンを飛ばすために許可が必要となるのは、①空港周辺の空域、②高度150m以上の空域、③人口密集地(DID地区)での飛行である
- 警備にドローンを用いる場合に特に問題となる規制は、①日中飛行、②目視外飛行、③ドローンと人や物件との距離を30m以上に保つことの3つである
- ドローンを目視外飛行させるための承認基準は、①機体の基準、②操縦の技能についての基準、③安全確保の体制についての基準の3つである
- 航空法に違反した場合、最大50万円の罰金を科される可能性がある
- 許可や承認の申請方式には、大きく分けて①個別申請と②包括申請がある
- 警備でドローンを使うための許可申請でポイントとなるのは、①操縦者の技能、②飛行マニュアル・安全飛行の意識と体制である
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。