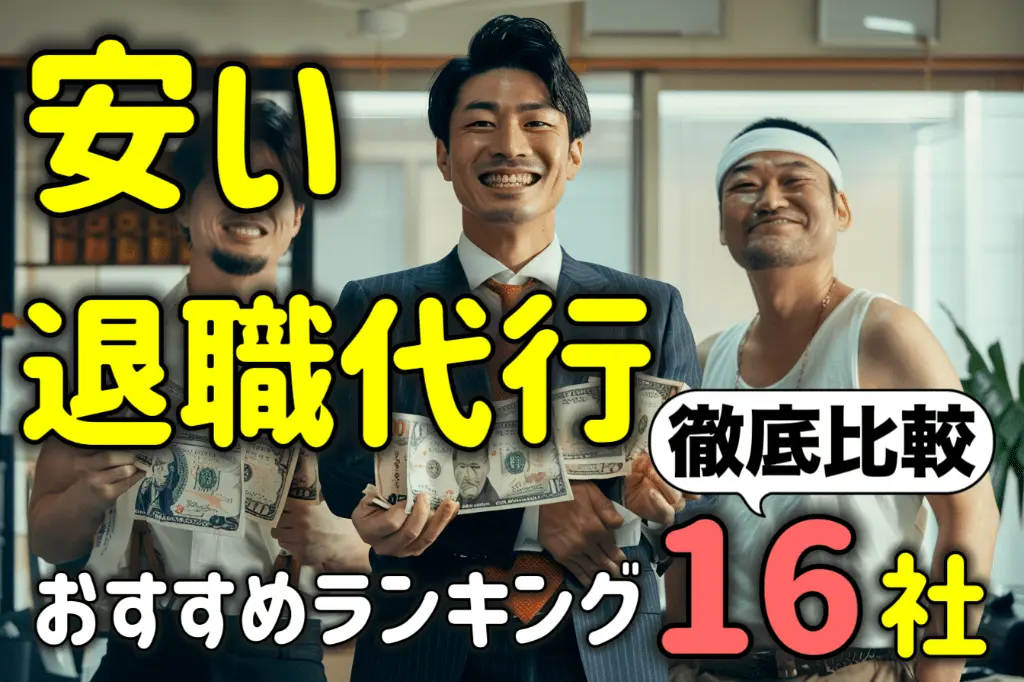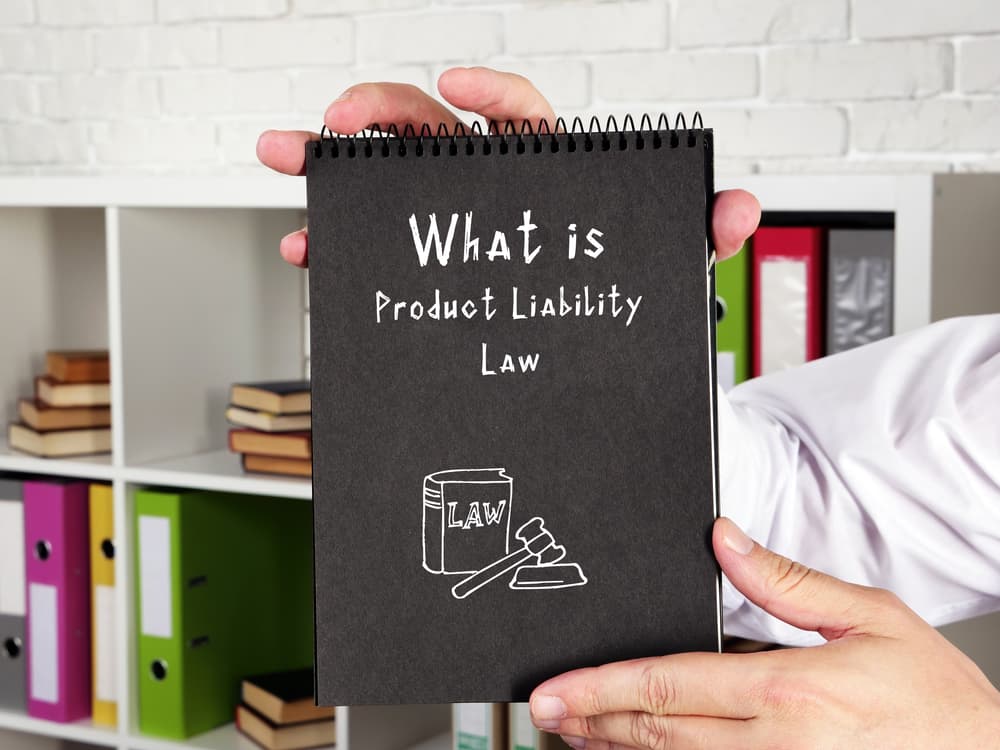後払い決済サービスに対する割賦販売法上の2つの規制を弁護士が解説

はじめに
後払い決済は、クレジットカード情報を入力する必要がなく、また、商品等を先に受け取ることができるため、一般消費者にとっては安心な決済方法の一つだといえます。
通販やECサイトを中心に決済手段として導入されており、そのニーズも高まっているため、新規参入を検討している事業者もいらっしゃるのではないでしょうか。
もっとも、後払い決済サービスを始めるにあたっては、いくつかの法規制をきちんと確認しておく必要があります。
今回は、後払い決済サービスへの法規制について、弁護士がわかりやすく解説します。
この記事を執筆したのは

- 弁護士・中小企業診断士 勝部 泰之
- 注力:知的財産権・著作権/ライセンス、ブロックチェーン、データ・AI法務
GWU Law LL.M.(知的財産法)
事業の成長とリスクを両立する実務寄りの助言に注力しています。 - 詳しいプロフィールはこちら
1 後払い決済サービスの仕組み
「後払い決済サービス」は、商品の購入時に代金を支払う必要がなく、その後に代金を支払うことを可能とする決済サービスです。
後払い決済サービスは、一般的に、以下のような流れでサービスが提供されます。
-
- 商品の購入(後払い決済を選択)
↓
-
- 後払い決済業者による商品代金の立替払い、販売店による決済手数料の支払い
↓
-
- 商品の発送
↓
- 利用者による支払い
このように、後払い決済サービスは、販売店から支払われる決済手数料によって収益を上げる事業です。
クレジットカードを持っていない人でも利用することができ、また、クレジットカード情報などを提供する必要もないため、情報漏えいのリスクも低く、安心して利用できる決済サービスの一つとなっています。
2 後払い決済サービスへの法規制
後払い決済サービスとの関係で知っておかなければならない法律が「割賦販売法」です。
具体的には、以下の2点を押さえておく必要があります。
(1)包括信用購入あっせん
「包括信用購入あっせん」とは、クレジット会社による審査を経て発行されたカードなどを使って、利用者がクレジットを利用することをいいます。
典型例は、クレジットカードです。
利用者はカードなどを用いて、上限の範囲内で繰り返しクレジットのシステムを利用することができ、加盟店で商品などを購入することもできます。
このような包括信用購入あっせんを事業として行う場合、事業者は、経産省に備える包括信用購入あっせん業者登録簿に登録を受ける必要があります。
【割賦販売法31条】
- 包括信用購入あつせんは、経済産業省に備える包括信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人(以下「登録包括信用購入あつせん業者」という。)でなければ、業として営んではならない。
また、包括信用購入あっせん業者が、当該決済サービスに係る加盟店契約の締結を事業として行う場合には、経産省に備える「クレジットカード番号等取扱契約締結事業者」の登録簿に登録を受けることが必要です。
ここでいう「クレジットカード番号等取扱契約締結事業」とは、「加盟店契約の締結」を事業として行うことをいいます。
さらに、包括信用購入あっせん業は、マネーロンダリングやテロ資金供与を規制する犯収法の適用対象にもなっています。
そのため、クレジットカード発行を内容とする契約を締結する際には、利用者に対する取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出などが義務付けられることになります。
(2)個別信用購入あっせん
「個別信用購入あっせん」とは、加盟店で商品などを購入するごとに、その商品を購入するためのクレジットを申し込む方法により利用することをいいます。
たとえば、自動車や携帯電話など、それぞれを購入する際にそのためのクレジットを申し込み、審査を受けたうえで利用するのが「個別信用購入あっせん」です。
個別信用購入あっせんを事業として行う場合も、事業者は、経産省に備える個別信用購入あっせん業者登録簿に登録を受けなければなりません。
【割賦販売法35条の3の23】
- 個別信用購入あつせんは、経済産業省に備える個別信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人(以下「登録個別信用購入あつせん業者」という。)でなければ、業として営んではならない。
3 法規制を回避するためのスキーム
割賦販売法は、「包括信用購入あっせん」および「個別信用購入あっせん」について、いずれも定義に含まない例外的なケースを規定しています。
具体的には、以下にあてはまる場合、当該後払い決済サービスは「包括信用購入あっせん」「個別信用購入あっせん」のいずれにも該当しないことになるため、上記のような登録を受ける必要がなくなります。
-
- 【定義に該当しないケース】
- 利用者と加盟店の間で締結された商品の売買契約から2ヶ月を超えない範囲内で、あらかじめ決められた時期までに決済サービス事業者が利用者から商品代金を受領する場合
たとえば、利用者が7月1日に決済サービスを利用した場合、決済サービス事業者が9月1日中に商品代金を受領することになっていれば(初日不算入の原則)、「2ヶ月を超えない」範囲内で、商品代金を受領しているといえるため、「包括信用購入あっせん」「個別信用購入あっせん」のいずれにも該当しないことになります。
もっとも、定義に該当しない場合であっても、先に見たように、包括与信型のサービスである場合には、犯収法の適用を免れることはできません。
また、加盟店向けのサービスである場合には、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者として、割賦販売法の規制を免れることはできないため、注意が必要です。
犯収法や割賦販売法上の規制を回避するためには、与信審査の仕組みを個別与信型に設計することが必要になると考えられます。
4 まとめ
後払い決済サービスは、原則として、割賦販売法の適用対象となるため、事業を始めるにあたっては、所定の登録手続きを行う必要があります。
もっとも、与信審査の仕組みによっては、法規制を回避することも可能だと考えられるため、その点も考慮のうえ、サービスを設計していくことが大切です。
弊所は、ビジネスモデルのブラッシュアップから法規制に関するリーガルチェック、利用規約等の作成等にも対応しております。
弊所サービスの詳細や見積もり等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。