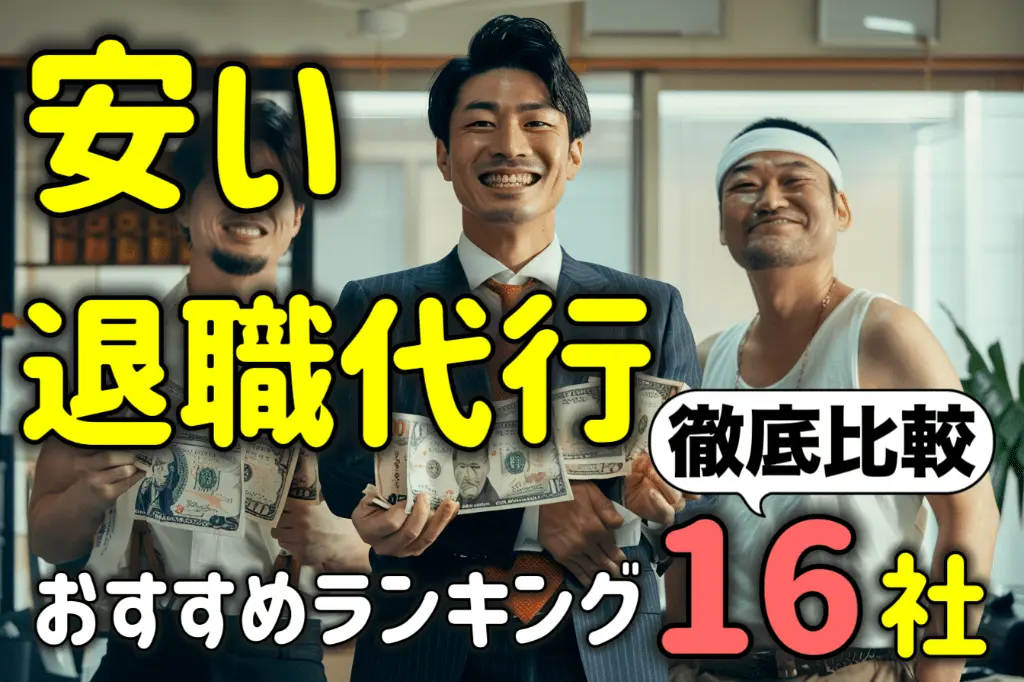かっぱ寿司の営業秘密侵害問題の焦点である3要件を弁護士が解説!

はじめに
回転寿司チェーン「かっぱ寿司」を運営するカッパ・クリエイト社の営業秘密侵害問題。
同社社長は、競合他社「はま寿司」の売り上げデータなどを元同僚から受け取ったことを認めており、ここでいうデータが「営業秘密」にあたるかどうかが専らの焦点となっています。
回転ずし店大手「かっぱ寿司」を運営するカッパ・クリエイトの田辺公己社長が同業他社の売り上げデータなどを不正に受け取ったとされる問題で、警視庁は不正競争防止法違反の疑いで捜査を本格化した。データが「営業秘密」にあたるかが焦点だ。中途退職者が関わる営業秘密の漏洩問題は増えており、フォレンジック調査など企業による自衛の動きも広がる。
日経新聞より
今回は、この「営業秘密」について、その該当性を判断するための要件を中心に弁護士がわかりやすく解説します。
1 営業秘密の3つの要件

不正競争防止法は、企業に係る「営業秘密」を不正に取得したり使用したりすることを禁止しており、違反者は罰則の対象となります。
ここでいう「営業秘密」とは、以下の3つの要件をすべて満たす情報をいいます。
- 秘密として管理されていること
- 事業等に有用なこと
- 公然と知られていないこと
今回のカッパ・クリエイト社による一連の問題では、同社社長が元同僚から受け取ったとされる売り上げデータなどが、ここでいう「営業秘密」にあたるかどうかが焦点となっているわけです。
2 秘密として管理されていること|秘密管理性

「秘密管理性」とは、その情報が客観的に「秘密」として管理されていることをいいます。営業秘密に係る3要件のなかでも、もっとも多く問題となるのがこの要件です。
秘密管理性が認められるかどうかは、言葉のとおり、情報が「客観的に秘密として管理されているかどうか」という観点から判断されます。
単に企業にとって秘匿性が高いというだけでは、秘密管理性が認められない可能性があります。
その情報が会社にとって秘匿性の高い情報であるということが、従業員等に対し客観的に示されていることが必要なのです。
たとえば、パソコン内に保存されているデータにアクセス制限を設けたり、秘匿性の高い書類にマル秘表示などを付しておくことが挙げられます。
秘匿性が高いということが従業員等に客観的に示されていて、そのことを踏まえた管理方法が採られていれば、秘密管理性が認められる可能性は高いといっていいでしょう。
3 事業等に有用なこと|有用性
「有用性」とは、その情報が技術上または営業上有用であることをいいます。
事業等においてその情報が有用であるかどうかは、客観的に判断されます。
とはいえ、秘密管理性(上記要件1)、非公知性(上記要件3)が認められる情報については、有用性も認められることが多いといえます。
裁判においても、秘密管理性と非公知性を満たす情報については、比較的有用性が認められやすい傾向にあります。
4 公然と知られていないこと|非公知性
「非公知性」とは、その情報が公然と知られていないことをいいます。
具体的には、「一般的に知られていない状態」または「簡単に知ることができない状態」であることが必要だとされています。
たとえば、一般に入手することが可能な書籍等に記載されていたり、インターネット上で広く公開されていたりするような情報は、「非公知性」が認められません。
5 営業秘密を侵害した場合のペナルティ
自社の営業秘密を不正に取得されたり使用されたりした場合、事業者は以下のような措置を講じることが可能です。
(1)民事的措置
民事的措置としては、以下の3つが挙げられます。
- 差止め請求
- 損害賠償請求
- 信用回復措置請求
①差止め請求
営業秘密の侵害行為によって、営業上の利益を害され、また、害されるおそれがある場合、事業者はその行為者に対して、行為の差し止めを請求することができます。
②損害賠償請求
事業者は、営業秘密の侵害行為により損害を被った場合、その行為者に対して損害賠償を請求することができます。
③信用回復措置請求
営業秘密の侵害行為によって、営業上の信用を害された場合、事業者はその行為者に対して、信用を回復するために必要な措置を取るよう請求することができます。
たとえば、「謝罪広告」や「取引先への謝罪文の発送」などが挙げられます。
(2)刑事的措置
不正競争防止法は、一定の行為を「営業秘密侵害罪」として、刑事罰の対象としています。
具体的には、不正な手段によって営業秘密を取得したり、または、自らが使用したり第三者に開示したりする行為は、営業秘密侵害罪に該当します。
営業秘密侵害罪に対しては、
- 最大10年の懲役
- 最大2000万円の罰金
のいずれか、または両方が科される可能性があります。
さらに、事業者が法人である場合には、違反行為者とは別に、法人についても、最大5億円の罰金が科される可能性があります。
6 まとめ
企業において、営業秘密の不正な持ち出しが急増しています。
企業間における競争の激化や人材の流動性の高まりなど、さまざまな要因が背景にあると考えられます。
ケースによっては、事業者が刑事責任を問われる可能性もあります。
そのようなことにならないよう、事業者はいまいちど、社内の秘密管理体制などを見直すなどして、然るべき対策を講じておくことが大切です。
弊所は、ビジネスモデルのブラッシュアップから法規制に関するリーガルチェック、利用規約等の作成等にも対応しております。
弊所サービスの詳細や見積もり等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。