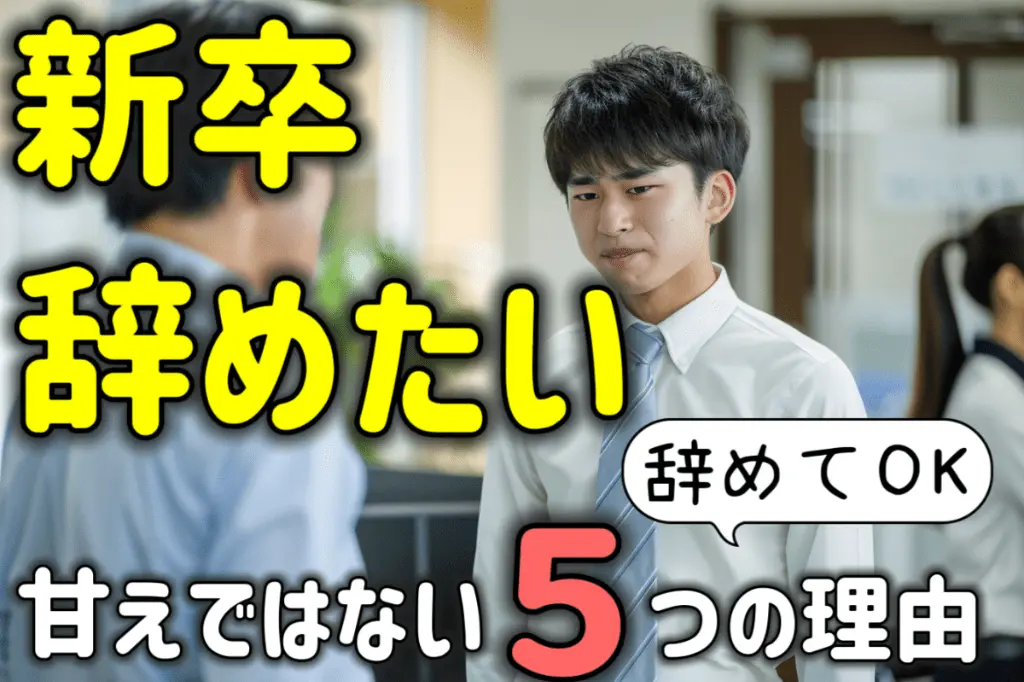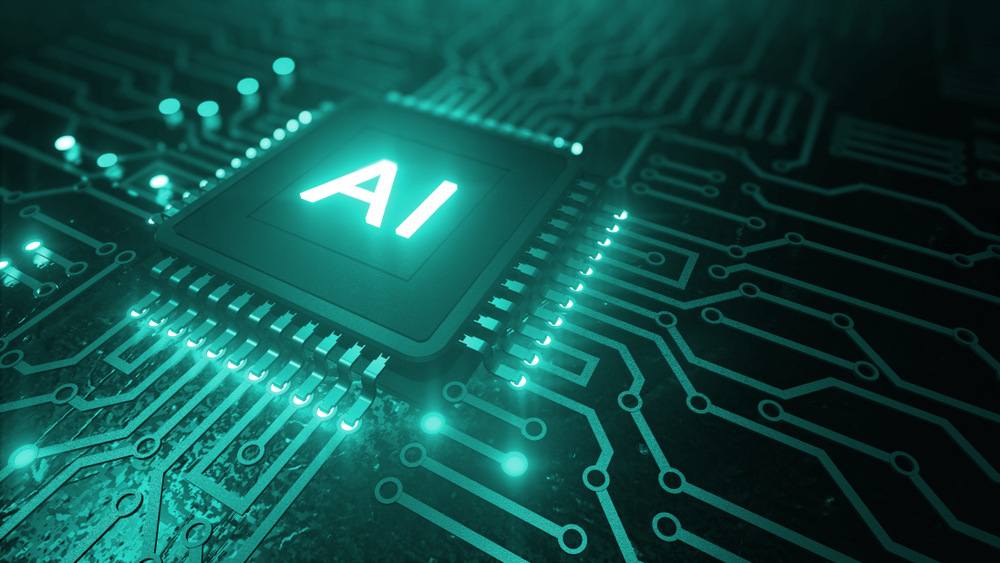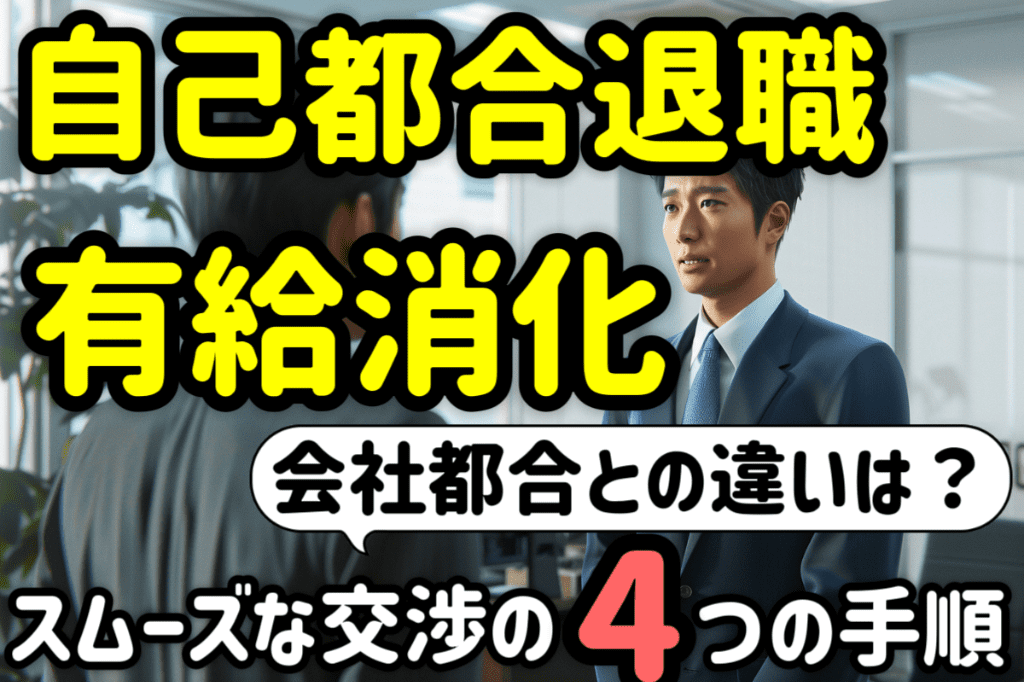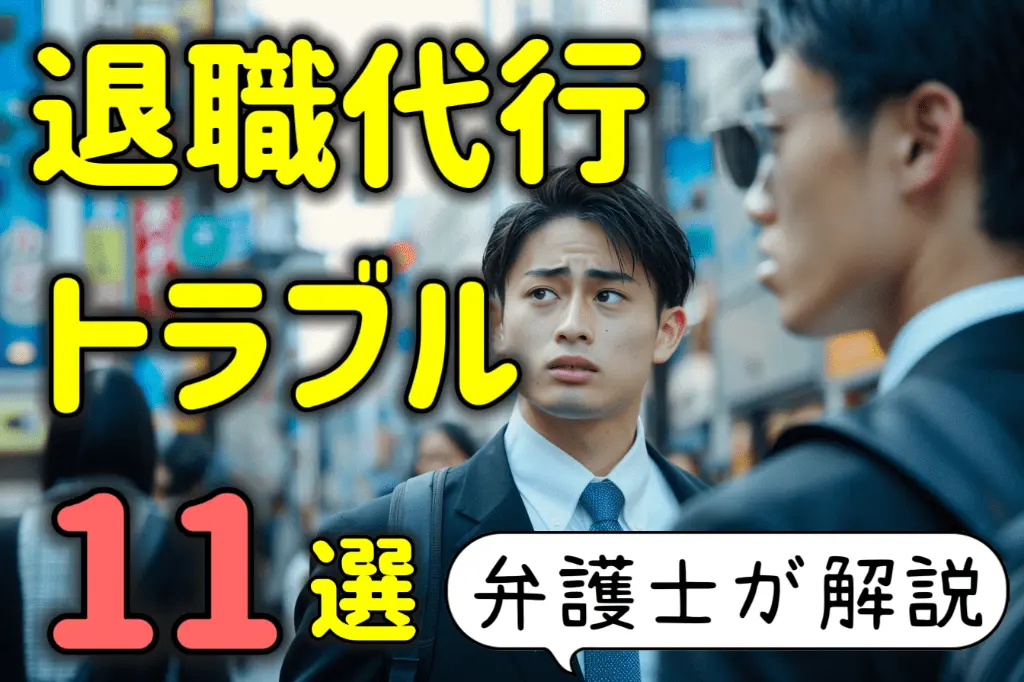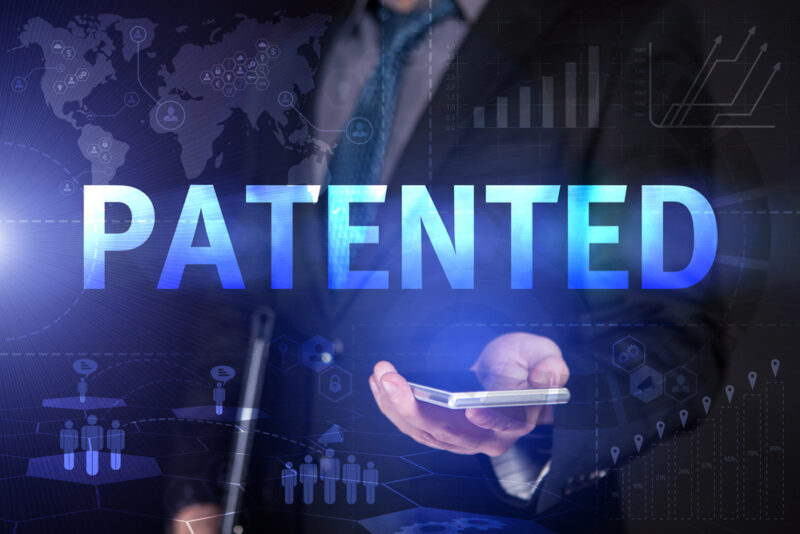スーパー早期審査とは?特許審査期間が短くなる3つの審査制度を解説
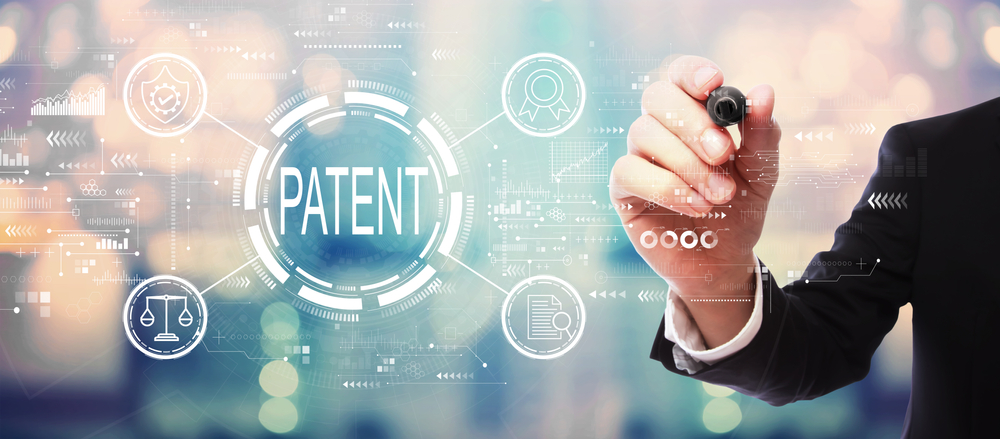
はじめに
発明を生み出したものの資本力に乏しいスタートアップやベンチャー、中小企業にとって、いかに早く特許を取得し市場で存在感を示せるかは死活問題と言っても過言ではありません。
また、スタートアップやベンチャー、中小企業だけでなく、
- 出願した発明を自社製品に使っている事業者
- まだ使っていないが、これからすぐに使いたい事業者
- 日本だけでなく外国にも同じ発明を特許出願している事業者
も同様に、可能な限り早く特許を取得したいですよね。
もっとも、特許を取得するには長い期間がかかるというイメージを持っていらっしゃる方が多いのではないでしょうか。
このようなイメージを持っている方に知って頂きたいのが特許庁が設けている早期審査制度です。
この制度を利用すれば、通常よりも早く審査を受けることが可能になり、特許審査期間を短縮することができます。
そこで今回は、特許の出願から権利化までに必要な期間や審査期間を短縮する方法・要件、新たにベンチャー企業対応になったスーパー早期審査について弁護士が詳しく解説していきます。
この記事を執筆したのは

- 弁護士・中小企業診断士 勝部 泰之
- 注力:知的財産権・著作権/ライセンス、ブロックチェーン、データ・AI法務
GWU Law LL.M.(知的財産法)
事業の成長とリスクを両立する実務寄りの助言に注力しています。 - 詳しいプロフィールはこちら
1 特許の権利化までに必要な期間は?
実際のところ、特許の権利化はどれくらいの期間がかかるのでしょうか。
「特許行政年次報告書2019年版」によれば、2018年度における審査期間は以下の通りでした。
- 一次審査通知(ファーストアクション)までの期間:平均9.3ヶ月(9ヶ月9日)
- 特許査定や拒絶査定などの結論がでるまでの期間:平均14.1ヶ月(1年2ヶ月3日)
これらの期間がどこからどこまでの期間を指しているかや、特許出願から権利化までの流れは、以下の図をご覧ください。
この図からも分かるとおり、出願した発明を審査してもらいたい場合、出願人は、出願から3年以内に特許庁に対して「出願審査請求」という請求をしなければいけません。
もっとも、出願審査請求をしてもすぐに審査が開始されるわけではありません。なぜなら、同じように出願審査請求をされた特許が何件もたまっており、順番に審査されているからです。
特許庁は、審査を通して、「新しい発明ではない」、「この発明は既に特許が取られている」など特許権を与えるのに値しない発明であると判断すれば、出願人に対して「拒絶理由通知」を送付します。逆に特許権を与えるのに値しないと判断すべき事情がなければ、「特許査定」をします。「一次審査通知までの期間(ファーストアクションまでの期間)」は、この特許庁から出願人に対する特許査定や拒絶理由通知がなされるまでの期間のことをいいます。2018年度にはこの一次審査通知までの期間が、平均9.3ヶ月となっています。
拒絶理由通知を受けても、出願人が意見書や補正書を提出することで特許査定になることもあります。こういった手続きを経て、特許査定・拒絶査定などの結論がでます。
出願審査請求から特許査定や拒絶査定などの結論がでるまでの期間が2018年度には平均14.1ヶ月となっています。
もちろん、一度も拒絶理由通知を受けずに特許査定されれば、「結論がでるまでの期間」=「一次審査通知までの期間」となります。
特許査定がでたあと、出願人は一定期間内に「登録料」を納付します。登録料の支払い後、設定登録を受けて、初めて特許権が発生します。
このように、出願審査請求をしてから特許庁から何らかの反応が返ってくるまで、非常に時間がかかるのです。もっとも、冒頭でも触れたように、早く特許権を取得したいという事情がある方もいるでしょう。
そこで設けられたのが早期審査制度です。どれくらい短縮が可能になるかや、利用するための要件について確認していきましょう。
2 審査の種類
特許の審査には、次の4種類があります。
- 通常審査
- 早期審査
- ベンチャー企業対応面接活用早期審査
- スーパー早期審査
1の項目で説明した期間は、①通常審査の場合の平均的な期間です。
①通常審査以外の②~④の早期審査を利用することでどれだけ期間の短縮が可能になるのでしょうか。
2018年の実績では、②の「早期審査」を利用した場合、早期審査の手続き後、平均2.3ヶ月までに一次審査通知がなされています。つまり、出願審査請求と同時に手続きをしてしまえば、通常審査の9.3ヶ月に比べて大幅に審査開始までの期間を短縮することができます。
また、特許査定や拒絶査定などの結論がでるのも、平均5.1ヶ月となっており、通常審査の半分以下の期間となっています。
さらに、④の「スーパー早期審査」を利用した場合は一次審査通知までの期間が平均0.7ヶ月、結論がでるのも平均2.5ヶ月とさらに期間を短縮することができます。
なお、②~④の審査を利用しても、特許庁に対して支払う費用(審査請求料)は変わりません。追加の費用なしで、迅速に特許権が得られるわけですから、これらの審査方法が利用が可能であれば、申請を検討した方がよいでしょう。
もっとも、誰でも利用できるわけではありません。対象者を制限したり、書面の提出など手続きが必要となっているものもあります。
それでは、②~④の審査の詳細について、以降の項目で確認していきましょう。
3 早期審査
(1)早期審査とは
「早期審査」とは、一定の要件の下で、出願人からの申請を受けて、審査を早期に行うものです。早期審査制度の中で最も要件が緩いといえます。
(2)早期審査の要件
早期審査の申請ができるのは、次の4つの要件を満たした場合です。
-
- 出願審査請求がなされていること
- 以下のいずれかに該当する出願であること
・中小企業、個人、大学、公的研究機関等の出願
・外国関連出願(日本以外の外国へも出願している場合)
・実施関連出願(出願人またはライセンシーが特許を使用しているか、2年以内に
使用予定である出願)
・グリーン関連出願(省エネ、CO2削減、省資源、環境負荷低減等の効果を有する
発明についての出願)
・震災復興支援関連出願
・アジア拠点化推進法関連出願
- みなし取り下げとなる予定がないこと
- 代理人が弁理士や弁護士などであること
出願人から出願審査請求がなされないと、特許庁による審査はスタートしません。そのため、出願審査請求がなされていることが早期審査の前提となっています(要件①)。
なお、出願審査請求と早期審査の申請の手続きは同時にすることも可能です。早期審査の手続きについては次の項目で説明します。
また、出願人が行うべき手続きを代理人がやる場合には、スムーズに審査を進めるために、弁理士、弁護士などが代理人にならなければいけません(要件④)。
なお、既に出願した発明に関して優先権を主張して新たな特許出願を行う場合、優先権の基となった出願については、一定期間経過後みなし取り下げが行われます。みなし取り下げとなることが見込まれる場合、早期審査を利用することができません(要件③)。優先権やみなし取り下げが何かよくわからない方は、自身が早期審査の要件を満たしているか弁理士や弁護士などの専門家に相談するのも1つの手です。
(3)早期審査の手続
早期審査の申請をする場合には、指定された様式にしたがって「早期審査に関する事情説明書」を作成して提出します。この手続きは、出願審査請求手続と同時に行ってもかまいません。
この「早期審査に関する事情説明書」には、
- 早期審査の要件に該当すること
- 関連する発明(先行技術)が掲載されている文献
- 先行技術との違い
などを書くことになります。
この手続きは、書面を提出する以外に、オンラインでも提出が可能となっています。書面で提出すると、特許庁側で書面を電子化するという作業が発生してしまうため、一刻も早く特許を取得したいのであれば、オンラインでの提出をおすすめします。
必要な手続きはこれだけです。
「早期審査に関する事情説明書」が提出された場合、特許庁は、早期審査とするかどうかの選定を行います。選定の結果、早期審査の対象としないと判断された場合のみ、出願人に通知されます。逆に、早期審査の対象となった場合は、特に出願人に通知されることなく、通常の案件に優先して速やかに審査が開始されます。
(4)早期審査を利用したい場合の留意点
早期審査を利用したい場合は、特に以下に注意しましょう。
①出願審査請求と同時にする場合
要件の中で説明したように、早期審査を利用できるのは、出願審査請求をすることが前提となっています。出願審査請求と早期審査の手続きは同時に提出可能ですが、出願審査請求がなされていることを確認しやすいように、「早期審査に関する事情説明書」には、【その他】の欄を設けて、「出願審査請求済」であることを記載するようにしましょう。
②審査請求料を支払っていない場合
せっかく、早期審査を行っても、特許庁に審査請求料を支払っていないと、早期審査の対象外となってしまいます。ご注意ください。
4 ベンチャー企業対応面接活用早期審査
(1)ベンチャー企業対応面接活用早期審査とは
「ベンチャー企業対応面接活用早期審査」(以下、「面接活用審査」といいます。)とは、早期審査に加えて、一次審査結果を通知する前に特許庁の審査官が出願人に対して面接を行うことによって、戦略的な特許権の取得につなげるというベンチャー向けの制度です。
面接においては
- 拒絶理由があれば、その概要
- 拒絶理由を解消する方法
- その他ベンチャー企業が利用できる施策
などの説明を審査官から受けることができます。
具体的な流れは、以下の図をご覧ください。
拒絶理由通知の内容は、専門家でなければ読んだだけではわかりづらいものです。直接特許庁で審査官に会って、その内容を説明してもらえるだけではなく、積極的に補正などの対応方法についても教えてもらえるという、出願人にとってはありがたい制度です。
(2)ベンチャー企業対応面接活用早期審査の要件
面接活用審査を利用できるのは以下の4つの要件を満たした場合です。
- 出願審査請求がなされていること
- ベンチャー企業による出願+実施関連出願であること
- みなし取り下げとなる予定がないこと
- 代理人が弁理士や弁護士などであること
早期審査の要件と似ていますが、②の要件が変わっており、面接活用審査を利用できる者が絞られています。
ここでいう「ベンチャー企業」とは、出願人が、次の3つのいずれかに該当する者のことをいいます。
- 事業を開始して10年が経っていない個人事業主
- 従業員数が20人以下+設立後10年が経っていない+大企業に支配されていない法人
- 資本金が3億円以下+設立後10年が経っていない+、大企業に支配されていない法人
なお、商業またはサービス業の場合は、従業員数20人以下ではなく、従業員数5人以下とさらに要件が厳しくなります。
(3)ベンチャー企業対応面接活用早期審査の手続
面接活用審査の手続きは、早期審査の手続きとほぼ同じです。指定された様式にしたがって「早期審査に関する事情説明書」を作成し、特許庁に提出します。
説明書の冒頭に「ベンチャー企業対応面接活用早期審査を希望する」ことを記載することで早期審査の選定とあわせて面接活用審査にするかどうかの選定もあわせて行われます。面接活用審査の対象となった場合は、一次審査結果の通知が行われる前に面接が行われます。
ここまで、通常審査よりも期間が短縮できる「早期審査」と「ベンチャー企業対応面接活用早期審査」について解説してきました。もっとも、さらに短い期間で特許を取得できる「スーパー早期審査」と呼ばれる審査制度があります。
5 スーパー早期審査
(1)スーパー早期審査とは
「スーパー早期審査」とは、2020年4月現在の制度では最短で特許権が得られる早期審査制度のことをいいます。もっとも、特に重要性の高い案件に絞るために、その申請のタイミングや手続きの方法など、要件が最も厳しくなっています。
(2)スーパー早期審査の要件
スーパー早期審査の対象となるのは、以下の4つの要件を満たした場合です。
- 出願審査請求がなされていること
- 審査着手前であること
- 以下のいずれかに該当する出願であること・外国関連出願+実施関連出願
・ベンチャー企業による出願+実施関連出願
- スーパー早期審査の申請前4週間以降のすべての手続きがオンライン手続きで行われた出願であること
要件③の外国関連出願や実施関連出願、ベンチャーによる出願は、早期審査(ベンチャー企業対応面接活用早期審査)と同じです。
「外国語関連出願+実施関連出願」であれば、ベンチャー企業でなくとも、スーパー早期審査の要件に該当する可能性がある点がポイントです。日本以外の国でも同じ発明について特許出願をする場合は、スーパー早期審査の利用を検討してみましょう。
また、ここでいう「審査着手前」(要件②)とは、特許庁から以下のいずれかの通知等が届く前のことをいいます。
- 拒絶理由通知
- 拒絶理由がないときに送られる特許査定の謄本の送達
- 先行技術に関する文献情報の開示がなされていないことを指摘する通知(先行技術文献情報開示要件違反の通知)
- 同じ発明の出願が同日にあり協議で特許を受ける者を決めるよう指示する通知
このとおり、「審査着手前」という要件は、文字通り審査官が審査を始めたかどうかを意味していないことに注意してください。
これらの通知が特許庁からなされたあとは、スーパー早期審査の要件を満たさなくなってしまうため、対象外となります。
(3)スーパー早期審査の手続
スーパー早期審査の手続きは、早期審査の手続きとほぼ同じで、指定された様式にしたがって「早期審査に関する事情説明書」を提出します。
スーパー早期審査を希望する場合には、説明書の冒頭に「スーパー早期審査を希望する」ことを記載します。
他方、ベンチャー企業がスーパー早期審査を希望する場合には、「ベンチャー企業対応スーパー早期審査を希望する」と記載します。
この点に関して、少しでも違う記載をすると、スーパー早期審査として扱われない可能性があるため、注意してください。
「早期審査に関する事情説明書」の冒頭にこれらの記載があるときは、スーパー早期審査とするかどうかの選定が行われます。スーパー早期審査の対象として選定された場合には通知はありませんが、それ以外の結果となったときには、理由とともにその旨の通知があります。スーパー早期審査の対象としないと選定された場合でも、早期審査の要件を満たしていれば、早期審査の対象となることもあります。
(4)スーパー早期審査を利用したい場合の留意点
スーパー早期審査を利用するうえで注意しなければいけない点は、大きく分けて以下の2つです。
- 方式不備
- 手続補正書の提出
スーパー早期審査は、審査期間を極力短縮しようとする手続です。出願人のミスや対応の遅れによって迅速な手続が見込めなくなるとスーパー早期審査の対象から外されてしまうため注意が必要です。
①方式不備
「方式不備」とは、特許庁に提出する書類が所定の形式や手続きに沿ってなされていないことをいいます。
「早期審査に関する事情説明書」の記載の不備以外の理由、たとえば、オンラインで手続きをしなければいけないのに、一部の手続きが書面の提出で行われていたり、スーパー早期審査の申請手続きと同時に行った「出願審査請求」の書面に不備があり、それが解消されないままだったりすると、方式不備としてスーパー早期審査の対象外となります。
せっかく苦労してスーパー早期審査の手続きを進めても、方式不備があっては、元も子もありません。方式不備がないようご注意ください。
②手続き補正書等の提出
拒絶理由通知が届いた場合には、出願人は「意見書」を提出して審査官に反論するか、「手続補正書」を提出して、出願時に提出した明細書等の内容を修正しなければ、そのまま拒絶査定となり、特許を取得することができなくなってしまいます。
スーパー早期審査の場合は、この意見書や手続補正書を、拒絶理由通知が発送された日から30日以内に特許庁に提出(応答)しなければいけません。この期間内に出願人から提出がなかったときは、スーパー早期審査の対象外となります。
また、通常の審査の場合には、この応答期間の延長を請求することができますが、スーパー早期審査の場合には、審査期間を短縮するという制度の趣旨があるため、延長請求ができなくなっています。この延長請求をすると、これもスーパー早期審査の対象外となってしまいます。
このように、拒絶理由通知が届いた場合には、出願人は速やかに応答しなければいけません。また、この手続きについても、オンラインで行わなければいけないことに注意してください。
ここまで解説したとおり、スーパー早期審査は、オンライン手続が必須とされているうえに、出願人にも手続きの正確さ、迅速さが求められます。初めて特許を出願するという人が、自分自身でスーパー早期審査を利用してすべての手続きをするということは現実的ではありません。特許の手続きはよくわからないけれど「スーパー早期審査」を使って少しでも早く特許を取りたい、という方は、弁理士・弁護士といった専門家に依頼した方が安心です。
6 小括
特許を出願してから権利化するまでには、通常の審査では1年以上の時間がかかります。
通常の審査の他に、この審査の期間を短縮するための「早期審査」「ベンチャー企業対応面接活用早期審査」「スーパー早期審査」という3つの早期審査があります。これらを使えば特許の権利化までの時間を大きく短縮することができるので、ぜひご活用ください。
7 まとめ
これまでの解説をまとめると、以下の通りです。
- 特許の審査は、通常審査の場合には、結論がでるまでの期間は14.1ヶ月、一次審査通知までの期間は9.3ヶ月かかる(2018年度)
- 審査の種類には①通常審査、②早期審査、③ベンチャー企業対応面接活用早期審査、④スーパー早期審査、の4種類がある
- 早期審査の申請の手続きは、「早期審査に関する事情説明書」を作成して提出する
- ベンチャー企業対応面接活用早期審査では、早期審査に加えて一次審査通知の前に出願人が審査官と面接をしてもらうことができる
- スーパー早期審査は、結論がでるまでの期間が最も短くなる審査方法である
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。