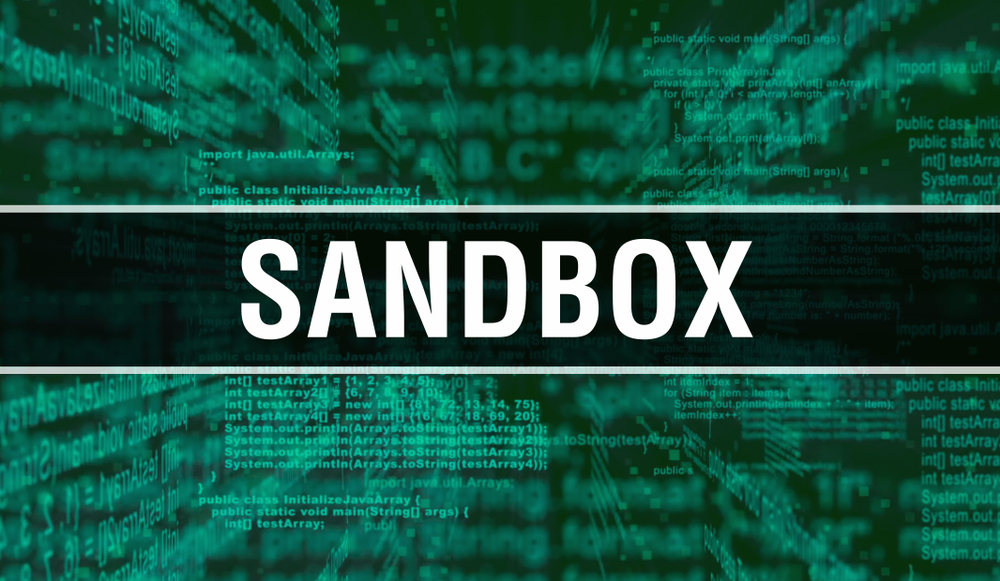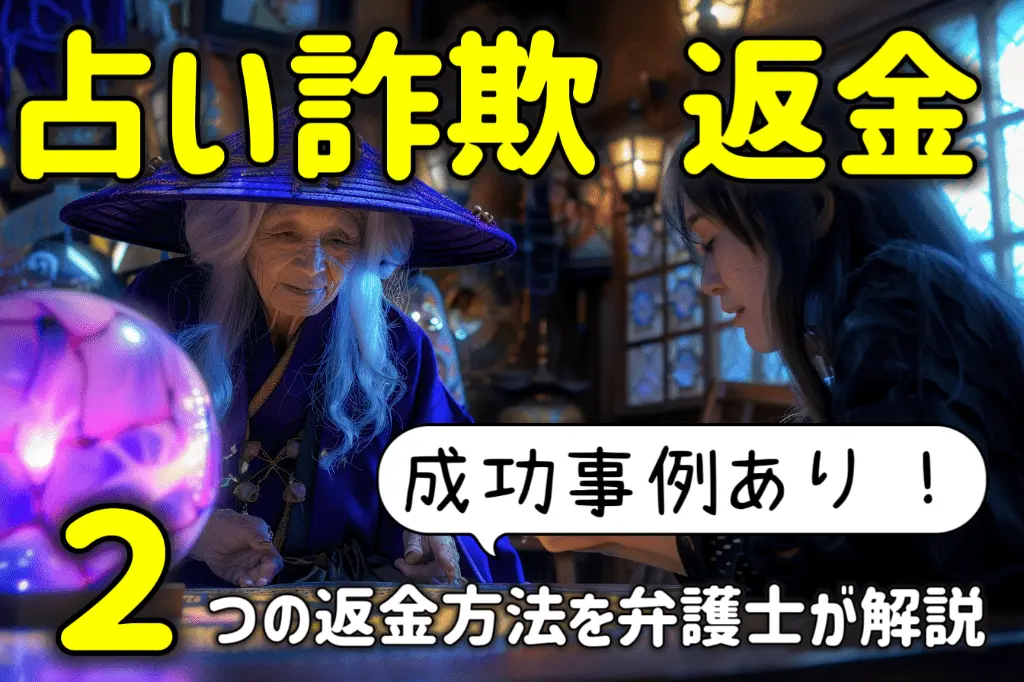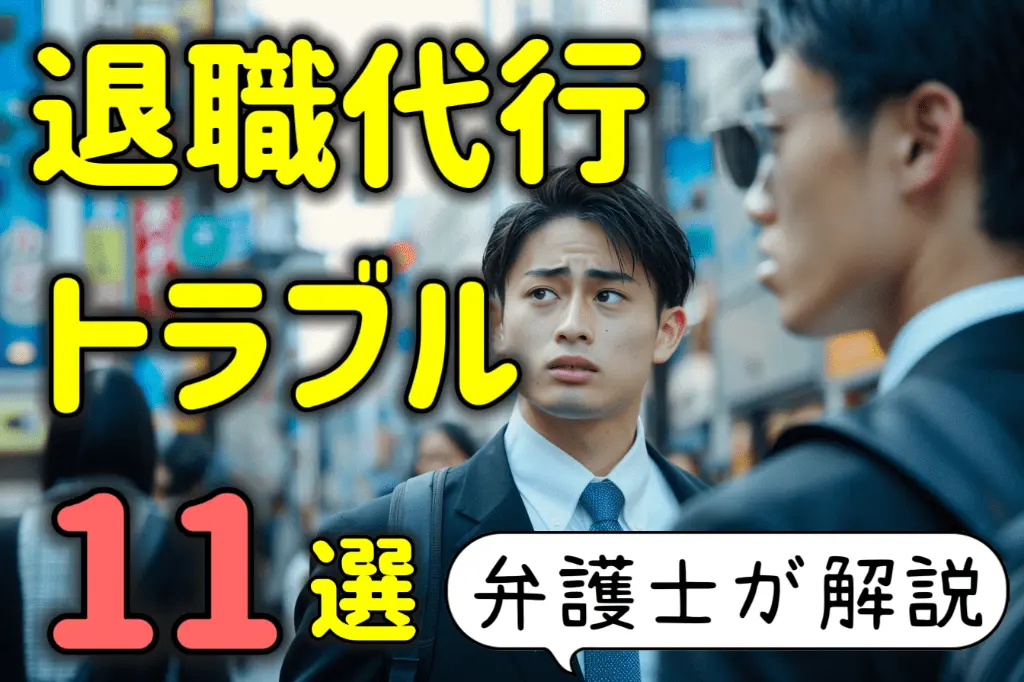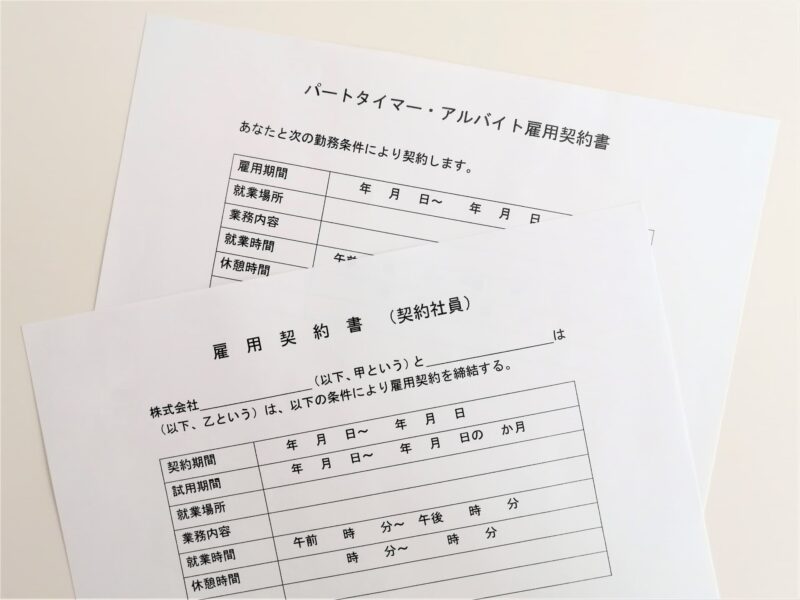パワハラを判断する2つの基準と事業者に課される義務を弁護士が解説

はじめに
セクハラやパワハラなどに代表されるハラスメント行為を許さないとする風潮が高まっています。
ハラスメントを行っていることについて自覚がない人もいますが、ハラスメントを受けた人は、そのような行為により嫌な思いをさせられ、思っている以上に傷ついたりします。
ハラスメント行為には多くの種類がありますが、そのなかでも「パワハラ」は、一般的に職場内で行われます。
2020年6月から施行された(中小企業は2022年4月施行予定)、いわゆる「パワハラ防止法」は、パワハラを防止するために必要な雇用管理上の措置を講じることを事業者に義務付けています。
事業者においては、いまいちど「パワハラ」にあたる条件を正確に理解しておくことをおすすめします。
今回は、パワハラの判断基準について、弁護士がわかりやすく解説します。
1 「パワハラ」とは
厚生労働省は、「パワハラ」について、以下のように定義しています。
-
職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる行為
厚労省の定義によれば、職場内で、職務上の地位や人間関係において優位に立つ者が、業務上必要な範囲を超えて、社員を怒鳴ったり罵倒したりするような行為は、パワハラにあたる可能性があることになります。
もっとも、これまでに部下を怒鳴ったことがあるという人もいらっしゃると思います。
このようなケースがすべて「パワハラ」にあたるわけではありません。
部下に向上・改善して欲しいという思いから怒鳴ってしまうこともあるため、パワハラにあたるかどうかは、このような事情も考慮のうえ、判断しなければならないのです。
※パワハラの類型について詳しく知りたい方は、「パワハラ防止法が施行!事業者が守るべき4つの義務を弁護士が解説!をご覧ください。
2 「パワハラ」該当性を判断するための2つの基準
みなさんもご存知のように、パワハラには、明確な線引きが存在しません。
そのため、パワハラ行為に至った経緯やその目的などを考慮したうえで、個別のケースごとに判断する必要があります。
具体的には、以下の2つの要素を検討することが必要です。
- 合理性の有無
- 業務上適正な範囲を超えていないか
3 合理性の有無
「なぜ、パワハラと疑われる行為に出たのか」という点が一つ目の判断基準です。
そこに、合理的な理由が認められれば、パワハラにあたる可能性は低くなります。
たとえば、上司の「怒鳴る」という行為について考えてみましょう。
「怒鳴る」という行為そのものは、決して評価される行為ではないかもしれません。
ですが、たとえば、怒鳴られた部下は、それまでにも再々にわたり上司から同じことを指摘されており、にもかかわらず、一向に改善しようとしなかったとします。
上司側からすれば、何とか成長・改善して欲しいという思いから、再三にわたり注意をしているにもかかわらず、本人に改善する姿勢が見られないと、怒鳴りたくもなるのではないでしょうか。
このように、「なぜ、怒鳴ったのか」というその理由が、部下の成長や改善を願ってのことであるような場合は、理由に合理性が認められるため、パワハラにあたる可能性は低くなります。
もっとも、部下をつかまえて長時間にわたり怒鳴り続けたり、部下の人格を執拗に攻撃するような態様で怒鳴ったりする場合は、部下の成長や改善を願って出た行為であるとはいえません。
そのため、理由に合理性が認められず、パワハラにあたる可能性が高くなります。
4 業務上適正な範囲を超えていないか
パワハラにあたらないといえるためには、パワハラと疑われる行為が、業務との関係で適正な範囲内にあることが必要になります。
たとえば、上司から業務上の指示を受けた部下がミスを犯し、その部下を上司が怒鳴りつける場面をイメージしてください。
ミスをされたという憤りから怒鳴るという行為に出てしまうこともあるでしょう。
それだけで、パワハラにあたると言い切ることはできませんが、エスカレートして、部下の人格や私生活を批判するようなことにまで及んでしまうと、もはや業務とは関係なく、「業務上の適正な範囲」を超えているといえます。
このような場合には、怒鳴るという行為がパワハラにあたる可能性は高いです。
一方で、多少の憤りはあるものの、怒鳴るという行為の大部分が、ミスを犯した原因の究明やその後の防止策などに向けられている場合は、「業務上の適正な範囲内」にあるといえ、パワハラにあたる可能性は低くなります。
5 事業者に課されるパワハラ防止法上の義務
パワハラ防止法は、職場内におけるパワハラを防止するために、以下の事項を事業者に義務付けています。
- 方針の明確化
- パワハラ発生後の対応
- 相談窓口の設置
(1)方針の明確化
事業者は、どのような言動をパワハラというのか、また、パワハラにあたる言動を行ってはいけないということを明確にする必要があります。
そのうえで、社員に周知することが必要です。
また、実効性を確保するために、パワハラ行為を行った場合には厳しく対処することを、就業規則などで定め、同様に周知することも必要です。
(2)パワハラ発生後の対応
パワハラが発生した場合に、迅速かつ適切な対応が取れるよう、体制を整備しておく必要があります。
具体的には、事実関係の聴き取り、再発防止措置などを迅速・適切に行えるようにしておくことが求められます。
(3)相談窓口の設置
事業者は、相談窓口を設置することにより、パワハラで悩む社員の受け皿を作る必要があります。
そのうえで、社員に周知することが必要です。
※事業者に課されるパワハラ防止法上の義務について詳しく知りたい方は、「パワハラ防止法が施行!事業者が守るべき4つの義務を弁護士が解説!」をご覧ください。
6 まとめ
パワハラ行為は、社員の士気を下げ、生産性の低下を招く要因になるだけでなく、社員の生命・身体に危険を及ぼすおそれすらあります。
職場環境の健全性を確保するためにも、パワハラを防止することは、事業者の責務であるといえます。
弊所は、ビジネスモデルのブラッシュアップから法規制に関するリーガルチェック、利用規約等の作成等にも対応しております。
弊所サービスの詳細や見積もり等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。