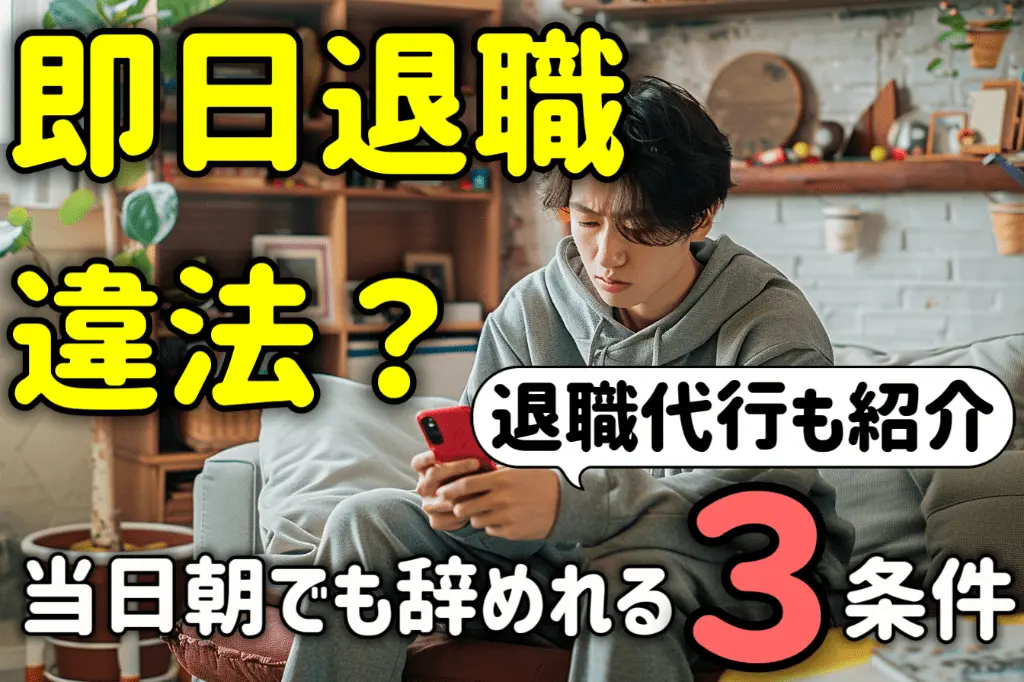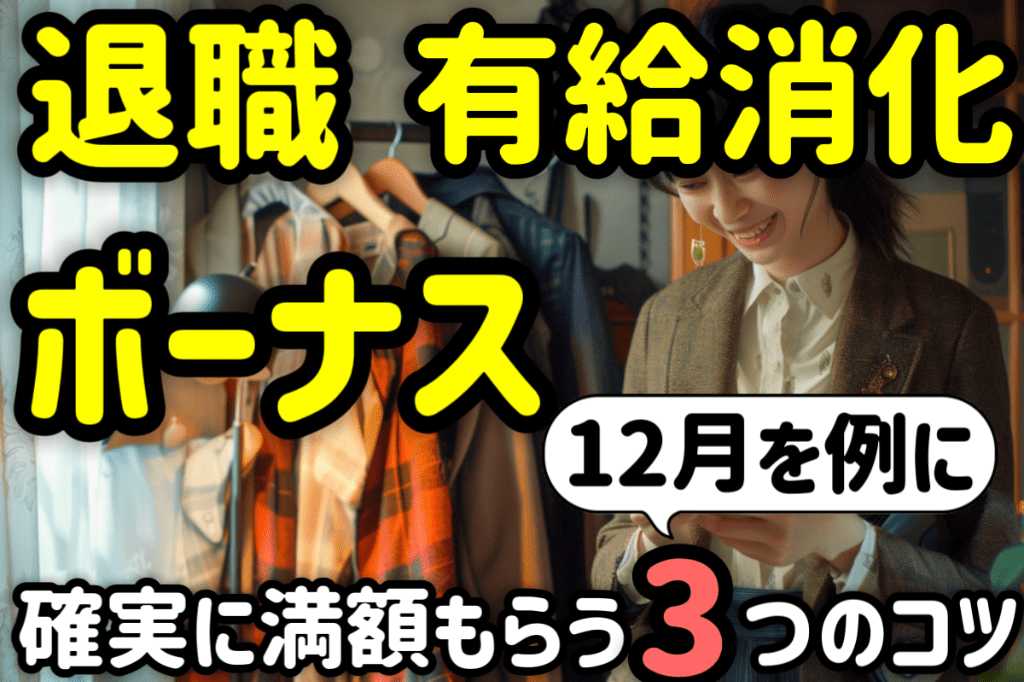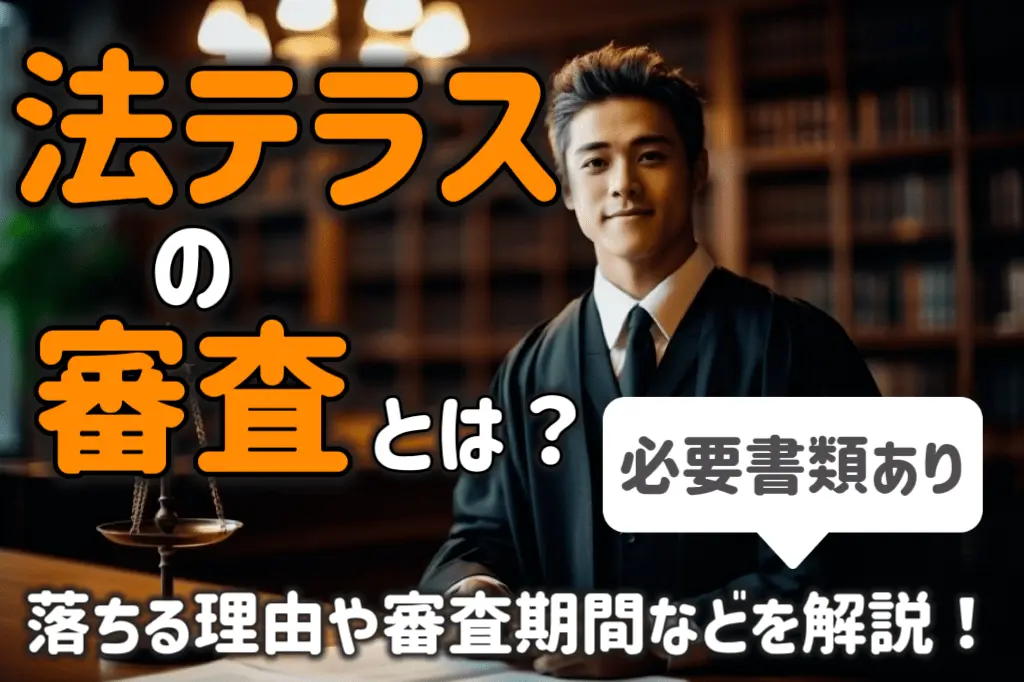テレワークにおける労務管理の注意点は?ポイント3つを弁護士が解説

はじめに
コロナ禍による影響で、テレワークを導入する企業が増えています。
これから導入することを予定している事業者の方もいらっしゃると思いますが、その場合、労務管理に違いは出てくるのでしょうか?
今回は、テレワークにおける労務管理で注意すべきポイントについて、弁護士がわかりやすく解説します。
1 テレワークとは?

「テレワーク」とは、tele(=離れた場所)とwork(=働く)を組み合わせた造語です。
時間や場所を制約されずに、柔軟に仕事ができる形態のことを意味します。
テレワークは、主に以下の3つに分類されます。
(1)在宅勤務
「在宅勤務」とは、従業員が自宅で業務を行うことをいいます。従来かけていた通勤時間がなくなるため、その時間を有効に活用することが可能です。
(2)サテライトオフィス勤務
「サテライトオフィス勤務」とは、従来従業員が業務を行っていたオフィス以外に設けられたオフィスを利用することをいいます。
従来より通勤時間が短くなることが多く、また、在宅勤務などにくらべると、作業に適した環境が整った場所で業務を行うことが可能です。
(3)モバイル勤務
「モバイル勤務」とは、スマホやノートパソコンなどを使って、従業員が選んだ場所で業務を行うことをいいます。
従業員が柔軟に場所を選ぶことができるという点で、業務の効率化を図ることが可能です。
このように、テレワークには、通勤時間の短縮や業務の効率化などといったメリットがあります。
2 テレワークにおける労務管理の課題

テレワークは、オフィスで執務するという従来の形態から、自宅などで執務するという形態に変わることになります。
そのことに起因して、さまざまな問題や課題が生じていることも報告されているのです。
たとえば、以下のような問題や課題が挙げられます。
- 労働時間の管理が困難である
- コミュニケーションに問題がある
- 進捗管理が困難である
- 情報セキュリティの確保に問題がある
このほかにも、賃金の決定が困難である、業務への評価が困難であるといった報告も上がっています。
テレワークは、就労場所を自宅に指定するだけで実施することが可能なため、安易に導入して労務管理が不十分になりがちです。
今後、テレワークを導入する事業者がますます増えていく可能性もあるため、適切な労務管理ができるよう体制を整備しておくことが重要になってきます。
3 テレワークにおける労務管理上のポイントは?

テレワークを実施する場合に、事業者が労務管理上注意しなければならないのは、労働基準関係法令です。
労働基準関係法令は、テレワークを実施する場合であっても、適用されます。
そのため、事業者は、これらの法令をきちんと守らなければなりません。
主には、以下の3つの法律を十分に理解しておくことがポイントになってきます。
- 労働基準法
- 労働安全衛生法
- 労働者災害補償保険法
次の項目から、それぞれについて詳しく見ていきます。
4 労働基準法

事業者が、労働基準法との関係で注意しなければならないのは、以下の4点です。
- 労働条件の明示
- 労働時間の管理
- 休憩時間の取扱い
- 時間外と休日労働の労働時間の管理
(1)労働条件の明示
事業者は、従業員と労働契約を交わす場合、従業員に対し、賃金や労働時間に加え、就業場所を明示する必要があります。
そのため、就労開始時にテレワークを実施させる場合には、テレワークの実施場所を就業場所として明示しなければなりません。
(2)労働時間の管理
事業者は、従業員の労働時間を適切に管理する責務を負っており、これはテレワークを実施する従業員との間でも同じです。
テレワークでは、従業員が目の届かない場所で就業しているため、労働時間を把握しにくい傾向にあります。
この点、厚労省が公表している「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」によれば、原則として、パソコンの使用時間などの客観的な記録により、従業員の始業と終業時刻を管理することが必要だとされています。
また、やむを得ず従業員の自己申告により労働時間を管理する場合であっても、自己申告による労働時間と実際の労働時間が合致しているかを適宜調査するなどして、自己申告制の適正な運用を確保するための措置を講じなければなりません。
さらに、テレワークで問題となるのが、いわゆる「中抜け時間」です。
「中抜け時間」とは、従業員が業務から離れる時間のことを意味します。
中抜け時間には、事業者が業務を指示することを禁止し、従業員は中抜け時間を自由に利用することが許されている場合には、中抜け時間の開始と終了の時間を報告させるなどして、その時間を休憩時間として扱うことが考えられます。
また、中抜け時間を有給休暇(時間単位)として扱うことも可能です。
(3)休憩時間の取扱い
休憩時間は、原則として、従業員に一斉に与える必要があり、これは、テレワークの従業員に対しても同じです。
具体的には、1日あたりの労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は60分以上の休憩を与えることが必要です。
もっとも、労使協定を締結することにより、一斉に与えることをしなくてもよくなるため、オフィスにおける休憩時間と違う時間帯で休憩を与えることができます。
(4)時間外と休日労働の労働時間の管理
実労働時間などが法定労働時間を超える場合や休日に労働をさせる場合には、36協定の届出や割増賃金の支払いが必要になります。
また、深夜に労働させた場合には、深夜労働に係る割増賃金の支払いも必要です。
これは、テレワークを実施する従業員との関係でも同じですので、事業者は、従業員に対し、業務時間を日報に記録させるなどして、労働時間を正確に把握する必要があります。
もっとも、就業規則などにおいて、時間外や休日に業務を行う場合には、事前に許可を受けることとなっているような場合に、許可を受けることなく、時間外や休日に業務を行った場合には、労働時間にあたらない可能性があるため、この点もしっかりと管理しておくことが必要です。
※労働基準法の適用に関する注意点について詳しく知りたい方は、厚労省が公表している「テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン」をご覧ください。
5 労働安全衛生法

「労働安全衛生法」とは、労働者の安全や健康を確保することを目的として、労働災害の防止のための基準などが定められた法律です。
テレワークを実施する場合も労働安全衛生法などの法律は当然に適用されますので、事業者はテレワークを実施する従業員に対し、健康診断やストレスチェックなどの実施をする必要があります。
特に、テレワークの多くはパソコン等を使った作業が中心になるかと思いますので、「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて」(厚生労働省)などに留意することが望ましいとされています。
※労働安全衛生法の適用に関する注意点について詳しく知りたい方は、厚労省が公表している「テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン」をご覧ください。
6 労働者災害補償保険法

「労働者災害補償保険法」とは、業務上の事由や通勤による負傷などに対して、必要な保険給付を行い、あわせて、労働者の社会復帰を促進することなどを目的とした法律です。
この点、テレワークであっても、その業務中に生じた災害については、労災保険の給付対象となります。
また、サテライトオフィス勤務やモバイル勤務では、場所の移動を伴うため、通勤災害が認められる可能性もあることに注意が必要です。
以下は、実際に起きた事例ですが、この事例では、労災が認定されています。
-
【事例】
テレワークにてパソコン業務を行っていた従業員が、トイレから作業場所に戻り椅子に座ろうとしたところ転倒した
この事例について、労働基準監督署は、従業員の転倒は、業務行為に付随する行為に起因するものであり、業務以外の私的行為によるものではないと判断しました。
※労働災害の補償に関する注意点について詳しく知りたい方は、厚労省が公表している「テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン」をご覧ください。
7 小括

コロナ禍がきっかけになったとはいえ、テレワークは今後もいっそう広く定着していく可能性があります。
就労場所がオフィスから自宅などに変わることになりますが、労働基準関係法令は従来通り、テレワークを行う従業員に対しても適用されることに注意が必要です。
事業者は、適正に労務管理を行うためにも、いまいちど、これらの法令がきちんと守られているかなどを確認するとともに、必要に応じて、体制を見直すことが求められます。
8 まとめ
これまでの解説をまとめると、以下の通りです。
- テレワークは、その形態によって、①在宅勤務、②サテライトオフィス勤務、③モバイル勤務の3つに分類される
- テレワークには、①労働時間の管理、②コミュニケーション、③進捗管理、④情報セキュリティの確保といった問題や課題がある
- テレワークにおいて、労務管理上ポイントとなる主な法律は、①労働基準法、②労働安全衛生法、③労働者災害補償保険法の3つである
- 労働基準法との関係で注意しなければならないのは、①労働事件の明示、②労働時間の管理、③休憩時間の取扱い、④時間外と休日労働の労働時間の管理の4点である
- 事業者は、労働安全衛生法に基づき、テレワークを行う従業員に対し、①健康診断、②医師による面接指導、③ストレスチェックを実施しなければならない
- 自宅でのケガ等についても労働災害と認定される可能性がある
近年、リモートワークなどの新しい働き方が急速に浸透しておりますが、法令対応が後手に回ることによって思わぬトラブルにつながる可能性もあります。
法規制についての詳細や社内規程の整備についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽に弊所までご相談ください。
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。