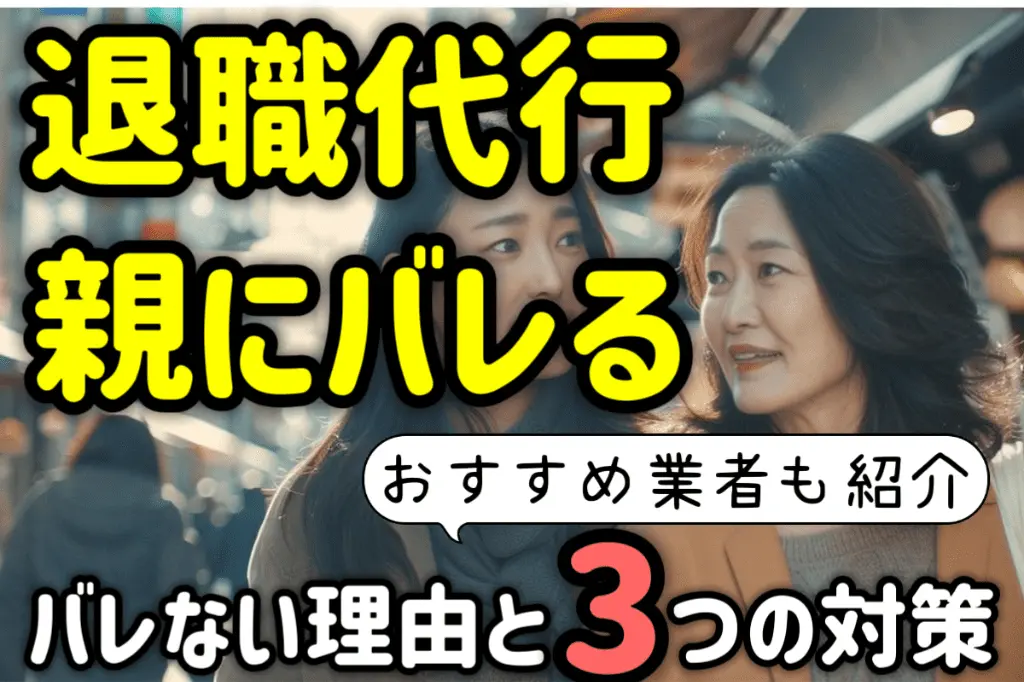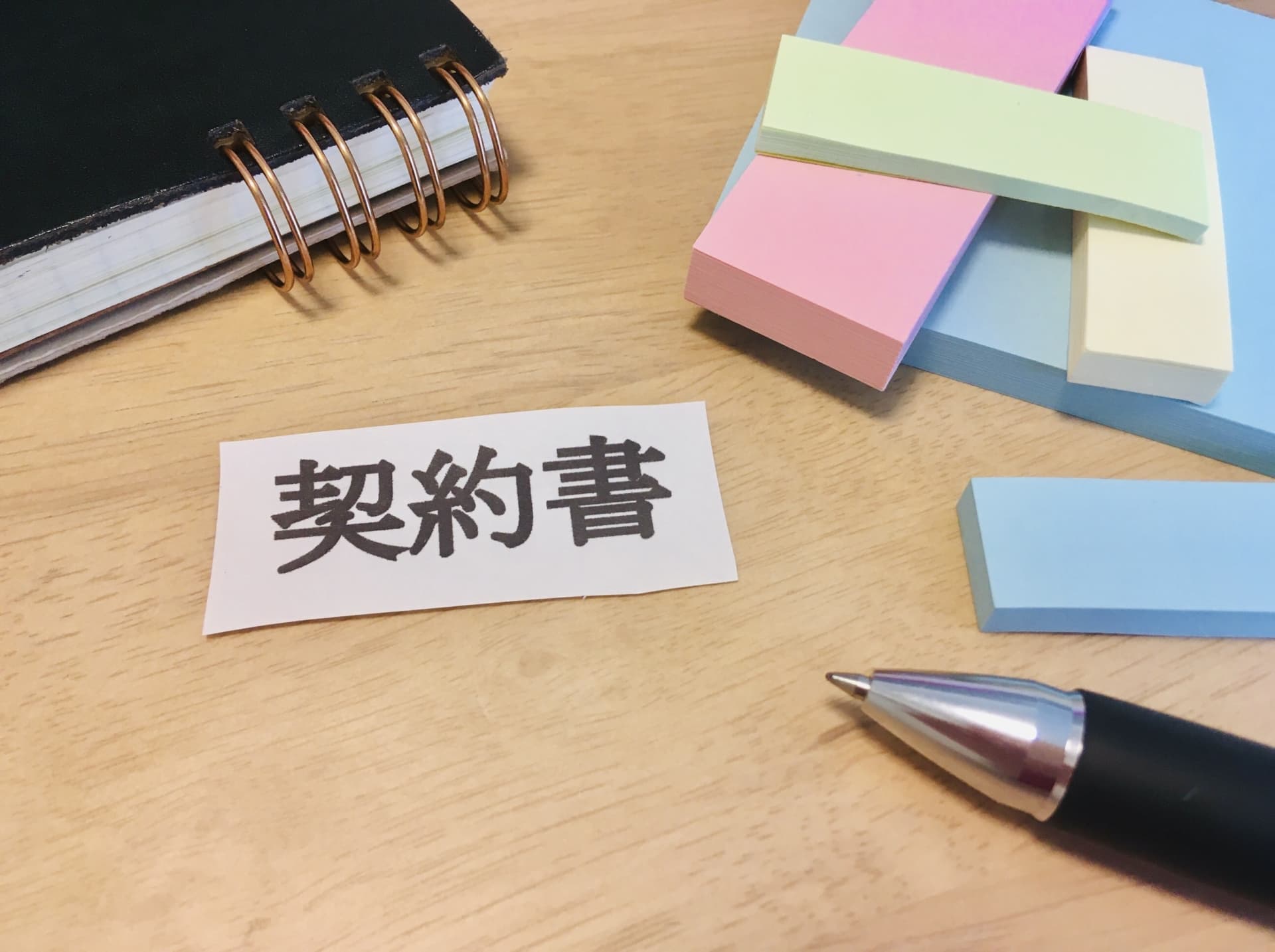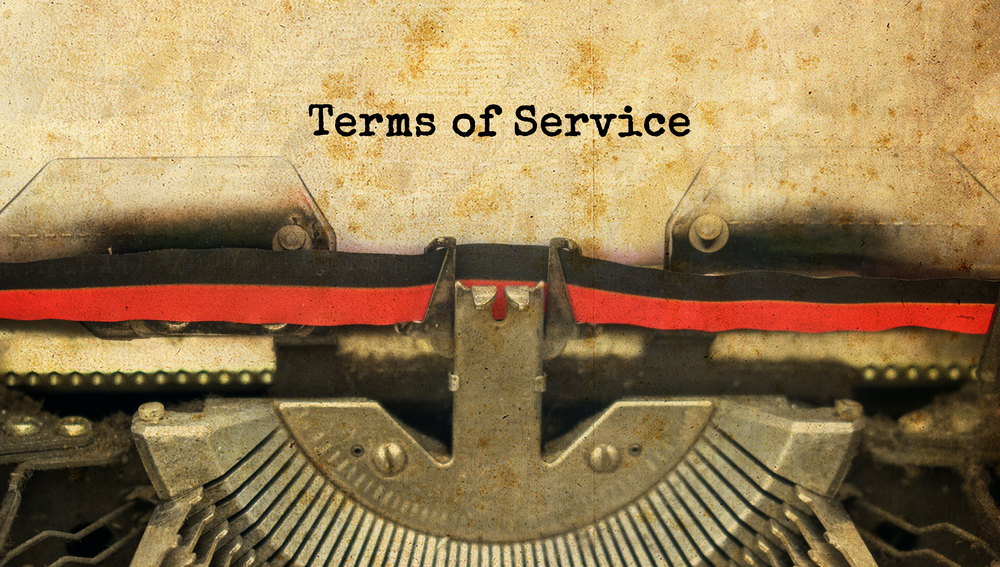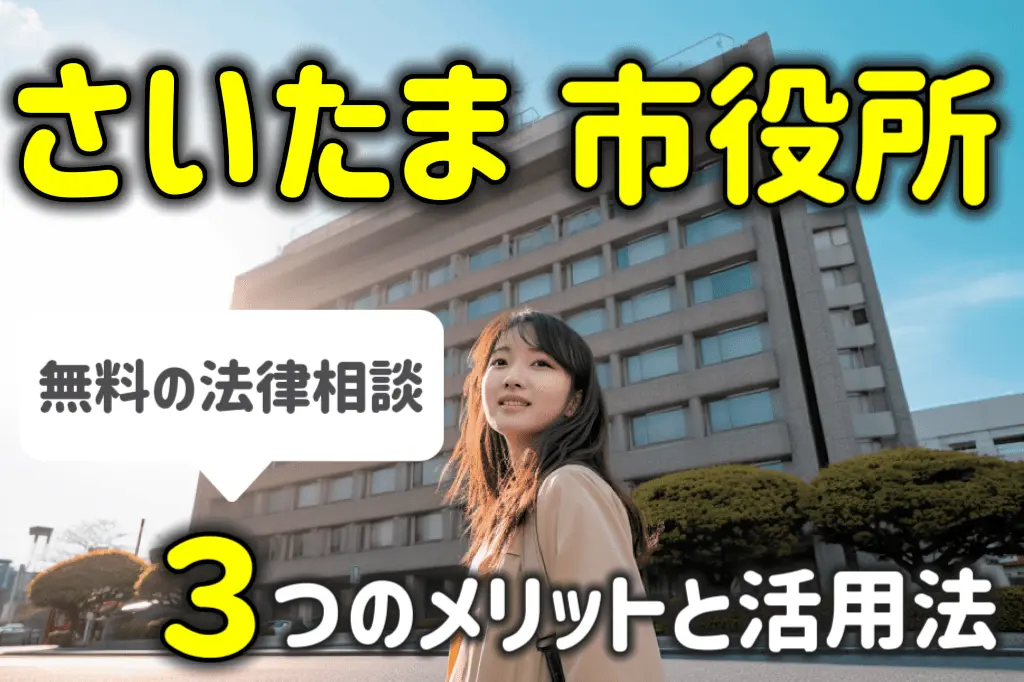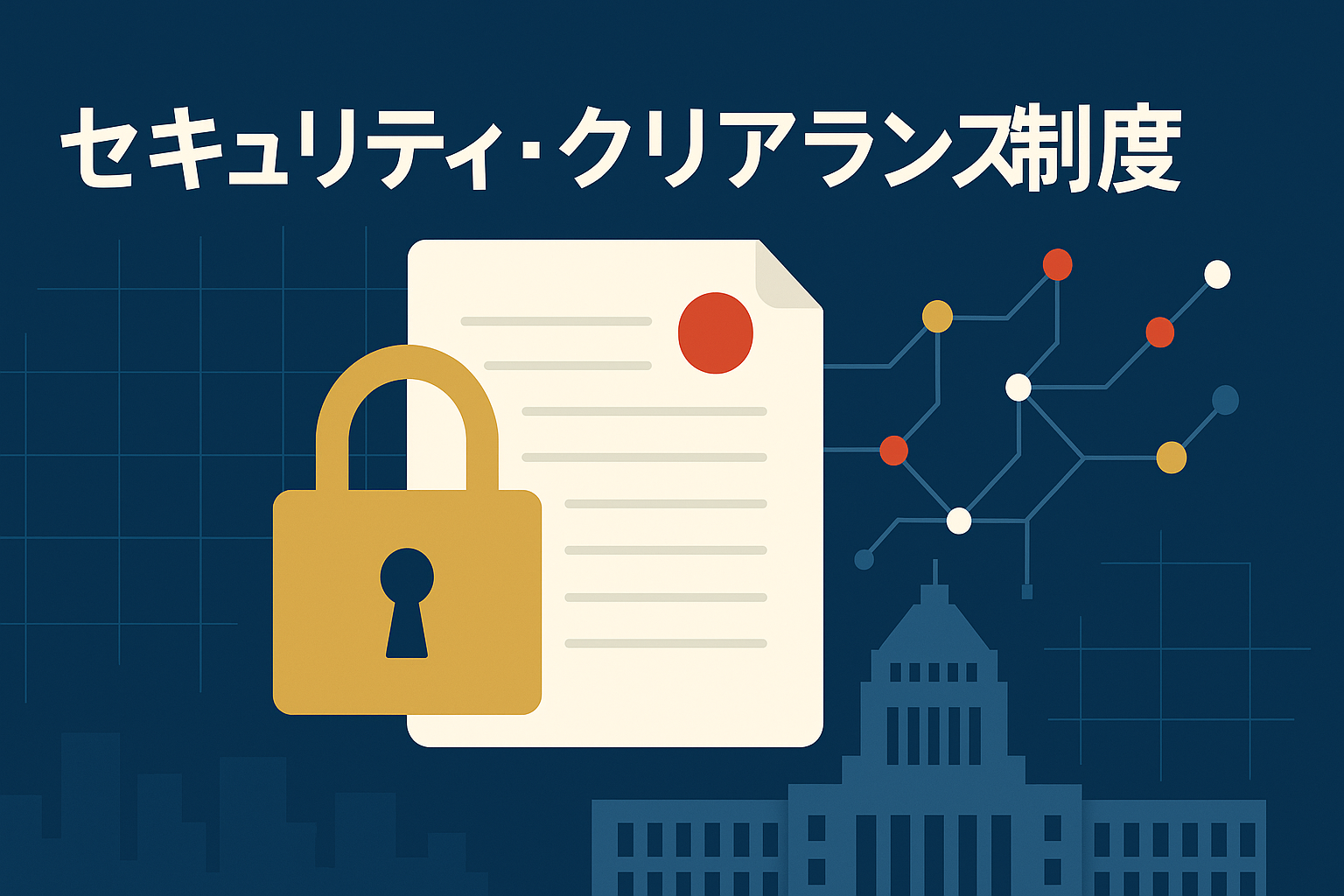4周年の自動貯金アプリ「finbee」のビジネスモデルを解説!

はじめに
2020年12月に、4周年を迎えた「finbee」というサービスをご存知でしょうか?
finbeeは、「株式会社ネストエッグ」が運営する自動貯金アプリサービスです。
PR TIMESより
今回は、この「finbee」について見ていきたいと思います。
1 「finbee」の概要

「finbee」は、貯金の目的や目標とする金額、貯金をする際のルールなどを設定することにより、ライフスタイルに応じた貯金を実現できるサービスです。
みなさんもご存知のとおり「貯金」をしていくことは決して簡単なことではありません。生活をしていると、何かと出費が多くなりがちです。
「気が付いたら財布の中のお金が減っている」「飲み会があるとどうしても参加してしまう」「無駄遣いをしてしまうことが多い」など、当てはまる方もいらっしゃると思います。
finbeeでは、貯金をするためのルールを設定するだけで、あとは生活を送る中で自然と貯金をすることができます。
たとえば、ウォーキング1000歩すると500円の貯金、最寄り駅にチェックインすると200円の貯金といったように、自身でルールを設定するわけです。
このように、日々の些細な出来事などをルールとして設定することにより、簡単に楽しく貯金することが可能になります。
2 「finbee」の特徴|メリット
(1)貯金意欲が高まる
finbeeでは、貯金の目的を設定し、その目的ごとに貯金目標額と期限を決めることができます。そのため、目的達成に向けて貯金をしようという意欲が高くなります。
たとえば、「温泉旅行に5万円」「新しい家電に10万円」といったように、目的ごとに目標額を決めて着実に貯金することができます。
(2)自由にルールを設定できる
finbeeでは、設定した歩数に達することを条件として貯金する「歩数貯金」や設定した場所にチェックインすることを条件として貯金する「チェックイン貯金」など、自由にルールを設定することができます。
また、毎日自動で貯金する「つみたて貯金」もあり、自身のライフスタイルに合わせたルールを設定することにより、自然と貯金ができる仕組みになっています。
(3)ポイントが貯まる
finbeeでは、貯金をするとその金額に対して0.1%のポイントがつきます。
貯まったポイントはAmazonギフト券に交換することができるため、一石二鳥です。
(4)協力して貯金ができる
finbeeでは、数名が協力して貯金をすることができます。
たとえば、友人数名で旅行するために貯金をしたり、高級レストランで食事をするために夫婦で貯金をしたりすることが可能です。
各参加者がどの程度貯金しているかがわかるようになっているため、目標額達成に向けてお互いに励まし合いながら貯金をしていくことができます。
(5)一括管理が可能
finbeeには「キープ機能」が備わっています。
そのため、ECサイトなどで気になった商品はいったんキープして一括で管理しておくことにより、後になってECサイトの該当ページに戻る必要もなくなります。
また、キープしていた商品を手に入れたいと思い立った時には、すぐに貯金を開始することができます。
3 「finbee」における貯金の仕組み

「finbee」を利用する場合、貯金が目標額に達するまでの仕組みは以下のようになっています。
(1)アプリをダウンロードする
まずは、finbeeのアプリをダウンロードします。
アプリの利用は無料となっており、10秒もあれば会員登録できるようになっています。
(2)銀行口座との連携
連携する銀行口座を選び、その口座をアプリに連携します。
(3)貯金の目的やルールを設定する
何のために貯金をするのか、また、目標貯金額をいくらにするのかなど、貯金に関するルールを設定します。
ここまでくると、あとは貯金を開始するだけです。
なお、貯金の元手となるお金は、(2)でアプリに連携した銀行口座の残高となります。
(4)貯金用の口座に自動で移動
設定したルールをクリアすると、連携口座から自動で貯金用の口座に設定した額が移動します。
(5)貯金目標額を達成
設定した貯金目標額を達成すれば、その貯金を使って目的を実現することができます。
4 法的検討

「finbee」は、アプリに連携させた銀行口座から貯金用口座に自動でお金が移動することにより貯金ができる仕組みになっています。
現金以外の方法により資金を移動させる取引を「為替取引」といいますが、為替取引は、基本的には銀行のみが取り扱える取引となっています。
銀行以外の会社がある銀行口座から別の銀行口座に資金を送金するサービスを始めようとする場合、2つの選択肢があります。
一つは、資金移動業の登録を得ることにより、自ら為替取引をすることができるようにすることです。
もう一つの方法として、電子決済代行業の登録を受けることにより、銀行系APIの利用をするという方法があります。
電子決済等代行業は、決済指図伝達事業者(PISP)と、口座情報利用事業者(AISP)の2つのサービスに分類されます。
決済指図伝達事業者(PISP)は、APIを通じてユーザーの銀行口座に対して送金指示等をすることが可能です。
これに対し、口座情報利用事業者(AISP)は、いわゆる参照系と呼ばれるAPI(残高照会をして入出金履歴をアプリに取り込むなど)を利用することが可能です。
銀行の業務などについて定めている「銀行法」には、以下のような規定があります。
-
【銀行法2条17項1号】
この法律において「電子決済等代行業」とは、次に掲げる行為(第一号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く。)のいずれかを行う営業をいう。
一 銀行に預金の口座を開設している預金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことの当該銀行に対する指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達(当該指図の内容のみの伝達にあつては、内閣府令で定める方法によるものに限る。)を受け、これを当該銀行に対して伝達すること。
-
【銀行法52条の61の2】
電子決済等代行業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
このように、電子決済等代行業を行う事業者は、内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。
「finbee」のサービスは、ユーザーの委託に基づいて、ユーザーが開設している口座の資金を貯金用口座に移動させる為替取引を行うことの指図を銀行に伝達することを内容としていますので、電子決済等代行業にあたることになります。
正確に言うと、為替取引の主体はあくまでも銀行で、電子決済代行業者は銀行系APIを通じて口座間振替を行っていることになります。
電子決済代行業者は令和3年2月24日現在で全国91社が登録されていますが、銀行のAPIを使うことを前提とした業登録であるため、安全にAPIにアクセスることができるシステム態勢及び社内態勢の整備をした上でないと、登録申請を進めることは困難です。
電子決済代行業者一覧(https://www.fsa.go.jp/)
finbeeを運営するネストエッグ社は、2018年に同業の登録を受けていますが、資金移動が絡む事業を展開する場合には、このほかにも資金決済法上の「資金移動業」など、検討しなければならない法規制があることに注意が必要です。
5 まとめ
私の周りを見ていても、貯金というのは、「するか・しないか」というよりも、その人の習慣に深く関与している行動であって、意思の力で実現しようとしても挫折してしまうケースが多いです。
貯金をするという意識的な行動に基づくのではなく、日々の行動等によって無意識のうちに貯金ができるというサービスは素晴らしいものだと思います。
また、電子決済代行業は2018年6月1日にスタートした比較的新しい登録業ですが、少しずつ銀行APIと連動した便利なサービスが増えてきているように感じます。
これからも、様々なフィンテックアプリの登場が期待されるところです。
弊所は、ビジネスモデルのブラッシュアップから法規制に関するリーガルチェック、利用規約等の作成等にも対応しております。
弊所サービスの詳細や見積もり等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。