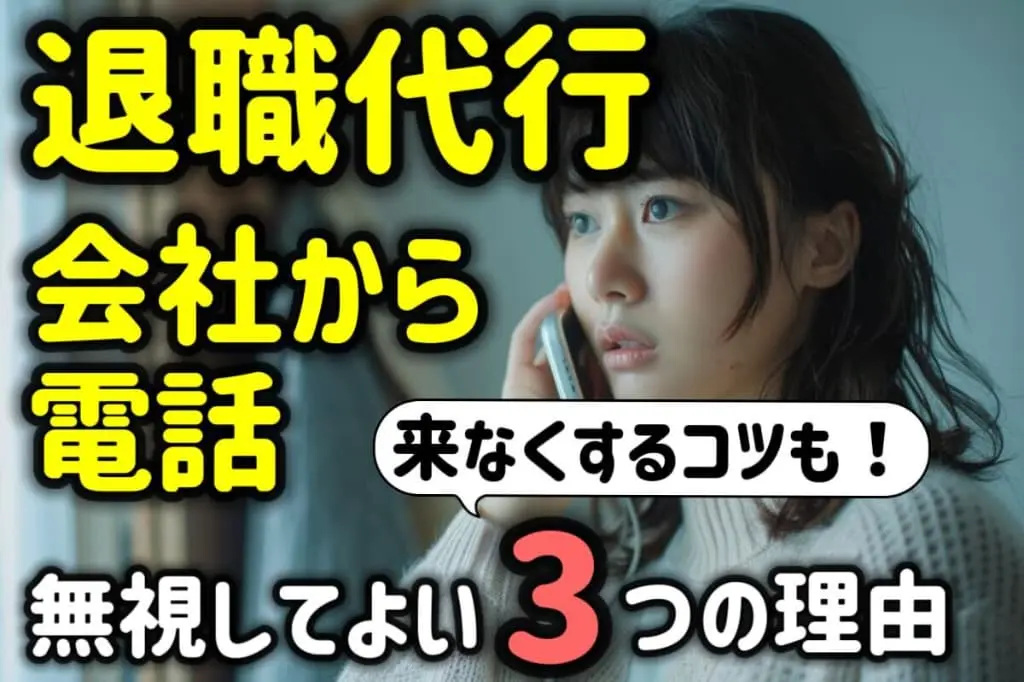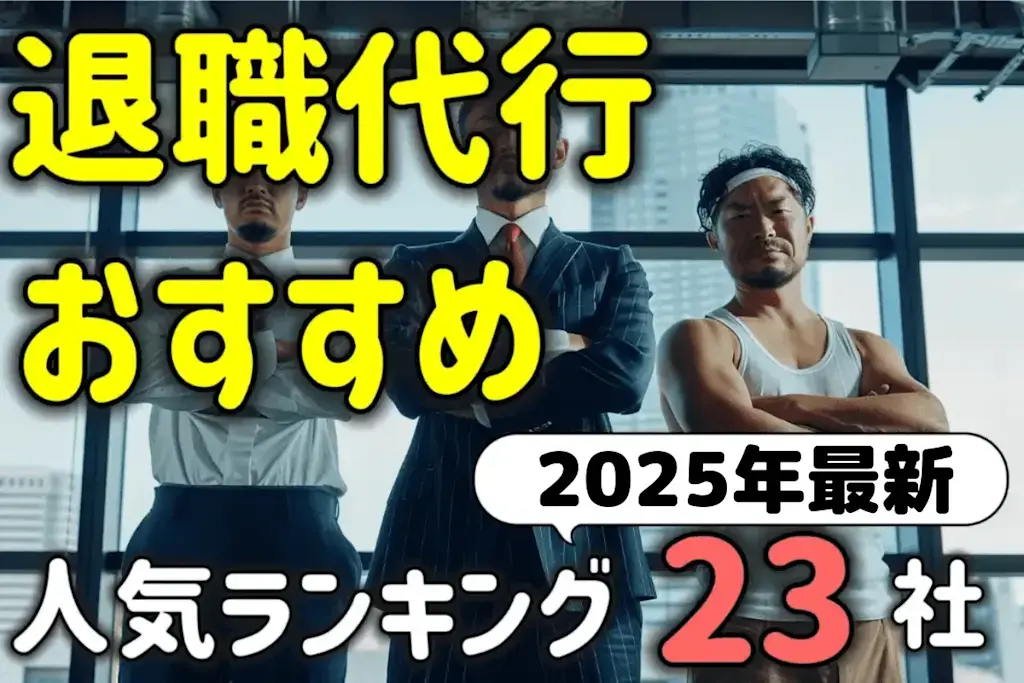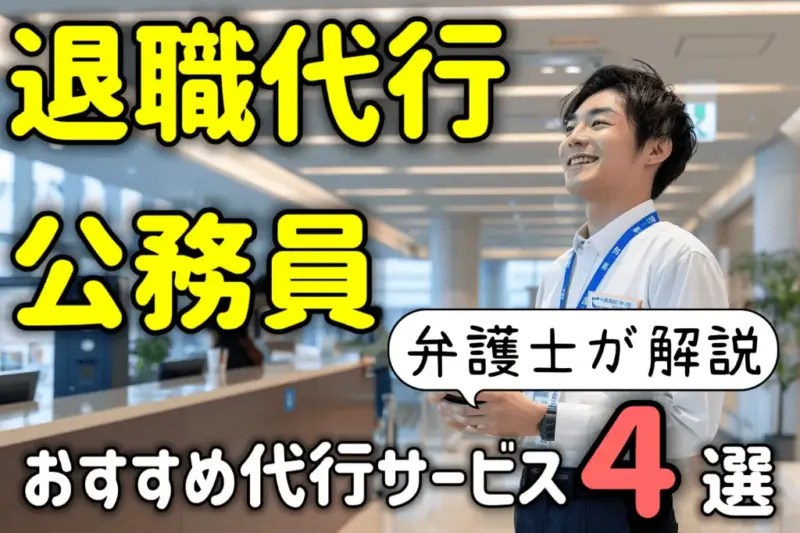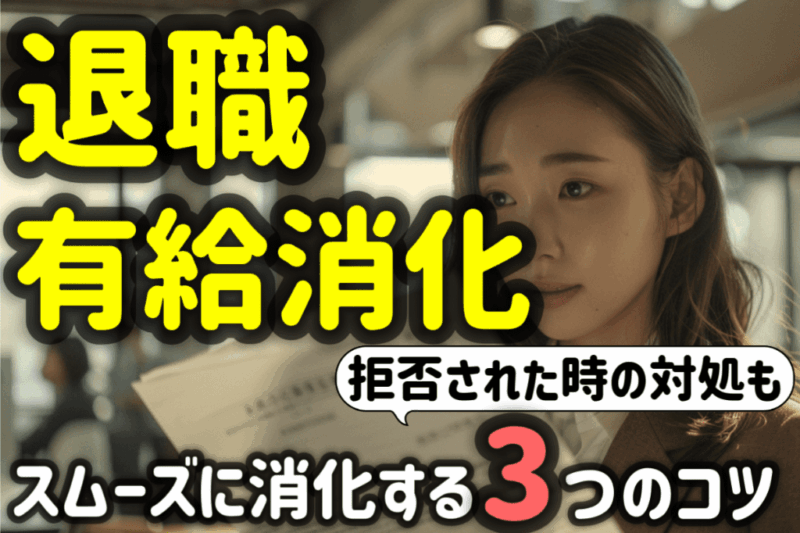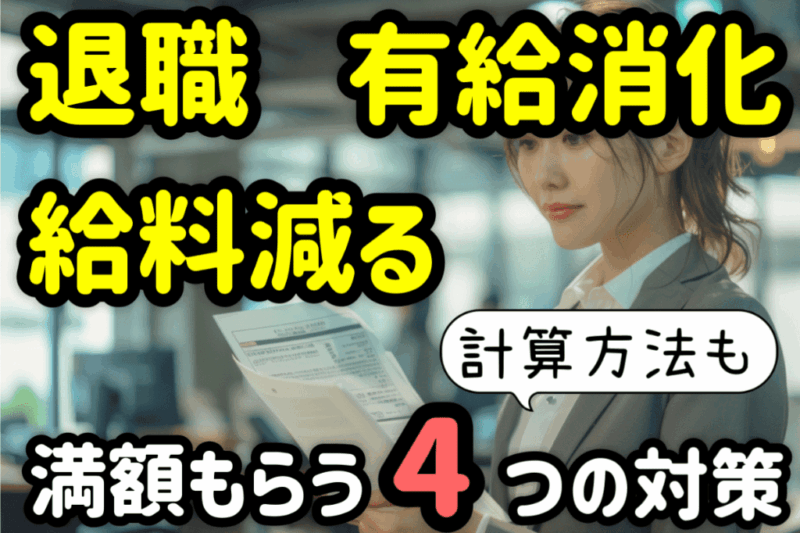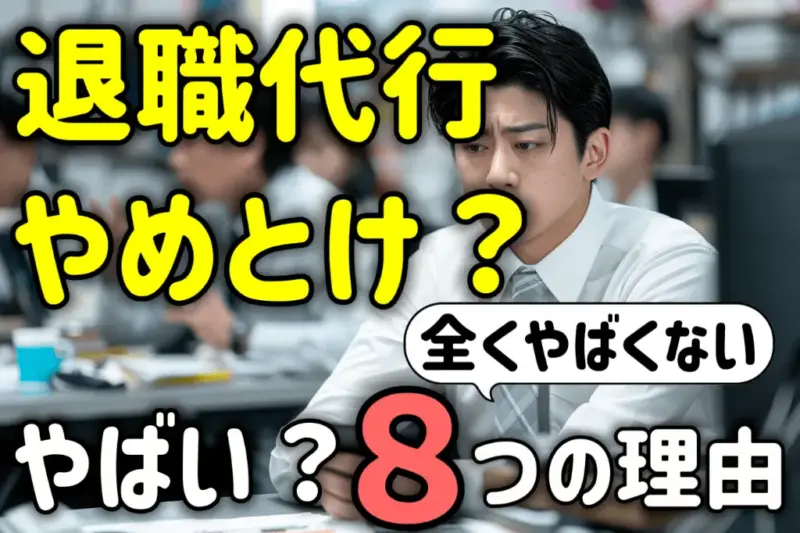辞めたいけど…退職を言い出せない・怖い時の辞め方4つのコツを解説
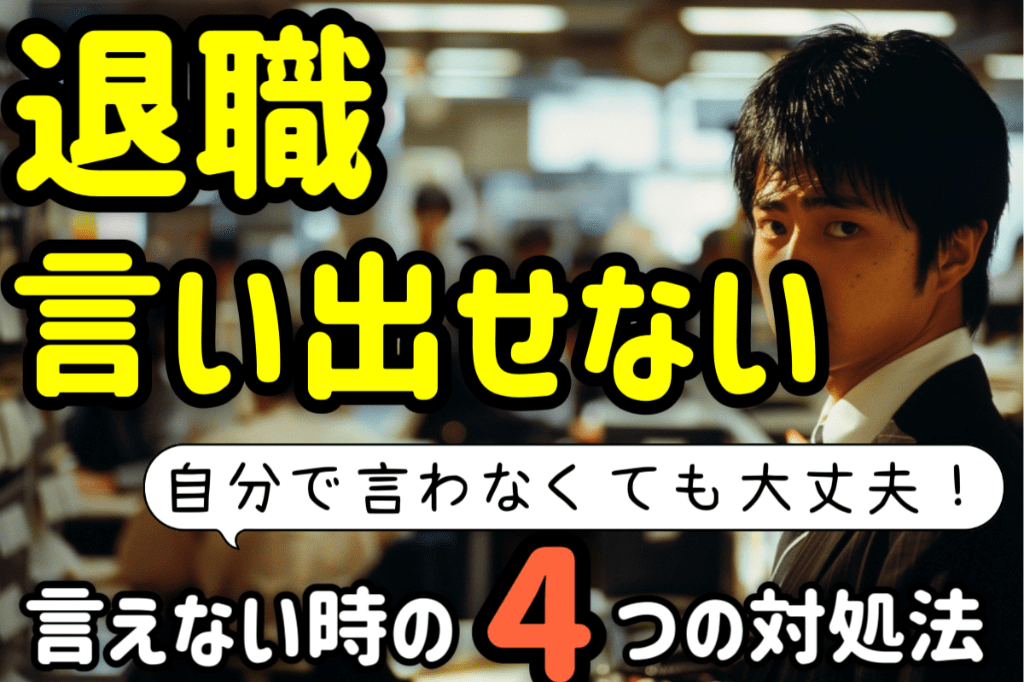
退職したいと考えながらも、上司が怖いなどの理由でなかなか言い出せずにいる方。
「退職を言い出せるようになるにはどうしたらいい?」「絶対に受け入れられる言い方などはないものか」といった疑問があるでしょう。
結論、言い出せないことの対処法は「勇気を持って自分で言う」か「退職代行サービスを使う」かの2通りの方法があります。
どうしても自分では言い出せないという方は、退職代行サービスを使うことで会社と直接やり取りせず、上司とも顔を合わせず辞められるので大丈夫です。
とはいえ自分で言えるに越したことはないので、本記事では「自分で言う」のを前提に、退職を上手く伝えるコツを伝え、その後に退職代行サービスのメリットも解説していきます。
ぜひ参考にしてください。
【この記事でわかること】
- 退職を言い出せないときの対処法は「勇気を出して自分で言う」か「退職代行サービスを使う」の2通りしかない
- 「勇気を出して自分で言う」場合は、退職が受け入れられやすいよう前向きな退職理由にし、引き継ぎをしっかりやる意思を伝えることが大切
- 「退職を言い出せない理由」別の5つの対応法も押さえておくとより退職しやすい
- 【ケース①】上司の反応が怖い:上司以外に相談する
- 【ケース②】人手不足で申し訳ない:気にしなくていいが繁忙期は避ける
- 【ケース③】転職活動が不安:転職先が決まってから言う
- 【ケース④】退職日まで気まずくなるのが嫌:退職代行で即日退職する
- 【ケース⑤】引き止められそう:引き止められにくい言い方をする
- 退職を言い出せないままだと、心身が不調になったり転職活動が不利になったりするリスクもある
- どうしても退職を言い出せないなら、退職の意思を代わりに伝えてもらえ即日退職もできる弁護士の退職代行サービスがおすすめ
1.退職を言い出せないときの根本的な2つの対処法

あなたが退職を言い出せない、言い出しづらい理由は、「上司にどう反応されるかわからなくて怖い」「人手不足だから辞めるのが申し訳ない」といったことが原因でしょう。
どうすれば良いかといえば、シンプルに対処法は2通りだけです。
【2つの根本的な対処法】
- 勇気を出して自分で言う
- 退職代行サービスを使う
(1.)まず思い浮かぶ選択肢は、「勇気を出して自分で退職を伝える」方法です。
この方法を取る場合は、「いかに会社に受け入れてもらいやすくできるか」「不安を払拭して言える状態になれるか」を考えて行動することが大切です。
(2.)2つ目は、「退職代行サービスを使う」方法です。
退職代行サービスとは、会社に「退職の意思」を伝えるところから、その後の退職の手続きを全て業者に代行してもらえるサービスです。
どうしても自分で直接「退職する」と言えない方は、退職代行サービスに頼ることで代わりに退職を伝えてもらえるため、精神的な負担もなく辞められます(詳細は7章で解説)。
退職代行サービスを使えば確実に退職を伝えられますが、どうしても利用料は発生するので、なるべく自力で伝えたいという方も多いでしょう。
そこでここからは、「自分で言う」ことを前提に、最大限会社に受け入れられやすい方法を解説していき、その後で退職代行サービスを使うメリットを順を追って詳しく述べていきます。
最後まで読んで、どちらの方法で退職を伝えるか判断してください。
2.基本編|退職を言い出すとき「受け入れられやすくなる」4つのコツ

自分で退職を伝えるなら、上司からの引き止めや拒絶はされない方がいいですし、周囲の同僚からも理解を得て円満退職を目指したいところです。
そのためには、退職を「受け入れてもらいやすくなる」コツを知っておき、退職を伝える際に実行することが大切です。
4つのコツについて、詳しく見ていきましょう。
1)前向きな退職理由を伝える
退職理由はなるべく前向きな内容にしましょう。
具体的には、「キャリアアップ」や「夢への挑戦」など、今の会社では実現が難しい「夢」を叶えるための転職であれば納得してもらいやすいです。
なお、転職先が既に決まっている場合、そのことを正直に伝えるのも引き止めにあわないために効果的です。
ただし、具体的な会社名を出すとトラブルに発展するおそれがあるので、社名は言わないように気を付けてください。
「会社への不満」を退職理由にするのは、会社との関係を悪くするおそれがあるので避けるようにしましょう。
2)会社や上司に対して感謝を述べる
会社や上司へ、これまでお世話になったことの感謝を述べるようにします。
実際には多くの不満があったとしても触れず、感謝のみで話を終わらせるようにしましょう。
「退職をスムーズに受け入れてもらうこと」が一番の目的である以上、会社や上司への不満を口にすると不要な波風を立てることになるからです。
感謝を伝えつつ、それでも理由があって辞める必要がある旨を伝えれば、今の会社を立てながらも「退職はやむを得ない」という印象を与えられます。
3)引き継ぎをしっかり行うと伝える
退職日までに引き継ぎをしっかり行うつもりであることを伝えましょう。
社員の退職が決まったとき、会社が特に心配するのが「業務の引き継ぎが上手くいくか」です。
引き継ぎをしっかりやる意思があると分かれば、会社側にも退職を納得してもらいやすくなります。
また、引き継ぎにかかる時間を考慮し、退職を伝えるタイミングもなるべく早めにしましょう。
「引き継ぎをしっかりやります」と言いながら、有給消化のため実質1日か2日しか引き継ぎ時間を取れないような場合、「口だけ」のように思われ印象を悪くするかもしれません。
4)上司の都合を聞いてから退職を相談する
退職の相談は、上司の都合を聞いてから行いましょう。
勤務時間中にいきなり退職について相談しようとすると、実務と関係ない話のため上司に悪印象になるおそれがあります。
「退職の相談をしたいのですが、ご都合のいい時間を教えてください」と尋ねて、上司の都合のいい時間を教えてもらうのがベストです。
これなら、相手が「勤務時間内で話したい」と思えばそのように返事をしてもらえるはずなので、相手の都合のいい時間帯にあわせて相談できます。
[banner id=”16503″ size=”m”]3.応用編|「言い出せない理由」別の5つの対応法

2章で述べた「基本」を踏まえた上で、「応用」として「退職を言い出せない理由」ごとの対応方法も把握しておきましょう。
退職を言い出しづらい理由は人によって違います。
各ケースの対応方法を把握しておけば「退職を言い出すこと」の心理的なハードルを下げられますし、退職自体もしやすくなります。
1)【ケース①】上司の反応が怖い
上司からどういう反応が来るか分からず、怖くて退職を言い出せない方は多くいます。
こうした場合は、絶対に直属の上司でなくてもいいので、信頼できる別の上司や、人事部門などに退職を伝えて相談してみてください。
実際に、上司の反応が怖くて言い出せなかったという以下のような体験談もあります。
苦手な適応障害の原因となってる上司に退職を言い出せません。
何て言われるだろうかとか考えてしまうし、会社に行くと仕事が次から次へと増えて次の日に自分がやらないといけないようになってしまうので次の日もいかないといけなくなってしまいます。
引用:Yahoo!知恵袋
基本的に退職は直属の上司に伝えるものですが、このように適応障害の原因になるほど苦手だったり、パワハラ気味であったりするケースでは言い出せなくても無理はありません。
直属の上司以外でも良ければ、退職を伝える心理的なハードルを下げられるでしょう。
2)【ケース②】人手不足で申し訳ない
職場が人手不足なのが分かっていて、自分が抜けることの申し訳なさから言い出せないケースも多いです。
この場合は、退職を伝えるタイミングや退職時期について「繁忙期を避けること」と、2章でも述べたように「引き継ぎをしっかりやること」を意識しましょう。
できる限りの配慮をしておくことで、退職を申し出る踏ん切りをつけられるようにするのです。
実際に、人手不足でなかなか退職を言い出せなかったという以下のような体験談もあります。
人手不足なのと入ってまだ1年目と言うこともありなかなか言い出せません。どうすればいいでしょうか、またどんなタイミングで言い出せばいいでしょうか?
引用:Yahoo!知恵袋
ですが、人手不足の解消は本来会社が日々取り組むべきことで、あなた1人が努力してどうにかできる問題ではありません。
「人手が足りないから」「入ってまだ1年目だから」と罪悪感から退職を言い出すことをためらう必要はないのです。
3)【ケース③】転職活動が不安
今後の転職活動がどうなるかが不安で、退職したいのに言い出せないケースもあります。
「勤務先でうまくやれるか」「辞めたら後悔しないか」など色々な不安を抱えた状態で、退職に踏み切れないのです。
この場合は、転職先を決めてしまってから退職を伝えることをおすすめします。
転職先が決まってしまえば、もう次の会社に行くしかないので、切り出すのを悩んでいる暇もなくなります。
ただし、今の会社と退職交渉が上手くいかずトラブルになった場合、転職先の入社日が決まった状態だと迷惑をかけてしまうおそれがある点には注意してください。
入社予定日まで十分に余裕を持った状態で今の会社に退職を伝えるか、入社が遅れる可能性があることをあらかじめ転職先に相談しておくといいでしょう。
4)【ケース④】退職日まで気まずくなるのが嫌
退職を伝えた後、退職日を迎えるまで周囲と気まずくなってしまうのが嫌で、退職をなかなか言い出せないケースがあります。
気まずい空気のまま過ごすのが我慢できないなら、冒頭で触れた退職代行サービス(詳細は7章で解説)を利用しましょう。
退職代行サービスを使えば即日退職ができ、使った日から出社せずに退職できるため、気まずい思いをしながら職場で過ごす必要がなくなります。
実際に、退職日まで気まずいのが嫌で退職を言い出せない方の以下のような体験談もあります。
普通に辞めるのであれば、何とか言い出せそうですが、少なくとも次の人が見つかるまでは止められそうで、その場合どうしたらいいのか、辞めたいけど辞めるまでの間気まづいのも嫌だ、それもずっと求人を出しているのに一向に見つかってないので辞めれる気がしません。
引用:Yahoo!知恵袋
自分で退職を伝える場合、退職日まで気まずい状態になるのはよくあることで、基本的にはそういうものと思って我慢するしかありません。
我慢できないなら、退職代行サービスを検討してみてください。
5)【ケース⑤】引き止められそう
退職を伝えたら上司から引き止められそうと感じ、言い出せないケースもあります。
この場合は、「引き止められにくい退職の伝え方」をした上で、さらに「実際に退職を引き止められたらどう行動するか」もあらかじめ考えておくことが大切です。
いざというときどう対応すべきかがわかっていれば、勇気を持って退職を伝えやすいでしょう。
例えば、退職を伝えるときは「退職したいと思っているのですが…」といった伺いではなく、「退職します」と確定的に伝えて、引き止められる余地がないようにします。
他にも、退職のスケジュールや「引き継ぎ」の日程について自分から提案するなど、退職の意思が動かないことを示すのも効果的です。
退職を引き止められた場合の断り方については以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひあわせて参考にしてみてください。
4.退職を伝えてから円満に辞めるための流れ

3章で述べたように、退職を言い出せない理由の多くには、「上司が怖い」「気まずいのが嫌」「引き止められたら…」といった円満に退職できるかわからない不安があります。
円満退職するには、退職を言い出す段階のみではなく、退職の意思を伝える~退職までの全体の「流れ」も把握しておくことが大切です。
流れを把握することで、退職までの解像度が上がり、円満に辞めるため何に気を付けるべきかもわかるようになります。
今退職を言い出せない方も一歩を踏み出しやすくなるはずです。
1)退職を伝える
少なくとも退職日の1ヶ月前には上司に退職の意思を伝えます。
なぜ辞めるのかを尋ねられることも多いので、2章で述べたように「前向きな退職理由」をあらかじめ準備しておきましょう。
「引き継ぎ」をしっかり行うつもりがあること、「会社や上司への感謝」も丁寧に伝えます。
さらに、3章で解説した「退職を言い出せない理由」別の5つの対応方法も参考に、退職の言い方や伝え先を変えてみてください。
2)引き継ぎや有給消化のスケジュールを上司と相談する
上司と相談し、引き継ぎや有給消化のスケジュールを決めましょう。
会社の業務の状況を確認しつつ、「◯日までに引き継ぎして、◯日分の有給を消化して、◯日に退職したい」と自分から提案してみてください。
提案した日程が必ず通るとは限りませんが、受け身すぎると会社の都合を押し付けられてしまうおそれもあります。
会社の状況にあわせて融通を利かせられるようにしつつ、無茶を言われたときはきちんと断りを入れて、双方が納得できるように話を進めてください。
退職時に有給消化するコツや手順については以下の記事でも解説しています。
3)退職届を提出する
退職までのスケジュールについて上司と合意を取れたら、退職届を提出します。
退職届は一度提出すると原則として撤回できないので、上司と相談の上、退職日が確定してから提出するようにしてください。
退職届のテンプレートもありますので、書き方に迷った場合は活用してください。
4)担当業務を後任や上司に引き継ぐ
退職日までの間に後任への引き継ぎ作業を済ませます。
引き継ぎといっても何ヶ月もかける必要はなく、最終出社日までの間に、あなたができる範囲の引き継ぎをしておけば大丈夫です。
後任がまだ決まっていない場合は、一時的に上司に伝えておくといいでしょう。
簡単な引き継ぎ用のマニュアルを作っておき、後任がすぐ確認できるようにしておくとより安心です。
特に、直近の業務の進捗や、あなただけが知っている資料やデータの保管先などは優先して共有しておきましょう。
5)私物の持ち帰り・貸与物の返却を行う
退職前には、会社にある私物を確認し、忘れ物がないようにすべて持ち帰っておきましょう。
会社から貸与されている以下の備品も退職前に必ず返却してください。
【返却が必要な貸与品】
- 社用PC・スマートフォン
- 制服
- USB
- 社内資料
- 社内施設の鍵
貸与品を返さずにいると、会社側から法的な責任を問われることもあるので注意してください。
6)会社でお世話になった人に挨拶する
最後に、お世話になった上司や同僚に挨拶します。
対面しやすい相手であれば、退職前に相手のもとに個別に出向いて、感謝を直接伝えに行きましょう。
対面での挨拶が難しい場合は、メールやLINEなどで伝えるだけでも問題ありません。
何もしないでそのまま退職してしまうよりも、丁寧で誠実な印象を与えられるでしょう。
[banner id=”16503″ size=”m”]5.退職を言い出せないことによる3つのデメリット

退職を言い出せないまま会社に残り続けると、あなたの今後の人生にも影響するような以下3つのデメリットがあります。
- 心身の不調が続く
- パフォーマンスが低下し減給や降格になる
- 転職が不利になるリスクがある
これらのデメリットを被らなくて済むように、退職したいと思った時点で早くから行動を起こすことが大切です。
1)心身の不調が続く
退職を言い出せずにずるずると会社に居続けると、職場環境や業務へのストレスが蓄積していき、心身の不調が続く可能性があります。
限界に達した場合、無断欠勤してしまったり、うつ病の発症につながったりすることもあります。
特に会社で何らかのハラスメント・残業・休日出勤が多すぎるといった状況なら、一刻も早く会社から離れるべきです。
心身を壊してしまうと取り返しがつかないため、なるべく早く退職のための行動を起こしましょう。
2)パフォーマンスが低下し減給や降格になる
退職を考えている状態が続くと、仕事に対する集中力やモチベーションが低下し、業務に身が入らなくなりがちです。
その結果、ミスが増加したり、求められる成果を上げづらくなったりして、上司や同僚からの評価が下がるおそれがあります。
また、仕事の質が低下すれば、減給や降格といった形で具体的なペナルティを受けることもありえます。
こうした状況は、さらにストレスにつながってしまい、前項の心身の不調を招く負のループとなってしまうでしょう。
3)転職が不利になるリスクがある
退職を言い出せないままだった場合、転職活動が不利になることがあります。
まず、「第二新卒」という言葉があるように、中途採用は若手の方が好まれます。
年齢を重ねるごとに採用のハードルが上がっていくのです。
よほど即戦力になれる実力があるなら別ですが、そうでないなら若いうちに行動した方が転職に有利なのは間違いありません。
また、退職のタイミングが遅れることで、応募したい企業の採用に間に合わなくなる可能性があります。
さらに、先に述べた心身の不調や業務のパフォーマンス低下により休職に追い込まれ、職歴に傷がつき、転職活動でも厳しく見られてしまう可能性もあるでしょう。
6.退職を切り出した結果しつこく引き止められたら?

これまで「勇気を持って自分で退職を伝え、受け入れてもらうための方法」を解説してきました。
ですが、退職をやっとの思いで切り出せたとしても、上司からしつこく退職を引き止められスムーズに退職できないことはあります。
そこで、ここでは退職をしつこく引き止められたときにどう動くべきかを解説します。
1)退職の気持ちが揺るがないことを示す
引き止められても動揺を見せないようにし、「退職する気持ちは変わらない」ことを繰り返し冷静に伝えましょう。
ここで迷ったり慌てたりする姿を見せてしまうと、「強く押せば気持ちが変わるかもしれない」と思われ、余計に引き止めがしつこくなる可能性があります。
最初から冷静に引き止めを断ることで、説得できる可能性はないとわかってもらう必要があるのです。
ただし、1度引き止められたからといって不機嫌な態度は取らないようにしてください。
上司があなたに「退職を考え直す気はないか」と確認すること自体が悪いわけではないからです。
2)法的な正当性を主張する
上司にしつこく引き止められたら、法的なルールに基づく「退職の正当性」を主張しましょう。
正社員は、退職を申し出てから2週間後には退職できます。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
つまり、退職の意思を伝えているにもかかわらず、2週間を過ぎても退職を認めないのは「違法」なのです。
こうした法的なルールについて丁寧に説明し、「退職を認めてもらえないなら労基や弁護士などの外部に相談する」と交渉してみてください。
面倒になることを嫌がり、退職を認めてもらえる可能性があります。
3)人事に相談する
上司から退職をしつこく引き止められるようなら、人事部門に相談してみましょう。
退職したいと言っている社員を退職させないのは「違法」であり、労働基準監督署が知れば指導の対象になりうる行為です。
人事部門であれば、そういった法的ルールについてもきちんと把握しているはずなので、すんなり退職を認めてもらえる可能性が高いです。
念のため、人事部門とのやり取りは書面や録音を使って証拠として残しておくようにしましょう。
4)弁護士の「退職代行サービス」を使う
上司がどうしても退職させてくれない場合は、弁護士がやっている「退職代行サービス」へ依頼(詳しくは7章で解説)しましょう。
退職代行サービスとは、会社に「退職の意思」を伝えるところから、その後の退職に必要な手続きを代行してくれるサービスです。
特に弁護士の退職代行サービスでは、弁護士があなたの「代理人」として、会社との交渉や退職に必要な手続きを全て引き受けることができます。
あなたの退職をしつこく引き止める上司に対し、退職を認めるように法的な根拠にもとづいて交渉し、確実にあなたの退職を認めさせてくれます。
7.退職を言い出せない人には弁護士の「退職代行サービス」がおすすめ

対応法やコツをどれだけ学んでも、どうしても上司が怖い、あるいは職場の雰囲気によって退職を言い出しにくいという方もいるでしょう。
そんなときは、無理せず退職代行サービスを利用するのがおすすめです。
退職代行サービスを使えば、後ろめたさを感じることなく、スムーズに退職手続きを進められます。
ここでは特に弁護士のサービスを使うメリットを詳しく解説するので、利用するかどうかの判断に活用してください。
利用を決めたときは、以下のバナーから無料相談もできます。
[banner id=”16789″ size=”m”]1)【理由①】自分で言い出す・交渉する心理的負担がなくなる
退職代行サービスを使えば、自分の代わりに退職代行業者に「退職の意思」を伝えてもらえます。
自分で言い出す心理的な負担なしに、退職手続きを進めてもらえるのです。
また、自分で会社を辞めようとするときは、「退職します」と伝えるだけでは終わらず、スケジュールを調整し引き継ぎなどの交渉も行わなくてはいけません。
パワハラするような問題ある上司が相手の場合、退職を伝えた後も交渉が続くことに強いストレスを感じる方もいるでしょう。
退職代行サービスに頼めば、引き継ぎ業務についても代行業者を通して連絡できますし、その他の退職に必要な交渉の一切を任せられます。
サービスを使うことで、会社と直接のやりとりを徹底的に避けられ、ストレスから解放されるのです。
2)【理由②】有給消化や退職金などの交渉も任せられる
弁護士の退職代行サービスであれば、有給消化や退職金の請求に関する交渉も任せられます。
こうした交渉を法的な根拠に基づいて行えるのは弁護士のサービスだけです。
会社によっては、もう辞めるんだからと有給消化を拒んできたり、もらえるはずの退職金を不当に支払わなかったりすることがあります。
弁護士なら、有給消化拒否や、もらえるはずの退職金の不支給は「違法」であると交渉してくれます。
あなたが確実に有給分の給料や退職金を受け取れるようにしてくれるでしょう。
3)【理由③】即日退職できるので気まずい思いをしない
退職代行サービスを利用すれば、確実に即日退職ができます。
そもそも、正社員は「退職する」と伝えれば2週間後には退職できると法律で決まっており、実質的な即日退職(明日から出社しない)も含めると以下の3つの方法があります。
【即日退職のやり方(明日から出社しない方法含む)】
- 会社と「即日退職」の合意を取る
- 退職日までの2週間を有給消化で過ごす
- 退職日までの2週間を欠勤扱いにしてもらう
ですが、あなたが会社に直接「今日で退職するので明日からもう会社に行きません」と伝えても、合意を取るのは難しいでしょう。
怒鳴りつけられたりする可能性もありますし、退職自体は認めてくれた場合でも、引き継ぎのためにある程度は出社するように言われるはずです。
退職代行サービスであれば、会社と「即日退職」の合意を取るための交渉や、残った有給を消化して退職するための交渉をしてくれます。
「明日から出社しない」こともできるため、職場で気まずい時間を過ごす必要もなくなるのです。
なお、退職代行を使って即日退職することについては以下の記事でも解説しているので、あわせて確認してみてください。
まとめ
退職を言い出せないときの対処法は、「勇気を出して自分で言う」か「退職代行サービスを使う」のどちらか2通りしかありません。
まずは「自分で言う」方向で考えてみて、難しそうなら「退職代行サービス」を使ってみましょう。
「勇気を出して自分で言う」場合は、退職が受け入れられやすいよう前向きな退職理由にするほか、引き継ぎをしっかりやる意思を見せることが大切です。
また、「退職を言い出せない理由」は人によって違いますが、言い出せずにいる理由別の5つの対応法でより退職を進めやすくなるので押さえておきましょう。
- 【ケース①】上司の反応が怖い:上司以外に相談する
- 【ケース②】人手不足で申し訳ない:気にしなくていいが繁忙期は避ける
- 【ケース③】転職活動が不安:転職先が決まってから言う
- 【ケース④】退職日まで気まずくなるのが嫌:退職代行で即日退職する
- 【ケース⑤】引き止められそう:引き止められにくい言い方をする
退職を言い出せないままだと、心身の不調を招いたり、転職活動が不利になったりするリスクもあります。
退職したいと思った時点で早くから行動を起こすことが大切です。
どうしても退職を言い出せないなら、退職の意思を代わりに伝えてもらえる上、即日退職も法的な根拠にもとづいて交渉できる弁護士の退職代行サービスがおすすめです。
[banner id=”16503″ size=”l”]