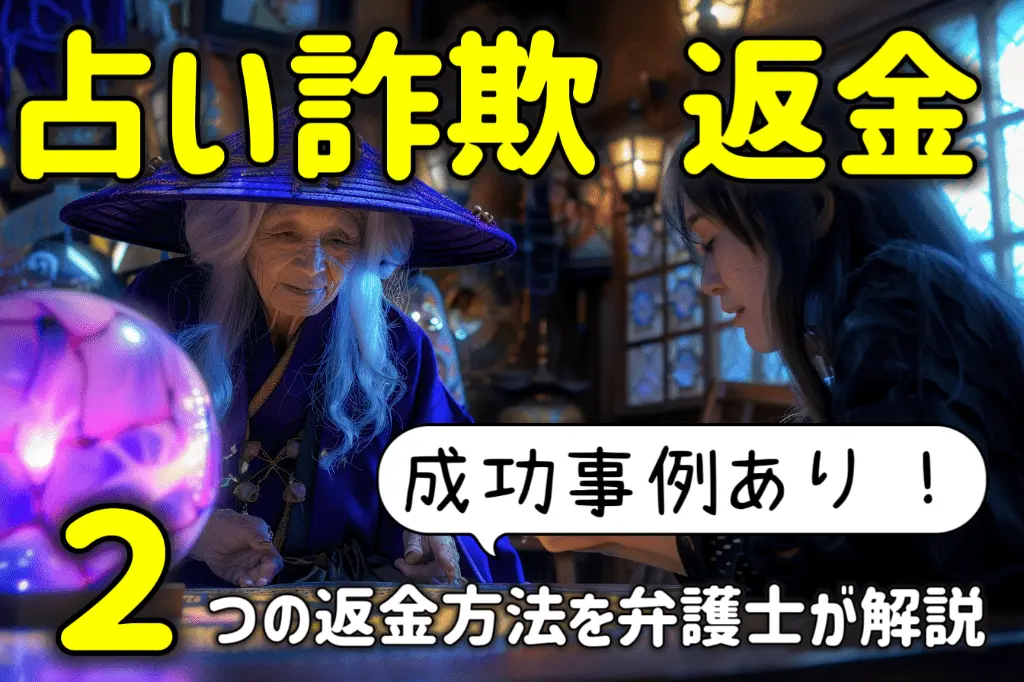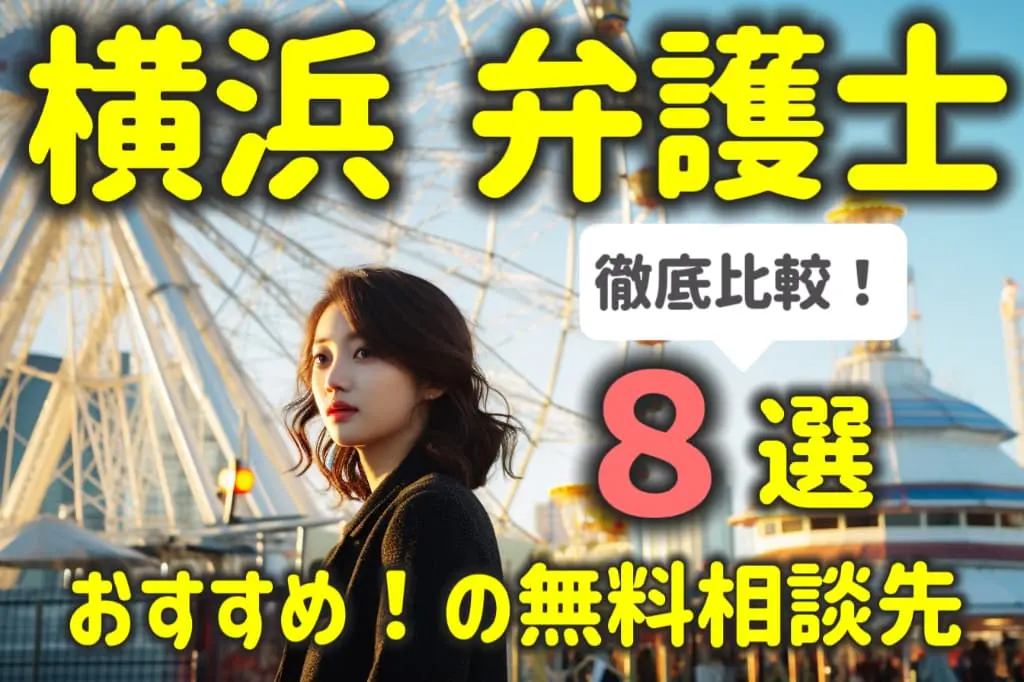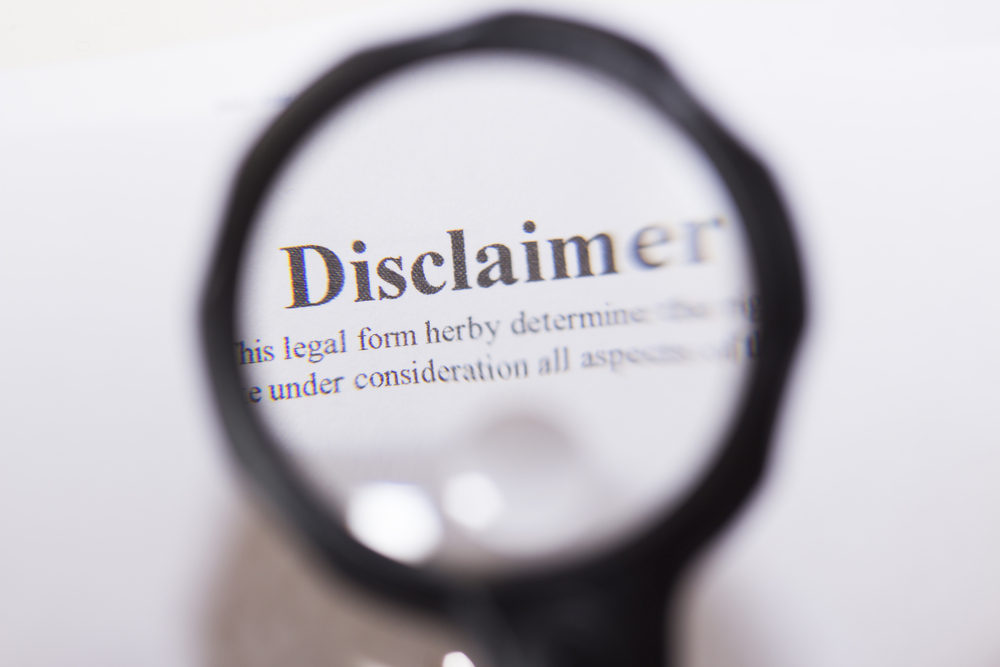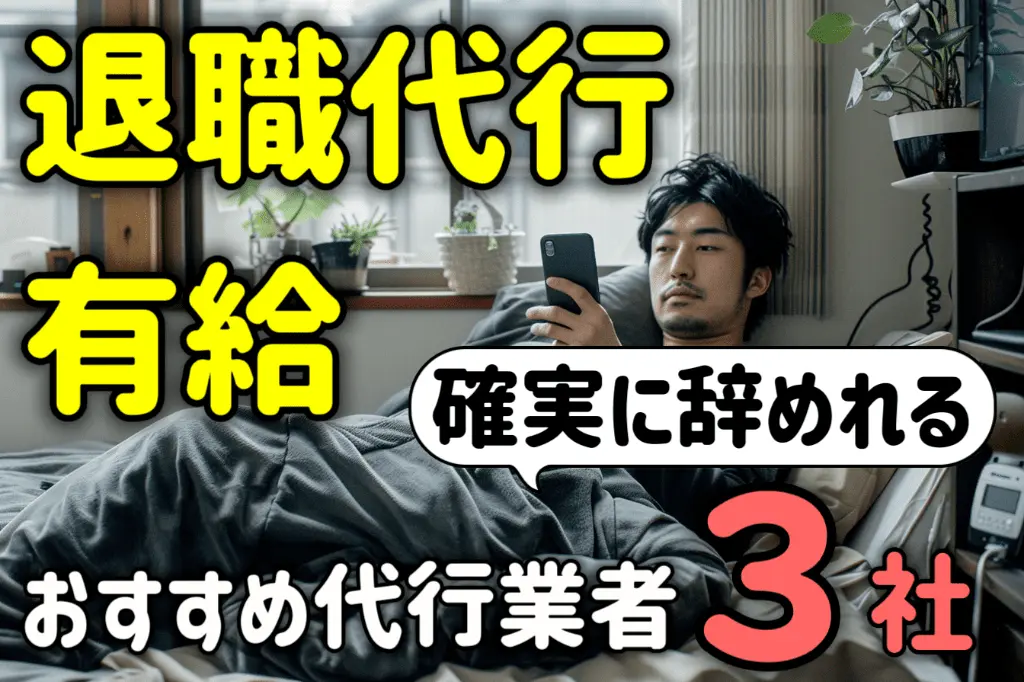NFTとは何かをゼロから分かりやすく解説します

0 はじめに
弁護士の勝部です。
この記事では、NFTとは何かについて詳しく説明していきたいと思います。
近年、Twitter創業者であるジャック・ドーシー氏が出品した「最初のツイート」が3億円以上の価格で落札されたというニュース(参照)が話題になりました。
このようなニュースの中で、NFTは「ブロックチェーンを使ってデジタルコンテンツを取引する仕組み」などと紹介されることが多いのですが、おそらくこれでは何のことだか意味が分からない方もいると思います。
そこで、今回は、そもそもNFTが何なのか、できる限り分かりやすく説明していきたいと思います。
1 トークンの概念
NFTとは「Non-Fungible Token」の頭文字を取った略称で、直訳すると、非代替の性質を持つトークンということになります。
こう言われても、非代替?、トークン?、といまいちピンとこないかも知れません。
そもそもトークンという単語が分かりづらいと思います。
(1)トークンとは何か?
トークンとは、何かを示すもの、しるしとか証拠を意味する概念です。
たとえば、ゲームトークンは、ゲームをするために購入するコインであり、ゲームセンター内ではお金の代わりとして使うことができます。
ゲーム用のコインはゲームをするためにお金を払った証拠であり、これをゲーム機に投入してゲームができます。
語源は異なりますが、クーポン、チケット、バウチャー等の単語と似た概念と理解しても、それほど間違ってはいないと思います。
トークンは、前払いで代金を支払って後で商品と交換したり、特定のチケットを持っている人だけに入場を許可したり、割引をしたり、という用途で用いられることが多いですが、トークンの用途はこれに限られません。
もう少し抽象化すると、トークンやチケットは、それを持っている人と持っていない人を区別して取り扱うことができるようにする媒介物、という理解をすることが可能です。
(2)ブロックチェーントークンとは
NFTはブロックチェーンの仕組みを用いて発行されるブロックチェーントークンです。
ブロックチェーントークンとは、ブロックチェーン技術を用いて実現したトークンの仕組みと説明できます。
ブロックチェーンは、もともとビットコインのホワイトペーパーで提唱された概念ですが、ブロックチェーンは、特定の管理者なしに、不特定多数のユーザーが同じ情報を共同して管理する、分散台帳を実現するための仕組みです。
ビットコインはもともと中央銀行を用いない価値交換をするための私的通貨として提唱されたので、ブロックチェーンも通貨の残高を管理するためのものでしたが、そこで管理可能なのは通貨の残高に限りません。
改ざん不可能な状態でデータを書き込むこともできますし、通貨以外のトークンなどを発行する用途にも転用することも可能です。
ビットコインのブロックチェーンシステムは、以下の図ように、どのアドレスからどのアドレスにどれだけの残高が移転したかの情報(transaction)を保有します。マイニングによって最初にビットコインが発生してから、誰に対して移転したのかの全ての情報がブロックチェーンに書き込まれているので、ブロックチェーンを参照すると、各アドレスにどれだけのビットコインが帰属しているかが分かります。

トランザクションを作成するためには、送信する側のアドレス保有者が自身の保管する秘密鍵を利用して電子署名をする必要があり、秘密鍵で署名できることが当該アドレスの保有者であることの証明となります。
この仕組みを応用すれば、アドレス単位で発行されたトークンが誰に帰属しているかを区別するシステムを構築できます。
これがブロックチェーントークンです。
2 NFTの概念
近年、NFTの仕組みが注目されていますが、NFTの概念自体は2017年頃からあります。
最初に述べた通り、NFTはNon-Fungible Token(非代替的なトークン)という意味で、NFTの仕様によって発行されたトークンは、それぞれ代替できないものとなります。
これに対し、1で説明したビットコインなど、通貨のように用いられるものは代替性があります。
代替性がある、ない、というとイメージしにくいと思いますが、ビットコインは、同じ1ビットコインであればどのビットコインも同じものとして扱います。
これに対し、NFTの仕組みで発行されたトークンはそれぞれ異なるものとして扱います。
ビットコインのような代替性は、通貨の機能(尺度、保蔵、交換)を果たすために重要です。
例えば、ビットコインアドレスに0.3BTCを送付した後に、同じビットコインアドレスに0.7BTC送信したとすると、このアドレスには合計1.0BTCが帰属しているというように処理されます。

NFTはそれぞれのトークンは別物と考えるので、このような処理はされません。
NFTの場合、すべてのトークンには異なる番号等が付されるなどして管理されるため、それぞれが異なるトークンとして扱われます。
そのため、xxxxxxxx1とxxxxxxxx2が同じアドレスに帰属しても、別々のトークンを合計2つ保有していると処理されることになります。

3 非代替であることの帰結
(1) 暗号資産に関する規制の適用外となる
NFTが非代替という性質を持つことにより、NFTは資金決済法上の「暗号資産」に該当しないと解釈される可能性があるという帰結が導かれます。
つまり、NFTを法定通貨や暗号資産で販売する事業を実施したとしても、資金決済法上の暗号資産交換業の登録をしなくてもよい、ということになるのです。
(2)なぜそのような解釈がされるのか
その理由は、資金決済法の「暗号資産」の定義にあります。
資金決済法第2条第7項1号によると、(1号)暗号資産の定義は以下のとおりです。
-
(1号)暗号資産の定義
物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
NFTは、一つ一つのトークンに代替性がないため、数量的に価値の尺度として用いることが困難であり、そうであるとすれば、支払手段としての経済的機能を果たすことができないということになります。
支払手段としての経済的機能が認められないのであれば、代価の弁済等に使用することができるという要件を充足しないことになり、暗号資産には該当しないということになるのです。
仮想通貨交換業(暗号資産交換業)の登録は時間もコストもかかり、かなり困難であると考えられていますので、このことは、ブロックチェーン関連技術を用いてビジネスを展開したい方に取ってのメリットとなります。
※「暗号資産交換業登録の概要」について詳しく知りたい方は、「【詳細解説】日本で暗号資産交換業者登録するために必要となる収益・資金は?」をご覧ください。
(3)「支払手段としての経済的機能を果たす」か否かの考え方
ただし、NFTであるから必ず暗号資産に該当しないとも言い切れないのが難しいところです。
そもそも、NFTは「代替性のない」トークンですが、ここで、「代替性がある」「代替性がない」というのはコンピュータープログラムの仕様によって定まります。
現在、トークンを生成するために最もよく使われているプラットフォームはイーサリアム(Ethereum)です。
イーサリアムというと、ビットコインと並んで人気のある暗号資産と理解されている方も多いですが、正確にいうと、イーサリアムはアプリケーションのプラットフォームです。
アプリケーションのプラットフォームですので、ユーザーは、イーサリアム上でアプリケーションプログラムを記述したり、実行したりすることが可能です。
そして、イーサリアム上でプログラムを記述したり動作させたりするために用いるプラットフォーム内の通貨がイーサ(Ether)であり、暗号資産交換所でイーサリアムとして取引されているのは、正確にいうとイーサであるということになります。
イーサリアムの機能を使って、自分の好きなトークンを発行することができるのですが、トークン発行時によく用いられる共通規格として、ERC20とERC721があります。
単純化して説明すると、ERC20は代替トークンを発行する場合に用いられる規格で、ERC721は非代替トークンを発行する場合に用いられる規格があります。
このような説明を前提にすると、要するにERC721に準拠して発行されたトークンは全てNFTであり、ERC721トークンは一般に販売しても何の規制もない、と誤解されがちです。
しかしながら、トークンに代替性がないからといって、必ずしも支払手段としての経済的機能を果たせないとも言い切れません。
例えば、一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会のガイドラインには以下の記述があります。
-
もっとも、NFTの技術的性質から直ちに決済手段性が否定されるわけではなく、当該NFTの性質・仕組み・用途、当該NFTを利用する事業やサービスの内容等を踏まえ個別具体的な検討を要する点に留意が必要です。例えば、日本銀行券(一万円札など)には通し番号がある点では個別性があるといえますが、通常はそれによって個々のお札は区別されず、決済手段として一律に用いられています。
当たり前ですが、通し番号を付けただけで各トークンを同じものとして扱えば決済に利用可能となります。
逆に、一般に代替性のあるトークン規格であるERC20をベースにしたとしてもNFTのような実装をすることができる可能性もあり、実際にそのような事例もあります。
ERC20やERC721は絶対的な規格ではなく、solidityというプログラミング言語でプログラムを作成する際の規格でしかないので、法規制と厳密にリンクしているわけではありません。
単純にERC721等のトークンであれば全てNFTというわけではないので注意が必要です。
仮に暗号資産に該当しなくても、利益配分を約束したトークンであれば金融商品取引法の規制が及ぶことも考えられるので、トークンの設計をする際には細心の注意が必要です。
4 まとめ
以上、NFTとは何かについて基本的な部分からご説明しました。
近年、多くの暗号資産交換業者がNFTプラットフォームのリリースに乗り出すなど、NFTのビジネスは大きな注目を集めています。
もはやレッドオーシャンとなってしまった代替性トークンよりも、高値で取引されやすいNFTの方がビジネスとしての可能性は大きいかも知れません。
アイディア次第でこれから様々なサービスが生まれてくると思います。
弊所は、ビジネスモデルのブラッシュアップから法規制に関するリーガルチェック、利用規約等の作成等にも対応しております。
弊所サービスの詳細や見積もり等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。