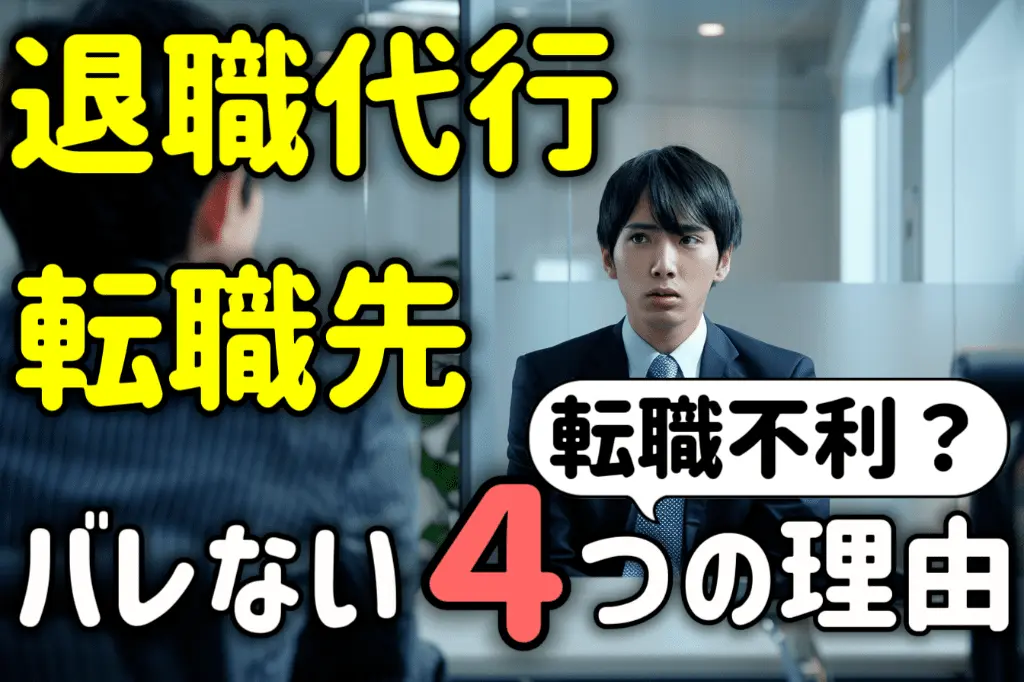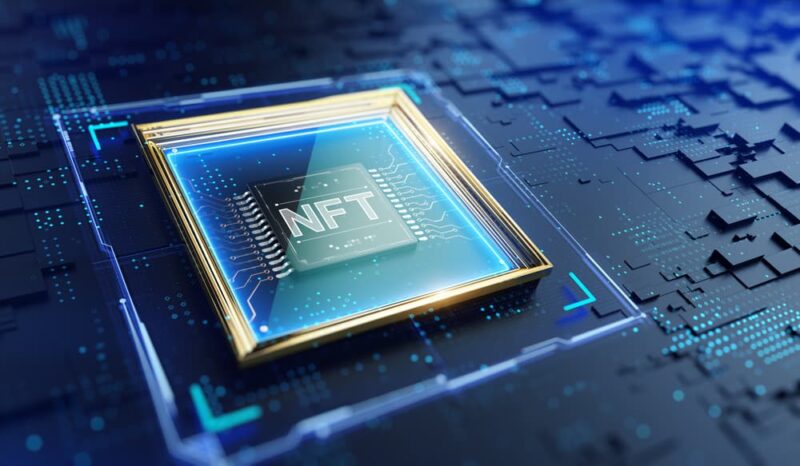【詳細解説】日本で暗号資産交換業者登録するために必要となる収益・資金は?

はじめに
こんにちは、弁護士の勝部です。
暗号資産交換業(仮想通貨交換業)を営むためには登録が必要です(資金決済法63条の2)。
そして、現在、日本で暗号資産交換業登録をしている会社はたったの31社です。
単純比較はできないとしても、第一種金融商品取引業者の数(308社)と比べて少ない印象です。
※ 登録業者の数はいずれも令和3年8月31日現在
そこで、このエントリーでは、「なぜ暗号資産交換業登録が少ないのか?」という点と、暗号資産交換業登録のためには、具体的にどれくらいの財務要件(毎月の想定コストや、資本金、初期の純資産)が必要なのかという点について説明をしていきたいと思います。
-
本エントリのポイント
- 暗号資産交換業の体制維持に必要な月額コストは概ね1000万円以上
- 暗号資産交換業登録のための要求水準は時期によって差異がある?
- 具体的な要求事項の内容は?
これから暗号資産事業(ブロックチェーン、NFTに関連するビジネス含む)の立ち上げを検討されている方の参考になれば幸いです。
1 暗号資産交換業登録の難易度
(1) 業登録難易度の遷移
暗号資産交換業登録の難易度には時期によって差がありました。
私が最初に交換業登録に携わったのは2017年上旬の新法改正直後でしたが、新法施行時にみなし業者になっていた事業者について言えば、登録の難易度は標準的で、一定レベルの社内態勢構築ができていればそう難しいものではなかった印象です。
もちろん、分別管理や内部統制などの基本的事項に問題のある業者については別ですが、当時の印象としては第二種金商業と同レベルで、一種業より難しいということはなかったと記憶しています。
(2) 冬の時代
状況が変わった一つのきっかけは、2018年初旬にあった大手仮想通貨交換業者の大規模流出事故です。この件によって、暗号資産交換業の遂行に関してこれまで潜在的にしか理解されていなかったリスクが認識されるようになりました。
遡ると、2017年の末頃から仮想通貨交換業登録希望の件数が異常な数に上ったために、登録申請の相談をしても全く進展がない状況となっていました。余りに登録審査が進まないため、既存登録業者に対するM&Aの噂もちらほら聞かれるようになっており、その時点からすでに仮想通貨交換業は取りにくいという状況が発生していたのですが、大規模流出によって登録のための要求水準は更に上がり、国内有数と言われる大手事業者ですら登録完了までかなりの時間を要する状況になりました。
2018~19年は相場の冷え込みもあって暗号資産冬の時代という様相で、この時期は十分な財務基盤を有する会社ですら多額の投資を放棄して撤退の憂き目にあう事例もあったほどです。
(3) 現状
他方、ブロックチェーン技術に関する開発に関する社会的関心は低迷期であってもそこまで影響を受けていなかったこと、日本国外においては大型案件も相変わらずあったこともあり、2020年には徐々に相場も盛り返し、2021年にはNFTブームで再び案件が増えてきているという状況です。
※ そもそもNFT関連事業に業登録が必要かという点については別エントリで解説予定です。
※「NFT規制の概要」について詳しく知りたい方は、「【NFTは暗号資産にあたる?暗号資産交換業の該当性を弁護士が解説!」をご覧ください。
法規制の面では、2020年5月に大きな法改正があり、STOやカストディ業に関する新たなルールがスタートしました。
登録の難易度としては、一時期の過剰なまでのレギュレーションは落ち着いたものの、相変わらず新規参入組にはなかなかハードルが高い状況であると言えます。
2 なぜ暗号資産交換業登録が難しいのか?
では、なぜ暗号資産交換業登録が難しいのか。
少なくとも、仮想通貨交換業に関する最初の規制状況は、当時の金融庁の方針もあり、比較的穏当なものでした。規制が厳しくなっていったのは理由もなくそうなったのではなく、それなりの理由があったというのが私の理解です。
規制の細かい部分は法務部や法律事務所の関心事であり、要因は様々ですが、これから事業を立ち上げたいプレーヤーの目線で説明するならば、シンプルな話、事業を維持するためのコストが非常に高くなり、事業計画が立てにくいという結論に行き着くということが言えると思います。
確かに、法令上求められる財産的基礎について言えば、資本金は1000万円以上(法第63条の5、内閣府令9条)であり、見た目上全くハードルは高くありません。
しかしながら、「この章(暗号資産)の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない法人」が登録拒否事由になっている(法63条の5第6号)ことから、財務局から見て必要な体制が備わっていないと判断されればいつまでも登録ができないということになります。実はこの「必要な体制」というのがポイントなのです。
そして、この体制整備のために高いコストがかかるので、結果的にお金がないと暗号資産交換業の登録はできないということになるのです。
限られたスペースで全ての要求事項を列挙するのは難しいですが、よくネックになるポイントをいくつか列挙します。
(1)KYC、取引時確認や不公正取引管理のコスト
暗号資産交換業者は犯罪収益移転防止法の特定事業者に該当するので、取引時確認が必須となります。
口座開設時の本人確認書類チェックの手間だけではなく、反社データベース(情報ベンダからの情報受領等含む)等も必要になってきます。
また、不公正取引に対応するためにはそのためのシステム構築も必要になってきます。
こういった業務を適切に実施するにはオペレーションやシステムのノウハウが不可欠ですし、これまで金融関連業の経験がない事業者の目から見ると想定以上のコストとして映るようです。
(2)監査費用、顧問弁護士、協会会費等
暗号資産交換業者は、顧客から預かっている暗号資産の管理方法について年一回分別管理監査を受けなければなりません。この義務は法令上の義務であるため、当たり前ですが全業者必須です(法63条の11)。
分別管理監査は監査法人にとって一般的な監査ではないため、対応できる監査法人は限られていますし、費用も相対的に高額になってきます。
また、必須ではありませんが顧問弁護士に登録申請やコンプライアンス態勢の整備を委託する場合はそのコストがかかってきます。
また、一般社団法人日本暗号資産取引業協会(JVCEA)の会費負担も発生してきます。協会への加入は法令上の義務ではありませんが、加入状況や加入のメリットを考えると基本的には加入の方向で検討するのが一般的です。
(3)人件費
暗号資産交換業者は顧客から大量の暗号資産を預かったり、取引に関与することになるわけですから、社内外において高いレベルの法令遵守を実現するために、様々な専門的知識・経験を有する人材の確保が必要になってきます。
金融関連法務の長い経験を有する有識者や、金融関連システムに精通した責任者、業務によっては複数の人員が必要になるものもあるため、必要とされる業務から逆算した人員の採用と、それを維持するための売上や資金が必要となってきます。
システム人員については外部委託によって外出しすることも可能ですが、金融のシステムベンダの単価は決して安くありません。約定速度の維持や帳簿類の対応も含めると、金融の経験のないベンダへの発注は躊躇せざるを得ません。
まして、暗号資産交換所は世界中の至るところからハッキング攻撃の対象になっていると言っても過言ではなく、そのリスクは現物を扱っている伝統的な証券会社よりも高いと言えます。
指摘を受けて後からシステム構築をやり直すくらいなら最初からきちんとしたベンダに発注するべきですが、スタートアップには辛い出費です。
3 結局いくら必要になるのか?
こういった事情から、暗号資産交換業を適正に遂行するためには非常に大きなコストを要することになります。
ただし、各コストが必要になるのは上記のようにそれぞれ理由があるものであって、必ず負担を求められるわけではないことに注意が必要です。
ビジネスモデルや業務スキーム設計、その他の工夫である程度省力化することは可能で、一概に「最低いくら必要」とか、逆に「いくらあれば十分」ということは言えない側面もあります。
それでも、一応の目安として数字を上げるならば、まともな暗号資産交換業者であれば、月平均で1000万円 ※くらいのコストは当たり前のように出て行ってしまうのではないかという印象です。これがミニマムというわけではないですが、これより少ないと維持が難しいのではという印象を持たれる可能性があります。
※ この数字は登録初期を想定した上での経験則的な見立ても含めた目安です。登録済の業者の開示情報を見ればそれぞれの業者の負担コストは把握可能です。
登録審査の際には、体制整備は当然の前提として、資金余力やビジネスモデルの中身も審査対象になってきます。
暗号資産取引の手数料収入は株式その他の金融商品に比べると高額ですが、ビットコインやイーサリアムといったメジャー暗号資産を買いたいという需要など、もはや実績のある大手業者でほぼ賄われており、新規参入組はまず口座開設をしてもらうところからスタートしなければなりません。
事業計画の中で、例えば2年後に収益化するというラインを引いたのであれば、収益化までの間接コストや顧客獲得コストは自己資金を当てにせざるをえません。
そのため、売上や純資産の多寡も暗号資産交換業の審査に大きく影響します。全く説得力のない事業内容であったり、資金的裏付けが乏しい登録申請である場合、登録申請まで進めることは事実上困難です。
4 まとめ
今回は比較的問い合わせの多い暗号資産交換業について、具体的な数字も交えて説明をさせて頂きました。
暗号資産、ブロックチェーンは、将来高い確率で社会を支える技術になると考えていることもあり、この分野に注力していますが、この記事がこれから暗号資産関連の事業を立ち上げようとしている方の参考になれば幸いです。
弊所サービスの詳細や見積もり等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。