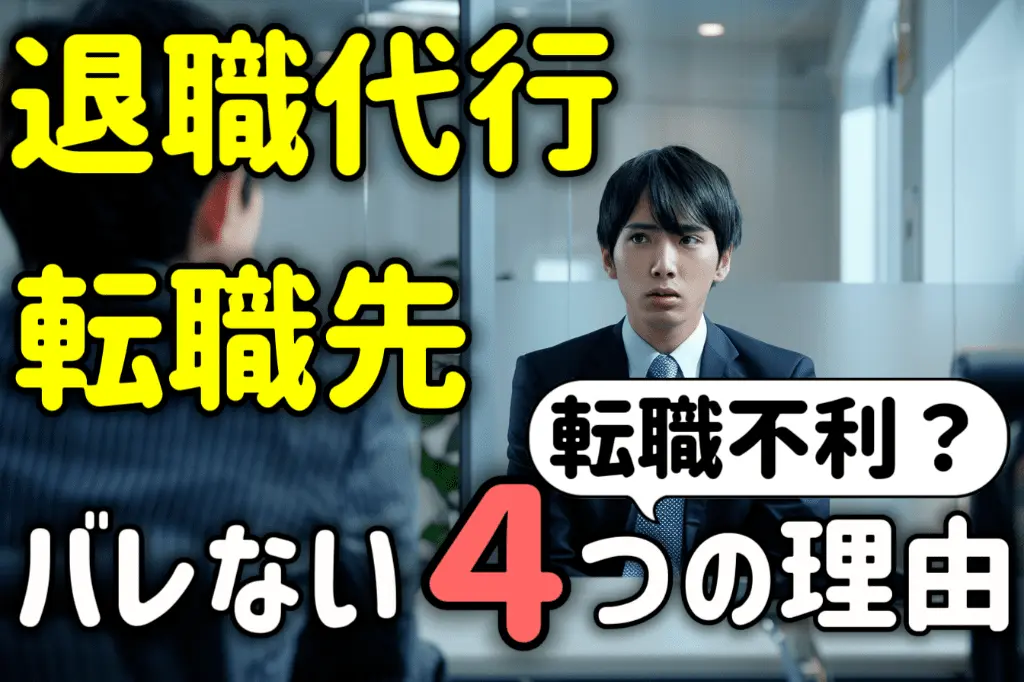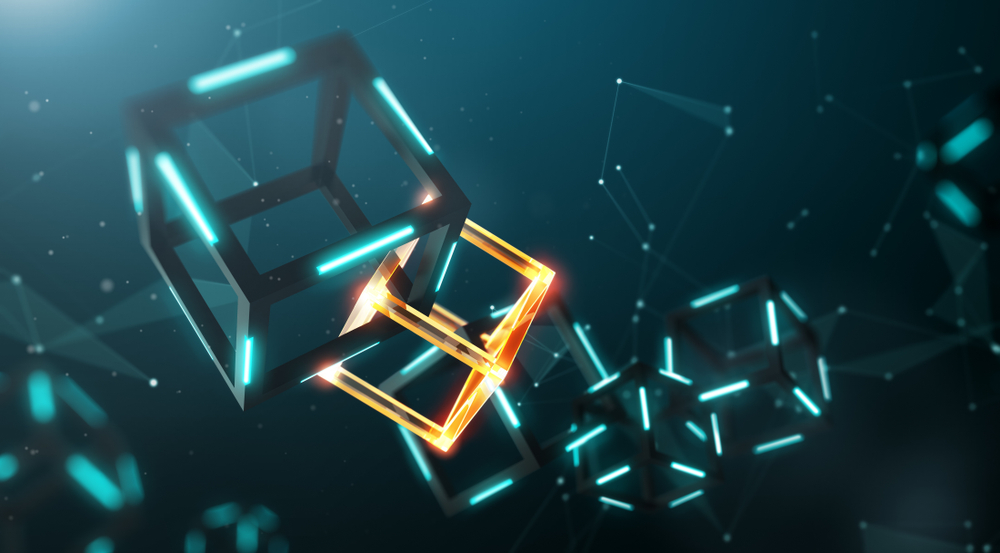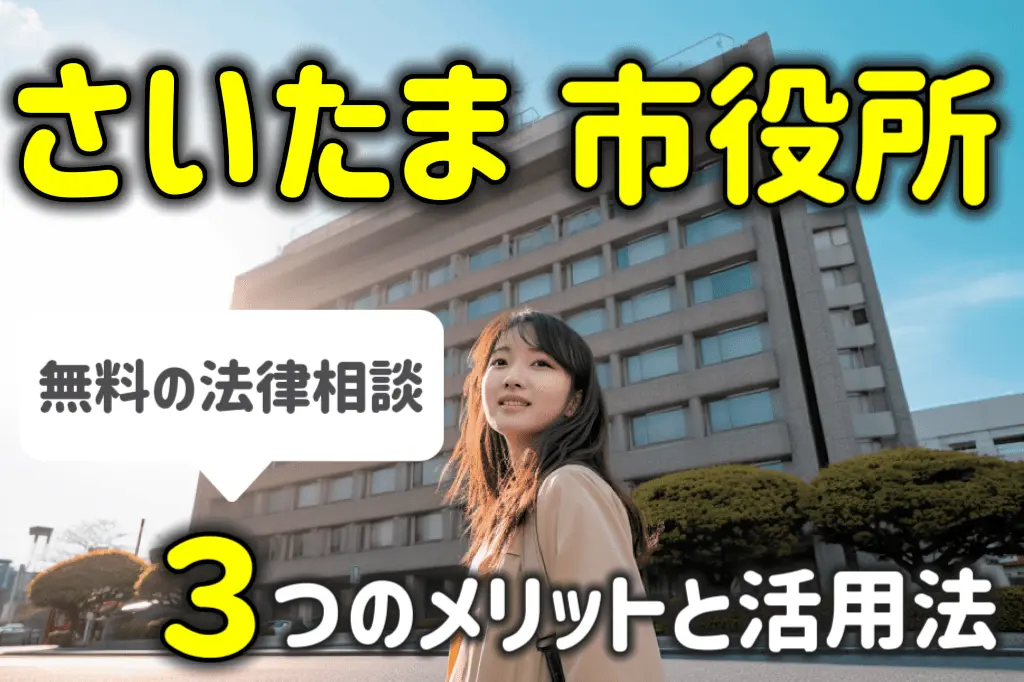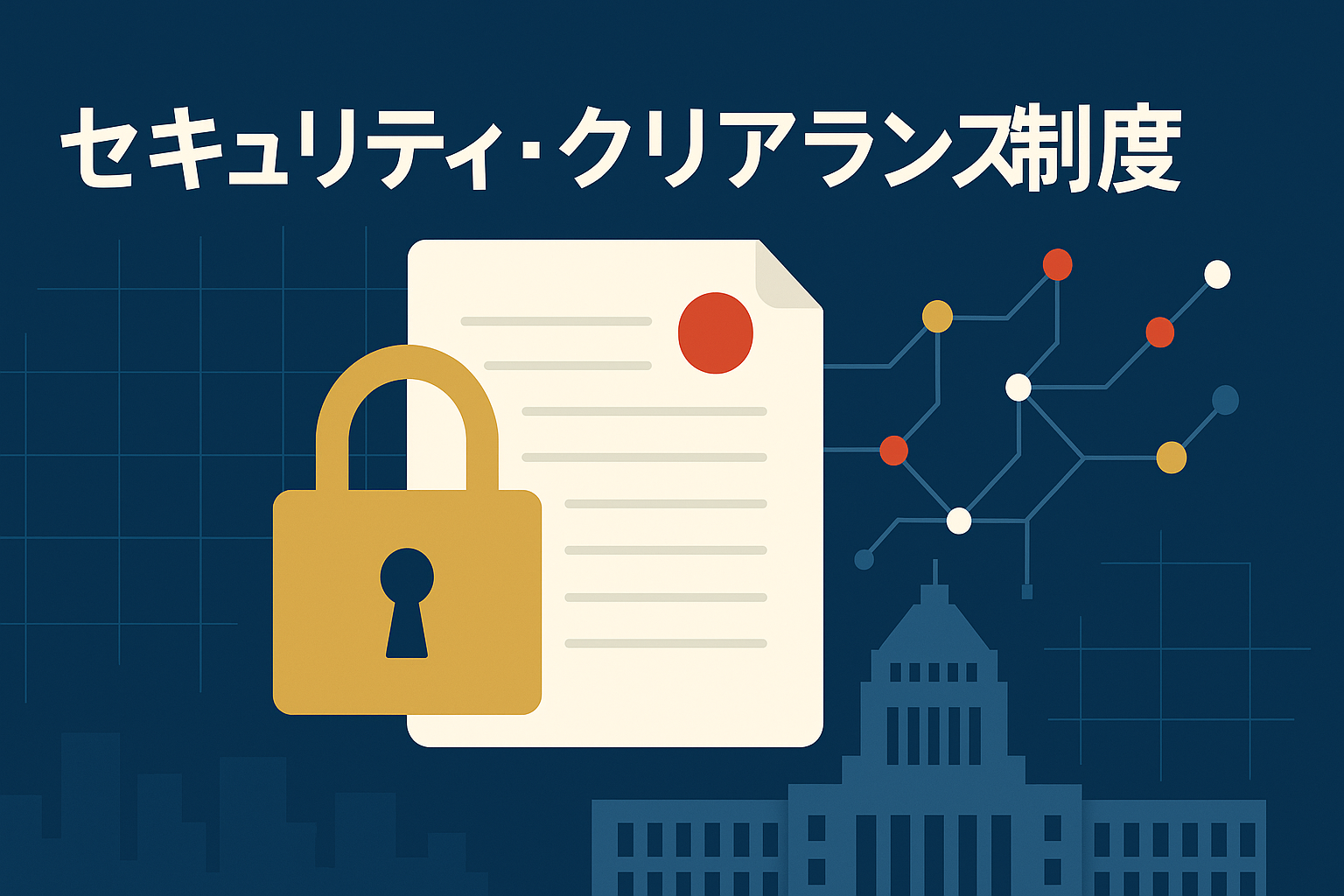サブスクサービスを始める事業者が押さえておくべき3つの法律を解説

はじめに
現在ではサブスクが生活の一部になったともいえるのではないでしょうか。
新型コロナウイルスにより、巣ごもりともいえる生活が続くなか、サブスクサービスの需要はいっそう高まりを見せています。
現状を踏まえ、サブスクを取り入れたサービスを始めようと検討している事業者もいらっしゃるのではないでしょうか。
サブスクサービスを始めるにあたっては、注意しなければならない法規制がいくつかありますが、法律の分野はよくわからないという方もいらっしゃると思います。
そこで今回は、サブスクサービスを始めようとする事業者が押さえておくべき法規制について、弁護士がわかりやすく解説します。
1 サブスクサービスとは
「サブスク(サブスクリプション)サービス」とは、商品やサービスの数とは関係なく、商品やサービスの利用期間に対して対価を支払うビジネスモデルのことをいいます。
最近では「月額定額制」を採用しているサービスが数多くありますが、月額定額制はサブスクサービスの代表例です。
音楽や動画、ファッションや飲食店などのように、さまざまな業種でサブスクサービスが展開されています。
事業者にとっては、何よりも毎月決まった収益を得られるという大きなメリットがあります。
業種を問わず取り入れることができるため、新規参入しやすく、ここ数年で需要は一気に高まっています。
2 サブスクサービスで注意すべき法律
サブスクサービスを始める事業者が注意すべき法律は、以下の3つです。
- 資金決済法
- 景品表示法
- 民法
(1)資金決済法
サブスクサービスのなかには、ユーザーが事前にポイントを購入し、そのポイントを使ってサービス利用料を支払えるようになっているものがあります。
このように、ユーザーがあらかじめポイントを購入して、そのポイントで支払いをすることができるような仕組みを採る場合、そのポイントは資金決済法上の「前払式支払手段」にあたる可能性があります。
「前払式支払手段」とは、買い物などの支払いに使う目的で、あらかじめお金を支払って購入するものをいいます。
分かりやすい例でいうと、SuicaやPasomといった交通系電子マネーや、商品券などは「前払式支払手段」にあたります。
サービス内でのみ利用できるポイントが「前払式支払手段」にあたる場合、発行したポイントの未使用残高が毎年3月末または9月末の時点で1,000万円を超えたときは、内閣総理大臣への届出が必要です。
また、この場合、未使用残高の2分の1以上に相当する金額を供託所に供託することが義務付けられます(供託義務)。
そのほかにも、資金決済法で定められた一定の事項(事業者の名称や前払式支払手段の支払可能金額等)をユーザーに提供することが必要になります(表示義務)。
この点、多くのサービスではウェブサイトなどで「資金決済法に基づく表示」というページを設ける形で表示義務を履行しています。
※「資金決済法に基づく表示」について詳しく知りたい方は、「「資金決済法に基づく表示」に記載すべき事項をわかりやすく解説!」をご覧ください。
(2)景品表示法(景表法)
サブスクサービスでは、「月額〇〇円で、△△放題」といった広告が打ち出されることが多いです。
広告を打ち出す場合には、より多くのユーザを獲得しようとその内容が大げさになってしまうことがあります。
ですが、あまりに内容が大げさになってしまうと、「景品表示法(景表法)」に違反する可能性が出てきます。
景表法は、以下のように2つの種類の表示を「不当表示」として禁止しています。
-
【優良誤認表示】
商品やサービスの品質などについて、実際の品質よりもすぐれていると表示すること
【有利誤認表示】
商品やサービスの取引条件(価格など)について、実際のものや他社のものよりもお得だと表示する
こと
たとえば、「△△放題」」と表示しておきながら、実際のところは、サービスを受けられる範囲が限られており、追加料金を支払ってはじめてすべてのサービスを受けられるような場合は、景表法上の「不当表示」にあたる可能性があります。
景表法に違反した場合、行政処分だけでなく刑事罰を受ける可能性もあるため注意が必要です。
(3)民法
サブスクサービスは、成人に加え未成年者も多く利用することが想定されます。
民法は、未成年者が契約などの法律行為を行う場合について、以下のような規制を設けています。
-
【民法5条】
1 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
このように、未成年者が契約をするには、原則として、保護者の同意を得る必要があり、同意を得ていない場合にはその契約を取り消すことができます。
言い換えれば、未成年者がサブスクサービスを利用する場合には、保護者の同意を得ていないことを理由にその契約を取消される可能性があるということです。
この場合、事業者はそれまでに未成年者から支払われた利用料等をすべて返金しなければなりません。
事業者としては、このような事態を避けるために一定の対策を講じる必要があります。
詳しくは、次の項目で解説します。
3 サブスクサービスを始める際の留意点
サブスクサービスを始める事業者は、以下の点に留意する必要があります。
(1)資金決済法による規制の回避
サービス内で発行するポイントが資金決済法上の「前払式支払手段」にあたる場合、事業者はさまざまな義務を課されることになります。
数ある規制のなかでも特に供託義務は負担が重く、事業者は最低でも500万円を供託しなければなりません。
そこで、何とかして供託義務を回避できないかと考える事業者は多いと思いますが、方法はあります。
具体的には、ポイントの有効期限を6ヶ月未満にすることで供託義務を回避することが可能です。
特にスタートアップ企業にとっては、負担が重いことから、供託義務を回避するスキームも併せて検討することが必要になってくるでしょう。
※供託義務の回避スキームについて詳しく知りたい方は、「資金決済法にいう「6ヶ月」とは?前払式支払手段の有効期限を解説!」をご覧ください。
(2)利用規約の策定
未成年者がサブスクサービスを利用するには、保護者の同意を得る必要があります。
とはいえ、実際に保護者から同意を得ているかどうかを確認することは困難です。
そこで、利用規約を作り、そのなかで保護者の同意が必要である旨を明示することが必要になってきます。
もっとも、利用規約に定めるだけでは十分でなく、利用規約の同意画面などにもその旨を明示しておくことが必要です。
このほかにも、サービスの内容や月額料金、解約に関する事項などを利用規約の中で、きちんと明示しておく必要があります。
4 まとめ
今後もサブスクサービスの需要は増えていくものと考えられます。
サービス展開を検討している事業者は、法規制をしっかりと確認しながら進めていくことが大切です。
弊所は、ビジネスモデルのブラッシュアップから法規制に関するリーガルチェック、利用規約等の作成等にも対応しております。
弊所サービスの詳細や見積もり等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。