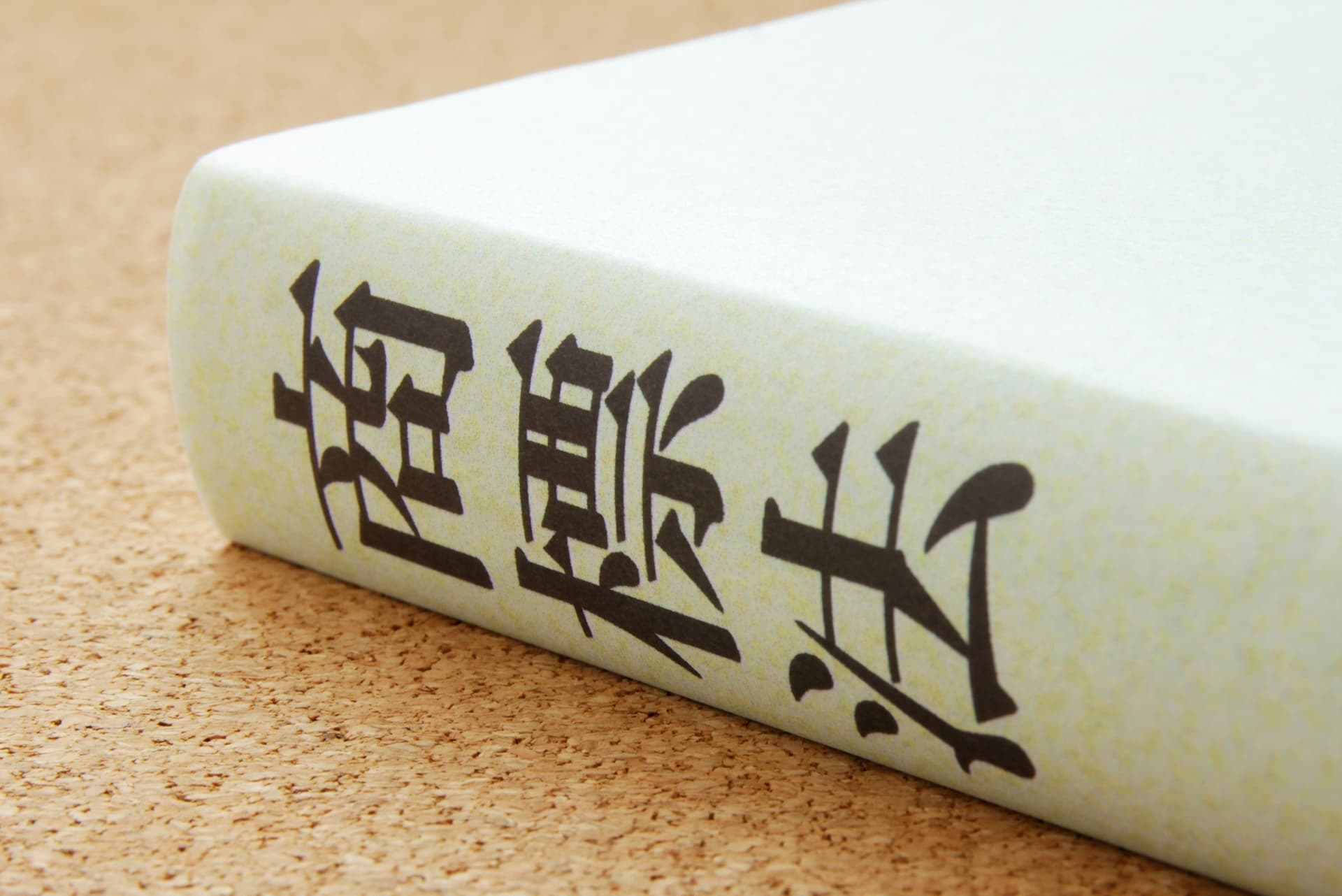NFTを利用したサービスとの関係で押さえておくべき4つの法律を解説

はじめに
NFT関連のサービスは多種多様であり、今後も分野を問わず新たなサービスが展開されていくことが予想されます。
NFTを利用したサービスを始めるにあたっては、利用するNFTとの関係で検討しなければならない法規制があります。
検討した結果、利用するNFTが規制対象となる場合には、届出や登録などの手続を踏むことが必要になります。
そこで今回は、NFTを利用するサービスについて押さえておくべき法規制を弁護士がわかりやすく解説します。
1 NFT関連サービスとの関係で注意すべき4つの法律
NFT関連サービスを始めるにあたり、特に注意すべき法律は以下の4つです。
- 資金決済法
- 金融商品取引法
- 刑法
- 景品表示法(景表法)
2 資金決済法
サービスで利用するNFTに、決済手段などの機能が備わっている場合、「資金決済法」を検討する必要があります。
この点、NFTは非代替性トークンとも呼ばれており、その性質上、それぞれが固有の値を有するものです。
そのため、一般的に決済手段の機能は備わっていないことが多いと考えられます。
ですが、すべてのケースにおいてNFTの決済手段性が否定されるわけではないため、NFTの性質や仕組み、NFTを利用するサービスの内容などを考慮したうえで、決済手段性の有無を検討する必要があります。
たとえば、NFTが他の商品やサービスとの交換、価値の移動などに使われるような場合は、決済手段性が認められる可能性もあるため、注意が必要です。
決済手段性が認められる場合、次に検討しなければならないのが、以下にNFTが該当するかどうかです。
- 暗号資産
- 前払式支払手段
- 為替取引
仮に、これらに該当すると、
- 暗号資産に該当 → 暗号資産交換業の登録
- 前払式支払手段 → 前払式支払手段発行者としての届出・登録
- 為替取引 → 資金移動業の登録
といった手続きが必要になる可能性があります。
※「暗号資産交換業取得の概要」について詳しく知りたい方は、「【詳細解説】日本で暗号資産交換業者登録するために必要となる収益・資金は?」をご覧ください。
※NFTの暗号資産該当性については、「NFTは暗号資産にあたる?暗号資産交換業の該当性を弁護士が解説!」をご覧ください。
3 金融商品取引法
NFTにおいて、それを保有することにより、一定の経済的利益を得られるような仕組みが採られている場合、「金融商品取引法」を検討する必要があります。
このような仕組みをもつNFTは、金商法上の「有価証券」にあたる可能性があり、仮に有価証券にあたる場合、事業者は内閣総理大臣の登録を受ける必要があり、登録後もさまざまな規制を課されることになります。
たとえば、NFTを保有することにより発行事業者の収益の一部が分配されるような仕組みである場合、いわゆる「集団投資スキーム持分」にあたり、金商法の規制対象となる可能性があります。
※「集団投資スキーム持分」について詳しく知りたい方は、「セキュリティトークンは違法?ファンド規制の3つのポイントを解説!」をご覧ください。
4 刑法
NFTは、一般的に財産的価値を有すると判断される可能性が高いものです。
そのため、サービスの内容などによっては、刑法上の「賭博罪」にあたらないよう注意する必要があります。
刑法上の賭博罪にあたるといえるためには、以下の2つの要件を満たしていることが必要です。
- 勝敗が偶然により決せられること
- 財産上の利益の得喪を争うこと
典型例として挙げられるのが「ガチャ」です。
ご存知の方も多いと思いますが、ここでいう「ガチャ」とは、ゲーム内で発行された通貨などを使って、ランダムにアイテムを得られる仕組みになっています。
そうすると、ガチャは、獲得するアイテムがプログラムでランダムに決定されるという意味で、上記要件1を満たしているといえます。
加えて、獲得することが可能なアイテムに財産的価値が認められれば、上記要件2も満たし、賭博罪が成立する可能性があると考えられます
5 景品表示法(景表法)
本体となるサービスに付随して、NFTを配布したりするような場合には「景品表示法(景表法)」を検討する必要があります。
「景品表示法(景表法)」とは、事業者が過大な景品類を提供することによって、消費者がそれに惑わされて質の良くないものなどを買わされてしまうことがないよう、景品類の最高額や総額を規制する法律です。
ここでいう「景品類」にあたるといえるためには、以下の3つの要件をすべて満たしていることが必要です。
- 顧客を誘引するための手段であること
- 事業者が提供する商品やサービスに付随して提供すること
- 経済上の利益が認められること
この点、NFTについては、取引がブロックチェーン上で自由に行われること、非代替性を有することなどから、その価格を算出するにあたっては、その方法などを慎重に検討する必要があります。
もっとも、本体となるサービスに付随して配布するのではなく、サービスの利用に伴う報酬として利用者に配布するのであれば、「事業者が提供する商品やサービスに付随して提供(上記要件2)」しているとはいえないため、景品類にあたらず、景表法の規制対象とならない可能性があります。
※景品類の金額について詳しく知りたい方は、「景品表示法が規制する景品の金額は?3つの類型ごとに上限などを解説」をご覧ください。
6 まとめ
エンタメ業界を中心に広がりを見せているNFTですが、NFTを利用したサービスを始める際には、さまざまな法規制を確認しておく必要があります。
そのためには、発行するNFTの性質・機能やサービス内容などを十分に理解することが重要になってきます。
法規制によっては、罰則も設けられているため、注意するようにしましょう。
弊所は、ビジネスモデルのブラッシュアップから法規制に関するリーガルチェック、利用規約等の作成等にも対応しております。
弊所サービスの詳細や見積もり等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。