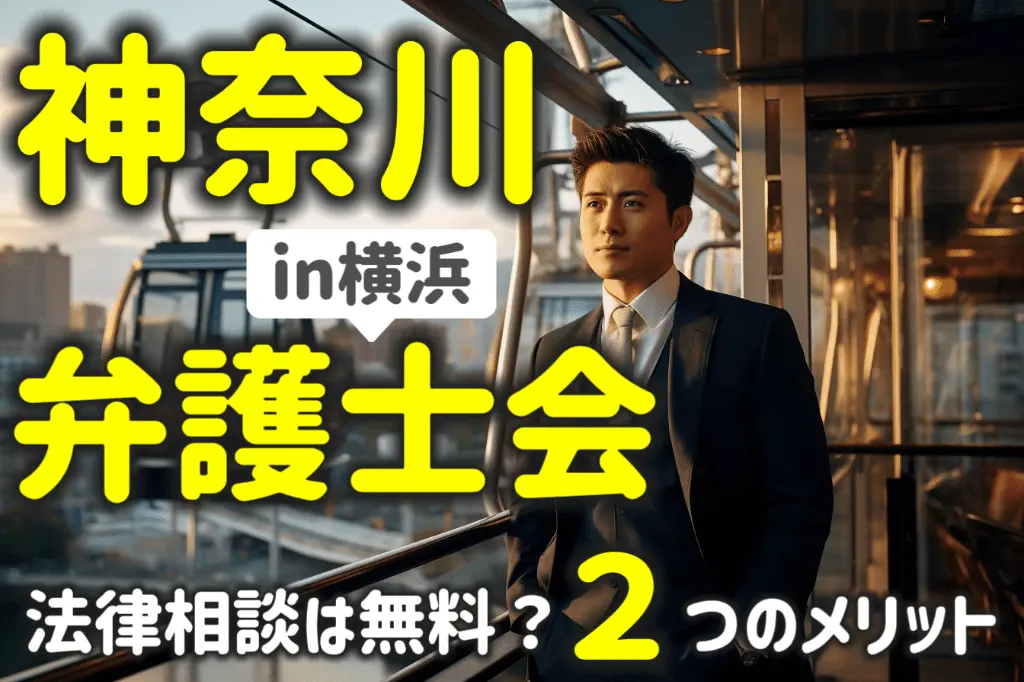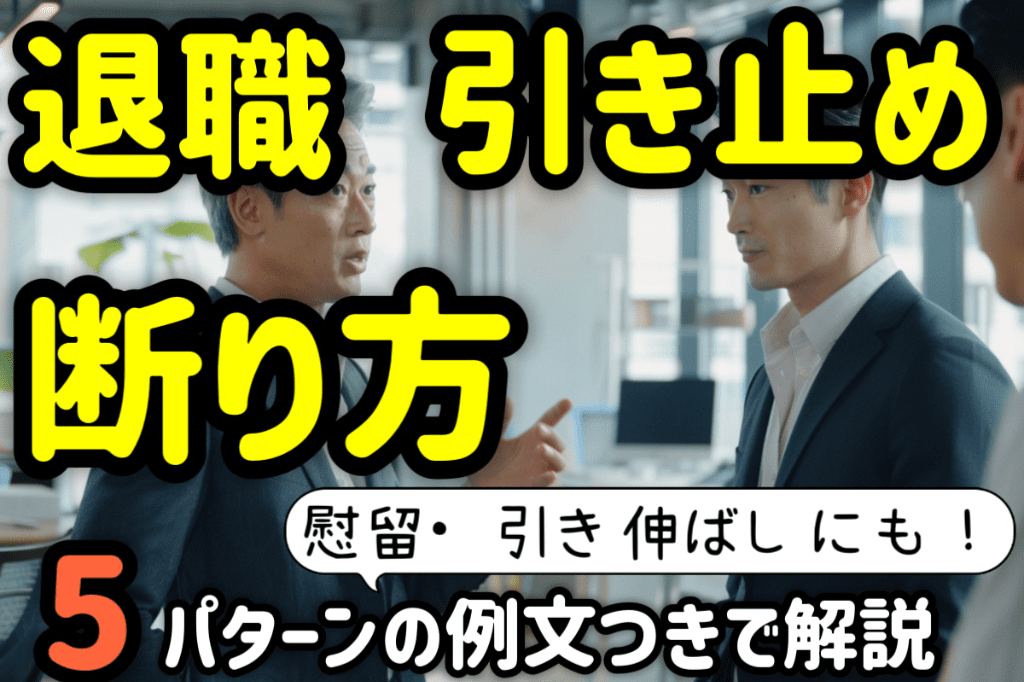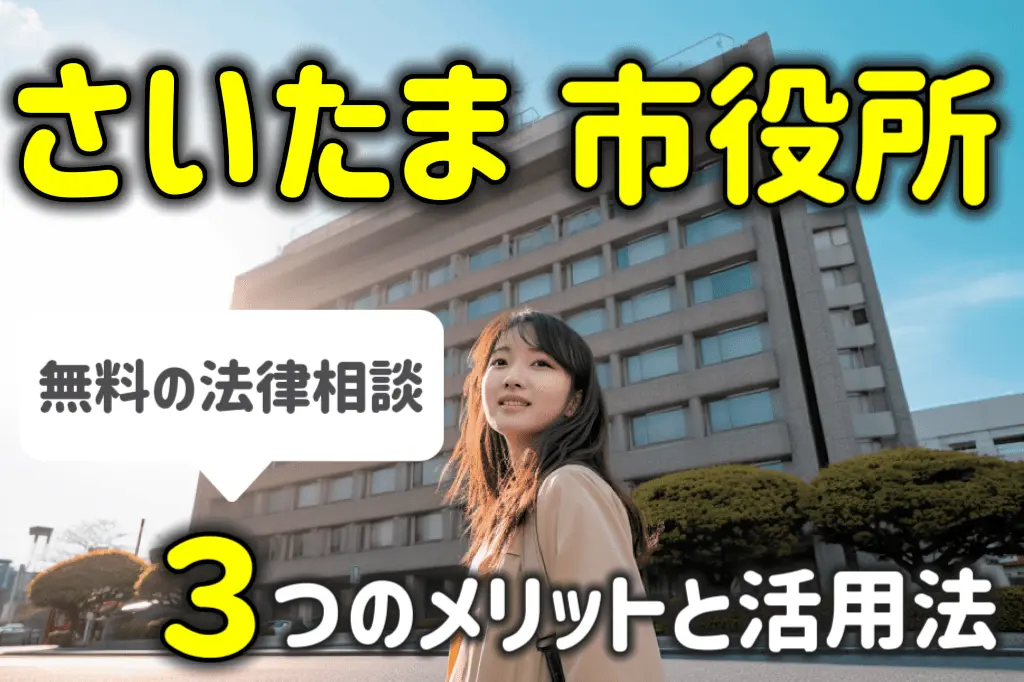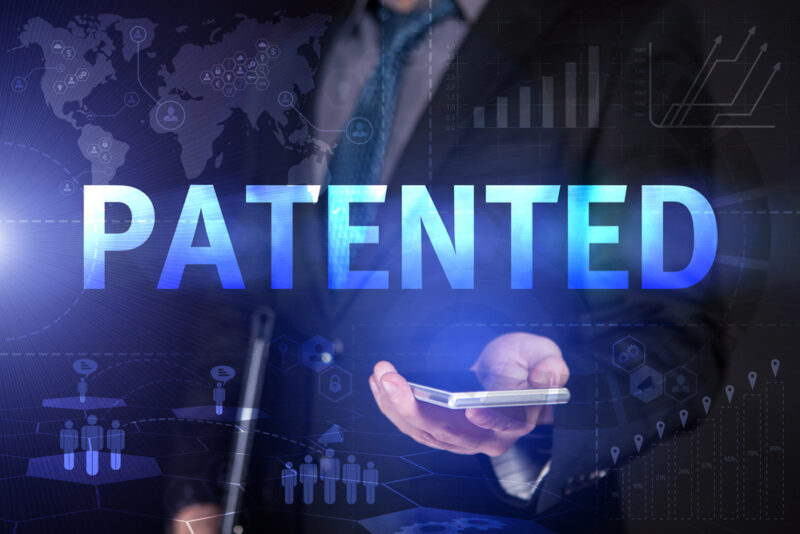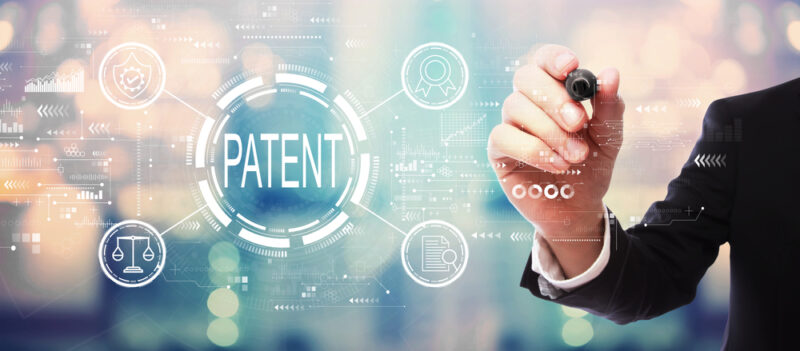特許のライセンス契約の7つのポイントについて弁護士が詳しく解説!

はじめに
技術を売りにしている事業者にとって、ビジネスを成長させるには、特許をいかに有効に活用するかについて戦略をたてることは不可欠です。
「特許を取得したものの、自社にはその特許を活かした製品を開発する工場・人材が足りなくて有効活用できていない……」なんてことをお悩みの事業者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。この場合、他社に特許の使用を許し、使用料を得るという選択肢があります。
また、「他社の特許を使わなければどうしても作れないものがある……勝手に使うと特許権侵害になるはずだし、どうすればいいんだろう……」といったことにお悩みの事業者もいるでしょう。
これらの場合に締結するべきは、「ライセンス契約」です。
もっとも、ライセンス契約を締結するにあたって、契約書に何を定めるべきか、何に注意しなければいけないのか、よくわからないですよね。
そこで今回は、特許に関する「ライセンス契約」に定めるべき事項について弁護士がわかりやすく解説していきます。
この記事を執筆したのは

- 弁護士・中小企業診断士 勝部 泰之
- 注力:知的財産権・著作権/ライセンス、ブロックチェーン、データ・AI法務
GWU Law LL.M.(知的財産法)
事業の成長とリスクを両立する実務寄りの助言に注力しています。 - 詳しいプロフィールはこちら
1 ライセンス契約とは
「ライセンス契約」とは、知的財産(特許・商標・著作権・ノウハウなど)を持つ者(ライセンサー)と、その知的財産を使いたい者(ライセンシー)とが、その使用料・実施料(ロイヤリティ)や使用の条件について取り決めを行う契約のことをいいます。
このように、単にライセンス契約といっても、特許に限らずさまざまな権利などが対象になります。そして、ライセンス契約というものは、その対象となる権利ごとに定めるべき事項や、注意点が変わってきます。
そのため、ライセンス契約の解説を読む際には、何に対するライセンス契約なのか?を確認することをおすすめします。
今回この記事では、特許のライセンス契約について解説していきます。
特許のライセンス契約は、ライセンサー、ライセンシーにとって、次のようにお互いがwin-winの関係になれる可能性がある契約となっています。
特許を取得しても、それを自社で使っていなければ、その特許発明は何の利益も生み出さず、他社への牽制にしかなりません。これでは宝の持ち腐れです。
他社への使用を許し、ライセンサーになることで、ロイヤリティ収入を確保し、これまでその特許発明に費やした研究開発費の回収を図ることができます。
他方、ライセンシーはライセンサーから特許発明の使用を許されることで、特許が取得された物を製造したり、自社製品に組み込んだり、特許が取得された方法を利用したりといったことが可能になります。
なお、ライセンス契約などを締結せずに、他人の特許発明を勝手に使うことは特許権侵害となる可能性があります。
他人の特許権を侵害しないためには、ライセンス契約を締結する他に、他人の特許発明を回避して使わない=他の技術で代用するという選択肢もありますが、使代替技術を生み出すにも時間とお金がかかるうえにうまくいくかわかりません。また使いたい技術の周辺まで特許を取得されていると、回避すること自体が難しい場合もあるでしょう。
ライセンス契約は、ライセンシーにとって、特許権侵害とならないだけでなく、研究開発費や時間を節約しつつ自社にない技術を使用することができるようになるという点で、非常に有効な手段となるのです。
では、このライセンス契約には、どのような事項を定めるべきでしょうか。
※著作権のライセンス契約について詳しく知りたい方は「著作権のライセンス契約とは?注意したいポイント3つを中心に解説!」をご覧ください。
2 特許のライセンス契約で定めるべき事項
特許のライセンス契約を結ぶ場合、その契約書には、以下の事項を定めるべきです。
- ライセンスを設定する対象
- ライセンスの種類
- ライセンスの範囲
- ロイヤリティ
- 特許権侵害への対応方法
- 改良発明・関連発明の取扱
- 不争条項
②「ライセンスの種類」と⑤「特許権侵害への対応方法」については、次項以降で詳しく解説します。
(1)ライセンスを設定する対象(事項①)
まずは、「何」に対してライセンスを設定するのかを明確にする必要があります。
対象を明確にしないと、使いたいと思っていた特許発明が含まれていない、利用を認めるつもりがなかった特許発明が含まれているといったトラブルが起きやすくなってしまいます。
対象となる特許発明を明確に特定するには、ライセンス契約書に「特許番号」と「発明の名称」を記載するという方法があります。
「特許番号(登録番号)」とは、特許を取得したときに、その特許発明に対して国が付ける番号です。特許の詳細については広く公開されていて、誰でもJ-platpatなどのWebサイトなどで検索でき、無料で特許番号を含め特許の詳細を見ることができます。
そのため、「特許番号」と「発明の名称」で特許発明を特定すれば、何がライセンス契約の対象となっているか、誰の目から見ても明確にすることが可能です。
また、1つの特許発明の一部分にだけライセンスを設定することもできます。
その場合には、特許のどの部分に対して実施を許諾するのかを契約書で明確に示さなければいけません。ライセンサーとライセンシーの間で、実施を許諾された範囲を正しく認識できるような記載にしておかないと、思わぬところで特許を侵害してしまう可能性もあるため注意が必要です。
(2)ライセンスの範囲(事項③)
「ライセンスの範囲」とは、期間・場所・内容など、どのような範囲でライセンシーに特許発明の利用を認めるかを意味しています。範囲を全く制限しないこともできますが、範囲が制限された場合、ライセンシーがその範囲を守らずに特許発明を利用していると、契約違反として損害賠償を請求される可能性があります。
例えば、2年間、東京に限り特許発明の利用が認められたにもかかわらず、ライセンシーが2年間を過ぎても利用し続けたり、大阪で利用したりすると、契約違反となります。
また、単に「特許発明を利用する」といっても、利用方法はさまざまです。ライセンス契約において、利用方法などの内容面でも制限をかけることができます。
例えば、特許発明の利用方法の一部を以下に挙げてみましょう。
- 特許発明となっている物を生産、使用、譲渡等する
- 特許発明となっている方法を使用する
- 物を生産する方法の特許発明を用いて生産した物を使用、譲渡等する
内容の制限としては、特許発明となっている物を生産することは認めるが、販売することは認めない。逆に、販売することは認めるが、生産することは認めないといったことができるわけです。
(3)ロイヤリティ(事項④)
「ロイヤリティ(ロイヤルティともいう)」とは、ライセンシーがライセンサーに対してライセンスの対価として支払う金銭をいい、「実施料」と呼ばれることもあります。
一般的に、ライセンス契約を結ぶときは、ロイヤリティを支払います。ロイヤリティについては、法律上に特に規定はないので、金額やその計算方法、支払方法などは、当事者間の合意で定められます。そのため、ロイヤリティの決め方についてはさまざまな方法があります。
代表的なロイヤリティの種類としては、「固定ロイヤリティ」と「ランニング・ロイヤリティ」の2つがあります。
「固定ロイヤリティ」とは、契約時にロイヤリティとして一定の金額を定めて支払う方法です。メリットとしては、契約時に金額と支払方法が確定できるので、わかりやすいという点が挙げられます。デメリットとしては、そのライセンス技術を導入することによってライセンシーの事業が成功するかどうかの予測は契約時点では難しく、双方がリスクを背負うという点です。ライセンシーは事業が想定どおりにいかなかった場合に負担が大きくなり、ライセンサーは事業が想定以上に成功した場合でも、追加してロイヤリティを受け取ることができません。
一方、「ランニング・ロイヤリティ」とは、ライセンスの対象となる技術の使用の程度に応じてロイヤリティの金額を定める方法です。ランニング・ロイヤリティ単体で用いられることもありますが、他にも、契約時に頭金として一定の金額を支払ったり、使用量が少なくても最低限支払う保証額を定める「ミニマム・ロイヤリティ」などと組み合わせたりする方法もあります。
ランニング・ロイヤリティの計算方法としては、実際の売上や生産量などが基準となります。この場合には、売上や生産量についての具体的内容(返品、交換品などをどう扱うかなど)についてや、使用量などを申告してからロイヤリティが支払われるまでの手続きについてなど細かく定めておく必要があります。
他にも、例えば医薬品の開発などで、許認可が得られたときにロイヤリティが発生するような条件付きロイヤリティや、研究開発の各フェーズごとにロイヤリティが支払われるマイルストーン・ロイヤリティなど、さまざまな種類のロイヤリティがあります。
(4)改良発明・関連発明の取扱(事項⑥)
ライセンスを受けた特許発明を利用する際に、ライセンシーが特許発明をより改良することや、関連した新たな発明をすることがあります。
通常、この発明は、ライセンシーが思いついたものであり、ライセンシーが特許を取得できるものです。
もっとも、ライセンサーとしては、その元となる発明の特許を持つわけですから、改良発明や関連発明に関する権利も自社のものにしたいと考えることでしょう。
ここでライセンサーが実務上気を付けなければならないのは独占禁止法です。独占禁止法では、取引相手の事業活動を制約したり、他の事業者の事業活動を排斥したりするような取引は、「不公正な取引」として禁止されています。
例えば、ライセンサーがライセンシーに対して、改良発明・関連発明に関する権利をライセンサー側に譲渡することを義務とした場合、この不公正な取引に当たる可能性があります。
なぜなら、ライセンサーの地位を強化し、ライセンシーにより良く改良しようという気をなくさせ、市場が停滞してしまうからです。
もっとも、この改良発明・関連発明の譲渡に対して、相応の対価をライセンサーがライセンシーに対して支払えば、基本的には不公正な取引に当たらなくなるでしょう。
このように、ライセンス契約では、改良発明・関連発明に関する取り扱いについても明確に定めておく必要があり、その内容は、不公正な取引とならないよう十分に気を付ける必要があります。
(5)不争義務(事項⑦)
「不争義務」とは、ライセンシーが、対象となる特許の有効性については争わない義務のことをいいます。
具体的には、ライセンシーに対して、ライセンスの対象となっている特許発明について「この特許発明は無効だ!」と無効審判を申し立てる行為などを禁止することをいいます。もし、ライセンサーが特許を取得した特許発明が、その出願の時点でネットに公開されている技術など、特許権という権利を与えて独占させるべきものでないことが後から分かった場合、一度特許権を取得することが認められた特許発明でも無効となることがあります。無効となれば、その発明は誰でも自由に利用できるようになり、ライセンシーはロイヤリティの支払を免れることができます。
ライセンサーとしては、せっかくライセンス契約を締結できたのに、特許権そのものを失いかねない事態はできれば避けたいものです。
もちろん、この不争義務に関する定めがあるからといって、ライセンシーが法律上認められている無効審判の申し立てができなくなるわけではありませんが、この定めがあれば、積極的に特許権が無効となる理由がないかライセンシーが探しにいくことを牽制できることでしょう。
他方、ライセンシーにとって、ロイヤリティなど払わずに発明を利用できることがベストです。もし、特許発明に無効となる理由があれば、積極的に無効にしていくつもりであれば、この条項は削除すべきだといえます。
このようにライセンス契約書に定めるべき事項は複数あります。加えて、ライセンス契約の締結にあたっては、必ずライセンスの種類を決定しなければいけません。
次の項目では、このライセンスの種類について、解説していきます。
3 ライセンスの種類(事項②)
(1)ライセンスの種類
特許発明を使用することができる権利のことを「実施権」といいます。
ライセンス契約における「実施権」は以下の3種類に分けることができます。
- 専用実施権
- 通常実施権
- 独占的通常実施権
ライセンサー、ライセンシーはどの種類の実施権を選択するか考えなければいけません。それぞれの実施権の特徴を確認していきましょう。
ライセンス契約を結ぶことによって、ライセンサーが許諾した条件のライセンス(実施権)が成立します。実施権には以下の3つがあります。
①専用実施権
「専用実施権」とは、ライセンシーが、独占的かつ排他的にその特許発明を使用することができる権利のことをいいます。この専用実施権が設定された範囲内では、ライセンサー自身もその特許発明を使用することができなくなるという強力なものです。
もっとも、この専用実施権は強力である一方で、ライセンス契約の締結だけでなく、特許庁に備えられている「登録原簿」に登録しなければいけないことになっています。
②通常実施権
「通常実施権」とは、ライセンス契約で設定した範囲内でライセンシーが特許を実施することができる権利です。①の専用実施権のような独占的・排他的なものではありません。
そのため、ライセンス契約の締結以外に特別な手続は不要で、通常実施権を設定しても、ライセンサー自身もその特許発明を使用することができます。
また、ライセンサーは複数の者にライセンスを許諾することも可能になっています
③独占的通常実施権
「独占的通常実施権」とは、通常実施権の一種で、ライセンサーが他の者に対して重ねて特許発明の使用を許諾しないという特約を付けたものです。
この独占的通常実施権では、②の通常実施権のようにライセンサーが複数の者にライセンスを許諾することができなくなります。
もっとも、あくまでも通常実施権の一種であるため、ライセンス契約の締結以外に登録原簿への登録は不要となっています。
また、独占的通常実施権のうち、ライセンサー自身が使用できない旨の特約があるものを、「完全独占的通常実施権」といいます。この完全独占的通常実施権が設定されない限りは、ライセンシー自身も特許発明を使用することができます。
(2)どれを選ぶべきか
①判断のポイント
それでは、上記の3つの実施権のうち、どれを選べばよいのでしょうか。
ポイントは、
- ライセンサーがその特許発明を使用させることでどれだけの利益を得られるか
- ライセンシーがその特許発明の使用を独占したいかどうか
というところにあります。
②ライセンサーが考えるべきこと
ライセンサーが考えるべきことは、誰にいくらでライセンスするかです。
例えば、その分野で事業を行っていれば、誰もが使わざるを得ない特許発明があったとしましょう。
この場合、複数の事業者がその特許発明を使用したがることが想定されます。
ということであれば、
- 複数の事業者それぞれに個別に通常実施権を設定した場合よりも、独占を条件にあるライセンシーが高いロイヤリティを支払ってくれる
- ライセンサーの特許を発明を使用させる対価として、ライセンシーがもっている特許発明の使用を逆に認めてもらう(いわゆるクロスライセンス)
などの事情がなければ、複数の事業者に対してライセンスを設定したほうがお得です。
③ライセンシーが考えるべきこと
ライセンシーが考えるべきは、その特許発明を独占するだけの価値があるかどうかです。
例えば、ライセンスの対象とする特許発明について、他社もそれを回避した特許発明を持っている場合はどうでしょう。
この場合、独占した特許発明を使用して製品を生産しても、他社もそれを回避して製品を生産できてしまうため、差がつかず、独占する価値はないと考えられます。
他方、特許発明に改良を重ねて、他社よりもいい物を生み出す技術力があるのであれば、特許発明を独占して、そもそも技術を改良する競争相手を減らすという選択肢もあります。この場合には、独占する価値もでてくるでしょう。
最終的に独占すべきか否かは、ロイヤリティとして支払う金額と、その特許発明を使用することで得られるリターンとを天秤にかけて判断することになるといえるでしょう。
このように、ライセンスの種類を選ぶ際には、
- 利用したい特許発明がどのようなものか
- その特許発明が属している技術分野の状況
- 自社の状況
- 競合他社の状況
など、さまざまな要素を検討しなければいけません。
そのため、ライセンスの種類をどうするかは、ケースバイケースだといえます。
もっとも、ライセンシーはもう1点、きちんと考えておかなければいけない要素があります。それは、使用可能となった特許発明を侵害された場合に、「何を行うことができるか?」です。実は、ライセンスの種類によって、ライセンシーが取り得る対応が異なっており、そのことを踏まえたライセンス契約にしなければ、特許権侵害に対して何もできないということになりかねません。
そこで、次の項目では、特許権侵害への対応方法について確認していきましょう。
4 特許権侵害への対応方法(事項⑤)
「特許侵害」とは、正当な権限を持たない者が、事業として特許発明を使用することをいいます。「正当な権限」には、当然ライセンス契約も含まれています。
ここでは、ライセンス契約の対象となっている特許発明をライセンサーでも、ライセンシーでもない者が勝手に使用したときのことを考えてみましょう。
ライセンサー、ライセンシーはどのような対応を行うことができるのでしょうか。
(1)ライセンサー(特許権者)が特許権侵害に対してできること
特許権が侵害されたときには、特許権者であるライセンサーは、ライセンシーに与えたライセンスの種類にかかわらず、、
- 直ちに侵害行為をやめるように相手方に請求すること(=差止請求)
- その侵害により被った損害額を請求すること(=損害賠償請求)
ができます。
(2)ラインセンシーが特許権侵害に対してできること
一方、特許権侵害に対してライセンシーが取ることのできる対応方法は、ライセンスの種類によって違います。
①専用実施権のとき
ライセンス契約で専用実施権が設定されているときは、ライセンシーにはライセンサーと同じように差止請求権と損害賠償請求権の両方があり、それらを行使することができます。
②通常実施権のとき
ライセンス契約で通常実施権が設定されている場合には、ライセンシーは、差止請求権も損害賠償請求もすることができません。
なぜなら、通常実施権を設定されたライセンシーは、特許発明を使用することを許されているだけであり、独占性や排他性が認められるわけではありません。
ライセンサー、ライセンシー以外の者が勝手に特許発明を使用したとしても、ライセンシーはその特許発明を使用することができなくなったり、邪魔されたりするわけではないため、差止請求も、損害賠償請求もできないことになります。
③独占的通常実施権(完全独占的通常実施権を含む)とき
通常実施権とは異なり、独占的通常実施権が設定されている場合には、ライセンシーは、損害賠償請求をすることができます。
なぜなら、ライセンサー、ライセンシー以外の者が勝手に特許発明を使用すると、特許発明を使用することに対して事実上独占的な地位を与えられたはずのラインセンシーの地位を侵害しているからです。
もっとも、損害賠償請求は認められているとしても、差止請求はできないことになっています。
なぜなら、ライセンシーの独占的地位は契約に基づいて発生したものにすぎないこと、また、差止請求を認めてしまうと差止請求と差がなくなってしまうからです。
ここまで解説してきた実施権の種類とその性質の違いをまとめると以下の表のようになります。
表のとおり、特許権が侵害されたときにライセンシーが取れる対応方法には制約があります。
(3)ライセンス契約で定めるべき内容
このように、第三者の特許侵害に対してできることは、ライセンサーとライセンシーに差があります。ライセンス契約において特許侵害時の対応方法を定めるときには、この点に留意した内容にしなければいけません。
例えば、特許侵害時の対応方法の定めがある場合でも、単に「侵害行為に対して、ライセンサーとライセンシーは協議して対応する」となっているケースを見かけます。ライセンシーが持つ実施権が専用実施権である場合は、このような内容でも問題はないかもしれません。
なぜなら、これまで確認してきたとおり、特許権侵害に対してライセンサーが対応しなくとも、ライセンシー自身が差止請求や損害賠償請求が可能だからです。
もっとも、ライセンシーの持つ実施権が通常実施権の場合には、自らこの侵害行為対応することはできません。
そのため、この場合には、ライセンサーが侵害行為を排除する義務を負うようにライセンス契約には定めるべきです。
ただし、必ず侵害行為を排除する行為をしなければいけないとすると、ライセンシーが難色を示して契約できないことがあります。
そのため、折衷案としては、以下のとおり定めることが考えられます。
-
- 第〇条(第三者による侵害への対応)
- ライセンサーは、第〇条に定める特許発明について第三者による侵害または侵害のおそれを確認した場合、自己の判断に基づき、その侵害の排除に関し合理的な措置を講ずるものとする。
このようにライセンサーにも選択肢を与えることで、多少なりとも契約締結しやすくなるでしょう。
このように、特許侵害に対して取りうる方法に差があることを理解したうえで、どの実施権を選ぶのかを定める必要があります。
※特許権の侵害と、その対応方法について詳しく知りたい方は、「特許権侵害をしていた・された場合の対応を事例とともに弁護士が解説」をご覧ください。
5 小括

ライセンス契約を結ぶことで、特許などの知的財産を有効利用することができます。
もっとも、ライセンス契約というものは、特許発明の内容や範囲、ライセンサー・ライセンシー双方の事業内容や今後の事業計画などをもとに、内容を調整しなければいけません。
そのため、実際に契約書を作成する場合には、専門家に相談することを強くお勧めします。
6 まとめ
これまでの解説をまとめると、以下の通りです。
- ライセンス契約とは、知的財産(特許・商標・著作権・ノウハウなど)を持つ者(ライセンサー)と、その知的財産を使いたい者(ライセンシー)とが、その使用料・実施料(ロイヤリティ)や使用の条件について取り決めを行う契約のことをいう
- ライセンス契約で定めるべき事項は、①ライセンスを設定する対象、②ライセンスの種類、③ライセンスの範囲、④ロイヤリティ、⑤特許侵害への対応方法、⑥改良発明・関連発明の取り扱い、⑦不争条項、である
- ライセンスの種類には、①専用実施権、②通常実施権、③独占的通常実施権、がある
- 第三者が特許を侵害したとき、ライセンサーは差止請求や損害賠償請求をすることができる。
- ライセンス契約で専用実施権が設定されたとき、ライセンシーは特許権者同様に差止請求や損害賠償請求をすることができる
- ライセンス契約で通常実施権が設定されたとき、ライセンシーは差止請求も損害賠償請求もできない
- ライセンス契約で独占的通常実施権が設定されたとき、ライセンシーは損害賠償請求はできるが、差止請求はできない
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。