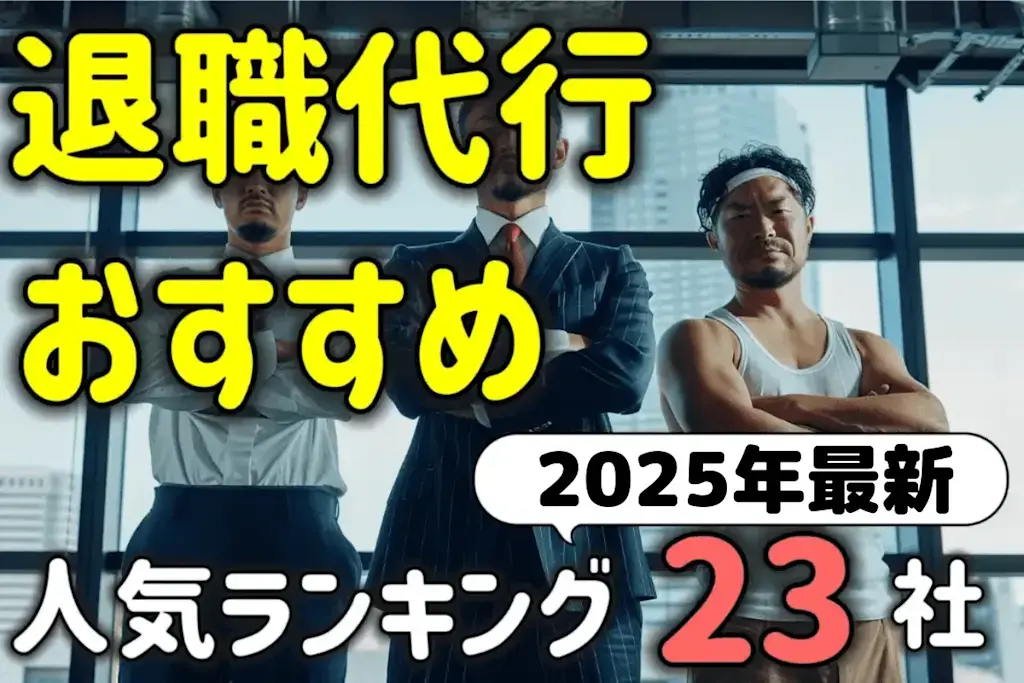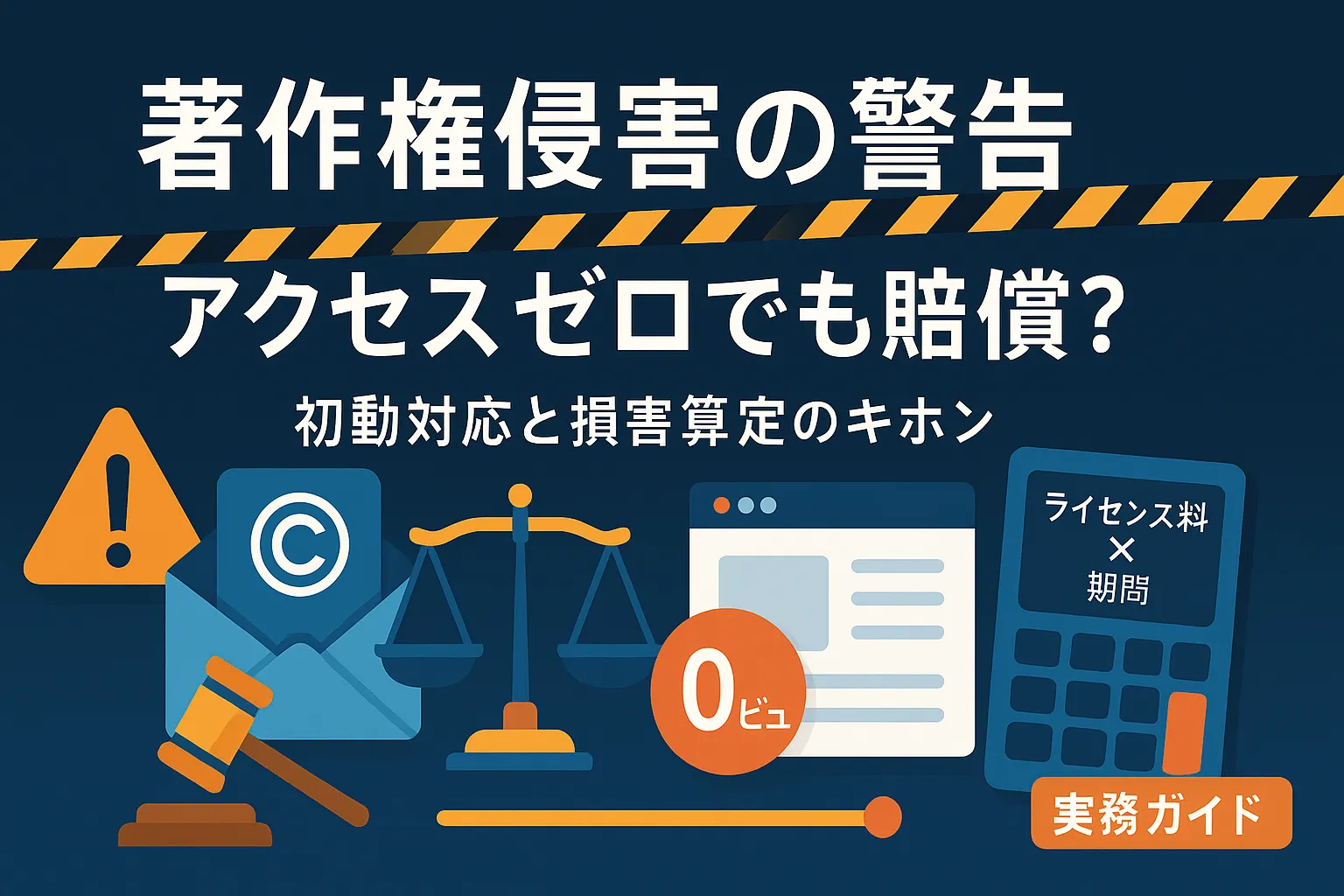ロゴにも発生する著作権?2つのケースに分けて適切な対応方法を解説

はじめに
起業や新規サービスの開始に当たり、自社やブランドのロゴマークを作成することがありますよね。他社にこのロゴを勝手に使用されたり、真似されたりしないよう商標登録を進めている方もいらっしゃることでしょう。
作成したロゴに関して商標登録の手続きさえ進めれば、一安心と思っていませんか?
そのロゴマークはどうやって作成しましたか?
作成にあたっては、社内で社員が作ったり、外部のデザイナーに依頼したりなどのケースがあるでしょう。
作成にあたって著作権についてきちんと対応しましたか?
もし、何も対応していないのであれば、この記事を読んでください。今からでも間に合うかもしれません。
この記事では、
- 著作権と商標権の違い
- ロゴの著作権の扱い
- ロゴ作成依頼(社内・社外)の諸注意
について、弁護士が詳しく解説していきます。
この記事を執筆したのは

- 弁護士・中小企業診断士 勝部 泰之
- 注力:知的財産権・著作権/ライセンス、ブロックチェーン、データ・AI法務
GWU Law LL.M.(知的財産法)
事業の成長とリスクを両立する実務寄りの助言に注力しています。 - 詳しいプロフィールはこちら
1 著作権と商標権
作成されたロゴに関して気をつけなければいけないのは、
- 著作権
- 商標権
です。これらの権利は、保護している対象や目的、権利の発生する手続きが異なります。そのため、「商標権を取得さえすれば、著作権は無視してよい」という関係にはならないのです。
そこで、まずは著作権とは何か、商標権とは何かを確認し、これらの権利の関係性を確認していきましょう。
(1)著作権とは
「著作権」とは、「著作者」(著作物を作成した人)に自然発生する、著作物を独占的に利用できる権利です。権利を得るために特別な手続き等は必要ありません。著作権制度は、著作者の権利の保護と著作物の公正な利用を通じて、文化を発展させるためにあります。
(2)商標権とは
他方、「商標」とは、事業者が自社のサービスや商品を他人のものと区別するために使用するマークです。商標があることで、消費者などは
- 〇〇という事業者がこの商品やサービスは提供していることがわかる
- 〇〇が提供している商品やサービスであれば品質はこのくらいだろうと予想できる
だけでなく、商標を使用する者が信頼を積み重ねることで
- 〇〇のマークがついている。〇〇の提供している商品やサービスだから買いたい
と思わせることも可能です。
このように、商標制度は、
- 商標を使用する者の業務上の信用を維持することで産業を発達をさせること
- 同じマークがついていれば、商品やサービスの提供者は同じであるという取引秩序を維持することで消費者などを保護すること
の2つが目的です。
また、商標権は商標となるマークと、そのマークを使うサービスや商品との組み合わせで成り立つ権利です。この2つを特許庁に出願し、審査を受けて登録が認められてはじめて発生するものです。著作権のように、作成すれば誰にでも与えられるものではありません。
(3)著作権と商標権の関係
このように、著作権と商標権は保護している対象や、それぞれの目的や役割が違います。
そのため、一つのロゴに対して、著作権を持っている者(著作権者)と商標権を持っている者(商標権者)が異なるということも当然あるのです。
この場合、商標権を持っているだけで、事業者はロゴを自由に使用できるのでしょうか。
答えはNoです。
たとえ、商標権を持っていても、著作権を侵害する場合は、使用することができないことが法律で明記されています。
そのため、ロゴを適法な形で使用したいのであれば、著作権を侵害しないようにしなければいけません。
では、ロゴを作成すれば、必ず著作権が発生するのでしょうか。次の項目で確認していきましょう。
2 ロゴに著作権は発生するのか
実は、作成されたロゴすべてに著作権が発生するわけではないのです。
(1)すべてのロゴに著作権が発生するわけではない
著作権とは、著作物を独占して利用できる権利でしたね。この定義にある通り、著作権が発生するのは、作成したものが著作物であった場合です。
著作物として認められるのは、下記の要件を満たしているものです。
- 思想または感情が表れていること
- 著作者の個性が表れていること
- 表現されたものであること
- 文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものであること
これらを見て、難しいと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、ここでいう①「思想または感情」とは、作者の考えや思いという程度の意味です。
また、④「文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」は、工業製品を著作物から除外するための要件です。そのため、ロゴの著作物性を検討するにあたって、この要件を厳密に検討する必要はないでしょう。
作成したロゴがこの4つの要件のうち、1つでも満たしていないものがあるときは、著作物にはなりません。著作物にあたらなければ、ロゴを使用するにあたって著作権の心配をする必要はありません。
次の項目では、著作物にはあたらず著作権が発生しないロゴにはどのようなものがあるかを確認していきましょう。
(2)著作権が発生しないロゴとは
単にロゴといっても、
- 文字列のみのロゴ
- 絵柄(シンボルマーク)のみのロゴ
- 文字列と絵柄などを組み合わせたロゴ(ロゴマーク)
の3つに分けることができます。
文字列のみのロゴのうち、既存のフォントが使用された文字列は、著作物として認められません。
なぜなら、ロゴが既存のフォントを使って作成されている場合、文字そのものは情報を伝える機能を持つものでしかなく、何ら独創性がないからです。独創性がなければ、先ほど挙げた要件の①②③を満たしていないと考えらえます。
たとえば、以下は上から順に「Helvetica」、「Courier New」、「Times New Roman」というフォントを使った文字列です。これらのロゴを作成しても、著作物とはいえません。
では、既存のフォントではなく、新規のフォントやデザイン性の高い文字を使った場合は、著作物になるのでしょうか。
たとえば、アサヒビールのロゴである「Asahi」という文字列について著作物にあたるか裁判で争われたケースがあります(ロゴマーク事件)。この裁判では、デザイン的な工夫があることは認められましたが、美的な創作性がないとして、著作物にはあたらないとされてしまいました。
そのため、たとえ、新規のフォントやデザイン性の高い文字を使ったとしても、文字列のみのロゴに著作権が認められる可能性は低いといえるでしょう。
他方、②絵柄(シンボルマーク)のみのロゴや③文字列と絵柄などを組み合わせたロゴ(ロゴマーク)は、どのような絵柄やシンボルを使うか、その形、サイズ、色、配置などロゴ作成者の考えや個性が表現されていることが多いでしょう。そのため、文字列のみのロゴと比較すると、これらは著作物として認められる可能性が高くなります。
なお、ロゴが著作物にあたるか、悩むケースは必ずあるでしょう。このような場合は、そのロゴが著作物になる前提で対応することをおすすめします。このように対応することで、余計なトラブルが生じることを防ぐことができます。
このように、場合によっては、ロゴも著作物となり、その結果、ロゴの作成者に著作権が発生します。では事業者は、ロゴに著作権が発生した場合、何に気をつければいいのでしょうか。以降の項目で確認していきましょう。
3 事業者が気を付けるべきこととは
事業者が気を付けるべきことは、誰がそのロゴを作るかによって、変わります。
- 外部のデザイナーにロゴの作成を依頼するとき
- 社内の従業員にロゴの作成を依頼するとき
の2つのケースに分けて、ロゴ作成にあたって事業者が気を付けなければいけないことを確認していきましょう。
4 外部のデザイナーにロゴの作成を依頼するとき
外部のデザイナーにロゴの作成を依頼する際は、著作権の譲渡と、著作者人格権についてあらかじめ契約書で明確にしておくことがポイントです。
(1)著作権を譲渡してもらうこと
①著作権を譲渡してもらわないと何が起こるのか
冒頭で説明した通り、著作権とは作成した著作物を独占的に利用できる権利です。この著作権は、著作物を生み出した著作者に最初に発生します。
そのため、外部のデザイナーが著作物にあたるロゴを作成した場合には、依頼した事業者ではなく、デザイナーに著作権が発生します。
著作権が発生したロゴを以下のように利用しようとする場合、事業者はその都度デザイナーから許諾を受けなければいけません。
- 名刺やホームページへのロゴの掲載
- ロゴの加工
これでは、とても業務を円滑に行うことはできなくなります。
また、発生した著作権に対して適切な対応を何もせずに無断で使っていると著作権侵害となる可能性もあります。
そのため、著作権侵害にならない形でロゴを使用できるように、デザイナーから著作権を譲渡してもらうようにしましょう。
②口頭・メールは危険?締結すべき契約とは
では、外部のデザイナーから著作権を譲渡してもらうためには、何をすればいいのでしょうか。口頭やメールで譲渡に関して約束をすればいいのでは?」と思われる方もいるかもしれません。
もっとも、口頭での約束は何も残らず、後から約束したことを証明することが難しいことが多々あります。また、メールも削除や改ざんをされる可能性があり、記録としては不十分な場合があります。
そのため、外部デザイナーとは必ず契約書を締結して、後から何を約束したか確認できるようにしましょう。そして、その契約書には、著作権の譲渡に関して明記するようにしましょう。もし、デザイナーとの契約が既にあり、そこに著作権について何も定めていない場合は、別途「著作権譲渡契約」を締結するという方法もあります。
③注意しなければいけない著作者人格権
もっとも、デザイナーから著作権の譲渡を受けるだけではまだ不十分です。もう一つ気をつけなければいけないのは、「著作者人格権」と呼ばれる権利です。
「著作者人格権」とは著作者の著作物に対する思いや名誉を守る権利です。
そのため、著作権を譲渡しても、著作権と一緒に著作者人格権に渡ることはなく、著作者のもとに残り続けます。
この著作者人格権があることで著作者は以下をすることができます。
- 著作物の公表の有無、公表する際の手段を決める「公表権」
- 著作物公表の際の氏名の有無、出す場合の実名や変名を決める「氏名表示権」
- 著作者の意に反した改変を勝手にされない「同一性保持権」
せっかく事業者が著作権の譲渡を受けても、デザイナーから「そのロゴに改変を一切加えてはいけない」「ロゴを出すときは必ず自分の名前を併記して」という要求や口出しをされる可能性があることになります。これでは、事業者としてはロゴが使いづらくなってしまいます。
こういったことを防ぐため、契約書の中では「著作者人格権を行使しない」という定めを入れておきましょう。著作者人格権の行使そのものを控えてもらうことで、余計な要求や口出しがされることを防ぐことができます。
(2)どうしても全ての著作権の譲渡をしてくれないとき
もしも著作者から全ての著作権の譲渡を拒否されてしまったときは、
- 権利を限定して譲渡してもらう
- ライセンス契約を締結し、一時的に利用できるようにする
という選択肢があります。
①権利を限定して譲渡してもらう場合
著作権は譲渡するときに、必ずしも全てを渡さないといけないわけではありません。一部の権利のみの譲渡も可能なので、「複製権」(コピーをすることができる権利)「翻案権」(加工や変更をすることができる権利)など、必要な部分を譲渡してもらうこともできます。
②ライセンス契約を締結し、一時的に利用できるようにする
著作者と「ライセンス契約(著作権利用許諾)」を締結すれば、著作者が著作権を譲渡しなくても、規定の利用料(ロイヤリティー)を支払えば、契約で設定した条件の範囲内で一時的にロゴを利用できるようになります。
もっとも、企業やサービスのロゴは長期的に業務のあらゆる部分で使用することになるものです。自由に使うことができないとなると、業務上に様々な制限が出てしまい、不都合が発生することもあるので、なるべく全ての権利を譲渡してもらう方が望ましいといえます。
※著作権譲渡契約について詳しく知りたい方は、【雛形付き】著作権譲渡契約書の作成で気を付けたい11のポイント!の記事をご覧ください。
5 社内の従業員にロゴの作成をさせるとき
社内の従業員にロゴの作成をさせたときは、「職務著作」の要件を満たしているかがポイントです。なぜ職務著作になるかどうかがポイントになるのか確認していきましょう。
(1)従業員が作ったロゴは会社のもの?
従業員が業務上でロゴを作成した場合、原則、そのロゴの著作者は従業員になります。
そのため、「社内で従業員が作成したから、自動的に会社のものになり自由に扱って良い」というわけにはいかないことになります。
もっとも、「原則」があるということは「例外」もあります。
(2)会社のものにするには?
従業員が作成した著作物を例外的に会社のものにするため(会社が著作者になるため)には、下記の「職務著作」の要件を満たしている必要があります。
- 法人等の発意にもとづくこと
- 法人等の業務に従事する者が職務上作成するものであること
- 法人等の名義の下に公表するものであること
- 作成時における契約、就業規則その他に別段の定めがないこと
1つでも満たさない要件があると、従業員の許諾なしにロゴを利用できなくなったり、ロゴを作成した従業員が退職した後に著作権を主張されたりといったトラブルにつながるおそれがあります。
4つの要件の中で特に注意しなければいけないのは④です。以下で著作権や知的財産権についてどのように定められているか確認しましょう。
- 従業員と締結した雇用契約書などの契約書
- 社内規程
「著作権を含む知的財産権は作成者である従業員に帰属する」などの定めがあると、④の要件を満たしていないことになってしまいます。
このように、外部のデザイナーに依頼する場合も、社内の従業員に作成を依頼する場合も著作権について適切に対応することが必要です。
これらに加えて最後にやっておくべきなのが作成されたロゴそのものが他人の著作権などの権利を侵害していないかという点です。
※職務著作について詳しく知りたい方は、「従業員が生み出したものは会社のもの?職務著作の4つの要件を解説!」をご覧ください。
6 ロゴの確認
ロゴが完成したら類似のロゴや画像がないかをインターネットの画像検索ツールなどで確認をしておきましょう。
なぜなら、万が一、ロゴの作成者が他人の著作物などを剽窃(いわゆる「パクり」)していると大きなトラブルとなるからです。
また、パクられた側からすると、誰がそのロゴを作ったかは通常わかりません。そのため、権利侵害に基づく損害賠償請求など各種請求の矛先はロゴを生み出した作成者ではなく、使用している事業者に向かってしまいます。
こういった意味でも、事業者は、公開前に慎重に確認したほうがいいでしょう。
なお、このようなパクりなどが発生しないように、作成者との間で、
作成前の契約段階に「他者の知的財産を侵害しない」という取り決めを契約書に盛り込んでおくことも防止の手段として有効だといえます。
7 小括
ロゴ作成の際の商標権と著作権の問題についてみてきました。
商標権さえ取得すれば著作権の問題は発生しないということはありません。また、商標権を取得したから著作権は無視してよいということもありません。
著作権の問題はロゴの作成時に適切に対応することで解消することができます。余計なトラブルに巻き込まれないようにロゴについては商標権だけでなく、著作権についても注意するようにしましょう。
8 まとめ
これまでの解説をまとめると、以下の通りです。
- 著作権は著作者に権利が自然発生するが、商標権は申請後、登録が認められなければ発生しない
- 全てのロゴが著作物として認められるわけではなく、著作物にあたらないロゴもある
- 企業がロゴの作成を社内または外部に依頼する際は、著作者人格権について把握し、著作権譲渡契約書の項目に含めておく
- 社内で従業員がロゴを作成する場合は、職務著作の要件を満たすようにする
- ロゴは剽窃など他人の著作権を侵害していないか、公表前にチェックをする
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。