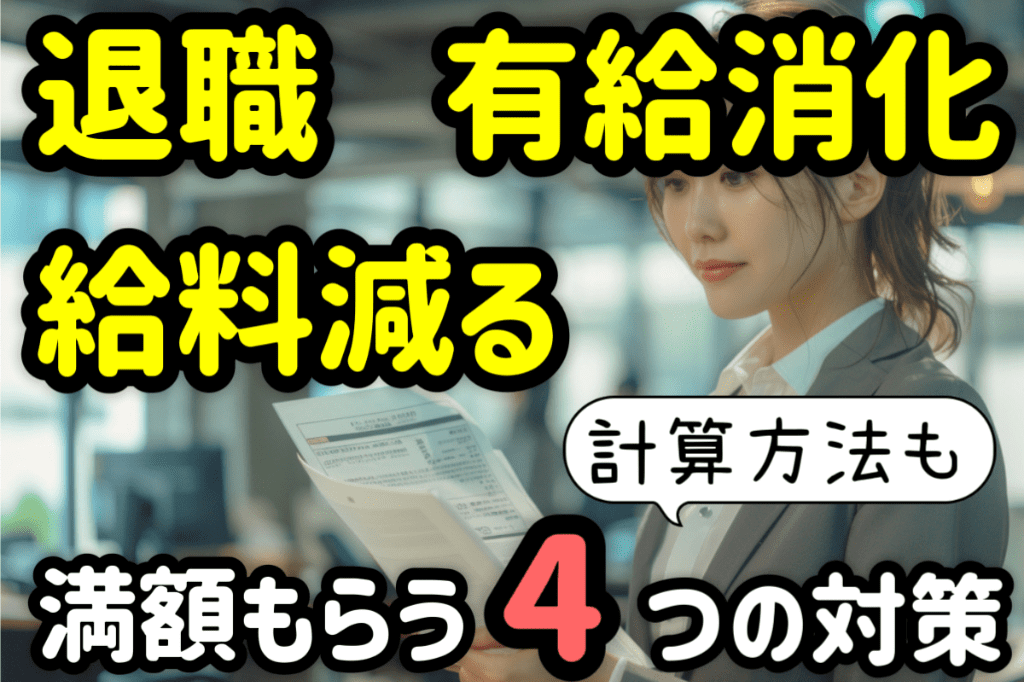著作権法改正がAI開発に与える影響は?2つの注意点を弁護士が解説

はじめに
2018年に著作権法が改正されたことでAI開発が大幅にやりやすくなりました(2019年1月から施行)。ですが、今回の著作権法改正により、AI開発において具体的に何がどのように便利になったのか?を正確に理解していないAI事業者は多いのではないでしょうか。
改正を受けて、何ができるようになり、何に注意しなければいけないのかをより深く理解することは、AI関連の事業を加速し、ビジネスチャンスを広げていくうえで大変重要です。
そこで今回は、主にAI開発事業者向けに、著作権法の改正がAI開発に与える影響について、ITに詳しい弁護士が解説していきます。
1 著作権法の改正理由

(1)著作権とは?
「著作権」とは、自分の考えや感情を独創的に表現したコンテンツ(=著作物)を、独占的に利用できる権利のことをいいます。
たとえば、著作物には、小説、楽曲、ダンスなどの振り付け、絵画、模型、写真、プログラムなどがあります。
著作権は、著作物を生み出した人(著作者=著作権者)に、自動的に発生します。
著作権が認められると、そのコンテンツを著作権者に無断で使ったりコピーすることは禁止されます。
そして、この著作権はAI開発のプロセスで使われるデータについても認められる場合があり、著作権法の改正理由となっています。
(2)改正理由
AI開発は、コンピュータが、大量のデータから学ぶ「機械学習」という手法で行われており、この学習用の大量のデータの中には、著作権が認められるものがあります。改正前の著作権法では、著作物をコピーしたり、コンピュータが学習しやすいよう加工したりする際には、著作権者の許諾が必要だったことから、著作物を機械学習に用いる障害となっていました。
そのため、機械学習を円滑に行い、AIという新しい技術の発展を促すために、著作権法が改正されたのです。
具体的には「権利制限規定」の変更と「情報解析の結果提供」の条項の新設です。
2 「権利制限規定」とは?

「権利制限規定」とは、例外的に、著作権者の許諾を得ずに、著作物を自由に利用できるようにするために設けられた著作権法上の規定のことをいいます。
著作権は、著作物を独占的に使用することができる権利であるため、著作権者以外が、著作物を無断で使用することは、原則できません。
もっとも、この原則を徹底すると、著作物を利用する際には、常に著作権者から使用の許諾を得なければいけなくなってしまいます。
たとえば、浮世絵を描くAIを生み出す場面を考えてください。
AIが絵を描くためには、
- 様々な人が作成した浮世絵のデータを集める
- 集めた浮世絵をAIに学習させる
- AIは絵の特徴から法則を見つける
- 「③」の法則を用いて絵を描く
↓
↓
↓
というステップを踏むことになります。
AIが浮世絵を描くようになるためには、大量の浮世絵のデータが必要です。
もっとも、著作物の無断使用禁止という原則を徹底すると、AI開発事業者は、学習に利用しようと思った全ての浮世絵の著作権者から許諾を得る必要があります。浮世絵のデータが大量である以上、現実的には困難であるうえ、このような不便な開発環境では、AI開発技術の向上は望めません。
そのため、著作権法は「権利制限規定」として、例外的に、著作権者の権利を制限し、著作権者の許諾を得ることなく著作物を自由に利用することができる場面を定めています。
今回の改正のポイントの一つが、この「権利制限規定」が見直された点にあります。先に見たように、旧著作権法は、AI技術などを想定した作りになっていませんでしたが、このことにより、具体的にどのような不都合が生じていたのでしょうか。
3 改正前の著作権法の問題点

(1)改正前の問題点
改正前の「権利制限規定」は、AIの登場を想定していませんでした。
改正前の「権利制限規定」の問題点は、法律の文言上、利用目的と利用方法が以下のように限定されていた点にあります。
- 著作物の利用目的:自ら行う「情報解析」であること
- 著作物の利用方法:「記録・翻案」であること
ここでいう「記録」とは、サーバーやHDDなどの記録媒体にデータを保存することをいい、「翻案」とは、ソフトウェアを改良するといった、既存の著作物を基に新たな著作物を生み出すことをいいます。
また、法律上明記はされていませんでしたが、「情報解析」には、AIのディープラーニングを含む機械学習が含まれると考えられていました。
すなわち、改正前の著作権法では、自らAIに学習をさせるという目的であれば、著作権者の許諾を得ることなく、著作物をサーバーやHDDなどの記録媒体にデータを保存したり、既存の著作物を基に新たな著作物を生み出すことができることになっていたといえます。
それでは、具体的に何が問題だったのでしょうか。
先ほどの浮世絵を描くAIを生み出す事例をベースに2つのケースで確認していきましょう。
(2)改正前の問題に起因する著作権侵害のケース
-
【ケース①】
AI開発の依頼者(ユーザ)が浮世絵のデータを用意し、AI開発事業者(ベンダ)がAIに学習させるケース
このケースでは、著作物の利用目的、利用方法それぞれにおいて著作権侵害と判断される可能性がありました。
①著作物の利用目的
このケースでは、ベンダがAIに学習させることになります。この場合、ユーザは、自らAIに学習(情報解析)をさせるという目的で著作物を利用していません。
そのため、先に示した著作物の利用目的をみたしていませんので、「権利制限規定」の適用は受けません。
以上から、改正前の著作権法では、このケースについて、著作権者の許諾なく浮世絵のデータを利用すると著作権侵害であるとの解釈がなされる可能性がありました。
②著作物の利用方法
このケースでは、ユーザが用意した浮世絵のデータがベンダに提供されることになります。著作物のデータを提供することは、著作物の利用方法である「記録・翻案」に含まれないため、「権利制限規定」の適用を受けません。
以上から、改正前の著作権法では、このケースについて、著作権者の許諾なく浮世絵のデータを利用すると著作権侵害であるとの解釈がなされる可能性がありました。
-
【ケース②】
ベンダAが既にAIに学習させた使用済みの浮世絵のデータセットを別のベンダBに販売するケース
このケースも、ケース①と同様です。ベンダAは自ら学習させるという目的をもっておらず、また、ベンダBにデータを提供している点で、「記録・翻案」にはあたりません。
そのため、このケースについても、「権利制限規定」の適用はなく、著作権者の許諾なく浮世絵のデータセットを利用すると著作権侵害との解釈がなされる可能性がありました。
このように、改正前の著作権法における「権利制限規定」は、著作物の利用目的・利用方法が限定的であったために、AIを学習するためのデータを用意する者と、AIに学習させる者が異なるケースに対応することができませんでした。
それでは、著作権法改正により、「権利制限規定」はどのように変わり、また、条項の新設により、AI開発において何ができるようになったのでしょうか。
4 注意点①:改正により可能になった行為
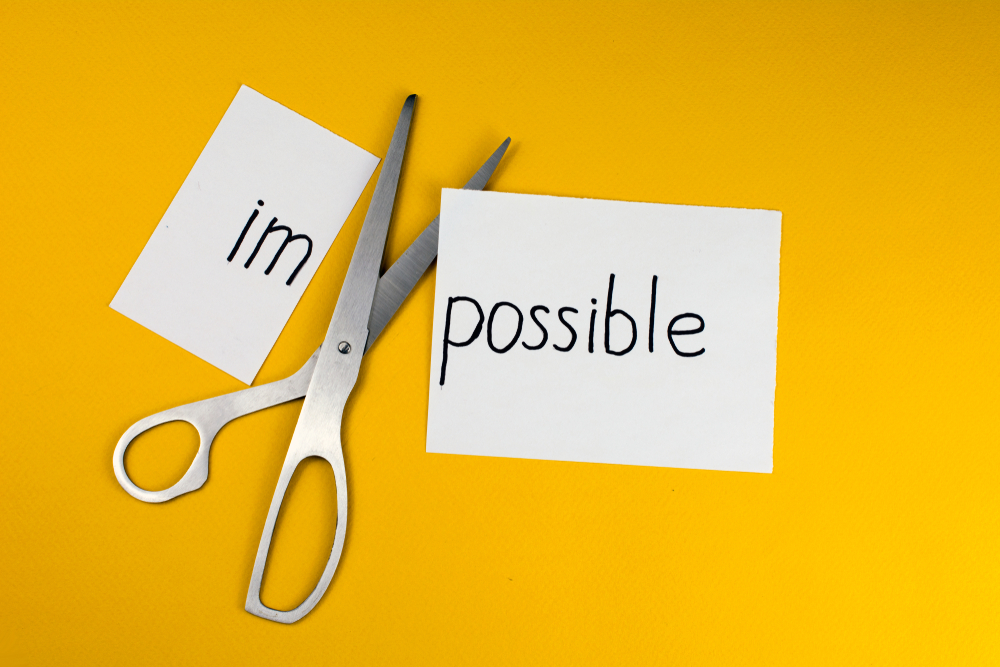
(1)「権利制限規定」の変更のポイント
「権利制限規定」の変更のポイントは、
- 「情報解析」の定義
- 利用目的
- 利用方法
- 著作権者の利益
という4つです。
①「情報解析」の定義
改正前の著作権法では、「情報解析」にAIのディープラーニングを含む機械学習が含まれるかどうかが、法文上不明確でした。
もっとも、著作権法改正により、「情報解析」の定義が設けられたことで、「情報解析」にはディープラーニングを含む機械学習も含まれることが、法文上、明確になりました。
②利用目的
改正前においては、著作権者の許諾なく著作物を利用するためには、自らが情報解析を行うことが利用目的となる必要がありました。
もっとも、著作権法改正により、「情報解析に役立てる」という利用目的があれば、著作権者の許諾なく著作物を利用できるようになりました。
このように、利用目的の範囲が広くなったため、ユーザ自らはAIに学習(情報分析)させることをせずに、ベンダに依頼する場合においても、ユーザが著作物を著作権者の許諾なく収集し、保存することができるようになりました。
③利用方法
②にあわせて、改正前は、著作物の利用方法が「記録・翻案」に限定されていたものが、改正により「方法を問わず」に変更されました。
そのため、ユーザが著作物を著作権者の許諾なく収集し、AIに学習させるためにその著作物をベンダに提供するということが可能となりました。
これら①~③の改正により、先に確認したケース①②ともに「権利制限規定」が適用されることなり、著作権者の許諾なく著作物を利用できるようになりました。
④著作権者の利益
②利用目的、③利用方法が緩和された一方で、著作権者の利益にも配慮してバランスを取る必要がありました。そのため、著作権法改正においては、著作権者の利益が不当に侵害されないよう、不当な侵害があれば、「権利制限規定」にあたらず著作権者の許諾が必要となるよう改正が行われました。この点に関しては、実務上の注意点として、後に詳細を説明します。
(2)新設された条項のポイント
新設された条項のポイントは、「情報解析の結果提供」に、著作物の利用を行うことができるようになった点です。
①情報解析の結果提供
「情報解析の結果提供」とは、情報解析によって新たな知見や情報を生み出して、その知見や情報を提供するサービスのことをいいます。
著作権法改正により、この「情報解析の結果提供」に関する条項が新たに新設されました。
具体的には、「情報解析の結果提供」を行うために、一定の条件のもとで、著作権者の許諾なく著作物の利用を行うことができるようになりました。
たとえば、「論文剽窃検証サービス」というサービスがあります。
「論文剽窃検証サービス」とは、検証の対象となった論文が他の論文や本の文章を盗んでいるかといった剽窃の有無やその割合を調べるサービスをいいます。
このようなサービスでは、盗まれているという事実だけでなく、盗まれたオリジナルの文章の該当部分(著作物)をあわせて報告することで、どの部分をどのように盗まれたのか分かりやすくなります。
もっとも、改正前では、オリジナルの文章の著作権者に利用の許諾を得る必要がありました。
ですが、この条項が新設されたことで、オリジナルの文章の著作権者から許諾を得ることなく、盗まれたオリジナルの文章の該当部分もあわせて報告することが可能となりました。
それでは、AIと「情報解析の結果提供」はどのように関わってくるのでしょうか。
②AIを用いた各種調査解析サービス
AIとの関係でこの条項は、完成したAIを利用する局面で関わってきます。
具体的には、AIによる調査解析を行い、その結果を提供するようなサービスを行う場合において、調査目的での軽微な著作物の利用が可能となりました。
「情報解析の結果提供」に際し、軽微な著作物の利用が可能になったことで、AIを用いた各種調査解析サービスの幅が広がったといえます。
このように、著作権法は、AI開発・AI技術の発展を目的の一つとして、改正されました。
もっとも、著作権者の利益を不当に害することになる場合にまで、「権利制限規定」を適用していては、誰も著作物を生み出そうとしなくなってしまいます。
この点について、実務ではどのような点に注意する必要があるのでしょうか。
5 注意点②:現状で実務上注意すべき点

実務上注意が必要なのは、「著作権者の利益を不当に害する場合」には、「権利制限規定」は及ばないということです。「権利制限規定」が及ばないということは、つまり、著作権者の許諾なく、著作物を利用することができなくなるということです。
「著作権者の利益を不当に害する場合」とはどのような場合をいうのかについては、司法の場で争われておらず、その解釈の判断基準は明確になっていません。
もっとも、「著作権者の利益」とは、著作物を見たい、聞きたい、使用したいという人から対価を得ることです。
たとえば、漫画のワンシーン(著作物)を広告に利用したい人がいれば、著作権者にそのワンシーンの使用料を対価として支払うことになります。
そのため、「著作権者の利益を不当に害する場合」にあたるかどうかが問題となるのは、著作権者が対価を得る機会を奪う場合、主に、著作物を集めて学習用のデータセットとして販売するような場面になると考えられます。
たとえば、ある有名な漫画家の全作品をデータとして集め「漫画家○○の作風学習用データセット」が販売された場合を考えてください。そのまま漫画として読める状態にデータが構成されていた場合、AI学習用のデータセットさえ買ってしまえば、漫画を買う必要がなくなってしまいます。このような場合、著作権者である漫画家は漫画を販売して対価を得る機会を奪われていることになります。
少なくとも、このような場合には、「著作権者の利益を不当に害する場合」にあたり、著作権法違反となる可能性があります。
このように、著作物を利用する際には、著作権者の市場と衝突し、著作権者の対価を得る機会を奪うことにならないかという観点を持ち、著作権法違反とならないように適切に著作物を利用することが、実務上注意すべき点だといえます。
6 小括

著作権法改正により、AIの学習に関連した著作物利用が緩和され、また、「情報解析の結果提供」のための軽微な著作物の利用が可能になりました。その結果、AIの開発や、AIを利用したサービスがやりやすくなったといえます。
今後は、著作物を利用したディープラーニングや、AIを学習させるデータセット販売、AIを利用した各種情報解析が盛んに行われることが想定されます。
もっとも、著作物を制限なく自由に使えるようになったわけではありません。著作権者の利益を不当に害し、著作権法違反とならないよう注意することが必要です。
7 まとめ
これまでの解説をまとめると、以下のとおりです。
- 「著作権」とは、自分の考えや感情を独創的に表現した著作物を、独占的に利用できる権利のことである
- AIに関係する2019年施行の著作権法の改正部分は、具体的には「権利制限規定」の変更と「情報解析の結果提供」の条項の新設である
- 「権利制限規定」とは、著作権者の権利を制限し、著作権者の許諾を得ることなく、著作物を自由に利用することができる場合に関して定めた著作権法上の規定のことである
- 改正前の「権利制限規定」の問題点は、①著作物の利用目的が自ら行う「情報解析」であること、②著作物の利用方法が「記録・翻案」であること、と限定されており、AIを学習するためのデータを用意する者と、AIに学習させる者が異なるケースに対応していなかった点である
- 著作権法改正によって「情報解析」にディープラーニングなどの機械学習も含まれるということが明らかになった
- 著作権法改正によって著作物の「利用目的」が広がり、「利用方法」の制限がなくなったため、AI開発に著作物を利用しやすくなった
- 「情報解析の結果提供」に際し、軽微な著作物の利用が可能になったことで、AIを用いた各種調査解析サービスの幅が広がった
- 実務上注意すべき点は、著作物を利用することで、著作権者の市場と衝突し、著作権者の対価を得る機会を奪わないかという観点を持つことである
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。