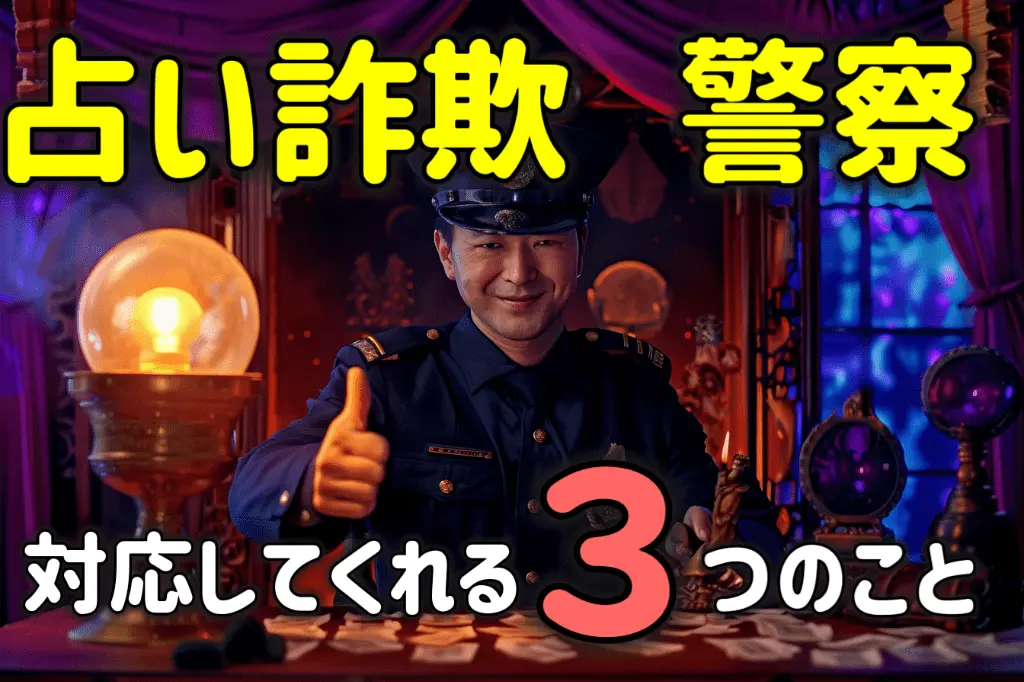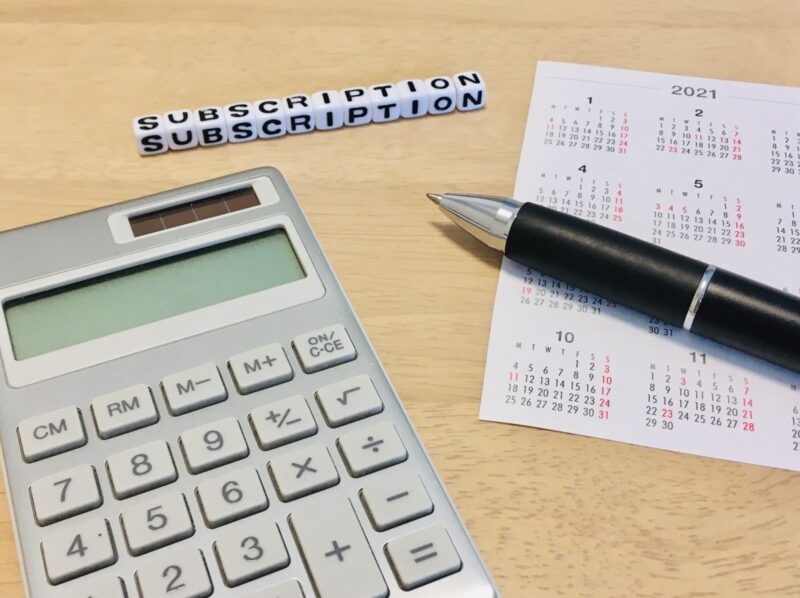民泊ビジネスの法律規制とは?違法にならないための4つのポイント!

はじめに
「民泊ビジネス」って流行っていますよね。
民泊と聞けば誰もが何となくはイメージできるほど、近年、民泊ビジネスが浸透してきています。
Airbnb(エアービーエヌビー)という民泊仲介サイトが日本に参入してからは、かなりの勢いで民泊が広まっていきました。
ただし、現状、民泊ビジネスは、「違法」・「グレー」などと言われているため、法的なリスクがネックとなって民泊に手を出しにくい、という方も多いのではないでしょうか。
そこで以下では、民泊ビジネスを始めたいホストと、Airbnbなどの民泊仲介サイトの立場から、民泊にかかわる法律規制の内容、違法なのかグレーなのか、対処法を詳しく解説していきます。
※なお、2017年に成立した「民泊新法」によって、全国的に民泊規制が緩和され、届出さえすれば、年間180日を上限として、誰でも民泊を始められるようになりました。ただし、民泊新法が施行されるのは2018年6月のため、それまでは今までどおりの法律に基づいた運用となります。
1 民泊って何?

(1)民泊とは
「民泊」とは、文字どおり民家に泊まることをいいます。
ただ、最近では、インターネットの民泊仲介サイトの出現によって、観光客などに個人の自宅や使っていない別荘・マンションなどを有料で貸し出すことを「民泊」と呼ぶことが多くなっています。
民泊が注目を集める理由として、まずは外国人観光客(インバウンド)の増加が挙げられます。訪日外国人数はここ最近毎年増加していて、2016年は約2404万人と、過去最高となりました。外国人観光客が急増したことで、今まであった宿泊施設だけでは対応しきれなかったことから、多くの外国人観光客が民泊を利用し、2016年は「民泊元年」とも呼ばれています。
また、現在全国的に深刻な問題となっている「空き家問題」を解決するため、空き家を宿泊施設として観光客に提供し始めたことも、民泊が普及した理由の一つとして挙げられます。
(2)民泊の仕組み
次に、民泊の仕組みについてみていきましょう。
実際に民泊を利用するときの流れは、ホテルの予約をするときを想像してもらえればほぼ問題ありません。
ただし、民泊は「ゲスト」(部屋に泊まる側)も「ホスト」(部屋を貸す側)も個人のため、Airbnb(エアービーエヌビー)などの「民泊仲介サイト」が間に入るケースがほとんどです。
民泊仲介サイトを利用する場合の仕組みは以下のようになっています。

宿泊までのおおまかな流れは以下のようになります。
- 民泊を利用したいゲストは、民泊仲介サイトを見て泊まりたい部屋を決め、ホストにリクエストを送る
- リクエストを受け取ったホストが承認すれば予約が確定する
- ゲストは仲介サイトに宿泊代を支払い、宿泊当日に宿泊場所にチェックインする
- 後日ホストに手数料が引かれた宿泊代が支払われる
2 民泊のメリット・デメリット

民泊といえば「空き部屋を使って副収入を得られる!」といったメリットがありますが、その裏にはもちろんデメリットもあります。
そこで、以下ではホストとメリット・デメリットを確認しておきましょう。
(1)民泊のメリット
ホストが民泊ビジネスをするメリットは以下のとおりです。
- 空き部屋を利用して手軽に収益をあげられること
- 外国人と交流ができること
- Airbnbでは、一部のホストを「スーパーホスト」として認定し、様々な優遇措置をしていること
(2)民泊のデメリット
ホストが民泊ビジネスをするデメリットは以下のとおりです
- 備品や家具の持ち帰りや破損するリスクが高いこと
- 犯罪の温床になる可能性があること
- 民泊仲介業者へ手数料を支払わなければならない
- 法律や条例の規制が複雑
以上がホスト・ゲストそれぞれのメリット・デメリットになります。
メリットの裏にあるデメリットをしっかりと理解したうえで、民泊を利用することがポイントです。
次の項目では、民泊ビジネスに対する法律規制について、①ホスト、②民泊仲介業者の視点からそれぞれ解説していきます。
3 「ホスト」への法律上の規制

最近、ニュースで違法な民泊を運営するホストが摘発されたニュースがよく報道されていますよね。
ニュースを見て、「民泊って違法なの?」と思った方も多いのではないでしょうか?以下では、ホストとして民泊の運営を始めるときの法律上の問題点・規制、対処法について解説していきます。
(1)民泊と旅館業法の問題
まず、基本的に、人を宿泊させてお金をもらう場合は「旅館業法」という法律に基づき、営業の許可を得なければならないというルールになっています。
「旅館業法」とは、旅館やホテルを運営する際のルールが書かれた法律です。
旅館やホテルには、たくさんの人が食事や寝泊りをすることから、運営者による適当な経営をされては宿泊客が困るため、運営者を規制するために作られた法律です。
もっとも、「旅館業」という言葉とは裏腹に、一般人が自宅や空き部屋を利用して行う民泊の場合でも、一定の要件をみたすときには「旅館業」として旅館業法によって規制され、民泊を運営するためには、営業の許可を得る必要があります。その結果、旅館業にあたるのに無許可で民泊を運営している場合には、民泊を運営するホストは、旅館業法違反となり、摘発されてしまいます。
反対に、「旅館業」にあたらないようなスキームの民泊ビジネスであれば、営業の許可を得る必要がないため、合法的に民泊を運営できます。
そこで、法律が定める「旅館業」の意味がポイントになってきます。
この点、「それじゃあちゃんと許可を取ればいいだけの話じゃないか」と思うかもしれません。ですが、旅館業法上の営業許可を取るためには、客室床面積についての規制や宿泊施設の設備条件など、細かい規制がたくさんあります。
そのため、これらの規制をすべてクリアしようと思ったら、民泊を始めることはとてもハードルの高いものとなってしまいます。しかし、そんな面倒な手続きをしてまで民泊ビジネスをしようと考える人はいませんよね?そのため、営業許可を得ることなく民泊ビジネスができるスキームを考える必要があるのです。
(2)旅館業とは
では、「旅館業」にあたらず、旅館業法の営業許可を取らなくても民泊を合法的に運営する方法はないのでしょうか?
ここで、どのような「民泊」に営業許可が必要となってしまうかを確認しておきましょう。
具体的には、以下の4つの要件をすべてみたした場合に「民泊」は「旅館業」となり、営業許可が必要になります。
- 宿泊料を徴収していること
- 社会性があること
- 反復継続性があること
- 生活の本拠ではないこと
これら4つの要件すべてにあてはまるのに無許可で民泊を営業した場合には、旅館業法違反となってしまいます。
反対に、これら4つの要件のうち1つでもあてはまらなければ、「民泊」は「旅館業」にあたらず、営業許可がなくても違法営業にはならない!ということになります。
わざわざハードルの高い営業許可を取らなくても、民泊の営業が可能となるわけです。
それでは以下で、4つの要件について具体的に見ていきます。
4つの要件に共通するポイントは、「名目や呼び方はどうであれ、内容をみて実質的に判断される」という点です。
このことを意識しながら解説を読んでみてください。
①宿泊料の徴収をしていること
「宿泊料」とは、寝具や部屋の使用料のことをいいます。
私たちがホテルなどに泊まるときに支払う宿泊料金のイメージです。
ただし、宿泊料以外の別の名目でお金を貰った場合でも、「実質的に寝具や部屋の使用料とみなされる場合」には「宿泊料」を徴収しているとされ、旅館業の営業許可が必要となります。
具体的には、休憩料・寝具賃貸料・寝具等のクリーニング代・水道光熱費・室内清掃費などの名目でゲストからお金をもらう場合です。
一方で、食事代やテレビ代をもらったとしてもそれは宿泊料とはみなされません。
呼び方がどうであっても、その中身が実質的に寝具や部屋の使用料なのであればそれは「宿泊料」になります。
②社会性があること
「社会性がある」場合とは、部屋の利用実態が、一般的にみて、個人が普通に生活として使用している範囲を超えている場合をいいます。
これは、どう考えても個人としての生活上の行為ではなくて、明らかにビジネスとして行っている場合などをいいます。
具体的には、
- Airbnbなどの民泊仲介業者を利用するなどして宿泊者を広く募集する行為
- 不特定多数の人を泊まらせたりするような行為
をいいます。
一方で、家族や友人を泊まらせる場合には、個人の生活上の行為にあてはまるため社会性があるとはみなされません。
広く宿泊者の募集をしているか、誰を泊まらせているかなど、その実態から実質的な判断がされます。
③反復継続性があること
「反復継続性」とは、繰り返し何度も・継続して宿泊施設の提供をすることをいいます。
具体的には、
- 宿泊募集を継続的に行っている場合
- 曜日や季節を限定していても、民泊として宿泊施設の提供を繰り返し行っている場合
などです。
一方で、毎年1回(2~3日程度)のイベント開催時などに周辺の宿泊施設不足が見込まれる場合に、自治体からの要請によって自宅を一時的に提供するような、公共性の高いものの場合は、反復継続性は認められません。
何回・何日以上はアウト、などの明確な基準がないため、反復継続性についても実質的に判断されます。
④生活の本拠ではないこと(宿泊者にとって)
「生活の本拠」とは、その部屋を生活の拠点とすることをいいます。
例えば部屋を借りて住み始めた場合、住民登録や住所変更、固定電話やネット回線を引くなどして、その部屋が生活をしていくための拠点になりますよね。
このような場合には「生活の本拠である」といえます。
これに対して、宿泊施設の場合は、宿泊者にとっては一時的に滞在するだけなので、生活の本拠になることはありません。
宿泊者からみて、「生活の本拠」といえるかどうかについては、基本的には使用期間が1か月未満の場合は「生活の本拠ではない」と判断されます。
ただし、利用期間が1か月以上の場合であっても、部屋の清掃や寝具類の提供をホスト側が行っている場合には、同じく宿泊者にとって「生活の本拠ではない」と判断されます。
やはり内容から実質的な判断がされているということですね。
※民泊と旅館業法の関係については、厚生労働省の「民泊サービスと旅館業法に関するQ&A」もご参照ください。
以上①~④の要件のうち、いずれか一つでも非該当の部分があれば、旅館業法の許可を得ていなかったとしても、ホストによる民泊ビジネスは、違法とはならず、合法的に運営できます。
反対に、①~④の要件をすべてみたす形での民泊は、「旅館業」にあたり、営業の許可なく行なわれる民泊は、違法となります。
(3)ペナルティ
ここまで「民泊」が「旅館業」にあたる場合の要件をみてきましたが、これらの要件にあてはまるのに無許可で民泊を営業し、旅館業法違反となってしまった場合のペナルティについてみてみましょう。
旅館業法に違反した民泊のホストに対しては、
- 最大6月の懲役
- 最大3万円の罰金
または
といったペナルティが科される可能性があります。
パッと見そこまで重くなさそうに思えますが、違法民泊の摘発についてはテレビなどのニュースで取り上げられることも多く、報道されれば社会的な信用を落とす可能性は大いにあります。
また、現在営業している民泊の大半が無許可営業という実態から、国は罰則の強化も検討しています。
そのため、民泊を始める場合には、合法的に運営するスキームを構築することが必要です。
(4)対処法
ここまで民泊が旅館業にあたる場合の要件や、違法となった場合のペナルティをみてきました。
でも民泊を始めようと思っているホストからすると、なんとか旅館業にあたらないラインで合法的に民泊を運営したいですよね。
そこで、旅館業の4つの要件にあてはまらず、民泊ビジネスが違法認定されないための対処法について考えてみたいと思います。
-
【旅館業の4要件】
- 宿泊料を徴収していること
- 社会性があること
- 反復継続性があること
- 生活の本拠ではないこと
①宿泊料について
まず、1番ポイントになる「①:宿泊料を徴収している」に該当しないためのスキームを考えてみましょう。
「宿泊料」とは、寝具や部屋の使用料を意味しましたが、宿泊料の該当性を判断するにあたっては、ネットカフェのモデルが参考になります。
ネットカフェは夜から朝まで過ごす人も多く、まるで「宿泊」しているように思えますが、お客さんはベッドを使用するわけではなくソファーや椅子で睡眠をとります。
この場合、「寝具を利用している」とはいえないため、利用料金をもらっても宿泊料にはあたらず、「旅館業」とはみなされません。
これを応用して、民泊施設として提供する部屋にはベッドを置かずにソファーやふかふかの椅子のみを置いておき、食事代やテレビ代として料金を受け取るというスキームをとれば「旅館業」にはあたらない可能性があります。
②「社会性」について
次に、「②社会性」のある・なしについて、違法認定を回避する方法を考えてみます。「社会性がある」場合とは、部屋の利用実態が、一般的にみて、個人が普通に生活として使用している範囲を超える場合を意味しました。
この定義をふまえ違法認定を回避するためには、インターネットなどに民泊の広告を載せずに、あくまでも自分の知り合いだけに部屋を使わせるぐらいの方法しかないのが現状です。
③「反復継続性」について
「③反復継続性」について違法認定を回避する方法を検討してみましょう。
「反復継続性」とは、繰り返し何度も・継続して宿泊施設の提供をすることを意味しました。
そのため、宿泊期間や日にちを限定して、部屋を提供するという方法が一案としてあります。また、出張等で家を不在にすることが多いという体で、「出張中にAirbnb等を通じて貸しているだけ」という形にする方法も考えられます。
もっとも、民泊として将来的に継続して貸し出すということであれば、結局、違法認定を回避することは難しいですね。
④「生活の本拠であること」について
最後に、「④生活の本拠であること」について検討しましょう。
「生活の本拠」とは、宿泊者からみて、その部屋を生活の拠点とすることを意味しました。
これを前提にすると、例えば
- 床や壁・家具の清掃は、ホストではなくゲスト側が行う
- 寝具の交換や洗濯はゲスト側が行う
- その上で、ゲストがその部屋を住民票上の「住所」とすることを許可する
などのスキームを構築できれば、「旅館業」にはあたらない可能性が高くなります。
ただし、これらの回避方法をとったとしても他の法律による規制対象となる可能性は十分あることには注意が必要です。
(5)特区民泊による規制緩和
これまでは、ホストが営業許可を得ることなく営む民泊が「旅館業」にあたらない方法を解説してきました。ただ、現実的には、多くの民泊ビジネスは、旅館業にあたり、違法と認定される可能性が高いのが実情です。
しかしそれでは、今後爆発的に増加するインバウンド需要に応えられず、国策としてはイケていません。
そこで国が設けた施策が「特区民泊」というシステムです。
「特区民泊」とは、国家戦略特区に指定されているエリアのうち民泊条例を制定している自治体に限定して、旅館業法の適用をうけずに(=規制緩和)運営することのできる民泊のことをいいます。
先ほど解説したとおり、民泊を営業するには基本的に旅館業法上の営業許可が必要ですが、特区民泊として認められれば旅館業法の適用を受けないことになるので、厳しいルールに従わなくても宿泊施設の提供をすることができるようになります。
特区民泊として規制緩和が図られた背景には、旅館業法が適用される場合のハードルが高すぎることから、近年の外国人観光客増加などによる宿泊ニーズにスムーズに対応しきれなかった事情があります。
特区民泊として認定されるためには、主に以下の要件をみたす必要があります。
- 宿泊施設が国家戦略特区内にあること
- ゲストの宿泊施設への滞在期間が(2泊)3日~(9泊)10日までで、自治体が定めた期間以上であること
- 1部屋の床面積が25㎡であること(自治体の判断で変更可能)
- 施設の使用方法に関する外国語の案内や緊急時の外国語による情報提供、その他の外国人観光客の滞在に必要なサービスが提供できること
- 滞在者名簿を備えること
- 周辺住民に対する適切な説明をすること
- 周辺住民からの苦情や問合せには適切・迅速な対応をすること
これらの要件をみたした上で、都道府県知事(保健所)の認定を受けられれば、旅館業法の適用を受けることなく民泊を営業することができるのです。
これだけ見ると特区民泊にはメリットしかないようにも思えますが、宿泊施設の提供日数として2泊3日以上の滞在が条件になっていたり、近隣住民とのトラブル防止措置が組み込まれているなど、旅館業法では定められていない規制があります。
特区民泊の認定手続きは確かに旅館業の営業許可よりは簡単ですが、その分短期宿泊客には対応しづらかったり、トラブル対応などの仕事が増えることもあらかじめ理解しておくことが必要です。
(6)民泊新法による規制緩和
みなさん、「民泊新法(住宅宿泊事業法)」ってご存知ですか?
2018年6月から施行される民泊新法によって、先ほど解説した国家戦略特区だけでなく、全国的に規制緩和されることになります。
具体的には、都道府県知事(例外あり)への届出をするだけで、旅館業法上の営業許可がなくても民泊営業ができることになりました。
「住宅」宿泊事業法という名前のとおり、民泊新法の対象は住宅施設を使って宿泊させる民泊です。
この他にも、特区民泊と違って1泊からでも宿泊施設の提供が可能だったり、営業日数の上限が定められるなど、民泊新法には様々なことが盛り込まれました。
これまで法的なリスクを心配して民泊に手を出していなかったホストも、民泊新法の施工によって、届出さえすれば合法的に民泊を運営することができるようになるため、自宅で民泊を始めるホストがかなり増えることが予想されます。
もっとも、届出だけで営業ができるのは「年間180日まで」という制限があります。そのため、365日民泊を稼働させたい場合には、今までどおり「旅館業法上の営業許可」を申請しなければならず、面倒な手続きをクリアする必要があります。
(7)他の法律規制
ここまで民泊を規制する旅館業法・民泊条例・民泊新法についてみてきましたが、ホストが民泊を始める場合にはこの他にも気を付けなければならないことがあります。
特に、
- 所有するマンションの一室を宿泊施設として提供する場合
- 借りているマンションやアパートの一室を宿泊施設として提供する場合
- 消防法や建築基準法が適用される場合
には、それぞれルールを守らないと管理規約や契約内容・法律に違反してしまう可能性があるのです。
以下で順番にみていきましょう。
①所有マンションの場合
自分が所有しているマンションの一室を使って民泊を始める場合、「そのマンションの管理規約で民泊が禁止されていないこと」が大前提となります。
「管理規約」とは、そのマンションに住んでいる住民みんなが守らなければならないルールのことをいいます。
「自分が買った家で何をしても自由じゃないか!」と思う方もいるかもしれませんが、マンションのように年齢や家族構成、職業などがバラバラの人たちが集まって生活している場合には、一定のルールを決めてみんなで守っていかないと気持ちよく生活できませんよね。
管理規約には必ず、専有部分(実際に住んでいる部屋のこと)をどのように使っていいかが書いてありますが、そこにはっきりと「専有部の民泊利用禁止」と書いてあれば、ホストはそこで民泊を始めることはできません。
一方、多くのマンションの管理規約のベースとなっている標準管理規約には、「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない」という条項があります。
この条項で民泊が禁止されているかというとそこはもう解釈の問題であって、民泊の可否についてはっきりとした判断基準がないためトラブルの原因となっています。
仮に管理規約に違反していると判断されれば、最悪の場合部屋の所有権を競売にかけられてしまう可能性もあります。
このような事態にならないよう、ホスト側は民泊を始める前に必ず管理規約を確認し、判断に困ったらマンション側に確認を取るようにしましょう。
また、マンション側としては、無用なトラブルを回避するためにも、民泊利用の可否についてはあらかじめ規約に明示しておくという方法があります。
②賃貸物件の場合
賃貸物件の場合でも、例えば分譲マンションの区分所有者から部屋を借りている場合には、賃借人についても区分所有者と同様にマンションの管理規約に従う必要があります。
一方、賃貸専用のマンションやアパートの場合には、使用についてのルールは基本的にオーナーと賃借人の間の直接の契約(賃貸借契約)によって決まります。
この賃貸借契約書にはたいてい「無断転貸禁止」という記載があります。
「無断転貸」とは、オーナーの許可なく第三者に部屋を貸すことをいいます。
そのため、借りている部屋で民泊を始めることはほぼほぼ不可能・・・ということになってしまいます。
また、賃貸借契約書に転貸について具体的な記載がない場合でも、民法で無断転貸が禁止されているため、記載がないからと言って転貸可能となるわけではありません。
要するに、「転貸しても良いですよ」とはっきり書かれていない限りは、転貸は違法となります。。
ただ、現実的には無断転貸禁止の条項を無視して民泊を運営しているホストがかなり多いようです。
仮に契約違反がオーナーにバレると、最悪の場合強制的に契約解除をさせられ、退去しなければならなくなるというリスクがあります。
最近では民泊許可物件を専門に紹介する不動産仲介サイトもあるようなので、賃貸物件で民泊を始める場合には、始めから民泊許可物件を借りるなどの工夫が必要になります。
転貸禁止としているオーナーから許可をもらうのはなかなか大変だと思うので、このようなサイトをうまく利用するのがポイントです。
③消防法や建築基準法が適用される場合
消防法上は、民泊についても、ホテルや旅館と同じ消防設備基準が求められます。
消防法については、人の命にかかわることなので規制緩和は無いようです。
どのような場合に規制がかかるのかというと、
【戸建て住宅の場合】
- 民泊に使用する部分が建物全体の半分以上ある場合
- 民泊に使用する部分が50㎡以上ある場合
この2つのうちどちらかにあてはまると、消防法上はホテルや旅館と同じように規制の対象となります。
民泊に使用する部分が上の要件にあてはまらないような小さい場合には、消防法の規制対象とはなりません。
【マンションやアパートの場合】
マンションやアパートのような共同住宅では、自分の部屋の一部のみをゲストに貸す、というスタイルは現状認められていないため、部屋の全てが民泊施設とみなされ消防法の規制対象となります。
規制の対象となった民泊施設には、消火器や誘導灯、火災報知機などの設置が義務付けられます。
また、建築基準法上、民泊を始めるときは建物の用途について以下のように変更する必要があります。
- 旅館業として運営する場合⇒「旅館・ホテル」
- 特区民泊として運営する場合⇒「住宅・共同住宅」
(7)小括
ホストとして民泊を始めるにあたっての注意点や法律の規制をみてきましたが、思ったより細かいルールがたくさんあって驚いた方も多いのではないでしょうか?
無許可の違法民泊を運営しているホストも多いのが現状ですが、今後、新たな法整備や違反した場合の罰則強化も予想されます。
民泊を始める場合には、どの法律の規制にかかるのかをきちんと把握した上で、合法的に運営をしていくことが重要です。
4 民泊仲介サイト運営者への法律上の規制

これまでは、「ホスト」が民泊を運営する場合にかかわる法律を解説してきました。
他方で、Airbnbなどの民泊を仲介するサイト運営者も規制の対象となるのでしょうか?
以下で確認していきましょう。
(1)民泊サービスの取次行為
ホストが民泊を始める場合、現在の法律では特区民泊以外は旅館業法上の営業許可をとる必要があることはすでに説明したとおりです。
では、Airbnbなどに代表される民泊仲介サイト運営者も同じように営業許可をとらなければならないのでしょうか。
これについては、サイトはあくまでもゲストとホストを繋ぐ役割をしているにすぎず、実際に自ら物件を貸し出しているわけではないため、サイト運営者自身は旅館業を営んでいるとはいえない、と考えられます。
そのため、Airbnbなどの仲介サイト運営者は、その意味では、旅館業法上の運営許可をとる必要はありません。
ただし、仲介サイトはその名のとおり、「ゲストとホストを繋ぐ役割」を果たしています。
この「ゲストとホストを繋いでいる」という部分については、貸出しているかどうかとは別の理由で、「旅行業法」という法律のの規制をうける可能性があります。
「旅行業法」とは、旅行の安全確保や、旅行業の公平を維持するための法律です。
旅行業法では、旅行者に対して「宿泊サービスを取り次ぐ行為」については「旅行業」にあたり、旅行業上の許可が必要になるとしています。
そのため、民泊仲介サイトが
- 宿泊サービスを
- 取り次いでいる
といえる場合には、その仲介サービスは「旅行業」にあたり、旅行業法上の許可が必要になってしまいます。
それでは以下で2つの要件について順番にみていきましょう。
①「宿泊サービス」について
ホストの運営する民泊のスタイルが旅館業であっても特区民泊であっても、その中身としてはゲストを民泊施設に宿泊させる「宿泊サービス」になります。
そのため、民泊仲介サイトは、「宿泊サービス」をマッチングしていることになり、①の要件にあてはまります。
②「取り次いでいる」について
「取り次ぎ」とは、他人の代わりに両者の間に立って契約など取引行為をすることをいいます。
民泊仲介サイトはあくまでもホストが提供する民泊施設の情報を掲載しているだけであって、宿泊についての契約はホストとゲスト間でなされることから、「取り次いでいる」というこはできません。
そのため、②の要件にはあてはまりません。
以上より、現段階では、Airbnbなどの民泊仲介サービスは「旅行業」にはあたらず、旅行業法上の許可は必要ありません。
(2)民泊新法
ただし、2018年6月に施行される民泊新法においては、現状の法律の解釈とは対照的に、Airbnbなどの民泊仲介サイト運営者は国からの登録を受けなければならない、と定められました。
そのため、2018年6月以降は、これまでのように、無許可でサイトを運営することができなくなります。
登録は5年ごとに更新され、その都度手数料9万円の登録免許税の支払いも義務付けられます。
無登録で仲介業務をした場合には、
- 最大1年以下の懲役
- 最大100万円の罰金
または
が科せられるリスクがあるため、必ず登録を済ませたうえでサイトの運営にあたることが必要です。
(3)小括
民泊仲介サイトについては、ホストに比べると現状そこまで細かいルールはありません。
ただし、民泊新法によって登録制になるなど、今後も民泊ビジネスの変化に応じて新たな規制が導入される可能性は大いにあります。
特に民泊新法では厳しい罰則規定が設けられているため、施行前に改めてその内容を確認しておくことをお勧めします。
5 まとめ
これまでの解説をまとめると以下のとおりです。
- 「民泊」とは、観光客などに個人の自宅や使っていない別荘・マンションなどを有料で貸し出すこと
- 民泊は、ホストとゲストが民泊仲介サイトを通じてやり取りをする仕組みとなっている
- ホストとゲストそれぞれにメリット、デメリットがある点に注意
- ホストへの規制は細かいルールがたくさんあるため、自分の運営する民泊にはどのような規制がかかるのかを把握することが重要
- 民泊仲介サイトへの規制は現段階ではほとんど無いが、民泊新法では新しい制度や罰則が規定されているため確認が必要
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。