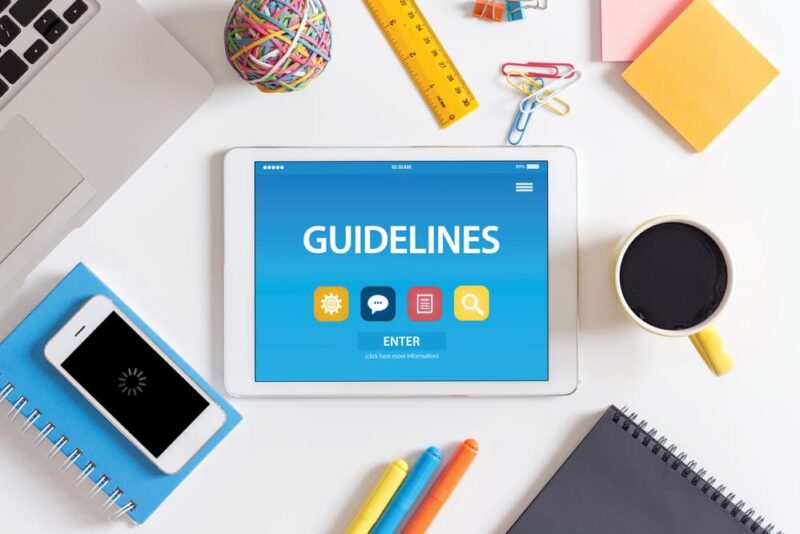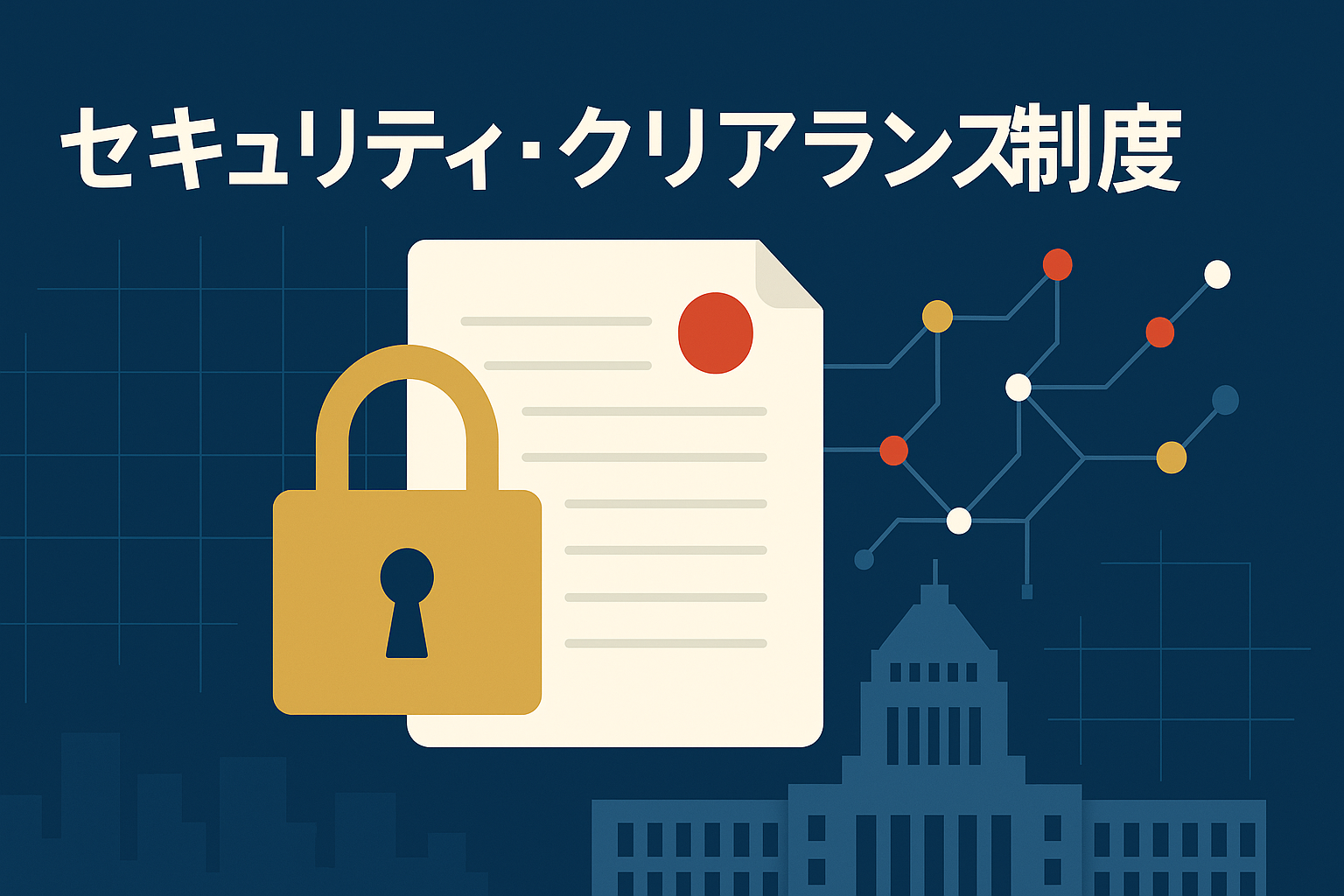名刺交換・問い合わせ対応だけで送っていい?特定電子メール法の「既存関係」の線引きと、特商法との関係、そして罰則まで

はじめに
営業現場では、名刺交換や問い合わせ対応を通じてメールアドレスを得る機会が日々あります。では、その関係性だけを根拠に、新商品やイベントの広告・宣伝メール(メルマガ/DM)を送ってよいのでしょうか。
答えは「ケースバイケース」です。
根拠法である特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(以下、特定電子メール法/“特電法”)は原則オプトインですが、限定的な例外も明文化されています。本稿ではその線引きを解説し、特定商取引法(通信販売の広告メール規制)との関係、俗称としての“迷惑メール防止法”の位置づけ、さらに罰則までを実務目線で整理します。
この記事を読むと分かること
-
広告・宣伝メールは「原則事前同意が必要」。
- 「名刺=書面同意」となりうるが、「何でも送ってOK」ではない。
-
問い合わせの返信に付随する軽い告知は可の場合あり。ただし継続配信には別途同意が必要。
-
SMS等のショートメッセージも規制対象になり得る。
-
「特定電子メール」に必ず記載すべきこと(送信者名、配信停止先など)。
- 通販メールは特商法の追加ルールも順守(オプトイン・表示・記録)。
-
罰則や行政処分の内容。
「メルマガを規制する法律は?2つの法律のポイントをわかりやすく解説」の記事も参考にしてみてください。
1. 似て非なる2つの枠組み
1-1. 「特定電子メール法」とは(通称“迷惑メール防止法”)
営利目的の広告・宣伝を行うための手段として送信される電子メールを規制し、短時間・多数配信による支障を防ぐ法律です。対象は送信者(営利団体・営業を営む個人)で、自社・他社の営業のための広告メールを含みます。SMS等も運用上の対象に含まれます(後掲)。
なお、世間で言う「迷惑メール防止法」はこの特定電子メール法の通称です(迷惑メール対策を所管・支援する機関の解説も同趣旨)。
また、SMS(電話番号宛のショートメッセージ)も迷惑メール相談センターの収集・周知対象である点に注意が必要です。広告・宣伝目的か否かの判断が基本です。
参照:迷惑メール相談センター
1-2. 特定商取引法(通信販売の電子メール広告)
通信販売の広告メールに関しては、特定商取引法でもオプトイン規制や記録保存義務(3年)が課されます。特商法の適用場面では特電法と別建てで遵守が必要です。
2. 規制対象と大原則(オプトイン)
2-1. 「特定電子メール」の定義
自社または他人の営業について広告・宣伝を行う手段として送るメールが該当します(送信者=営利目的の団体・営業を営む個人)。他人の営業(広告主が別)のために送る場合も対象です。
2-2. 原則:同意(オプトイン)のない送信は禁止
特定電子メールの送信は、原則として受信者の事前同意がなければ禁止。これが特電法の根幹です。
2-3. 例外:「既存関係」で許される場合がある
ただし、次の限定された例外は同意なしでも送信可とされています。
-
(1) 事前の同意通知をした者(オプトイン)
-
(2) 自己のメールアドレスを送信者等に「通知」した者(方法は原則書面=名刺等。施行規則が「書面による通知」を明記)
-
(3) 当該広告・宣伝に係る営業の取引関係にある者
-
(4) 自己のメールアドレスを(営業に関して)公表している団体・営業を営む個人
ただし、乱用は不可で、オプトアウト意思(配信停止)に反して送信してはなりません。
ポイント:「名刺交換=常に送信可」ではない
(2)は“通知”の事実が前提で、社会通念上相当な範囲での利用が前提。名刺をもらったからと言って無制限・恒常的な宣伝配信まで当然に許容されるわけではありません。不適切な継続配信は措置命令や違反認定のリスクがあります。特定電子メールの送信等に関するガイドライン
2-4. 「問い合わせ対応メール」の扱い
配達日時の確認など“非広告目的”の返信に付随的な広告が含まれる程度は、オプトアウト通知後でも例外的に可とされる場面があります(法3条3項ただし書)。ただし、その後の継続的な広告配信は別途オプトインが必要です。
3. 同意の取り方と証跡の残し方
3-1. 適正な同意取得の実務
代表例は以下のとおり(ガイドライン参照)。
-
チェックボックスによる明示同意(デフォルトオフ推奨、小さな文字・目立たない表示は不可)
-
同意相手方(送信者または送信委託者)が誰かを明確に表示
-
ダブルオプトインは推奨(本人性・意思確認の強化)
これらは「通常の人なら広告配信を認識できる表示」を求める趣旨です。
特定電子メールの送信等に関するガイドライン
※ ダブルオプトインとは、本人意思確認のため、一度広告を含まない電子メールを送信する+受信者の操作(「送信に同意する場合にはここをクリック」など)を経る方法です。
3-2. 同意記録の保存期間(特電法/特商法の二重基準)
-
特電法:同意を証する記録は、当該アドレスへの送信をしないこととなった日からおおむね1か月の保存が原則(措置命令を受けた場合は原則1年等、ガイドラインで詳細整理)。
-
特商法(通信販売):最後に広告メールを送信した日から3年の保存が必要。通販事業者は両法を併用して判断し、より長い保存を担保する運用が安全です。
改正特定商取引法における「電子メール広告規制(オプトイン規制)」のポイント
実装メモ:フォーム画面の版管理、同意文言、タイムスタンプ、IP・UA、配信停止処理のログ(誰が・いつ・どの経路で停止したか)まで可視化しておきましょう。
4. 送信者に課される義務(同意があっても必要)
4-1. 表示義務(メール本文等に必須)
以下の項目を受信者が認識しやすい形で表示する義務があります。
-
送信者の氏名/名称
-
受信拒否(配信停止)の通知先:メールアドレス又はURL
-
受信拒否ができる旨の明記(通知先の直前又は直後に)
-
住所(任意の場所)
-
苦情・問合せ先(電話・メール・URLのいずれか、任意の場所)
文言だけでなく導線の分かりやすさが重視されます。
4-2. 送信者情報の偽装禁止
送信に用いたメールアドレスや送信設備の識別符号等の送信者情報を偽ってはならないと明記。なりすまし・ドメイン偽装等は刑事罰の対象にもなり得ます。
4-3. 架空アドレス宛送信の禁止
自動生成等で作成した架空アドレス宛に多数送信する行為は禁止。検証目的送信の名目でもリスクが高い領域です。
4-4. オプトアウト(配信停止)への即時対応
停止通知を受けた後に送ることは原則違法。全配信基盤で即時反映できる体制(外部配信業者・MAツールとの連携を含む)が必須です。
5. 名刺・問い合わせはどこまで許されるか(実務の線引き)
5-1. 名刺交換=「通知(書面)」の一形態だが、範囲は限定
施行規則2条は、特電法3条1項2号の「通知方法」を「書面」と定義しています。つまり、名刺などの書面により自己の電子メールアドレスを通知した場合には、電子メールの送信が行われることについて予測可能性があるため、名刺の交付=特定電子メール送付の同意があると考えられるのです。しかし、通知の事実があっても、内容・頻度・継続性が社会通念上相当な範囲を超えると問題化します。配信停止意思が示されれば直ちに停止が必要です。
5-2. 問い合わせ対応は「付随広告」なら可でも、継続配信は要同意
FAQ返信や納期連絡といった非広告目的のメールに付随的に広告が含まれる程度は例外が成立し得ますが、メルマガ登録扱いとするには別途の明示同意が必要です。
5-3. 通販(BtoC)メールは特商法も適用:3年保存と表示・同意要件
通信販売の広告メールは特商法の規律がかかります。請求・承諾を受けた記録の3年保存など、特電法とは別建ての実装が必要です。
6. 違反時の行政府対応と罰則
6-1. 措置命令(業務改善)
総務大臣・内閣総理大臣は、オプトイン違反/表示義務違反/偽装送信/架空アドレス送信等が認められ、送受信上の支障防止に必要な場合、送信方法の改善などを命令できます。公表リスクも含め、企業のレピュテーションに直結します。
6-2. 特定電子メール法の刑事罰
-
業務停止命令違反:1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(併科あり)〔33条〕
-
送信者情報の偽装(法5条)や措置命令違反(法7条):1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金〔34条〕
-
措置命令違反等:100万円以下の罰金
-
虚偽届出・記載義務違反等:30万円以下の罰金
-
両罰規定(法37条):法人は3,000万円以下の罰金(法34条違反の場合)
――いずれも条文に基づく上限額です。最新条文にて確認してください。
6-3. 特商法側のリスク
特商法の電子メール広告規制でも、請求・承諾のない広告送信の禁止、記録保存3年、違反時の行政処分・刑事罰が設けられています(第72条・詳細は経産省・消費者庁資料の「電子メール広告規制(オプトイン)」ポイントを参照)。通信販売事業者は両法の同時順守が前提です。
7. 保存して使えるミニマムチェックリスト
-
取得画面:広告配信の事実/送信者(又は送信委託者)を明瞭表示。デフォルトオフ・二重同意推奨。
-
証跡:同意画面の版管理(スクリーンショット等)、取得日時・IP/UA、同意相手方、オプトアウト対応ログを保持。
-
保存期間:
-
特電法=送信をしないこととなった日から原則1か月(命令時は原則1年)。
-
特商法(通販)=最後の広告送信日から3年。通販なら3年保管を基本に。
-
-
表示義務:本文に氏名/名称、受信拒否先(メール or URL)、“受信拒否ができる旨”、任意で住所と苦情窓口。短縮URLのみや視認困難な色・サイズは避ける。
-
配信停止:全基盤で即時反映(MA・配信事業者含む)。停止後送信は原則違法扱いです。
-
名刺運用:名刺は“通知(書面)”に該当し得るが、あらゆる宣伝の包括同意ではない。目的適合・頻度・オプトアウトを厳格に。
8. まとめ:「既存関係」ではなく、明確な同意を中核に
-
原則はオプトイン。名刺や取引関係、公表アドレスといった法定例外はあるものの、濫用は不可という認識が重要です。オプトアウトを尊重し、過度・継続は避けましょう。
-
通販メールは特商法の3年保存等の別規制。自社の取引形態に応じて両法の要件を同時に満たす設計が必要です。
-
違反のコストは高い(措置命令、刑事罰、法人3,000万円以下の罰金、公表リスク等)。表記・同意・停止の三点を疎かにしない運用が、法令順守とレピュテーション管理の土台となります。
免責:本稿は一般的解説であり、特定事案の法的助言ではありません。実装・運用に当たっては、最新の条文・官公庁ガイドライン・社内規程と照合してください。
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。