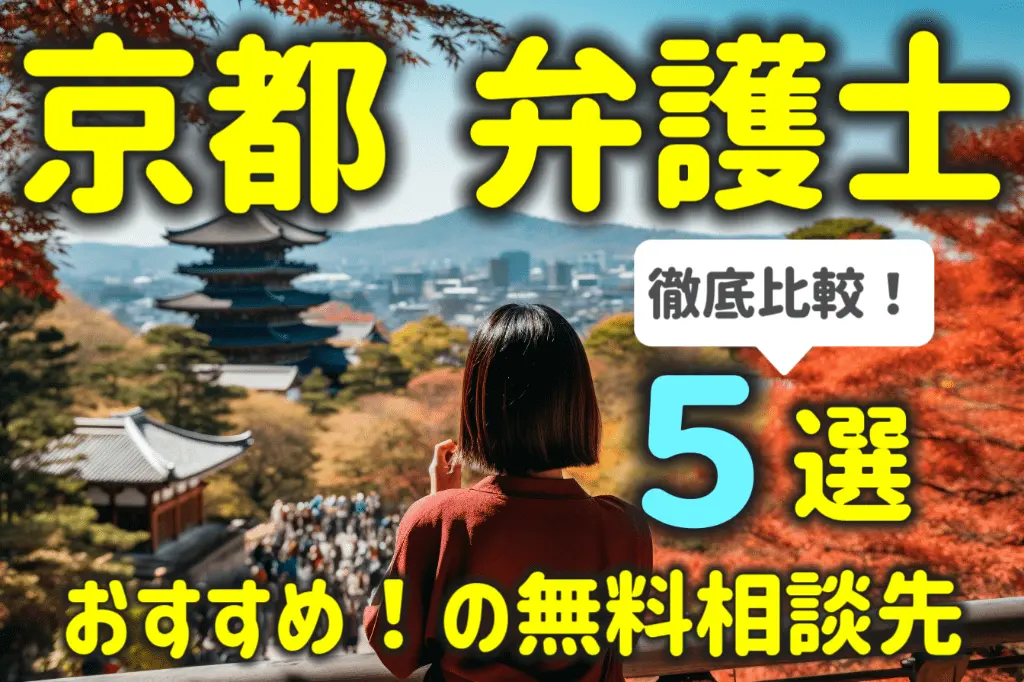結局どうだった?フリーランス法——施行から1年の「勧告・指導」総ざらいと、基本の再確認
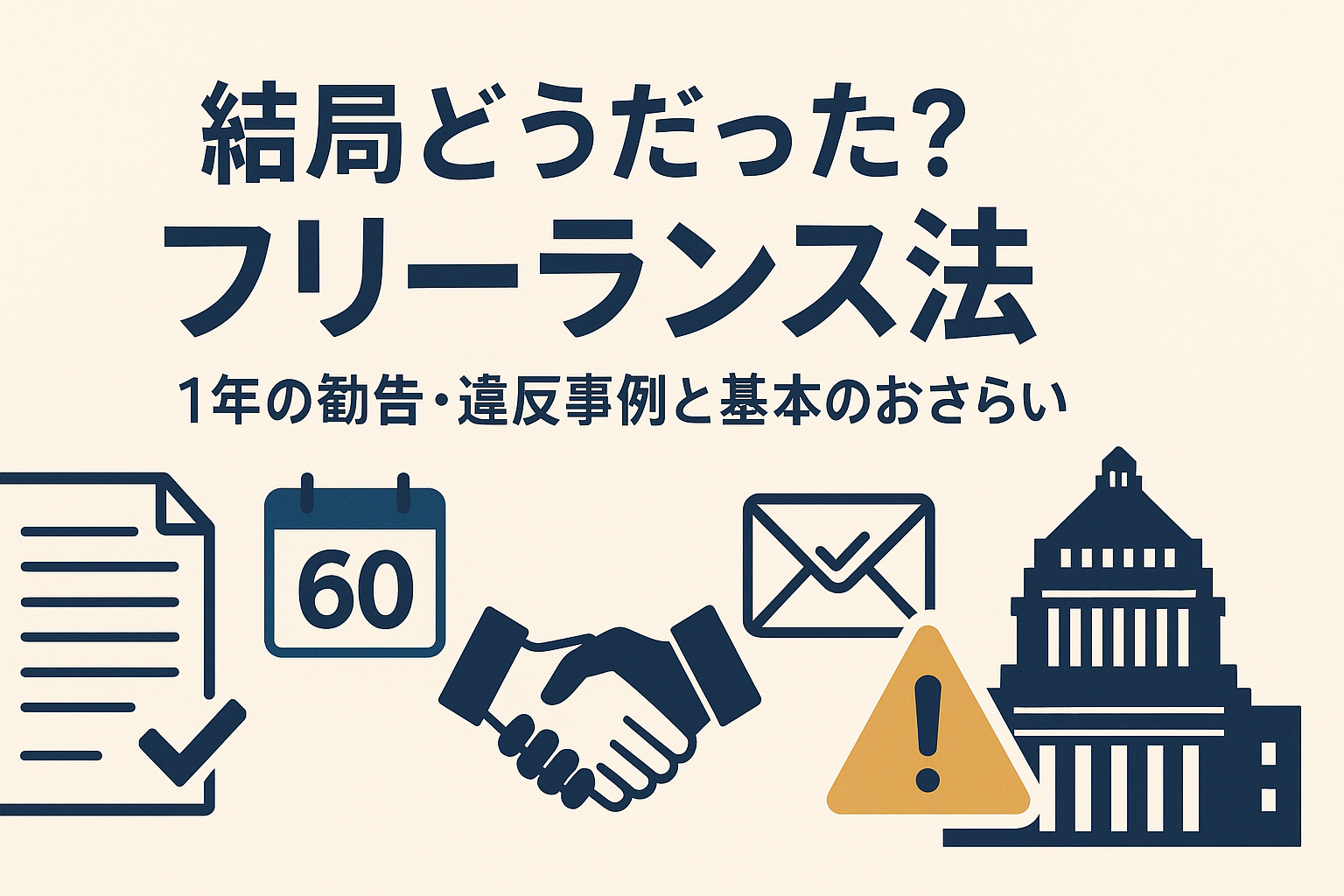
はじめに
2024年11月1日に施行された「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(通称:フリーランス法)。
この1年、公正取引委員会(以下、公取委)や関係省庁はどんな運用をしたのか。実際に何が違反とされ、どんな是正が求められたのか。
まずは主要トピックをざっと俯瞰し、そのうえで実務の基本をおさらいします。
この1年で何が起きた?(実例でざっくり把握)
1) 初の「勧告」:出版2社(明示義務・60日内支払)
2025年6月、小学館と光文社に対し、(1)発注時の取引条件の明示(法3条1項)の不備、(2)期日における報酬支払義務(法4条5項)違反が認められ、勧告が出ました。
小学館は月刊・週刊誌の原稿・写真・イラスト・ヘアメイク等の委託で明示を怠り、期日内支払も不履行。光文社も同趣旨で、取締役会決議で是正方針の確認などを求められました。公取委の公式リリース・企業側のお知らせで詳細が確認できます。
https://www.jftc.go.jp/houdou/250617_fl_syogakukan.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/250617_fl_kobunsya.html
2) 島村楽器:無償体験レッスンの不当な経済上の利益の提供要請
2025年6月、公取委は島村楽器に対して、(1)明示義務、(2)60日ルール違反に加え、1か月超の委託で体験レッスンを無償実施させた行為が法5条2項1号(不当な経済上の利益の提供要請)に当たるとして勧告。無償分の対価支払い・社内体制整備・取引先周知・報告等を求めました。「翌々月10日払」等の期日設計にも要注意です。
https://www.jftc.go.jp/houdou/250625_fl_shimamuragakki.html
3) 九州東通:テレビ番組制作分野での明示・支払期日
2025年9月、九州東通に対し、映像制作(撮影・音声・出演等)の委託について、(1)明示義務、(2)支払期日未設定・期日内不払いが認定され、勧告。取締役会での是正確認、社内研修、取引先通知等を指示。メディア制作系の委託も典型的な適用領域になっています。
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/sep/250926_flkyusyu_kyusyutotsu.html
4) 業界横断の「指導」:ゲーム・アニメ・リラクゼーション・フィットネス
2025年3月、公取委は45名への指導を公表。オンラインゲームのイラスト、アニメ原画・音響、整体施術、グループレッスン、SNS動画投稿など、発注直後に明示をしていない/期日を特定していない(例:「翌月10日まで」)/60日超の期日設定/「直ちに」明示していない等の典型パターンが示されました。支払い期日については下請法(2026年1月以降は「取適法」)と同様、「納品の日から60日以内の支払日を定める」必要があり、そもそも支払日を明示していない場合は納品日から支払い遅延扱いになります。「請求書到着の翌月末払」のような社内ルールは納品日や役務提供日次第で違法化し得る点を示す実例です。 また、小売業でよくある「消化仕入取引」についても支払い日の定めのない発注とみなされる可能性が高いです。
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/mar/250328_FL.html
5) 調査・周知の強化と「自発的申出」
2025年2月には、関係3省庁のオンライン調査(問題事例の多い業種を中心に発注者3万人対象)が告知され、下請法調査に近い厳格運用が示唆されました。また、公取委は下請法と同様に「自発的申出」によって勧告・社名公表を回避し得る運用を示しています(公取委会見・考え方資料参照)。
まとめると、この1年で可視化された「つまずきポイント」はほぼ共通です。
(A) 取引条件の「直ちに」明示(9項目)、(B) 60日以内のできる限り短い支払期日、(C) 1か月超の委託での不当な無償作業の強要NG。
とりわけ「社内慣行の支払サイト」と「口頭・チャットのみの発注」が、そのままでは法要件を満たさない典型例として浮き彫りになりました。
今さら聞けない「基本」のおさらい(公式ガイドライン準拠)
適用対象(誰とどの取引が対象?)
特定受託事業者=従業員を使用しない個人、または一人社長法人等。
特定業務委託事業者=上記へ業務を委託する事業者(従業員を使用する個人・法人等)。
対象の委託=物品製造、情報成果物の作成、役務の提供(B2B)。雇用契約・消費者相手取引は除外。
労働関係法令・独禁法・下請法との関係は、政府ガイドライン(2021策定、2024改定)で整理。自社のスキームがどの法領域に入るかを先にマッピング。
3条:取引条件の明示(発注直後に電磁的方法等で)
必須の9項目(当事者情報、委託日、給付内容、受領・提供期日、場所、検査期日、報酬額、支払期日、非現金支払の条件)を書面または電磁的方法(メール・DM等)で直ちに明示。未定がある場合は、未定の理由と確定予定時期を明示し、確定後直ちに補充通知。本年の勧告・指導の最多指摘ポイントです。
4条:報酬の支払期日(原則60日以内)
受領(検査の有無を問わず)から60日以内のできる限り短い期間で期日を定め、その期日までに支払う。未合意なら受領日が期日、60日超の合意は無効で60日目の前日が期日に。再委託の例外では、元請の支払期日から30日以内で設定可・前払金配慮義務あり。「請求月の翌々月10日」等の横出し慣行は特に要注意。
5条:禁止行為(1か月超継続委託が軸)
受領拒否/報酬減額/返品/買いたたき/購入・利用強制 等の1項類型。
不当な経済上の利益の提供要請/不当なやり直し・仕様変更 等の2項類型。
今年は「無償体験レッスンの強要」が不当な経済上の利益として初めて正面から問題視され、実費・相当対価の精算まで踏み込んだ是正が示されました。
12~16条:募集表示の適正化/ハラ防止体制/育児介護配慮/30日前予告と理由開示
募集表示は虚偽・誤認・旧情報の放置NG。
ハラスメント対策は方針・相談体制・事後対応の三点セットを整備。
育児・介護等の配慮は申出ベースでの実現可能性の検討・説明義務。
中途解除・不更新は少なくとも30日前の予告と、請求があれば理由開示。
これらは独禁法・下請法の「優越的地位の濫用」領域とも重なり得るため、横断統制が必要です。
ガイドラインの条文対応表で自社ルールを点検しましょう。
実務でやること(最短To-Do)
発注テンプレの刷新:9項目を網羅し、未定時の補足明示フローを定型化(発注書・電磁明示ログを残す)。
支払サイトの見直し:受領基準の期日計算に変更。固定の翌々月払いは60日上限と衝突しやすい。
無償作業の全面棚卸し:体験・サンプル・やり直し無償をやめ、追加指示=追加対価を契約書に明記。
長期委託の解除運用:30日前予告・理由開示の実装(テンプレ通知・社内手順)。
相談窓口の周知:社内・取引先向けにハラ相談窓口や**外部申出窓口(オンライン)**を提示。
「自発的申出」オプションの社内方針:重めの違反兆候を把握したら、勧告・社名公表の回避も視野に自発的申出の要否を検討(法的助言前提)。
よくある落とし穴(今年の指摘から逆算)
「請求書受領月の翌月末払い」運用:受領基準の60日に合っていなければアウト。
「翌月10日まで」等のあいまい期日:具体的な日付で特定を。
口頭・チャット発注のみ:電磁明示(メール等)での直ちに通知が必要。
体験・お試し・テスト無償:継続委託かつ発注者の便益に該当しうる場合、有償評価が原則。
公式の相談・申出窓口
フリーランス法 申出オンライン窓口(公取委・中小企業庁・厚労省 共同)
公取委 特設ページ/ガイドライン(適用関係の整理・周知資料)
おわりに
この1年の運用は、「まずは基本の徹底」というメッセージが明確でした。
直ちに明示、60日内支払、無償強要の禁止——ここを外さなければ、多くのリスクは避けられます。
逆に、社内慣行のままだと、社名公表を伴う勧告につながり得ることが、実例ではっきり示されました。
テンプレ・ワークフロー・支払サイトの三点が特に重要だったという結果だったと感じます。
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。