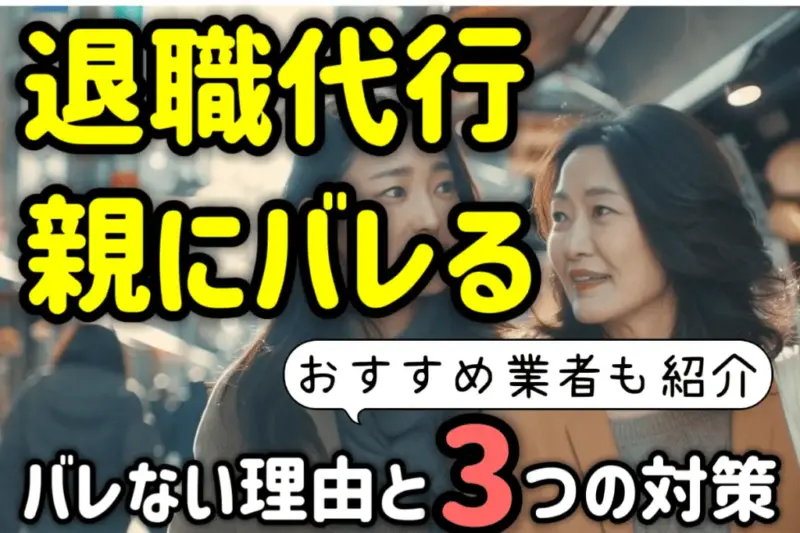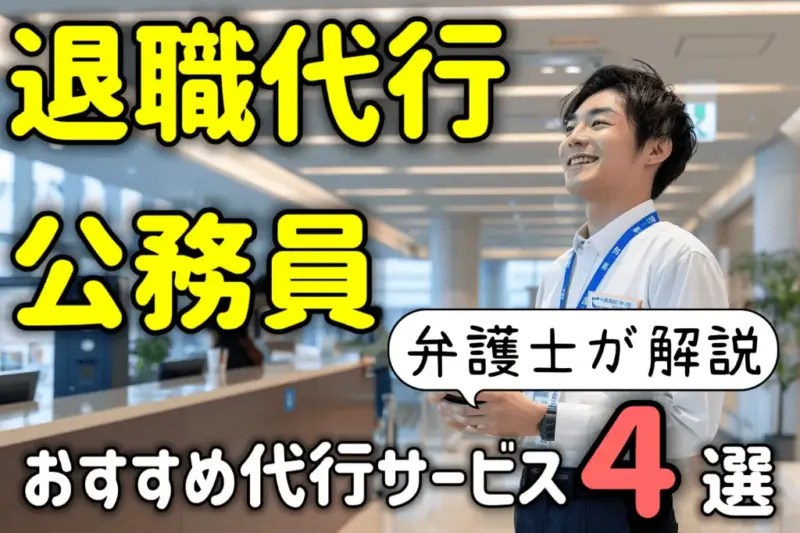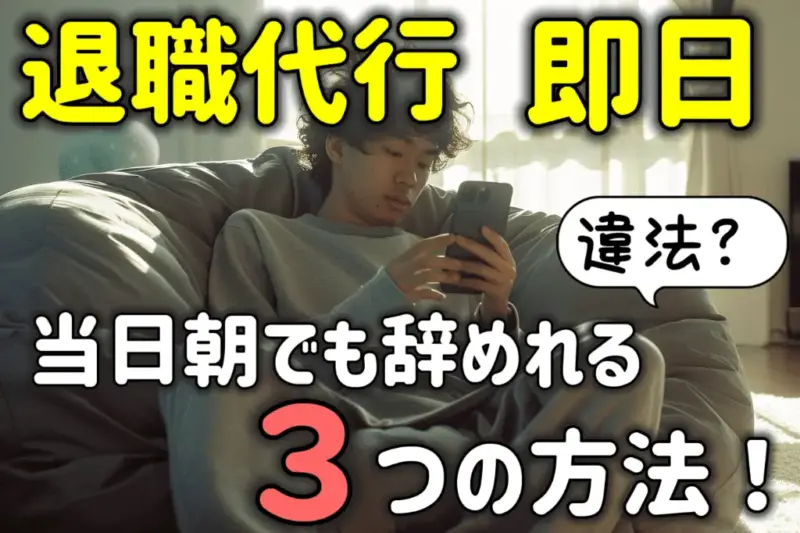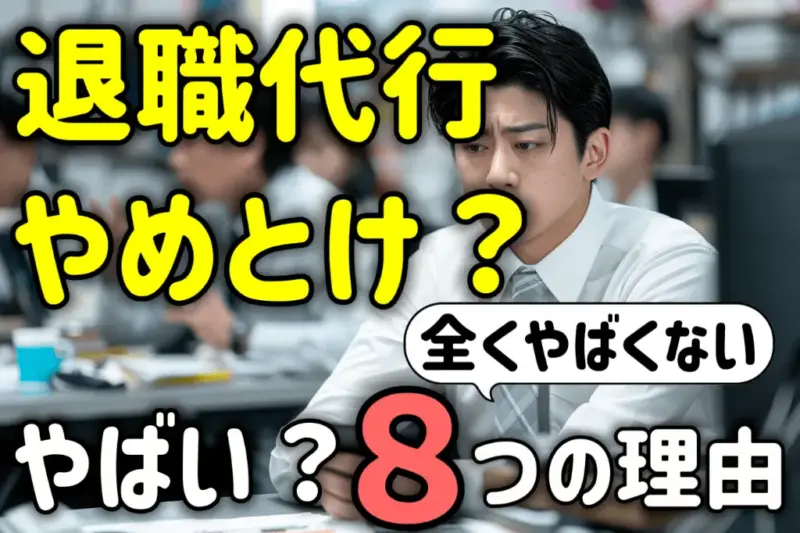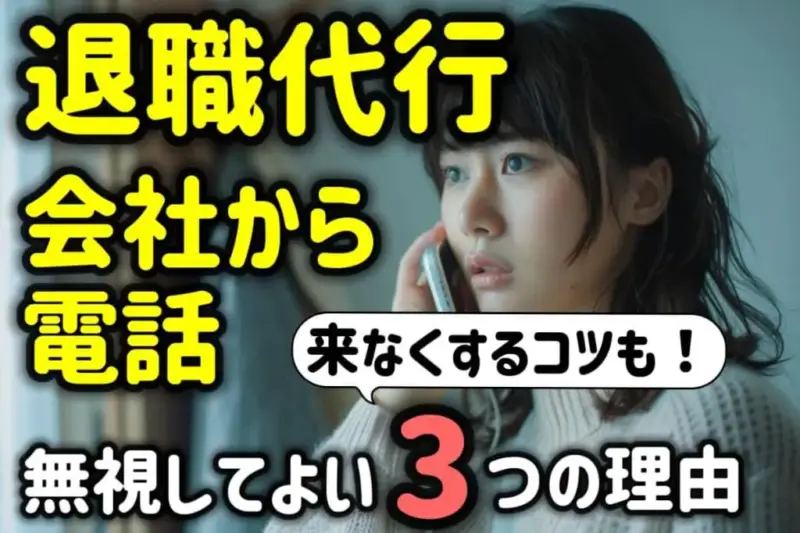退職届が受理されないでも退職はできる!2つの対処法を弁護士が解説
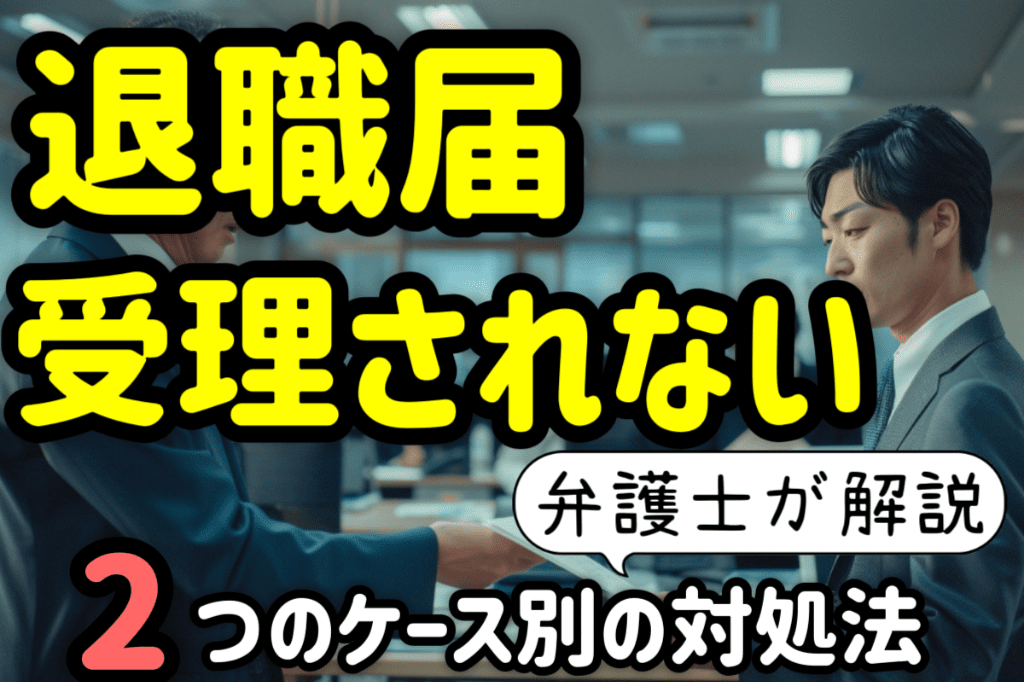
退職届を出したけど、上司から無視や拒否をされて受理されなかった方。
「退職届を拒否されたらどうしたらいい?」「退職届を受理されなくても退職できる?」といった疑問や不安があるでしょう。
結論を言うと、退職届が受理されなくても、法律上は「必ず退職できる」ことになっているのでご安心ください。
ただし、退職届が受理された上での退職のほうが後々のトラブルは避けられますから、受理されるに越したことはありません。
そこで本記事では、退職届が受理されない場合の2つのケース別に、受理させるための対処法を解説し、ベストな退職届の「書き方」も説明します。
会社が悪質で「辞めさせる気がない」場合についても、対抗できる手段と相談先を紹介しているので、困っている方はぜひ参考にしてください。
【この記事でわかること】
- 退職届を受理されないときは2つのケースに応じて対処法を考えよう
- 【ケース1】何も相談せずにいきなり退職届を出した
- ⇒直属の上司に改めて「相談・交渉」する
- 【ケース2】相談しようと試みたがどうにもならず退職届を出した
- ⇒「人事に相談」したり「内容証明郵便」を出すなどの対処
- 会社が退職届を受理しなくても、「退職の意思」を明確に会社に示していれば、必ず2週間後に退職(=会社との労働契約を解除)できる
- 退職届をきちんと作成して「退職の意思を会社に伝えた」という証明を残すことが大切
- 交渉してもなお上司が退職届を無視・拒否してくる場合は、法的な根拠にもとづいて確実に退職を認めさせてくれる「弁護士」への依頼が最もおすすめ
なお、「会社を辞めさせてもらえない」状況については以下の記事でも詳しく解説しているため、あわせて参考にしてください。
[banner id=”16503″ size=”l”] [articleIndex]1.退職届を受理されない場合はどうすればいい?2つのケースごとの対処法
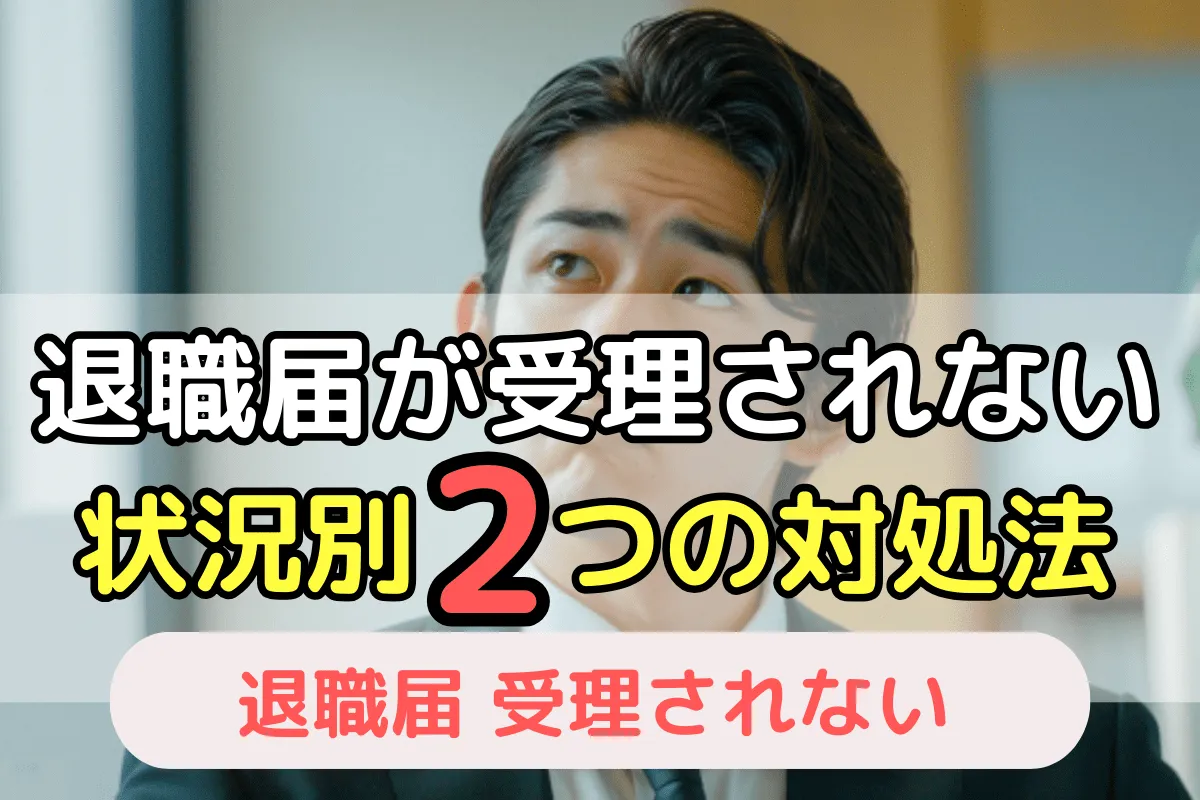
あなたが退職届を出したのに受理されなかった場合、「退職届を出す前に、上司に退職について相談したか」によって今後取るべき対応が変わってきます。
まずは、あなたが以下のどちらのケースであるかを確認してください。
- 何も相談せずに、いきなり退職届を出した
- 相談しようと試みたがうまくいかず、退職届を出した

1)何も話し合わずにいきなり退職届を出した場合
上司に何も相談せず、いきなり退職届を出して受理されなかったケースでは、まず退職について「上司に相談・交渉」しましょう。
これは、いきなり退職届を出した理由が、ただ「会社に退職の意思を伝えよう」とか、「早く退職したいから手続きがすぐ済むように」という意図であった場合です。
ちなみにこの場合は、退職届よりもむしろ「退職願」を出すのが一般的です。
退職届は、基本「会社と相談の上、退職日が確定してから」出します。
退職届には「◯月◯日に退職します」と退職日を明記しますが、会社も人手が足りないなどの事情があるので、いきなりこの日に退職すると言われてもすぐにOKと言えないこともあるからです。
会社と退職についてきちんと合意を取ってからなら、すんなり退職届を受け取ってもらえる可能性が高いので、まずは上司に「相談・交渉」してみましょう(⇒この手順について詳しくは3章で解説)。
ただし、「上司がパワハラ気味の人で、とても相談できない」といった事情から退職届をいきなり出していた場合は、直接交渉は難しいかもしれません。
その場合は社内の人事部門や弁護士の「退職代行サービス」などに相談してみてください(⇒こちらは4章で解説)。
2)事前に相談したが無視・拒否されて退職届を出した場合
退職について話そうとしたのに上司から無視・拒否されるなどして話が進まず、退職の話を動かすためにやむなく退職届を出すケースもあります。
例えば、以下のようなケースです。
- 退職について話そうとしたが全く取り合ってもらえない
- 「また今度話し合おう」と言われたが何度促してもその機会を作ってもらえない
- 退職の日程を話し合おうとしても、上司から一方的に「最低半年はこのまま働いて」「有給消化はダメ」など要求されるばかりで交渉ができない
上司にこのような対応を取られ続けたら、退職届を出して状況を変えようとするのは仕方のないことです。
会社が辞めさせてくれず、退職届すら受理されないようなら、会社の人事に直接確認をとったり、弁護士に相談するなどの対処が必要になります。
このような対処法は4章で解説しているので、当てはまる方はリンクからジャンプして解説をご覧ください。
2.【まず押さえよう】退職届の「役割」と「書き方」とは?
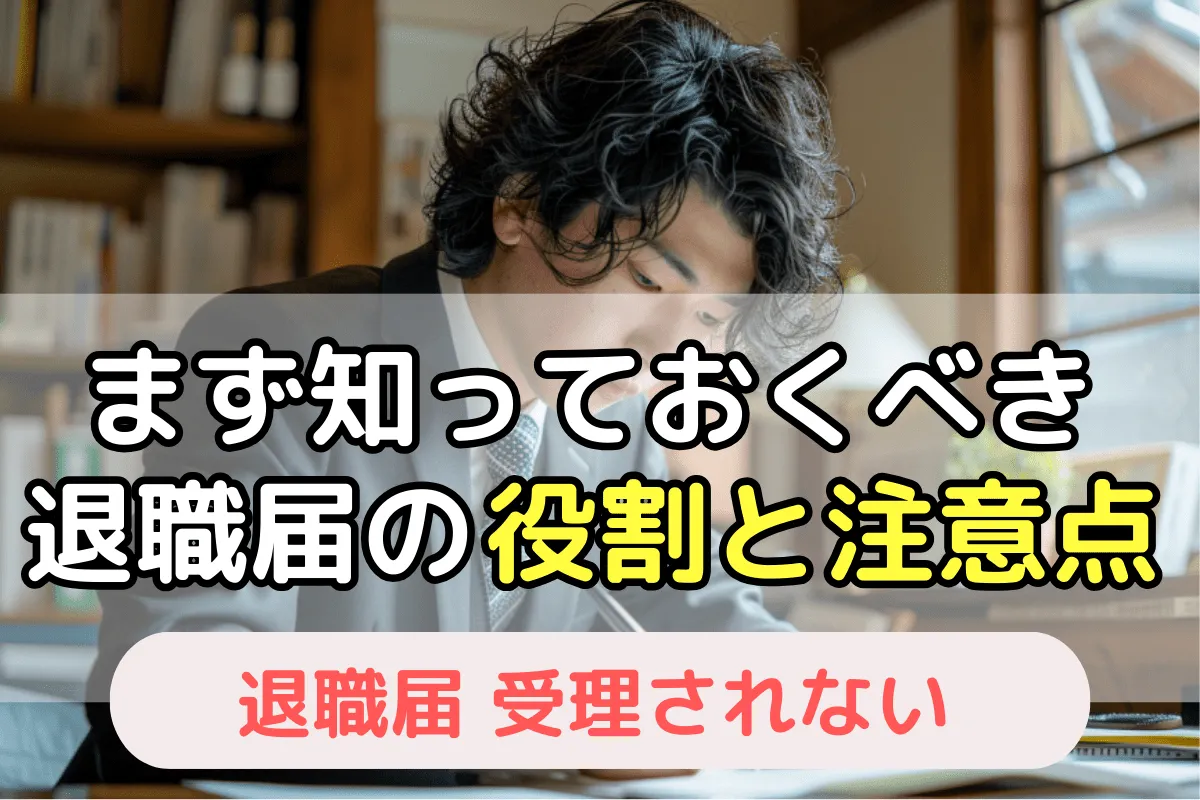
実は、退職届が受理されなくても、法律上では必ず2週間後に退職(=会社との労働契約を解除)できることになっています。
民法では、以下のように定められているからです。
雇用の期間に定めがない(=無期雇用)ときは、解約(=退職)の申入れから2週間が経過すると雇用契約が終了する
参考:民法第627条第1項
あなたが「退職の意思」を明確に会社に示していれば、会社側が退職を拒否しようが2週間後には退職できるということです。
このため退職届をきちんと作成して「退職の意思を会社に伝えた」という証明を残しておくことが大切です。
まず「退職届」の重要性と、実際にどのように書くのか「書き方」を確認しておきましょう。
ちなみに「退職願」もあり混同されがちですが、この2つは意味合いも提出タイミングも違うことをおさえておきましょう。

退職届が「この日に絶対退職します」と伝えるものだとすると、退職願は「この日に退職したいのですが、どうでしょうか」と伺いを立てるものです。
一般的には、「退職願」を出して上司と交渉し、退職日が確定したら「退職届」を出すという流れなので覚えておきましょう。
1)退職届は「絶対に退職する」と会社に伝える役割がある
退職届を出すと、「絶対に退職する」という意思を会社に伝えたことになります。
無期雇用(働く期間が決まっていない労働)なら、「退職の意思」を会社に伝えて2週間で退職できることは先に述べた通りです。
つまり、退職届が受理されなくても、退職届を出していたことが証明できれば、2週間後には確実に辞められるのです(※有期雇用の場合は認められない場合もあるので注意)。
実は、退職の意思を伝えるだけなら、口頭で告げるだけでも法的には問題ありません。
ですが、口頭では「言った」「言わない」と後からトラブルになる可能性もあるため、「退職届」で意思を形にして残しておくことが大切なのです。
なお、退職届を出したことを客観的に証明する方法として、「内容証明郵便」があります。
この方法を利用すれば、退職届を内容証明郵便で出す⇒会社に退職の連絡⇒退職日まで2週間出社しない⇒退職という形で実質的な即日退職ができるケースもあります。
2)退職届は撤回できないため「退職日」は慎重に判断する
注意すべき点として、退職届は「絶対にこの日に退職する」と決まっていない段階で出してはいけません。
退職届を一度出すと、会社との合意がない限りは基本的に撤回できないためです。
一方で、退職願なら会社に承認されるまでは撤回できるという話もありますが、会社に退職の意思を伝えている以上、退職届も退職願も基本的には撤回できないと考えておいた方が無難です。
これらを踏まえて、退職届や退職願に書く「退職日」は、後から変更できないものと思って書く必要があります。
特に有給休暇が残っており、消化してからの退職を検討している場合は、早々に「退職日」を決めてしまうことで消化しきれなくなるおそれがあるので慎重に判断しましょう。
3)退職届がスムーズに受理されるよう「会社規定の書き方」をする
退職届は会社と話し合ってから提出するのが基本なので、その話し合いの中で会社規定のフォーマットがあるか確認してください。
また、会社によって求められる様式が違うので、印鑑はどうするかなど細かい書き方についてもできれば確認してから作成することをおすすめします。
会社規定のフォーマットが特になければ、自分で1から準備するか、ぜひ以下のテンプレートをご活用ください。
以下は退職届の例文です。

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ①冒頭 | 「退職届」と書きます。 |
| ②私議 | 「わたくしごとではありますが…」という意味で、書き出しに使います。私事でもOK。 |
| ③退職の理由 | 転職や病気による退職など、自分の都合で退職するときは「一身上の都合」とだけ書けば大丈夫です。 |
| ④退職日 | 会社と退職日について合意がとれている場合を除き、基本的には2週間以上後の日付にします。 |
| ⑤提出日 | 退職届を提出する日を書きます。 |
| ⑥所属・氏名 | 氏名の箇所は手書きにします。 氏名まで印刷で対応する場合は、署名の後に押印します。 |
| ⑦宛先 | 会社の代表者の氏名を書きます。 「殿」ではなく「様」でもOK。 |
ちなみに退職届の用紙は、「白い無地」または「白い地に罫線が入っている」など、ビジネス向きのシンプルな用紙であれば何でも構いません。
コピー用紙に印刷するのでも、便箋に手書きするのでも大丈夫です。
また、退職届を作成する上で「印鑑」は必須ではなく、自分で退職届を1から作成する場合は特に必要ありません。
ただし、会社から押印を求められることもあるので、あらかじめ確認しておくと安心です。
必要だと言われたら、「認印」で指示された箇所に押印しましょう。
退職届を収める封筒は白い無地のものを使い、表に「退職届」、裏に「所属・氏名」を書きましょう。
[banner id=”16503″ size=”m”]3.退職届を円満に受け取ってもらうための5つの手順
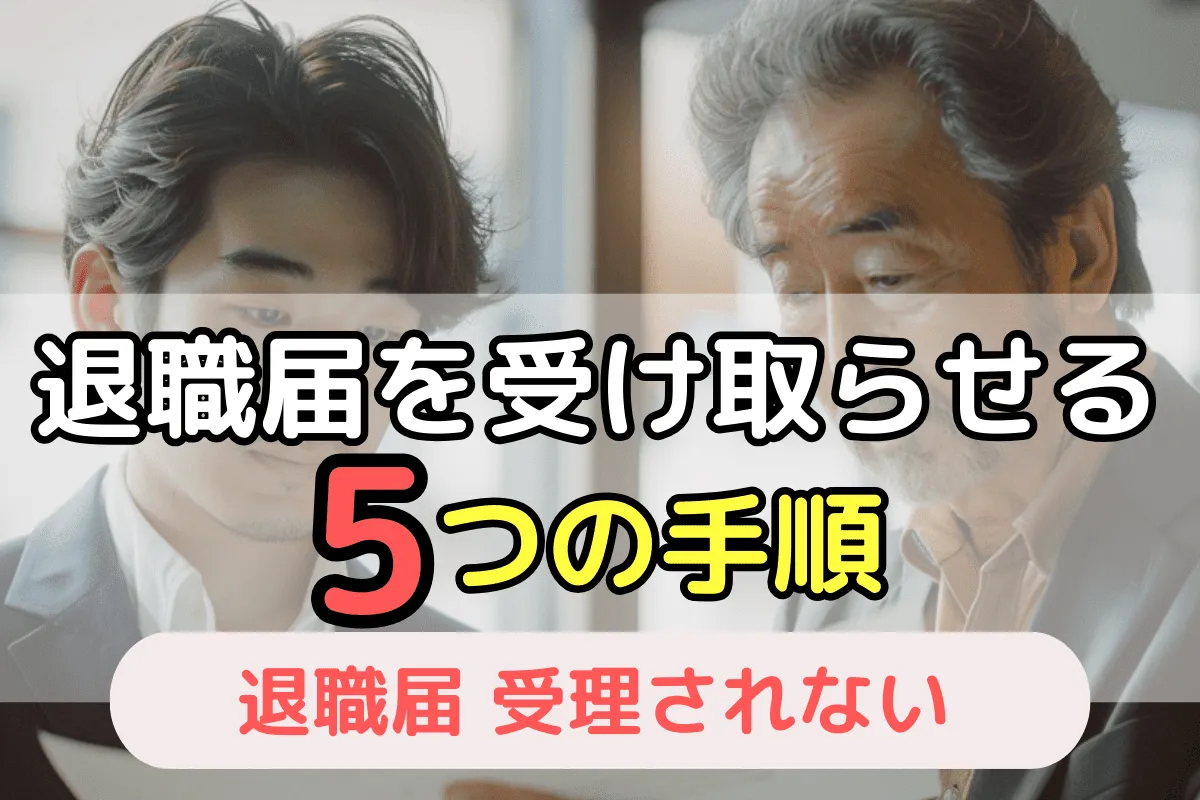
なるべく円満に退職届を受理してもらうためには、事前の相談・交渉が最も重要です。
1章の1で述べた「いきなり退職届を出した人」や、「これから退職届を出すつもりだが受理されないかもと不安な人」は、これから解説する手順を参考に行動してみてください。
1)「就業規則」確認のうえで退職時期を決める
まず「就業規則」で退職についての規程を確認しましょう。
引き継ぎや新しい人員の手配が必要になることを考慮して、就業規則に「退職するなら3か月前に申し出ること」といった退職時期のルールが設けられている場合があります。
こうしたルールについては、なるべく従った方が会社とトラブルにならずに済みます。
退職日をどうしても動かせない場合を除いて、基本的には就業規則にのっとって退職時期を考えてください。
ただし、6ヶ月前などあまりに長い期間が設定されているときは、そこまで規程通りにすべきかどうか、あなた自身の都合もふまえて検討した方がよいでしょう。
法律では2週間前に退職の意思を伝えれば十分で、就業規則に6ヶ月と書かれていようと本来は法律が優先されます。
円満退職を重視して就業規則に従うか、会社とさらに交渉が必要なものの早期の退職をとるかはあなたの判断です。
2)上司に退職について相談しスケジュールを調整する
就業規則に書かれていればその通りに、何も規程がなければ1ヶ月前など十分な余裕をもって上司に退職の意向を伝え、退職までのスケジュールを調整しましょう。
あまりに忙しすぎると話を先送りされる可能性があるので、なるべく繁忙期を避けたタイミングで退職について相談するようにします。
調整する内容としては、以下があります。
- 引き継ぎの期間:◯月◯日~◯日
- 有給消化の期間:◯月◯日~◯日
- 退職日・最終出勤日をいつにするか など
ちなみに「退職願(≒退職届)」を出す場合は、上司に退職を伝えるこのタイミングに出すようにしましょう。
退職時の有給消化の交渉については、以下の記事でも詳しく解説しています。
3)適切な「書き方」で退職届を作成する
2章で詳しく解説したように、会社規程のフォーマットがあればそれを使い、適切な「書き方」で退職届を作成します。
スムーズに受理されるように、不備がないよう十分に気を付けましょう。
ただし、退職届の様式などが規定と違うからといって、それを理由に会社が「退職を絶対に認めない」としてくるのは不当です。
書き方に間違っている部分があれば、一般的な会社ならきちんと指示があるはずなので、「提出日」「退職日」以外はそこまで神経質にならなくても大丈夫です。
4)「退職届」を直属の上司に提出する
作成した退職届を直属の上司に提出し、確認してもらいます。
これまで解説してきた手順通りに進めていれば、退職までのスケジュールについて事前に合意をとれている状態なので、問題なく受け取ってもらえるはずです。
万が一内容に不備があれば指摘されるので、指示に従って修正対応しましょう。
また、何かトラブルがあったときのために、提出前にコピーを取って保管しておくと安心です。
5)引き継ぎや退職の手続きを進める
上司と相談しておいた通り、退職日までに引き継ぎや退職手続きを進めましょう。
引き継ぎについては、引き継ぎ内容をリストアップしておき、作業手順をまとめたマニュアルなどを作成しておくと効率的に進められます。
退職手続きについては、以下について担当部署に確認しておき、退職前に慌てることのないよう進めておきましょう。
- 離職票・源泉徴収票などの書類の受け取り
- 私物の回収
- 貸与品の返却など
4.交渉してもなお上司が退職届を無視・拒否してくる場合の対応4選
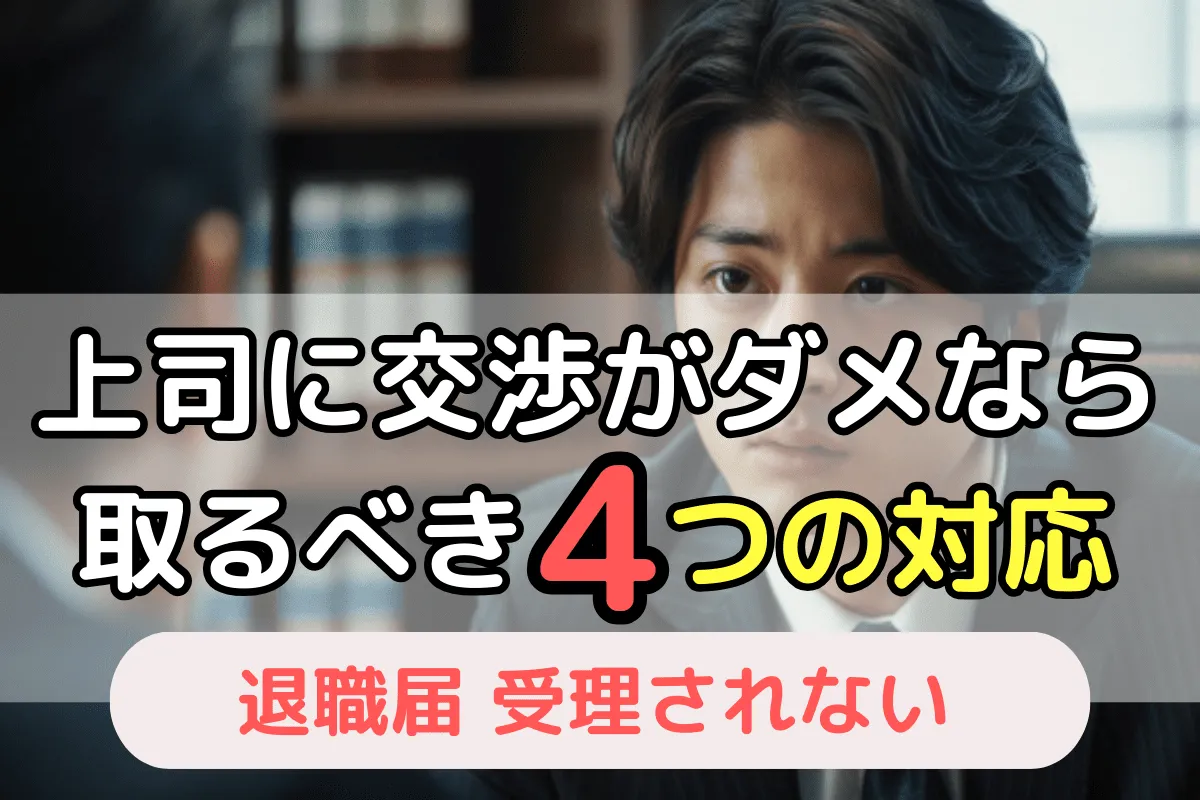
1章の2でも述べたように、退職を押し通すために「退職届」を出したものの、なお無視や拒否をされる場合、上司はあなたの退職を認める気がないと考えられます。
また、「退職届を出したけど受理されたかわからない」という方も、同じような状況でしょう。
この場合は、「円満に話し合いで解決」とはいかないため、こちらとしても断固としたアプローチが必要です。
具体的には、以下4つの対応を検討しましょう。
- 人事に相談する
- 退職届を内容証明郵便で送る
- 労働基準監督署に相談する
- 弁護士に依頼する
中でも最もおすすめなのは、どのようなケースにも対応でき、確実に退職を認めさせられる「弁護士への依頼」です。
順番に見ていきましょう。
1)人事に相談する
直属の上司が退職届をどうしても受け取らない場合は、人事に相談してみましょう。
人事であれば退職について法的なルールを理解しており、退職を拒むことが「違法」であると知っているため、上司に話を通して退職手続きを進めてくれる可能性があります。
退職を頑なに認めないタイプの上司は、「人手不足で業務に余裕がないから」といった現場の都合で、独断で退職を拒んでいるケースが多いです。
上司の独断なら、人事から「正しい対応をするように」と促されれば、きちんと対応してもらえることも期待できるのです。
2)退職届を「内容証明郵便」で送る
人事など社内の他部署にかけあっても「退職届」を受理してもらえない場合は、「内容証明郵便」で退職届を出しましょう。
「内容証明郵便」とは、「いつ(日時)、誰が(差出人)、誰に(宛先)、どんな文書を送ったか(内容)」を証明できる郵便サービスです。
これにさらに「配達証明」をつけることで、「相手に届いた日時」も証明できるため、「会社に退職の意思を伝えた」という証拠になります。
例えば11月末日を退職日とする退職届を11月12に送付し、11月14日に相手が受け取ったとすると、「11月14日に退職の意思を会社に伝えた」ことになるため、2週間後の11月末日には問題なく退職できるのです。

ただし、退職届を送るからと会社に一切連絡せず、バックレとみなされるような行動を取るのは、会社から大量に電話されるといったリスクがあるのでおすすめしません。
電話で退職届を送ったと一報を入れる、またはこの後で説明する「弁護士」に代行を頼むなどの対応をセットで行うようにしましょう。
2)労働基準監督署に相談する
「労働基準監督署」に相談する方法もあります。
労働基準監督署は「労基」とも呼ばれており、会社が「労働基準法」を守っているか監督する機関です。
「会社が退職届を受理してくれない」と相談すれば、改善するよう指導・勧告してくれる可能性があります。
ただし、労基はあなたのトラブルを個別に解決してくれるわけではなく、動いてもらうために証拠をそろえる必要がありますし、できることも基本は「指導・勧告」までです。
会社が理由をつけて指導に従わない場合もあるので、相談すれば即解決してもらえるわけではない点に注意してください。
実際は、「労基に相談していること」を会社に伝え、退職を認めてもらうための交渉に使うのが効果的です。
不当な対応を続けるようなら調査が入る可能性があるとアピールすれば、会社側も下手なことはできないと考え、退職を認めてもらいやすくなるでしょう。
3)弁護士に相談する
どうしても会社が退職届を受理しない場合は、弁護士への依頼をしましょう。
弁護士は、あなたの「代理人」として会社との交渉や退職に必要な手続きを引き受けてくれます。
また、退職届を受理しないと言い張る上司に対しても、退職を認めるように法的な根拠にもとづいて交渉してくれます。
法律に「退職の自由」が認められている以上、会社が退職届を受け取らず退職を認めないのは「違法」です。
法的な正当性がある案件について弁護士が失敗することはなく、確実にあなたの退職を認めさせてくれます。
会社側も、「弁護士がついている」とわかれば訴訟などのリスクをおそれて退職を認める可能性が高く、確実性という点で最もおすすめできる方法といえます。
①特に「退職代行サービス」を扱っている弁護士がおすすめ
退職届を受け取ってもらえず悩んでいるなら、特に「退職代行サービス」をやっている弁護士に依頼するのがおすすめです。
退職代行サービスとは、会社に「退職の意思」を伝えるところから、その後の退職に必要な手続きを全て代行してくれるサービスです。
先ほど述べた「内容証明郵便」による退職届の提出も代行してもらえます。
「弁護士に相談する」とだけ聞くとハードルが高く感じられるかもしれませんが、退職代行サービスであればわざわざ事務所に訪問する必要はなく、スマホ1つで申し込みが完了します。
また、費用も最安値のサービスであれば2万円を切るため、金銭的に余裕がない人でも使いやすいサービスなのです。
②退職を拒否されそうなら最初から頼むのも手
あなたの職場が「退職届を出しても拒否されそう」なブラックな会社の場合、退職届を出す前に最初から弁護士の退職代行サービスに頼むのも手です。
例えばパワハラ気質の上司が相手だと、交渉以前に「退職したい」という意思を伝えることすら難しいケースがあります。
下手をすると、怒鳴りつけられたり、嫌がらせされたりする可能性もあるでしょう。
最初から退職代行を頼んでおけば、退職の申し入れから、その後必要な手続きの一切も弁護士が引き受けてくれるので、上司と直接交渉することなく、ストレスなく退職できるのです。
退職について交渉するのは難しそうと感じたら、ぜひ退職代行を使ってみてください。
以下のバナーから、LINEを使った無料相談ができます。
[banner id=”16503″ size=”m”]5.弁護士ならこんなケースでも対応できる|3つの事例つきで紹介

「退職届を出したのに受理されない」という事例は実際に数多くあります。
ですが、弁護士であればいずれのケースにも対応し、確実にあなたの退職を実現してくれます。
同じような状況にあって「弁護士への相談」を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
1)後任が見つかるまで退職を引き止められる
退職届(退職願)を出したら、後任のスタッフが入るまで退職届は受け取れないと言われたケースがあります。
4月中旬に当事務所の管理者へ「退職願い」を出しましたが拒否され、受理されず。GW明けに施設長にはなしをしたら。5月末の退職は受け取れない。(退職日時まで1カ月未満だから)との回答。つぎのスタッフが入るまで待っていて。と言われています。
引用:Yahoo!知恵袋
この事例では、後任のスタッフを確保するまでは退職されると困るため、「退職日まで1か月未満の申し出だから」という理由を持ち出して退職を拒んでいるのです。
ですが、先述したように、法律上は退職すると伝えてから2週間後には退職できます。
たとえ会社のルール上では1ヶ月未満であっても、労働者が希望するなら会社は2週間後の退職を認めなくてはいけません。
弁護士であれば、「1か月未満だからと退職を認めないのは違法」として会社の不当な対応を指摘し、退職を認めさせられます。
2)受理されたかわからないまま放置される
退職届(退職願)を出したのに、何の反応もされないまま放置されるケースがあります。
退職願っていつ頃受理されるものなのでしょうか?
1月末に今年度いっぱいで退職したいと社長宛の退職願を上司に渡したのですが、2週間経っても、受理しましたと報告があるわけでもなく、止めるでもなく、相談されるでもなく、何にも音沙汰がありません。
引用:Yahoo!知恵袋
こうしたケースではまず上司や人事部に「退職の話はどうなったか」を尋ねて確認するのがベストです。
単に対応を忘れていたというだけなら、話を進めて貰えるでしょう。
ですが、上司がパワハラ気質である場合は退職届を握りつぶされている可能性もあり、話しかけようとしても怒鳴られたり無視されたりして直接の確認すら難しいことがあります。
このように「退職届が受理されたかわからない」状況が改善できそうになければ、「弁護士への依頼」で解決できます。
弁護士にあなたの「退職の意思」を改めて会社に伝えてもらい、その後の連絡や手続きを代行してもらえば、たとえ会社が「退職届を受け取っていない」と言い張ったとしても退職できます。
3)退職するなら「違約金を払え」または「訴える」と脅してくる
退職を認めたくない上司から、退職するなら「違約金を払え」「損害賠償請求をする」といった言葉で脅されるケースがあります。
4月半ばに退職の意思を示し、それから何の音沙汰も無く理解出来ない業務指示が4月に出てそれに関してもその時に自分では出来ない旨も伝えたにも関わらず、5月になって何故それを進めて無いのか?と問われ
そこで私は「退職の件はどうなってますか?」と聞いたら「そんな話は聞いてない」と言い張り
それが度重なり、現在体調不良で休んでいるのですが、それに対して今日突然
「これ以上の業務拒否、職場放棄をするならモラハラで告発する」と脅しのようなLINEを送って来ました
引用:Yahoo!知恵袋
この事例では、退職しようとするのを拒否して話し合いすらしないことが「違法」であるにもかかわらず、上司は社員を告発するという脅しをしており、これ自体がパワハラといえます。
弁護士に頼めば、上司の言い分は法的に何の正当性もなく、逆に社員に対して行っていることこそがパワハラであると指摘し、確実に退職を認めさせられるので安心です。
また、弁護士がついているとわかれば、退職を渋っていた上司も訴訟されるリスクを考え、多くの場合は退職を認めるようになるでしょう。
6.退職届の受理についてよくある質問
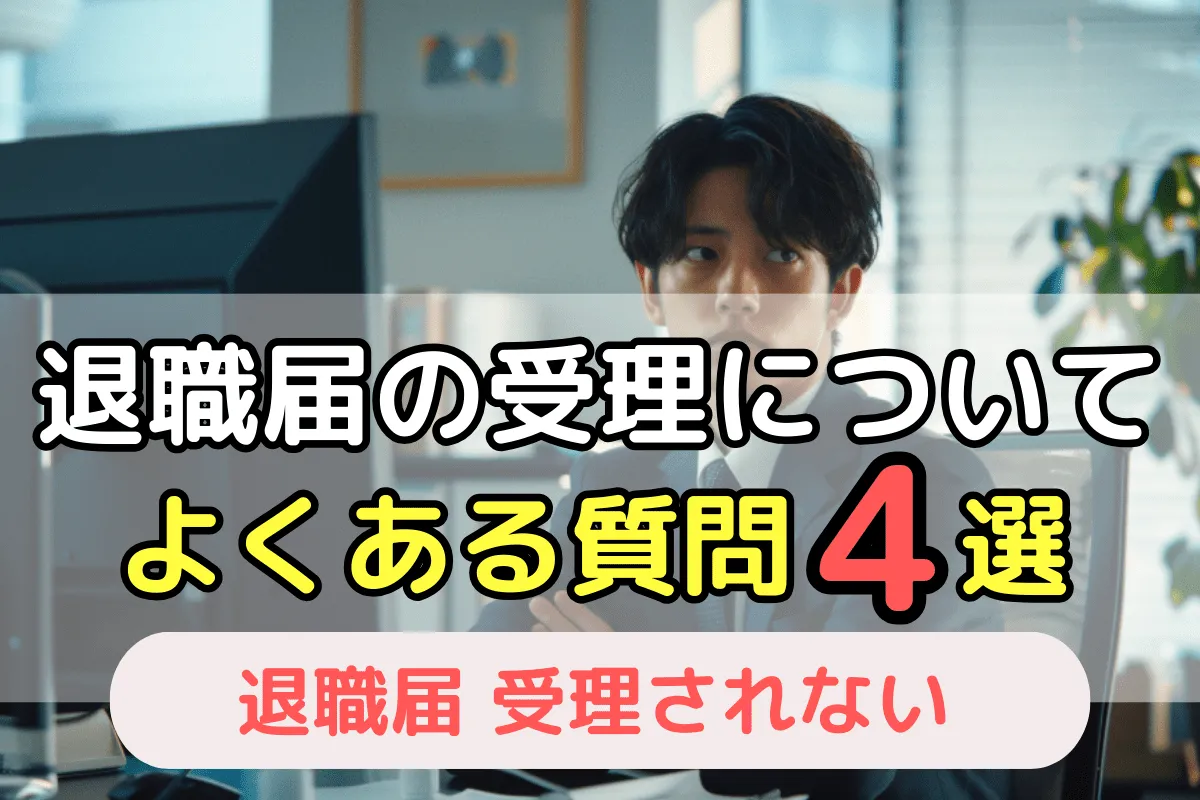
退職届の受理についてよくある質問をまとめました。
1)退職届が受理されないのは「違法」ですか?
退職届が受理されない=「退職を拒否されている」といえるため、基本的には「違法」です。
退職の申し出から2週間後には退職できると民法で定められており、これを拒むのは「違法」だからです。
ただし、退職届に書く「退職日」が退職を伝えた日から2週間を切っており、会社と合意もとれていない場合は、不備扱いで受理されない可能性があるので注意してください。
また、有期雇用(決まった期間の労働)だと、場合によっては「違法ではない」こともあります(詳しくはこの項目で解説)。
2)退職願を出さずに退職届だけで退職できますか?
退職願を出さずに退職届だけで退職できます。
そもそも「退職する」というだけなら、退職願も退職届も法的に必須ではありません。
特に退職願は「会社に退職の伺いを立てる」ものなので、仮にあなたが上司に「◯日に退職したいのですが…」と口頭で相談した場合、退職願と同じ役割を果たします。
ただし、口頭だけでは「言った」「言わない」と後からトラブルになる可能性もあるため、こうしたトラブルを避けたいなら作成しておくと安心です。
状況に応じて判断しましょう。
3)公務員は退職届を受理されないことがあるのでしょうか?
公務員でも「退職の自由」は認められており、公務員であることを理由に退職届が受理されないことはありません。
そもそも公務員は原則として「退職願」を必ず出し、承認を得てから「退職届」を出します。
「退職願」の段階で引き継ぎや調整を行ってから「退職届」を出すので、「退職届が受理されない」という状況はめったにないでしょう。
ただし、退職にあたっては、任命権者(職員の採用決定の権限を持つ機関)からの許可が必要です。
また、公務員の場合、民間企業のように「退職の申し入れから2週間後に退職できる」と定めた法律はありません。
そのため、退職を申し出てから実際の退職までの期間は現場の暗黙のルールなどによって違う可能性があります。
4)アルバイト・パート・派遣などの有期雇用(期限つきの労働契約)の場合、退職届が受理されなくても退職できますか?
アルバイト・パート・派遣などの有期雇用の場合、退職届が受理されない(=会社が退職について合意しない)と、状況によっては退職できないことがあります。
有期雇用は、契約期間中は自由に退職できないことになっており、退職を認められるのは以下のような条件のときだけだからです。
- 契約期間の初日から1年を経過した
- 病気・介護・怪我・会社の不正やパワハラなどの「やむを得ない事由」がある
- 会社と退職について合意している
このため、有期雇用でかつ上司が退職を全く認めようとしない場合は、今述べた「退職できる条件」に当てはまっていないと退職が難しい点に注意してください。
とはいえ、退職したいと申し出ている相手を無理やり雇用し続けても仕方ないので、会社も退職に合意して辞めさせてくれることがほとんどです。
退職できる条件に当てはまっているのに会社が退職届を受理しない場合は、弁護士への相談を検討しましょう。
また、アルバイト・パートが使える退職代行サービスについて以下の記事でも解説しているため、参考にしてみてください。
まとめ
退職届を出したのに受理されないときは、2つのケースに応じて対処しましょう。
1つめは、何も相談せずにいきなり退職届を出したケースです。
引き継ぎなどの事情があり、「いきなり退職届だけ出されてもOKを出せない」という考えかもしれないので、まずは直属の上司に改めて「相談・交渉」してみてください。
2つめは、相談しようと試みたが無視されたり無茶を言われたりでうまくいかず、退職届を出すことで話を動かそうとしたケースです。
相談しようとしてもダメ、退職届を出して話を動かそうとしてもダメなら、上司以外にあたってみるしかありません。
この場合は「社内の人事部門」や「外部」へ相談してみましょう。
法律では、たとえ会社が退職届を受理しなくても、「退職の意思」を会社に示してさえいれば、必ず2週間後に退職(=会社との労働契約を解除)できると決まっています。
つまり「退職の意思を会社に伝えた」という証明を残すことが大切なので、内容証明郵便を使って「退職届を出したこと・会社に配達されたこと」が記録に残るようにしましょう。
また、退職について相談してもなお上司が退職届を無視・拒否してくる場合に最もおすすめなのは、「弁護士への相談」です。
弁護士の退職代行サービスに頼めば、法的な根拠に基づき、あなたの退職を確実に認めさせてくれるため、ぜひ検討してください。
[banner id=”16503″ size=”l”]