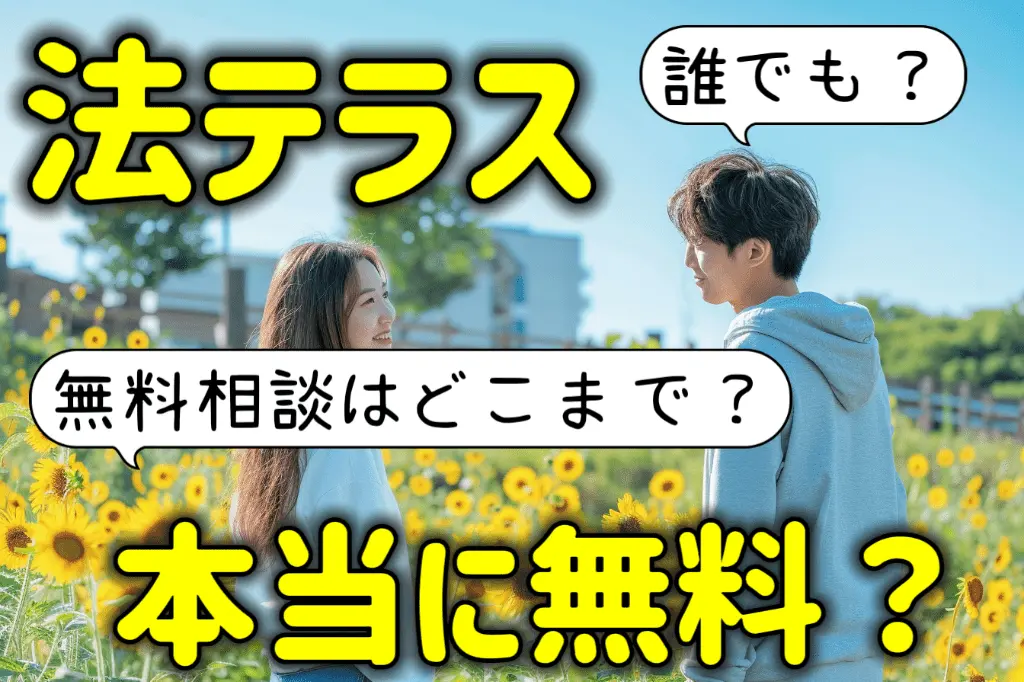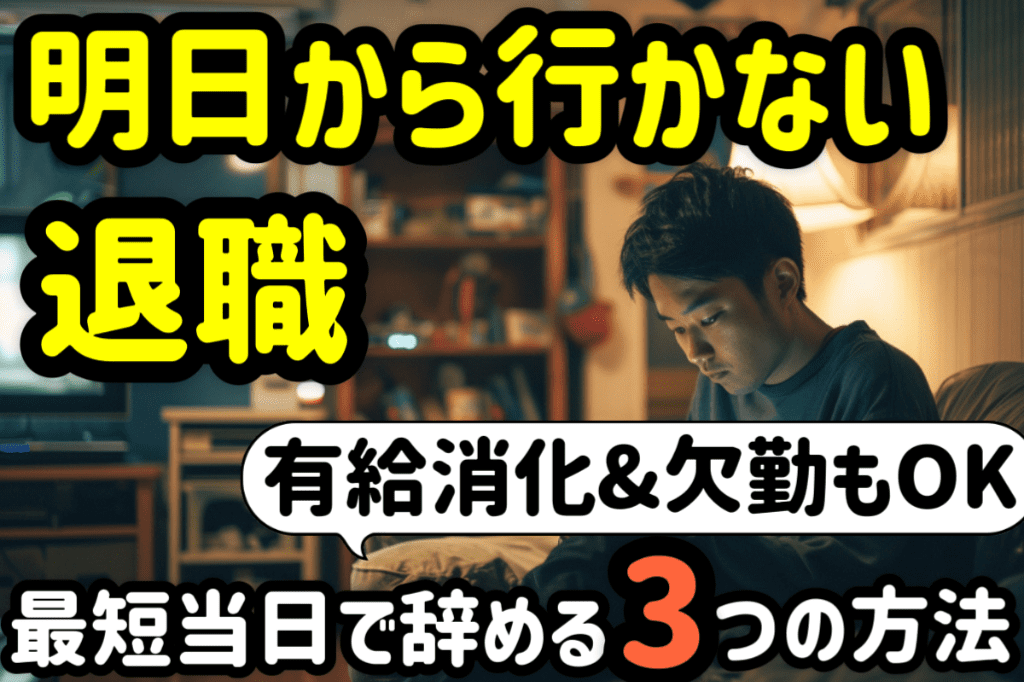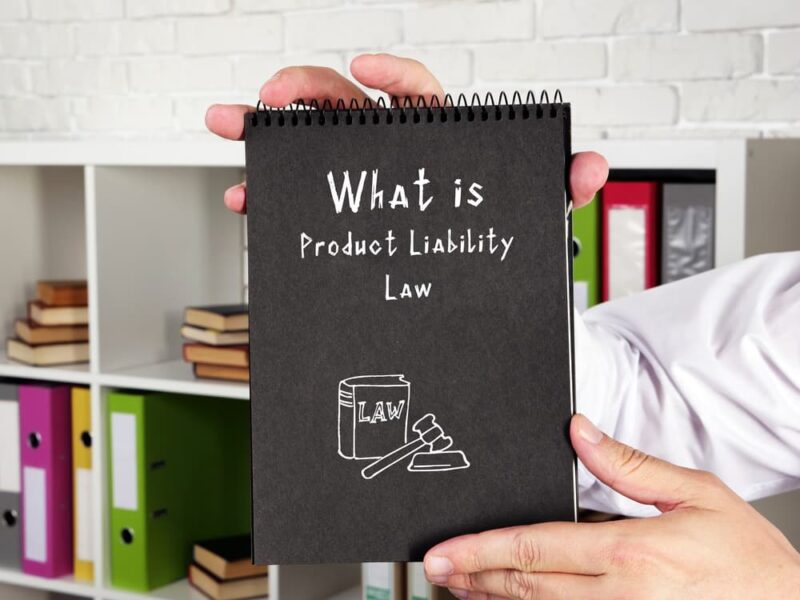「電子決済代行業」に対する3つの規制を弁護士がわかりやすく解説!

はじめに
平成30年6月1日より開始された「電子決済等代行業」の制度ですが、そもそもどのような業務が電子決済等代行業にあたるのでしょうか。
また、電子決済等代行業を行う場合、どのような法規制を受けることになるのでしょうか。
今回は、「電子決済等代行業」について、事業の概要と法規制を中心に見ていきたいと思います。
1 電子決済等代行業とは?|事業の概要

「電子決済等代行業」は、銀行法上の制度であり、同法では以下のように定義しています。
-
【銀行法2条17項】
この法律において「電子決済等代行業」とは、次に掲げる行為(第一号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く。)のいずれかを行う営業をいう。
一 銀行に預金の口座を開設している預金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことの当該銀行に対する指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達(当該指図の内容のみの伝達にあつては、内閣府令で定める方法によるものに限る。)を受け、これを当該銀行に対して伝達すること。
二 銀行に預金又は定期積金等の口座を開設している預金者等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該銀行から当該口座に係る情報を取得し、これを当該預金者等に提供すること(他の者を介する方法により提供すること及び当該情報を加工した情報を提供することを含む。)。
以上からもわかるように、電子決済等代行業はその事業内容によって、以下の2つに分かれています。
(1)決済指図伝達事業者(PISP):銀行法2条17項1号
「決済指図伝達事業者(PISP)」とは、銀行に預金口座を開設している人の委託に基づき、当該銀行に預金の移動を伝達することを業とする事業者のことをいいます。
このサービスは、預金口座の残高に変動(更新)が生じることになるため、「更新型」とも呼ばれます。
現在では、多くの人が利用しているネットバンキングですが、ネットバンキングを通じて決済の指図やその旨を伝達する方法で行われる銀行振込サービスは「更新型」にあたります。
(2)口座情報利用事業者(AISP):銀行法2条17項2号
「口座情報利用事業者(AISP)」とは、銀行に預金や定期積立などの口座を開設している人の委託に基づき、当該銀行から口座情報を取得し、その情報を預金者などに提供することを業とする事業者のことをいいます。
このサービスは、更新型とは異なり預金口座の残高に変動が生じることはありませんが、口座情報を取得・提供することにより、利用者がその情報を参照できるようになるため、「参照型」とも呼ばれます。
たとえば、家計簿アプリは預金口座と連携させることにより、預金残高や入金状況といった情報を参照することができるため、「参照型」にあたります。
2 電子決済代行業の登録

電子決済代行業を行う場合、以下のとおり銀行法上の登録を受けなければなりません。
-
【銀行法52条の61の2】
電子決済等代行業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない
もっとも、銀行法では登録拒否事由が多数定められているため、これらの事由に該当する場合には、登録を受けることはできません。
登録拒否事由としては、たとえば、以下のようなものがあります。
(1)財産的基礎がないこと
電子決済等代行業を適正・確実に行っていくのに必要となる財産的基礎があることが必要です。
ここでいう「財産的基礎」とは、純資産額がマイナスでないことを意味します。
(2)体制が整備されていないこと
電子決済等代行業を適正・確実に行っていけるだけの体制が整備されていることが必要です。
既に見たとおり、電子決済代行業者が取り扱う業務は、利用者に係る預金の移動や口座情報の取得に関わりを持つことになるため、適正・確実に遂行されなければなりません。
(3)一定の処分を受けてから5年を経過していないこと
たとえば、事業者が不正な手段を使って電子決済代行業の登録を受けていたことが判明して、登録が取り消された場合、その取消しから5年が経過していないと登録を受けることはできません。
3 電子決済等代行業に対するその他の法規制

電子決済代行業者は、登録を受けた後も以下のような法規制を受けることになります。
(1)利用者に対する説明義務
電子決済等代行業者は、業務を行うにあたり、利用者に対して一定の事項を明らかにしなければなりません。
たとえば、事業者の名称と住所、取引によって生じた損害の賠償に関する事項、苦情や相談を受け付ける窓口の連絡先などが挙げられます。
このほかにも、電子決済等代行業が銀行業と誤認されないために必要とされる情報を提供することや、事業者が取引によって取得した利用者情報を適正に取扱うために必要な措置を講じることなどが義務付けられています。
(2)銀行との契約締結義務
電子決済等代行業者は、事業を行う前に銀行との間で以下のような事項を定めた契約を締結し、これに従つて事業を行わなければなりません。
- 利用者に損害が発生した場合における銀行と電子決済等代行業者との損害賠償責任の分担に関する事項
- 取引に関して取得した利用者情報を適正に取扱うために行う措置と電子決済等代行業者が同措置を行わない場合に銀行が行うことができる措置
これらの事項を定めた契約を銀行との間で締結した場合には、インターネットなどを使って公表しなければなりません。
(3)帳簿書類・報告書の作成義務等
電子決済等代行業者は、事業に関する帳簿書類を作成してこれを保存しなければなりません
また、事業年度ごとに、事業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出する必要があります。
4 電子決済代行業と資金移動業の違い

これまで「電子決済代行業」について見てきましたが、更新型と似た事業に「資金移動業」があります。
資金移動業は、銀行法ではなく資金決済法上の制度であり、同法では以下のように定義しています。
-
【資金決済法2条2項】
この法律において「資金移動業」とは、銀行等以外の者が為替取引(少額の取引として政令で定めるものに限る。)を業として営むことをいう。
電子決済等代行業(更新型)の定義と比較すると、資金移動業はシンプルに定義されており、為替取引を取り扱うという点で電子決済等代行業(更新型)と共通しています。
ですが、両者には為替取引を行う主体であるか否かという点で違いがあります。
電子決済等代行業(更新型)が、利用者に係る預金の移動(為替取引)を銀行に「伝達」することを業としているのに対し、資金移動業は直接主体となって為替取引を行うことを業としています。
つまり、前者において為替取引を行う主体はあくまで銀行であるのに対し、後者において為替取引を行う主体は資金移動者なのです。
このように、電子決済等代行業(更新型)と資金移動業は、一見似た事業ではありますが、事業を規制する法律も異なり、事業者に課される義務も異なるため注意が必要です。
5 まとめ
電子決済代行業は、更新型と参照型いずれについても、APIの利用を想定したサービスですが、これらの利用を前提としていないサービスであっても、電子決済等代行業にあたる可能性はあります。
そのため、利用者の預金口座やその情報を取扱うことを事業内容としている場合には、電子決済等代行業にあたるかどうかを検討する必要があります。
弊所は、ビジネスモデルのブラッシュアップから法規制に関するリーガルチェック、利用規約等の作成等にも対応しております。
弊所サービスの詳細や見積もり等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。