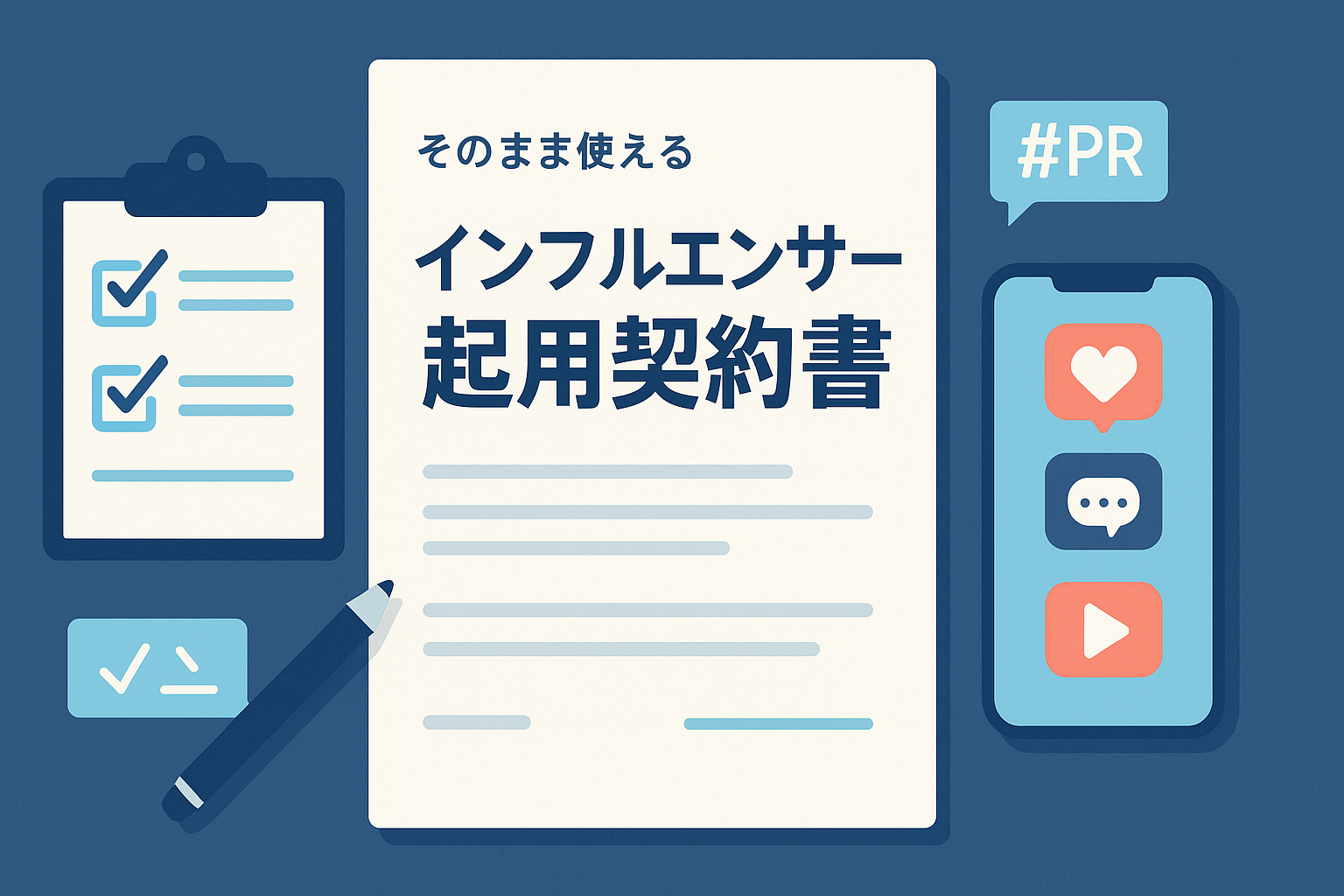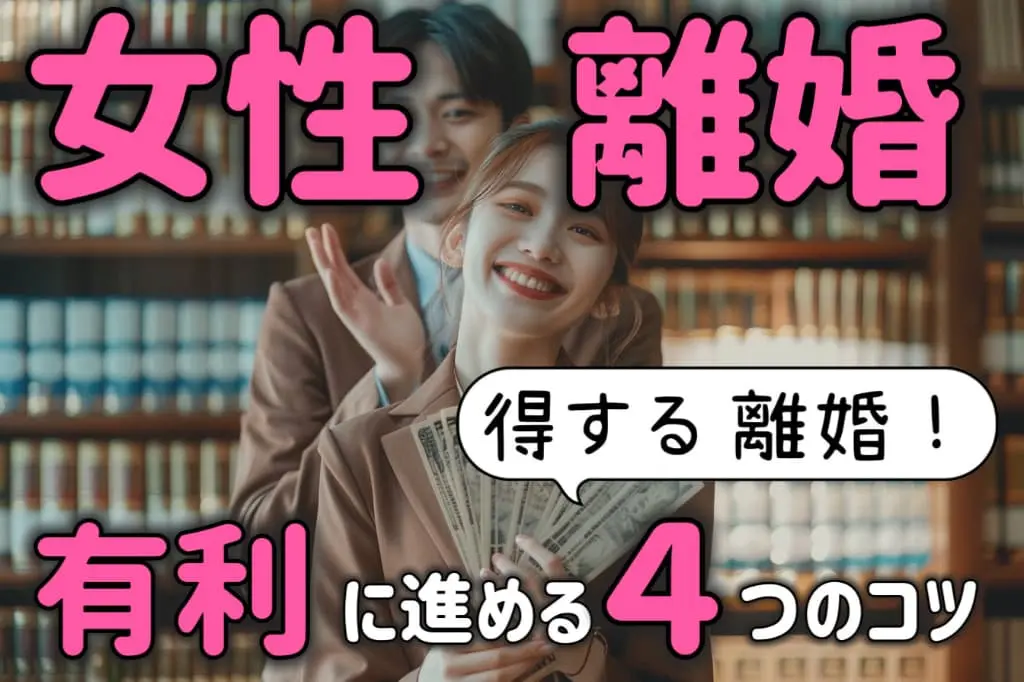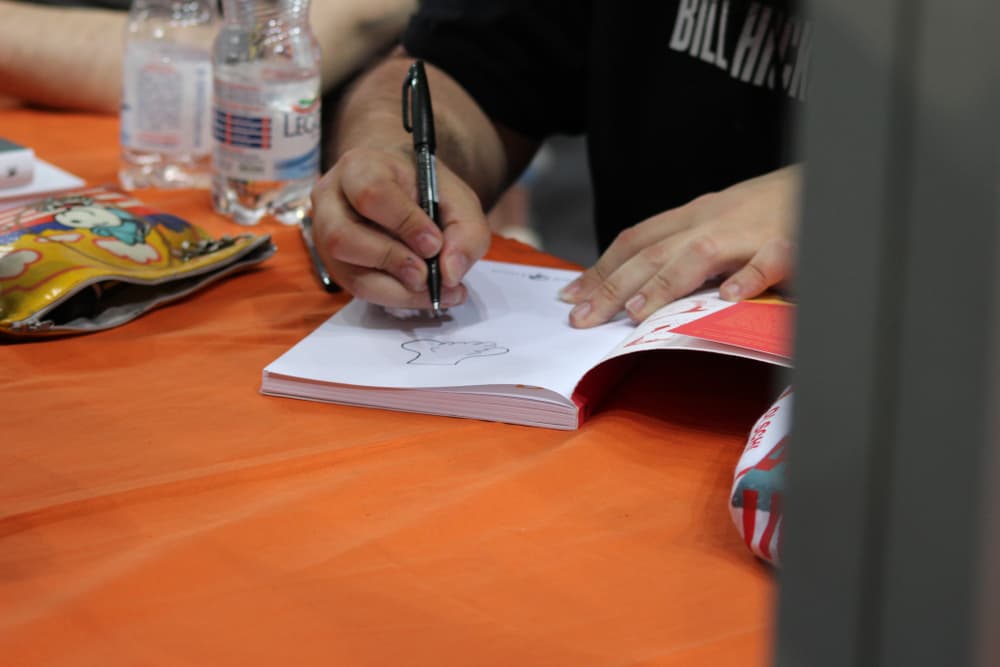キャラクターに著作権なし?4つの事例でどこまで利用してよいか解説

はじめに
昨今、小説や漫画、映画、アニメ、ゲームだけでなく、企業の広告にまで、様々なキャラクターが登場するようになりました。
新規にキャラクターを生み出したり、既に存在するキャラクターを商品化してグッズを作成したりといったことが頻繁に行われています。
もっとも、キャラクターに関する権利関係は複雑です。
「キャラクターには著作権はない」と、どこかで見たことがある人もいるでしょう。かといって自由に利用することはできない。では、どこまで利用できるのか…と悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、
- キャラクターに著作権はあるのか
- キャラクターは自由に使えるのか
などキャラクターにまつわる著作権について、弁護士が詳しく解説をしていきます。
当事務所ブログ「キャラクターはどこまで“似せて”OK?—サザエさん判決に学ぶ『連想ライン』の実務ガイド」も参考にしてください!
この記事を執筆したのは

- 弁護士・中小企業診断士 勝部 泰之
- 注力:知的財産権・著作権/ライセンス、ブロックチェーン、データ・AI法務
GWU Law LL.M.(知的財産法)
事業の成長とリスクを両立する実務寄りの助言に注力しています。 - 詳しいプロフィールはこちら
1 キャラクターに著作権はあるのか、ないのか
まず、ざっくり結論から申し上げると、キャラクター“そのもの”に著作権はないということになります。
ただし、具体的表現は著作物となり保護の対象、したがって無断利用NGです。
商用・二次創作は許諾やライセンスが必要になります。
引用など、著作権法上許される使用は可能ですが、名称は商標権侵害となっていないか等、注意が必要です。
まず、キャラクターそのものに著作権がないという点から説明しますが、ここでいうキャラクターとは何を指しているのでしょうか。
(1)キャラクターとは
「キャラクター」とは、性格や外見などを組み合わせた抽象的な概念(人物像)のことをいいます。
忘却探偵シリーズという小説の「掟上今日子」、マーベルシリーズの映画に登場する「スパイダーマン」、子供向けアニメの「アンパンマン」、熊本県PRマスコットの「くまモン」、東京スカイツリーの「ソラカラちゃん」などがキャラクターであることに異論はないでしょう。
たとえば、アンパンマンは
- 頭があんパンでできている
- 頭は食べることが可能
- 新しい顔と交換が可能
- マントをつけており、空を飛べる
などの特徴で構成されています。
このような特徴を組み合わせた抽象的な概念が、アンパンマンというキャラクターなのです。
(2)著作権とは
では、なぜ抽象的な概念であるキャラクターそのものに、著作権がないのでしょうか。
著作権がないのは、キャラクターそのものが著作権の保護対象に含まれていないからです。
「著作権」とは、「著作物」を独占的に利用できる権利です。
著作権の保護対象は、「著作物」であり、著作物にあたらないものを生み出しても、著作権を得ることはありません。
著作物にあたるためには以下の4つの条件を満たす必要があります(著作権法2条1項1号)。
- 思想または感情が表れていること
- 著作者の個性が表れていること
- 表現されたものであること
- 文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものであること
(3)キャラクターそのものに著作権はない
冒頭で説明したとおり、キャラクターそのものはあくまでも抽象的な概念にすぎません。どんなにそのキャラクターの性格、外見などに対し、キャラクター作成者の思いや個性が発揮されていても、それが具体的な形で表現されない限りは、著作物の4つの条件のうち「③表現されたものであること」という条件を満たしていません。
そのため、著作物にあたらず、キャラクターそのものには著作権はないということになるのです。
では、キャラクターそのものに著作権はないとしても、キャラクターは自由に使用できることになるのでしょうか。
2 キャラクターは自由に使えるのか
たしかに、キャラクターそのものに著作権はありません。もっとも、キャラクターは自由に利用できるわけではないのです。
(1)キャラクターは自由に使えるわけではない
なぜ、キャラクターそのものに著作権はないのに、自由に使えないのでしょうか。
それは、キャラクターそのものに著作権はなくても、キャラクターを小説や漫画、映画、アニメ、ゲーム、ポスターなど具体的な形で表現すれば、「③表現されたものであること」という条件を満たし、著作権が発生するからです。もちろん、③だけでなく、著作物の4つの条件を満たす必要がありますが、具体的な表現物に作者の考えや思いが個性という形で表れていれば条件を満たします。
まとめると、以下のとおりになります。
キャラクターそのもの⇒著作権なし
キャラクターを具体的に表現したもの⇒著作権あり
そのため、キャラクターというものは、具体的に表現することで著作権で保護されます。その結果、具体的に表現されたキャラクターは自由に使えないということになるのです。
実際にキャラクターの著作権について判断された「ポパイネクタイ事件」と呼ばれる裁判例を確認しましょう。アメリカンコミックであるポパイの漫画の図柄をネクタイにしたことが、著作権侵害にあたるか争われた裁判です。
この裁判では、ポパイというキャラクターそのものに対する著作権は、「表現されていない」ことを理由に、否定されました。
その一方、この事件では、ポパイの登場する漫画の著作権は認められ、著作物を無断でコピー(複製)したことが著作権侵害と判断されました。
(2)著作権侵害のペナルティ
ポパイネクタイ事件のようにコピー(複製)などを行い著作権侵害をした場合、どのようなペナルティを負うのでしょうか。
この場合、
- 最大10年の拘禁刑(2026年6月1日から「懲役刑」が「拘禁刑」に一本化されました)
- 最大1000万円の罰金
のどちらか、またはその両方を科せられる可能性があります(著作権法119条2項1号)。
想像以上に重いペナルティに驚かれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
(3)キャラクターを利用するためには
ペナルティを負わずにキャラクターを利用したい場合、
- 著作物の権利者(著作権者)から著作権を譲渡してもらう
- ライセンス契約を結び、許諾の範囲内で利用する
という2つの方法があります。
①著作権者から著作権を譲渡してもらう
「著作権侵害」とは、著作物の権利者(著作権者)の許諾を得ずに、勝手に利用することをいいます。そのため、著作権者から著作権を譲渡してもらい、著作権者になってしまえば、著作権侵害にはならず、ペナルティを負うこともありません。
著作権譲渡については、「【雛形付き】著作権譲渡契約書の作成で気を付けたい11のポイント!」の記事で詳しく解説しているので、ご覧ください。
②ライセンス契約を結び、許諾の範囲内で利用する
もっとも、著作権の譲渡を受けるのは、なかなか難しい場合が多いでしょう。なぜなら、著作権を譲渡してしまうと、譲り渡した元著作権者は、著作物を利用できなくなってしまうからです。
このように、権利の譲渡を受けるのが難しい場合は、著作権者から利用許諾を得ることで著作権侵害のペナルティを負うことを回避しつつ、著作物を利用することができます。
利用許諾を受ける場合には、ライセンス契約を締結するようにしましょう。ライセンス契約については「著作権のライセンス契約とは?注意したいポイント3つを中心に解説!」の記事で詳しく解説しているので、ご覧ください。
これまで、著作権とキャラクターとの関係、どのようにすれば問題なく利用できるかなど、基本的な事項を解説してきました。もっとも、これだけでは、どこまで利用できるかはわからなかったかと思います。
以降の項目では、よく問題となる利用方法について、どこまで利用できるのかなどを4つの事例にわけて解説していきます。
3 原作者とは別の人がキャラクターを描くのは問題ないのか
好きなキャラクターを趣味で描いてイラストサイトに投稿したり、コミックマーケット(コミケ)において同人誌を発売したりと二次創作をしている方もいらっしゃることでしょう。
このように原作者(著作権者)とは別の人が、キャラクターを描くことは著作権との関係で問題ないのでしょうか。
(1)著作権侵害となる可能性
原作者(著作権者)とは別の人が、原作者から許諾を得ることなくキャラクターを描くと、著作権侵害となる可能性があります。
著作権という権利の中には、
- 著作物をコピー(複製)する権利(複製権)
- 著作物に変更を加えて新たな著作物を生み出す権利(翻案権)
などの権利が含まれています。
そのため、著作権をもつ著作権者のみがコピー(複製)したり、著作物に変更を加えて新しい著作物を生み出したりすることができるということになります。
元のキャラクターのイラストをそのまま模写(トレース)した場合には複製権の侵害の可能性が、キャラクターのイラストを0から何も見ずに書けばコピー(複製)にはなりませんが、翻案権の侵害となる可能性があります。
【注:表現上の本質的特徴を直接感得させるレベルの改変は二次的著作物となりうる(=原著作物の利用には原著作権者の許諾が必要)。/根拠:著作権法2条1項11号・28条】
(2)キャラクターがどこまで似ているとNGなのか
もっとも、イラストなどは、書く人によって、表現がバラバラです。同じキャラクターについて描いていても、何を描いているかわからないとった場合もあるでしょう。
では、キャラクターを書く場合、どこまで似ていると複製権や翻案権などの著作権侵害となるのでしょうか。「サザエさんバス事件」という判例から確認していきましょう。
この事件は、バス会社が自社で運行する観光バスに、原作者に無断で漫画「サザエさん」に登場するキャラクター3人(サザエ、ワカメ、カツオ)の顔を描いており、それを売りに「サザエさん観光」としてサービスを展開し、それに対して原作者側が著作権侵害で訴えた事件です。
実際にバスに描かれた3人は以下のとおりです。
この事件において、裁判所は、バスに描かれた3人が、「サザエさん」の漫画のどのコマを元にして書いたかの特定は不要とした上で、誰が見てもサザエさん、カツオ、ワカメが描かれていることがわかるとして、漫画の著作権侵害を認めました。
誰が見てもわかるということは、漫画のサザエさん達がもつ性格、外見などの本質的な特徴が、バスにおいても表現されているということを意味しています。
そのため、このイラストを元ネタに描いたということが具体的に特定されるか否かにかかわらず、〇〇のキャラクターを書いているということが、一般人が見てわかるレベルで描かれていれば、著作権侵害の可能性がでてくるといえるでしょう。
- 当事務所ブログ記事:キャラクターに関する著作権の概観的な解説をしています。
キャラクターはどこまで“似せて”OK?—サザエさん判決に学ぶ『連想ライン』の実務ガイド
(3)描くだけで罪となるのか
とはいえ、そっくりなキャラクターを描き、著作権侵害となっていても、すぐに処罰されるわけではありません。
なぜなら、著作権侵害の多くは、著作権者が処罰を求めなければ処罰されない「親告罪」とされているからです。
この点に関して、よく話題にあがるのが、コミックマーケット(コミケ)における同人誌です。
これまで、確認してきたとおり、本来、キャラクターをもとに新たな作品を生み出せるのは原作者だけです。そのため、著作権者が許諾していないキャラクターを描いた同人誌も翻案権侵害となります。
もっとも、同人誌は、原作の絵をそのまま流用することはないことや、原作とは別の市場で売られるため、原作が売れなくなるということは起きにくいでしょう。加えて、ファン活動やイベントなどの活性化なども見込めます。
そのため、著作権者があえて親告しないケースもあり、「あくまでもお目こぼし」されているといえます。
その一方で、勝手な二次創作を一切許さない原作者であれば、翻案権侵害などの著作権侵害で訴えられる可能性がある点に注意してください。
【追記(非親告罪の例外)】
「著作権侵害は原則として親告罪」ですが、次の3要件をすべて満たす場合に限って、権利者の告訴がなくても捜査・起訴が可能です(非親告罪化)。
①対価を得る目的または権利者の利益を害する目的があること、
②有償で提供・提示されている著作物等(=有償著作物等)を原作どおり複製・譲渡・公衆送信すること、
③その結果、権利者の利益を不当に害すること。
※通常の二次創作・同人誌は上記②を満たさない限りこの例外に当たりません。/根拠:著作権法123条2項・3項、同119条関係。文化庁「環太平洋パートナーシップ協定等に伴う著作権法改正の概要」
補足(用語):「有償著作物等」は、有償で公衆に提供・提示されている録音・録画された著作物等を指します。典型例は市販の音楽・映画・有料配信コンテンツです。
4 キャラクター名だけの使用は問題ないのか
それでは、キャラクターの造形ではなく「名前」だけを使用するならば、著作権上どのような問題があるのでしょうか。
(1)著作権侵害とならない可能性が高い
キャラクター名だけでは著作物とならない可能性が高いといえます。
なぜなら、キャラクター名というものは、文字列自体に作者の個性が発揮されにくく、著作物の4つの条件のうち①~③の条件を満たさないことが多いからです。
たとえば、先ほど紹介した「ポパイ」というキャラクター名についても、裁判所は、著作権があるとは判断しませんでした。
もっとも、キャラクターの名称は「商標登録」をされている場合があります。この場合、著作権侵害をしていなかったとしても、「商標権」を侵害してしまう恐れがあります。
そのため、キャラクター名が商標登録をされていないか、J-PlatPatで確認するようにしましょう。
たとえば、「ポパイ」や「くまモン」というキャラクターの名称は、商標登録がされています。
この商標登録の確認を怠り、勝手にキャラクター名を使用し、商標権を侵害してしまうと、
- 最大10年の拘禁刑(2026年6月1日から「懲役刑」が「拘禁刑」に一本化されました)
- 最大1000万円の罰金
のどちらか、または、その両方を科せられる可能性があるため、ご注意ください(商標法78条・82条)。
※商標登録されているかどうかを調べるやり方を知りたい方は、「商標とは?誰でもできる商標登録の出願の方法を弁護士が5分で解説!」をご覧ください。
(2)キャラクター名を守りたいなら商標登録
自社または自分が取り扱う商品やサービスを他者と区別するために使用する名称や図形などのマークを「商標登録」することで、
- 登録が受けた名称などを独占的に使用すること
- 同一・類似の名称などの使用を排除すること
ができるようになります。
そのため、キャラクター名を勝手に使われないように守りたいのであれば、「商標登録」が有効です。
(3)商標を取っていなくても守ることができる場合
また、商標を登録しなければキャラクター名を守る術がまったくないわけではありません。
もし、商標登録をしていなくても、キャラクター名が全国的に知られているものである場合、不正競争防止法で保護される可能性があります。
具体的には、有名なキャラクター名を、勝手に自己の商品や営業に使用した者に対して、
- 最大5年の拘禁刑(2026年6月1日から「懲役刑」が「拘禁刑」に一本化されました)
- 最大500万円の罰金
のどちらか、またはその両方を科される可能性があります(著名表示冒用・周知表示混同惹起等)(不正競争防止法2条1項1号・法21条3項1号・2号)。
有名なキャラクター名にあやかった「ただ乗り(フリーライド)」はNGということです。
5 著作権フリーのキャラクターの使用は問題ないのか
このほか、インターネット上にはキャラクターイラストのフリー素材サイトが多数存在します。
このようなサイトは必ず利用規約があり、「規約の範囲内であれば無料で使用できる」といった場合がほとんどです。
営利目的の使用は禁止、または点数その他制限をかけていたり、ライセンス料(ロイヤリティー)が発生したりする場合があるので注意しましょう。
たとえばご当地ゆるキャラの『くまモン』の場合は「ライセンス料は必要ないけれど、利用許諾は必要」というスタンスをとっているため、使用する際には、著作権者である熊本県に必ず申請しなければなりません。
「著作権フリー」という表現で素材を提供していたり、使用者側でそのような解釈をしてフリー素材サイトを利用している場合は、一度利用規約などを見直してみましょう。
当然ながら、利用規約から外れた使い方をしていれば著作権侵害となりペナルティを受ける可能性があります。ご注意ください。
6 キャラクターを社内だけで使用することは問題ないのか
他人が作成したキャラクターを社内資料などで使用することは著作権侵害にならないのでしょうか。
下記の2つのケースをみてみましょう。
- 社内資料にキャラクターを使う場合
- キャラクター商品を作るための提案資料を作成する場合
(1)社内資料にキャラクターを使ってもいい?
著作物は、家庭またはそれに準じる範囲で、個人的な使用目的で私的にコピー(複製)をする場合は侵害とはなりません。
もっとも、事業者が社内で使用する場合は「個人的な使用目的」ではなくなります。家庭内などの範囲にも当たらないため、著作権者の許諾を得なければ著作権侵害になります。
たとえば、上記のくまモンの例でも「企業内でその社員だけが閲覧する資料であれば許諾は必要ないが、著作権者のコピーライト表示をすること」というルールを設けています。
こちらもご覧ください(関連記事):社内資料の配布は著作権法違反?企業活動における著作物利用の基本とリスク(令和7年版)【チェックリスト付】
(2)キャラクター商品を作るときはどうすればいいの?
企業がキャラクター商品の企画・検討を行うに当たり、そのキャラクターの著作権者の許諾を得ることを前提として、企画書や会議資料に当該キャラクターを掲載することがあります。
このような許諾前提の検討の過程での利用については、著作権者の利益を不当に害さない範囲で、引用要件を満たすことで必要な限度において無断で利用することが認められています(著作権法30条の3)。
ただし、資料が社外に広く頒布されたり、検討目的を超えて利用された場合には、この規定の対象外となり、著作権侵害となるおそれがあります。
これら2つのケースは「著作権の制限」といい、著作権者がキャラクターの使用について権限の行使を制限されている状態です。著作権は、他にもいろいろなケースで制限されます。制限について詳しく知りたい方は、「著作権の制限とは?無断で使用することができる7つのパターンを解説」をご覧ください。
7 小括
キャラクターそのものに、著作権はありません。もっとも、キャラクターを小説・イラストなどの形で具体的に表現すれば、表現したものには著作権が発生する可能性があります。そのため、キャラクターには著作権がないから自由に使ってもよいということにはなりません。
また、キャラクターには、著作権以外にも、商標登録や不正競争防止法による保護を受ける可能性があります。
これらの権利を侵害しないようにキャラクターを利用するとともに、自身がキャラクターを生み出した場合には、必要に応じてこれらの権利でキャラクターを守っていきましょう。
8 まとめ
これまでの解説をまとめると、以下の通りです。
- キャラクターそのものは著作物ではなく、著作権も発生しない
- キャラクターを具体的に表現すれば、著作物になる
- キャラクターを自由に使いたい場合は著作権譲渡やライセンス契約が必要
- 原作者とは別の人がキャラクターを描くのは、権利侵害になる可能性がある
- 名前だけの文字列は著作物性がないが、商標登録されていたり、著名なキャラクターやなどを勝手に使用することはできない
- インターネット上の「著作権フリー」とされる素材については、「利用規約の範囲内でなら自由に使える」という意味であるため、規約を無視した使い方はできない
- 私的利用や、提案資料などの場合も原則は許諾が必要だが、引用要件を満たせば許諾なくキャラクターを利用できる場合がある
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。